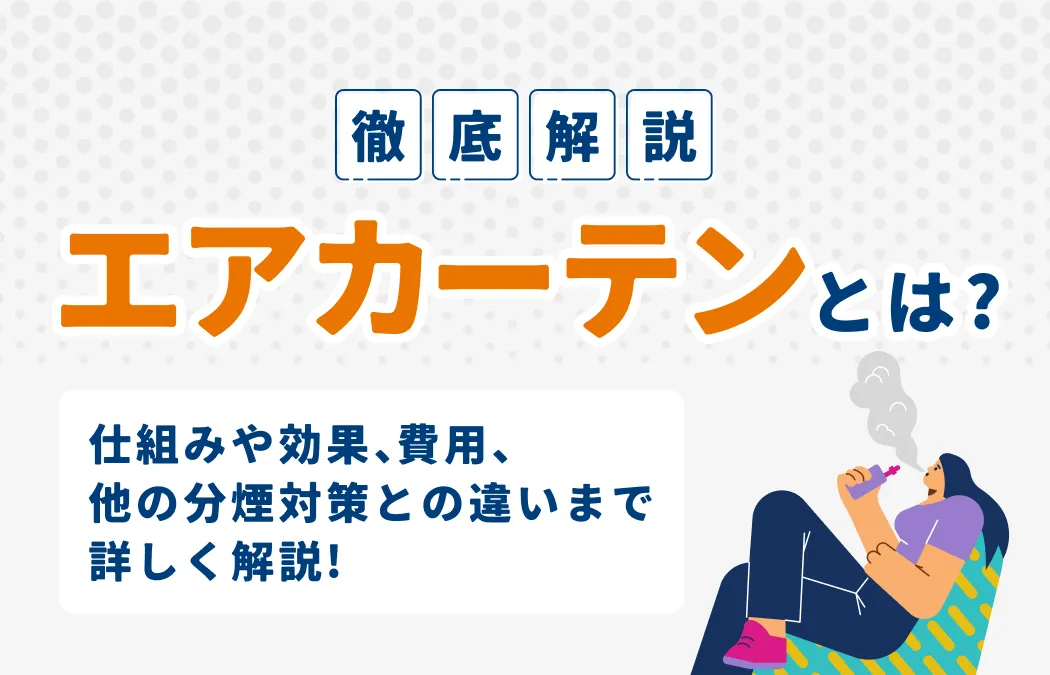店舗を運営していると、こんな悩みを抱える方は少なくありません。
そこで注目されているのが「エアカーテン」です。高速の気流で見えない仕切りをつくり、煙や臭い、虫の侵入を防ぎつつ空調効率も保てる便利な設備です。
本記事では、エアカーテンの仕組みや効果、導入メリットや費用、他の分煙対策との違いまで解説し、導入を検討するための判断材料を整理していきます。
目次
▼この記事で紹介している商品
分煙ニーズとエアカーテンの関係
改正健康増進法による喫煙規制の強化
2020年に全面施行された「改正健康増進法」により、多くの飲食店や店舗では原則屋内禁煙 となりました。
これにより店舗オーナーは、受動喫煙対策を講じることが必須になり、違反すれば罰則対象になる可能性もあります。ただし、多くのユーザーは「法律そのものの細かい条文」ではなく、なぜ分煙や喫煙対策が重要視されるようになったのかを知りたいと感じています。
こうした規制強化が、店舗オーナーに「エアカーテン」など新しい分煙手段を検討させる大きな背景となっています。
飲食店が直面する分煙課題とは?
規制が進んだことで、 飲食店や小規模店舗は「完全禁煙化」か「分煙設備導入」かの判断を迫られています 。しかし、スペースやコストの都合で喫煙ブースを設置できない店舗も少なくありません。そこで課題となるのが以下の点です。
飲食店の分煙課題(例)
- 限られた店舗スペース
→ 狭小店舗では喫煙ブースを置く余裕がない - 空調・換気の効率低下
→ 扉の開閉で煙や臭いが店内に広がりやすい - 顧客満足度の両立
→ 喫煙客・非喫煙客双方に配慮する必要がある - コスト負担
→ 喫煙ブースや換気設備は高額投資になりやすい
これらの課題を前に、「省スペースで導入でき、かつ煙や臭いを遮断する効果がある」エアカーテンが注目されています。特に、出入口や喫煙エリアとの仕切りに設置すれば、物理的な壁を作らずに空気の流れを制御できるため、店舗のレイアウトを大きく変えずに分煙対策が可能です。
飲食店の分煙対策に効果的なエアカーテンとは?
「エアカーテン」は、工場や店舗などにおいて、冷暖房の遮断やホコリ、虫やにおいなどの侵入防止に使われている装置です。さらにエアカーテンは、分煙にも効果的になるため、壁やパーテーションなどの設備を組み立てる必要なく、広々とした空間を維持したまま利用することができます。目に見えない空気のカーテンによって遮断するので、人の出入りを妨げることもなく、室内をキレイな空気のまま保つことが可能です。
サイズも幅広く、店内の広さに合わせて複数台設置することもできます。空気を送る設備なので、風が出てくる音はしますが、エアコンのように天井の高い位置に設置するので、下を行き来しても気になるものではありません。
エアカーテンの仕組みは?
エアカーテンは、建物の出入口などに早い空気の幕を作ることで、内と外の空気移動を遮断する機能があります。遮断する幕は、空気でできた気流なので、人や物が通過しても問題はありません。
気流の吹き出し方法は大きく2種類あり、出入口などの上から降ろす「上下流式」と、横から噴き出す「横流式」があります。
なおエアカーテンを設置する際は、風量を強くしてしまうと床で分裂してしまったり、逆に弱すぎると気流の幕が効果を発揮せずに、ホコリや煙が入ってしまうので意味がありません。
エアカーテンで実現できる分煙効果
煙や臭いを遮断する仕組み
エアカーテンは、 出入口や仕切り部分に高速の空気の幕を作り出し、見えない壁として空気の流れを制御 します。
これにより、喫煙スペースから煙や臭いが店内へ広がるのを抑制する効果があります。特に飲食店では、非喫煙者からの「臭いが気になる」というクレームを防ぐのに有効です。
エアカーテンの仕組み(特徴)
- 空気のバリアを形成:高速気流で物理的な壁の代替
- 煙の拡散防止:喫煙スペースからの空気の流出を抑制
- 臭い移動を軽減:料理や煙の匂いがフロアに広がるのを防止
このように、エアカーテンは「煙を完全に除去する機械」ではなく、空気の流れを制御して拡散を防ぐ設備である点が重要です。喫煙ブースのような密閉設備が難しい場合でも、一定の分煙効果を得られることが評価されています。
空調効率・防虫対策としての効果
エアカーテンは 分煙だけでなく、空調効率の維持や防虫効果でも導入メリット があります。
出入口に設置することで外気の流入を抑え、冷暖房の効率を維持しながら、同時に外からの虫の侵入も防止できます。これは飲食店やコンビニ、小売店舗にとって非常に重要な要素です。
エアカーテンの副次的効果
- 空調効率アップ
→ 外気の侵入を防ぐことで冷暖房費を削減できる - 防虫効果
→ 空気の流れを嫌う虫が侵入しにくくなる - 顧客の快適性向上
→ 出入口付近でも温度差や不快感を軽減できる
例えば、夏場に出入口を開閉すると冷気が逃げやすいですが、エアカーテンを導入すれば店内温度を安定させられます。結果として、 分煙目的だけでなく省エネ・衛生対策にも有効 であり、導入コストを正当化しやすくなります。
エアカーテン導入のコストと補助制度
設置にかかる費用の目安
エアカーテンの導入費用は、機器の種類や設置規模によって大きく変わります。
一般的な 小型モデルであれば数万円から導入可能ですが、飲食店や工場など出入口が大きい場合は業務用機器が必要 になり、20〜50万円程度が相場となります。さらに、設置工事費用も加わり、配線工事や空調設備との調整が必要な場合は追加費用が発生します。
費用の内訳例
- 本体価格:5万〜30万円(家庭用〜中小店舗向け)
- 業務用大型モデル:30万〜50万円以上
- 工事費用:5万〜15万円(設置条件により変動)
つまり、合計で10万〜60万円ほどを想定しておくと現実的です。 初期投資は決して安くありませんが、分煙対策だけでなく空調効率改善による光熱費削減効果を考えると、中長期的にはコストメリットを得やすい 設備といえます。
ランニングコスト(電気代・メンテナンス)
エアカーテンは 常時稼働させるケースが多いため、電気代や維持費も把握しておく 必要があります。一般的な機器の消費電力は1,000〜2,000W程度で、1日8時間稼働した場合、月額で数千円〜1万円前後の電気代が目安です。
また、定期的なフィルター清掃やモーター点検が必要となり、年に1〜2回のメンテナンスで数千円〜数万円かかるケースがあります。
ランニングコストの内訳例
- 電気代:5,000〜10,000円/月(稼働時間・出力により変動)
- メンテナンス費用:1〜3万円/年(業者依頼の場合)
- 部品交換費用:数千円〜数万円(ファン・モーター劣化時)
これらを考慮すると、 導入前に「光熱費削減や防虫・分煙効果でどれだけリターンがあるか」を試算しておく必要があります 。結果として、省エネ効果と快適性向上による顧客満足度改善が、コストを上回る投資対効果につながります。
助成金・補助金の対象例
エアカーテンは 「受動喫煙防止対策設備」として、自治体や国の助成制度の対象になる 場合があります。特に飲食店や小規模事業者を対象とした補助金制度では、導入費用の2分の1〜3分の2が補助されるケースもあるため、必ず確認しておきたいポイントです。
助成対象となる例
- 厚生労働省:受動喫煙防止対策助成金(中小企業対象)
- 自治体独自の助成制度(東京都・大阪府など)
- 商工会議所や業界団体の補助事業
補助制度を利用するメリット
- 初期投資の大幅な軽減
- 国・自治体の認可を受けた安心感
- 設備導入による企業イメージ向上
申請には見積書や図面、導入計画書の提出が必要となる場合が多いため、 導入を検討する際は必ず自治体や商工会議所に確認することが重要 です。補助金を活用すれば、費用面のハードルが大きく下がり、実質的な投資回収期間を短縮できます。
エアカーテンと他の分煙対策の比較
喫煙ブースとの違い
喫煙ブースはもっとも確実に煙を遮断できる方法ですが、設置スペースと高額な費用が大きなネック となります。
一方、 エアカーテンは空気の流れを制御することで煙の拡散を防ぐ仕組みのため、完全密閉には劣るものの、省スペースかつ低コスト で導入できる点が強みです。
-
比較ポイント
- ・費用:喫煙ブースは100万円以上かかる場合が多い/エアカーテンは数十万円規模
・スペース:喫煙ブースは数㎡の空間確保が必要/エアカーテンは出入口や仕切りに設置可能
・効果:喫煙ブース=煙をほぼ完全遮断/エアカーテン=煙拡散を抑える
パーティション・空気清浄機との違い
分煙対策として 安価に導入されやすいのがパーティションや空気清浄機 です。しかし、これらは物理的な煙の遮断力に乏しいという課題があります。
パーティション
- 長所:設置コストが低い、簡単に導入可能
- 短所:空気は上部や隙間から流れるため、煙や臭いは拡散する
空気清浄機
- 長所:タバコ臭や浮遊粒子の軽減効果あり
- 短所:即効性が弱く、大量の煙を完全には処理できない
一方、 エアカーテンは「空気を遮断するバリア」を形成するため、煙の拡散防止という点では上記より優れています 。ただし、空気清浄機との併用により「遮断+浄化」の相乗効果を得られるため、単独ではなく組み合わせて導入する選択肢も現実的です。
どのような店舗に向いているか(店舗タイプ別)
-
小規模飲食店・バー
→ エアカーテン:低コスト・省スペースで分煙可能 -
大型商業施設・空港
→ 喫煙ブース:完全分煙が必須のため最適 -
オフィス・カフェ
→ エアカーテン+空気清浄機の併用:快適性と臭い対策を両立 -
工場・倉庫
→ エアカーテン:出入口利用が多く、防虫・空調効率も重視される環境に有効
エアカーテンは「完全分煙が絶対条件」という場面では不十分ですが、コストやスペースの制約がある中小規模店舗に最適です。また、副次効果として防虫・省エネも得られるため、喫煙対策だけでなく店舗全体の環境改善に寄与します。
エアカーテン導入の流れと活用事例
導入の手順(設置〜運用まで)
エアカーテンを導入する際は、 単に機器を購入するだけでなく、現場調査から設置後の運用までの流れを理解しておく ことが重要です。一般的な手順は以下の通りです。
-
STEP.1
現地調査・要件確認
出入口の大きさや設置環境を確認。風量や機種選定に直結。
-
STEP.2
機種の選定・見積取得
店舗規模や用途に応じて小型〜業務用を比較。費用感を把握。
-
STEP.3
設置工事
専門業者による設置。電源工事や空調設備との調整が必要な場合あり。
-
STEP.4
試運転・調整
風量や角度を調整し、煙や外気の流入を最小化。
-
STEP.5
運用・定期メンテナンス
フィルター清掃・動作確認を行い、長期的な効果を維持。
この流れを踏むことで、導入後のトラブルを避けられます。特に 「出入口のサイズに合った機種選定」と「設置後の風向き調整」が効果を大きく左右するため、専門業者に依頼するのが安心 です。
-
導入・活用事例まとめ
-
業種 導入目的 効果例 飲食店 分煙+空調効率維持 非喫煙者の快適性向上、光熱費削減 オフィス 喫煙室と執務室の分離 タバコ臭の流出防止、社員満足度向上 工場 衛生・分煙対策 虫侵入防止、衛生基準維持 倉庫 空調効率と分煙 冷暖房費削減、作業環境改善
まとめ
今回は、改正健康増進法の施行にともない、飲食店などで手軽に分煙が可能になる「エアカーテン」について解説してきました。空気のカーテンによって、ニオイや煙を遮断するエアカーテンは、すでにさまざまな飲食店や店舗で使用されています。
分煙対策は、ほとんどが助成金の対象となっているため、コストをかけずに始めることができます。まだまだわからないことも多いと思いますので、気になる場合はぜひ専門家に相談してみてください。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!