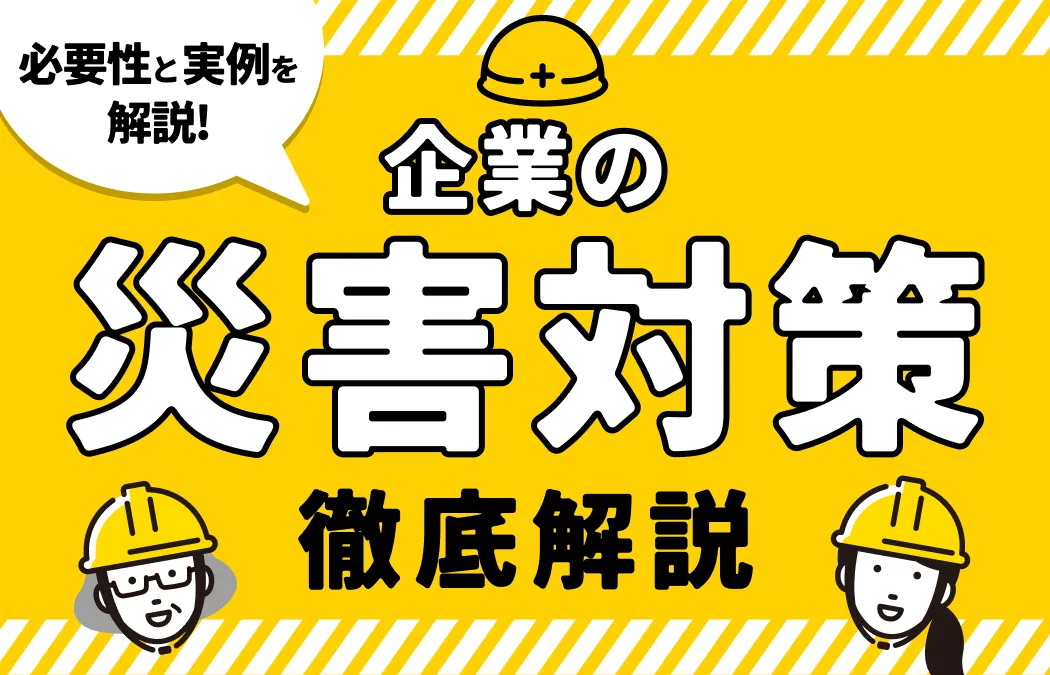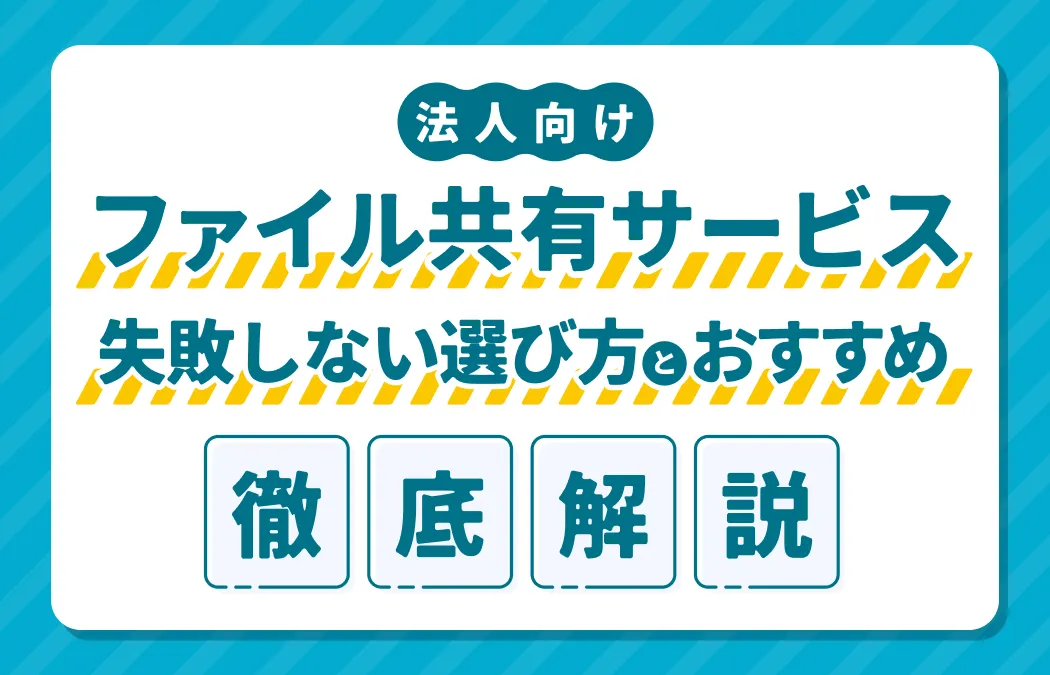「災害時における企業の役割や義務は?」
地震や火災などの自然災害が頻発する日本において、企業が防災対策の取り組みを行うことは重要です。
しかし「企業防災で備蓄すべきものは?」「災害対策本部の設置基準は?」など、具体的な災害対策について詳しく分からない企業も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、企業防災の必要性と対策を詳しく解説していきます。
企業防災を行うポイントや成功した企業の取り組み事例も紹介しているので、これから防災対策を行う企業は必見です!
目次
【企業防災とは】自然災害時に企業が取り組むべき対策

企業防災とは、 自然災害が起きた際、企業が損害を防ぐために取り組む活動のことです。
事業の継続性を確保するために、事前にリスクを認識し対策を立てることが重要です。
具体的には、「防災」と「事業継続」の2軸で、企業として取り組むべき災害への備えが定義されています。
-
BCP(事業継続計画)の策定
-
避難訓練
-
防災マニュアル・BCPマニュアルの整備
-
備蓄品の管理 など
企業防災の基礎
企業防災は、「企業に所属する人の命を守る”防災”」と「被災した際に業務を止めない、または早期復旧を図るための”事業継続”」の2軸で、企業として取り組むべき災害への備えが定義されています。
企業防災の考え方1|防災の観点
企業防災における防災の観点は、 「従業員の安全確保」「施設や機器の被害軽減」「業務の継続性確保」の3つがあります。
-
従業員の安全確保:避難訓練や防災マニュアルの整備、安否確認手段の確立などが求められる
-
施設や機器の被害軽減:耐震化や防災対策を施した建物の構築、適切な設備管理、備蓄品の管理が必要
-
業務の継続性確保:BCPの策定や、データバックアップ、代替オフィスの確保などが求められる
上記の観点を踏まえた防災対策を総合的に行うことで、企業は災害時におけるリスクを低減し、事業の継続性を確保することができます。
企業防災の考え方2|事業継続の観点
事業継続は企業にとって非常に重要な課題であり、地震や自然災害などのリスクに対応するため、事前に対策を講じることが求められます。
理由としては、まず、被災時において従業員の安全を確保し、業務の継続を図ることで、 顧客へのサービス提供を維持することが可能になります。
また、復旧までの期間を短縮することで、収益機会の損失を最小限に抑えることができるため、 企業の経営上のリスクも軽減されます。
-
企業は事業継続計画(BCP)の策定や訓練を実施し、具体的な対応方法をマニュアル化することが望ましい
⇒災害発生時に迅速かつ適切な対応が可能となり、被害の最小化が図れる -
企業は安全対策や防災対策を徹底し、日常業務においても従業員の意識向上に努めるよう取り組むことが重要
⇒例えば、定期的に避難訓練を実施したり、備蓄品の確認や整備を行うことが求められる
企業の災害対策ではBCPとBCMが重要
BCPとは有事に備えるための「事業継続計画」
BCPは「Business Continuity Plan」の略で、 有事の際に事業活動を継続するための計画 を指します。
緊急事態は突然発生するため、あらかじめBCPを策定しておくことで、企業は損害を最小限に留め、災害やシステム障害などのリスクに対して適切に対処できます。
企業の業務がITシステムに依存する昨今は、 IT環境の安定性が事業の継続に大きく影響 するようになりました。それゆえ、IT環境におけるBCPがますます重要になっています。
BCMとはBCPを実行可能にするための「事業継続マネジメント」
BCMは「Business Continuity Management」の略で、 BCPで定めた対策計画を実行可能なものとして機能させるための運用計画 で、BCPの中に織り込ませて記載するのが一般的です。
基本的には、訓練を中心にPDCAサイクルを回しながら、外的な環境変化と、内部の体制変化に合わせて、運用のしくみを継続的に強化していくことが求められます。
BCPの修正点などを事前チェックし、訓練で従業員の判断力や対応力を鍛えたり、BCPの見直し・改善案を整理したりしてブラッシュアップを図ります。
日本国内において企業防災が必要な理由
国内企業に防災が必要な理由は、 「日本が自然災害が多い国であること」「事業を継続できるように業務インフラを守ること」「従業員や顧客の安全確保を図ること」などが挙げられます。
特に地震や台風などの大規模災害が発生した際、企業に大きな被害が及ぶことがあり、その対応が事業の存続や復旧に大きく影響します。
また、従業員の安全確保ができない場合、業務が停滞し、顧客へのサービス提供も困難になるため、企業防災は重要な経営課題となります。
リスクマネジメントの一環
自然災害の発生によって、事業継続が不可能になるほどの損失が発生したり、売上減少などが起こったりすると、企業は経営不振に陥り、最悪の場合倒産してしまいます。
例えば、自社で少所有する 事業所や機器が損壊した場合や、従業員の多くが被災した場合などは、事業活動ができなくなってしまいます 。
上記のような事態を避けるためのリスクマネジメントとして、防災対策は非常に重要な課題となるため、多くの企業は災害対策への取り組みを強化しているのです。
企業の社会的責任の観点から
企業には、従業員、消費者、取引先、地域住民といった利害関係者(ステークホルダー)が抱える様々な社会的問題の解決に向けて、貢献する社会的責任(CSR)があります。
防災対策への取り組みは、災害発生時に従業員や顧客の安全を確保したり、地域住民に避難場所や水、食料といった備蓄品を提供したりして、地域社会への貢献することが目的です。

編集部
企業はCSRに則った取り組みを通して、ステークホルダーとの良好な関係を築くことで、将来にわたって成長していくことが期待できます。
【企業防災のポイント】災害時における企業の役割・義務
日本は地震をはじめとする自然災害が発生しやすいため、企業は地域社会の一員として、 地域の防災活動にも協力し、相互支援を行うことが求められます。
国の防災基本計画でも「企業防災」の促進が重要視されており、災害時に企業が果たすべき役割について記述があります。
具体的には、「生命の安全確保」「二次災害の防止」「事業の継続」「地域貢献・地域との共生」が企業の役割とされています。
防災マニュアルの作成と周知を徹底する
防災マニュアルは、 自然災害や事故などが発生した場合に「企業が迅速かつ適切に対応するための手引書」であり、従業員の安全確保や業務の継続が図れるよう設計されています。
-
災害発生時の対応プロセス:状況判断、安否確認、避難誘導、連絡体制の確立など
-
BCP(事業継続計画)の策定:災害発生時における最低限の業務やサービス提供方法の決定
-
定期的な訓練の実施:事前に想定されるシナリオに基づいて対応訓練を行い、実際の災害発生時に迅速に対応できるようにする
-
備蓄品の用意と管理:食料、水、衛生用品などの備蓄品の定期的な入れ替えと管理を行う
また、防災マニュアルは作成さするだけでなく、 従業員への周知が重要です。
- マニュアルの配布:すべての従業員に対してマニュアルを配布し、必要に応じて研修を行う
- 社内ネットワークへの掲載:社内イントラネットなどでマニュアルを掲載し、いつでも閲覧できるようにする
- 定期的な情報発信:メールや社内報を通じて防災に関する情報を定期的に発信し、従業員の意識を高める
これらの方法を通じて、防災マニュアルの作成と周知を徹底し、自然災害に対する企業のリスクを最小限に抑えることが可能です。
災害時は「人命の安全確保」を最優先に意識する
地震や火災などの自然災害が発生した場合、 企業は「人命の安全確保」を最優先に意識することが重要です。以下の取り組みを行い、安全確保に努めましょう。
-
災害対策の徹底:防災マニュアルを策定し、周知と訓練を行い、迅速かつ適切な対応ができるようにする
-
避難経路の整備:オフィス内の避難経路を確保し、避難経路の表示を明確にする
-
定期的な点検と整備:建物や設備の安全性を確認し、必要に応じて改修や整備を行う
-
安全意識の向上:従業員に対して定期的に安全教育を行い、安全意識を向上させる
また、災害発生時には以下の対応が必要です。
-
速やかな安否確認:災害発生時にすぐに従業員の安否確認を行い、必要に応じて救助活動を実施する
-
適切な情報収集と共有:災害発生時の状況や被害状況を正確に把握し、関係者に適切な情報を提供する
-
迅速な避難誘導:定められた避難経路を使って、従業員を安全な場所に誘導する
これらの取り組みにより、「人命の安全確保」を最優先に意識し、 企業としての社会的責任を果たすことができます。
災害の二次被害を食い止めるために行動する
災害発生時に迅速かつ適切な対応を行うことで、二次被害を防ぐことが可能です。
-
企業は事業継続計画(BCP)を策定し、従業員に対する訓練を実施しておく
L災害発生時にどのような対応が必要であるかを確認できるだけでなく、従業員がより安全な行動を取ることが可能となります。
-
災害発生時における連絡体制の確立
L従業員同士、企業内外の関係者との連絡が円滑に行われることで、現状の把握や安否確認が迅速にでき、適切な対応が可能となります。 -
自社の業務やサービスに関連するリスクの特定や評価、対策の立案
L災害時における被害の最小化や事業停止期間の短縮が期待できます。
日本では自然災害が多発しており、 企業としての防災対策や復旧支援が求められることが増えています。
このため、事前に万全の準備を行っておくことが重要であり、二次被害を未然に防ぐことが可能となります。
日ごろから防災備蓄品の使用について講習を行う
日ごろから防災備蓄品の使用についての講習を行うことが、 災害時において被害を最小限に抑える上で非常に有効です。
-
講習では防災備蓄品の正しい選定方法や使用方法を説明する
L災害時に備えている備蓄品が適切であり、備蓄品に異常がないことを確認できます。 -
講習を定期的に実施する
L講習を定期的に実施することで、従業員の防災意識の向上が期待できます。
災害時にはパニックになりやすいため、日頃からの訓練が冷静な判断を下す上で重要です。 -
防災備蓄品を使用する際の注意点や効果的な活用方法を説明する
l避難時に持ち出すべきものや、非常食の選び方、簡易トイレの設置方法など、具体的な内容を提供できます。
防災備蓄品の使用についての講習は、 今後も不測の状況に直面した際に自己の安全や他者への支援を的確に行う上で、大変有益なものであると言えるでしょう。
防災における周辺地域との連携を強化
地域と企業が連携を強化することで、災害時の被害を最小限に抑え、復旧を迅速に行うことができます。
地域と企業が互いに助け合い、情報を共有することは、災害対策において重要な役割を果たします。
連携を強化する方法としては、 まず地域で実施される防災訓練に企業が積極的に参加し、 地域と連携した避難計画や安否確認方法を確立するのがおすすめです。
また、企業は地域の防災組織や自治体と協力して、 緊急時に使用できる物資や避難場所を事前に確認しておく必要もあります。

編集部
さらに、地域と連携したBCP(事業継続計画)を策定し、地域に根ざした企業の防災対策を検討することで、効果的な対策ができます。
これにより、地域全体の災害への対応力が向上し、被害の拡大を防げるでしょう。
災害への危機意識を風化させない
災害への危機意識を風化させないことは、企業の災害対策において不可欠です。
災害への危機意識を風化させないためには、 定期的な研修や訓練を実施して危機意識を維持し、災害時に迅速かつ適切に対応できるように準備を整えることが重要です。
また、 社員一人ひとりが自分の立場や役割を理解し、災害時の対応策を身につけることも、危機管理能力を向上させるうえで大切なポイントです。

編集部
さらに、災害時におけるリーダーシップやコミュニケーションスキルを向上させることも、危機意識を風化させないために重要な要素です。
災害別に見る企業防災事例と具体的な取り組み
地震への備えと企業事例
地震は日本企業にとって最も発生頻度が高く、かつ被害が大きい災害です。企業は耐震工事や建物の安全性強化だけでなく、社員の安全確保や事業継続の視点から多面的に備える必要があります。
主な取り組み例は以下の通りです。
- 建物・設備の耐震化:オフィスや工場の耐震補強工事を実施
- 避難訓練の実施:年2回以上の避難訓練や防災マニュアルの更新
- 安否確認システム導入:災害時に社員の安否を即時に把握
水害・台風に備える企業の取り組み
近年の気候変動により、集中豪雨や台風による水害リスクは増加しています。浸水や停電による業務停止を防ぐため、企業は立地・設備・情報システムの観点から備えることが重要です。
主な取り組みは以下の通りです。
- ハザードマップの活用:事業所のリスク把握と拠点移転の検討
- 浸水対策:止水板の設置、重要設備の高所配置
- ライフライン確保:非常用電源や衛星電話の導入
感染症・パンデミック対応の実例
新型コロナウイルスの影響から、感染症への備えは企業防災の重要テーマとなりました。感染拡大時に事業を止めないためには、社員の健康管理と柔軟な働き方の仕組み作りが欠かせません。
代表的な取り組みは以下です。
- テレワークの推進:在宅勤務体制の整備、VPNやクラウドサービス導入
- 衛生管理の徹底:マスク・消毒液・空気清浄機の常備
- 事業継続体制:分散勤務や交代制勤務の導入
-
防災グッズを準備するときのポイント
- ・オフィス内に十分な量の飲料水や非常食を備蓄する。
・備蓄期間や消費期限を確認し、定期的に補充や入れ替えを行う。
・オフィス内に避難所を確保し、適切な防災グッズを用意する。
・防災グッズの管理には専用の管理者を任命し、適切な管理方法や入れ替え時期をミスなく把握する。
・従業員に対して防災グッズの存在場所や使用方法を周知する。
BCPに直結する企業防災の実践事例
データバックアップとITシステムの冗長化
災害時に 最も深刻な被害の一つが「情報の喪失」 です。顧客データや会計情報、設計図面などが消失すれば、業務再開は困難になります。そのため企業はデータの多重保存やシステム冗長化を進めています。
代表的な取り組みは以下です。
- クラウドバックアップ:主要データをクラウドに保存し遠隔から復旧可能に
- オンプレ・クラウド併用:物理サーバー+クラウドで二重化
- DR(ディザスタリカバリ)拠点の設置:別地域にバックアップサーバーを用意
社員安否確認と連絡体制の整備
BCPで欠かせないのが「人の安全確認」 です。社員の安否が分からなければ、復旧作業を誰が行えるのか判断できません。そのため多くの企業が安否確認システムや緊急連絡網を整備しています。
主な取り組みは以下です。
- 安否確認アプリ:災害発生時に一斉通知・自動集計
- 多様な通信手段の確保:メール・電話・チャットを併用
- 安否確認訓練の実施:年数回の訓練で運用定着
事業拠点の分散とサプライチェーン対策
災害で本社や工場が被災した場合、事業が完全に止まるリスク があります。そのためBCPでは「拠点分散」と「取引先リスク分散」が必須です。
主な施策は以下です。
- 事業拠点の多拠点化:本社・工場を複数エリアに配置
- 代替生産ラインの確保:他工場や協力企業で生産可能に
- サプライヤー分散:仕入れ先を複数確保して供給停止リスクを低減
企業防災の必要性と効果

法令遵守・企業責任の観点からの必要性
企業防災は単なるリスクマネジメントではなく、法令遵守や社会的責任を果たす行為 でもあります。労働安全衛生法や災害対策基本法では、事業者に対して従業員の安全確保や事業継続努力が求められています。
もし対策を怠れば、従業員や顧客の命に関わるだけでなく、法的責任や社会的信用失墜にも直結します。
具体的な必要性
- 労働安全の確保:従業員の生命・身体を守る法的義務
- 社会的責任:顧客や取引先へ影響を及ぼさない配慮
- コンプライアンス:法令遵守と企業ガバナンス強化
従業員・顧客の安全確保につながる効果
企業防災の第一の効果は「人命を守ること」です。災害時に従業員や顧客を守れなければ、事業継続はあり得ません。防災対策は社員の安心感を高め、顧客や取引先の信頼にもつながります。
代表的な効果は以下です。
- 従業員の安全確保:避難訓練や安否確認システムにより、災害発生時の混乱を最小化
- 顧客の安全配慮:商業施設や店舗での誘導体制整備により事故を防止
- 安心感によるモチベーション向上:社員が安心して働ける環境が生産性にも寄与
災害時の損失を最小化し事業継続を実現する効果
企業防災のもう一つの大きな効果は、災害による損失を最小限に抑え、事業を早期に再開できる点です。BCPの整備やシステムの冗長化は、直接的な売上損失の低減や取引先からの信用維持に直結します。
効果を整理すると以下の通りです。
- 経済的損失の抑制:設備被害や在庫損失を最小化
- 取引継続性の担保:納期遅延を防ぎ顧客離脱を回避
- 企業ブランドの維持:災害後も迅速に対応できる企業として評価
防災対策を行なっている企業の割合
内閣府が実施した「令和3年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、 防災対策を行う企業は増加傾向にあります。
特に中小企業(中堅企業)で、平成19年度は「BCP策定済みである」「BCP策定中である」合わせて15.7%でしたが、令和3年度は51.9%と半数を超えるまでに増加しています。

海外企業の災害対策、BCP対策の状況は?

企業防災意識とBCPの徹底
海外企業においても、災害対策やBCPの取り組みは重要視されています。
特に、 欧米をはじめとする先進国の企業では、災害への対策が経営戦略の一部として位置づけられていることが多く、自社のリスク管理体制や事業継続計画の策定が徹底されています。
また、地震や台風、洪水などの自然災害が頻発する地域に拠点を置く企業においては、災害対策やBCPの重要性はさらに高まります。
これらの地域では、政府や地域の組織が企業や住民向けの防災支援や情報提供を行っており、 企業の災害対策への意識が引き上げられています。
また、サプライチェーンのグローバル化が進む中で、 企業は海外パートナーや子会社との連携も含めたBCPを構築する必要があります。
その際、地域や国ごとの災害リスクを把握し、早期復旧や事業継続を可能にするための具体的な対策を検討し実施することが求められます。
海外企業の災害対策やBCPの状況は、企業規模や業界、所在地などによって異なりますが、経営戦略の一環として取り組みが推進され、事業の継続性や社会的責任を果たすための対策が重要視されています。
海外でも高まりを増す防災意識
近年 「地球温暖化による自然災害の増加」や「過去の大規模な災害への実体験」が影響し、海外でも防災意識が高まっています。
このような状況を受け、多くの国々が災害対策を強化し、国民の安全を確保するための取り組みが行われています。
具体的な取り組みの一つとして、各国は 災害対策の国際協力を進めています。
例えば、日本は世界で最も自然災害の多い国の一つのため、長年培った災害対策のノウハウを海外に提供しています。
このように、国際協力を通じて互いの知識や技術を共有し、防災対策を向上させることが大切です。

編集部
海外でも高まる防災意識に対応するため、国際協力や地域特性に応じた対策、企業や団体の取り組みが重要です。
企業の防災対策における問題・課題

部署間の連携が難しい
企業の防災対策では、 異なる専門分野を持つ部署間で意思疎通が難しいため、スムーズに連携できないという課題・問題があります。
また、業務範囲や責任範囲の違いにより、互いの業務を十分に理解できないことから、役に立たないBCPが完成することもあります。

編集部
業務範囲や責任範囲の違いとは、例えば「情報システム部署と営業部署の間で、災害時のデータ復旧やオフィス環境の確保に関する認識が異なる」などです。
このような場合、 部署間の連携を強化するために、定期的な会議や情報共有の仕組みを整備することが必要です。また、経営陣からの明確な方針や支援も重要となります。
防災マニュアルの策定や訓練を実施する際には、部署間の連携を重視し、お互いの業務を理解し合う努力が求められます。
お互いの業務を十分に把握できることで、BCPが効果的に機能し、災害発生時の被害軽減や早期復旧が可能となります。
企業防災マニュアル策定の人手を確保できない
企業の防災対策における問題・課題に、従業員の業務負担が大きく、BCP策定に携わる人手を確保できないことも挙げられます。
特に中小企業では、 人手不足や業務の多様化に対応するために、従業員が複数の業務を担当することが一般的です。そのため、BCP策定や防災対策に取り組む余裕がない場合があります。
また、 災害対策や事業継続に関する知識やスキルが不足しているため、適切な人手が確保できないことも要因となります。
策定する人手を確保できない場合、外部の専門家やコンサルタントを活用することで、BCP策定に必要な知識と経験を補完することができます。
BCP対策に対する現場の意識が低い
企業の防災対策における問題・課題に、 「BCPの重要性に対する理解」や「実際の訓練やマニュアルの活用」が不十分であることから、BCPに対する現場の意識が低いことが挙げられます。
BCPに対する現場の意識が低いと、地震発生時においても従業員が適切な避難行動を取れなかったり、安全確認が遅れたりすることが考えられます。
また、被害が拡大し、業務再開が遅れることにより、顧客へのサービス提供が滞るリスクも生じます。
・企業の経営陣がBCPの重要性を徹底的に理解し、現場の意識向上に取り組むことが重要です。
L具体的な取り組み:定期的な防災訓練の実施や、マニュアルの見直し、現場での役割や責任を明確にする
・従業員一人ひとりが緊急事態に対する意識を高めるために、日頃から防災に関する情報収集や自分自身の安全確認を行うことが大切です。
L具体的な取り組み:企業としても、防災に関連する研修や教育を定期的に行い、現場の意識を高める
災害時に身を守るための企業防災対策の流れ
-
STEP.1
対策方針を決める
まず、企業防災対策の基本方針を決定することが求められます。これには「災害リスクの評価」や「防災対策の目的設定」が含まれます。
対策方針の策定ポイント-
リスク評価:自社にとってどのような危険があるかを明確にし、適切な対策を立案する
-
目的設定:どのような地域や状況下で事業を継続するかを検討し、具体的な対策を計画す
重要なポイントとして、経営陣が主導的に取り組み、全従業員が防災対策に関心を持つことが求められます。
そして、企業内での情報共有や連携を図って、効果的な対策を実施することが大切です。
-
-
STEP.2
企業防災マニュアルの作成・周知
次に、企業防災マニュアルの作成と周知が求められます。
【マニュアルの作成】
マニュアルでは、災害発生時の具体的な行動指針や手順を明記し、全従業員が緊急事態に対応できるようにします。
マニュアル作成時は、各部署や役職ごとに異なる役割や責任を明確にし、業務継続や安全確保がスムーズに進むように計画します。
災害発生時の防災マニュアル作成手順STEP1:事前準備を行う
STEP2:災害発生前の対応についてまとめる
STEP3:災害発生直後の初動対応についてまとめる
STEP4:安全確保後の業務再開対応についてまとめる
STEP5:BCP(事業継続計画)を策定する
【マニュアルの周知】
また、マニュアルの内容を周知するためには、定期的な研修や訓練を実施し、緊急時に迅速かつ適切な対応が取れるようにすることが大切です。
さらに、状況や環境の変化に柔軟に対応できるように、マニュアルの見直しも定期的に行うことが求められます。
-
STEP.3
起こりうる被害への事前対策
地震や火災などの自然災害が発生した際に、被害を最小限に抑えるために、企業は起こりうる被害への事前対策を行うべきです。
事前対策の具体例BCP(事業継続計画)の策定、災害時の連絡体制の確認、マニュアルの整備
また、システムの復旧を迅速に行うために、データを定期的にバックアップし、オフィス外の場所に保管するようにしましょう。
-
STEP.4
企業で防災訓練の実施
企業では、防災訓練を実施することで、従業員が災害時の適切な行動を身につけることができます。
実施方法として、避難訓練や消火訓練のほか、帰宅困難者対策の練習、避難経路や避難場所の整備もおすすめです。
これらを通じて、企業は自社の災害対策を強化し、事業の継続性を高めることができます。
-
STEP.5
企業内で防災備蓄品の準備
災害時に従業員の生活環境を維持するために、企業内で防災備蓄品を準備しておきましょう。
具体的には、備蓄品のリスト作成、備蓄スペースの確保、定期的な備蓄品の入れ替えを行います。
企業に必要な防災備蓄リスト-
水
-
主食(アルファ米、クラッカー、乾パン、カップ麵)
-
毛布
-
保温シート
-
ポータブル電源・自家発電機
-
簡易トイレ
-
衛生用品
-
携帯ラジオ
-
懐中電灯
-
乾電池
-
ヘルメット
-
担架
-
緊急医療薬品類
-
敷物
-
企業防災に関係する自然災害の種類(特徴・対策)

地震
| 地震に関する被害の特徴 | 地震発生時にとるべき行動 |
|---|---|
|
|
津波
| 津波に関する被害の特徴 | 津波発生時にとるべき行動 |
|---|---|
|
|
火山災害
| 火山災害に関する被害の特徴 | 火山災害発生時にとるべき行動 |
|---|---|
|
|
大雨・台風(水害)
| 大雨・台風に関する被害の特徴 | 大雨・台風発生時にとるべき行動 |
|---|---|
|
|
土砂災害
| 土砂災害に関する被害の特徴 | 土砂災害発生時にとるべき行動 |
|---|---|
|
|
竜巻
| 竜巻に関する被害の特徴 | 竜巻発生時にとるべき行動 |
|---|---|
|
|
雪害
| 雪害に関する被害の特徴 | 雪害発生時にとるべき行動 |
|---|---|
|
|
災害対策に向けた企業の取り組み事例【一覧】
まとめ:企業防災による災害対策の実践と効果の最大化を目指そう
企業における災害対策は、被害の最小化や事業継続性の確保を目指すものです。
事前対策の実施、防災訓練の実践、備蓄品の準備などを通じて、従業員の安全確保や事業継続性の向上が図られます。
これらの対策を今後も継続的に実施し、定期的に見直すことで効果を最大化できます。
さらに詳細な対策や取り組み例を知りたい方は、専門家や資料を参考にして、自社に合った対策を検討しましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!