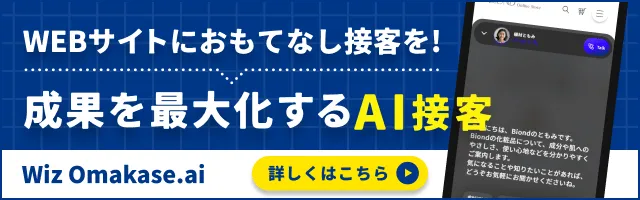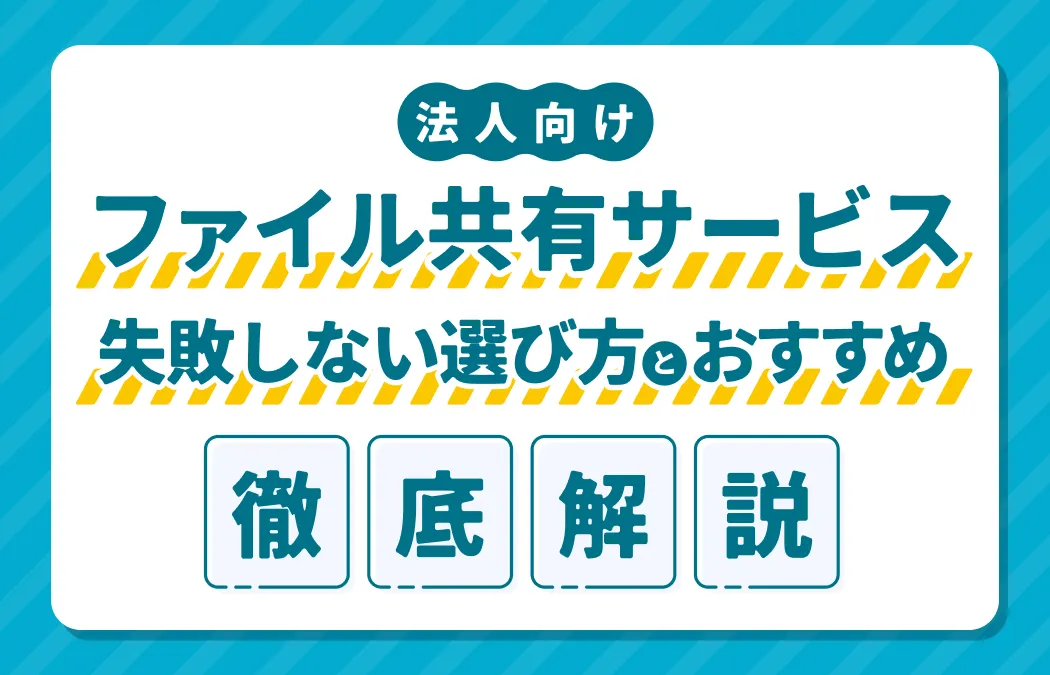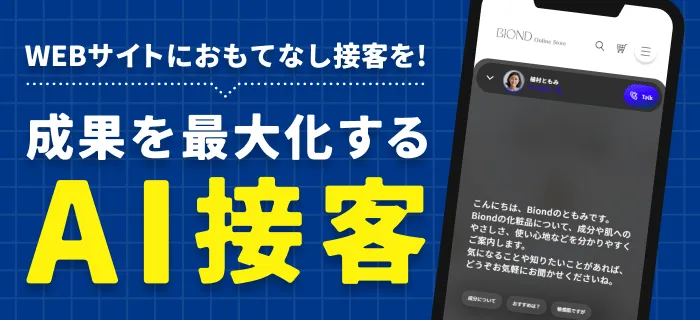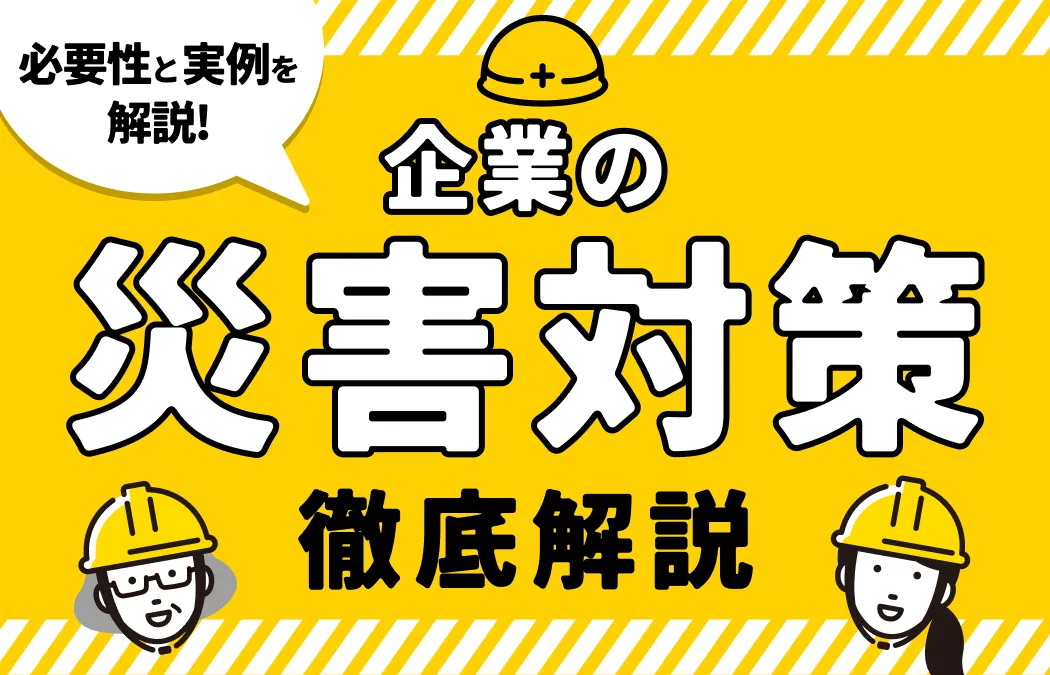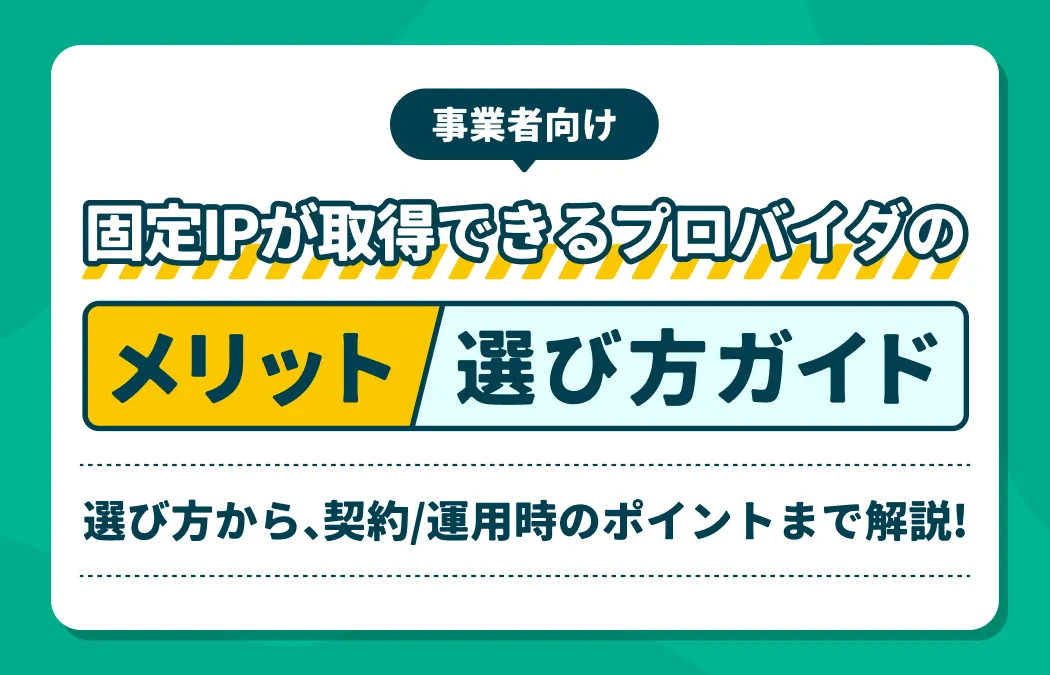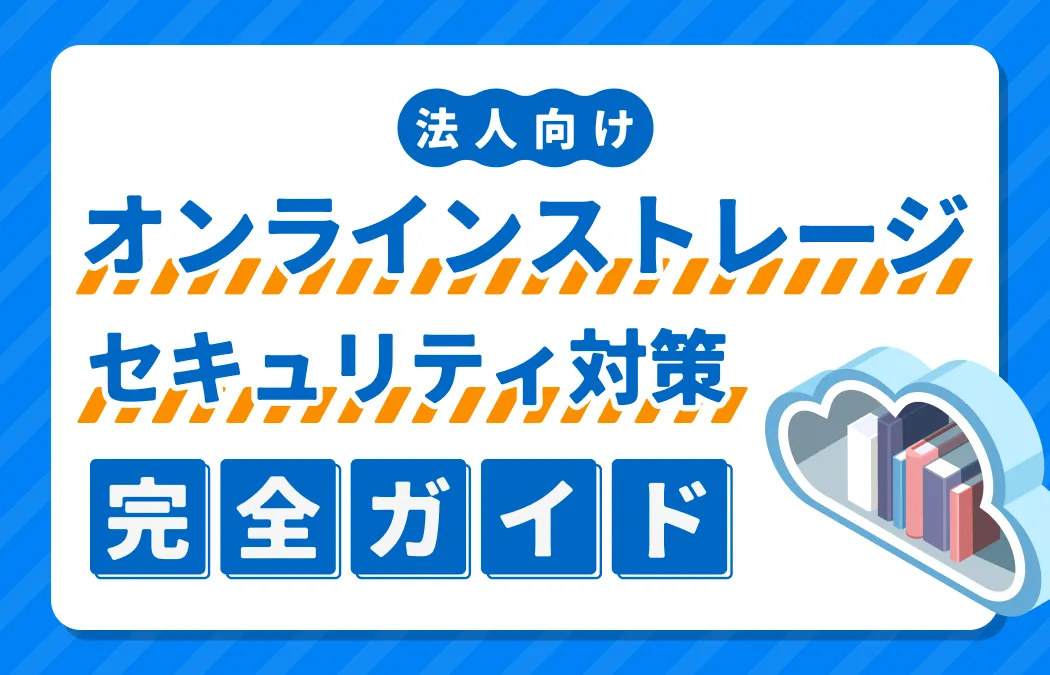「情報共有のフローが曖昧でミスや漏えいが頻発…」
ファイル共有サービスとは、クラウド上で複数人・社内外とファイルを安全に「共有・同期・管理」できるサービスです。
しかし「セキュリティが甘そう」「運用が複雑そう」といった懸念から、導入に踏み切れない企業も少なくありません。
本記事では、法人向けに「選び方の基本」「失敗しない比較軸」「おすすめサービス5選」などを解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
ファイル共有サービスとは?基本概要と最新動向
ファイル共有サービスとは?
ファイル共有サービスとは、 インターネット上で複数人が同じファイルを「保存・閲覧・編集・共有」できる仕組み のことです。
従来のメール添付やUSBでのやり取りとは異なり、クラウド上でリアルタイムにアクセスできるのが特徴で、企業の情報共有やテレワーク環境での必須ツールになっています。
「クラウドストレージ」や「ファイル転送サービス」との違い
- クラウドストレージ:データやファイルの保存が中心
- ファイル転送サービス:データやファイルの一時的な送信が中心
- ファイル共有サービス:リアルタイムかつ継続的な情報の更新・共有を共同で行うためのプラットフォーム
国内・海外の市場規模と拡大トレンド
ファイル共有サービスの市場は年々拡大しており、特に法人利用が急増しています。 背景には、リモートワークの定着や「脱PPAP」などセキュリティ意識の高まりがあります 。
国内でも大手企業だけでなく中小企業や店舗単位で導入が進み、データ共有の効率化が経営課題の一つとなっています。
海外ではBoxやDropbox、Google Driveなどが主流であり、国内市場でも同様のクラウド化が進行中です。
今後は「セキュリティ×利便性」を両立したサービスが求められる時代へと変化しています。
法人/店舗が導入すべき理由:メリットを整理
- 業務効率と情報セキュリティの両立
社内での資料共有や取引先とのファイル送付を一元化できるため、作業時間の削減につながる - セキュリティリスクの低減
アクセス権限や履歴管理が可能なため、誤送信や情報漏えいのリスクも軽減できる - リモートワークの推進を後押し
クラウド共有により、出張先や自宅からもデータにアクセス可能 - 組織全体の生産性向上
テレワークや複数拠点を含め、社内の業務連携がスムーズになり、生産性が向上
法人・店舗が押さえておくべき選び方のポイント
機能面で抑えるべき項目
ファイル共有サービスを選ぶ際は、まず「使いやすさ」と「業務効率化」を左右する機能面を確認しましょう。以下は、特に重要な機能例です。
- フォルダ構造の柔軟性
- アクセス権限の細かい設定
- リアルタイムでの共同編集機能
- リンク共有や期限付きアクセスの有無(社外とのファイル共有を行う場合)
これらの機能が整っているサービスほど、社内外での情報共有がスムーズに進みます。導入後に「思ったより機能が少ない」とならないよう、 利用シーンを明確にした上で選定することが大切 です。
セキュリティ・コンプライアンス観点
法人が導入する際に最も重視すべきは、セキュリティ対策です。社外とのファイル共有には常に情報漏えいリスクが伴います。
そのため、 通信や保存時のデータ暗号化、アクセスログの自動記録、IP制限や多要素認証など のセキュリティ機能を確認しましょう。
また、国内の法令や業界基準(ISMSやISO27001など)への準拠も重要です。
特に医療・金融・教育業界などでは、法的な要件を満たすかどうかが導入可否を左右します。
運用・導入・コスト面での視点
コスト面では、初期費用だけでなく「1ユーザーあたりの月額料金」や「容量追加費用」にも注目が必要です。
特に 中小企業では、少人数利用から始めて段階的に拡張できるプランが現実的 です。
また、管理者の設定や権限管理が複雑すぎると運用負担が増えるため、UIの分かりやすさやサポート体制も比較しましょう。
導入後に操作方法の教育やルール整備が必要になるケースも多いため、運用コストも考慮して選定するのが理想です
よくある失敗・注意点
- 「無料プランで十分」と判断してしまう
⇒無料版では容量制限やアクセス管理機能が不十分なことが多く、法人利用には不向き - 社内ルールの未整備
⇒運用指針が社内に浸透せず、結局メール添付へ逆戻りするケースがある - アクセス権の設定が適切でない
⇒機密情報が誰でも閲覧できる状態になり、情報漏えいのリスクが高まる
導入時は「機能・運用・ルール」をセットで設計することが大切で、 システムだけに頼らず“運用設計”を重視する ことが成功のポイントです。
利用シーン別おすすめのサービスタイプ
少人数/スタートアップ向け
少人数のチームや創業間もないスタートアップには、 シンプルで低コストなファイル共有サービスが最適 です。
導入・運用の手間が少なく、無料または数百円から始められるプランも多く存在します。
たとえば「Google Drive」や「Dropbox Business」は、アカウント登録だけで利用でき、端末を問わずアクセス可能です。
重要なのは、コストを抑えつつ業務効率を上げること。将来的にチームが拡大してもスムーズに上位プランへ移行できる拡張性の高いサービスを選ぶことで、成長フェーズにも対応できます。
大容量データを扱う制作/設計部門向け
デザイン・動画・CADデータなどの大容量ファイルを扱う部門では、 ストレージ容量と転送速度が重要 です。
こうした業務には「Box」や「OneDrive for Business」などの高容量プランが適しています。特にBoxはファイルのバージョン管理や共同編集機能に優れ、チーム全体で効率的に作業が可能です。
また、アップロード制限や転送上限を気にせず使える環境を整えることで、納期遅延やデータ破損といったトラブルも防げます。
安定した通信環境と十分な容量を確保することが生産性向上の鍵です。
高セキュリティ・機密情報を扱う企業向け
顧客データや設計図、契約書など機密性の高い情報を扱う企業では、 セキュリティ特化型の共有サービスが求められます 。
「クリプト便」は、通信・保存時の暗号化、IP制限、ワンタイムパスワード発行など高度な安全対策を備えています。また、操作ログの記録や権限設定が細かく行えるため、社内監査にも対応可能です。
セキュリティ対策を怠ると情報漏えいによる信頼損失につながるため、機能だけでなく安全基準を満たしているかを確認して導入しましょう。
取引先・外部と頻繁に共有する必要がある企業向け
社外とのやり取りが多い企業には、 外部共有機能に優れたサービス がおすすめです。
たとえば「Dropbox Business」や「Box」は、共有リンクにパスワード設定や有効期限を設けられるため、セキュアにファイルを送受信できます。
取引先ごとにフォルダを分け、アクセス権限を制限することで情報管理もしやすくなります。また、共有先がクラウド未導入でもURL経由で受け取れる点も便利です。
社外との共同作業を安全かつスムーズに行うためには、「共有範囲の制御」と「操作性」のバランスが欠かせません。
法人向けファイル共有サービスおすすめ5選【比較表】
主要サービス比較表
| 主な特徴 | 料金 | |
|---|---|---|
| Box | 高いセキュリティ | 月額:1,980円(税込)/ユーザー~ (最低購入ユーザー数3名) |
| Dropbox Business | シンプルなUIと高速同期。 大容量ファイルの送信もスムーズ |
月額:1,500円(税込)/ユーザー~ ※個人向けプランは1,200円(税込)~ ※税表示なし |
| Google Drive (Google Workspace) |
Gmailやスプレッドシート等と連携可能。 操作が直感的 |
月額:800円/ユーザー~ ※税表示なし |
| OneDrive for Business | Microsoft 365連携でOffice利用者に最適。 | 月額:1,689円(税込)/ユーザー~ ※OneDriveのみは823円(税込)/ユーザー~ ※年間契約 |
| クリプト便 | 官公庁・金融機関も導入。 送信専用型で極めて安全 |
月額:1,000円/ユーザー~ ※税表示なし ※ユーザ数・送信数を超過した場合、超過料金が発生 |
おすすめサービスの特徴と強み
Box
Box最大の強みは、機密性の高さです。監査ログやアクセス制御機能、エンドツーエンドのデータ保護を提供し、情報漏えいを防止。
7段階の権限レベル、パスワード保護、アクセス制限などによる厳格な制御が可能 で、HIPAAやFedRAMPなどの規制要件も満たします。また、アップロードされたコンテンツは暗号化されます。
さらに、Box AIの活用、Box Signによるネイティブな電子サイン、多様な業務アプリとの連携、最新バージョンを保証するバージョン管理機能 により、重要な業務プロセスを加速します。
Dropbox Business
Dropboxでは、 コンテンツの保存、PDFの編集、動画の共有、書類への電子署名(Sign)など、重要な業務プロセスを1か所で完了 できます。
3TB以上のストレージとバックアップ機能のほか、ファイルの復元、パスワード保護、透かし、閲覧者履歴などのセキュリティ機能も利用可能です。
また、Transferによる大容量ファイルの安全な送信もできるほか、Replayを活用して会議を減らし、動画プロジェクトのフィードバックや承認プロセスの効率化にも寄与します。
Google Drive(Google Workspace)
Google ドライブは、 リアルタイムな共同編集を強みとし、リモートワークや多拠点間の情報共有もスムーズ に行えます。
特筆すべきは、AIを活用した効率化です。Gemini in Google ドライブにより、複数のドキュメントの要約や情報の統合が可能となり、AIを活用した検索で関連性の高い結果を迅速に表示します。
スプレッドシートやドキュメントなど、Google提供の各種ツールと柔軟に連携できる点も魅力です。
OneDrive for Business
OneDrive for Businessは、各種Officeアプリと連携しており、WordやExcelをクラウド上で共有・編集可能です。
特に、既存のMicrosoft環境を活かしたい企業に最適です。
クリプト便
クリプト便は、機密情報の安全な受け渡しに特化したファイル転送・共有サービスです。 「送信専用」で情報漏えいリスクを最小化し、官公庁や金融機関でも利用される堅牢なセキュリティ を誇ります。
サービス開始から20年以上の実績があり、高セキュリティが求められる金融業界を中心に採用されています。
また、メールライクな操作画面と、ファイル転送とファイル共有の使い分け機能により、利便性を確保しつつ、誤操作などの人的要因による事故リスクを最小化できる点も魅力です。
自社に合ったサービスを見つけるための選定ポイント
ファイル共有サービスは「すべての企業に最適な1社」が存在するわけではありません。コスト・セキュリティ・操作性の3要素をバランスよく比較することが大切です。
例えば、コスト重視ならセキュアSAMBA、セキュリティ優先ならクリプト便やBizストレージが有力候補です。また、既存のGoogle WorkspaceやMicrosoft 365を活用している企業は、それぞれの連携サービスを選ぶことで運用コストを抑えられます。最終的には「どんな共有が多いか」「誰と共有するか」を明確にし、自社に最もフィットするプランを選ぶことが重要です。
導入から運用まで:設計〜定着までのステップ
-
STEP.1
社内現状の整理(共有フローと課題の把握)
まず取り組むべきは、現在どのようにファイル共有が行われているかを可視化することです。
メール添付やUSBなど、旧来の方法が残っている場合はセキュリティリスクが高い状態といえます。
部署ごとに使用しているツールやファイル形式を洗い出し、重複や属人化が起きていないかを確認しましょう。
現状を把握することで、「どの機能が必要か」「どの範囲で共有すべきか」が明確になります。導入の第一歩は、課題を整理し、改善すべき業務フローを定義することです。
-
STEP.2
サービス選定と試験導入(トライアルの活用)
現状把握ができたら、候補となる複数のサービスを比較し、実際にトライアルを行いましょう。
多くの法人向けサービスでは無料体験期間が設けられており、UIの使いやすさやアクセス制御のしやすさを確認できます。
また、ファイルのアップロード速度や共同編集の安定性など、運用時に影響する要素も事前に検証しておくと安心です。
特に大規模導入を予定している場合は、一部部署で試験導入し、課題や要望をフィードバックすることで、本格導入時のトラブルを防げます。
-
STEP.3
運用ルール策定と社内浸透
ツールを導入しても、運用ルールが定まらなければ定着しません。共有フォルダの命名規則、アクセス権限、外部共有の可否などを明文化し、社内に浸透させることが大切です。
あわせて、担当者の教育も重要です。操作マニュアルを整備したり、定期的に研修を行うことで、利用者の習熟度を高められます。
管理者がルールを統一的に運用できる環境をつくることで、ファイル共有のトラブルや重複登録を防ぎ、業務全体の効率化につながります。
-
STEP.4
定着化・効果測定(改善サイクルの構築)
ファイル共有サービスの導入はゴールではなく、運用を安定させて成果を出すことが目的です。
定期的に「共有時間の短縮」「誤送信件数の減少」「検索効率の向上」などのKPIを設定し、効果を測定しましょう。
利用状況をログから分析することで、使われていない機能や改善余地が見えてきます。
課題が見つかった場合は、運用ルールの見直しや権限再設定を行い、より最適な運用へとブラッシュアップしていくことが重要です。
-
STEP.5
セキュリティ・継続改善(おまかせサイバーみまもりとの連携)
運用が軌道に乗った後も、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクは常に存在します。
安全で継続的な運用体制を整えるためには、ツール導入と併せてセキュリティ運用支援サービスの活用が有効です。
例えば、NTT東日本が提供する「おまかせサイバーみまもり」はファイル共有サービスの利用状況を監視し、不正アクセスや異常操作を早期検知することで、情報漏えいを未然に防ぎます。
セキュリティ対策なら「おまかせサイバーみまもり」
おまかせサイバーみまもりは、NTT東日本が提供する法人向けのUTM(統合脅威管理)です。
専用BOXをネットワークの出入口に設置するだけで手軽にセキュリティ対策でき、通信のプロが通信状況のモニタリングや有事の際の復旧までサポートいたします。
標的型攻撃メールやウイルスへの対策はもちろん、フィッシングやスパイウェアまで幅広く対策できます。
なお、最新のパターンファイルへ自動更新されるため、常に社内のセキュリティ環境を最新状態に保つことが可能です。

よくある質問(FAQ)
A
多くのファイル共有サービスでは無料プランが用意されていますが、法人利用には制約が多いのが実情です。無料プランでは容量制限や共有リンク数の上限があり、アクセス権限の細分化や操作ログ管理など、セキュリティ面で必要な機能が不足しています。特に顧客情報や契約書など機密データを扱う場合は、無料版を避け、法人向けの有料プランで安全性と管理機能を確保するのが安心です。
A
はい、多くの法人向けファイル共有サービスでは、既存の社内サーバーやNASからのデータ移行に対応しています。ツールによっては自動移行ツールやサポートが用意されており、業務を止めずにクラウド環境へスムーズに切り替えることが可能です。ただし、ファイル構成や権限設定の再設計が必要になるケースもあります。事前に「どのデータを移行するか」「誰が管理するか」を明確にしておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズなクラウド移行が実現します。
A
法人でファイル共有サービスを導入する場合、ISO27001(ISMS)などの国際的なセキュリティ認証を取得しているベンダーを選ぶことをおすすめします。これらの認証は、情報管理体制や運用手順が国際基準に適合していることの証明です。特に顧客データや社外秘情報を扱う業種では、社外からの信頼にも直結します。
A
取引先と共有する場合は、アクセス制限・パスワード保護・期限設定ができる機能を活用しましょう。共有リンクを発行する際は、閲覧権限のみに制限したり、ダウンロードを禁止することで安全性が高まります。また、共有履歴を残すことで、誰がいつアクセスしたかを追跡できる点も重要です。特に機密データのやり取りでは、暗号化通信(SSL/TLS対応)が必須です。
A
ファイル共有ツールの管理業務を最小限にするには、「監視・ログ管理・権限設定」を自動化できる仕組みを導入することが効果的です。特に中小企業では、IT担当者のリソースが限られるため、外部サービスを活用するのがおすすめです。
まとめ
ファイル共有サービスは、単なるデータ保存ツールではなく、企業の業務効率とセキュリティを支える“インフラ”です。
導入時には、自社の利用目的・共有範囲・必要なセキュリティレベルを明確にし、最適なサービスを選定することが成功の鍵となります。
また、導入後はルール整備と運用体制を構築し、継続的に改善していくことが大切です。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!