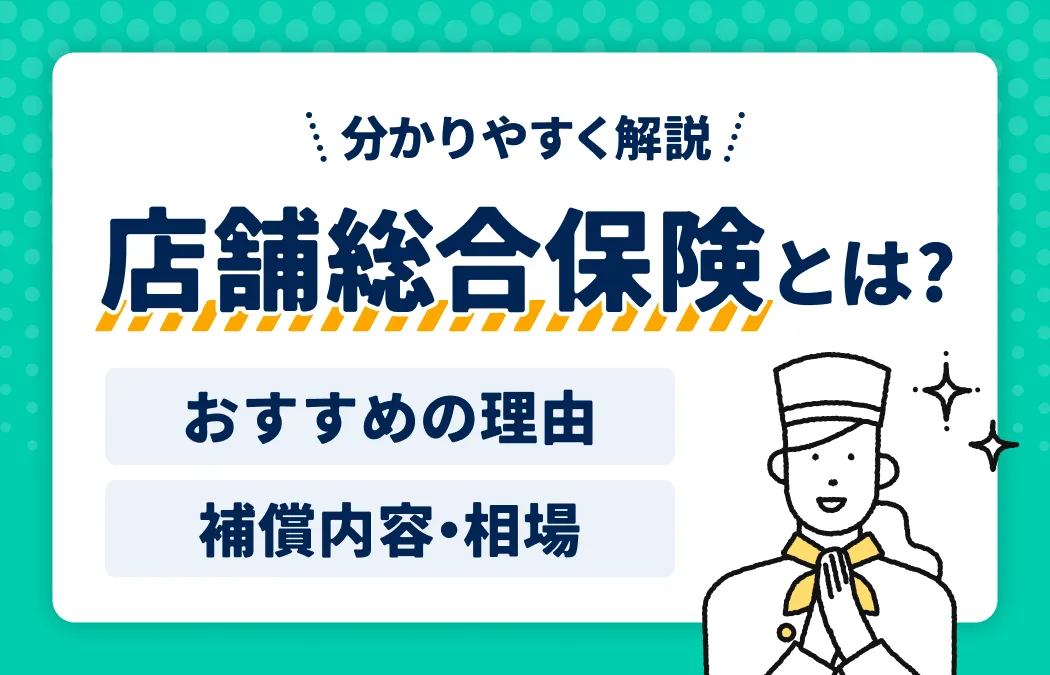「得する掛け方や節税効果はある?」
「個人保険との違いはなに?」
「法人保険とは、契約者を法人とし、被保険者を役員・従業員にする生命保険や医療保険などを指します。
ただし、“節税になる”という認識だけで加入すると、税務上の制限やキャッシュフロー圧迫などの落とし穴もあります。
本記事では、法人保険がもたらす主なメリットを整理したうえで、併せて注意点・リスクも丁寧に解説します。
目次
法人保険とは何か?
法人保険契約の基本構造(契約者/被保険者/受取人)
法人保険とは、契約者を「法人(会社)」とし、 被保険者を「役員や従業員」として契約する保険 です。保険金の受取人は法人または遺族のいずれかで、目的に応じて設定します。
たとえば経営者の死亡時に法人が保険金を受け取る場合、会社はその資金を事業継続費や借入金返済に充てることができます。
このように法人保険は、万が一の備えだけでなく、企業の資金繰り安定や経営リスク対策にも役立ちます。個人向け保険と異なり、契約内容や税務処理が複雑な点が特徴です。
個人保険との違い
法人保険と個人保険の最大の違いは、「目的」と「税務処理」にあります。個人保険は家族の生活保障が目的で、保険料は自己負担・非経費計上です。
一方、 法人保険では会社の経費(損金)として保険料の一部を計上できる場合があり、節税効果を得られる のが特徴です。
また、保険金の受取人が法人であれば、万が一の際に事業継続資金や退職金原資として活用できます。
つまり、法人保険は「企業経営を守る仕組み」として設計されており、経営上のリスクマネジメントと税務対策の両面で効果を発揮します。
法人保険に含まれる主な種類
法人保険にはさまざまな種類があります。主流となるのは「生命保険」「医療・がん保険」「損害保険」の3つです。
- 生命保険:経営者や役員の死亡リスクに備えるもので、解約返戻金を退職金や事業承継資金に充てるケースが一般的
- 医療・がん保険:役員・従業員の病気や入院リスクに対応し、福利厚生の一環として導入される
- 損害保険:火災や事故などの物的損害を補償するもので、事業継続のリスクを軽減
これらを 目的に応じて組み合わせることで、経営の安定と従業員の安心を両立できる のが法人保険の強みです。
法人保険導入の主なメリット
- 事業保障・リスクマネジメント
- 退職金・福利厚生支援
- 事業承継・相続対策への活用
- 節税・損金算入によるキャッシュフロー改善効果
事業保障・リスクマネジメント
法人保険の最大の目的は、 経営リスクへの備え です。
経営者や主要役員が病気や事故などで突然不在となった場合、企業は売上減少や借入金返済など深刻な影響を受けることがあります。
法人保険に加入しておけば、万が一の際に保険金を事業継続資金として活用でき、会社の経営を守ることができます。
また、契約者貸付制度を利用すれば、急な資金需要にも対応可能です。つまり法人保険は、突発的なリスクを最小限に抑え、安定的な経営を支える“経営防衛ツール”として機能します。
退職金・福利厚生支援
法人保険は、退職金や福利厚生の財源としても活用できます。たとえば、 経営者や役員の退職時に解約返戻金を受け取り、それを退職金として支給するケース があります。
定期的に積み立てることで、将来的な退職金準備を効率的に進められるのがメリットです。
また、医療保険やがん保険などを法人契約することで、従業員の健康リスクに備える福利厚生制度としても機能します。
従業員満足度の向上や離職防止にもつながるため、「人を守り、企業を守る」仕組みとして注目されています。
事業承継・相続対策への活用
法人保険は、事業承継や相続対策にも有効です。
経営者が死亡した際に、法人が受け取る保険金を 「自社株の買い取り資金」や「相続税の納税資金」に充てることで、スムーズな事業承継を実現 できます。
特に中小企業では、後継者が高額な相続税を一括で支払えないケースも多く、保険金を活用することで事業の継続性を守れます。
さらに、事前に名義変更を行うことで、税務上の負担を分散する方法もあります。事業承継対策としての法人保険は、資金計画の安定化に大きく貢献します。

節税・損金算入によるキャッシュフロー改善効果
法人保険のもう一つの重要なメリットは、節税効果です。一定条件を満たす保険商品では、 保険料の一部または全額を「損金」として計上でき、課税所得を減らすことが可能 です。
これにより、税負担を軽減しつつ、実質的なキャッシュフロー改善につながります。
ただし、税制改正により損金算入が制限されるケースもあるため、制度を正しく理解して活用することが大切です。
節税目的だけでなく、長期的な資金計画とリスク対策を両立させる視点が求められます。
法人保険のリスク・注意点
- キャッシュフロー悪化リスク
- 解約返戻金が払い込み保険料を下回る可能性
- 税務上の課税・益金参入リスク
- 制度改正・運用コストリスク
キャッシュフロー悪化リスク
法人保険は将来の備えとして有効ですが、短期的には資金繰りを圧迫するリスクもあります。
特に長期契約の場合、 毎月の保険料支払いが固定費として重くのしかかり、業績悪化時に負担となるケース があります。
さらに、節税目的で加入した場合でも、解約時に返戻金が益金として課税されることがあり、結果的にキャッシュフローが悪化することもあります。
契約前には、毎月の支払額だけでなく、全期間を通じた支出計画を立て、将来的な資金バランスを確認しておくことが重要です。
解約返戻金が払い込み保険料を下回る可能性
法人保険では、解約のタイミングによっては「支払った保険料より返戻金が少ない」ケースがあります。特に 契約初期の解約では返戻率が低く、損失を生むことも珍しくありません 。
たとえば、10年契約の保険を3年で解約すると、返戻率が50%未満になる場合もあります。
解約返戻金のピーク時期(解約返戻率が最も高い時期)を把握し、その時期を目安に資金計画を立てることが大切です。
短期的な資金需要で安易に解約するのではなく、長期的視点での運用を意識する必要があります。
税務上の課税・益金参入リスク
法人保険の保険金や解約返戻金は、税務上「益金(収益)」として扱われることがあります。
たとえば、 解約返戻金を受け取ると、会計上は一時的な利益が発生し、法人税の課税対象に なります。結果として、当初の節税効果が帳消しになるケースも少なくありません。
また、損金算入できる保険とできない保険の区別が複雑で、税務上の処理を誤ると追徴課税のリスクもあります。
契約時は税理士などの専門家に確認し、税制改正にも対応できるよう最新情報を把握しておくことが欠かせません。
制度改正・運用コストリスク
法人保険は、税制改正や制度変更の影響を受けやすい商品です。特に 2019年以降、国税庁による「損金算入ルールの見直し」により、多くの節税型保険が制限されました 。
今後も制度変更により、損金算入範囲や返戻率のルールが変わる可能性があります。
また、保険会社によっては手数料や運用管理費が高く設定されていることもあるため、長期契約時の実質的コストを確認することが重要です。
制度の変化やコスト構造を理解したうえで、継続的に見直しを行う姿勢が求められます。
節税視点:制度ルール・活用方法を理解する
損金算入制度とその制限
法人保険の節税効果は、保険料を「損金」として経費計上できる点にあります。
損金算入とは、 法人が支払う保険料の一部または全額を経費扱いにすることで、課税所得を減らす制度 です。
ただし、すべての保険が対象ではなく、契約内容によって損金割合は異なります。たとえば「長期平準定期保険」は保険金額や返戻率によって一部のみ損金算入できるケースもあります。
税制改正後は、返戻率が高い商品ほど損金扱いの制限が厳しくなっており、契約前に税務ルールを確認することが重要です。
「30万円特例」・小口保険料制度の活用条件
中小企業が法人保険を活用する際に知っておきたいのが「30万円特例」です。これは、 年間保険料が30万円以下の少額短期保険について、全額を損金算入できる制度 です。
たとえば、従業員向けの医療保険やがん保険などをこの範囲で契約すれば、節税と福利厚生を両立できます。
ただし、複数契約を組み合わせて年間保険料が上限を超える場合は対象外となるため、注意が必要です。
小口保険は柔軟性が高く、資金繰りに負担をかけにくいため、初めて法人保険を導入する企業にも向いています。
課税繰延の仕組みと限界
法人保険の節税効果は、実際には「課税の繰延(先送り)」である点を理解しておく必要があります。
保険料を支払う段階では損金として経費計上できる一方、解約時に返戻金を受け取ると益金として課税される仕組みです。
つまり、税負担を“減らす”のではなく、“時期をずらす”だけの効果にとどまる場合もあります。
短期で解約すると課税額が増えるため、長期運用を前提とした計画が重要です。
税制改正の影響
法人保険の税制は頻繁に改正されており、過去のルールがそのまま通用するとは限りません 。
たとえば2019年には、返戻率が高い「節税型保険」に対し、損金算入が大幅に制限されました。これにより、多くの企業が想定していた節税効果を得られなくなりました。
今後も国税庁の方針次第で制度が変更される可能性があるため、最新の税務情報を常に確認することが重要です。
特に保険の目的が「節税」に偏っている場合、改正の影響を受けやすいため、「経営リスク対策」や「退職金準備」など複数の目的で契約するのが望ましいです。
保険種類別のメリット・活用ケース比較
定期保険
定期保険は、一定期間だけ保障を受けられるタイプの法人保険です。特に 「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」は、経営者や役員の死亡リスクに備える目的 で活用されます。
長期平準定期は契約期間中の保障額が一定で、安定した経営防衛が可能です。一方、逓増定期は年々保険金額が上昇し、業績拡大期のリスク対応に適しています。
いずれも保険料の一部を損金算入できる場合があり、節税と保障を両立できます。ただし、解約返戻率や税務処理の条件が複雑なため、契約時には専門家の確認が欠かせません。
養老保険・終身保険
養老保険は 「貯蓄性」が高い法人保険で、満期まで保険料を支払うと保険金を受け取れる点が特徴 です。
満期保険金を退職金や事業承継資金として活用する企業も多く、安定的な資産形成が可能です。
終身保険は保障期間が一生涯続くため、経営者の万が一の際に確実に保険金を受け取れるのが強みです。一方で、いずれも保険料が高額になりやすく、キャッシュフローへの影響を考慮する必要があります。
保障重視なら終身保険、資産形成重視なら養老保険といったように、目的に応じた選択が重要です。
医療/がん/就業不能保険
医療・がん・就業不能保険は、役員や従業員の健康リスクに備えるタイプです。
法人契約にすることで、 病気や入院時の費用補填を企業がサポートでき、福利厚生の充実につながります 。
特に中小企業では、優秀な人材の定着や採用競争力の強化にも効果的です。また、保険料の一部を損金算入できる場合もあり、節税メリットも得られます。
ただし、従業員個人の保障目的に偏ると経費として認められないことがあるため、契約時には「事業上の必要性」が明確であることが前提となります。
損害保険(事業リスク対応型)
損害保険は、 火災・盗難・自然災害などの物的損害や、取引先への賠償責任リスクに備える法人向け保険 です。
たとえば店舗やオフィス、工場などを所有する企業では、火災保険や施設賠償責任保険が基本的な備えとなります。
こうした損害保険は、経営上の不測の事態による損失を最小限に抑える重要な役割を果たします。
法人保険の中でも即効性の高いリスク対策手段であり、他の生命保険型商品と併用することで、経営リスクを多角的にカバーできます。
複合型・特約付き商品(死亡+医療など)
最近では、複数の保障を組み合わせた「複合型保険」や「特約付き保険」も増えています。
たとえば、 死亡保障に加えて医療・がん保障を付けることで、一つの契約で幅広いリスクをカバーできます 。
特約を活用すれば、契約内容を柔軟にカスタマイズでき、自社のニーズに最適な保障設計が可能です。
特に中小企業では、経営者一人の健康リスクが事業継続に直結するため、こうした複合型保険は高いコストパフォーマンスを発揮します。
導入判断のポイントとプロセス
自社のリスク・資金状況の棚卸
法人保険を導入する前に、まず行うべきは「自社のリスクと資金状況の棚卸」です。
経営者の万が一に備えるべきか、 「退職金準備が優先か」「節税を重視するのか」など、目的によって最適な保険は異なります 。
また、毎月の保険料支払がキャッシュフローに与える影響を把握することも重要です。特に中小企業では、急な資金繰りの変動が経営に直結します。
導入前に「想定リスク」「必要保障額」「支払い可能額」を可視化し、保険導入が本当に経営にプラスかどうかを慎重に判断することが成功の第一歩です。
費用対効果シミュレーション
法人保険は長期契約が多く、費用対効果のシミュレーションが欠かせません。
たとえば、 10年間で支払う総保険料と、解約返戻金・節税額・保障額の合計を比較 し、どの程度の経済的メリットがあるかを把握します。
表面的な返戻率だけでなく、支払期間中の資金拘束リスクや、解約時の課税も考慮することが大切です。
また、複数の保険商品を比較する際は、同条件での返戻率・保障内容・税務処理を一覧化すると判断しやすくなります。定量的な分析を行うことで、導入効果をより明確に評価できます。
複数保険商品の比較評価視点
法人保険を選ぶ際には、 返戻率や保障内容だけでなく、経理処理方法まで含めて比較する必要があります 。
たとえば、返戻率が高くても損金算入できない保険では、短期的な節税効果は得られません。逆に損金算入できる保険でも、返戻率が低ければ資産形成効果は限定的です。
さらに、保険金の受取時に益金処理が必要かどうかも重要な判断軸です。
複数の商品を比較表にまとめ、目的ごとに「保障重視型」「節税型」「資産形成型」に分類して検討すると、最適なプランを選びやすくなります。
導入後の定期見直し・解約判断基準
法人保険は一度加入すれば終わりではなく、定期的な見直しが必要です。業績の変化や経営方針の転換により、当初の目的と合わなくなることもあります。
特に、 保険料負担が重くなっていないか、解約返戻率のピーク時期を過ぎていないかなどを定期的に確認 することが大切です。
また、税制改正や保険商品の更新も見直しのタイミングです。解約を検討する際は、返戻金に対する課税額をシミュレーションし、手取り額を正確に把握したうえで判断しましょう。
適切な運用管理が、法人保険を最大限に活かす鍵となります。
他施策との併用・補完戦略
倒産防止共済との併用
法人保険は「倒産防止共済」との併用で、より強力な経営リスク対策になります。
倒産防止共済(中小企業倒産防止共済制度)は、 取引先が倒産した際に貸付を受けられる制度 で、保険とは異なる形で資金を確保できます。
法人保険では経営者や役員のリスクに備え、共済では取引先リスクをカバーできるため、両者を組み合わせることで経営の安定性が大きく高まります。
また、共済掛金も損金算入できるため、節税面でも相乗効果があります。単体ではカバーできないリスクを補完し合うのが、この併用戦略の強みです。
役員報酬・退職給付制度・小規模企業共済との使い分け
法人保険は、 他の退職金準備制度と組み合わせて運用することで、より柔軟な資金計画が立てられます 。
たとえば、経営者個人向けの「小規模企業共済」は退職金原資を個人単位で積み立てられる制度で、法人保険と併用することで、法人・個人双方の退職金対策が可能です。
また、役員報酬制度や退職給付制度とバランスをとることで、税負担を平準化できます。
目的ごとに制度を整理し、「会社として備える部分」と「個人として積み立てる部分」を明確に区別することが、賢いリスク分散のポイントです。
社内資金積立・運用とのバランス検討
法人保険を導入する際は、社内留保や積立資金とのバランスも重要です。すべてを保険で賄うのではなく、手元資金を一定割合残しておくことで、解約リスクを抑えられます。
特に 景気変動や売上減少期において、保険料支払いが固定費化すると経営を圧迫する恐れ があります。
そのため、保険・共済・現預金・投資といった複数の資産運用手段を組み合わせ、リスク分散を図るのが理想です。
法人保険は「リスク対策+資金運用」の一手段として位置づけ、全体の財務バランスを見据えた導入を心がけましょう。
ケーススタディ・数値シミュレーション
中小企業の導入モデル(保険料・返戻金・税務効果例)
社員20名規模の中小企業A社は、 ”経営者のリスク対策と退職金準備”を目的とし、長期平準定期保険(保険期間15年・年間保険料120万円)に加入 しました。
上記のケースでは、年間保険料の1/2を損金算入できるため、課税所得を抑えつつ将来の返戻金を積み立てられます。
10年経過時点での解約返戻率は約70%で、解約時には返戻金約840万円を受け取ることが可能です。
この資金を退職金に充てることで、実質的な税負担を平準化できます。節税とリスク備えを両立できる好例といえるでしょう。
リスクシナリオ比較
法人保険の有無による影響を比較すると、その重要性がより明確になります。たとえば、経営者が急逝した場合、保険未加入の企業と保険導入企業では以下のような差があります。
- 保険未加入の企業:事業資金や借入返済に窮するリスクが高まる
- 保険導入企業の場合:死亡保険金により即座に資金を確保でき、従業員の給与支払や取引先対応を継続可能
また、 倒産リスクの低下は信用維持にもつながり、取引先や金融機関からの信頼を保てる 点も大きなメリットです。
このように、法人保険は「もしも」の際に企業を守る防衛線として機能し、経営の安定に直結します。
失敗例・導入トラブル事例と回避策
法人保険を誤って活用した結果、損失を招くケースとしてよくあるのが、 節税目的だけで高返戻率の保険に加入し、途中解約によって返戻金が想定を下回るケース です。
また、損金算入ルールの変更を把握しておらず、解約時に課税が発生して想定外の納税負担が生じることもあります。
これらを防ぐには、契約前に「保険期間」「返戻率のピーク」「税務リスク」を明確に理解し、長期的視点で運用することが重要です。
短期的な節税よりも、経営安定という本来目的に立ち返ることが成功の鍵です。
導入後に押さえる運用と見直しポイント
定期モニタリング指標
法人保険を導入した後は、契約を放置せず、定期的にモニタリングすることが重要です。 確認すべきは「解約返戻率」「保険料負担率」「業績変動への耐性」などの指標 です。
たとえば、返戻率が上昇するタイミングを把握すれば、解約や満期の判断が最適化できます。また、保険料が経費全体に占める割合が高すぎると、資金繰りを圧迫する恐れがあります。
年に1度は保険会社や税理士とともに契約内容を見直し、会社の経営状況に合わせた調整を行うことで、リスクとコストのバランスを保つことができます。
契約変更・追加の考え方
企業の成長段階や事業構造の変化に応じて、法人保険の内容を変更・追加 することも検討すべきです。
たとえば、従業員数が増加した場合は医療保険や福利厚生型保険の拡充を行い、事業規模が拡大した際には保障額を見直すとよいでしょう。
また、新たなリスクに対応するために特約を追加するのも有効です。ただし、安易な追加契約はコスト過多を招くため、既存契約との重複を避けることが大切です。
経営戦略と連動させた保険設計を行うことで、法人保険をより効果的な経営ツールとして活用できます。
解約リスクを最小化するタイミング戦略
法人保険の解約タイミングを誤ると、大きな損失につながることがあります。
特に、 返戻率がピークを迎える前に解約すると、支払った保険料の多くを回収できず、益金計上により税負担が増すケースも あります。
解約を検討する際は、必ず返戻率の推移表を確認し、ピーク時期以降に解約するのが基本です。
また、複数契約を保有している場合は、資金需要に応じて一部のみ解約するなど、段階的に調整する方法も有効です。
税務申告時の扱い・申告注意点
法人保険の保険料や解約返戻金は、税務申告時の処理を誤るとトラブルにつながります。
保険料の損金算入割合や益金算入の扱いは、契約内容によって異なるため、会計処理を統一することが大切です。
特に 解約時には、返戻金を「雑収入」として正しく申告しなければ、税務署から指摘を受ける可能性 があります。
さらに、退職金に充てた場合は、支給額の根拠となる契約情報を明示しておくことが望ましいです。税務リスクを防ぐためにも、申告前に税理士へ確認し、正確な処理を徹底しましょう。
まとめ
法人保険導入の「メリットとリスク」の再整理
法人保険は、経営者や役員の万が一に備えるだけでなく、 退職金準備や事業承継、福利厚生、節税など、多面的な経営メリット をもたらします。
一方で、保険料負担によるキャッシュフローの圧迫や、税制改正による損金制限など、注意すべきリスクも存在します。
重要なのは「なぜ導入するのか」を明確にし、自社に合った目的とスキームを選定することです。
法人保険は単なる節税商品ではなく、“経営を安定化させる戦略ツール”として、計画的に活用することが成功の鍵となります。
自社にとって導入すべきかの判断チェックリスト
法人保険の導入可否を判断するには、以下の観点をチェックしてみましょう。該当する項目が多いほど、法人保険を導入する意義が高いといえます。
- 経営者・役員のリスク備えが必要か:万が一の際に事業継続資金を確保できるか
- 退職金・事業承継の計画があるか:解約返戻金を資金に充てられるか
- 現在のキャッシュフローに余裕があるか:毎月の保険料支払が経営を圧迫しないか
- 節税よりも経営安定を重視しているか:損金算入だけを目的にしていないか
- 税理士・保険会社と連携できる体制があるか:運用・見直しを継続的に行えるか
法人保険は契約内容が複雑であり、企業規模・目的・財務状況によって最適なプランは異なります。自社にとって最も効果的な保険を見極めるためには、専門家への相談が不可欠です。
経営防衛・節税・事業承継など、どの視点を重視すべきかを整理しながら、最適な契約プランを検討してみましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!