目次
▼この記事で紹介している商品
保育園・幼稚園でICTシステムを導入すべき理由
ICTシステムとは、情報・通信を利用したシステムの総称で、いわゆるITと同じ意味です。
保育園・幼稚園の業務は保育、事務、保護者対応と多岐にわたります。昨今、待機児童の問題がクローズアップされていますが、この問題の原因のひとつには保育士不足があると言われています。
保育士が不足する理由のひとつは待遇が良いとは言えない状況のため、保育士のなり手が少ないことが挙げられます。本来保育園・幼稚園の経営は社会に貢献するものです。しかし肝心の保育士の待遇が悪ければ、社会貢献もままなりません。
保育士の待遇改善には経営の改善が急務ですが、いまだ紙の台帳などに頼った業務をしていないでしょうか。紙に頼った業務では紙から紙への転記の手間や複数の台帳にまたがる記録の閲覧、日誌の作成などの効率がとても悪いです。保育士の残業常態化の原因になると考えられます。
また保護者対応においても電話や連絡の手間がかかります。事務処理では保育料の計算・請求などの業務に大きな時間を割くこともあるでしょう。
ICTシステムを導入すれば、これらの業務はかなり改善され、残業時間の短縮や有給消化率の向上につながり、経営と保育士の待遇改善に寄与します。
ペーパーレス化にも役立つため、ICTシステムを導入しない手はありません。
保育園・幼稚園向けICTシステムCoDMON(コドモン)
CoDMON(コドモン)は保育園・幼稚園向けのICTシステムで、保育士や事務、経営業務をパソコンやスマホ、タブレットなどで行えるようになります。紙の台帳から解放され、転記の手間もかなり少なくなります。
また保護者専用アプリも用意されており、保護者への連絡や欠席・延長の申請もスムーズになります。
ICT補助金の対象となるCoDMON(コドモン)
保育園や幼稚園、中小企業・小規模事業者等の業務効率化には自治体や国から補助金が出ることになっています。CoDMON(コドモン)は補助金の交付対象となるICTシステムのため、経費的な面でも導入のハードルはそれほど高くありません。ここでは補助金や補助金の種類を解説します。
適用されるICT補助金の種類解説
コドモンの導入に際して受けられる補助金には以下のものがあります。
・IT導入補助金
・職場意識改善助成金
補助金は保育園・幼稚園の業務改善やICTシステム導入により売上アップや経費削減、保育士の待遇改善などを目的としたものです。
補助金ごとに交付要件が異なりますが、すべてコドモンの導入に当たって受けられる補助金です。
CoDMON(コドモン)でできること
CoDMON(コドモン)が提供する機能、受けられる恩恵を解説します。すべての機能は解説できませんが、経営改善・保育士の業務効率化に大きく寄与する機能をご紹介します。
登降園管理と保育料請求を自動化
登降園、特に登園は朝の混雑を招きます。また園児が帰宅する際、保護者確認などの業務にも追われてしまうでしょう。
コドモンはタッチパネルやICカード、保護者が持つICマネーカードによるタッチで登降園時刻を打刻します。よって混雑解消や登降園時刻の管理業務が簡素化され、業務効率化に貢献します。
また打刻された時間は保育料計算機能と連動しており、請求書まで自動で作成します。保育料計算のために登降園時刻を紙から紙へ転記する手間が省けるため、手間を削減し、ミスも防ぎます。
電話連絡に時間を取られなくなる〜欠席・延長連絡
保護者との電話対応も時間を取られてしまう業務です。コドモンを使えば、保護者からの欠席・延長申請をPCやスマホ、タブレットで受けられるため、電話連絡の手間が省けます。また保護者に向けた連絡も、保護者のスマホにプッシュ通知で連絡できるため、電話に比べて手間が省けます。保護者も無理に電話に出る必要がありません。
質の高い指導案・日誌作成
指導案・日誌作成の業務は週次計画、月次計画などを参照しながら作りますが、紙の台帳では確認の手間が大きいです。コドモンは指導案・日誌作成時に他の台帳と連携が取れるため、他の台帳を確認する手間が軽減されるだけでなく、質の高い指導案・日誌作成に貢献します。
発達記録・健康チェック
発達記録の項目はあらかじめ用意されており、独自にカスタマイズすることも可能です。入力は選択式のためサクサク記録できます。健康チェックの入力も簡素化されており、さらにタブレットで記録可能なことから、子どものそばでリアルタイムに記録できます。
従来の紙記録では、転記の手間がかかるだけでなくミスの原因にもなります。また発達記録や健康チェックは指導案・日誌作成と連携できるため、業務効率が大きく高まります。
職員のシフト作成と出勤管理
職員のシフト作成は事務の中でも面倒な作業です。特に必要な職員数の計算や調整は大変ではないでしょうか。コドモンは必要職員数を自動的に計算し、職員シフトの迅速な作成をサポートします。
また職員の残業管理もできるため、一部の職員に負担がかからないように配慮した職員シフト作成を実現します。
職員同士の情報共有
職員は情報を共有する必要がありますが、日誌や口頭による情報共有では大切な事柄が共有されなかったり、勘違いが発生したりしがちです。コドモンは職員同士の掲示板機能を持っているため、誰でも情報を共有できます。また職員への一斉メールなどICTを活用した情報共有もできます。全体会議などの時間短縮にも繋がるでしょう。
保護者への緊急連絡
保護者への連絡業務は職員にとって大きな負担になりがちです。コドモンは保護者全体・クラスごと・特定の保護者という区分で情報を送信できるため、保護者へのスムーズな連絡が可能です。
連絡帳機能
連絡帳は記入しやすく作られており、保護者から家庭での様子などを受け取ったり、保育園・幼稚園での子どもの様子を保護者に伝えたりできます。
また紙の連絡帳をペーパーレス化できるため、文書を減らし、経費も削減できます。
保護者アンケート機能
さまざまな調査(例えば行事への参加確認など)をコドモンで行えます。紙のアンケートはアンケート用紙の手渡しや集計の手間がかかりますが、コドモンはアンケート結果を自動的に集計するため、業務を大幅に改善します。
行事予定の共有
保護者に向けた情報の中でも重要な行事予定などを共有できます。保護者が行事予定を忘れることを防止するだけでなく、連絡業務を簡素化します。
CoDMON(コドモン)のおすすめポイント
CoDMON(コドモン)はとても使いやすく、サポートも充実しています。ここではコドモンのおすすめポイントを解説します。
画面がシンプルで使いやすい〜音声入力にも対応
コドモンはシンプルな操作で使えるようにデザインされており、わかりやすい画面が特徴です。どの機能も使いやすく作られているため、システム導入後、職員や保護者はスムーズにコドモンを使えるようになるでしょう。
サポートが充実していて安心〜電話で質問もOK
万が一コドモンでわからないことやトラブルがあった場合、電話によるサポートを受けられます。使い方やわからないことを気軽に尋ねられることは、コドモンに慣れないうちは特に重宝するでしょう。
必要な機能だけカスタマイズして取り入れられる
コドモンの機能は豊富ですが、すべての機能を導入することはありません。欲しい機能だけをカスタマイズして導入できます。すべての保育園・幼稚園で活用できるシステムがコドモンです。
コドモンを導入して、経営課題を乗り越える
コドモンは豊富な機能で保育園・幼稚園の経営をサポートします。導入には補助金も使えるため、経費的なハードルはあまり高くありませんし、業務の効率化に大きな威力を発揮します。
保育士、職員だけでなく、保護者の手間も減らします。
経営の効率化や保育士の待遇改善は保育園・幼稚園にとって大きな課題です。この課題を乗り越えるために素晴らしい機能を豊富に備えたシステムがコドモンです。
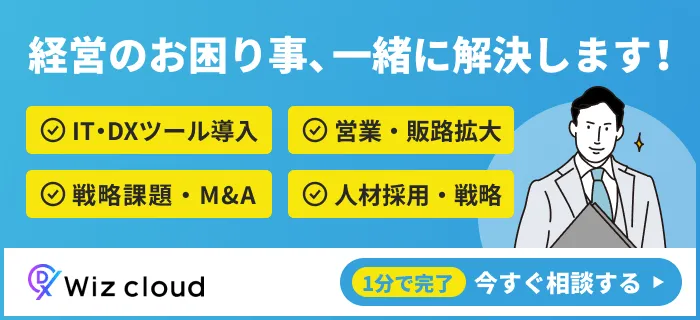

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!













