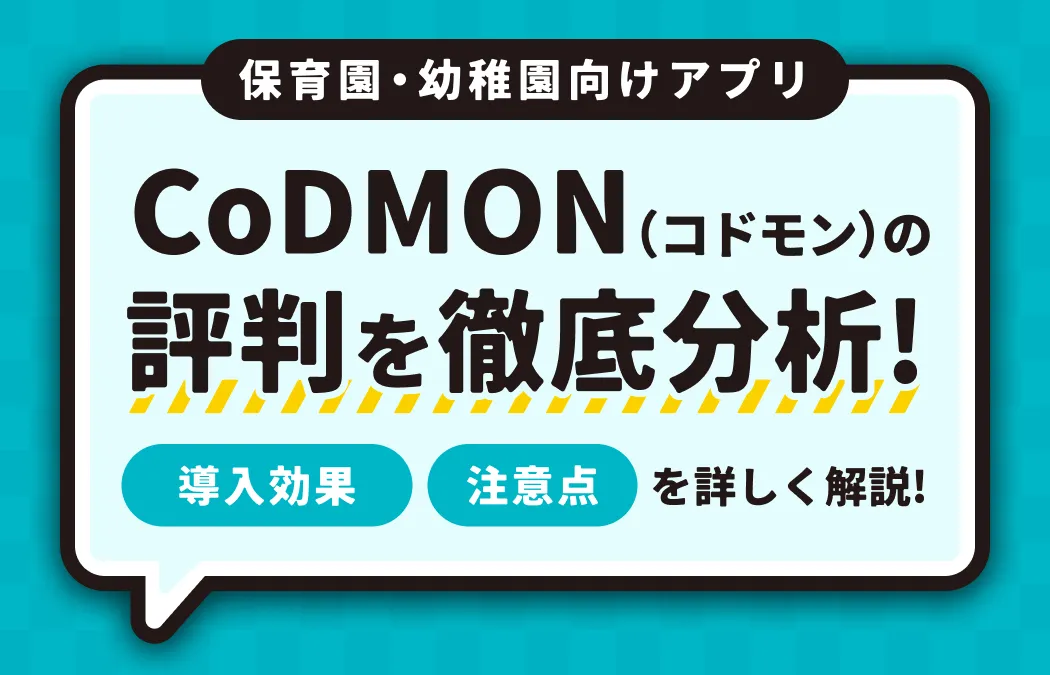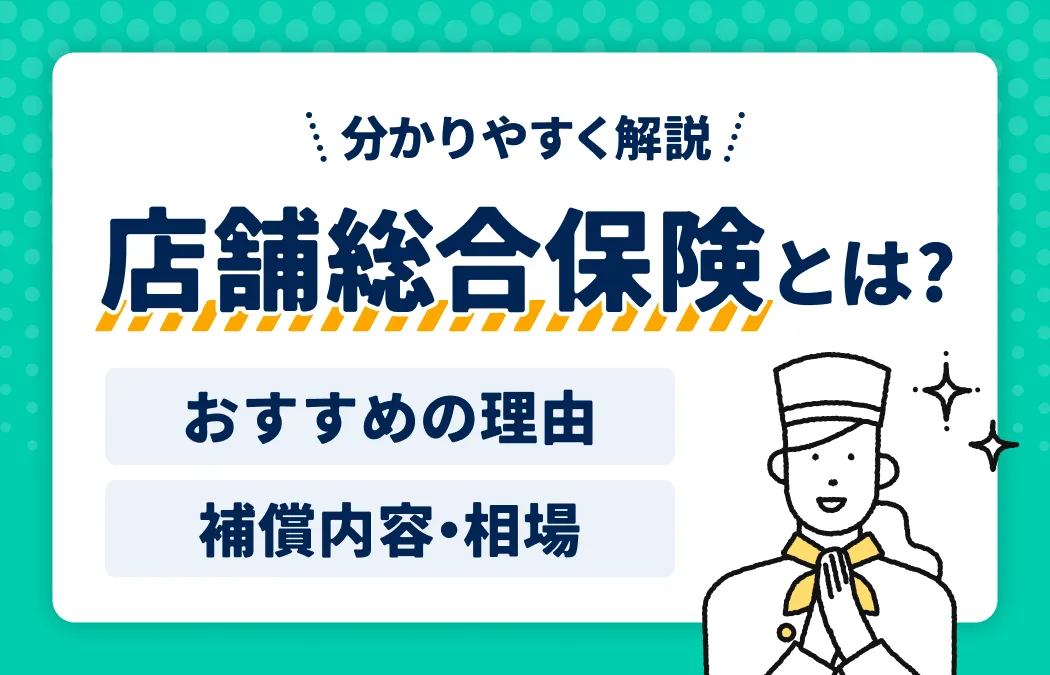「どんな機能が使える?導入効果やメリットは?」
CoDMON(コドモン)は、保育園や幼稚園などの教育施設向けに特化した保育アプリ/SaaS型システムとして、多くの施設や自治体で導入実績があります。
ただ、「実際の評判はどうか?」「費用対効果は出るか?」「運用における注意点は?」など、導入前に不安や疑問を抱えている施設も少なくありません。
本記事では、コドモンの評判・口コミを整理し、他システムと比較した際の強み、導入前に押さえておくべき注意点、活用を成功させるポイントまでを解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
コドモンとは何か?基本情報と導入状況
サービス概要と運営会社
CoDMON(コドモン)は、 保育・教育施設向けの業務支援ツール です。保育園や子ども園のほか、学童保育、幼稚園、小中学校、学習塾、習い事など幅広い施設で導入されています。
主な機能は、出欠管理や連絡帳のデジタル化、帳票作成、給食管理、保護者との情報共有など多岐にわたります。
紙や電話中心だった業務をオンライン化することで、職員の事務負担を軽減し、子どもと向き合う時間を増やせる点が特徴です。
保育ICT市場でもトップクラスのシェアを誇り、自治体への導入実績も豊富で、信頼性の高いシステムといえます。
運営会社は株式会社コドモンで、全国の教育・保育現場で導入が進んでいます。
コドモンが対応する業務領域
コドモンは、保育業務を幅広くカバーするオールインワン型のシステムです。 登降園管理や保護者連絡帳、健康チェック、帳票作成、給食アレルギー管理など、園の日常業務を包括的に支援 します。
また、園児情報を一元管理できるため、職員間の情報共有もスムーズです。
さらに、保護者向けのアプリでは欠席連絡やお知らせ配信が可能で、連携ミスや伝達漏れの防止にもつながります。
業務ごとに異なるツールを使い分ける必要がなく、1つのシステムで園全体を管理できる点が大きなメリットです。
他社サービスとの位置づけ・特徴
保育ICT市場には「きっずノート」「Kidsly」など複数のサービスがありますが、コドモンは 「現場主導の改善スピード」と「導入実績」で優位性があります 。
保育士の声をもとに年間数百件単位で機能改善を行っており、使いやすさが高く評価されています。また、自治体導入も進んでおり、公共施設でも採用される信頼性の高さが特徴です。
UI設計が直感的で、ITに不慣れな職員でも短期間で操作に慣れやすい点も強みです。
こうした実績とサポート体制により、コドモンは業界のスタンダード的存在となっています。

実際の評判・口コミでわかるメリット
ユーザーから挙がるポジティブな声
- 連絡帳のやり取りがアプリで完結して便利
- 写真販売やお知らせ配信がスムーズ
- 手書き帳票や電話連絡が減り、業務効率が向上した
- UIが使いやすい
- 保育園での様子が写真付きで確認できて安心
特に登降園管理や給食チェックなど、日々の細かな業務を自動化できる点が好評です 。ITが苦手な職員でも操作しやすいUI設計が評価され、園全体でのICT活用を後押し しています。
結果として、業務時間の短縮と職員の負担軽減に繋がっているのです。
口コミ例
子供の保育園のやり取り、お知らせプリント(PDF)、連絡帳などはコドモンがあるからめちゃめちゃ便利なんだけど、小学校に上がったら謎文章プリントと向き合わなきゃいけないんだよね…自治体がコドモン導入してるところもあるけど、ぜひ入学予定の小学校でも活用してほしいなぁ。
— みゆでニャース.ᐟ.ᐟ🐼 (@miitwi_57) July 22, 2025
コドモンの会社やってくれないかな?👀
— 工藤@リットリンク作ってます (@kudo_tieups) July 21, 2025
コドモン本当に使いやすくてUIUXも神に近い https://t.co/VUicdkTuTK
最近は便利ですね!
— パグ@BBK (@pugbbkun1937) October 22, 2025
コドモンって保育園と保護者の連絡用アプリがあり保護者が招待をすれば家族で共有できるので共有していて毎日の保育園の様子がよく分かります。
今日は登園した時に大泣きだったと聞き心配していましたが、写真付きの先生のコメント見ると初めは泣いていたが教室に入ると..
つづく
保育園経営者・現場職員における好評価ポイント
経営者層からは 「職員が無理なく使えるICT」「サポート対応が丁寧」 といった声が多く寄せられています。導入後も専任担当者が定着支援を行うため、園内への浸透がスムーズです。
また、コドモンは定期的な機能アップデートを重ねており、現場の課題解決に即した改善スピードが高く評価されています。
帳票作成や保護者対応にかかる時間を削減できることで、保育の質を維持しながら経営効率も向上します。
特に人手不足や残業問題を抱える園にとって、負担軽減効果の高さが選ばれる理由になっています。
導入事例から見える具体効果
導入園の事例を見ると、コドモンの効果は数字にも表れています。
たとえば、帳票作成時間を従来の半分以下に短縮した園や、保護者アンケートの回収率が100%になった事例もあります。
ペーパーレス化によって印刷コストを削減しつつ、情報の共有スピードも向上 。現場では「事務処理に追われず、子どもと向き合う時間が増えた」という実感が多く聞かれます。
さらに、保護者の利便性が高まったことで満足度も上昇し、園の信頼度向上にもつながっています。効率化とサービス品質向上の両立を実現している点が、導入園に共通する成果です。
評判で確認すべきデメリット・懸念店
ユーザーから挙がるネガティブな声
- データ検索がしづらい、過去の記録を探すのに時間がかかる
- 誤入力した際に編集できないため不便
- 入退出を記録する際、アプリの反応が遅く感じる
- お知らせが一方通行で、保護者と園が相互にコミュニケーションできない点が不便
コドモンは デジタルツールに慣れない職員にとっては、導入初期に戸惑うケースも 見られます。機能が多い分、すべてを使いこなすまでに時間がかかる点も課題です。
ただし、これらの意見は「慣れれば便利」「アップデートで改善された」との声も多く、導入後の研修やフォロー体制によって解消される傾向があります。
口コミ例
うちもコドモンだけど園から一方的にお知らせ来るだけで、親からは手書きの連絡帳😂
— HAL_5y👦🏻 (@mnnitph16) August 2, 2021
コドモンの機能まじムカつきすぎて
— 歯科と不動産。 (@h1011911) July 23, 2025
会社に電話しようかな
編集できないのおかしいやろ
人間やから間違えるやろ
気づいて修正出来ないの不快
息子氏の保育園にコドモン導入されてウレシイ。強いて要望をあげるなら毎朝QRかざすのにアプリ起動がもう少し早くなるか、Widget用意してもらうか、いっそNFCタッチで入退室できるようになると最高
— こにふぁー (@konifar) September 18, 2025
導入・運用時に起こりうる注意点
導入時に注意すべきは、職員全員の理解と協力体制を整えることです。ICTツールを導入しても、運用が定着しなければ効果は半減します。
特に、 紙中心の運用からデジタル化に切り替える際は、業務フローの見直しが必要で す。また、通信環境が不安定な園ではシステム遅延が起こることもあります。
こうした課題を防ぐためには、導入前にWi-Fi環境や端末の整備を行い、管理者が操作ルールを統一しておくことが重要です。
初期設定やマニュアル作成を丁寧に行うことで、スムーズな運用が可能になります。

料金体系・導入コストとROI(費用対効果)
料金プランの概要
コドモンの料金は、 施設の定員数によって決まる基本利用料+任意のオプション料金の合計 で決まります。
なお、初期費用は不要で、職員数や端末数に制限はありません。
| ~30名 | 3,300円 / 月(税込) |
|---|---|
| 31~60名 | 5,500円 / 月(税込) |
| 61~100名 | 8,800円 / 月(税込) |
| 101名~ | 定員100名ごとに5,500円 / 月(税込)を加算 |
-
基本利用料に含まれる機能
- ・園児・児童台帳
・連絡帳
・連絡帳製本販売
・アンケート
・写真共有、販売
・お知らせ一斉配信
・欠席・遅刻連絡
・行事予定管理
・ファイル共有
・施設内連絡
・園児 / 職員募集
・保育研修
・保育用品のオンラインストア
オプション
コドモンは、施設の状況に合わせて、必要なオプションを追加できます。料金プラン変更および機能の追加・削除は、月単位での変更が可能です。
なお、 オプション料金は各3,300〜8,800円 / 月 に設定されています。
-
オプション例
- ・登降園・出退勤管理
・帳票管理
・シフト管理
・請求管理
・保育ドキュメンテーション
・データあんしんパック
・発育・健康記録
・給食管理
・月間献立配信
・動画配信
・求人無制限
・バス運行管理
・口座振替代行
・保育料計算
・ヒヤリハット上記以外にもさまざまなオプションが提供されています。
オプションサービス使い放題
ほぼすべてのオプションを無制限で利用できるパックプランも用意されています。
特に、 「はじめてICTを導入する」「オプションを3つ以上利用する」という場合におすすめ です。
| ~30名 | 27,500円 / 月 |
|---|---|
| 31~100名 | 33,000円 / 月 |
| 101名~ | 38,500円 / 月 |
導入から得られる効果と費用回収の視点
コドモンは導入コストこそかかるものの、その投資は中長期的に回収が可能です。 手書き作業や紙印刷の削減によるコストカット、保護者対応や帳票作成の時短効果 がその要因です。
たとえば、職員一人あたりの事務作業時間が月10時間削減されれば、人件費削減額は年間数十万円規模に達します。
さらに、業務効率化によって残業時間を減らせるため、働き方改革にも寄与します。
費用対効果(ROI)の面でも優れており、単なるシステム導入ではなく「経営改善の一環」として位置づけられるツールです。
導入前にチェックすべきポイント
コドモン導入を検討する際は、費用だけでなく 「運用体制」と「活用範囲」を明確にすることが重要 です。
- 園の課題を洗い出し、どの業務を効率化したいのか具体化:必要な機能に絞って始めるのがおすすめ
- 職員への研修やマニュアル整備:ICTリテラシーの差を埋めるために欠かせません
- Wi-Fi環境や端末台数などのインフラ面も事前に確認:導入後のトラブルを未然に防げる
他の保育ICTシステムと比較して“コドモンが選ばれる理由”
コドモンの強み/弱みを整理
コドモンの強みは、 導入後のサポート体制と現場の声を反映した改善スピード です。機能面でも幅広く、保育業務を一元化できる点が大きな魅力です。
特に、初期設定や基本的操作のマニュアルはもちろん、わかりやすい解説つきの動画など、豊富なサポートを受けられる点は高く評価されています。
一方で、弱みとしては「多機能ゆえに慣れるまで時間がかかる」「契約内容によって料金に大きく幅が出る」といった声もあります。
| 強み | 弱み | |
|---|---|---|
| 操作性 | 直感的で初心者にも使いやすい | 機能が多く慣れに時間がかかる |
| サポート | 導入後も丁寧なフォロー体制 | 対応時間が限られる場合あり |
| コスト | 機能に対してコスパが良い | オプションを複数契約すると高額になる可能性 |
導入検討時の判断軸
コドモンを検討する際は、園の規模と運用方針に合わせて比較することが大切です。
職員数が多く、情報共有や帳票作業の負担が大きい園ほど、コドモンの総合力が活きます 。
一方、小規模園で最低限の機能だけを求める場合は、シンプルなシステムのほうが合うケースもあります。
判断のポイントは「サポート体制」「導入実績」「機能の拡張性」の3つです。コドモンはこのバランスに優れており、長期的な運用を見据えた導入先として適しています。
導入を成功させるためのステップ&活用のコツ
導入前:現状業務の棚卸しとKPI設定
コドモンを効果的に導入するには、まず自園の業務フローを明確に把握することが重要です。
紙や電話、Excelなどで行っている業務を洗い出し、「どの作業をデジタル化したいのか」を整理しましょう 。
導入目的が曖昧なままだと、現場が混乱しやすく、定着に時間がかかります。
あわせて、導入効果を測るKPI(例:残業時間の削減率、書類作成時間の短縮など)を設定しておくと、成果を数値で確認できます。
事前の棚卸しと目標設定が、スムーズな運用と費用対効果の最大化につながります
導入時:職員研修・運用体制の整備
導入段階では、職員全員がシステムを理解し、操作に慣れることが不可欠です。
コドモンは直感的に操作できますが、導入初期は研修やマニュアル整備を行うことで、混乱を防げます。
特に 「誰がどの業務を担当するか」「どのタイミングで記録を入力するか」を明確にしてお くことが重要です。
また、導入担当者やICT推進リーダーを設置し、職員からの質問を集約できる体制を作ると定着が早まります。
園全体で共通ルールを持つことで、ミスや入力漏れを防ぎ、安定した運用が実現します
運用後:データ活用・改善フィードバック・保護者巻き込み
コドモンの導入はスタートに過ぎません。 運用が軌道に乗った後は、蓄積したデータを活用して園運営の改善につなげる ことが大切です。
たとえば、登降園データを分析して職員配置を最適化したり、保護者アンケート結果から満足度を高める取り組みを行ったりできます。
また、保護者にも活用方法を周知し、双方向のコミュニケーションを促すことで利用価値が高まります。
運用後も定期的に職員の意見を取り入れ、アップデートを重ねることが長期的な成功の鍵です。
成功事例に学ぶ“定着させる”ための工夫
導入園の成功事例に共通するのは、 「小さく始めて徐々に拡大する」アプローチ です。
最初から全機能を使おうとせず、まずは連絡帳や出欠管理など主要機能からスタートし、職員の習熟度に応じて範囲を広げていくのが効果的です。
また、コドモンのカスタマーサクセスチームが行うサポートを活用し、課題を相談しながら改善を進めた園ほど定着率が高い傾向にあります。
現場の負担を最小限にしつつ、徐々にICT文化を根付かせることが、成功への近道です。
よくある質問(FAQ)
A
コドモンでは通信データを暗号化し、外部からの不正アクセスを防止する仕組みを採用しています。サーバーは国内の安全な環境で管理され、定期的なセキュリティ診断も実施。職員ごとに利用権限を細かく設定できるため、情報漏えいリスクを最小限に抑えられます。また、保護者データも厳重に保護されており、自治体や公立園でも採用されるほど信頼性が高いのが特徴です。
A
コドモンでは、日々の園務を効率化するための多彩な機能が利用できます。園児台帳では入園から卒園までの情報を一元管理し、紙台帳を完全にデジタル化できます。連絡帳機能は、保護者とのやり取りをスマホで完結でき、記録の抜け漏れも防止できます。さらに、行事写真をオンライン販売できる「写真販売機能」や、アレルギー情報を自動反映する「給食管理機能」も搭載。
A
コドモンは、他社システムからの乗り換えや解約にも柔軟に対応しています。既存データはCSV形式でエクスポート・インポートできるため、移行作業がスムーズです。導入時には専任スタッフがサポートし、稼働停止のリスクを最小限に抑えながら移行できます。解約時もデータを安全に保管できる仕組みが整っており、保育記録や登降園履歴など重要情報を失う心配はありません。運用開始から終了まで一貫したサポート体制がある点も、ユーザーから高く評価されています。
まとめ
コドモンは、保育現場の声を反映しながら進化を続ける信頼性の高いICTシステムです。特に、業務効率化・保護者連携・データ管理を強化したい園には最適といえます。
一方で、職員のICTリテラシーが低い場合や、通信環境が整っていない園では定着に時間がかかることもあります。
導入を成功させるには、事前準備と職員間の協力が不可欠です。
評判を踏まえても、総合的な満足度は高く、長期的に見れば業務改善と園の信頼性向上の両方を実現できるツールといえるでしょう。
今すぐできるチェックリスト
導入検討中の園は、次のポイントをを洗い出すことで、コドモンの導入効果を明確にできます。
- 現在の業務で非効率な部分はどこか?
- 職員がICTを使いこなせる体制は整っているか?
- 保護者との連絡に時間がかかっていないか?
- データの管理や情報共有でミスが起きていないか?
導入は目的ではなく、園運営を改善するための手段です。課題を整理した上で、最適なプランを比較検討することが成功への第一歩となります。
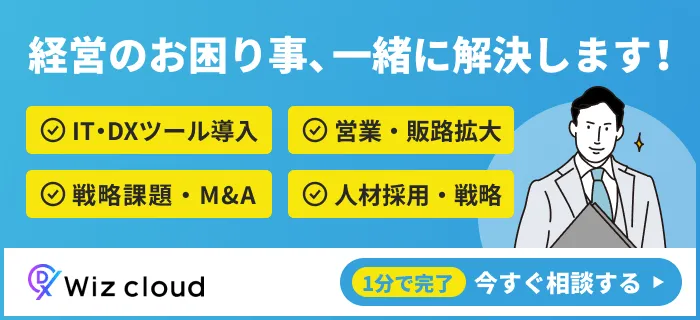

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!