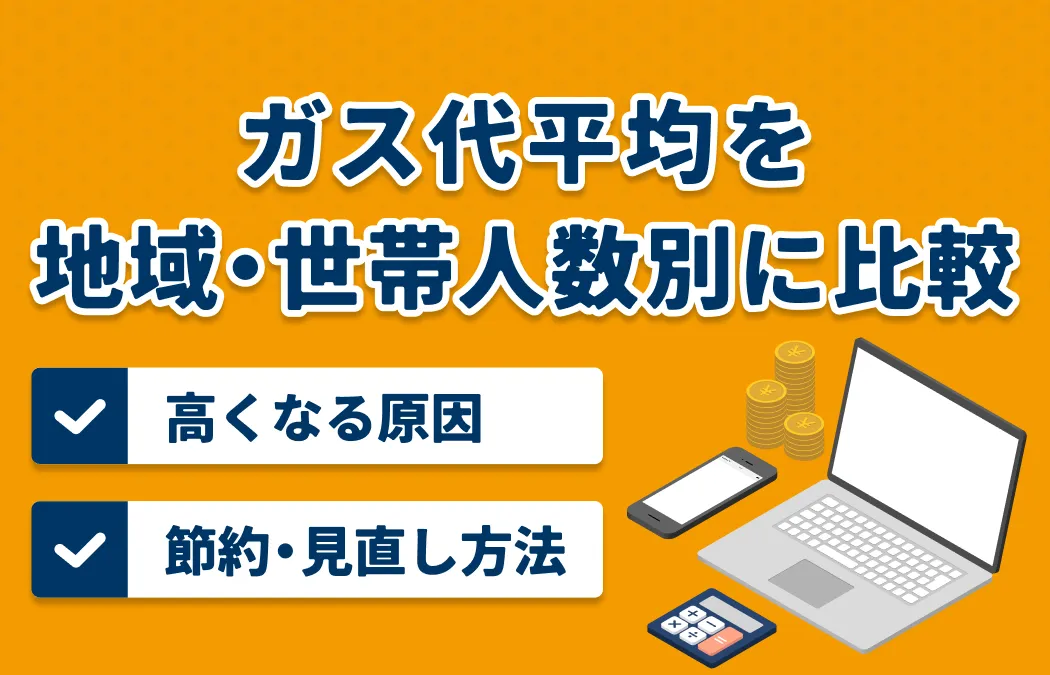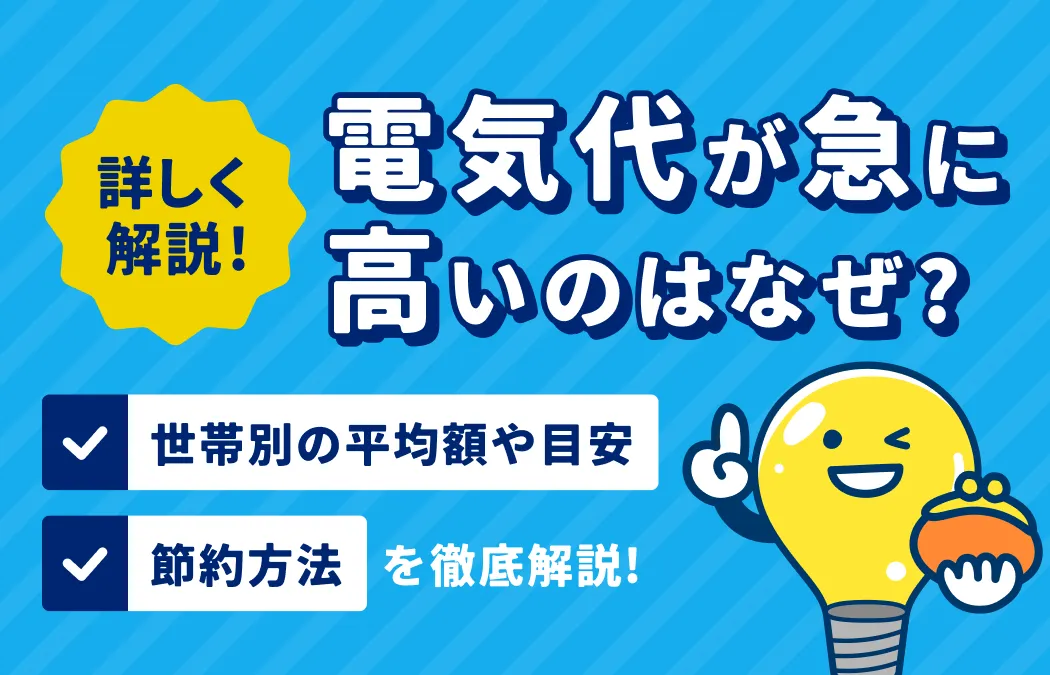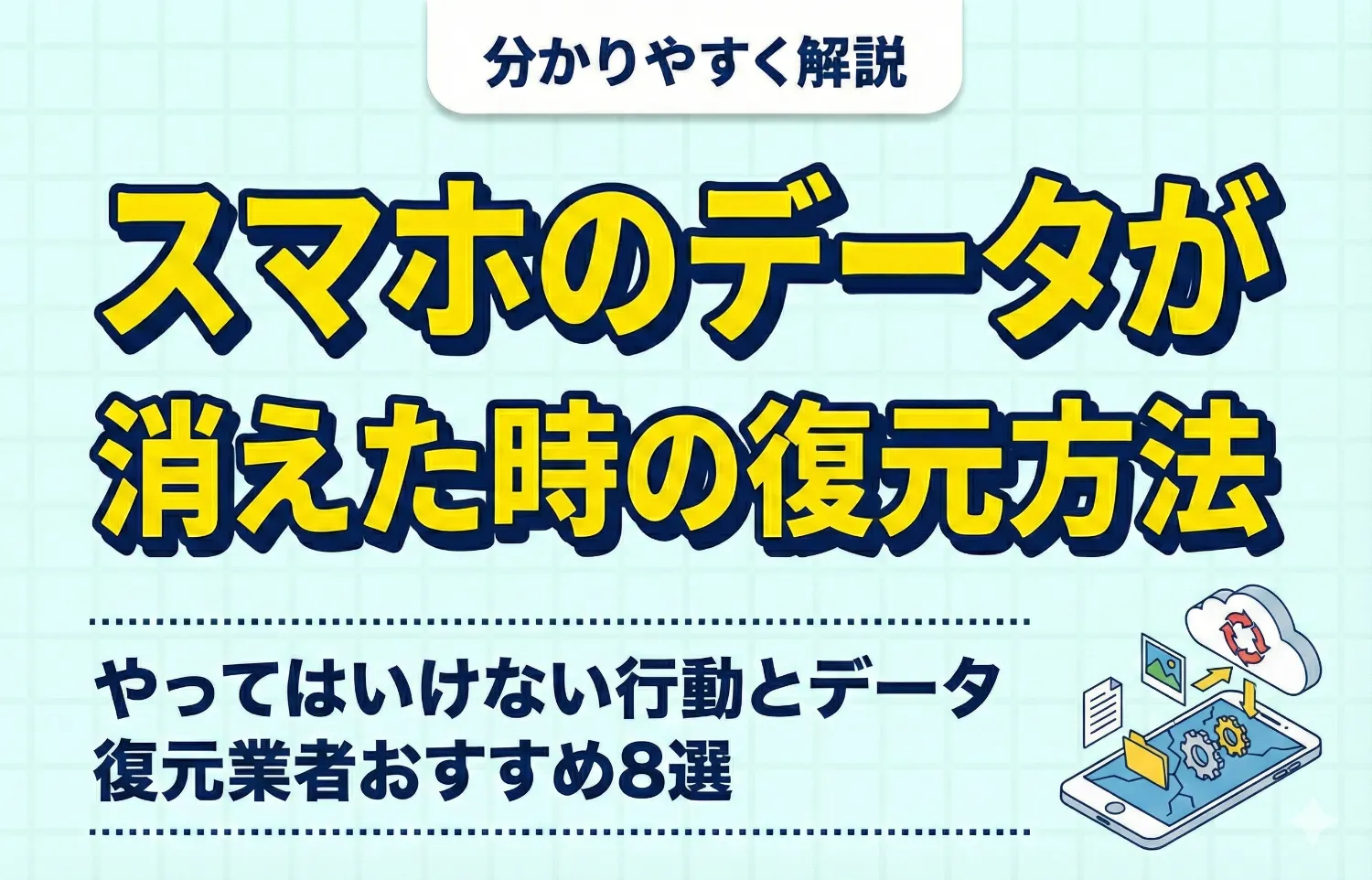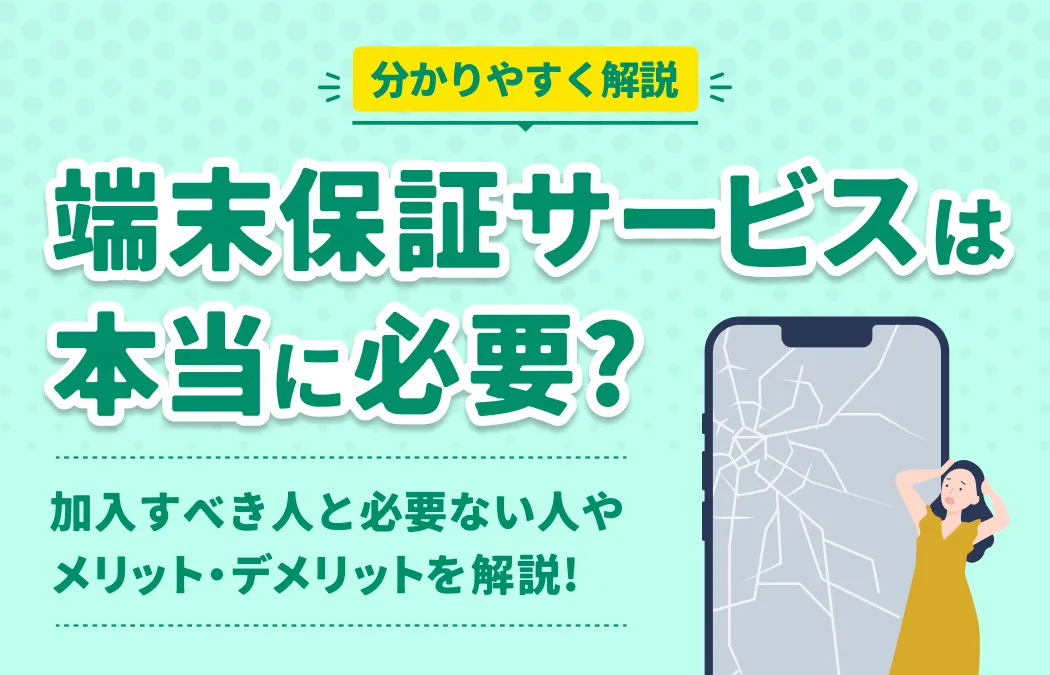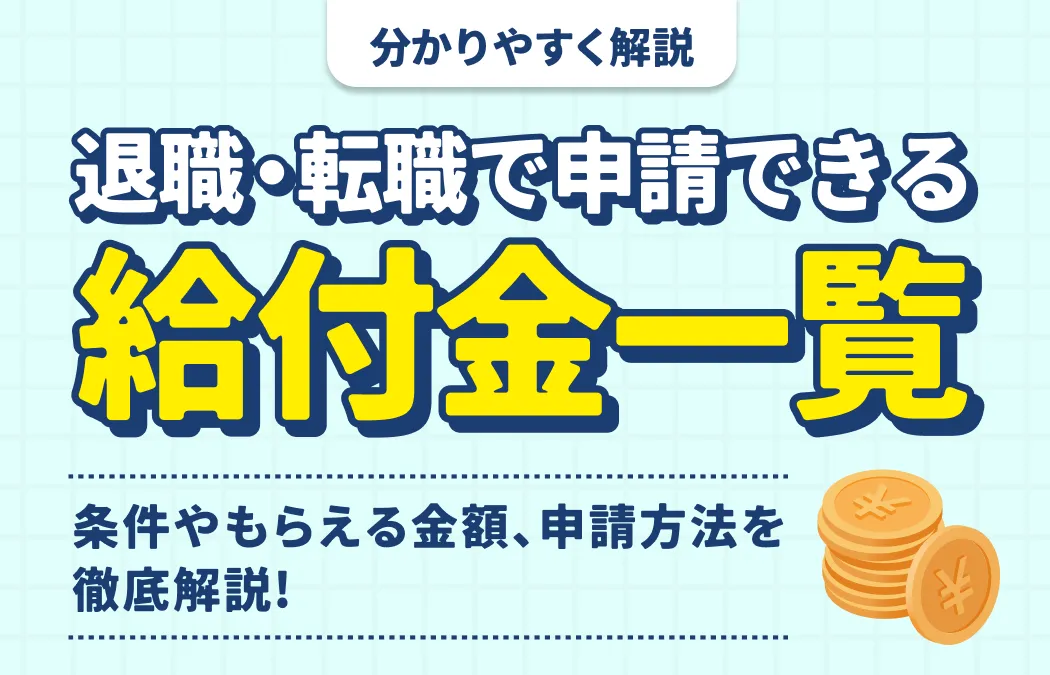「平均と比べて自分のガス代が適正か知りたい」
「ガス代が高い原因は?」
ガス代の平均はは、契約しているガスのプランや世帯人数、時期、地域によって変動します。
しかし、平均がわかっても「自分はなぜ高いのか」「どう改善すればいいか」がわからないという方が多いです。
本記事では、ガス代の平均(全国・地域・世帯別)を可視化し、あなたの料金が高い理由を検証し、節約・切替可能性まで含めてステップごとに解説します。
目次
全国・地域・世帯別のガス代平均データ
全国平均と単価推移
| 2024年 | 4,109円 |
|---|---|
| 2023年 | 4,527円 |
| 2022年 | 4,547円 |
| 2021年 | 4,066円 |
全国のガス代平均は、 ひと月あたり4,000円〜4,500円前後が目安 です。
総務省「家計調査」によると、都市ガスの平均支出は年々上昇傾向にあり、特に2022年以降は燃料価格の高騰により1〜2割ほど高くなっています。
単価は地域やガス会社によって差がありますが、平均で1㎥あたり150〜180円程度が相場です。今後も燃料費調整の影響で変動が続く見込みのため、定期的に最新データを確認することが重要です。
地域別の平均比較
以下は、総務省「家計調査」に基づく、2024年における地域別のガス代平均を示したデータです。
| 北海道地方 | 4,499円 | 近畿地方 | 4,377円 |
|---|---|---|---|
| 東北地方 | 3,691円 | 中国地方 | 3,296円 |
| 関東地方 | 4,370円 | 四国地方 | 3,530円 |
| 北陸地方 | 3,564円 | 九州地方 | 3,431円 |
| 東海地方 | 4,363円 | 沖縄地方 | 3,735円 |
ガス代は地域によって大きく異なります。特に、 寒冷地の北海道は暖房需要が高く、反対に中国・四国・九州・沖縄地方は比較的安価 です。
さらに、同じ地域内でも「都市ガス」か「プロパンガス(LPガス)」かで差が生じます。
地域特性とガス種別の両面から料金を比較することで、自宅のガス代が高いのかをより正確に判断できます。

世帯人数別の平均比較
ガス代は、家族構成や住居タイプによっても大きく変わります。以下は、総務省「家計調査」に基づく、世帯人数別のガス代平均を示したデータです。
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 3,056円 | 3,359円 | 3,331円 |
| 2人世帯 | 4,497円 | 4,971円 | 4,900円 |
| 3人世帯 | 5,121円 | 5,591円 | 5,555円 |
| 4人世帯 | 5,015円 | 5,284円 | 5,427円 |
| 5人世帯 | 4,284円 | 5,131円 | 5,506円 |
参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯用途分類 004 用途分類(世帯人員別) | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
特に、単身世帯、2人世帯、3人世帯と人数が増えるにつれ、平均額は上昇する傾向があります。一方、3人~5人世帯は、人数に比例して大きく平均金額が増えることはありません。
また、床暖房のある家庭では、冬場のガス代が高くなりやすい傾向にあります。
ガス代が「高い」と感じる原因/要因分析
使用量の変動
ガス代が高く感じる最も一般的な原因は「使用量の増加」です。
特に 冬はお湯の使用量や暖房需要が増えるため、ガス消費量が大幅に上昇 します。たとえば、シャワーを1日10分多く使うだけでも、月に数百円単位で請求額が変わります。
また、家族が増えるほどお風呂や調理の頻度が高まり、比例してガス代も上がります。
さらに、床暖房を使う家庭や料理を頻繁に行う世帯では、年間を通して平均より高くなる傾向があります。
自宅の使用量を把握し、季節・生活スタイルとの関係を確認することが節約の第一歩
契約プラン・基本料金・従量単価の差
同じ地域でも契約内容によってガス代は大きく異なります。 ガス料金は「基本料金」と「従量料金(使用量に応じた単価)」で構成 されており、契約プランごとにその比率が違います。
たとえば、使用量が少ない家庭なら基本料金が低いプランを選ぶほうが割安になりますが、使用量が多い家庭は単価が安いプランを選ぶほうが得です。
特にプロパンガスでは業者間で単価が100円以上違うことも珍しくありません。
契約当初の料金がそのまま据え置かれているケースもあるため、定期的なプラン見直しが無駄な支払いを防ぐ重要なポイントです。
原料費調整・燃料コスト変動の影響
ガス代が上昇する背景には、国際的な燃料価格の変動もあります。
都市ガス・LPガスともに、原料となる液化天然ガス(LNG)や原油の価格が上がると、 ガス会社が設定する「原料費調整額」に反映され、毎月の料金に上乗せされます 。
特に近年は、世界情勢や円安の影響により燃料調達コストが高止まりしており、消費者の負担が増えています。この調整は自動的に行われるため、節約努力では直接コントロールできません。
ただし、燃料調整の上限を設けている会社へ切り替えることで、価格変動の影響を抑えられる可能性があります。
ガス会社体制・地域独占・競合性の違い
ガス料金の高さは、ガス会社の体制や地域の競争環境にも左右されます。
都市ガスは地域ごとに供給会社がほぼ固定されており、競争が起こりにくいため料金が安定 する一方で、大幅な値下げは期待しにくい構造です。
対してプロパンガス(LPガス)は自由料金制のため、本来は事業者間競争が働くはずですが、地域によっては特定業者のシェアが高く、実質的な独占状態に近いケースも見られます。
こうした場合、平均より高い単価が設定されていることもあります。複数社の見積もり比較を行うことで、自分の地域の適正価格を把握でき、無駄な支払いを防げます。
自分のガス代を「平均と比べる」方法
検針票の見方・確認すべき項目
自分のガス代が平均より高いかどうかを確認するには、まず検針票(請求書)を見直すことが大切です。
検針票には「基本料金」「従量料金」「使用量(㎥)」「単価」などが記載されています。注 目すべきは、1㎥あたりの単価と月間使用量のバランス です。
特にプロパンガスの場合、従量単価が高く設定されているケースが多いため、平均より割高な可能性があります。
また、前年同月の使用量や料金も確認し、季節要因や生活習慣による増減を把握しましょう。こうした項目を整理することで、料金の「構造」を理解でき、次の見直しや切り替え判断がしやすくなります。
平均基準との比較シミュレーション
検針票で把握した使用量をもとに、平均値と照らし合わせることで「自分のガス代が高いのか」を判断できます。
自宅のガス料金が 平均額を大きく上回る場合、単価設定が高いか、使用量が多い可能性 があります。
インターネット上の「ガス料金比較シミュレーター」などを活用すれば、他社との料金差も数分で確認可能です。
数百円〜数千円の差が年間では数万円単位の負担になるため、平均比較→要因分析→見直し行動という流れを習慣化することが重要です。
ガス代を下げるための節約テクニック
利用量削減の具体アクション
ガス代を下げる最も直接的な方法は、使用量そのものを減らすことです。
- シャワー時間を1分短縮するだけでも、年間で数千円の節約につながる
- 給湯温度を1〜2℃下げる、鍋やヤカンにふたをして調理するなど、小さな工夫でもガス消費を抑えられる
- 入浴は追い焚きよりも「まとめて入る」ほうが効率的
こうした日常の小さな行動を積み重ねることで、平均的な家庭でも年間1〜2万円の節約効果が期待できます。
機器の更新・効率化
古いガス機器を使い続けていると、知らぬ間にエネルギーロスが発生していることがあります。
最新の省エネ型給湯器は、従来機よりも熱効率が高く、年間ガス使用量を10〜15%削減できる といわれています。
また、断熱性の低い浴槽や古いコンロも熱損失の原因になります。
初期投資は必要ですが、長期的に見れば光熱費全体のコスト削減につながる賢い選択といえます。
割引プラン・セット契約・ポイント利用
最近では、 ガスと電気をまとめる「セット割」 を提供する企業が増えており、年間数千円のコスト削減が見込めます。
さらに、クレジットカード支払いによるポイント還元や、契約継続で割引が適用されるプランもあります。また、契約地域によってはWeb申し込み限定の特典がある場合も。
こうした仕組みをうまく活用することで、無理なく支出を減らせます。使い方を変えずに節約できる最も手軽な方法です。
プロパン→都市ガス切替事例(可能地域であれば)
都市ガス導管が整備されている地域では、LPガスから都市ガスへの切替で大幅なコスト削減が期待できます。
たとえば、 プロパン単価250円から都市ガス単価160円に変わると、同じ使用量でも月あたり35〜40%の節約が可能 です。
切替にはガスメーターや配管工事が必要ですが、自治体の補助金やガス会社のキャンペーンで初期費用を抑えられることもあります。
さらに、CO₂排出量も減らせるため環境面のメリットも大きいです。コスト削減とエコの両立ができるため、条件が合う地域では積極的に検討したい切替方法です。
ガス会社を切り替える/見直す方法と注意点
切替できるか?地域・導管制限の確認
ガス会社の切り替えを検討する際は、まず自分の地域で切り替えが可能かを確認する必要があります。
都市ガスは、地域の導管を管理する事業者が決まっており、そのエリア内で契約先を自由に選べる 仕組み(小売自由化エリア)と、まだ切り替えに対応していない地域があります。
一方、プロパンガス(LPガス)は全国的に自由化されているため、基本的にはどの地域でも切り替えが可能です。
ただし、アパートや賃貸住宅では大家や管理会社の許可が必要な場合があります。まずは供給元と契約形態を確認し、自分が自由に選べる立場かを明確にすることが第一歩です。
切替手順とスケジュール
ガス会社の切り替えは、手続きが複雑そうに見えて実は簡単です。主な流れは「(1)見積もり依頼 → (2)契約手続き → (3)切替工事・利用開始」という3ステップです。
都市ガスの場合は、導管工事が不要なため1〜2週間で完了 します。プロパンガスでは、ボンベやメーターの交換を伴うため立ち会いが必要ですが、工事は1時間程度で終わります。
切替の際、旧契約の解約手続きは新しいガス会社が代行するケースがほとんどです。思っているより手間がかからず、1か月以内に料金効果を実感できるのが切替の魅力です。
注意点・リスク
ガス会社を切り替える際には、いくつかの注意点もあります。
- 契約期間中に解約すると違約金や解約手数料が発生する可能性
⇒特にキャンペーン割引を利用して契約した場合は要確認です。 - プロパンガスでは不当な値上げや供給停止などのトラブルが報告されることもある
⇒契約前に「料金表が公開されているか」「単価や諸費用が明記されているか」を必ずチェックしましょう。
信頼できる会社を選べばリスクは最小限に抑えられます。契約条件を事前確認することが、安心して切替を進めるための基本です。
ガス会社を選ぶポイント・比較軸
最適なガス会社を選ぶには、複数社を比較することが重要です。比較時は「料金単価」「基本料金」「契約条件」「サポート体制」の4点を中心にチェック します。
料金が安いだけでなく、原料費調整の上限や、緊急時の対応体制が整っているかも信頼性の判断材料です。
また、電気とのセット割を提供する会社なら、光熱費全体の最適化も図れます。最近ではオンライン比較サービスやシミュレーターを使えば、数分で自宅の最安プランを確認可能です。
価格と安心のバランスを見極めて選ぶことで、長期的にコストを抑えられます。
Q&A・よくある質問
A
季節的な使用量増加や、燃料費調整の影響で単価が上がっている可能性があります。特に冬季はお湯・暖房利用が増え、前年同月より30%以上高くなるケースも珍しくありません。また、プロパンガスの場合は事業者の価格改定が要因のことも。請求書で「単価」と「使用量」の両方を確認し、どちらが上昇しているかを見極めるのが重要です。
A
信頼できる会社を選べば、基本的にトラブルは起きません。多くの会社は解約手続きや切替工事を代行し、利用者側の負担はほとんどありません。ただし、契約前に「料金表の公開」「違約金の有無」「原料費調整の上限」などを必ず確認しておきましょう。
A
年1回の見直しをおすすめします。燃料価格や為替の変動により、ガス単価は定期的に上下しています。特にプロパンガスは事業者間で価格差が大きく、見直しを怠ると知らぬ間に割高契約のまま継続してしまうこともあります。1年に一度は比較サイトや見積もりを活用し、現在の契約内容が適正か確認しましょう。
まとめと次のステップ
ガス代は、地域やガス種別・使用量などによって大きく異なります。自分の料金を「平均と比較」し、原因を分析すれば、無駄なコストが見えてきます。
まずは検針票を確認し、必要に応じてガス会社の切り替えを検討しましょう。
切り替えを行うことで、年間数万円の節約につながるケースも珍しくありません。特にプロパンガスを利用中の方は、複数社の見積もり比較が効果的です。
光熱費の見直しは今すぐ始められます。まずは、下記からお気軽にご相談ください。

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!