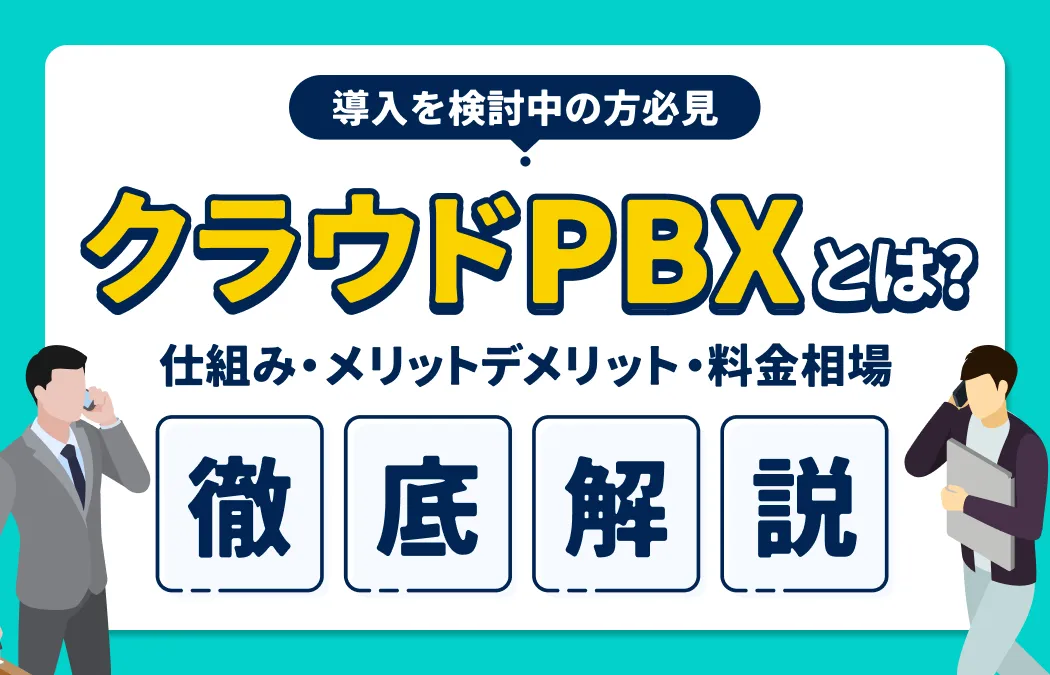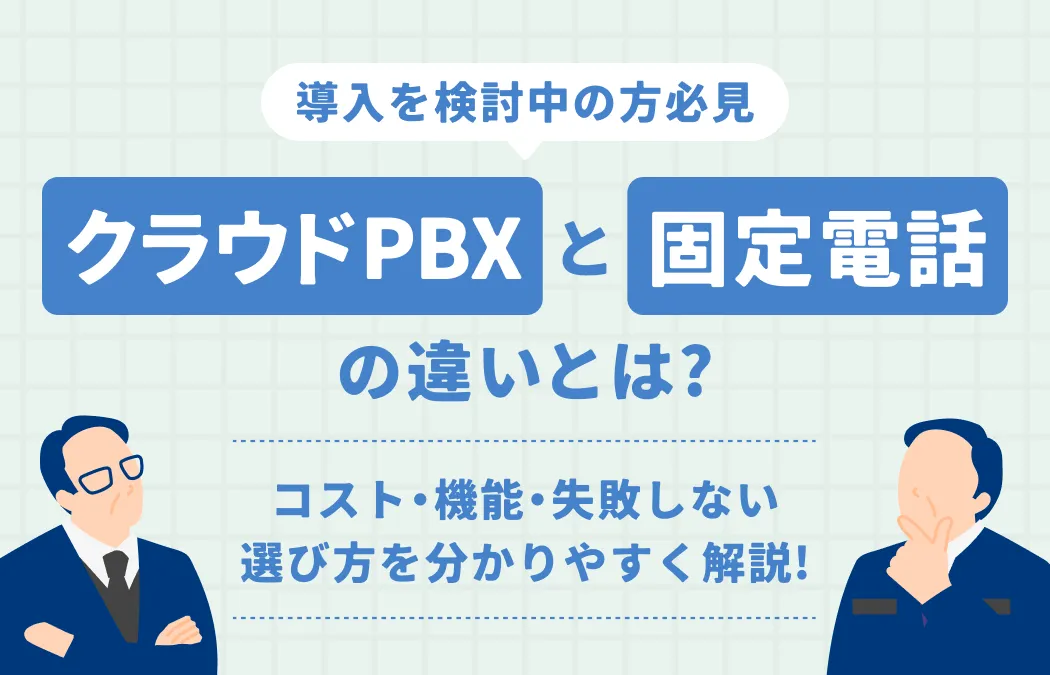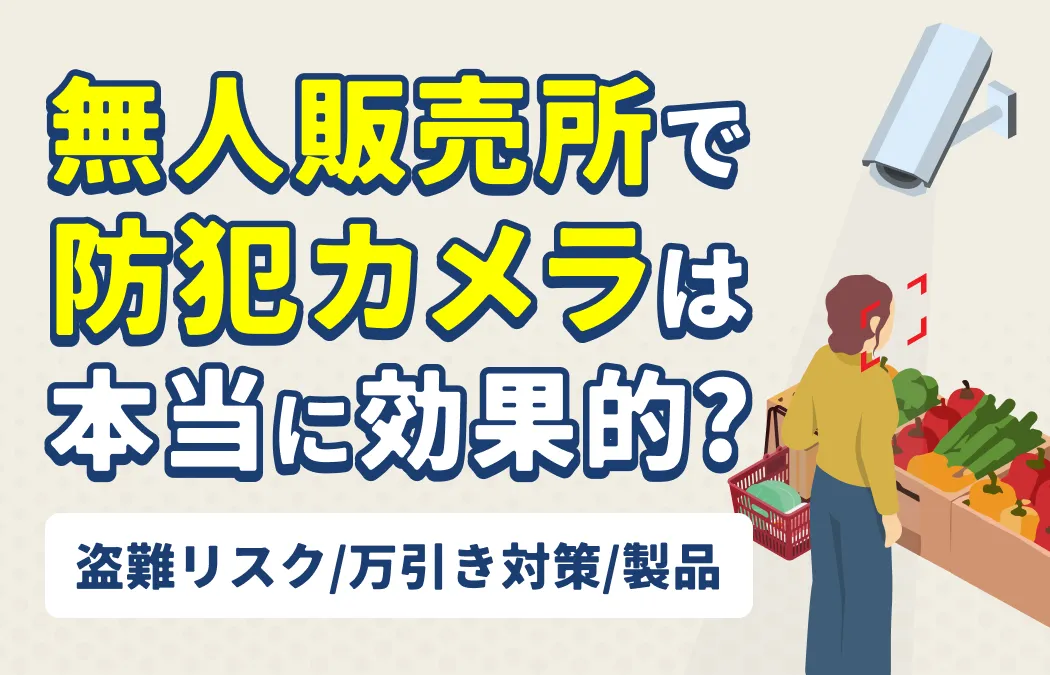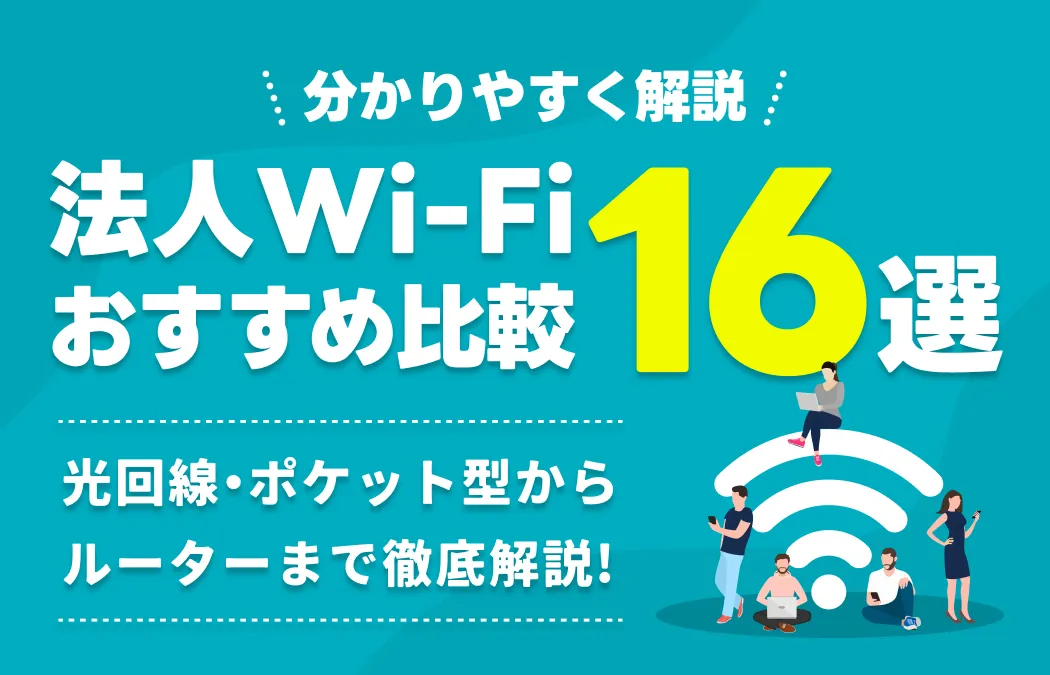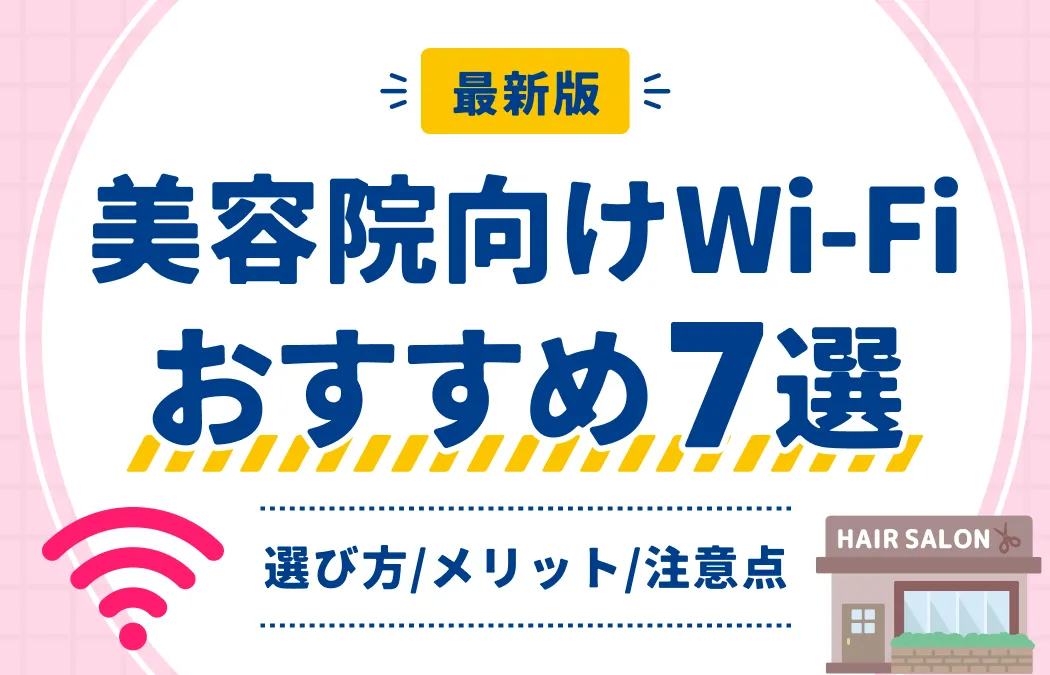「従業員や顧客のネット利用時、情報漏洩リスクを防ぎたい」
Wi-Fi通信には、情報漏えいやデータの盗み見など、様々なセキュリティリスクが伴います。実際に侵入や盗聴、偽アクセスポイントによる被害事例も少なくありません。
しかし、「セキュリティ規格の種類がわからない」「セキュリティ設定の確認方法は?」など、具体的な対策について知識がない方も多く見られます。
本記事では、想定されるWi-Fiのセキュリティ脅威とその対策を徹底解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
Wi‑Fiセキュリティが法人にとって重要な理由
盗聴・不正アクセスによる情報漏洩のリスク
無線通信は電波でやり取りされるため、 Wi‑Fiセキュリティが甘いとネットワークがサイバー攻撃の標的になり、第三者に傍受されるリスク が高まります。
特に、顧客情報や業務データを扱う企業にとって、情報漏洩は信用問題に直結します。
たとえば、来店者用のフリーWi‑Fiを適切に分離していないと、社内ネットワークに侵入される可能性があります。
このような脅威を防ぐためにも、セキュリティ対策は事業者にとって不可欠です。
- 通信内容が盗み見られるリスク
通信が暗号化されていない場合、悪意のある第三者がパケットを傍受し、ユーザーの送受信データを解析(=スニッフィング)することで、メールやチャットの内容、ウェブサイトの閲覧履歴、ログイン情報、クレジットカード番号などを盗み見られる可能性があります。 - 機密情報が外部に漏れてしまうリスク
攻撃者が通信を傍受し、送信されたパスワード、個人データ、業務情報などを盗み出す可能性 があります。 - 無断で端末にアクセスされるリスク
攻撃者は、ネットワーク内のデバイスを探索し、侵入可能なポートを特定して不正アクセスを試みます。これにより、 データの閲覧や盗難、さらにはデバイスの遠隔操作が行われる危険性 があります。 - Wi-Fiルータを経由したデータ改ざんのリスク
ユーザーが訪れるウェブサイトが偽装される「DNSスプーフィング」や、正規のウェブページが改ざんされてマルウェアが配布される恐れがあります。また、ユーザーの通信内容を変更されることで、誤った情報を伝達させたり、詐欺サイトに誘導されるリスクも発生します。 - DDoS攻撃のリスク
攻撃者が不正にルータを操作し、他のネットワークやサービスを標的とする膨大なトラフィックを送り込まれると、 利用者自身が知らないうちに犯罪行為に関与してしまう可能性があります。また、ルータ自体が攻撃を受け、ネットワークが使用不能になることもあります。
実際の攻撃ケース例
Wi‑Fiの脆弱性を狙った攻撃は実際に発生しており、被害も深刻です。
- KRACK:WPA2の暗号化を解除し、通信内容を盗み見られる脅威。
- Dragonblood:WPA3の認証方式にある欠陥を突く攻撃。
- Emotet:Wi‑Fi経由で社内ネットワークに感染を拡大することもあるマルウェア。
これらの事例は、最新の暗号化方式であっても対策が不十分だと被害に遭うことを示しています。つまり、 Wi‑Fiセキュリティは常に最新の知識と技術で守る必要がある のです。
主要なWi‑Fiセキュリティ要素
暗号化技術(WPA2(AES)/WPA3/OWE)
Wi‑Fiの暗号化は、通信の盗み見や改ざんを防ぐ基本的な仕組み です。特に法人利用では、強力な暗号方式を選ぶことでセキュリティレベルが大きく変わります。
現在推奨されているのはWPA2(AES)またはWPA3という方式です。WPA3は、パスワードの推測耐性が高く、より安全ですが、古い機器では非対応の場合もあります。
またOWE(Opportunistic Wireless Encryption)は、ゲスト用ネットワーク向けに暗号化を提供する新しい技術です。どの方式を使うかは、機器の対応状況と用途に応じて選ぶ必要があります。
認証とキー管理(PSK/SAE認証、WPSの脆弱性)
Wi‑Fi接続時に使う認証方式もセキュリティを大きく左右します。
法人環境では、従来の「共有パスワード(PSK)」より、 安全性の高い「SAE認証(WPA3で導入)」への移行が推奨 されます。
PSKはパスワードが漏れると誰でも接続できるのに対し、SAEは推測や再利用を防ぐ仕組みがあります。
また、WPS(Wi‑Fi Protected Setup)は便利ですが、PIN方式に脆弱性があり、企業利用では無効化が望ましいとされています。安全性を保つには、適切な認証方式の選定と定期的なキー管理が重要です。
SSIDとゲストネットワーク運用(命名・ステルス、隔離設定)
Wi‑FiのSSID(ネットワーク名)の設定も、セキュリティに関わる要素のひとつです。 SSIDに社名や部署名などを入れると、外部から組織構造が推測されやすくなります 。
不要なリスクを避けるためにも、汎用的な名前を使い、必要がなければSSIDの「ステルス化(非表示)」も検討しましょう。
加えて、顧客向けのゲストネットワークは、業務用ネットワークと物理的・論理的に分離し、アクセスできる範囲を制限することで、外部端末から社内システムへの侵入を防げます。
必須のルーター・ネットワーク管理対策
管理者パスワードの見直しと強化
ルーターの管理画面に設定された 初期パスワードをそのまま使っていると、外部からの不正侵入を許してしまう恐れ があります。
特に「admin/password」などの初期設定は、ネット上に広く公開されているため非常に危険です。
法人環境では、8文字以上で英数字・記号を組み合わせた強固なパスワードに変更し、定期的に見直すことが基本です。
ファームウェア&端末OSの自動更新設定
Wi‑Fiルーターや接続端末のソフトウェア(ファームウェアやOS)は、日々のアップデートで脆弱性が修正されています。
更新を怠ると、既知のセキュリティホールを突かれて攻撃されるリスクが高まります 。そのため、法人では「自動更新機能」を活用し、常に最新状態を保つことが大切です。
特に、業務で使用するスマートフォンやタブレットも定期的にチェックし、アップデートを習慣化しましょう。更新はセキュリティ維持の第一歩です。
不要機能の無効化
ルーターには便利な機能が多く備わっていますが、業務利用では 一部機能をあえて無効化することで安全性が高まります 。
たとえばWPS(ボタン一つで接続できる機能)は便利な反面、PINの脆弱性が外部侵入の手口になることがあります。
また、UPnP(ネットワーク機器の自動認識)やリモート管理機能も、企業ネットワークではセキュリティホールとなり得ます。
下表のように、設定の見直しによってリスクを軽減することが可能です。
| 機能の内容 | 法人での推奨設定 | |
|---|---|---|
| WPS | ワンタッチ接続 | 無効化 |
| UPnP | 自動ポート開放 | 無効化 |
| リモート管理 | 外部から管理画面にアクセス可能 | 社内IPのみに制限 |
| ファーム更新 | ルーターソフトの自動更新 | 有効化(自動) |
物理対策・ネットワーク構成の工夫
アクセスポイント配置で電波範囲を限定(物理流出対策)
Wi‑Fiのセキュリティ対策では、 電波の届く範囲を制御する「物理的対策」も重要 です。
電波は壁を越えて屋外や隣室まで届くため、悪意のある第三者に拾われる可能性があります。
たとえば、窓際や通路付近にアクセスポイントを設置すると、外部からの傍受リスクが高まります。
これを防ぐには、アクセスポイントを建物中央に設置したり、出力を調整するなどの工夫が有効です。
ネットワークセグメント分離(ゲスト/社内端末/IoT)
安全なWi‑Fi運用には、ネットワークを用途ごとに分離する「セグメント化」が欠かせません。
社内端末とゲスト用Wi‑Fi、さらにはIoT機器まで同じネットワークに接続されていると、 万が一どれかが侵害されたときに全体へ被害が波及してしまいます 。
そこで、用途別にネットワークを分け、アクセス範囲を制限することで、被害の拡大を防ぐことができます。以下に基本的な構成例を示します。
| 用途 | 代表的な接続機器 | 特徴・対策 | |
|---|---|---|---|
| 社内用 | 社員の業務端末・サーバー | PC、NAS、業務アプリ | 最も重要。厳重に管理。 |
| ゲスト用 | 来訪者のスマホ・PC | 顧客・外部業者の端末 | 社内ネットワークと完全隔離。 |
| IoT用 | カメラ・プリンタなど | IPカメラ、複合機、POS端末 | 最低限の通信のみ許可する設定。 |
ファイアウォールやIDS/IPS・セキュリティ監視体制
ネットワークの境界を守るためには、 ファイアウォールやIDS(侵入検知)・IPS(侵入防止)といったセキュリティ機器の導入も必要 です。これらは、不審な通信を検出し遮断する「番人」のような存在です。
たとえば、社外からの不正アクセスをファイアウォールで防ぎつつ、社内で発生した異常通信をIDS/IPSが検知してくれます。
また、ログ監視やアラート通知の仕組みも整備すれば、問題発生時に素早く対応できます。
物理的な分離と技術的な防御を両立させることが、安心できるネットワーク環境の鍵です。
運用フェーズでの追加対策
接続端末の定期確認とログ監視
Wi‑Fiの安全を保つには、一度設定して終わりではなく、継続的な運用管理が欠かせません。
特に 接続端末の把握は重要で、不審な端末が社内ネットワークに紛れていないかを定期的に確認する 必要があります。
ルーターやセキュリティツールで「接続履歴」や「通信ログ」をチェックすれば、異常なアクセスの兆候も把握できます。
たとえば、深夜に社内から海外サーバーにアクセスがあるといった不審な通信が見つかれば、早期に対応が可能です。
退職者や役割変更時のアクセス権見直し
社内のWi‑Fiセキュリティを守るには、ユーザーごとのアクセス権限を適切に管理することも必要です。
退職者のアカウントが残っていたり、部署異動後も以前のネットワークにアクセスできる状態が続くと、思わぬ情報漏洩の原因 となりかねません。
そのため、組織変更や人員の出入りがあったタイミングで、Wi‑Fi接続の許可端末やIDの見直しを行うことが推奨されます。
運用ルールを整備することで、ヒューマンリスクも最小化できます。
定期的な脆弱性診断・ペネトレーションテスト
ネットワーク環境は常に変化し、完璧な状態を保つのは困難です。
だからこそ、 定期的な脆弱性診断やペネトレーションテスト(疑似攻撃)を通じて、Wi‑Fiセキュリティの状態を客観的に確認 することが重要です。
診断では、パスワード設定やポート開放、不要機能の残存などをチェックし、問題があれば早期に改善します。
第三者によるテストを導入することで、自社では気づきにくいリスクも明らかになります。継続的な点検が、安全な運用を支える基盤です。
非常時のインシデント対応フロー策定
万が一、Wi‑Fi経由で不正侵入やマルウェア感染が発生した場合に備えて、インシデント対応の体制を事前に整えておくことも欠かせません。
具体的には、 誰が初期対応を行うか、通信遮断の手順、社内外への報告ルールなどを文書化し、関係者と共有しておく 必要があります。
対応が遅れると被害が拡大し、信用失墜にもつながるため、シナリオを想定した訓練も有効です。準備があることで、いざという時の被害を最小限に抑えられます。
フリーWi‑Fi/ゲストWi‑Fi運用と注意点
偽アクセスポイント(なりすまし)のリスク
フリーWi‑Fiを提供する際に最も注意すべきなのが、偽アクセスポイントの存在です。
これは、正規のWi‑Fiに似せたSSIDを用いて、第三者が設置する不正な無線ネットワークのことです。
利用者が気づかずに接続してしまうと、ID・パスワード・カード情報などの個人情報が盗まれる可能性 があります。
たとえば、店舗のSSIDが「Store_WiFi」である場合、「StoreFreeWiFi」など紛らわしい名前が使われることがあります。
このようなリスクに備えるためにも、公式SSIDの掲示や、事前の注意喚起が欠かせません。
セキュアなゲストネットワーク設計(パスワード運用/QRコード接続)
ゲストWi‑Fiを安全に運用するには、 社内ネットワークと完全に分離した専用ネットワークを設けることが前提 です。
そのうえで、接続用パスワードの定期変更や、接続手段にQRコードを活用することで、より安全性と利便性を両立できます。
QRコードは入力ミスを防ぎつつ、SSIDやパスワードを外部に公開しない手段として有効です。
また、利用時間を制限する設定や、接続先ドメインを制限するフィルタリング機能も併用すれば、不正利用の抑止力になります。
利用時の注意喚起(HTTPS限定、利用制限)
来訪者が安心してゲストWi‑Fiを利用するためには、事前にセキュリティ面での注意喚起を行うことも重要です。
特に 「HTTPS通信のあるサイトのみ利用する」「個人情報やパスワードの入力は避ける」といった基本的な注意点を伝える だけでも、情報漏洩リスクの軽減につながります。
また、業務用の端末でゲストWi‑Fiを使わない、という社内ルールを明確にしておくことも効果的です。
よくあるQ&A
A
結論から言うと、WEPやTKIPは「使えるが、使ってはいけない」暗号方式です。WEPは20年以上前の技術であり、数分で解読されてしまうほど脆弱です。TKIPもWPAの初期段階に採用されましたが、現在の基準では安全とは言えません。実際、最新のWi‑Fi認証ではWEPやTKIPを非推奨と明記しており、機器メーカーもサポートを終了しつつあります。法人や店舗で安全なWi‑Fiを構築するには、WPA2(AES)かWPA3への移行が必須です。古い規格は早急に見直しましょう。
A
WPA3はセキュリティ性の高い最新の暗号化方式ですが、古いルーターや端末は対応していないことがあります。対応状況は機器のスペックやメーカーによって異なり、ファームウェア更新で使えるようになる場合もあれば、物理的に対応できないこともあります。確認方法としては、メーカーサイトで製品型番を調べるのが確実です。もし非対応であれば、セキュリティの観点からも新しい機器への買い替えが望ましいと言えるでしょう。
A
モバイルWi‑FiやIoT機器も、原則として同様のセキュリティ対策が必要です。特にIoT機器は「セキュリティが弱く、管理されにくい」という特徴があり、攻撃の足がかりにされやすい存在です。たとえば、IPカメラやスマート照明の初期パスワードをそのまま使っていると、外部から不正操作される恐れがあります。また、モバイルWi‑Fiも暗号化やパスワード管理を怠ると、社外で情報漏洩するリスクがあります。
A
Wi‑Fiセキュリティをより強化するには、VPN(仮想プライベートネットワーク)やクラウド型セキュリティの導入が効果的です。VPNは通信を暗号化し、外出先やゲストWi‑Fiなどでも安全な通信環境を保てます。特にリモートワークや外部業者との連携がある場合には必須と言えるでしょう。また、クラウド型UTMやエンドポイントセキュリティを併用することで、ネットワーク全体を可視化し、未知の脅威にも対応できます。
まとめ
Wi‑Fiは便利な反面、セキュリティを怠ると情報漏洩や不正アクセスといった重大リスクを招きます。
本記事では、暗号化方式の選定からルーター設定、ゲストWi‑Fiの運用、さらに運用後の監視体制まで、法人・店舗が取るべき対策を体系的に整理しました。
Wi‑Fiの安全は、一度きりの設定ではなく「継続的な管理」と「正しい設計」があってこそ守られます。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!