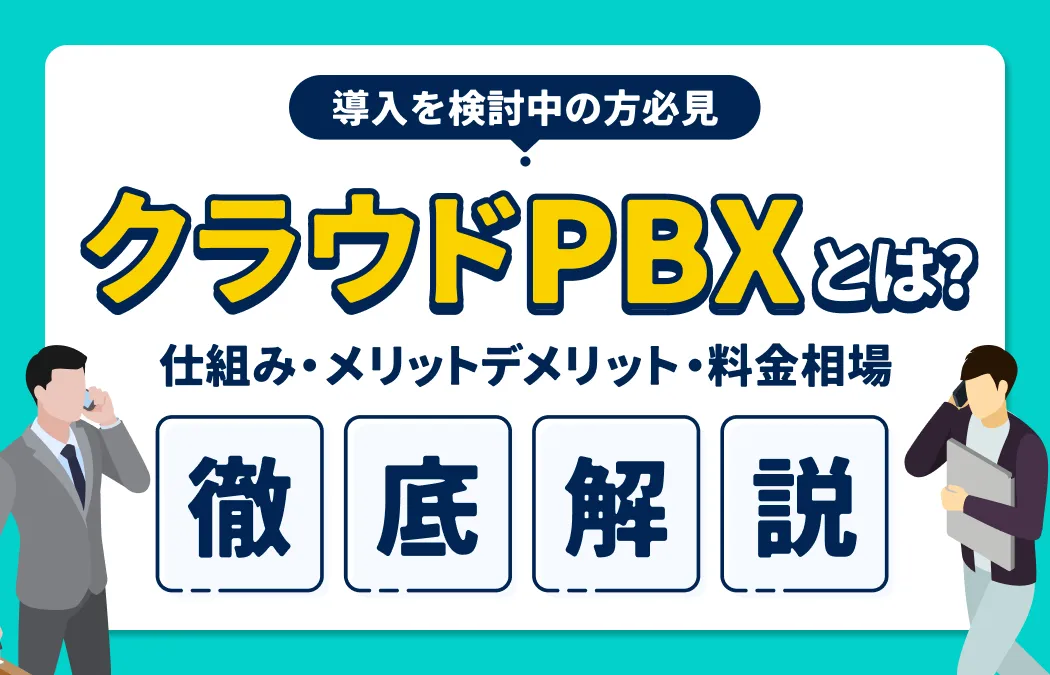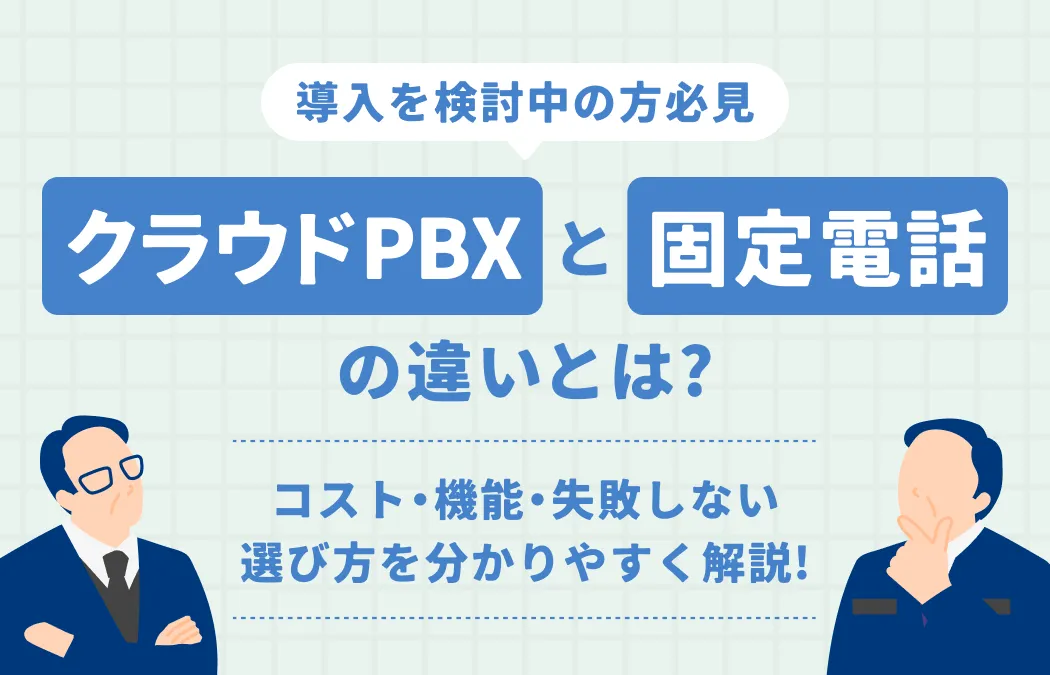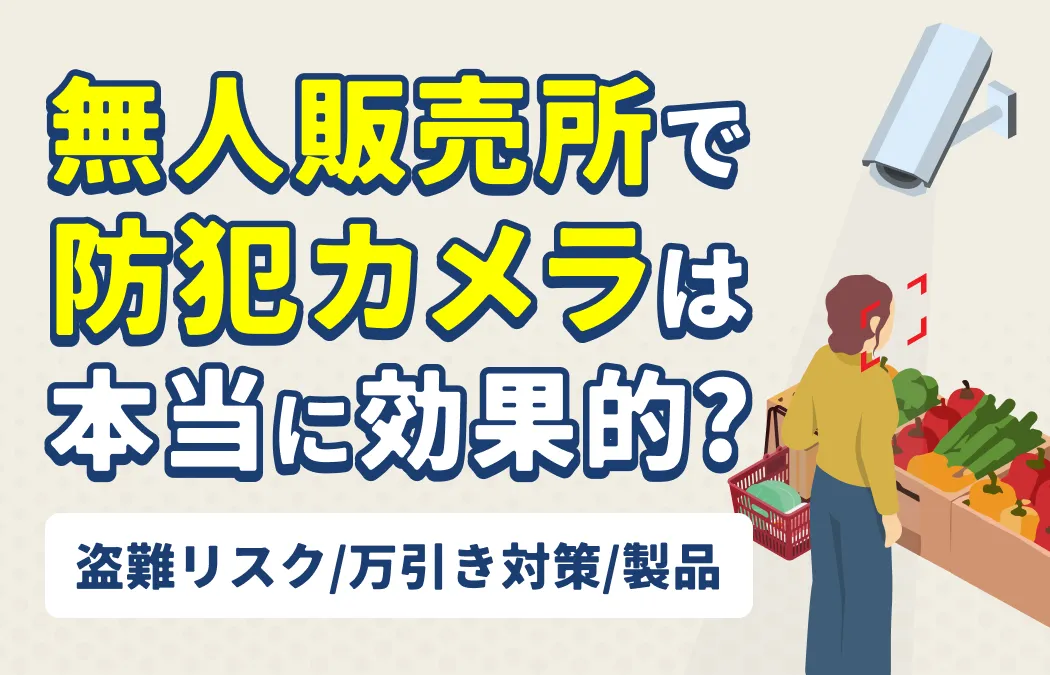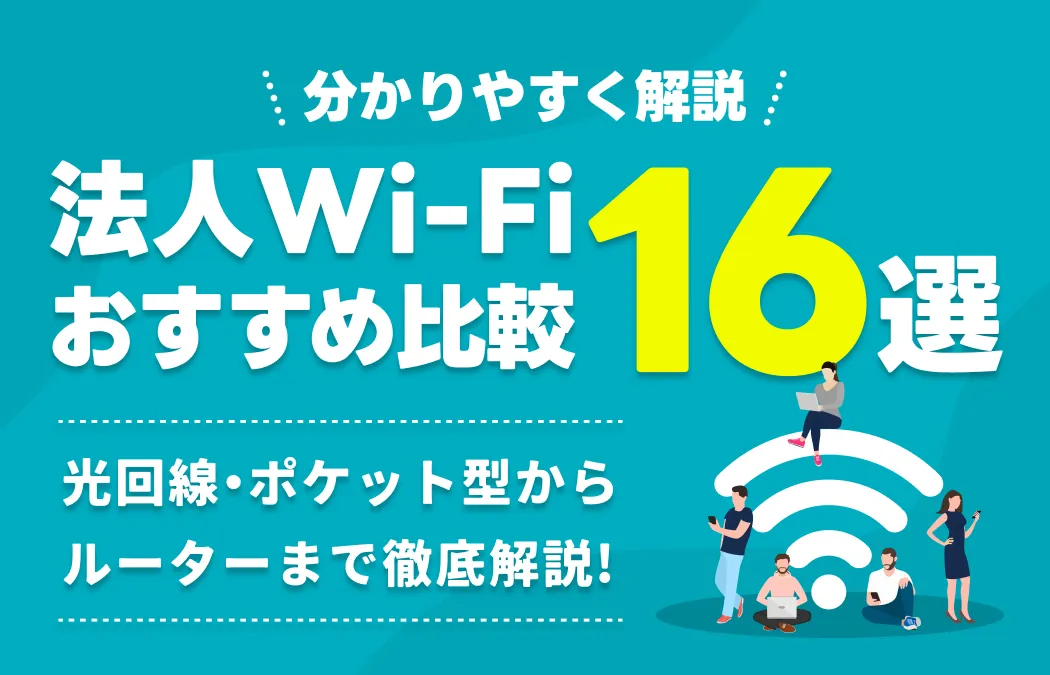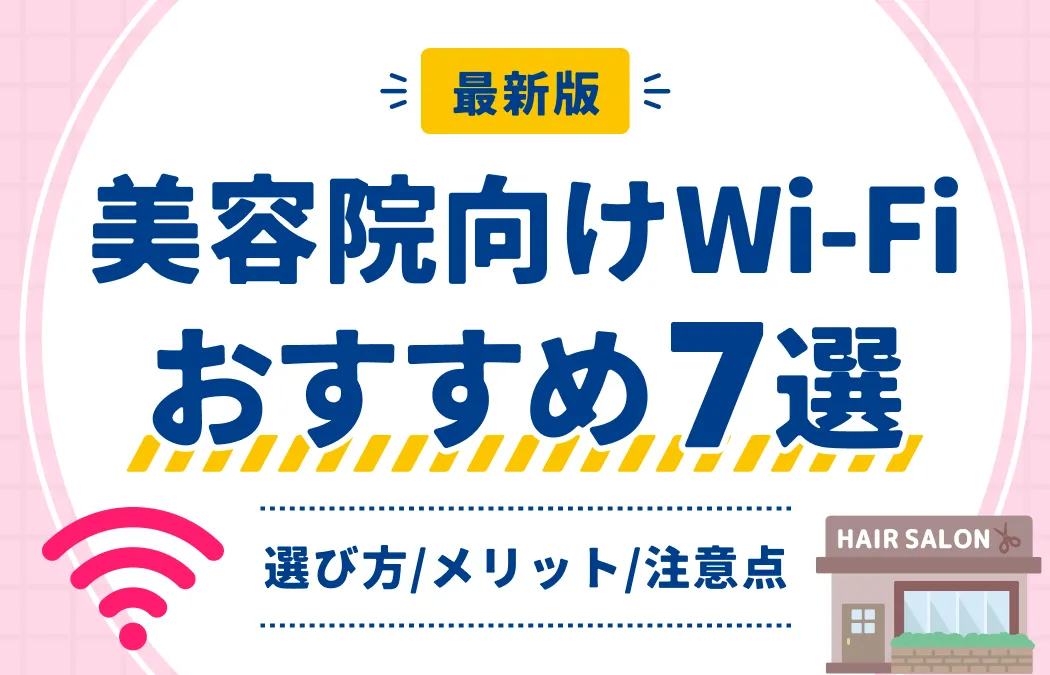「帯域の違いで、通信速度や接続安定性は本当に変わるの?」
自宅やオフィスのネット環境を快適にしたいと思ったとき、Wi-Fiの“帯域(周波数帯)”の違いに迷う方は少なくありません。
実はこの帯域の選び方によって、通信速度や接続の安定性、障害物への強さなどが大きく変わります。
しかし、「どっちの帯域がおすすめ?」「どっちに繋がってるか調べる方法は?」といった疑問を抱く方もいるはずです。
本記事では、2.4GHzと5GHzの特徴や違いをわかりやすく比較し、用途に応じた最適な選び方を解説します。
周囲の電波干渉を避けたい、オンライン会議が途切れて困る…そんな悩みを解決するヒントがきっと見つかります。
目次
▼この記事で紹介している商品
Wi‑Fi帯域(周波数帯)とは?基礎知識と規格概要
Wi‑Fi帯域とは何か?
Wi‑Fi帯域とは、 電波が飛ぶ「周波数の範囲」 のことを指します。
現在のWi‑Fiでは主に2.4GHz帯と5GHz帯の2種類があり、それぞれに特徴と使い分けがあります。
- 2.4GHz帯 :広い範囲に届きやすいのが強みで、障害物にも比較的強く、古い機器にも対応。
- 5GHz帯 :通信速度が速く安定しやすい反面、電波の届く距離が短く、壁などの障害物に弱いという欠点も。
Wi‑Fiの通信品質は、この帯域の選び方によって大きく左右されるため、正しく理解することが重要です。
IEEE802.11 規格と帯域対応(Wi‑Fi4〜6/Wi‑Fi 6E の6GHz含む)
Wi‑Fiには 「IEEE802.11」という国際規格があり、世代ごとに性能と対応帯域が異なります 。
たとえば、Wi‑Fi 4(802.11n)は2.4GHzと5GHzの両方を使えますが、Wi‑Fi 5(802.11ac)は5GHz専用です。
またWi‑Fi 6(802.11ax)は両帯域に対応し、より高速で多接続にも強くなっています。さらにWi‑Fi 6Eでは新たに6GHz帯が加わり、混雑の少ない広い帯域が利用可能に。
規格によって利用できる周波数が変わるため、端末やルーター選びでも確認が欠かせません。
現在の最新規格は「Wi‑Fi 7(IEEE 802.11be/EHT)」です
Wi‑Fiの規格ごとの特徴
| 対応帯域 | 最大通信速度の目安 | 主な特徴 | IEEE規格 | |
|---|---|---|---|---|
| Wi‑Fi 4 | 2.4GHz / 5GHz | 最大600Mbps | 初のデュアルバンド対応、現在も広く普及 | 802.11n |
| Wi‑Fi 5 | 5GHzのみ | 最大6.9Gbps | 高速通信に対応、5GHz専用で混雑に強い | 802.11ac |
| Wi‑Fi 6 | 2.4GHz / 5GHz | 最大9.6Gbps | 多接続に強い(OFDMA・MU-MIMO対応) | 802.11ax |
| Wi‑Fi 6E | 2.4 / 5 / 6GHz | 最大9.6Gbps以上 | 新たに6GHz帯を追加、干渉の少ない広帯域を実現 | 802.11ax(拡張) |
| Wi‑Fi 7 | 2.4 / 5 / 6GHz | 最大46Gbps(理論値) | 320MHz幅/多重同時通信で大容量・低遅延を実現 | 802.11be |
2.4GHz帯のメリット・デメリット
2.4GHz帯のメリット|遠くまで電波が届きやすく、幅広い機器と互換性あり
2.4GHz帯の最大のメリットは、 電波が遠くまで届きやすく、壁などの障害物にも比較的強い点です。一戸建ての2階や奥まった部屋でも接続が安定しやすい傾向があります。
また、多くの機器が2.4GHz帯に対応しているため、互換性の高さも魅力。古いスマホやプリンターなど多くの機器が対応しており、倉庫の監視カメラや古いノートPCなどでも問題なく接続可能です。
2.4GHz帯のデメリット|干渉が多く、通信速度が低下しやすい
2.4GHz帯は電波干渉を受けやすく、通信が不安定になることもあります。電子レンジやBluetooth機器など電と周波数が重なっており、電波が混雑しやすい点に注意が必要です。
また、理論上の通信速度が5GHz帯と比べて低いため、大容量ファイルの送信やオンライン会議には不向きです。複数人が動画を同時視聴すると、画質低下や接続が切れることも。
5GHz帯のメリット・デメリット
5GHz帯のメリット|高速・安定通信で動画や会議に最適
5GHz帯の大きな魅力は、通信速度が速く、電波干渉が少ない点です。2.4GHz帯と比べて、家電製品や他の無線機器との競合が少ないため、安定した通信が可能。
特に、高画質な動画のストリーミングやオンライン会議、クラウド上のデータ編集など、高速かつ安定した接続が求められるシーンに最適です。
たとえば、店舗でPOSレジや監視カメラなど複数機器を同時に使う場合でも、通信がスムーズに行えます。
5GHz帯のデメリット|距離と障害物に弱く、接続が不安定になることも
5GHz帯は電波の特性上、壁や床などの障害物に弱く、通信範囲が狭くなる傾向があります。そのため、ルーターから離れた部屋では通信が届きにくくなることがあります。
さらに、日本国内では気象レーダーや航空レーダーと干渉する「DFS」機能により、一時的に通信が切断されるケースもあります。
たとえば、動画を見ている途中に突然接続が切れる、といった現象が起こることも。利点の多い帯域ですが、利用環境によっては注意が必要です。
WiFiの見直しをプロがサポート
【無料】お問い合わせはこちら2.4GHz と 5GHz の使い分けシーン別比較
自宅での利用なら2.4GHzが有利なケースもある
自宅でWi‑Fiを使う場合、ルーターから離れた部屋や、壁が多い間取りでは2.4GHz帯が有利です。
この帯域は電波が遠くまで届きやすく、障害物の影響も受けにくいため、 2階や玄関先などルーターから離れた場所でも通信が安定しやすくなります 。
たとえば、寝室にあるスマートスピーカーや防犯カメラを接続する場合、2.4GHz帯のほうが安定した利用が可能です。
速度よりも「どこでもつながること」を優先したい場合は2.4GHz帯が適しています。
高速通信を重視するなら5GHzがおすすめ
オフィス・店舗での利用や、動画視聴、オンライン会議、ゲームなど、通信速度と安定性が求められる用途 では5GHz帯が効果的です。
5GHz帯は他の家電との干渉が少なく、通信速度が速いため、通信量が多い状況でもスムーズに処理できます。
たとえば、店舗でタブレットを使った接客や、オフィスでのクラウド業務には5GHz帯が適しています。
ただし、壁や階の影響で電波が届きにくいこともあるため、利用場所に応じた判断が必要です。
スピード優先なら5GHz帯を選びましょう。
バンドステアリング機能で自動切り替えも可能に
最近のルーターには「バンドステアリング」と呼ばれる機能が搭載されているものもあり、これを活用すれば 2.4GHzと5GHzの最適な帯域を自動で切り替えてくれます 。
混雑状況に合わせて、端末が5GHz帯から2.4GHz帯にスムーズに切り替わることで、接続が途切れることなく安定します。
SSIDを分けずに1つにまとめることで、ユーザーは帯域を意識せずに快適な通信が可能になるのです。
特に、複数端末が混在する環境ではこの機能の活用が効果的です。
最適な帯域選びの3ステップ
- リ接続する端末の場所や用途を確認
- 使用機器がどの帯域に対応しているかを調べる
- 2.4GHzと5GHzの特性をふまえて、それぞれの環境に適した帯域を設定
たとえば、 距離が遠いスマート家電は2.4GHz、動画視聴や会議に使う端末は5GHzに設定することで、速度と安定性を両立可能 です。帯域を意識するだけで、通信環境は格段に改善されます。
Wi‑Fi環境改善の設定と確認ポイント
ルーター設定で帯域の有効化やチャンネル調整を行う
Wi‑Fiが不安定な場合、まずはルーターの設定を見直すことが大切です。 2.4GHzと5GHzの両方が有効になっているか、管理画面で確認 してみましょう。
また、近隣と電波が重なっていると干渉が起きやすくなるため、「チャンネル」を手動で変更するのも効果的です。
たとえば、2.4GHz帯は1・6・11番のいずれかを選ぶと、干渉を避けやすくなります。こうした設定の最適化により、通信の安定性を大きく改善できる可能性があります。
混雑状況は「Wi‑Fiアナライザー」で目視確認を
自宅やオフィスでどの周波数が混雑しているかを把握するには、「Wi‑Fiアナライザー」アプリの活用がおすすめです。
このツールを使えば、 周辺のアクセスポイントや使用チャンネルがグラフで可視化され、自分のWi‑Fiが干渉を受けているかどうかがひと目で分かります 。
たとえば、同じチャンネルに複数のルーターが集中している場合、通信速度が著しく低下する原因になります。
事実を把握し、的確な設定を行うために、分析ツールの活用は非常に有効です。
古い端末の規格・帯域対応もチェックしよう
意外と見落とされがちなのが、使っている端末のWi‑Fi規格です。
古いスマートフォンやパソコンは最新のWi‑Fi規格や5GHz帯に対応していない場合があり 、せっかく高速なルーターを導入しても、性能を十分に引き出せません。
たとえば、Wi‑Fi‑nまでしか対応していない端末では、Wi‑Fi 6ルーターの恩恵を受けにくくなります。
通信環境を改善するには、端末の対応状況も含めて確認することが重要です。
Wi‑Fi帯域だけで解決できないケースと導入検討のすすめ
多数同時接続や業務利用では帯域だけでは限界がある
Wi‑Fiの帯域を最適化しても、接続台数が多かったり、大容量通信が頻発する環境では限界があります。
特に オフィスや店舗などでは、スマホ・タブレット・POSレジ・監視カメラなど、同時接続される機器が増えやすく、それだけで通信が不安定に なることも。
たとえば、昼休みの時間帯にWi‑Fiが極端に遅くなるといった現象は、帯域だけでは解消しきれない課題です。
複数端末が常時つながる環境では、より包括的な対策が必要になります。
建物構造や外的要因で電波が届かないケースもある
Wi‑Fiの電波は建物の構造や材質によっても大きく影響を受けます。
たとえば、 鉄筋コンクリート造の建物や、金属製の棚が多い倉庫では、電波がうまく届かず、通信が不安定になる ことがあります。
また、近隣の無線環境や電波干渉など、外部の要因も無視できません。
こうした場合、単に帯域を切り替えるだけでは効果が薄く、アクセスポイントの増設や専用Wi‑Fi設備の導入が求められます。
プラットWi‑Fiの導入で広範囲・安定接続を実現

プラットWiFiは、従来のWiFiルーター製品よりも広範囲かつ高速で安定的な通信を実現する店舗向けの高性能WiFiです。
複数のアクセスポイントを設置して、より広範囲までWiFiを行き渡らせる ため、接続台数が増えても快適な通信環境を維持できます。
また、高性能ルーターに加え、インターネット環境も一緒に見直しして高速化することも可能です。
さらに、WiFiを使ったチラシや1000万ダウンロードアプリとの連携で集客・売上アップも実現できます。
サービス詳細をチェックす
サービス詳細ページはこちらサービスについて問い合わせる
【無料】お問い合わせはこちらよくある質問(FAQ)
A
はい、現在の多くのルーターでは2.4GHzと5GHzの同時利用が可能です。これは「デュアルバンド対応」と呼ばれ、端末ごとに適した帯域へ自動で接続できます。たとえば、古いスマートフォンは2.4GHz帯に接続し、動画視聴に使う最新のタブレットは5GHz帯に接続するといった使い分けが可能です。同時接続によって通信の効率が上がり、混雑や干渉を減らす効果も期待できます。
A
使用している端末が5GHzに対応しているかを調べるには、取扱説明書やメーカーの公式サイトでWi‑Fi規格を確認するのが確実です。「Wi‑Fi‑ac」「Wi‑Fi‑ax」と記載されていれば、5GHz帯への対応があると判断できます。また、接続できるSSIDに「5G」や「_5GHz」といった名称が表示されていれば、対応している可能性が高いです。古い端末では2.4GHzのみ対応のものもあるため、通信速度に不満がある場合は、対応機器への買い替えも検討してみましょう。
A
トライバンドとは、1台のルーターで「2.4GHz帯」と「2つの5GHz帯(または5GHz+6GHz帯)」の3つの周波数を同時に利用できる機能です。これにより、複数端末が同時に接続しても混雑しにくく、通信速度の低下を抑えられます。たとえば、動画配信やオンライン会議、IoT機器の制御などを同時に行っても、それぞれが異なる帯域を使うことでスムーズな通信が可能です。
まとめ|最適な帯域選びと通信環境の見直しでWi‑Fiは劇的に改善できる
Wi‑Fiの通信品質は、「2.4GHz」と「5GHz」という周波数帯の特性を正しく理解し、用途に応じて使い分けることで大きく改善できます。
2.4GHz帯は広範囲への安定した接続に、5GHz帯は高速で干渉に強い通信に向いており、状況に応じた選択が肝心です。
ただし、機器の性能や建物の構造、接続端末の数によっては、帯域の切り替えだけでは限界があります。
通信環境の不安定さに悩んでいるなら、まずは現在のWi‑Fi設定を見直しつつ、必要に応じてプロに相談してみるのが最も確実な一歩です。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!