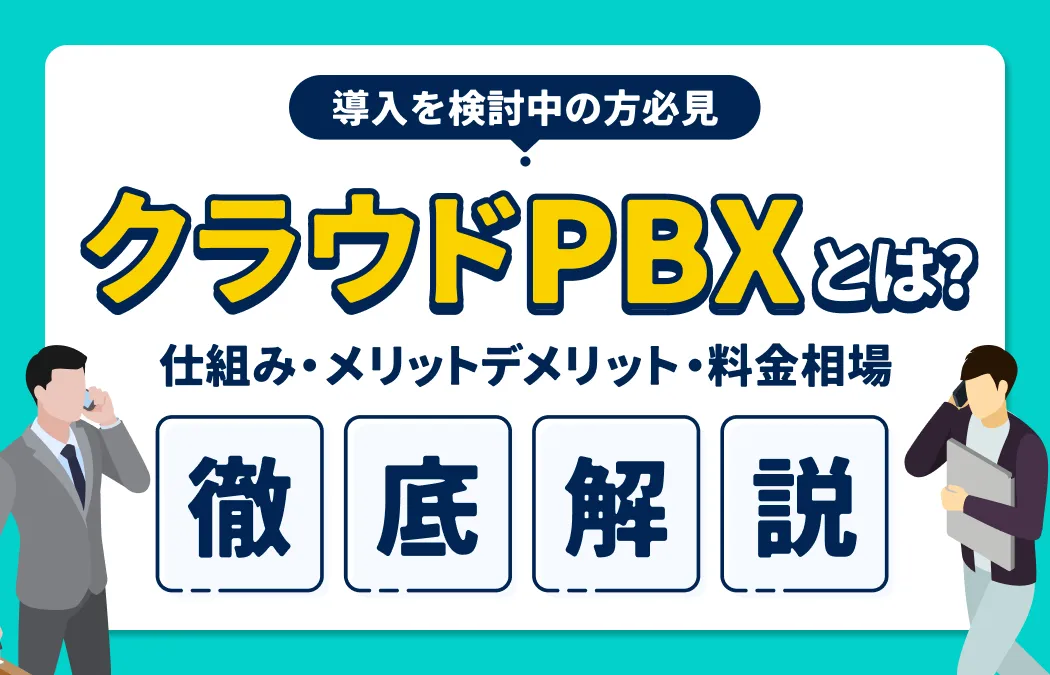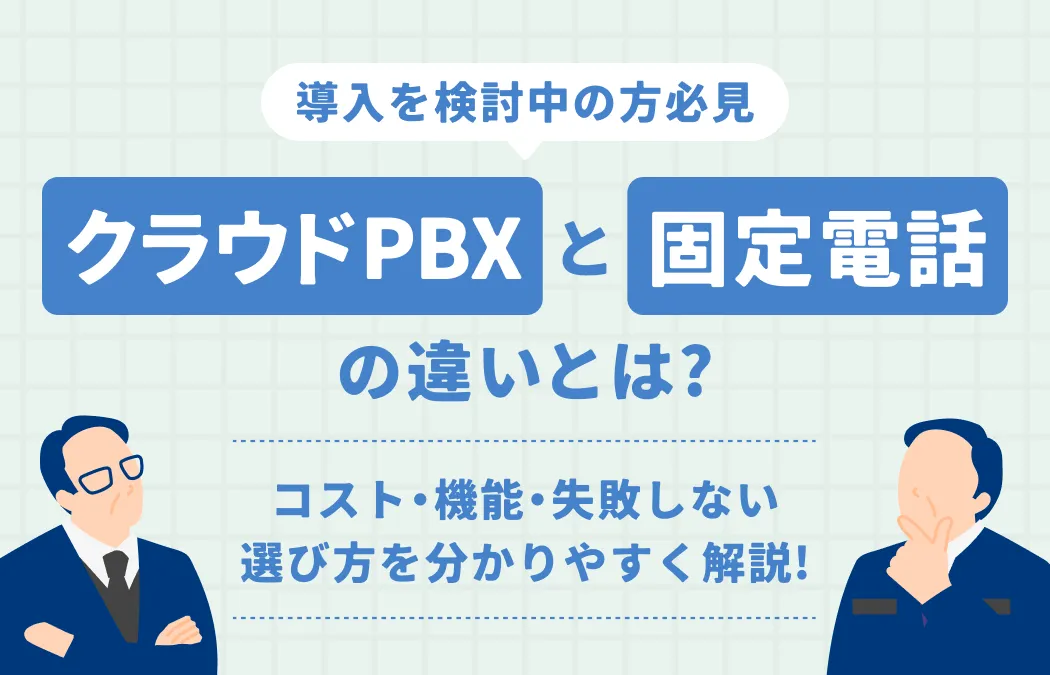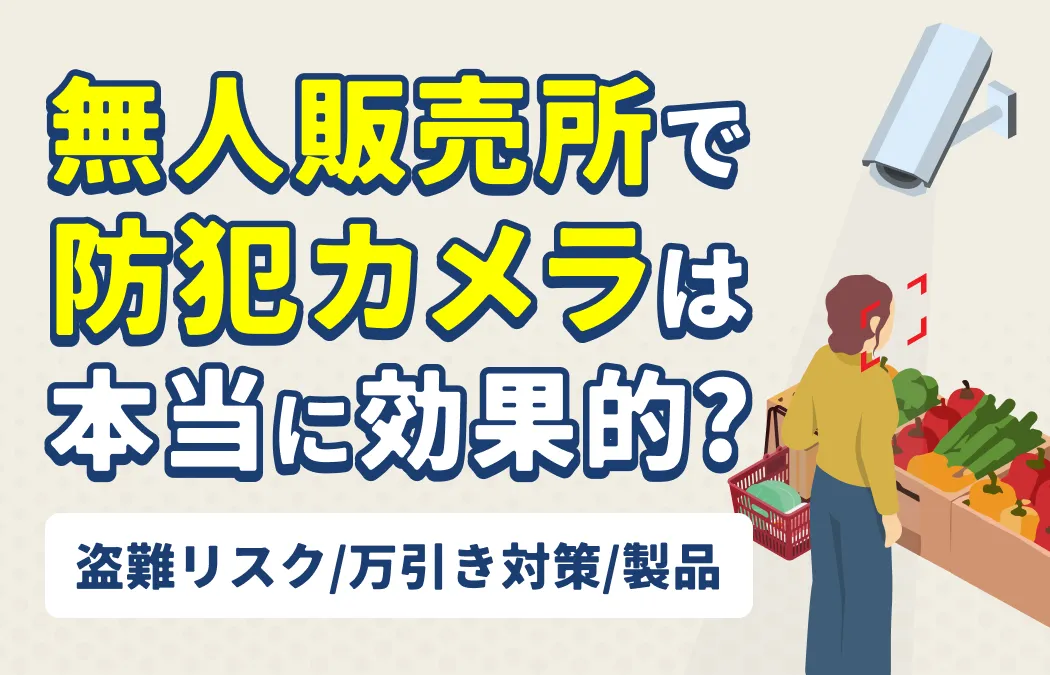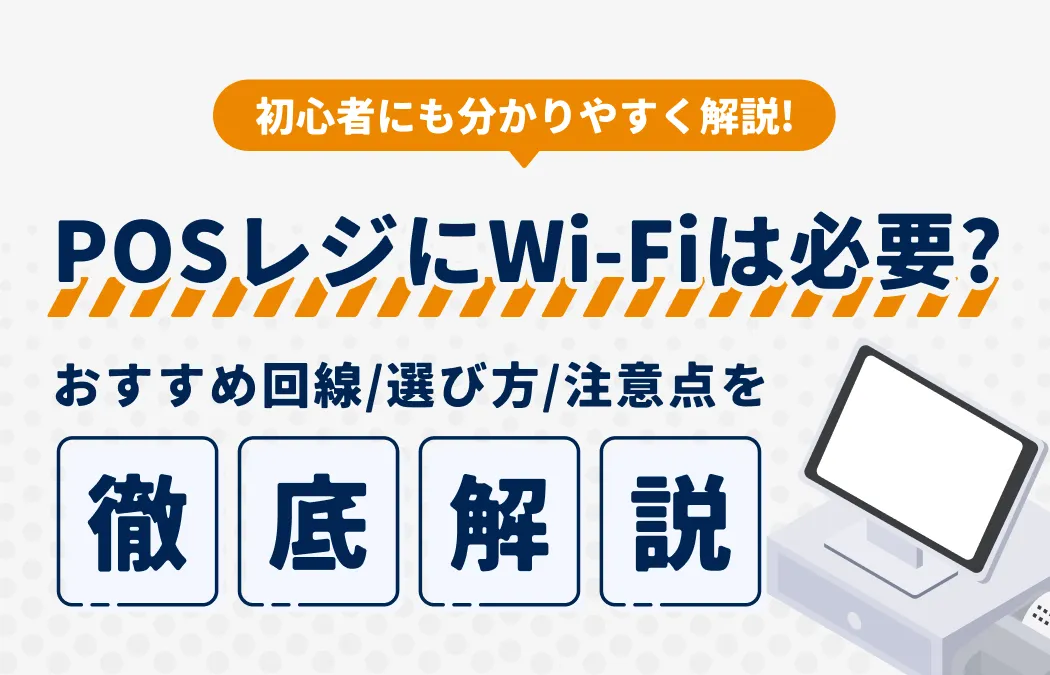「Wi-Fi 6との違いは?」
「自宅の通信速度を思いっきり上げたい!」
「Wi‑Fi 7」は、2023年に日本で解禁された最新の無線規格です。
しかし、「Wi-Fi6と比べてどのくらい速くなる?」「対応端末でないと使えない?」といった疑問を抱く方も少なくないはずです。
本記事では、WiFi 7について、従来のWi‑Fi 6/6Eとの違い、対応端末、導入メリットを自宅や店舗で活かす方法までをわかりやすく解説します。
目次
Wi‑Fi 7とは何か?
正式名称と規格(IEEE 802.11be/EHT)
Wi‑Fi 7の正式名称は「IEEE 802.11be」で、Enhanced High Throughput(EHT)とも呼ばれる次世代の無線LAN規格です。
これは、 Wi‑Fi 6の進化版として、通信速度や安定性、遅延の少なさをさらに向上させたもの です。
IEEE(米国電気電子学会)により標準化されており、家庭用だけでなく業務用ネットワークにも幅広く対応できるよう設計されています。
現在の最新規格として、今後10年の通信インフラを支える基盤となる存在です。
Wi‑Fi6/6Eとの比較
Wi‑Fi 7は、Wi‑Fi 6や6Eと比べて大幅に性能が向上しています。
最大通信速度はWi‑Fi 6の約9.6Gbpsから、 Wi‑Fi 7では理論値で最大46Gbpsにまでアップ。これは約5倍近い速度です 。
さらに、通信の通り道である「帯域幅」も160MHzから320MHzへ拡張され、より多くのデータを同時にやり取りできるようになりました。
また、Wi‑Fi 6Eが6GHz帯に初めて対応したのに対し、Wi‑Fi 7ではそれをさらに活用し、混雑を避けた高速通信が可能になります。
Wi‑Fi 7の主要技術とその効果
320MHzチャネルのメリット(帯域拡張効果)
Wi‑Fi 7では、最大320MHzのチャネル帯域が利用できるようになり、従来のWi‑Fi 6の2倍の幅を持つ通信が可能になります。
帯域幅とは、データの通り道の広さを表すもので、広いほど一度に大量の情報をやり取りが可能 です。
たとえば、高速道路において、160MHzが2車線道路だとすれば、320MHzは4車線のようなイメージです。
この拡張により、より多くのデバイスが同時に高速で通信できるようになり、混雑や速度低下が起きにくくなります。
これにより、自宅でもオフィスでも快適な通信環境を維持しやすくなります。
4096‐QAMによる変調効率化
Wi‑Fi 7では、「4096-QAM(キューエーエム)」という新しい変調方式が採用されています。これは、通信品質の底上げに貢献する技術です。
具体的には、 1回の信号でより多くのデータを送れる仕組みで、従来のWi‑Fi 6が使っていた1024-QAMよりも約20%通信効率が向上 します。
つまり、 同じ電波環境でもより多くの情報を詰め込めるため、速度の向上が期待できます 。
特に、高画質な動画ストリーミングや、大容量ファイルのアップロード・ダウンロードをスムーズに行いたい場面で、この変調方式の恩恵を強く感じられるでしょう。
Multi‑Link Operation(MLO)で通信安定化&低遅延
Wi‑Fi 7の目玉機能のひとつが「Multi‑Link Operation(MLO)」です。
これは、 2つ以上の周波数帯(2.4GHz/5GHz/6GHz)を同時に使って通信する技術で、従来のように1つの帯域に依存しません 。
これにより、ネットワークが混雑している場合でも別の帯域で即座に通信を切り替えられるため、通信が途切れにくく、遅延も最小限に抑えられます。
オンラインゲームやビデオ会議のようにリアルタイム性が求められる用途では、MLOの効果がとても大きいです。
プリアンブルパンクチャリング/Multi‑RUで混雑回避
Wi‑Fi 7では、電波の混雑に強くなるための仕組みも導入されています。
- プリアンブルパンクチャリング
電波の一部が他の電波とぶつかって使えないとき、使える部分だけを切り出して効率的に通信する技術。
従来は全体が使えなければ通信できませんでしたが、これにより無駄が減ります。 - Multi‑RU
複数の小さな通信単位(RU)を柔軟に割り当てることで、多数の機器を同時に効率よく通信させる機能。
カフェやイベント会場など、多数の接続がある場面で特に力を発揮します。
DFS不要の6GHz帯とAFC活用
Wi‑Fi 7は、6GHz帯という新しい周波数を活用することで、従来よりも広くて空いている通信空間を使えるようになります。
6GHz帯は他の機器との干渉が少なく、スムーズ通信が可能 です。
さらに、「AFC(自動周波数制御)」という仕組みによって、周囲の電波状況を自動的に判断し、安全に周波数を割り当てることができます。
これにより、屋外や高出力が必要な環境でも、安定かつ高速な通信が実現できます。

Wi‑Fi 7がもたらす5つのメリット
超高速通信(大容量ファイル・4K/8Kストリーミング)
Wi‑Fi 7の最大の魅力は、圧倒的な通信速度です。理論上は最大46Gbpsとされており、これは光回線の限界をも凌ぐレベル。
高精細な4K・8K映像のストリーミングや、数GBに及ぶファイルの送受信もストレスなく こなせます。
従来のWi‑Fiでは読み込みに時間がかかったコンテンツも、Wi‑Fi 7なら即再生が可能です。
日常利用はもちろん、映像制作やデザイン業務など、高速通信を必要とする場面で特に力を発揮します。
極めて低いレイテンシ(オンラインゲーム・VRにも最適)
Wi‑Fi 7では、遅延(レイテンシ)も大きく改善されています。通信にタイムラグがあると、オンラインゲームでの操作ズレや、ビデオ会議での音声途切れなどが発生しがちです。
しかし、Wi‑Fi 7は MLO(マルチリンク)などの技術により、瞬時に最適な帯域へ切り替えることができ、安定したリアルタイム通信を実現 します。
特にVRやクラウドゲームといった高精度なレスポンスを必要とするコンテンツにおいては、Wi‑Fi 7の低遅延性能がその体験価値を高めてくれます。
多端末同時接続・高密度対応
家庭内やオフィスで複数の端末を接続するのが当たり前になった今、Wi‑Fi 7はそのニーズにしっかり応えます。
複数ユーザーが同時に動画視聴やリモート会議をしていても、速度低下が起きにくいのが特徴です。
これは 「Multi‑RU」や広帯域化によって通信リソースを細かく分け、多数の端末を効率よく処理できる ようになったためです。
スマート家電やIoT機器が増えるこれからの時代には、Wi‑Fi 7の多端末対応力が大きな安心材料になるでしょう。
安定性向上と干渉回避(ビジネス利用でも安心)
Wi‑Fi 7は、混雑した環境下でも安定した通信を保てるように設計されています。
特に都市部やマンションでは、周囲のWi‑Fi電波と干渉することで接続が不安定になることもあります。
Wi‑Fi 7では、 プリアンブルパンクチャリングやMLOといった技術を組み合わせることで、干渉を避けながら効率的に通信を続けることが可能 です。
これにより、業務で大事な会議中に通信が途切れる、といったトラブルも大幅に減らせます。ビジネスの安定運用にも頼れる通信環境を提供します。
互換性と導入しやすさ(既存機器との共存も可能)
Wi‑Fi 7は、新技術でありながらも、既存のWi‑Fi規格との互換性を保っているため、段階的な導入が可能です。
たとえば、 ルーターをWi‑Fi 7対応に切り替えても、今まで使っていたWi‑Fi 5や6の機器もそのまま接続できます 。
これにより、すべての機器を一気に買い替える必要はなく、予算や利用状況に応じた柔軟な運用が可能です。
Wi‑Fi 7の対応端末について
Wi‑Fi 7対応ルーターが必要
Wi‑Fi 7対応ルーターは、すでに国内外で続々と登場しています。
特に ASUSやTP-Linkなどの大手メーカーからは、高性能なゲーミング向けや法人利用を想定したモデルも発売中 です。
Wi‑Fi 7ルーターを選ぶ際は、6GHz帯の対応やMLO機能の有無に注目するのがポイントです。早めに導入すれば、今後の普及期に先駆けて最適なネットワーク環境を整えられます。
スマホ/PC:対応状況(Apple/Samsung等)
Wi‑Fi 7に対応したスマートフォンやパソコンも徐々に増えています。代表的な対応機種としては、Galaxy S25シリーズ以降やXiaomi 13 Proなどが挙げられます。
また、今後登場するiPhoneやPixelシリーズでもWi‑Fi 7対応が見込まれています。 パソコンの場合、最新のIntelチップを搭載したモデルや、Wi‑Fi 7対応のUSBアダプターを使えば利用可能 です。
とはいえ、端末側もWi‑Fi 7に対応していないと、その恩恵は最大限に受けられません。新製品を選ぶ際には必ずスペック表を確認しましょう。
2025年以降の普及見通し
Wi‑Fi 7は、2024年から本格的に対応機器の登場が始まり、2025年以降にかけて急速に普及が進むと見られています。
すでに 一部の高性能ルーターやハイエンド端末では採用が進んでおり、今後は中価格帯製品にも広がっていくでしょう 。
また、法人向けネットワーク機器でもWi‑Fi 7対応が標準になる流れが予想されます。
新しいWi‑Fi規格が世の中に浸透するまでには2〜3年かかるのが通例です。そのため、今から準備しておくことで、最先端の通信環境をいち早く手に入れることができます。
導入前に押さえる注意点
理論値と実効速度のギャップ
Wi‑Fi 7は 理論上、最大46Gbpsという驚異的な通信速度を誇りますが、実際の利用環境ではここまでの速度は出ません 。
壁や家具などの障害物、利用中の端末性能、周囲の電波状況などが影響し、速度は大きく左右されます。
たとえば、家庭用では1〜2Gbps程度が一般的な実効速度となることが多いです。これは決して性能が劣っているわけではなく、どのWi‑Fi規格でも避けられない現実です。
導入時には理論値に期待しすぎず、実環境での速度を重視することが大切です。
対応機器のコストと入手性
Wi‑Fi 7対応機器はまだ新しい規格であるため、価格は高めに設定されています。
たとえば ルーターでは5万円〜10万円前後が相場で、スマートフォンやノートPCも上位モデルに限られる傾向 があります。
また、対応チップセットの供給や技術検証の関係で、製品によっては在庫が不安定なケースもあります。
そのため、導入には予算面と入手タイミングの調整が必要です。早めに情報収集を始め、段階的な機器入れ替えを検討するのがおすすめです。
周波数制限やDFS/AFCルールの地域差
Wi‑Fi 7で利用可能な6GHz帯は、国や地域ごとに使用ルールが異なります。
例えば、 日本では一部の帯域で利用が制限されており、DFS(レーダー検知機能)による通信停止の可能性 があります。
さらに将来的にはAFC(自動周波数制御)に関する規制も関わってくる見通しです。これにより、海外製ルーターをそのまま国内で使うと電波法違反になるリスクもあります。
導入に際しては、日本国内の技術基準に適合しているかどうかを必ず確認する必要があります。
既存ネットワークとの互換性
Wi‑Fi 7は下位互換性があり、Wi‑Fi 6やWi‑Fi 5(ac)などの旧規格の端末とも接続できます。
ただし、 ルーターと端末の両方がWi‑Fi 7対応でなければ、本来の性能は発揮されません 。
また、ルーターの設定やファームウェアが古いと、通信の安定性に影響することもあります。
既存ネットワークの見直しやアップデートが必要になる可能性もあるため、導入前には現在の機器構成と性能を確認しておくと安心です。互換性はありますが、準備は不可欠です。
WiFiの見直しをプロがサポート
【無料】お問い合わせはこちらWi‑Fi 7の導入でできること|シーン別活用法
自宅:高画質動画・ゲーム・スマート家電
Wi‑Fi 7を家庭に導入すると、日常のネット利用が格段に快適になります。
特に 高画質な4K・8K動画のストリーミングや、容量の大きいゲームのダウンロードがスムーズ に行える点は大きな魅力です。
また、スマートテレビや冷蔵庫、照明などのスマート家電も同時に安定接続できるため、家全体のネットワークが一段と効率化されます。
家族が複数のデバイスを使っても通信が遅くならないので、ライフスタイルがますますデジタル化する今、Wi‑Fi 7は自宅ネットワークの中心的存在となるでしょう。
テレワーク:安定性を活かした遠隔業務
Wi‑Fi 7は遅延や途切れの少ない通信が可能なため、Web会議やクラウドアプリの使用時にもスムーズに対応できます。
特に MLO機能により、複数の帯域を同時利用することで回線混雑の影響を受けにくくなります 。
VPN接続やリモートデスクトップでも高速かつ安定した作業環境を構築できるため、出社と変わらないレベルの業務効率が実現します。
在宅勤務が一般化するなかで、Wi‑Fi 7による通信の安定性は仕事の生産性に直結します。
店舗・ビジネス:混雑環境での安定提供/顧客Wi‑Fi品質向上
飲食店やサロン、オフィスなどの店舗では、多数の端末が同時にWi‑Fiに接続する状況が日常的にあります。
Wi‑Fi 7は、こうした 高密度環境でも安定した通信を維持できる点が強み です。
たとえば、来店客用Wi‑Fiと店舗運営用のネットワークを分けながら、どちらも高速かつ安全に保つことが可能になります。
また、SNS投稿や口コミ投稿を促す際に、快適なWi‑Fi環境が整っているかどうかは顧客満足にも影響します。
Wi‑Fi 7の導入ステップ
-
STEP.1
対応ルーターと端末の確認
Wi‑Fi 7の導入前には、スペック表や製品公式ページで自宅や職場の通信機器が対応しているかを確認しましょう。
特に ルーターがWi‑Fi 7に対応していなければ、その性能を活かすことはできません 。
また、接続するスマートフォンやパソコンなどの端末も、Wi‑Fi 7対応モデルであるかが重要です。
対応していない機器でも接続は可能ですが、従来規格での通信となり、速度や安定性の恩恵は得られにくくなります。
-
STEP.2
導入と設定
対応機器がそろったら、次はWi‑Fi 7ルーターの導入と設定です。
多くの最新ルーターは、アプリを使った簡単なセットアップに対応しており、専門知識がなくても短時間で導入できます。
初期設定時にはWi‑Fiの名称(SSID)やパスワードを変更し、セキュリティを高めるのがおすすめ です。
もし設定に不安がある場合は、専門業者の初期設定サービスや遠隔サポートを活用しましょう。
-
STEP.3
通信速テストと運用改善
導入後は、実際にどのくらいの速度が出ているのかを測定することが大切です。「Speedtest」などの無料ツールを使えば、簡単に回線の状態を把握できます。
また、 家のどの場所で電波が弱いのかを確認し、必要に応じてメッシュWi‑Fiの導入やルーターの設置位置の見直しを行う ことで、全体の通信品質をさらに高められます。
Wi‑Fi 7の性能をフルに発揮するには、定期的なメンテナンスと環境最適化がポイントです。
Wi‑Fi 7に関するよくある質問(FAQ)
A
いいえ、Wi‑Fi 7対応ルーターは旧世代の端末(Wi‑Fi 6/5など)とも互換性があり、接続は可能です。ただし、通信は端末側の規格に合わせた速度になります。そのため、Wi‑Fi 7の性能を最大限活かすには、ルーターと端末の両方が対応していることが望ましいです。
A
Wi‑Fi 7は、通信速度・安定性・同時接続数を求める人に特におすすめです。具体的には、オンラインゲームや高画質動画を楽しみたい方、複数人でのテレワーク環境を構築したい家庭、そして業務で安定したWi‑Fiが欠かせないオフィスや店舗などが該当します。今すぐ最大性能を使う必要がなくても、今後の環境変化に備えて導入しておけば安心です。
A
Wi‑Fi 7は最新のセキュリティ規格「WPA3」に対応しており、従来よりも安全性が大幅に向上しています。WPA3は、パスワードの総当たり攻撃に強く、個別暗号化によって通信内容の盗聴も防ぎます。また、複数の帯域を使うMLOにおいても、それぞれの通信経路に対して暗号化が施されるため、総合的なセキュリティレベルは非常に高いといえます。
A
Wi‑Fi 7は、理論上は最大46Gbpsの速度を実現できますが、実際の通信速度は使用環境によって異なります。たとえば、Wi‑Fi 6が1Gbps〜1.5Gbps程度であるのに対し、Wi‑Fi 7では2Gbps〜5Gbps超の実効速度も可能です。これは大容量の動画ファイルが数秒で転送できるレベルです。特に6GHz帯を活用し、干渉の少ない環境が整えば、その差はより顕著になります。
A
Wi‑Fi 7は下位互換性があるため、Wi‑Fi 6や6Eと問題なく共存できます。つまり、Wi‑Fi 7対応ルーターにWi‑Fi 6のスマートフォンやWi‑Fi 5のPCを接続しても、従来通りの通信が可能です。また、Wi‑Fi 7対応端末だけが最新の機能(MLOや4096-QAMなど)を利用する形となるため、段階的な環境移行が現実的に行えます。既存のネットワーク機器を無駄にせず、必要に応じて少しずつWi‑Fi 7に切り替えていくことができる点も大きな利点です。
まとめ
Wi‑Fi 7は、通信速度・安定性・同時接続性のすべてを飛躍的に高めた次世代規格です。
4K/8K動画やオンライン会議、IoTの普及といった現代のニーズにしっかり対応できる性能を備えています。
とはいえ、すぐにすべての機器を買い替える必要はありません。互換性があるため、まずはルーターだけでもWi‑Fi 7対応に切り替えることで、今後の環境整備がスムーズになるでしょう
WiFiの見直しをプロがサポート
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!