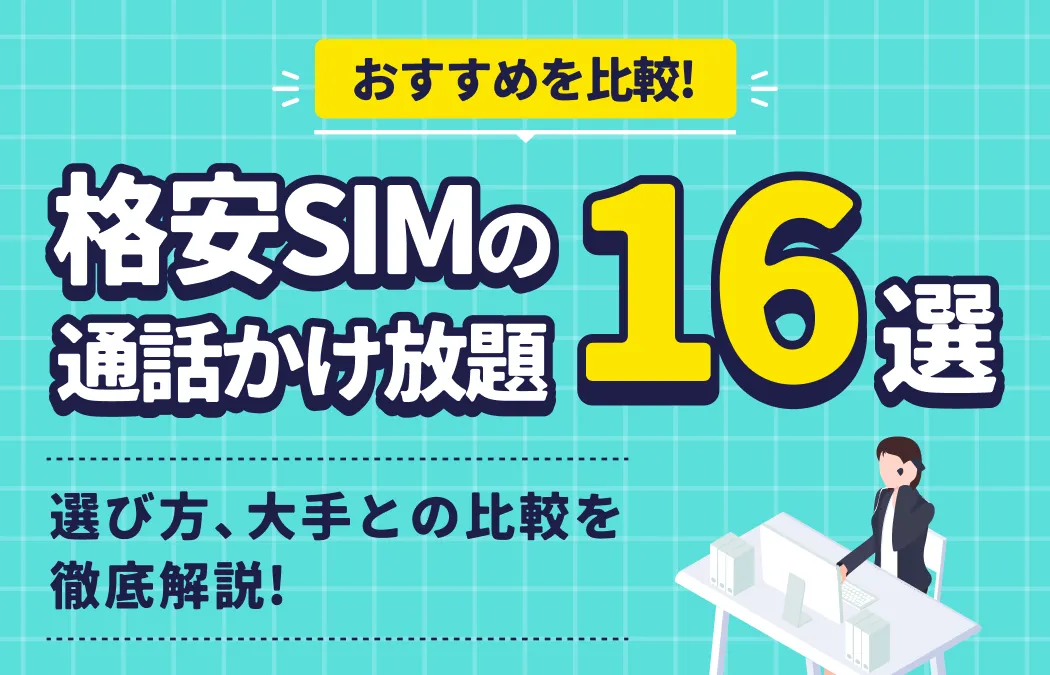「つけっぱなしにした方が電気代が安くなるってホント?」
冷房とドライは、活用すべきシーンが異なるため、目的や状況に合わせて適切に使い分けるのが電気代節約のコツです。
しかし、「冷房とドライってどう違うの?」「ドライは意味がないってホント?」など、疑問も多いはずです。
本記事では、エアコンの冷房とドライの違い、それぞれの役割と使うべきシーン、電気代を節約するための適切な使い方について詳しく解説していきます。
目次
冷房とドライ(除湿)の仕組みと違い
| 冷房 | ドライ(除湿) | |
|---|---|---|
| 仕組み | 室内の熱を外に逃がし、室温を下げる | 空気を冷やして水分を凝縮させ、湿度を下げる |
| 主なメリット |
|
|
| 電気代の傾向 |
|
|
| おすすめのシーン |
|
|
| 快適性の特徴 |
|
|
冷房|部屋の温度を下げる
冷房は室内の空気を冷却し、温度を下げる ことで快適な環境を作ります。空気中の水分も同時に取り除くため、温度と湿度をバランスよく下げられるのが特徴です。
特に猛暑日や帰宅直後など、素早く部屋を冷やしたいときに有効です。一方で、設定温度を低くしすぎると電力消費が増えるため注意が必要です。
適切な温度設定を心がければ、冷房は効率的かつ経済的に利用できる運転モードです。
ドライ(除湿)|部屋の湿度を下げる
ドライ運転には「弱冷房除湿」「再熱除湿」「ハイブリッド除湿」の3種類があり、 部屋の湿度を下げること を目的とした機能です。
- 弱冷房除湿|冷房運転に近く、空気を少し冷やしながら湿度を下げる方式で、比較的電気代が抑えられる
- 再熱除湿|冷房によって冷えた空気を再度温めながら湿度を下げるため、消費電力が高め
- ハイブリッド除湿|両者の特性をバランス良く取り入れた運転で、省エネ性能に優れている
特に、弱冷房除湿は電気代を節約しやすい一方、除湿の効率がやや低いため注意が必要です。
-
湿度が高いと暑さを感じやすい
-
湿度が高いと、同じ気温でも体が感じる暑さが増します。これは、汗が蒸発しにくくなることで体温調節がうまくできず、体内に熱がこもってしまうからです。
例えば、気温30℃で湿度が70%以上になると、体感温度は35℃近くに感じられる場合もあります。この状態では、熱中症のリスクも高まるため注意が必要です。
エアコンの除湿運転やサーキュレーターで湿気を減らすだけでも、体感温度を下げて快適さを保つことができます。
冷房やドライ(除湿)はつけっぱなしの方が安い?
エアコンは短時間の外出なら、つけっぱなしの方が経済的なケースがあります。
起動直後は室内を一気に冷やすため大きな電力を消費しますが、設定温度に達した後は温度を維持するように運転するため、消費電力が安定します。
短時間でオン・オフを繰り返すと、そのたびに湿度と室温を大きく下げるため多くの電力を消費 します。一方、つけっぱなしなら室内環境が安定し、消費電力も低く抑えられます。
特に、30分~1時間未満の外出では、エアコンをつけたままで問題ないでしょう。ただし、1時間~2時間以上部屋を空ける場合は、一度電源を切る方が効率的です。
ドライ(除湿)方式ごとの消費電力・料金目安を比較
ドライ(除湿)の消費電力と、1時間当たりの電気代は以下が目安となります。
| 消費電力(kWh/h) | 料金目安 ※31円/kWh換算 |
|
|---|---|---|
| 弱冷房除湿 | 0.2〜0.5 | 約6〜15円/h |
| 再熱除湿 | 0.5〜0.7 | 約17〜22円/h |
| ハイブリッド除湿 | 0.3〜0.6 | 約9〜18円/h |
弱冷房除湿の電気代は冷房より安い傾向
弱冷房除湿は冷房と同じ冷媒を使いますが、 温度の下げ幅が緩やかな分、冷房よりも消費電力を抑えやすい のが特徴です。
主に、室温を大きく下げず湿度だけを調整したいときに効果的で、梅雨時期や夜間の利用に向いています。
ただし、設定温度や外気温によっては冷房と同等の電力を使う場合もあるため、環境に応じて使い分けることが重要です。
再熱除湿は冷房より高くなる仕組み
再熱除湿は湿気を取り除いた冷たい空気を再び温めて室温を保つ仕組みです。この加温のプロセスに追加の電力を使うため、 冷房より電気代が高くなる傾向 にあります。
1時間あたりの消費電力は他の除湿方式よりも多い傾向にあり、長時間使用すると料金がかさみやすい点がデメリットです。
ただ、室温を下げずに湿度だけを調整できるので、肌寒さを感じやすい時期や冷え性の方には快適な環境を作れるモードです。
ハイブリッド除湿は比較的安い傾向
ハイブリッド除湿は弱冷房除湿と再熱除湿の特性を組み合わせ、省エネと快適性を両立した方式です。
湿度を効率よく下げながら室温の変化を抑えられる ため、体調管理が必要な家庭でも安心して使えます。
電気代は弱冷房除湿とほぼ同程度で、季節を問わず幅広いシーンで使えるため、近年では多くの最新モデルに採用されています。
冷房や除湿の効果は方式・使用環境によって変動
メーカーやモデルによる方式の違い
エアコンの除湿方式はメーカーや機種によって異なります。例えば、 同じ「ドライ」表示でも弱冷房除湿を採用する機種と再熱除湿を使う機種があります 。
リモコンの表示や取扱説明書を確認すれば、どの方式なのかを見分けることが可能です。
方式が分かれば、最適な運転モードを判断しやすくなり、電気代節約にもつながります。まずは自宅のエアコンの仕様を確認することが、賢い使い方の第一歩です。
設定温度・湿度条件による変動
電気代は、設定温度と外気温、室内の湿度によって大きく変わります。
例えば、設定温度が外気温より低すぎると冷房モードの稼働時間が増え、電力消費が増大します。逆に、 外気温との差を少なく設定すれば消費電力を抑えられます 。
また、湿度が高い状態では除湿モードが長時間稼働するため、結果的に電気代が高くなることもあります。環境に合わせた設定調整が、効率的な節電につながります。
冷房とドライは、一概に「どちらが安い」とは言えない
冷房とドライのどちらが安いかは、一概には決められません。 エアコンの機種、使用時間、外気温や湿度など、多くの要因が電気代に影響 します。
そのため、短時間なら冷房が効率的でも、長時間の運転では除湿の方が有利な場合もあります。
重要なのは、シーンや目的に合わせて柔軟にモードを使い分けることです。状況を見極めた運転が、快適性と節約の両立に最も効果的です。
シーン別おすすめの使い分け方
- 暑さが厳しい・帰宅直後で室温が高い→冷房
- 気温は高くないが湿気が多くジメジメ→ドライ(除湿)
- 洗濯物の室内干しや睡眠時の湿気対策→ドライ(除湿)
暑さが厳しい・帰宅直後で室温が高い:冷房
猛暑日や帰宅直後に部屋が熱気でこもっている場合は、冷房モードで一気に室温を下げるのが効率的です。短時間で快適な温度にでき、無駄な電力消費を抑えられます。
室温が安定したら温度を1〜2度高めに設定し、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる とさらに節電効果が高まります。
冷房は初動で力を発揮するモードと捉え、短時間での切り替えを意識すると電気代の無駄を防げます。
気温は高くないが湿気が多くジメジメ:ドライ(除湿)
外気温がそれほど高くないのに湿気で不快なときや、冷房で室温が十分に下がっているのに湿気だけが気になる場合は、ドライ(除湿)が最適です。
温度を下げすぎず、 室温を一定に保ちながら湿度を効率的に下げられるため、冷え過ぎを防ぎつつ快適さを保てます 。
特に冷えを防止し、体調を優先したいときや、肌寒さを感じやすい方に適した使い方です。また、湿気によって暑苦しさを感じやすい梅雨の時期や雨の日にも効果的です。
洗濯物の室内干しや睡眠時の湿気対策:ドライ(除湿)
部屋干しで湿気がこもるときや、夜間の湿気による寝苦しさを解消したい場合は、除湿モードの活用がおすすめです。
湿度を下げることで乾燥が早まり、カビやダニの発生を防ぐ効果も あります。
特に、弱冷房除湿なら消費電力を抑えながら快適さを維持しやすく、必要に応じてタイマー機能を活用すればさらに節約可能です。
電気代節約の追加対策:運転効率と料金プラン見直し
サーキュレーター・扇風機の併用
冷房や除湿と併せてサーキュレーターや扇風機を使うと、室内の空気が循環し、体感温度も下がります。
エアコンから出た空気が効率的に部屋全体へ行き届くため、 設定温度を高めに保ったまま快適さを維持でき、消費電力を抑えられます 。
例えば、サーキュレーターで冷房効率を高め、冷房設定を1度上げるだけでも、年間で数千円の節約に繋がる可能性があります。
電気代を効率よく削減したいなら、空気の流れを工夫することが重要です。
自動運転や高めの設定温度を活用
エアコンの自動運転機能は、 最適な温度と風量を自動で調整してくれるため、余分な電力消費を防ぐ 効果が期待できます。
また、設定温度を1〜2度高めに設定するだけでも電気代を大幅に削減可能です。特に長時間使用する場合は、この小さな工夫が大きな節約につながります。
無理に冷やし過ぎないことで体への負担も軽減でき、健康面でもメリットが得られます。
電気料金プラン・電力会社の見直し
エアコンの効率的な運転と合わせて、電気料金プランの見直しも効果的です。
例えば使用量が多い家庭なら、 従量制から定額制プランへの変更や電力会社の乗り換えで年間1万円以上の節約になるケースも あります。
近年はシミュレーションツールも充実しており、自宅の使用状況に最適なプランを簡単に比較できます。
運転方法の工夫と料金見直しを組み合わせることで、節約効果を最大化できます。
冷房とドライ(除湿)に関するよくある質問
A
リモコンや取扱説明書で確認するのが一番確実です。「再熱除湿」や「再熱ドライ」と表記があれば再熱方式、それ以外は弱冷房除湿の可能性が高いです。メーカーサイトでも仕様を調べられるので、購入時や使用前に確認すると安心です。
A
「ドライ運転は意味がない」というのは誤解です。ドライ運転は湿度を下げて体感温度を下げる効果があり、梅雨時や夜間の寝苦しさ対策に有効です。ただし、気温が高い真夏日は冷房の方が効率的な場合が多く、状況に応じた使い分けがポイントです。
A
長時間運転で室内が適度に乾燥していれば、カビの発生リスクはむしろ低くなります。ただし、停止後に室内機内が湿ったまま放置されるとカビが生える原因になります。冷房・ドライ運転後は送風運転や内部乾燥機能で内部を乾かすことが効果的です。
A
基本的に「除湿」と「ドライ」は同じ機能を指し、呼び方が違うだけです。ただし、メーカーによっては「除湿=再熱除湿」「ドライ=弱冷房除湿」とモードを分けている場合があります。機種ごとの仕様を確認し、目的に合ったモードを選ぶことが大切です。
A
31円/kWh換算の場合、エアコンの除湿を1ヶ月つけっぱなしにした場合の電気代は以下が目安です。
・弱冷房除湿の場合:6~15円/h×24時間×30日=4,320円~1万800円
・再熱除湿の場合:17~22円/h×24時間×30日=1万2,240円~1万5,840円
・ハイブリッド除湿の場合:9~18円/h×24時間×30日=6,480円~1万2,960円
まとめ
冷房と除湿の電気代は、使用時間や環境によって変動するため、自宅の状況に合わせた調整が必要です。
室温や湿度、利用シーンを踏まえて運転モードを使い分けることで、無理なく電気代を抑えられます。日中の冷房、夜間や梅雨時の弱冷房除湿など、賢い組み合わせを意識しましょう。
さらに電気代を抑えるなら、電力会社の乗り換えを検討しましょう。今の使用状況を確認したうえで適したプランを選べば、年間で数千円〜数万円の節約も可能です。
最適な電力会社をプロがご提案!
【無料】お問い合わせはこちら
この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!