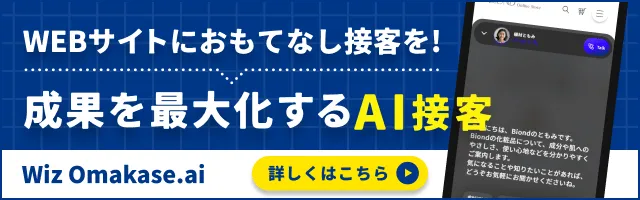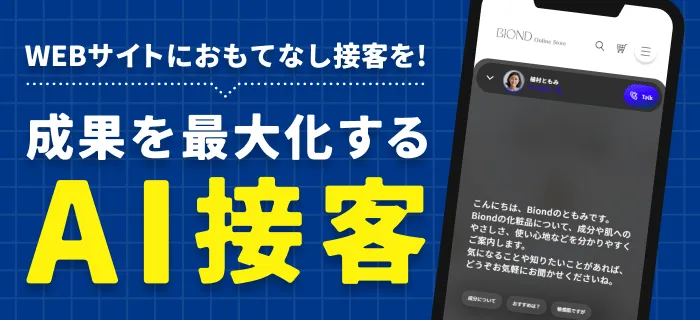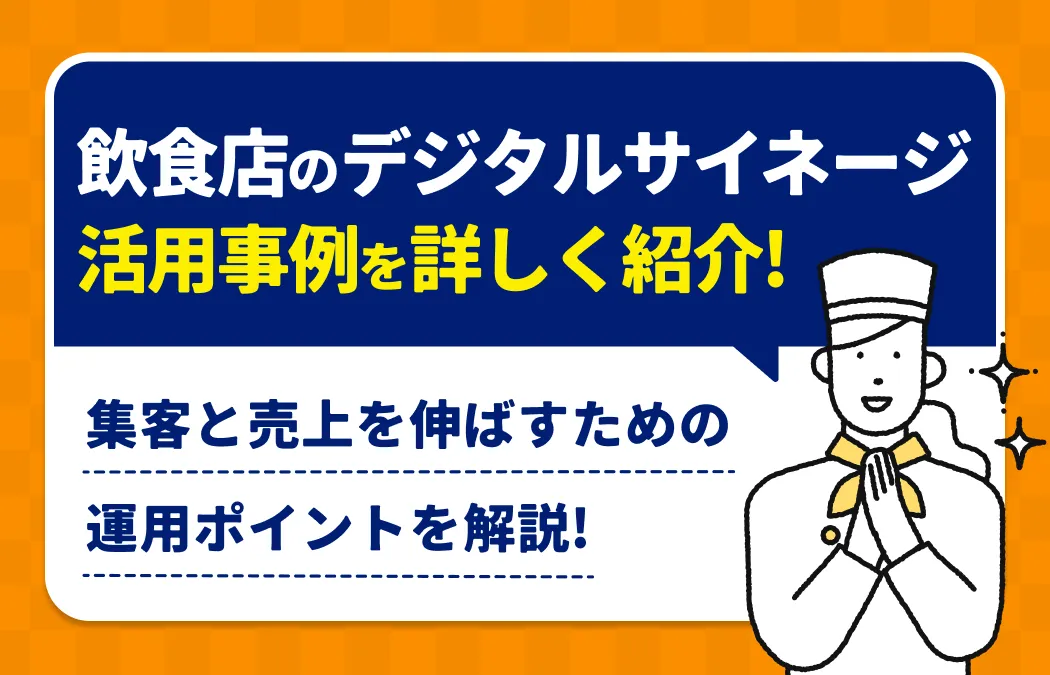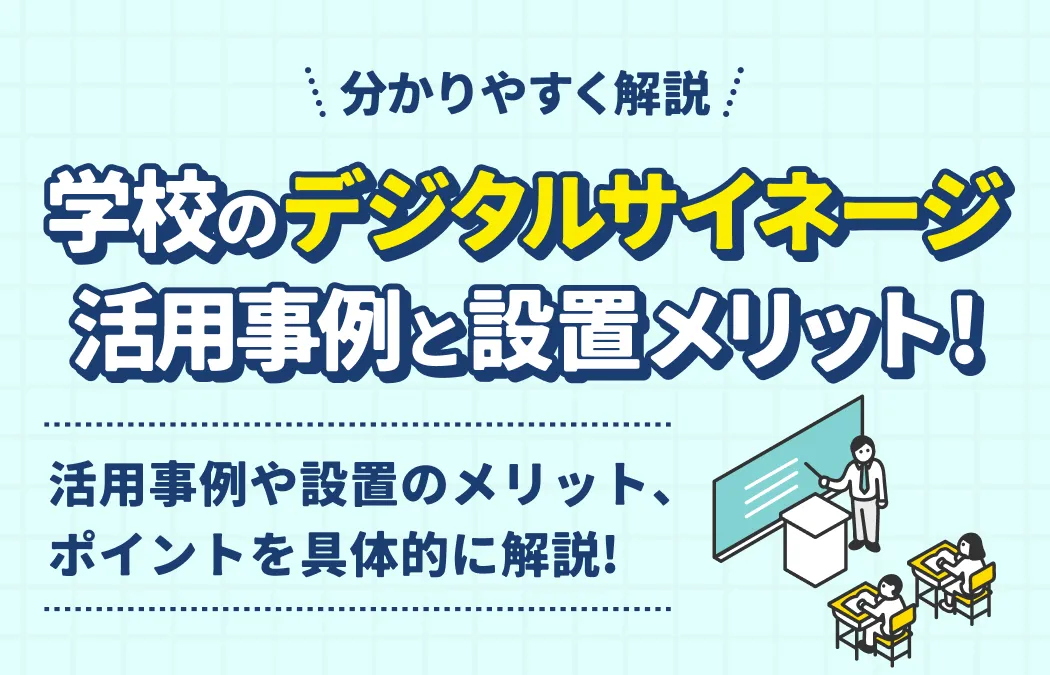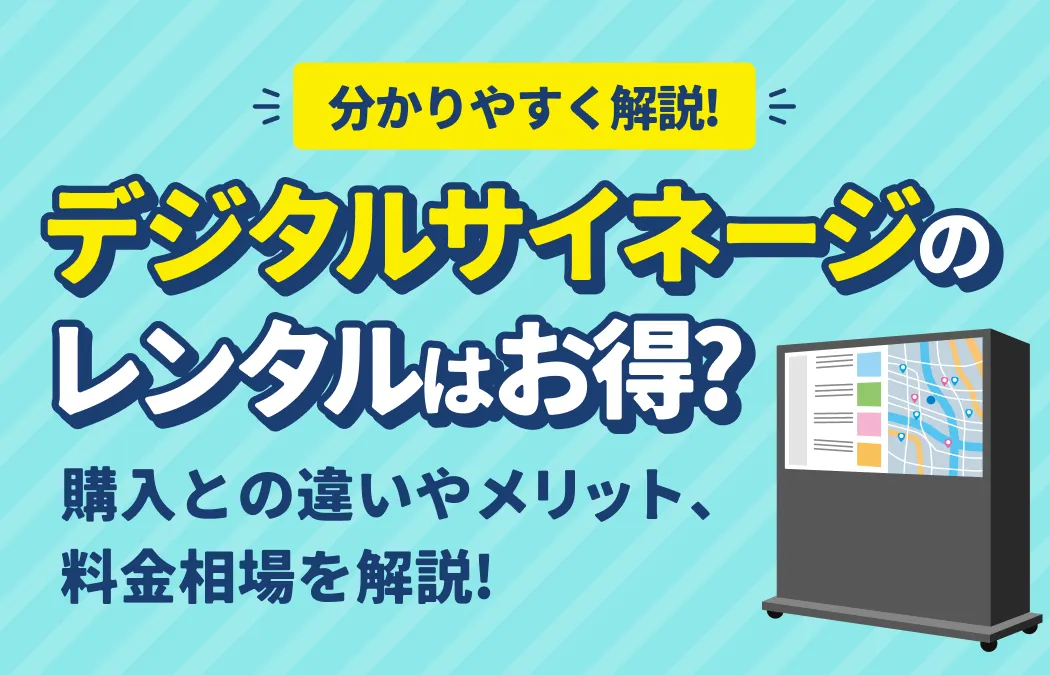「クラウド型とスタンドアロン型の違いは?」
「機種やソフトごとの費用を比較したい」
デジタルサイネージは、動画や画像を使って情報を発信する“デジタル看板”です。
しかし、製品や配信ソフトの種類が多く、自社の目的や設置環境に合わない選び方をすると、費用対効果が下がってしまうこともあります。
本記事では、主要なデジタルサイネージの特徴や価格を比較表で整理し、導入目的・運用規模に応じた最適な選定ポイントをわかりやすく解説します。
※本記事はアフィリエイト広告を含みます。
目次
▼この記事で紹介している商品
導入前に押さえるデジタルサイネージの基礎知識
デジタルサイネージとは「デジタル看板」のこと
デジタルサイネージは、 液晶ディスプレイやLEDパネルなどの電子表示装置を使い、動画や画像を通じて情報を発信するシステム です。
構成要素は「表示装置」「STB(配信端末/小型再生機)」「CMS(配信管理ソフト)」「通信ネットワーク」の4つで、これらを組み合わせることで遠隔操作やリアルタイム更新が可能になります。
近年は人感センサーやビーコン(小型発信機)を連携し、通行量や天候に応じて自動でコンテンツを切り替える高機能型も増えています。
デジタルサイネージのメリット
- 印刷物や張り替え作業の手間を減らし、長期的な費用を抑えられる
- 動的な映像や画像で来店意欲や購買意欲を高められる
- 視覚的に印象的な情報発信で企業イメージを向上

デジタルサイネージのコンテンツ配信方式の違い
デジタルサイネージは、 コンテンツの配信方式により「スタンドアロン型」と「ネットワーク型」に分けられます 。
ネットワーク型はさらに、インターネット経由で配信する「クラウド型」と、自社内サーバーで管理する「オンプレミス型」に分類されます。
多店舗を運営する企業では、クラウド型CMS(配信管理ソフト)で本部からリアルタイムに遠隔管理することが、情報鮮度と業務効率を高めるポイントです。通信不要で確実に稼働させたい場合はスタンドアロン型が適しています。
また、タッチ操作やAI機能を持つ「インタラクティブ型」は、顧客データの収集・分析を通じて販促戦略に活かせます。
| 種類 | スタンドアロン型 | ネットワーク型 (クラウド型) |
ネットワーク型 (オンプレミス型) |
インタラクティブ型 |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | USBやSDカードでコンテンツを直接表示。ネットワーク不要でオフライン運用可能。 | インターネット経由でクラウドサーバーから遠隔配信。 | 自社内サーバーを使い、社内ネットワークで配信。 | タッチパネルやセンサーで双方向操作可能。 |
| 選び方 | 初期費用を抑えたい小規模店舗や、通信リスクを避けたい場所に最適。 | 多店舗一括管理や、時間帯・天候に応じた自動配信など柔軟な運用が必要な場合に推奨。 | 専用サーバー管理体制が整い、内部セキュリティ要件が厳しい場合に適する。 | 視聴者の行動や属性データを収集・分析し、セルフオーダーや高度な販促に活用したい場合に有効。 |
LEDビジョンと液晶ディスプレイの違い
デジタルサイネージの導入では、設置環境に応じて「表示方式」を選ぶことが重要です。
屋外か屋内か、視聴距離が長いか短いかによって、最適なディスプレイは大きく異なります。
屋外では高輝度で耐候性に優れたLEDビジョン、屋内では高精細で細かな情報表示に適した液晶ディスプレイが使われるのが一般的 です。
それぞれ発光方式や輝度(明るさ)、解像度、視認距離(離れて見える最適な距離)などの特性が異なるため、設置目的と環境条件を明確にして選定することが、導入後の満足度を大きく左右します。
| LEDビジョン | 液晶ディスプレイ | |
|---|---|---|
| 発光方式 | LED素子による自発光 | バックライト透過型 |
| 輝度 | 2,000〜8,000cd/m²(屋外向け) | 400〜1,200cd/m²(屋内向け) |
| 視認距離 | 5〜50m(遠距離向き) | 1〜3m(近距離向き) |
| 解像度 | ピッチサイズ※で変動 ※LEDの粒の間隔 |
FHD〜4K対応が主流 |
| 設置環境 | 屋外・スタジアム・大型広告 | 屋内・店舗・公共施設 |
| 耐候性 | 高い(防塵・防水仕様) | 低い(屋外設置は原則不可) ※専用筐体や屋外用モデルを除く |
デジタルサイネージ導入に必要な要素と費用
デジタルサイネージ導入に必要な主要要素一覧
デジタルサイネージは、 表示装置(ディスプレイ)・STB(配信端末)・CMS(配信管理ソフト)・通信ネットワークの4要素で構成 されます。
中でも配信端末はコンテンツ再生を制御する「頭脳」にあたる部分で、再生スケジュールや画面分割、電源の自動制御などを担います。
クラウド型の場合、配信管理ソフトを通じて複数拠点への一括更新や配信状況のモニタリングも可能です。
導入後は運用費・通信費・サポート契約料が継続的に発生するため、初期費用だけでなくトータルコストで比較することが重要です。
| 表示装置(ディスプレイ) | STB(配信端末) | CMS(配信管理ソフト) | 通信ネットワーク | |
|---|---|---|---|---|
| 役割 | コンテンツを表示するディスプレイ。設置環境に応じて輝度・視認距離・耐久性が異なる。屋外では防塵(IP65以上)・防水が必須。 | 配信管理ソフトから配信データを受信し、再生を制御する小型端末。システム全体の中枢を担う。 | コンテンツ制作・配信・稼働監視を行う管理システム。多拠点展開に必須。 | コンテンツを配信管理ソフトから端末へ転送する通信基盤。安定性とセキュリティが重要。 |
| 主な形式 | 屋内型液晶(LCD) / 屋外型高輝度液晶 / LEDビジョン(自発光) | 外付け型配信端末 / 内蔵プレーヤー型ディスプレイOS:Android / Windows / Linux | クラウド型(インターネットで遠隔更新) / オンプレミス型(自社内サーバー運用) | スタンドアロン型(USB) / 社内LAN(社内用ネットワーク)/ VPN(専用の安全な回線)/ LTE(携帯回線)/ Wi-Fi(無線LAN) |
| 相場 | 屋内型(43インチ):4〜12万円 屋外型(43インチ・高輝度):50〜100万円超 |
配信端末単体:5,000円〜2万円 高機能型(4K対応・遠隔制御):2〜5万円 |
クラウド型:月額1,000〜1万円/台 オンプレミス型:50万〜100万円(初期費) |
クラウド型:通信費 月3,000〜1万円 スタンドアロン型:通信費不要 |
| 選び方 | 設置環境と視聴距離で決定。屋外・日中利用なら高輝度/LED、屋内は高解像度LCDを選定。 | 設置方法と拡張性で選ぶ。既存モニター活用なら外付け型、スマート設置なら内蔵型。 | 運用体制とセキュリティ方針で選ぶ。拠点数が多ければクラウド、閉域環境ならオンプレミス型。 | 更新頻度と管理体制で選ぶ。頻繁更新ならクラウド、単独運用ならスタンドアロン型。 |
デジタルサイネージの初期費用と相場
デジタルサイネージの 初期費用は、主に表示装置(ディスプレイ)費用と設置工事費で構成 されます。
屋内用43インチ液晶なら4〜12万円、屋外用高輝度・防水仕様では50〜100万円が目安です。
さらに、外壁設置・天井吊り・電源工事などが必要な場合は、数百万円規模になることもあります。
| 屋内表示装置(43インチ) | 屋外表示装置(43インチ) | 設置工事(簡易) | 設置工事(大規模) | |
|---|---|---|---|---|
| 相場 | 4〜12万円 | 50〜100万円超 | 〜10万円 | 100〜1,000万円 |
| 備考 | 高解像度で近距離視認に最適。家電用モニターも転用可能だが、長時間稼働では焼き付き・輝度低下のリスクがあるため業務用を推奨。 | 直射日光下での視認性を確保するため、高輝度(2,000cd/m²以上)とIP65以上の防塵・防水性能が必須。耐熱・防錆構造も考慮が必要。 | 移動が容易で、店舗前やイベントなど短期運用に最適。電源確保と転倒防止策を整えれば導入が容易。 | 高所・外壁・天井吊りなど構造補強を伴う施工。景観重視の埋め込み型や大型設置では設計・安全管理費が高額になりやすい。 |
デジタルサイネージの配信方式別の長期運用コスト
デジタルサイネージの 運用費は、配信方式によって費用が発生するタイミングと人件負担の大きさが異なります 。
スタンドアロン型は機器代のみで運用できるため初期費用が安い反面、USBなどで現地更新が必要となり、多拠点展開では人件費が累積します。
クラウド型は遠隔で一括更新できる利便性が高い一方、1台あたり月1,000〜1万円程度の利用料が継続的に発生する点に注意が必要です。
オンプレミス型は初期費用が高額(50〜100万円以上)ですが、長期運用では最も安定したコスト構造を実現できます。
| スタンドアロン型 | オンプレミス型 | クラウド型 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 安価(約10〜20万円) | 高額(約50〜100万円以上) | 中程度(約20〜50万円) |
| 月額費用 | 不要(電気代のみ) | 不要(保守契約のみ) | 発生(1台あたり1,000〜1万円) |
| 更新方法 | USBなどで手動更新 | 社内用ネットワークで遠隔更新 | インターネット経由で遠隔更新 |
| 人的コスト | 高い(現地訪問が必要) | 低い(社内で一括管理) | 低い(自動配信可能) |
| 長期運用コスト | 更新頻度が多いと割高 | 長期運用で最も効率的 | 長期運用で費用が累積 |
| 適した環境 | 小規模・単店舗向け | セキュリティ重視の企業 | 多拠点・チェーン展開向け |
短期レンタルと長期購入・リースの選び方
デジタルサイネージの 導入方法は、大きく短期レンタルと長期購入・リースの2種類に分けられます 。
短期レンタルは初期費用を抑えられるため、展示会・イベント・期間限定キャンペーンなどの短期利用や、導入効果を確認するPoC(試験導入)に適しています。
一方、5〜10年単位の運用を想定する場合は、購入またはリース契約の方が総コストを抑えやすく、保守・保証体制の確保にも有利です。
近年は、1年レンタル後に機器を無償譲渡するプランも登場しており、初期投資リスクを抑えながら所有権を得られる柔軟な選択肢として注目されています。

デジタルサイネージ導入で使える補助金
デジタルサイネージの導入費用は、国や自治体の補助金制度を活用することで一部を軽減できる場合があります。
代表的なのは小規模事業者持続化補助金で、販路開拓を目的としたサイネージ機器やコンテンツ制作費が対象 です。
また、IT導入補助金では、配信管理ソフトやクラウド型配信システムなど、ソフトウェア関連費用の支援が受けられます。
補助金は募集時期や採択率、対象経費の範囲が毎年変更されるため、申請前に商工会議所や自治体の最新公募情報を確認しておくことが重要です。
IT導入補助金2025:最終の7次締切分は、2025年12月2日(火)17:00締切!

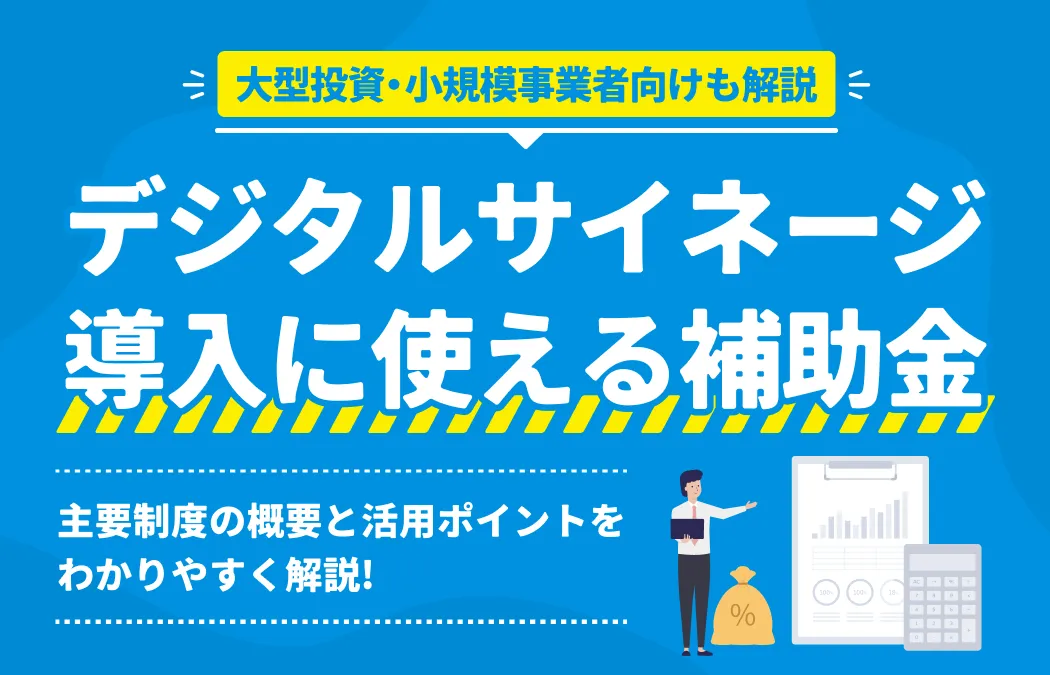
デジタルサイネージ導入で失敗しない選び方
多拠点管理や頻繁更新にはクラウド型が必須
複数拠点でサイネージを運用する場合は、クラウド型配信管理ソフトによる一元管理が不可欠です。
スタンドアロン型では、店舗ごとにUSB更新や現地作業が発生し、人的コストが膨らみます 。
クラウド型であれば、インターネット経由で全拠点のコンテンツを本部から即時更新でき、タイムセールや天候連動キャンペーンなどリアルタイム施策にも柔軟に対応できます。
さらに、サーバー保守やセキュリティ対策も不要で、月額制で運用できるため、スモールスタートから全国展開まで段階的に拡張しやすい点も利点です。
コンテンツ訴求力を高める機能の確認
デジタルサイネージの効果を最大化するには、配信管理ソフトの機能性が重要です。
天候や時間帯に合わせて自動的に表示内容を切り替える「スケジュール配信」や、POS・CRMと連携して顧客層に応じたパーソナライズ表示を行える機能 があると、販促精度が大きく向上します。
例えば、昼時のみランチメニューを自動配信する設定により、人的作業を減らしながら販売機会を逃さず訴求が可能です。
さらに、タッチパネル操作や人感センサーなどの双方向機能を備えたシステムであれば、閲覧データの収集と分析が行え、広告効果の検証や次回施策への改善につなげられます。
- POS(Point of Sale)…店舗での販売時に、商品のバーコード読み取りや決済、在庫管理などを行うシステム
- CRM(Customer Relationship Management)…顧客情報や購買履歴を一元管理し、マーケティングや営業活動に活かす仕組み

安定運用に必要なOSとサポート体制の確認
デジタルサイネージを長期的に安定運用するには、端末OSの選定とサポート体制の整備が重要です。
Windowsベースの端末は、業務システムや社内ネットワークとの互換性が高く、複数拠点を統合管理する大規模施設での導入に適しています 。
一方、Androidベースは初期費用を抑えられる点が魅力ですが、機種ごとに動作の安定性やアップデート対応に差があるため、メーカー保証のある業務用モデルを選定することが推奨されます。
さらに、導入後の保守・監視体制も安定運用の鍵です。クラウド型システムでは、提供事業者がリモートで死活監視(機器が動いているかの自動見守り)や障害対応を行うケースが多く、現場に専門担当者がいなくても継続的な運用を実現できます。
デジタルサイネージ配信ソフトおすすめ20製品比較
無料で試せるデジタルサイネージ配信ソフト
デジタルサイネージの 導入を初めて検討する企業や、小規模店舗・施設では、無料または低コストで利用できる配信ソフトが最適 です。
スタンドアロン型の中には、ネット環境がなくても即日利用できるタイプや、有料版と同等の基本機能を備えた無料プランもあります。
短期イベントやPoC(試験導入)で操作性や表示品質を確認できるため、長期運用前のテストに有効です。
| 製品名 | SmartSignage | Nomoad | 時間割看板 |
|---|---|---|---|
| 提供元 | 福猫(株) | NOMOSOFT合同会社 | (株)アイ・オー・データ機器 |
| 提供形態 | スタンドアロン型/ソフト単体 | スタンドアロン型/クラウド型対応 | 無料ソフト/オンプレミス型/スタンドアロン型 |
| 特徴 | Windows/Mac対応のシンプルソフト。無料版あり。画像/動画/PDF/Webコンテンツの自動切り替え表示。 | テンプレートを利用した簡単なコンテンツ作成。リアルタイム情報表示システム構築可能なカスタム版あり。フリー版あり。 | Windows PCとディスプレイで環境構築。曜日・時間を指定した自動再生、自動シャットダウン機能。 |
| 参考価格 (税込) |
無料版あり。ライセンスキー:4,500円(税込) | フリー版:無料。通常版:3万1,680円/1ライセンス〜 | ソフト自体は無料(※再生用配信端末や機器費は別途) |
| 推奨される 導入ケース |
配信台数が少なく、手軽にコンテンツを自動切り替え表示したい単独店舗。 | 簡単なテンプレートでコンテンツを作成したい個人事業主や、リアルタイム情報表示が必要な施設。 | コストをかけずに、PCと既存ディスプレイで時間指定の自動再生を実現したい場合。 |
多機能・多拠点運用向けクラウド型ソフト
複数拠点を運営する企業や全国展開を行うチェーン店では、クラウド型サイネージシステムが主流 です。
ネットワーク経由で全拠点のコンテンツを一括更新でき、スケジュール配信や死活監視(機器が動いているかの自動見守り)などの自動管理機能を備えています。
配線工事を不要にするLTE(携帯回線)通信型や、障害時でも再生を継続できる高信頼モデルも登場しており、大規模運用に最適です。
| 製品名 | CloudExa | クラモニ | CYBER Signage | StellarSign | DiSi CLOUD | リコー デジタル サイネージ |
Scala | e-Signage S | DAiS Signage | デジサイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供元 | (株)クラウドポイント | (株)ビーツ | ソフネットジャパン(株) | (株)ステラリンク | アビックス(株) | リコージャパン(株) | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | シャープ(株) | 情報技術開発(株) | サイバーステーション(株) |
| 提供形態 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型/オンプレミス型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | スタンドアロン型/クラウド型/オンプレミス型 |
| 特徴 | 遠隔配信・スケジュール編成、4K対応、スマホからの状態監視。映像配信をメインとしたクラウドシステム。 | 直感的操作。AIカメラ接続による属性検知・映像切替が可能。 | コンテンツ制作から運用までWeb上で100%完結。フルハイビジョン配信に対応。 | タッチパネル操作、多言語配信に強い。オプションでタッチレス仕様にも対応。1画面で複数コンテンツを同時配信。 | ドラッグ&ドロップの直感配信管理ソフト。遠隔操作で複数ディスプレイに表示。配信後は障害が発生しても停止しない。 | 約600種類の業種別テンプレートを提供。ブラウザからの配信・管理。ディスプレイ選定からのトータルサポート。 | 世界100か国以上での豊富な実績。外部データ連携(天気、ニュース)の自動配信。ネットワーク障害時も表示可能。 | 最大1,000台対応のネットワーク版など4プラン。コンテンツ編集、定期配信、フォルダ連携機能。 | 大規模・長期運用向け。LTE(携帯回線)通信対応で配線工事不要。視聴データ分析、天気コンテンツ配信、テロップ・二画面配信。 | 再生装置・配信管理ソフト・コンテンツサービスを一体化。PowerPoint形式のテンプレート400種以上。多様な配信端末に対応。 |
| 参考価格 (税込) |
要問い合わせ | 要問い合わせ | Light:1,300円〜、Basic:2,950円〜、その他プランあり | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 初期費用:5万円〜、月額:1,500円/台〜 ※税表示なし |
要問い合わせ |
| 推奨される 導入ケース |
多数の店舗や拠点を持つ企業での映像コンテンツの集中管理・遠隔配信。 | コストを抑えたい小規模店舗や、視聴者属性に合わせた広告を試したい場合。 | Web完結で場所を選ばずサイネージを管理したい場合。 | インバウンド対応が必要な施設や、タッチ操作・非接触操作を組み込みたい案内板。 | 操作の容易さを重視し、安定した配信(障害時の再生継続)を求める施設。 | コンテンツ制作スキルがない、または短期間で業種に合ったサイネージを始めたい企業。 | 大規模な国際展開、安定性と実績を重視する企業。ニュースや天気などの自動連携を求める場所。 | シャープ製ディスプレイとの連携を重視する企業や、最大1,000台の超大規模ネットワークを構築したい場合。 | ネットワーク配線が難しい屋外や、イベント会場など。視聴データ分析まで行いたい大規模運用。 | PowerPointでコンテンツ制作を行いたいユーザーや、配信端末を含めたワンストップでの導入を求める企業。 |
業界・用途別特化ソフト(店舗・オフィスなど)
業界・用途に特化したデジタルサイネージソフトは、既存システムとの連携性や現場課題の解決力に優れています。
広告配信にとどまらず、社内情報共有・接客支援・業務効率化など、現場の実務に即した運用が可能 です。
特に医療、オフィス、観光、商業施設などでは、汎用配信管理ソフトでは実現しづらい専門機能の有無が導入成否を左右します。
| 製品名 | ファーマシーGo! | オフィスdeサイネージ | セールスパフォーマー | AIさくらさん | InterPlay Elastic Framework | MONOLITHS | ABookSmartLink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供元 | (株)MEDIENCER | (株)ディグロス | (株)セブンティーン | (株)ティファナ・ドットコム | アルプス システム インテグレーション(株) | (株)マイクロアド | (株)エージェンテック |
| 提供形態 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 | クラウド型 |
| 主な特徴 | 薬剤師監修の医療コンテンツ200種以上を搭載。受付番号と情報コンテンツを同一画面に表示し、待合室の混雑緩和・業務効率化を実現。 | 営業実績共有や表彰機能を搭載。受注速報や目標カウントダウンをリアルタイム表示。ChatworkやLINE連携で社内コミュニケーションを可視化。 | 特許取得の「営業グラフ予実管理」機能を搭載。モニター掲示とスマホ連携で、営業進捗や成果をリアルタイム共有。 | AI音声対話+有人対応切替により、接客を自動化。来訪者を感知してAIが声がけし、多言語字幕・地図案内・通訳にも対応。 | 14言語翻訳+アバター遠隔接客を実現。災害発生時には自動で緊急案内モードへ切替。公共・観光施設に最適。 | 店頭や屋外広告向けの収益化支援型サイネージ配信管理ソフト。広告販売・配信を一元管理し、ロケーションオーナーの収益最大化を支援。 | タッチ操作+QR連動で情報を持ち帰れる導線を構築。オプションで360°VRコンテンツ表示に対応し、展示会・ショールーム運用にも最適。 |
| 参考価格(税込) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 月額1万3,750円〜 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 想定業界 用途 |
薬局・医療機関(受付効率化・健康啓発) | オフィス(営業実績共有・社内活性化) | オフィス(営業管理・モチベーション向上) | 接客・案内業務(観光・交通・商業施設) | リモート接客・多言語案内(駅・ホテル・公共施設) | 店頭・屋外ビジョン(広告収益モデル構築) | インタラクティブ型(製品カタログ・体験型展示) |
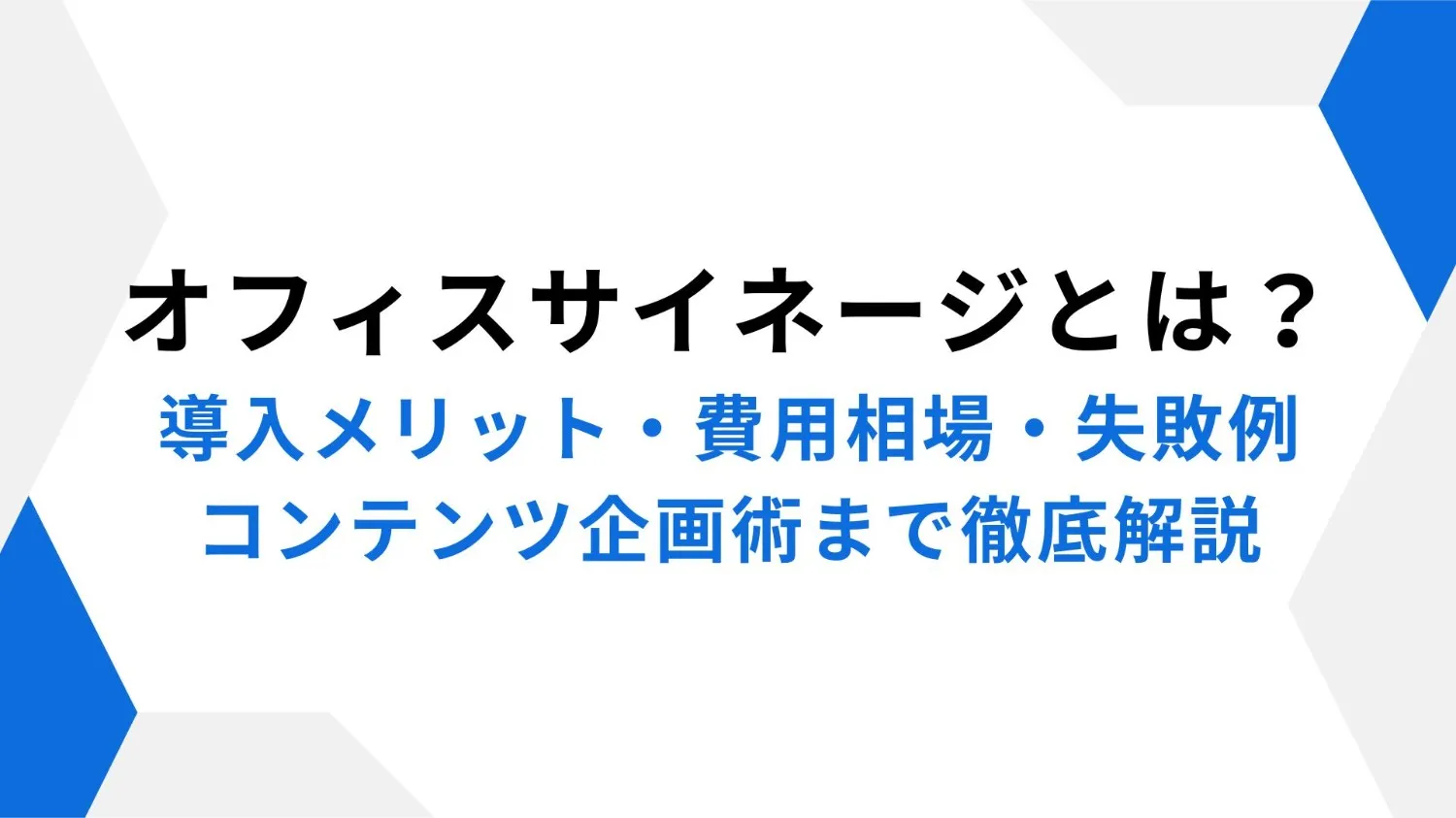
オフィスサイネージとは?導入メリット・費用相場・失敗例・コンテンツ企画術まで徹底解説
オフィスにおけるデジタルサイネージの導入メリットや失敗例、活用事例、費用相場に加え、おすすめ比較12選まで徹底解説
詳しくはこちら
導入・運用を専門チームが徹底サポート!
Wizサイネージの詳細はこちらデジタルサイネージ配信機器おすすめ4製品比較
デジタルサイネージの導入において、表示装置(ディスプレイ)は最も重要な構成要素のひとつです。
ここでは、画質・輝度・連続稼働性能・サイズのバランスに優れた4製品を厳選し比較します。
いずれもUSBメモリによるスタンドアロン再生に対応しており、ネット環境がない場所でも即日運用が可能な点が特徴 です。
| アイ・オー・データ機器 4K液晶ディスプレイEX-U551D |
JAPANNEXT 大型液晶モニター JN-i55U-U |
JAPANNEXT 4K液晶ディスプレイ 43インチJN-Si43UHDR-24 | シャープ インフォメーション ディスプレイ 32型PN-Y326C |
|
|---|---|---|---|---|
| モニターサイズ 解像度 |
55インチ/4K | 55インチ/4K | 43インチ/4K | 32インチ/フルHD |
| 配信方式 | スタンドアロン型 | スタンドアロン型 | スタンドアロン型 | スタンドアロン型 |
| 最大輝度(cd/m²) | 500cd/m² | 320cd/m² | 350cd/m² | 450cd/m² |
| 連続稼働時間 | 18時間 | 24時間 | 24時間連続稼働対応 | 24時間連続稼働対応 |
| 主な特徴 | 明るい室内でも視認性を維持する高輝度設計。コンテンツ内容に応じて色温度を微調整できる。 | IPSパネルで上下左右178°の広視野角を実現。多人数が閲覧するロビーやホール向き。 | 24時間365日稼働可能。高画質IPSパネル採用で商業施設や店舗前のサイネージに最適。 | コンパクト設計で小規模店舗や受付にも設置可能。メディアプレイヤー内蔵でUSB挿入後の自動再生に対応。 |
- 屋内でも直射日光が当たる場所では、500cd/m²以上の高輝度モデルが推奨
- 営業時間が長い施設や24時間営業の店舗では、24時間連続稼働対応モデルを選ぶ
- 通行客が多い通路や店頭では43〜55インチ、大型店舗では70インチ以上も検討価値あり
- ネット環境が整っていない現場では、USBで完結するスタンドアロン型が運用しやすい
デジタルサイネージ導入の流れ
-
STEP.1
目的設定と配信方式の選定
まず、導入目的(販促・情報提供・空間演出など)を明確にします。
設置場所(屋内/屋外)や視認距離(離れて見える最適な距離)に合った画面サイズ・輝度を選び、屋外では防塵・防水性能が必須です。
更新頻度や拠点数に応じて、スタンドアロン型・オンプレミス型・クラウド型から最適な配信方式を選定します。
-
STEP.2
配信管理ソフトの導入
配信や更新を管理する配信管理ソフトを選びます。
対応OS(Windows/Androidなど)、スケジュール配信や遠隔操作などの機能、保守体制を確認しましょう。
既存システムと連携する場合は、Windowsベースの配信管理ソフトが適しています。
-
STEP.3
表示装置と配信端末の設置
配信管理ソフトに対応した表示装置と配信端末を設置します。
・表示装置:屋内では高解像度型、屋外では高輝度・耐候性タイプを選定
・配信端末:設置方法(スタンド・壁掛け・天井吊り)により、工事費や期間が大きく異なる -
STEP.4
コンテンツ制作と運用開始
目的に沿った動画・画像・テロップなどを制作し、配信管理ソフトで配信を設定します。
曜日・時間帯ごとのスケジュール配信で訴求力を維持し、定期的に内容を更新。
配信後は視聴データを分析し、PDCAサイクルで改善を重ねることで効果を最大化します。
デジタルサイネージ導入後のコンテンツ運用
購買意欲を高める動画コンテンツ制作
動画コンテンツは、短時間で商品やサービスの魅力を伝え、購買行動を促す最も効果的な手段です。 制作時は、映像美だけでなく「行動導線」の設計が欠かせません 。
例えば、動画の最後にQRコードやクーポン表示を組み込み、視聴後すぐに購入・予約へ誘導すると、来店率や成約率が向上します。
また、無音環境でも伝わるようにテロップを活用し、夜間ではLEDビジョン特有の高コントラスト映像を用いることで、視認性と訴求力を高められます。
動画コンテンツ制作の具体例
| 目的 | 即時購買誘導 | 店内誘導・滞在促進 | 情報量の効率化 | 夜間・屋外訴求 | 受動的行動促進 |
|---|---|---|---|---|---|
| 具体例 | 商品紹介動画の終盤にQRコードや「今すぐ購入」ボタンを設置し、ECサイトや予約ページへ遷移できる構成にする。 | 新商品・キャンペーンを高コントラストかつ短尺(3〜5秒)動画で反復表示。 | 使用方法や機能比較を映像+テキストテロップで構成し、製品理解を深める。 | LEDビジョンの特性を活かし、黒を締めた高コントラスト映像で制作。 | 医療機関や施設の待合で、定期検診案内などを流し、「受付でお声がけください」などの行動指示を最後に表示。 |
| 効果 適した環境 |
視聴意欲が高まった瞬間にアクションを促し、衝動買い・即時予約を誘発。 | 通行客の目を引き、入店率や滞在時間を向上させる。 | 紙媒体で伝えにくい内容を短時間で可視化し、購買判断を支援。 | 夜間・屋外でも鮮明で遠距離視認性の高い訴求を実現。 | 待機時間中の視聴者の意識を高め、その場での行動転換を促進。 |

PDCAで回す効果測定(視聴データ・タッチログ)
デジタルサイネージの効果を正確に把握するには、 単なる「再生回数」ではなく、誰に・どのように視聴されたかを分析することが重要 です。
AIカメラを用いて視聴者の年齢層・性別・視聴時間を取得したり、タッチパネル型サイネージの操作ログ(閲覧履歴)を解析することで、各コンテンツがどの層に反応されたかを明確に把握できます。
さらに、時間帯別の成果を基に配信スケジュールを最適化するなど、データに基づくPDCA(計画→実行→評価→改善のサイクル)運用を行うことで、広告効果を継続的に向上させることが可能です。
効果測定の活用例
| 目的 | 視聴者属性データ | 時間帯・立地別効果 | タッチログ(操作履歴) | エンゲージメント率 | 稼働状況監視 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析方法 | AIカメラ・センサーを用い、画面前の視聴者の年齢層・性別・滞在時間を自動取得。 | クラウド型配信管理ソフトのスケジュール機能で15分単位の配信変更を検証。 | タッチパネル型端末で、ユーザーの操作回数・滞在時間・選択傾向を記録。 | 視認人数と実際の反応数を比較し、反応率(関与度)を算出。 | 配信管理ソフトの遠隔監視機能で再生状態や電源を常時モニタリング。 |
| データ活用例 | 属性別に訴求力を分析し、ターゲットごとに最適化した映像を配信。 | 時間帯・立地別の売上変動を比較し、最も成果の出る配信時間帯を導出。 | 閲覧動線を分析し、関心の高い情報を上位表示するなどUIを改善。 | 高反応コンテンツを抽出し、配信比率を最適化して訴求効率を向上。 | 異常停止を即時検知・リモート修復し、機会損失を防止。 |

制作リソース不足時の対応方法
自社でコンテンツ制作リソースを確保できない場合は、 自動更新機能や外部データ連携を活用するのが効果的 です。
例えば、ニュース・天気・地域イベントなどを自動取得・表示すれば、更新頻度を維持しながら人手を減らせます。
また、ExcelやCSVのデータを直接配信管理ソフトに取り込むことで、日替わりメニューや価格変更を即時反映できます。
さらに、PowerPoint形式のテンプレートやAI自動生成ツールを利用すれば、デザインスキルがなくても高品質なコンテンツ制作が可能です。
【手間なし・費用軽減】Wizサポート付きサイネージ導入

Wizサイネージは、 導入検討から運用、補助金申請までを専門チームが一貫して支援するサービス です。
補助金活用による初期コスト削減を重視しており、見積書作成や必要書類の作成・申請サポートまで対応します。
さらに、集客や宣伝効果を考慮した静止画・動画コンテンツの制作もチーム内で行えるため、外部業者への依頼や追加費用の手間を省き、スピーディーな設置と運用が可能です。
- 提案から導入・運用まで一括サポート付き
- 集客・宣伝用コンテンツ制作まで幅広く柔軟に対応
- 補助金活用で導入コストを最小限に
- さまざまなシーンに合うサイネージのラインナップ

まとめ
デジタルサイネージは、映像や情報を動的に発信できる「次世代のデジタル看板」です。
導入には表示装置や配信管理ソフトなど複数の要素が関わるため、最初は難しく感じる方も少なくありません。
しかし、目的と設置環境を整理すれば、自社に最適な構成や運用方法を見つけられます。
まずは無料で試せる配信ソフトや補助金サポートを活用し、実際の運用を体感してから導入を検討することが、失敗しない第一歩です。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!