「水漏れが原因かもしれないと不安になっている」
「どこから節水すれば効果が出るかわからない」
飲食店では、皿洗いや厨房清掃、お手洗いなどで水の使用量が多いため、請求書を見て「先月より急に高い」と驚くことも少なくありません。
水漏れが原因と思われがちですが、実際には調理や洗浄の方法、設備の状態によって水道代が高くなるケースもあります。
本記事では、飲食店の水道代の仕組みや高額になる原因、さらに今すぐ実践できる節水対策をわかりやすく解説します。無駄な水道代を抑えて利益改善につなげたい飲食店オーナーは必見です。
目次
▼この記事で紹介している商品
飲食店の水道代と光熱費の目安
全国・地域別の水道代平均
飲食店の水道代は地域によって異なるため、全国一律の平均値で把握することは困難 です。しかし、各地域の施策を確認することは、経費削減のヒントになります。
例えば、東京都23区では令和7年夏季、小口径(13〜25mm)の基本料金が4か月間無償化される臨時措置(※1)が実施されています(使用水量に応じた従量料金や下水道料金は対象外です)。
さらに、パン製造小売業や日本そば店、中華そば店など特定の生活関連業種を営む飲食店は、地域により下水道料金の減免措置(※2)を受けられる場合があります。
店舗規模別の水道代目安
飲食店の水道代は、店舗の規模や使用するメータ口径によって目安が異なります 。
例えば、東京都23区の場合、13mm口径で月額860円、20mm口径で1,170円、25mm口径で1,460円が基本料金です。小規模店舗は13〜20mm口径が一般的です。
経営指標として坪月商と水道光熱費の比率を用いることも可能で、例えば坪月商20万円の店舗で水道光熱費を売上の5%に抑える場合、月額約1万円が目安となります。
水道代に含まれる下水道料金の割合
水道料金には下水道料金が含まれ、原則として使用水量と同量で算出されるため、厨房で多くの水を使用する飲食店では下水道料金も高額になりやすい です。
東京都23区の下水道料金体系では、汚水の種類に応じて料率が設定されており、特定の生活関連業種(例:パン製造小売業、日本そば店)では減免措置が適用される場合があります。
月50〜200m³の汚水排出に対して1m³あたり5円(110%乗じた額)が減免されることもあり、基本料金が無償化されても下水道料金は影響を受けないので、コスト管理の重要ポイントとなります。
飲食店の光熱費の目安と利益の確保
飲食店の光熱費は、売上に対して一般的に5%~8%が目安 とされますが、ラーメン店では7%~10%、バーでは3%~5%と業態により変動します。
この光熱費の中でも、電気代が70%~80%と最も大きな割合を占め、特に業務用冷蔵庫やエアコンといった電気を大量に消費する設備、および低圧電力プランの契約がその主な要因です。
飲食店の利益を確保するには光熱費の削減が重要
飲食店の利益を確保するためには、光熱費の削減が不可欠です。主な削減策としては以下があります。
| 空調の効率化 | 200V業務用機器の 契約電力最適化 |
電力・ガス料金プランの見直し | 定期的な使用状況のチェック |
|---|---|---|---|
| プロペラファンを導入することで、空調の風を均等に循環させ、消費電力を約20%削減できる。 客席や厨房の温度ムラを減らすことで、冷暖房の過剰稼働も防げる。 |
業務用エアコンや冷凍冷蔵設備で200V電源を使用する場合、電子ブレーカーの導入により契約電力の基本料金を抑えられる。 導入時には、JETのPSEマーク取得製品であることや、電力会社への正式申請が行われているかを必ず確認する必要あり。 |
2016年の電力自由化以降、各電力会社やガス会社の料金プランは多様化している。 営業時間や営業形態に合わせて最適なプランを選択することで、光熱費を効率的に削減できる。 |
設備ごとの消費電力や稼働時間を定期的に確認し、ピーク時間の分散や不要稼働の削減を行うことも効果的。 |
光熱費削減に役立つサービス



飲食店の水道代の仕組み
水道代の基本料金・従量料金と請求の流れ
飲食店の水道代は 「基本料金」「従量料金」「下水道使用料」の合計で請求 されます。
| 基本料金 | 従量料金 | 下水道使用料 |
|---|---|---|
| 水道メータの口径(呼び径)によって定額で決まる料金 例:東京都23区(13mm:月額860円/20mm:月額1,170円/25mm:月額1,460円) メータの大きさが大きいほど基本料金も高くなるため、厨房での設備容量に応じて口径を選ぶことがコスト管理に直結する |
使用した水量に応じて課金され、使用量が増えるほど単価が段階的に上がる「階段式料金体系」 例:最初の20m³は1m³あたり○円、20〜50m³は○円、と段階的に上昇 使用量の多い厨房では、少しの使用量の増減でも請求額に大きく影響する |
厨房やトイレで排出された汚水を浄化・処理するための費用として算出される 例:食材の洗浄、食器洗浄機の使用(油分や食品残渣も処理対象)、トイレでの使用水など 使用水量が増えると従量制で下水道料金も高くなる。節水型食洗器や調理工程の水管理でコスト削減が可能 |
水道代はなぜ地域で差があるのか
飲食店の水道代は地域ごとに大きく異なります。 差が生まれる主な要因は、水源の距離や水質処理コスト、貯水・配水設備の規模、そして人口密度 です。
例えば、清浄な水源が近い都市部では処理費用が抑えられ、既存の配水網を利用できるため料金は低めです。
一方、人口密度が低くインフラ整備費が高い地方では、1m³あたりの水道代が高額になる傾向があります。
開業や移転時には、地域ごとの水道代を事前に確認してコスト計算に組み込むことが重要です。
飲食店の水道代が高くなる原因
- 水漏れ(厨房配管・グリストラップ)
- 水の使いすぎ(仕込み・洗浄・食洗器)
- 水道料金の値上げによる高額請求
水漏れ(厨房配管・グリストラップ)
飲食店で水道代が急に高くなった場合、まず疑うべきは水漏れです。目に見えなくても地中配管やグリストラップ(※1)の下で漏れている ケースがあります。
確認方法として、水道をすべて止めた状態でメーターの「パイロット(※2)」部分の動きをチェックします。
動き続けていれば水漏れの可能性が高いため、専門業者に点検・修理を依頼してください。早期対応が高額請求を防ぐポイントです。
- ※1 グリストラップ…厨房の排水に含まれる油脂分(グリース)や食品残渣(カス)を水道管に流さないための装置
- ※2 パイロット…水道メーターに付いている小さな目盛りや回転する表示部分のこと。水を使っていないときは動かないのが正常
水の使いすぎ(仕込み・洗浄・食洗器)
水の使用量が多いことも、水道代が高くなる大きな要因です。調理でのゆで汁、食洗器の連続運転、洗い物の出しっぱなしなどが積み重なります 。
節水の工夫として、調理時の残水利用や節水コマ(※)の設置、洗浄手順の見直しがあります。
日々の使用量を意識することで、水道代のコストを数千円単位で削減可能です。
- ※ 節水コマ…蛇口に取り付ける小さな部品で、水の流量を制限するための装置
水道料金の値上げによる高額請求
水道代自体の値上げも、飲食店の請求額を押し上げる要因です。人口減少による収入減や老朽化した水道施設の更新費用が背景 にあります。
水道管の法定耐用年数は約40年で、この更新時期には自治体によって料金改定が行われることがあります。
明細の基本料金や従量料金が上がっている場合は、地域の値上げを疑いましょう。
水道使用量が少ないのに高額請求になる原因
水の使用量が少ないのに高額請求になる場合、 見落としがちな原因として、検針ミスや請求期間のズレ、下水道料金の加算など が考えられます。
また、厨房設備の故障や小型水漏れ、契約口径の変更による基本料金増も影響します。
請求額が予想より高い場合は、明細を確認し、自治体や水道業者に問い合わせて原因を特定することが重要です。
飲食店で押さえておく節水の基本
つけおき洗い・作業順序の工夫
飲食店の節水の基本は、つけおき洗いと作業順序の工夫です。
洗い桶に40度以上の湯と洗剤を入れ、油汚れのついた食器を一定時間つけておくことで、流水で洗う量を大幅に削減 できます。
さらに作業順序を「汚れの少ない皿から先に洗う」「同種類の食器をまとめて洗う」といった手順にすることで、水や洗剤の使用量を抑えつつ洗浄効率も向上します。
水道代の可視化・計測方法
飲食店の水道代を節約するには、まず使用量を可視化することが重要です。
毎月の請求明細から水量や料金を把握し、グラフ化や表で従業員と共有すると節約意識が高まります 。
さらに水道メーターの確認でリアルタイムの使用量を計測すれば、作業ごとの水量傾向も把握可能です。
洗い場や調理での無駄遣いが明確になり、節水施策の効果も数字で確認できるため、店舗経営に直結する管理手法となります。
水道・下水道料金の恒常的な減免措置
水道料金と下水道料金には減免制度があり、 一定条件を満たす飲食店は申請で支払いを軽減できます 。
業種や排水量に応じた計算が必要なため、店舗開業時や契約更新時に把握しておくと、無駄なコスト削減につながります。
例:東京都23区の減免・減額制度の概要
| 飲食店が活用できる下水道料金減免 | 施設・事業所向けの減額例 | 制度活用のポイント |
|---|---|---|
対象業種は、パン製造小売業、日本そば店、中華そば店、大衆食堂、大衆すし店、民生食堂など
|
|
|
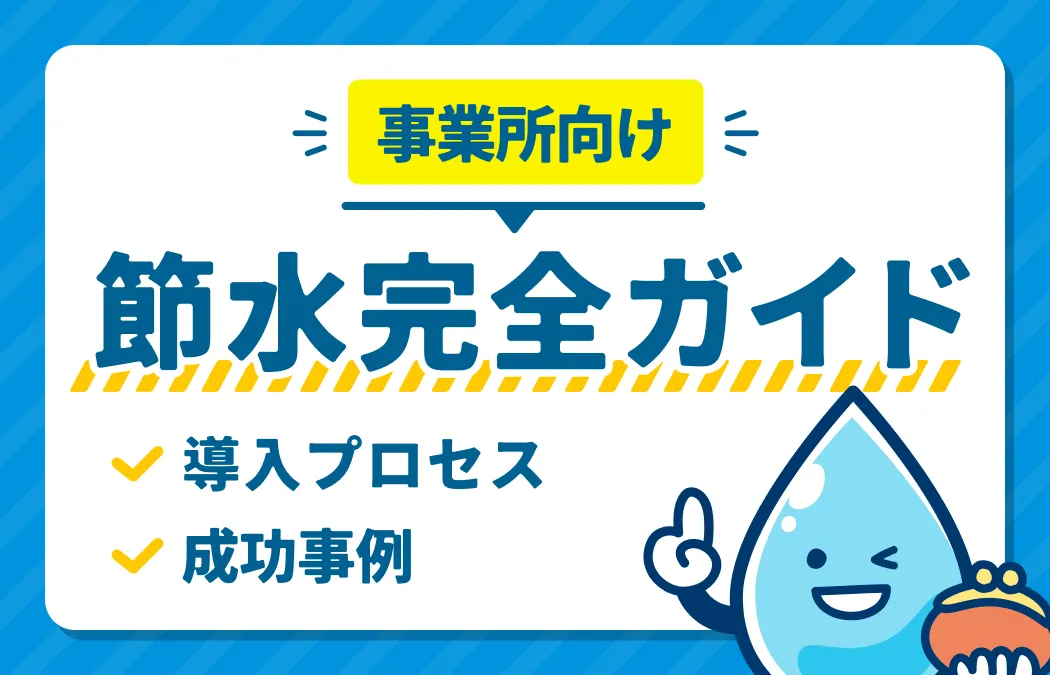
飲食店ですぐできるおすすめ節水対策
- 油汚れを広げず水量を抑える
- 汚れの少ない順で食器を洗い水を節約
- ゆで汁や残り水を再利用して洗浄に活用
- 業務用食洗機で水量と手間を削減
- 節水コマで蛇口からの水量を効率的に減らす
油汚れを広げず水量を抑える
飲食店では家庭よりも油汚れの強い食器が多く、水の使用量も増えやすいため、油汚れを広げない洗い方は重要です。
具体的には、 洗う前にキッチンペーパーで余分な油をふき取り、食器同士が接触しないように並べて洗う ことで、汚れの拡散を防ぎます。
油が広がらないことで、洗浄時の水流を弱めても汚れが落ちやすくなり、結果として使用水量を抑えられます。
汚れの少ない順で食器を洗い水を節約
水の使用量を抑えるには、食器の洗い順にも工夫が必要です。 基本は「汚れの少ないものから先に洗う」 ことです。
例えば、グラスや小皿から始め、油やこびりつきのある皿、鍋類の順に洗うと、洗剤や水の効率が上がります。
順番を決めることで、汚れの広がりを防ぎ、洗浄水を何度も交換する必要がなくなります。
加えて、同じ種類の食器をまとめて洗うことで流水時間を短縮でき、忙しい営業時間でも節水と作業効率の両立が可能です。
ゆで汁や残り水を再利用して洗浄に活用
うどんやパスタのゆで汁には、でんぷんやグルテンが溶け出しており、洗浄時に汚れを浮かせる 働きがあります。
そのため、ゆでた麺の残り湯を鍋やフライパンのつけ置き洗いに活用すると、洗剤使用量を減らしつつ汚れを効率よく落とせます。
温かい方が効果が高いため、フタをして保温するのがポイントです。また、野菜の下茹でや米のとぎ汁なども汚れ落としや下洗いに活用できます。
業務用食洗機で水量と手間を削減
業務用食洗機を導入すると、 手洗いと比較して水量を1/7~1/9に削減できます。洗浄効率が高く、人件費の節約にもつながります 。
ボタン操作だけで一定量の水を自動供給するため、スタッフによる水量調整ミスがなく、忙しい時間帯でも安定した洗浄が可能です。
高温スチームや節水モード付きの機種を選ぶと、より少ない水量で頑固な汚れも落とせ、飲食店の厨房に適しています。
節水コマで蛇口からの水量を効率的に減らす
節水コマは蛇口内部のコマを交換し、水流を制御する節水アイテムです。東京都水道局によると、 開度によっては最大50%の節水効果 があります。
飲食店では、洗浄力の高い高圧タイプの節水コマを選ぶと、少ない水量でも油やこびりつきを効率的に落とせます。
さらに、節水コマには空気を含ませて水流を強く見せるタイプや、シャワー状で洗浄力を高めるタイプなどがあり、厨房の用途に合わせて選択するとより効果的です。
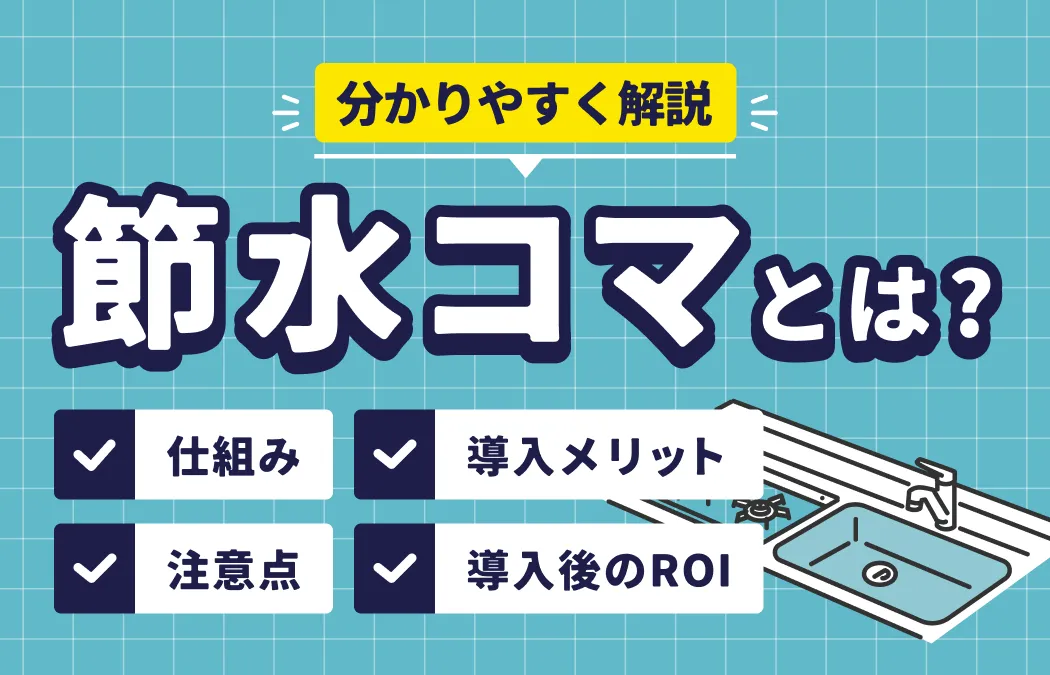
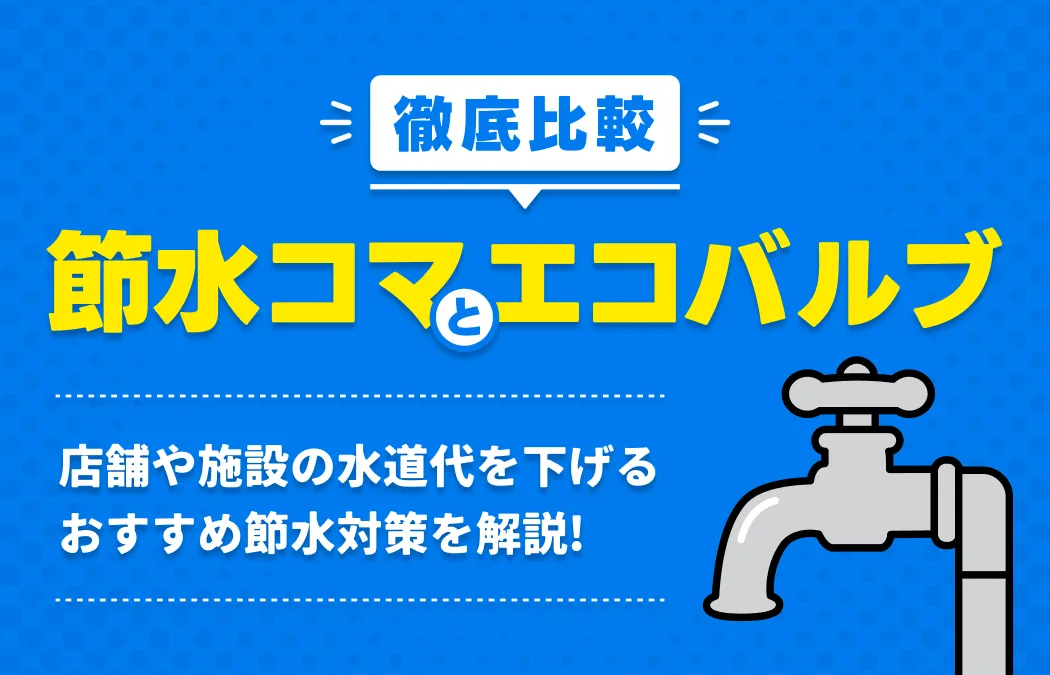
まとめ
飲食店の経営において、水道代と光熱費は無視できないコストです。
特に水道代は、地域によって料金や減免措置が異なるため、店舗の所在地にある水道局への確認が不可欠です。
水漏れや使用量の見直し、節水コマの活用など、日々の細かな対策がコスト削減につながります。
また、光熱費の大部分を占める電気代についても、契約プランの見直しや省エネ設備の導入で大きな削減効果が期待できます。
「どの会社が良いか分からない」「切り替えの手続きが大変そう」とお悩みの方は、ぜひWiz Cloudまでお問い合わせください。
【無料】お問い合わせはこちら
光熱費削減に役立つサービス




この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!















