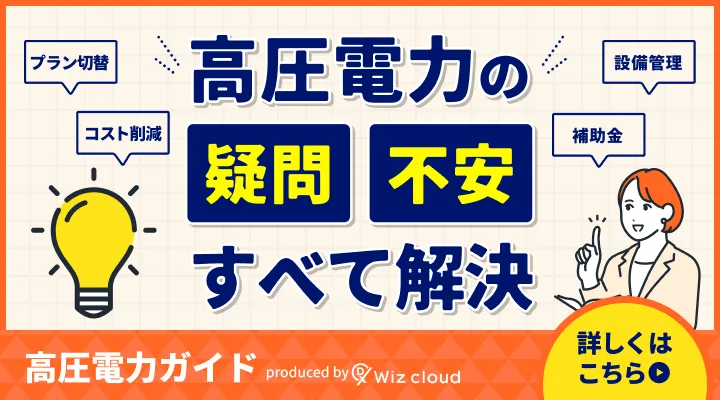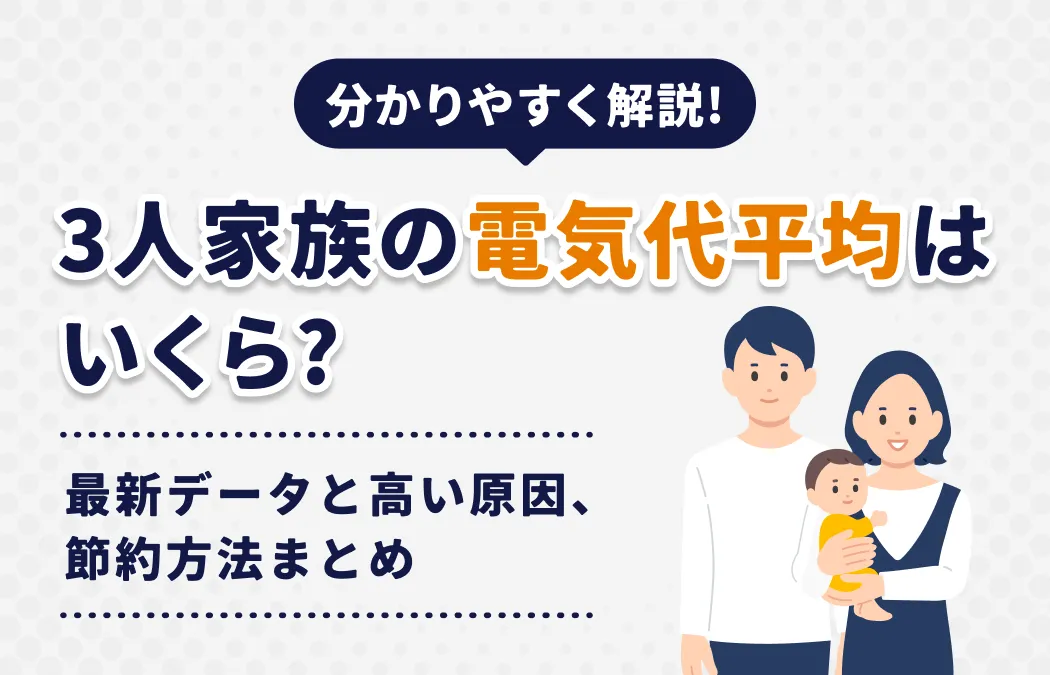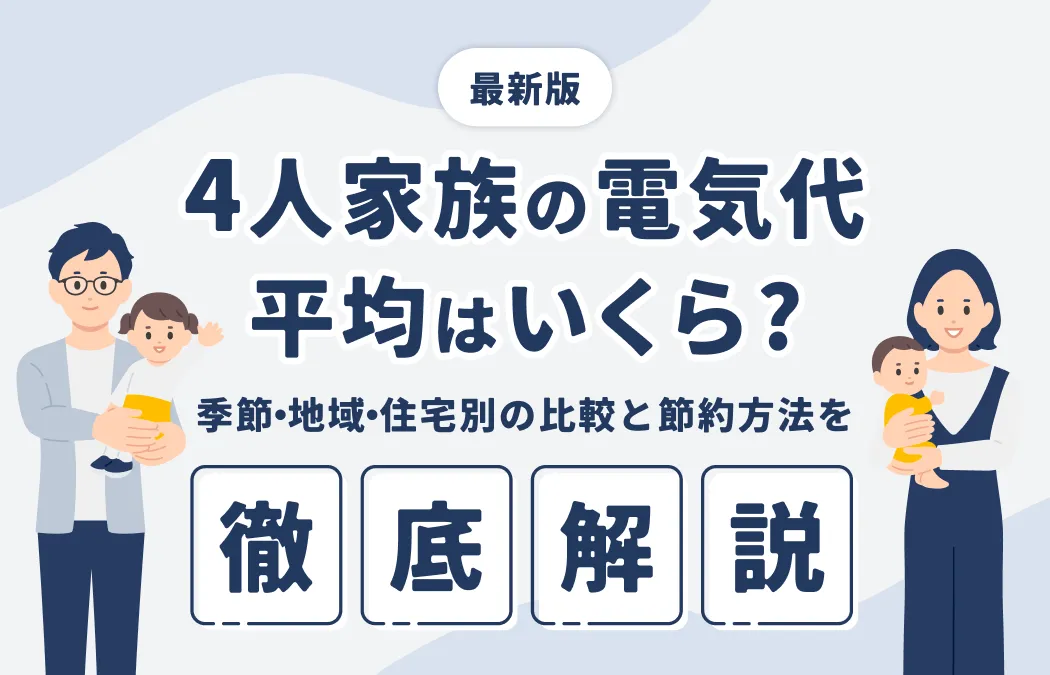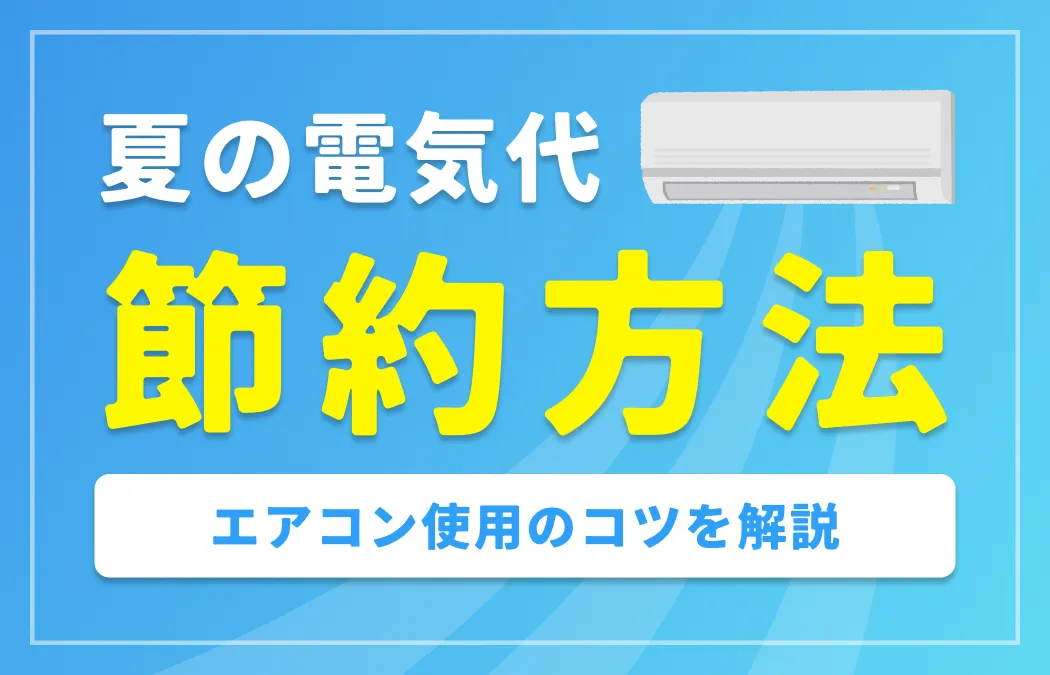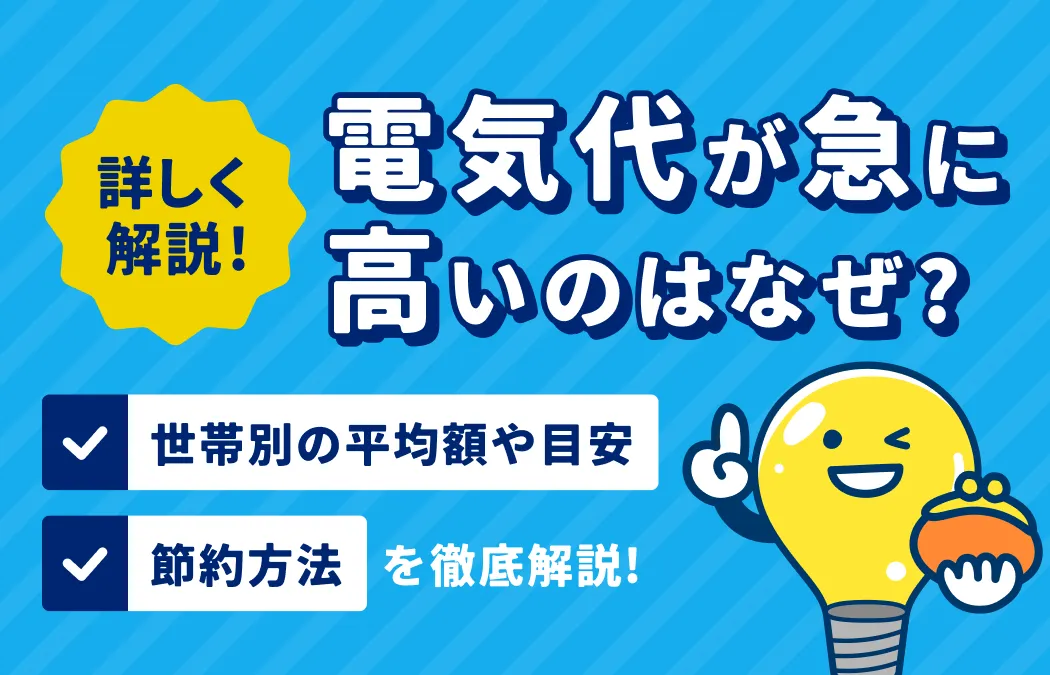「いつから値上げが始まったの?」
「この高騰はいつまで続く?」
2025年の電気料金は、政府補助金の段階的終了と再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の過去最高水準への上昇が重なり、全国で実質的な値上げが進んでいます。
この値上げは一時的ではなく、燃料費高騰や円安などの構造的要因により、2028年まで高止まりすると予測されます。
本記事では、値上げの原因や推移を解説するとともに、新電力への切り替えや太陽光発電・蓄電池導入など、電気代高騰時代を乗り切る具体的な対策を紹介します。
※本記事はアフィリエイト広告を含みます。
目次
▼この記事で紹介している商品
2025年電気代の値上げはいつから?
2025年の電気料金は段階的に上昇しています。まず4月検針分(3月使用分)で値上げが始まり、その後5月検針分(4月使用分)には大手電力10社すべてで値上げが確定しました。
この電気料金上昇は、単なる電力会社の値上げではなく、政府補助の終了と再生可能エネルギー関連費用の増加が主因です。
4月・5月検針分で値上げが確定した主要因
2025年4月~5月の 電気代上昇は、「政府による電気料金補助金の段階的終了」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の上昇」の2点が中心 です。
1. 政府による電気料金補助金の段階的終了
政府は「電気・ガス料金負担軽減支援事業」で家計負担を抑制してきましたが、2025年4月使用分で支援が完全終了しました。
低圧契約の家庭では月数百円から1,000円程度の値引きがなくなり、実質的な値上げとなっています。
| 使用分 | 値引き単価 |
|---|---|
| 2025年1~2月 | 1kWhあたり2.5円 |
| 2025年3月(4月検針) | 1kWhあたり1.3円 |
| 2025年4月(5月検針) | 支援終了 |
| 2025年7月(8月検針) | 1kWhあたり2.0円 |
| 2025年8月(9月検針) | 1kWhあたり2.4円(増額) |
| 2025年9月(10月検針) | 1kWhあたり2.0円 |
| 2025年10月(11月検針) | 支援終了予定 |
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の上昇
2025年度の再エネ賦課金(※1)は過去最高水準の1kWhあたり3.98円に引き上げられ、前年度から0.49円の増加。標準家庭(260kWh/月)では月額約127円の上乗せとなります。
再エネ賦課金の単価推移
- 2024年度:3.49円/kWh
- 2025年度:3.98円/kWh
2025年5月の値上げの主因は、政府補助金の終了と再エネ賦課金増加による基礎料金部分の上昇です。
今後、燃料価格や円安の影響で燃料費調整額(FCA)(※2)が変動すると、電気代全体に追加の影響が及ぶ可能性があります。
- ※1 再エネ賦課金…再生可能エネルギーの普及に必要な費用を、電気を使う全国の利用者が電気料金に上乗せして負担する制度。
- ※2 燃料費調整額(FCA)…火力発電に使う石油・LNG・石炭などの燃料価格や為替レートの変動に応じて、電気料金を毎月自動的に増減させる仕組み。
大手電力10社・モデル別の値上げ幅一覧
標準的な家庭(低圧契約、月260kWh)を想定した電気料金の推移と5月請求分(4月使用分)の前月比値上げ幅は以下の通りです。
| 電力会社 | 4月請求分 | 5月請求分 | 値上げ幅 | 値上げ要因 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道電力 | 9,155円 | 9,549円 | +394円 | 補助金終了 + 再エネ賦課金増額 |
| 東北電力 | 8,485円 | 8,919円 | +434円 | 同上 |
| 東京電力EP | 8,595円 | 9,031円 | +436円 | 同上 |
| 中部電力ミライズ | 8,379円 | 8,818円 | +439円 | 同上 |
| 北陸電力 | 7,406円 | 7,791円 | +385円 | 同上 |
| 関西電力 | 7,326円 | 7,791円 | +465円 | 同上 |
| 中国電力 | 8,103円 | 8,531円 | +428円 | 同上 |
| 四国電力 | 8,197円 | 8,639円 | +442円 | 同上 |
| 九州電力 | 7,223円 | 7,671円 | +448円 | 同上 |
| 沖縄電力 | 9,232円 | 9,650円 | +418円 | 同上 |
関西電力は値上げ幅が最大の465円ですが、元々の単価が低水準だったため補助金終了の反動が大きく出ています。
西日本は原子力比率が高く火力依存が低いため、電気料金が相対的に安く維持されやすい一方、東日本は火力依存が高く、料金水準が比較的高くなっています。
電気代高騰に不安96%・不満95%
2025年5月の電気料金の値上げは、国民生活に大きな影響を及ぼしています。
LIVIKAの調査(回答者100名、5月18日~6月1日)によると、 電気代の高騰に不安を感じる人は96%に上ります 。
| 意識基本 | 割合 | 詳細 |
|---|---|---|
| 今後の電気代高騰への不安 | 96% | 高騰に不安を感じる |
| 値上げに対する不満 | 95% | 「大変不満」60%、 「やや不満」35% |
| 補助金終了による値上げ認知 | 76% | 知っている |
| 値上げをきっかけに節電意識 | 85% | 節電行動を意識 |
標準的な4人世帯(月400kWh)では、年間で約3万3,600円の負担増が見込まれ、節電だけでは対応しきれない方も多いでしょう。
そのため、家庭や企業では料金プランの見直しや太陽光発電・蓄電池の導入など、長期的な光熱費管理への関心が高まっています。
電気代は何で決まる?内訳と仕組み
電気料金は、単に「使用量」だけで決まるわけではありません。
契約種別(個人向け低圧、法人向け高圧・特別高圧)や電力会社ごとの料金構造に応じて、基本料金・電力量料金・燃料費調整額・再エネ賦課金など複数の要素が組み合わさって算出されます。
各項目の変動を理解することで、家庭も企業も効率的な節約やコスト管理の戦略を立てやすくなります。
個人向けの電気代の内訳
一般家庭や小規模事業者が契約する 低圧プラン(従量電灯など)の電気料金は、主に「基本料金」「電力量料金」「燃料費調整額(FCA)」「再エネ賦課金」の4つで構成 されます。
| 内訳 | 基本料金 | 電力量料金 | 燃料費調整額 | 再エネ賦課金 |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 契約アンペア数(10A、20A、30Aなど)や電圧に応じて固定で発生 | 実際に使用した電力量(kWh)に応じて発生 | 発電燃料(原油、LNG、石炭等)の価格変動を反映 | 再生可能エネルギーの普及を支える費用を全国一律で負担 |
| 変動の 仕組み |
契約アンペア数を変更することで削減可能 | 段階制料金で使用量が増えるほど単価上昇 | 国際価格・為替の影響で毎月変動 | 毎年単価改定、2025年度は過去最高の3.98円/kWh |
- 電力量料金は段階制が多く、使用量が増えると単価が上がる
- 燃料費調整額の規制料金プランは上限あり、自由料金プランは上限なしで高騰リスク
- 再エネ賦課金は制度開始以来の最高水準で、電気代上昇の持続要因
法人向けの電気代の内訳
法人契約は、 契約電力に応じて「低圧電力」「高圧」「特別高圧」に分類され、家庭向けとは異なる構造的特徴があります 。
特に大量電力を消費する製造業やデータセンターでは、内訳が経営コストに直結します。
| 契約種別 | 低圧電力 | 高圧 | 特別高圧 |
|---|---|---|---|
| 契約電力の目安 | 50kW未満 | 50kW~2,000kW未満 | 2,000kW以上 |
| 主な利用形態 | 小規模業務用機器、家庭向けとは異なる料金体系 | 中小規模工場、ビル、病院、商業施設。基本料金はデマンド値で決定 | 大規模工場・商業施設・鉄道。燃料費調整額は卸市場単価に連動 |
法人契約特有の変動要因
| 変動要因 | デマンド値に 基づく基本料金 |
燃料費調整額と 卸市場価格の連動 |
容量拠出金 | 託送料金 (送配電コスト) |
政府補助金の適用差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 契約期間中の最大需要電力(デマンド値)で基本料金を算定 | 高圧以上はJEPX市場価格に連動 | 将来の供給力確保のための制度コスト | 送配電ネットワーク使用料 | 法人向けは低圧家庭向けより値引き単価が低く設定される場合あり |
| ポイント | ピーク時の使用量を抑える「ピークカット」がコスト削減の鍵 | 自由料金プランは上限保護なしで、急激な価格変動リスクあり | 電力事業者経由で料金に転嫁される可能性がある | 地域ごとに変動、料金改定の要因となる | 負担増の一因となる |

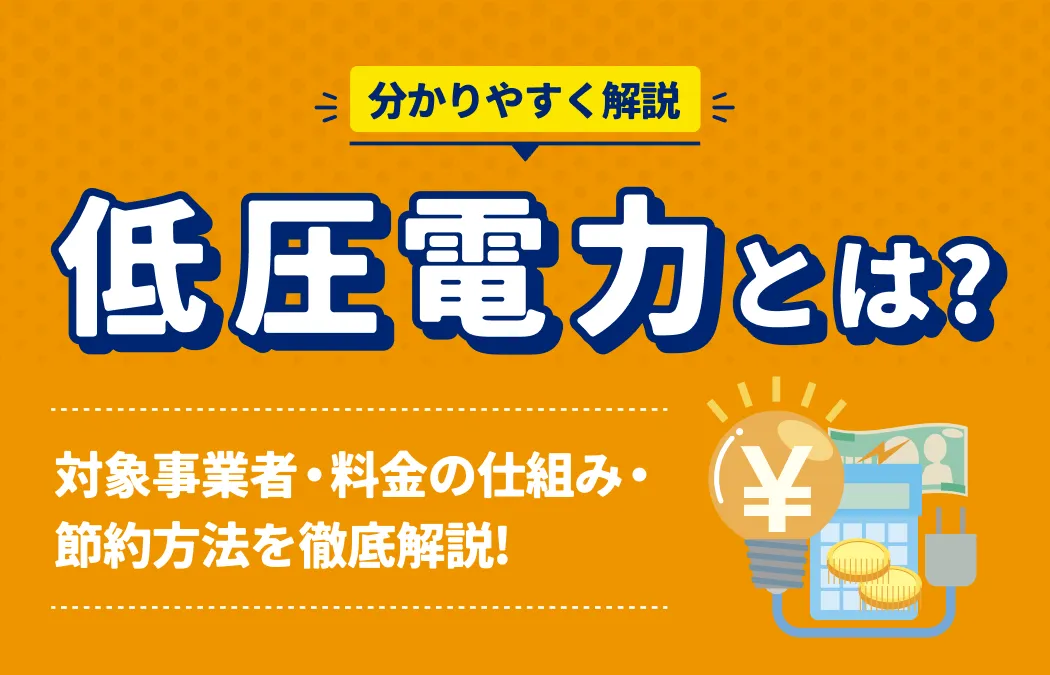

なぜ電気代高騰は止まらない?3つの原因
近年の電気料金高騰は、一時的な季節要因や燃料価格の変動だけでなく、日本のエネルギー構造と政策コストが複雑に絡み合った構造的問題によるものです。
特に2025年は、政府補助金の終了に加え、以下の3つの恒常的コストが電気代高止まりの主因となっています。
- 再エネ賦課金が過去最高の3.98円/kWhに上昇
- 燃料費高騰と円安継続で燃料費調整額が増加
- 託送料金改定・容量市場拠出金でコスト増
再エネ賦課金が過去最高の3.98円/kWhに上昇
電気代上昇の主因の一つが「再生可能エネルギー発電促進賦課金」です。
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は FIT制度やFIP制度に基づき、電力会社が再エネ電力を高額で買い取った費用を、全国の利用者が負担する仕組み です。
2025年度の単価は1kWhあたり3.98円と過去最高で、標準家庭(月260kWh使用)では月約127円の上乗せとなります。
単価算定には「回避可能費用(※)」が関わり、市場価格に応じて毎年変動するため、今後も上昇傾向が続くと予測されます。
※回避可能費用…再エネで発電された電気を使うことで、本来なら火力などで発電した際にかかる燃料費などを“回避”できると見なして算定される費用。
燃料費高騰と円安継続で燃料費調整額が増加
燃料費調整額は、発電に使用するLNG・原油・石炭の価格変動を毎月料金に反映する調整費です。
日本は火力発電依存が70%以上で燃料をほぼ輸入に頼るため、国際価格や円安が電気代に直結します 。
地政学リスク(※)や天然ガス需要増で燃料費が高騰する一方、自由料金プランでは上限がなく、国際情勢の変化で料金が急上昇するリスクがあります。
法人契約は卸市場単価に連動する場合もあり、市場変動の影響を直接受けやすい構造です。
※地政学リスク…国際的な政治・軍事・外交上の対立や不安定要因によって、資源価格や経済活動に悪影響を及ぼすリスク。中東情勢やロシア・ウクライナ情勢が原油や天然ガスの価格高騰につながるケースが代表例。
託送料金改定・容量市場拠出金でコスト増
電力の安定供給を維持するため、託送料金と容量市場拠出金という新たな制度コストが加わっています 。
託送料金は送配電網の維持・管理費で、利用者に転嫁される割合は全体の3~4割程度です。
容量拠出金は将来の供給力(kW)を確保する費用で、小売電気事業者経由で料金に上乗せされます。
2024年以降の改定では、家庭向け低圧プランでも地域によって1kWhあたり数円程度の負担増となり、今後も長期的な料金上昇の要因です。
【予測】2028年までの電気代推移とリスク
2025年以降の電気料金は、政府補助金の終了や再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の過去最高額上昇に加え、国際燃料価格の不安定化、円安、国内発電構成など構造的要因により、2028年まで高止まり傾向が続くと予測されます。
将来の電気料金は予測が難しいため、いくつかのパターンを想定してリスクを見ておくことが大切です。
電気料金「悲観シナリオ」が示す年間コスト増の試算
リスク管理の観点では、燃料価格の高止まりや原子力再稼働の遅れなど、悪条件が重なる最悪ケース(高インフレ)も想定しておくことが大切です。
| シナリオ | 年間電気料金上昇率(予測) | 3年間累計上昇幅 | 1kWh単価(2028年予測) |
|---|---|---|---|
| 悲観シナリオ | 4~5% | 13~16%前後 | 約35円(2025年30円基準) |
| 標準シナリオ | 2~3% | 6~10%前後 | 約32~33円 |
ガス併用世帯とオール電化世帯の負担差
オール電化世帯は給湯や調理も電気を使うため使用量が多く、電気代が上がると負担額も大きくなります 。
一方、ガスも使う世帯は電気使用が少ない分、値上げによる影響は比較的小さくなります。
| 世帯モデル | 2025年 月額電気代 | 2028年 月額電気代 | 3年間での月額増加 | 3年間での年間増加 |
|---|---|---|---|---|
| 4人家族(ガス併用)400kWh/月 | 約1万6,000円 | 約1万8,800円 | +2,800円 | +3万3,600円 |
| 4人家族(オール電化) 550kWh/月 | 約2万4,000円 | 約2万8,800円 | +4,800円 | +5万7,600円 |
| 共働き夫婦(ガス併用) 250kWh/月 | 約8,500円 | 約1万円 | +1,500円 | +1万8,000円 |

編集部
オール電化は電気料金高騰リスクを直接受けますが、都市ガスやLPガスの高騰リスクを避けられるメリットもあります。太陽光発電や蓄電池などの自家消費型対策を集中的に施しやすい点もオール電化の強みです。
地域差の要因:関西・九州の安さと北海道の負担増
電気料金は発電構成や電力需要、送配電コストの違いで地域差があります。
関西・九州は原子力比率が高く安定していますが、 北海道は火力依存度が高く、冬季暖房需要や託送料金改定により負担増のリスクが大きくなります 。
| 電力会社 | 標準月額電気代(約400kWh) | 地域特性 |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 約1万300円 | 火力依存高、暖房需要多い |
| 関西電力 | 約7,400円 | 原子力比率高、コスト安定 |
| 九州電力 | 約7,300円 | 原子力比率高、コスト安定 |
| 沖縄電力 | 約9,300円 | 火力依存度高い |
【短期対策】今すぐできる電気代節約術
大型家電の節電で短期的に効果を出す
家庭で電力消費が多いのはエアコン、冷蔵庫、照明など です。特別な設備投資をせずとも、使用方法の工夫で短期的な節電効果を得られます。
| 冷暖房機器の効率化 | 冷蔵庫の節電 | 高効率家電への切替 |
|---|---|---|
|
|
|
契約アンペア数を見直して固定費を削減する
電気料金は基本料金と電力量料金から成り、基本料金は使用量に関わらず毎月発生する固定費です。
契約アンペア数を自身の使用状況に適した値に調整することで、固定費を恒常的に削減できます 。例えば、30A契約から20Aに変更すると、月額数百円の削減が可能です。
ただし、同時使用する家電の総消費電力を確認しないと、ブレーカー落ちのリスクがあるため注意が必要です。
電力会社の乗り換えで無駄なコストを防ぐ
電力自由化により、家庭や事業の使用状況・ライフスタイルに応じて電気料金プランを選べるようになりました。
乗り換えを行えば、基本料金や従量料金の単価を抑えられ、年間で数万円規模の節約も可能 です。
さらに新電力の中には、固定単価プランや特典付きプランを提供する会社もあり、電気代高騰リスクを抑えつつ追加のメリットも得られます。
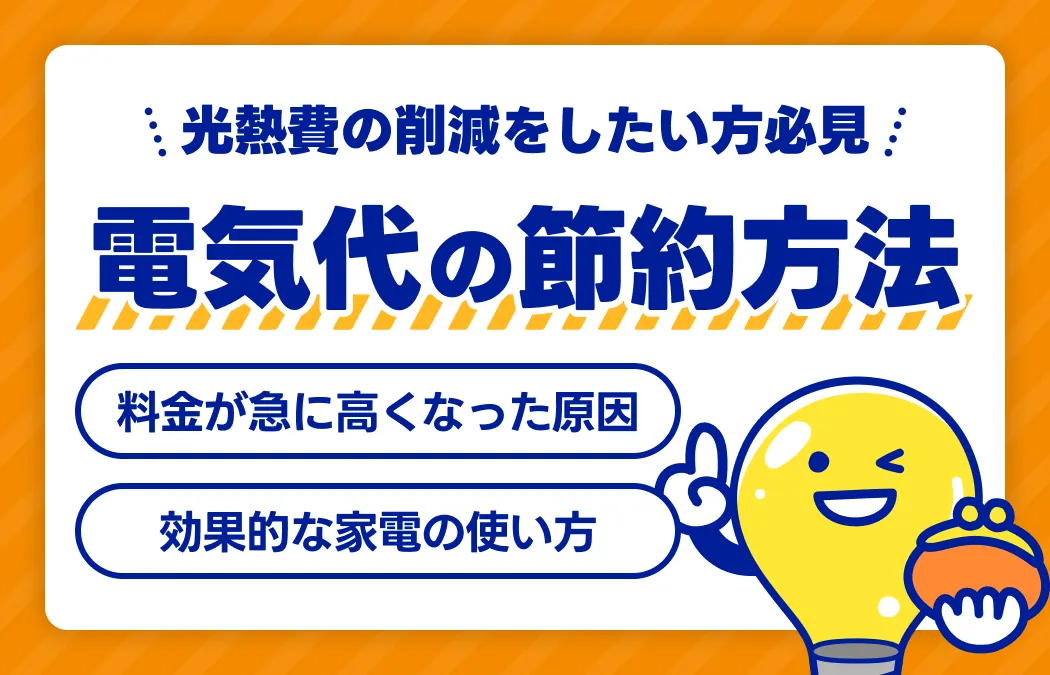
電気代を安くできる新電力おすすめ10選(法人向け)
| 会社名 | ハルとくでんき | Looopでんき | シン・エナジー | 楽天でんき(Business) | USENでんき (U-POWER) |
丸紅新電力 | ENEOSでんき | ソフトバンクでんき forBiz |
東急でんき | エコログDenki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象電圧 | 低圧、高圧 | 低圧、高圧、特別高圧 | 低圧、高圧、特別高圧 | 低圧、高圧、特別高圧 | 低圧、高圧 | 高圧、特別高圧 | 低圧、高圧、特別高圧 | 低圧、高圧 | 低圧、高圧、特別高圧 | 低圧、高圧 |
| 料金体系の 主な特徴 |
低圧供給量No.1実績。電力使用量が多い部分(第三段階)で大幅な値引きがある。 | 主力プランは市場連動型「スマートタイムONE」で、電源料金に加え7円/kWhのサービス料と託送費等が必要。 | 市場連動型が主。燃料費調整額ゼロ (沖縄除く)。電源調達調整費あり。 | 基本料金0円。市場価格調整単価あり(変動リスクあり)。 | 高圧は市場連動型、ハイブリッド型、固定料金型の3種から選択可。 | 個別に最適な単価を算出し提案。長期安定供給力に強み。 | 燃料調達ネットワークを活かした供給力。全国に自社発電所を保有。 | 従来大手電力会社より基本料金が1%以上安い。東北・東京・関西・九州エリアは電力市場連動額を導入。 | 固定型プランと市場連動型プランを選択可能。 | 市場連動型高圧プランで、超過分を3か月後に繰り延べできる機能あり。 |
| 契約期間 解約金 (税込) |
原則3年。途中解約金:1万3,650円 (または割引分全額)。 | 契約期間の縛りなし。解約金:0円。 | 原則1年。契約手数料・解約金:0円。 | 契約期間の縛りなし。契約手数料・解約金:0円。 | 3か月前通知がなければ1年ごと自動継続。契約を1年未満で廃止すると、契約電力分の料金に20%の割増が遡って適用される。 | 原則1年。プランHの場合、契約期間中の解約では、残存期間に応じて月1,026円の支払いが発生する可能性あり。 | 原則1年。解約金:0円(「にねん とく2割」は2年縛りで途中解約時に1,100円の違約金が発生)。 | 原則3年。契約解除料:9,800円。低圧電力(動力)の契約解除料は5,500円。 | 原則1年。解約金:0円。 | 契約期間3年。契約解除料はプランにより異なる(スタンダードプランでは3,850円)。 |
| 主な特典 特徴 |
ガスセット割あり。初期費用・工事原則不要。 | 実質再エネ100%オプション「eneco」あり。ガスセット割(東京エリア、電気単価1円引き)あり。 | 違約金ゼロ・初期費用ゼロで導入可能。高圧切替で28%削減や36%削減の実績あり。昼間利用や繁忙期変動が大きい法人に効果的。 | 楽天ポイントが貯まる・使える(200円につき1P、ガスセットで優遇)。個人事業主/フリーランスも利用可能。 | 再エネ比率を10% / 50% / 100%で選択可能。RE100基準準拠プランあり。 | 特別高圧販売量で新電力中3位のシェア。低圧向けプランは新規申込一時停止中。 | 電気開発・都市ガス販売などエネルギー事業を幅広く展開。契約件数74万件(法人・個人合算)。 | 携帯・光回線とのセット割引。低圧向けに環境オプション分が最長2年間無償となるキャンペーンあり。 | 法人用東急カード決済で1%ポイント還元。CO₂フリー特約を追加可能。 | CO2フリーオプションあり。設備トラブル時の訪問サポートや専門家への電話相談オプションあり。 |


手間なく料金比較!無料一括見積もりサービス

「電力会社の切り替え」は無料の一括見積もりサービス
「電力会社の切り替え」は、 法人や店舗向けに特化した完全無料の電力一括見積もりサービス です。
全国の600社以上の電力会社から厳選した30社のプランを、中立的な立場で徹底比較し、最適な契約プランを提案します。見積もりの取得から契約切り替え完了まで、追加費用は一切不要です。
利用者は現在の契約内容や使用状況に応じて、電気代の削減を目指したプラン選定が可能です。
サービスの詳細はこちら「電力会社の切り替え」サービスを利用するメリット
「電力会社の切り替え」を利用する 最大のメリットは、多忙な法人オーナーでも比較検討や手続きを最小限にできる点 です。
窓口が一元化されるため、複数社とのやり取りに時間を割く必要がありません。プロスタッフが見積もり取得から値下げ交渉、切り替え完了まで無料でサポートしてくれるため安心です。
飲食店やオフィス、工場など業種に合わせた最適プランの提案に加え、LED照明や太陽光発電、蓄電池など、電気代削減に役立つ周辺サービスの案内も受けられます。
過去の切替事例(電気料金の削減例)
| 商業施設 | 宿泊施設 10施設 | 薬局 約260契約 |
|---|---|---|
|
|
|
【脱却戦略】太陽光・蓄電池で電気代から卒業
太陽光発電で自家消費し値上げリスクを回避する
電気料金の高騰は再エネ賦課金の上昇や燃料費調整額(FCA)の影響が大きく、特に2025年度の再エネ賦課金は3.98円/kWhと過去最高です。
自家消費型の太陽光発電により日中の電力を自ら賄うことで、買電量(※1)を削減し賦課金負担を軽減できます 。
例えば、5kWのシステムでは年間約1,800kWhを自家消費可能で、年間約6万円の電気代削減効果が見込まれます。
余剰電力は売電(※2)に回すことも可能ですが、近年は売電単価が低下しているため、自家消費による節約効果の方が大きい傾向にあります。
- ※1 買電量…電力会社から購入する電気の量。使用量が多いほど賦課金や燃料費調整額の負担も増える。
- ※2 売電…家庭や事業所で余った電気を電力会社に販売すること。例えば、昼間の発電が消費を上回った場合に、その余剰分を電力会社へ送電して収入を得られる。
太陽光+蓄電で自家消費率アップ、電気代負担を軽減!


蓄電池で夜間利用と災害時の電力を確保する
太陽光発電は日中しか電気をつくれないため、夜間や停電時の電力を確保するには蓄電池が重要 です。
蓄電池を組み合わせれば、自家消費率(自分で発電した電気を自分で使える割合)が約30%から60%へ改善し、電気代削減効果も大きくなります。
また、夜間の安い電気をためて昼間に使う運用も可能で、電気料金の高い時間帯の支出を抑えられます。
さらに、停電時には非常用電源としても機能するので、自然災害や国際情勢による電力不安への備えとしても効果的です。
補助金活用と一括見積もりで導入コストを抑える
太陽光・蓄電池の導入費用は高額ですが、 国・自治体の補助金制度を活用することで初期費用を大幅に抑えられます 。
さらに、一括見積もりサービスを利用することで、複数の優良業者から価格や施工内容を比較可能です。
一部地域では外壁塗装と組み合わせることで、太陽光発電の導入費用を実質0円にできる独自プランもあります。

編集部
家庭向けには「太陽光・蓄電池補助金」、法人向けには「省エネ補助金・助成金」などがあります。自治体独自の制度も多いため、必ず地域ごとの公募要項を確認しましょう。
まとめ
2025年の電気料金は、政府補助金の終了と再エネ賦課金(3.98円/kWh)の上昇により、多くの家庭で実質値上げとなりました。
大手10社では4月使用分(5月検針分)に値上げが確定し、標準家庭では家計に直撃する月数百円~数千円の負担増となり、日々の節約だけでは追いつかない方も多いでしょう。
このため、料金プランの見直しや契約アンペアの適正化が、短期的な負担軽減策として有効です。
長期的には、太陽光発電や蓄電池で自家消費率を上げることが、再エネ賦課金や買電量を減らす根本的な対策になります。
初期費用を抑えつつ将来の負担を軽減するには、補助金や一括見積もりなども活用してみましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!