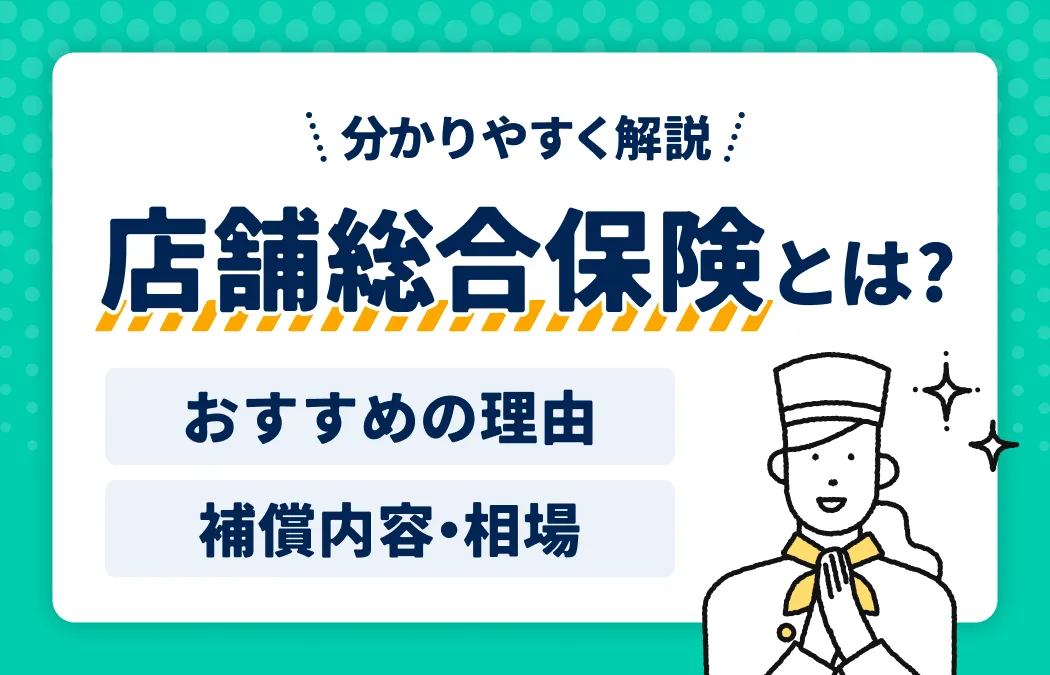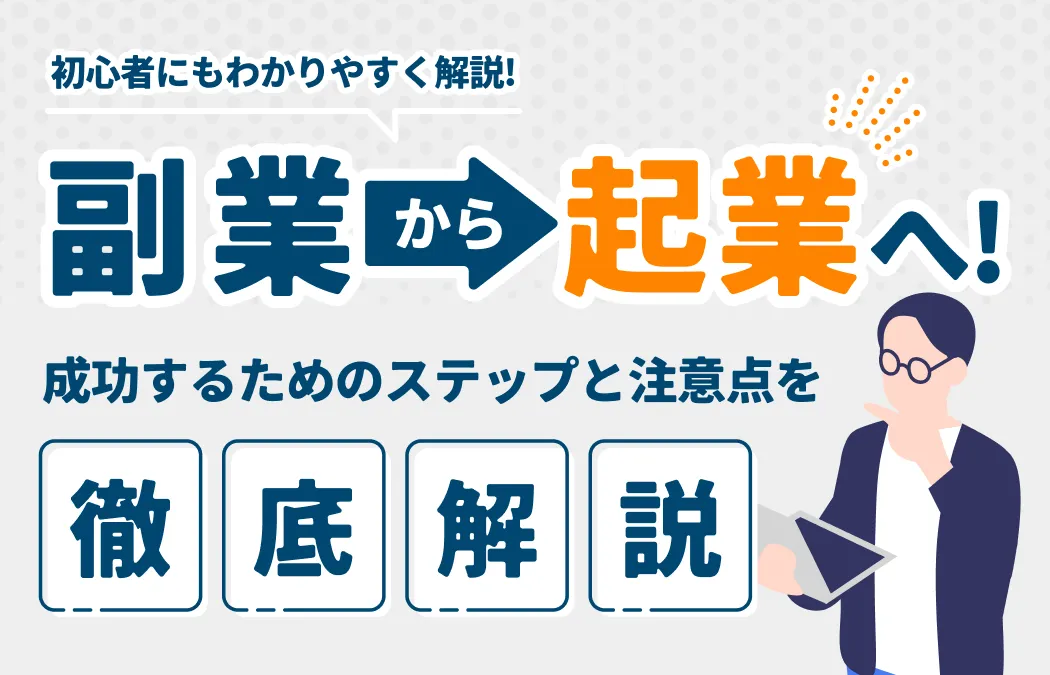開業を本格的に考え始めると、まず気になるのが“資格や手続き”の話。
でも、調べてみると「食品衛生責任者」「防火管理者」「営業許可」など、似たような名前がずらっと並んでいて、何が本当に必要で、いつまでに準備すべきなのか混乱しがちです。
この記事では、飲食店の経営にあたって最低限必要な資格・届出・保険のことを整理しながら、取得方法やスケジュール感まで具体的に解説します。
初めての開業でも、やるべきことがスッキリ見えるようになりますよ。
目次
▼この記事で紹介している商品
飲食店を経営する上で必要な2つの資格
食品衛生責任者
飲食店や食品を販売する店舗では、 「食品衛生責任者」という資格を取得している従業員が1名在籍していることが必要 となります。
店舗の衛生管理を行うことが食品衛生責任者の主な仕事であり、従業員の衛生管理方法を指導したり、管理や徹底させることも役割の一つとなります。そのため、食品衛生についての正しい知識を身につけておかなくてはいけません。
資格取得方法に関しては、各地域の保健所で講習とテストを受ける必要があります 。なお、テスト費用は1万円ほどでテスト内容も比較的易しいものとなります。
防火管理者
飲食店を経営する上で必要となる資格の2つめが「防災管理者」です。店舗の収容人数が30人以上の場合はこの資格を取得しなければいけません。各地域の消防署で講習を受け取得する流れとなります。
なお、「防災管理者」の講習は1日から2日ほどで修了し、費用は3,000円から5,000円程度となります。
-
調理師免許は必要?
- 飲食店を経営する上で多くの人が気になるのが「調理師免許」についてでしょう。よく誤解されるケースとして、調理師免許を取得しないと飲食店を開業できないと思っている方も少なくないようです。
じつは、飲食店を経営するにあたり調理師免許はとくになくても開業はできます。ただし、調理師として本格的にスキルアップしたいと考える方は取得してみてもいいでしょう。調理に関するさまざまな知識を得ることができるため、取っておいても損はない資格といえるでしょう。
開業までの手続きをプロに相談したい方!
お酒を提供する場合に必要な届出・手続きとは?
酒類を提供するための基本ルール
飲食店でお酒を出すこと自体には、 特別な「資格」は基本的に必要ありません 。お客様に料理と一緒にお酒を提供する場合(店内提供)は、通常の「食品営業許可」があれば営業可能です。ただし、営業時間や提供形態によっては、別途「届出」や「免許」が必要となるケースがあります。
特に注意したいのは、 深夜0時以降の営業や、酒類のボトル販売(物販) を行う場合です。これらは風営法や酒税法に関連する規制の対象となり、所轄の警察署や税務署への手続きが求められます。知らずに営業を開始すると、営業停止や罰則の対象になるため、必ず事前に確認・準備をしておきましょう。
深夜にお酒を提供する場合の届出
お酒を主に提供する飲食店(バー、居酒屋、ダイニングなど)で、 深夜0時以降に営業を続ける場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要 です。この届出は風俗営業法に基づく手続きであり、主に治安維持の観点から定められています。
対象店舗の例
- 深夜0時以降に営業するバー、クラブ、ラウンジなど
- メインの提供が酒類で、接待行為を伴わない店舗
手続きの流れ
- 図面の作成(営業所の平面図・周辺略図)
- 申請書類の作成(様式あり)
- 店舗所在地を管轄する警察署・生活安全課に提出
- 営業開始の10日前までに提出が必要
注意点
- 深夜営業と風俗営業(接待・同席など)を同時に行う場合は、別途「風俗営業許可」が必要になります。
- 申請書類は自治体ごとに若干異なることもあるため、管轄の警察署へ事前相談することが推奨されます。
酒類販売業免許が必要なケース
お酒を「その場で飲んでもらうために提供する」のではなく、 ボトル単位で販売(持ち帰り販売や通販)する場合には、税務署の管轄である「酒類販売業免許」が必要 です。これは「物販」に該当し、酒税法に基づく免許制度の対象となります。
対象となるケースの例
- ワインやクラフトビールなどのボトル販売(店頭・イベント・オンライン含む)
- 飲食店に併設された物販スペースでの販売
- ギフトセットなどの発送販売
手続きの概要
- 管轄税務署へ申請(審査あり)
- 申請には事業計画書、販売計画、倉庫設備の詳細などの資料が必要
- 審査期間は2〜3ヶ月かかる場合もあるため、早めの準備が重要
種類別免許の違い
- 一般酒類小売業免許(店頭販売)
- 通信販売酒類小売業免許(オンライン)
- 飲食店等併設型(限定的な販売形態)
飲食と販売は法的な区分がまったく異なる ため、営業の一環でお酒を販売したいと考えている方は、開業前に税務署に相談するのが確実です。
-
資格取得から開業までのスケジュール例
- 飲食店の開業準備は、資格取得や物件契約、許可申請など複数の工程が重なります。ここでは一般的な開業準備のスケジュール例をご紹介します。
時期 やること 備考 開業6ヶ月前〜 ビジネスプラン作成/開業形態・業態の決定 事業計画書の作成を 開業5ヶ月前〜 資格取得の準備(食品衛生責任者講習など) 開催日は地域ごとに異なる 開業4ヶ月前〜 出店エリアの調査/物件探し 設備基準に注意 開業3ヶ月前〜 物件契約/内装業者手配 並行して保健所に事前相談を 開業2ヶ月前〜 許可申請(食品営業許可・防火管理者届など) 書類準備に時間がかかる 開業1ヶ月前〜 備品準備/スタッフ募集・研修/各種保険加入 就業規則の整備も検討を 開業直前 保健所の現地調査/許可証の取得/販促準備 開店告知・SNS活用も忘れずに
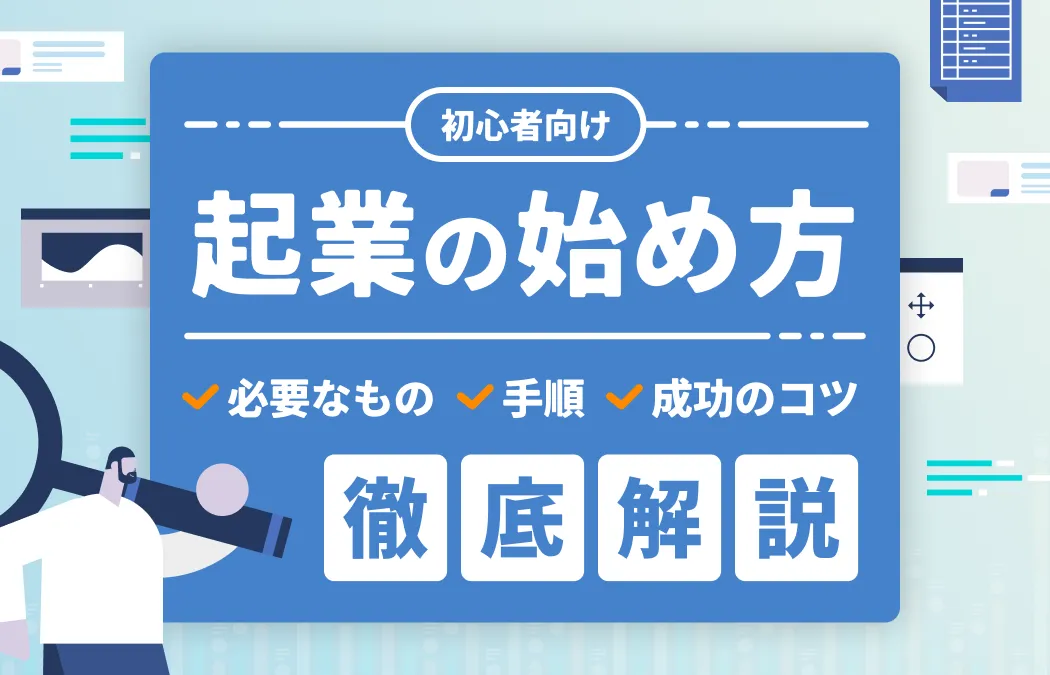
飲食店開業に必要な許可・届出・法的手続きまとめ
許可が必要なもの:食品営業許可(必須)
飲食店を 開業するには、地域の保健所から「食品営業許可」を取得しなければなりません 。これは食品衛生法に基づく制度であり、調理や飲食を提供する全ての店舗に義務づけられています。
申請には以下のような手続きが必要です。
-
事前相談(任意)
物件の図面を持参し、厨房設備の配置が基準を満たしているか確認してもらいます。 -
申請書の提出
営業許可申請書、営業施設の図面、構造・設備の概要、講習修了証などが必要です。 -
施設検査(現地立会)
保健所職員による現地確認が行われます。不適合がある場合は改善の指導を受けることになります。 -
許可証の交付
検査に合格すると営業許可証が発行され、営業が可能になります(通常10日程度)。
届出が必要なもの
防火管理者選任届
収容人数が30名以上の飲食店では、 防火管理者の選任と、消防署への「防火管理者選任届」の提出が義務付けられています 。これは火災予防・避難誘導のための法的な体制づくりを求めるものです。
-
対象となる施設 :収容人数が30名以上の飲食店、特に複合施設内のテナントや大型店舗
-
必要な資格 :所定の講習(2日間)を受講し、防火管理者資格を取得する必要があります。
-
届出の方法 :管轄の消防署に、選任届と資格修了証のコピーを添えて提出します。
深夜酒類提供飲食店営業届(該当する場合のみ)
前述のとおり、 深夜0時以降に酒類を提供する場合には警察署への届出が必要 です。 必要書類や審査基準も複雑なため、物件契約前から要件を確認しておくことをおすすめします。
保険・制度加入が必要なもの
防火管理者選任届
飲食店で従業員を雇用する場合、 労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要 です。これらの手続きは、開業後にスムーズな運営と従業員の安心を確保するために重要です。
-
労災保険(強制加入)
従業員の業務中のケガや病気に備える保険。1人でも雇用するなら加入義務があります。手続きは労働基準監督署で行います。 -
雇用保険(週20時間以上勤務で対象)
従業員が失業した際に給付を受けるための制度。ハローワークでの手続きが必要です。 -
社会保険(法人 or 従業員が5名以上の個人事業主)
法人は常時加入義務あり。個人事業でも一定規模になると義務が生じます。日本年金機構で手続きします。
飲食店経営を始める上で、どれくらい準備費用が必要?
飲食店を開業する場合は、はたしてどれくらいの準備費用が必要なのでしょうか。ここでは個人で開業する小規模の場合の準備費用と詳細についてご紹介します。
準備費用目安:700万円~1,200万円(店舗の業態や規模、エリアによって異なる)
①物件に関する費用
店舗の物件を借りる場合は、敷金とよばれる保証金が必要です。とくに住居用の物件と違い、賃料の約10か月分が敷金の相場となります。例えば、月25万円の物件を借りようとする場合は、250万円の敷金を用意しないといけないことになります。
また賃貸とは別に、前の店舗の内装や設備をそのまま受け継ぐ「居抜き」の場合は、前の借主へその譲渡金を支払う必要があります。居抜きの金額については、経過年数に加え、内装や什器の状態などにより数十万から週百万までさまざまなケースがあります。
②店舗の設備投資にかかる費用
店舗投資にかかる費用としては、厨房機器・看板・備品・内外装などがあります。居抜き物件の場合は、厨房機器や什器、内外装はそのまま使用できることもあり投資額を抑えることが可能です。
具体的な費用については、業種や業態、店舗物件の条件によっても異なるためひと口に言えませんが、目安としては敷金・礼金・手数料など店舗の取得費以外で内外装費や機材費なども含めて、1坪当たり50万円から80万円は必要となります。仮に20坪から30坪の広さの店舗を開業しようとする場合、1,000万円から1,600万円ほどはかかるということになります。ただしここ最近では、費用を少し抑えることのできる居抜き物件が人気となっています。
飲食店経営を始める際に使える補助金・助成金
飲食店経営を開始する際にぜひ知っておきたいのが国や自治体が交付している補助金や助成金情報です。飲食店が活用できるものもあるため、飲食店を開業する際はぜひチェックしておきましょう。
ここでは、飲食店の運営に適した2つの補助金・助成金についてご紹介します。
地域創造的起業補助金(旧:創業補助金)
地域創造的起業補助金は、既存技術の活用や新しいアイディアによって需要や雇用を生む可能性のある事業者に支給される補助金のことです。平成29年までは創業補助金と呼ばれていました。
補助金支給対象は新たに創業を予定しており、従業員を新しく1名以上雇用することや、認定の市区町村や認定の連携創業支援者業者による支援を受けることが条件になります。なお、公募期間は例年4月から5月となっています。
≪対象者≫
・新たに創業を予定している人、
・事業のために、新たに従業員を1名以上雇用すること
・認定市区町村や認定連携創業支援者業者による支援を受けること
≪補助率≫
補助対象となる経費の1/2以内
≪支給額≫
・外部調達資金がある場合:50万円以上200万円以内
・外部資金調達がない場合:50万円以上100万円以内
小規模事業者持続化補助金
次に、小規模事業者持続化補助金も飲食店の運営に活用できる補助金としておススメです。この補助金は販路開拓や生産性の向上の取り組みを支援してくれるものです。たとえば、ホームページ制作やチラシ作成、店舗改修などに利用することが可能です。また以前に受給していた場合でも今回新たな取り組みを行う際は支給の対象となります。
≪対象者≫
全国の小規模事業者、サービス業の場合であれば、従業員5名以下が対象
≪対象経費≫
ホームページ作成、看板やチラシ作成、移動販売車・内装改装費など
≪補助率≫
対象経費の2/3
≪補助上限額≫
50万円
参考:全国商工会連合会
よくある質問(FAQ)
A
必要なのは「資格」というよりも「許可」です。必須なのは「食品営業許可」であり、あわせて「食品衛生責任者」の資格取得が必要です。
A
店舗の規模やエリアによりますが、物件取得費・内装費・設備費・人件費を含めて300万〜1,000万円程度が目安です。
A
はい、一部の行政書士や開業サポートサービスでは、申請代行やスケジュール管理を行ってくれるプランがあります。時間や手間を節約したい方にはおすすめです。
A
はい、営業時間に関係なく、食品を提供する店舗は保健所からの営業許可が必要です。夜のみ営業でも例外ではありません。
A
基本的には同様ですが、 営業許可は移動販売専用の基準があります 。事前に保健所へ確認を取りましょう。
まとめ
今回は、将来飲食店を開業しようと考える方に向けて、飲食店経営に必要となる資格や手続き、開業までの準備について詳しく解説しました。
とくにはじめての開店で一番陥りやすい計算違いは資金不足となります。失敗しない資金計画の基本は、下調べを徹底的に行うことです。お金のかかることは紙に書き出して、それぞれの項目について細かく積み上げていくことが大切です。飲食店開業向けの補助金や助成金などもしっかり活用しながらオープン準備を行いましょうね!
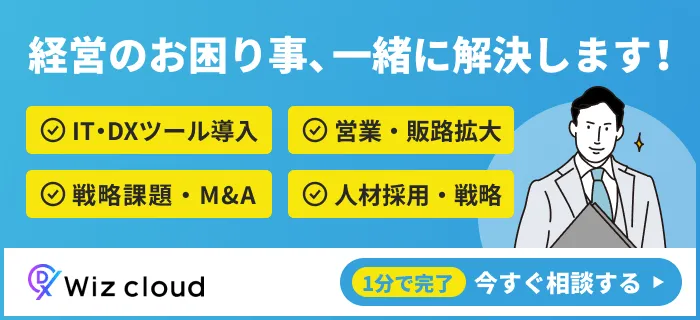

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!