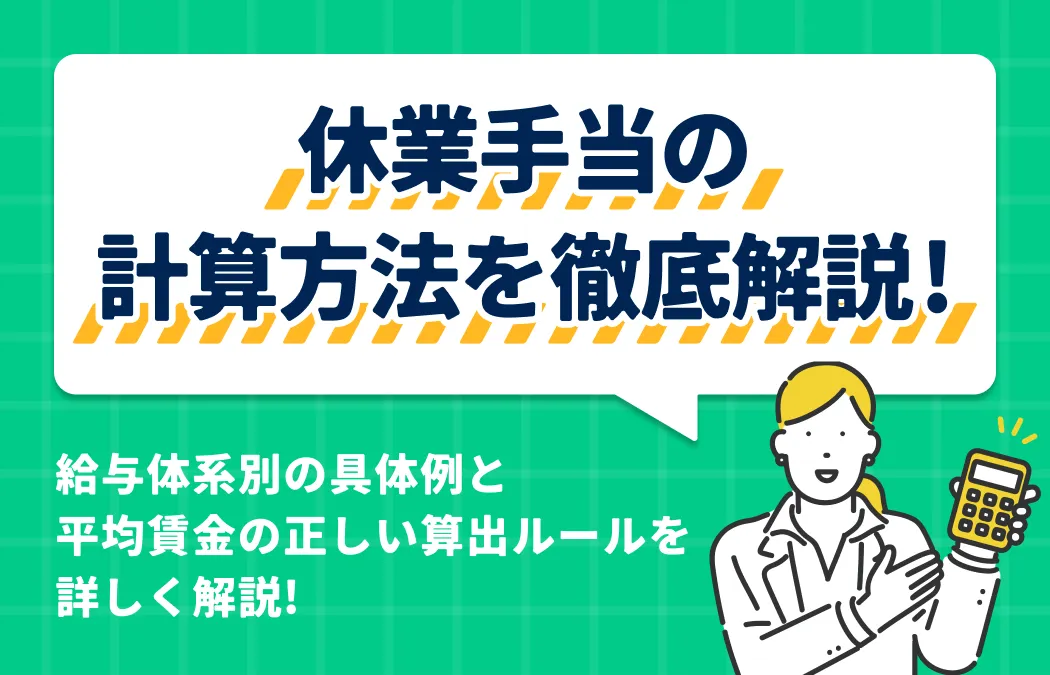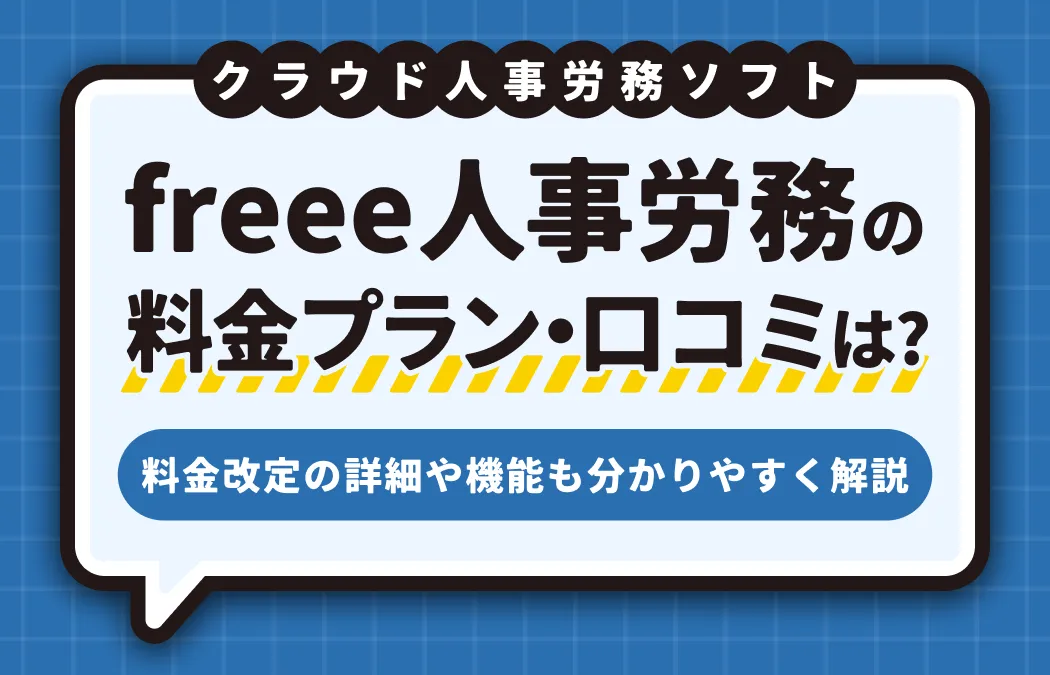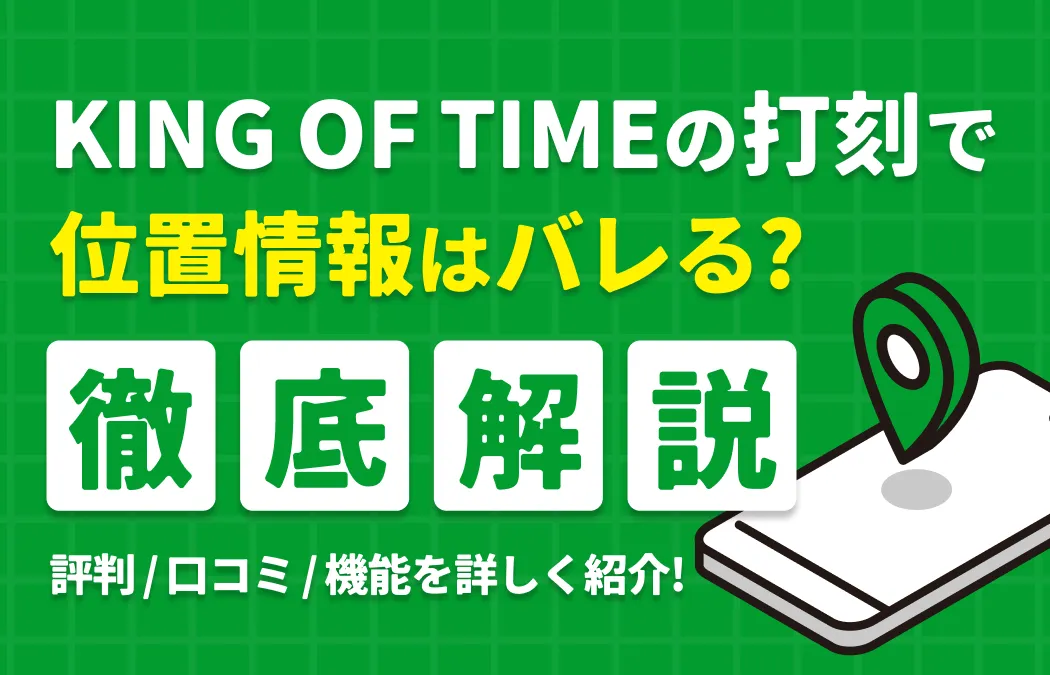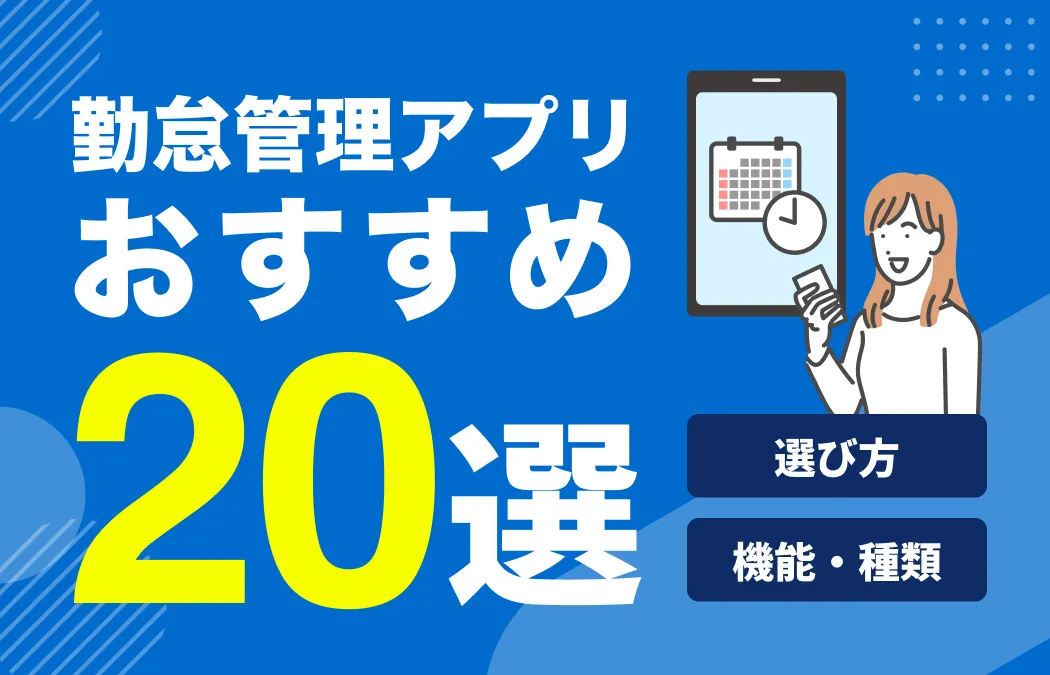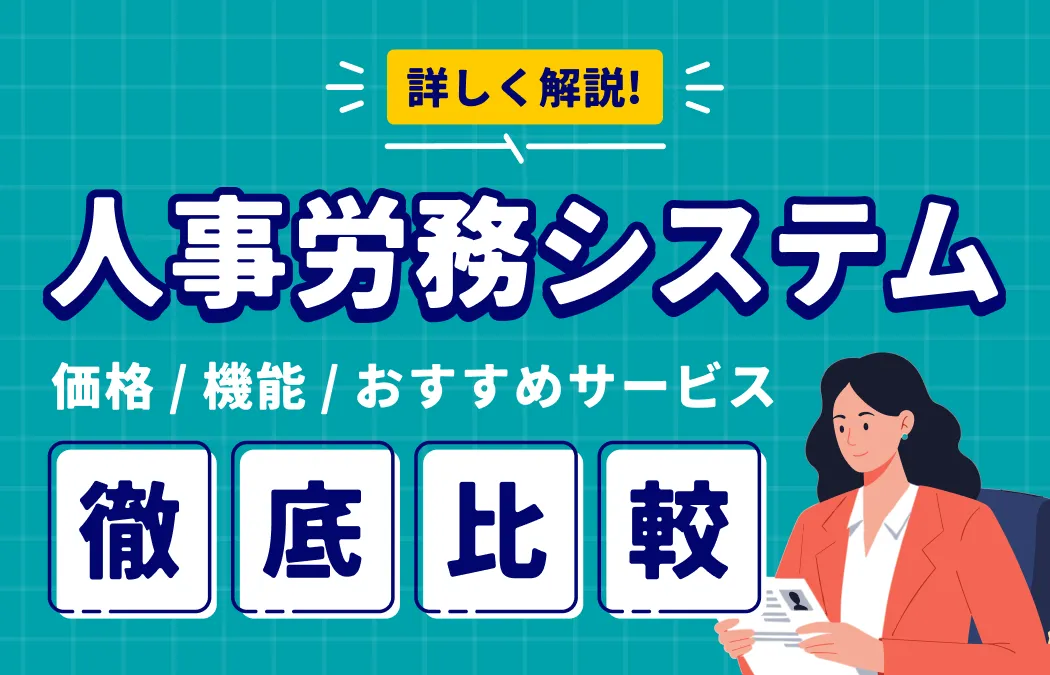「休業手当って“基本給の6割”を払えばいいんだよね?」
しかし実際には、労基法で定められた計算式に基づき「平均賃金の60%以上」を支払う必要があります。
月給制や日給制、時給制など給与体系によって算定方法は異なり、誤解のまま対応すると労務トラブルに発展することも。
本記事では、休業手当の基本ルールから給与体系別の具体的な計算例、注意点まで整理し、実務で迷わず使える知識をまとめました。
目次
休業手当とは?
休業手当とは、 労働者が働く意思を持っていたにもかかわらず、会社の都合で労働できなかった場合に支払う賃金補償 を指します。
労働基準法第26条により、使用者の責めに帰すべき事由による休業時には「平均賃金の60%以上」を支払うことが義務づけられています。これは、会社都合で仕事ができない状況に対して、労働者の生活を守るために設けられた制度です。
休業・休暇・休日の違い
休業手当を 正しく計算するには、まず「休業」「休暇」「休日」の違いを押さえておくことが重要 です。これらを混同すると、支払義務の判断を誤り、法令違反や従業員とのトラブルにつながる恐れがあります。以下のように整理すると分かりやすいでしょう。
| 区分 | 意味 | 典型例 | 休業手当の支払い義務 |
|---|---|---|---|
| 休業 | 会社の都合で労働させない | 設備故障、経営悪化による操業停止 | あり(労基法第26条に基づき平均賃金の6割以上) |
| 休暇 | 労働者の権利として取得する休み | 年次有給休暇、産前産後休暇等 | 休業手当ではなく、有給や法定給付が適用 |
| 休日 | 就業規則で定められた労働義務のない日 | 日曜、祝日、シフトでの休日 | 原則なし(労働義務がそもそもないため) |
-
ポイント
- ・休業
会社の責任による「働けない状態」を指します。業務量減少や機械トラブルなど経営側の都合で労働ができない場合が典型です。労基法26条により、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。
・休暇
労働者の申請や法律で定められた権利として取得する休みです。年次有給休暇や育児休業などが該当し、会社都合ではないため「休業手当」ではなく、通常の有給や法定給付が適用されます。
・休日
就業規則や雇用契約で労働義務が設定されていない日を指します。会社が定めた休日はもとより働かない日なので、休業手当の対象にはなりません。
休業手当と有給・休業補償の違いを整理
休業手当は「会社の都合で働けないとき」に支払われるものですが、似た制度に「有給休暇」や「労災の休業補償」があります。これらを混同すると、支払額を誤ったり、不必要な手当を二重に支給してしまう恐れがあるため、明確に区別して理解しておくことが重要です。
| 制度名 | 主な根拠 | 支払主体 | 支給額の基準 | 適用される状況 |
|---|---|---|---|---|
| 休業手当 | 労働基準法第26条 | 会社 | 平均賃金の60% | 会社都合による休業時 |
| 有給休暇 | 労働基準法第39条 | 会社 | 通常賃金100% | 労働者が権利として取得する休み |
| 休業補償(労災) | 労災保険法 | 労災保険 | 平均賃金の60%+特別至急20% | 業務上の災害や通勤災害による休業時 |
休業手当の支払い義務が発生するケース
休業手当の支払い義務は、 労働基準法第26条により「使用者の責めに帰すべき事由」で休業が発生した場合に生じます 。
つまり、労働者本人に責任がなく、会社の都合や判断で働けない状態になったときに休業手当の支払いが必要です。これを誤解すると、不要な支払いをしたり逆に未払いで労基署から是正勧告を受ける可能性があるため、状況ごとに整理して理解することが重要です。
支払い義務が発生する主なケース
- 設備や機械の故障
例:工場の生産ラインが止まり従業員が働けない → 会社責任にあたるため休業手当が必要。 - 経営上の理由による操業停止
例:売上減少で一時的に店舗を閉鎖 → 使用者都合として支払い義務あり。 - シフト削減・勤務調整
例:人件費削減のために出勤日数を減らす → 会社の判断で労働機会を奪うため支払い対象。
休業手当で支払う方法
休業手当を支払う際には 「いくら払うか」だけでなく、「どのように支払ったかを明示すること」が重要 です。
労基法では平均賃金の6割以上の支払いを義務づけており、単に給与と一緒に振り込むだけでなく、給与明細や帳票上に算定根拠を明示することが望ましいとされています。根拠が曖昧なままでは、従業員からの不信感やトラブルにつながる恐れがあります。
支払いの基本的な流れ
- 平均賃金を算出する
過去3か月の賃金総額 ÷ 総日数 で平均賃金を求めます。残業代や手当も含める点に注意が必要です。 - 休業手当額を計算する
平均賃金 × 60%以上 × 休業日数で算出します。実務では端数処理のルールも明示すると安心です。 - 給与明細に明記する
「休業手当」「算定基礎日額」などの項目を明記し、通常の賃金と区別して支払います。
-
実務上の注意点
- ・根拠を説明できるようにする
労働者からの問い合わせに備え、算定表や計算過程を保存しておくことが推奨されます。
・就業規則との整合性
就業規則に「休業手当の計算・支払い方法」を明記しておくと、トラブル回避につながります。
・振込方法は通常の給与と同じで問題なし
重要なのは「支払い方法」よりも「明細での区分と根拠提示」である点です。
休業手当の基準は「平均賃金の6割」
休業手当の計算式と算出プロセス
休業手当の支払い額は 「基本給の6割」ではなく、労基法第26条に基づく平均賃金の60%以上で算出するのが正しいルール です。
まず「平均賃金」を計算し、その上で休業手当額を求めるプロセスを理解しましょう。平均賃金とは、直前3か月間に支払った総賃金を暦日数で割って算出します。残業代や手当も含まれるため、固定給だけで計算してしまうと不足額が生じるため注意が必要です。
休業手当の計算プロセス
- 直前3か月間の総賃金額を算出する
基本給、残業代、各種手当を含め、賞与や実費精算は除外。 - 平均賃金を計算する
総賃金 ÷ 総日数(暦日数ベース)。 - 休業手当を算出する
平均賃金 × 60%以上 × 休業日数。会社が厚く保障する場合は60%を超える額で設定可能。
-
計算例
- ・直近3か月の総賃金:600,000円
・総日数:92日
・平均賃金:600,000 ÷ 92 = 6,521円
・休業手当(10日休業):6,521 × 60% × 10 = 39,126円
平均賃金に含まれるもの・含まれないもの
平均賃金の算定対象となる 賃金には、すべての支給項目が含まれるわけではありません 。以下のように整理すると分かりやすいです。
| 含まれる賃金 (労働の対価として継続的に支払われるもの) |
含まれない賃金 (労務の提供と直接関係がない臨時金や実費精算) |
|---|---|
| 基本給 | 臨時の結婚祝い金など一時的な見舞金 |
| 残業代・深夜手当 | 出張旅費・交通費(実費計算) |
| 各種手当(役職手当・資格手当) | 賞与(毎月支給なら算入対象になる場合あり) |
誤解しやすいポイントと注意点
休業手当の計算では、多くの担当者が次の点でつまずきます。
-
誤解①:基本給だけで計算してよい
→ 誤り。平均賃金には残業代や手当も含まれるため、基本給だけでは不足額が発生します。 -
誤解②:賞与は必ず含める
→ 原則は含まれません。ただし毎月固定で支給される場合は賃金とみなされ算入対象になる場合があります。 -
誤解③:60%きっかりであれば問題ない
→ 法律上は60%以上の支払い義務があるため、企業判断で60%を超えて上乗せすることも可能です。 -
誤解④:計算式の端数処理は適当でよい
→ 実際は小数点処理をどう扱うか就業規則で定めておく必要があります。
これらを 正しく理解することで、従業員とのトラブルや監督署からの指導を防ぐ ことができます。
給与体系別に見る休業手当の計算方法
月給制の場合の計算例
月給制の従業員は 毎月一定額の給与が支払われるため、一見すると計算は単純 に思えます。
しかし、休業手当は「基本給」ではなく平均賃金を基準に算出するため、正しい手順を踏むことが重要です。特に残業代や各種手当を除外してしまうと過少支給になり、労基署から是正勧告を受けるリスクがあります。
月給制での計算手順
- 直近3か月の賃金総額を確認
基本給、残業代、役職手当などを含め、賞与や実費精算は除外。 - 平均賃金を算出
賃金総額 ÷ 総日数(暦日数ベース)。 - 休業手当を計算
平均賃金 × 60%以上 × 休業日数。
-
計算例
- ・直近3か月の総賃金:600,000円
・総日数:92日
・平均賃金:600,000 ÷ 92 = 6,521円
・休業手当額(10日休業):6,521 × 60% × 10 = 39,126円
日給制の場合の計算例
日給制の従業員は、 働いた日ごとに給与が決まるため、休業手当の計算も「直近3か月間の支給実績」を基準に算出 します。
月給制と違い、勤務日数が変動しやすいため、暦日数で割る平均賃金の算出がより重要になります。誤って「1日の日給額×60%」と短絡的に計算すると、正しい支払額にならないケースがあるため注意が必要です。
日給制での計算手順
- 直近3か月の総賃金を集計
日給、残業代、諸手当を合算。臨時の祝い金や実費精算は除外。 - 平均賃金を算出
総賃金 ÷ 総日数(暦日数)。勤務日数ではなく暦日数で計算する点がポイント。 - 休業手当を算出
平均賃金 × 60%以上 × 休業日数。
-
計算例
- ・直近3か月の総賃金:300,000円
・総日数:90日
・平均賃金:300,000 ÷ 90 = 3,333円
・休業手当額(5日休業):3,333 × 60% × 5 = 9,999円
感染症や災害など特別なケースの休業手当
感染症による休業
新型コロナウイルスやインフルエンザなどの 感染症により従業員を休業させる場合、状況によって会社が支払うべき手当が異なります 。
基本的に 会社の判断で休業を命じた場合 は「使用者の責に帰すべき事由」とされ、労基法第26条に基づき休業手当の支払い義務が発生します。一方で、従業員が自主的に出社を控えた場合は休業手当の対象外となるケースもあります。
対応の基本パターン
- 会社都合の休業命令:休業手当が必要(平均賃金の6割以上)
- 従業員の自主判断での欠勤:原則として無給。ただし有給休暇を充てる運用は可能
- 行政の休業要請や出勤停止命令:状況により「不可抗力」と判断され、休業手当不要になる場合がある
このように「誰の判断で休業となったか」「会社が労働させる意思を持っていたか」が支払い義務を判断する重要なポイントです。
自然災害や不可抗力の場合
台風・地震・大雪などの 自然災害で事業継続が不可能となった場合は、会社側に責任がない「不可抗力」とされ、休業手当の支払い義務は原則発生しません 。
ただし、従業員がすでに出勤していたのに突然の災害で帰宅を命じた場合や、災害後の対応が不十分で休業を長引かせた場合は「使用者の責めに帰す」ケースと判断される可能性もあります。
| ケース | 休業手当の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 台風で電車が止まり全員出勤不可 | 不要 | 会社責任ではなく不可抗力 |
| 事務所の設備不良により休業 | 必要 | 会社都合に当たるため |
| 出勤後に災害で操業停止 | 状況次第 | 安全面からの帰宅命令でも、一定の労務提供があれば対象となる場合あり |
自然災害の場合でも「不可抗力か会社都合か」の判断はケースバイケースです。 災害リスクが高い地域では、事前に就業規則へ対応方針を明記しておくと、従業員とのトラブルを防止できます 。
まとめ
休業手当は「基本給の6割」ではなく、労基法に基づく平均賃金の60%以上を支払うことが正しいルールです。
計算方法は給与体系によって異なり、月給制・日給制・時給制・歩合給制ごとに算定式や注意点があります。さらに、感染症や自然災害などの特殊ケースでは、会社都合か不可抗力かによって支払い義務が変わる点にも注意が必要です。
正しい理解と算出ができなければ、労務トラブルや是正勧告につながりかねません。自社の状況に即した正確な対応を行うために、専門家への相談や計算ツールの活用をおすすめします。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!