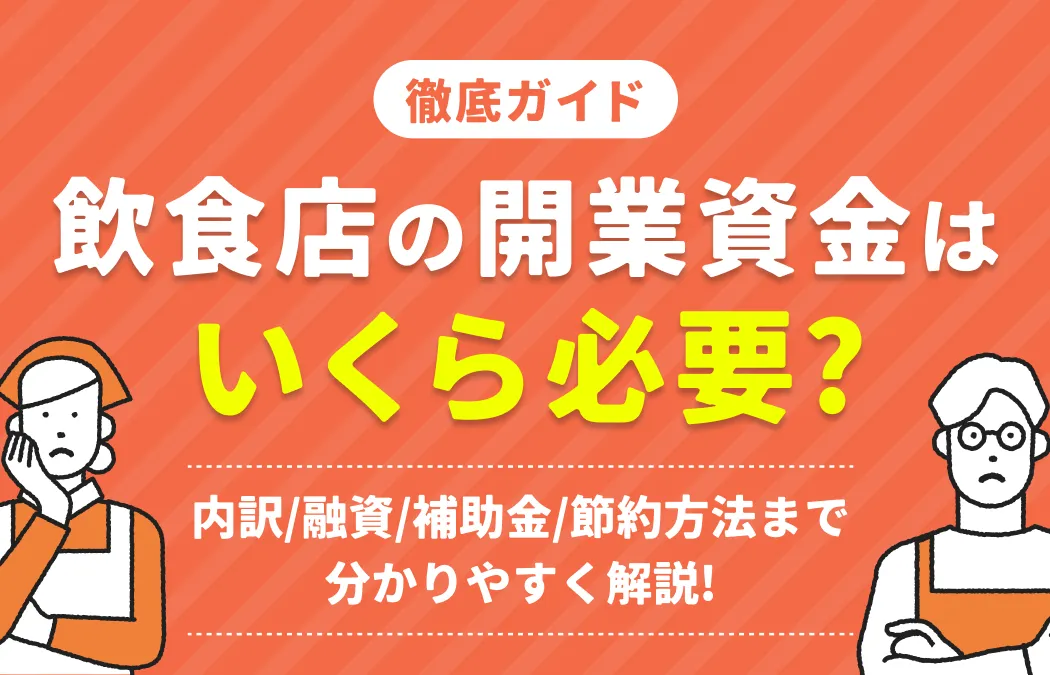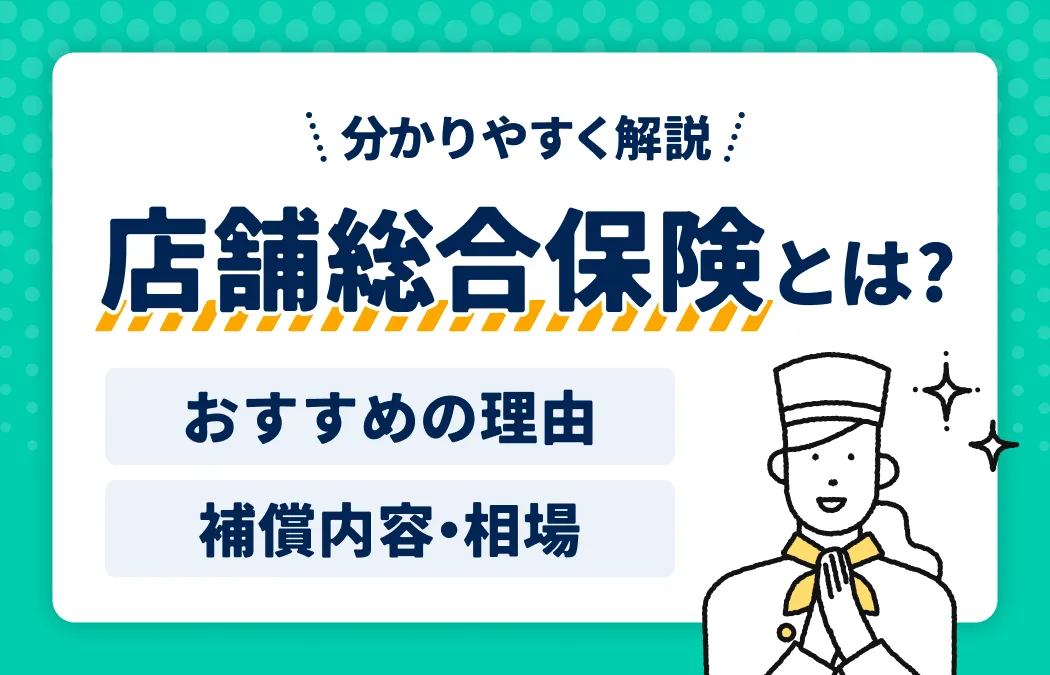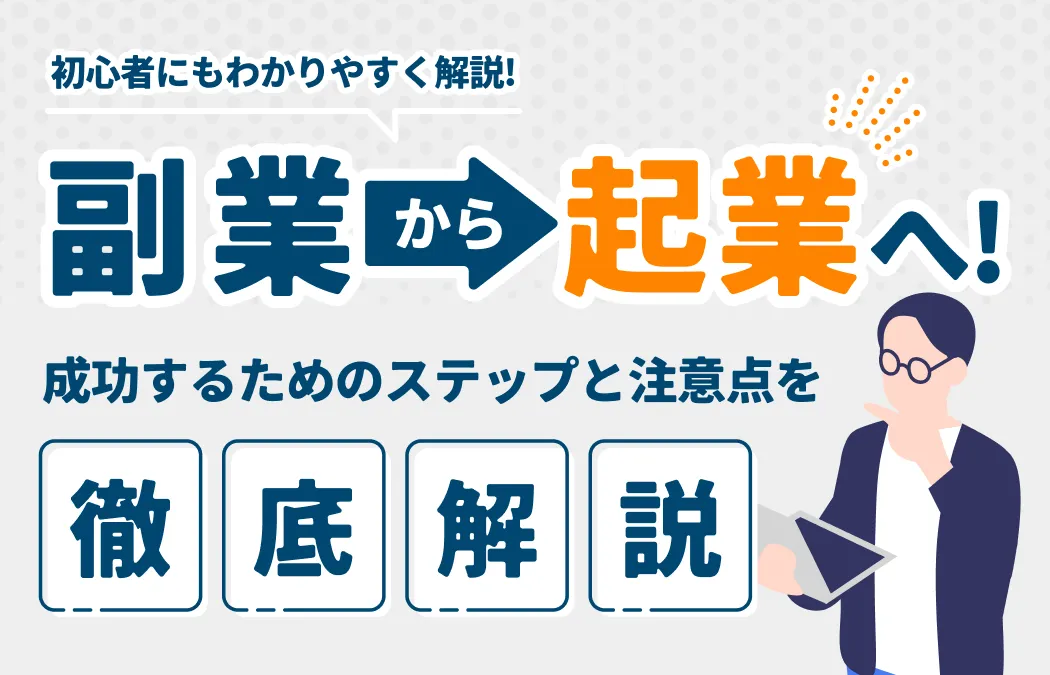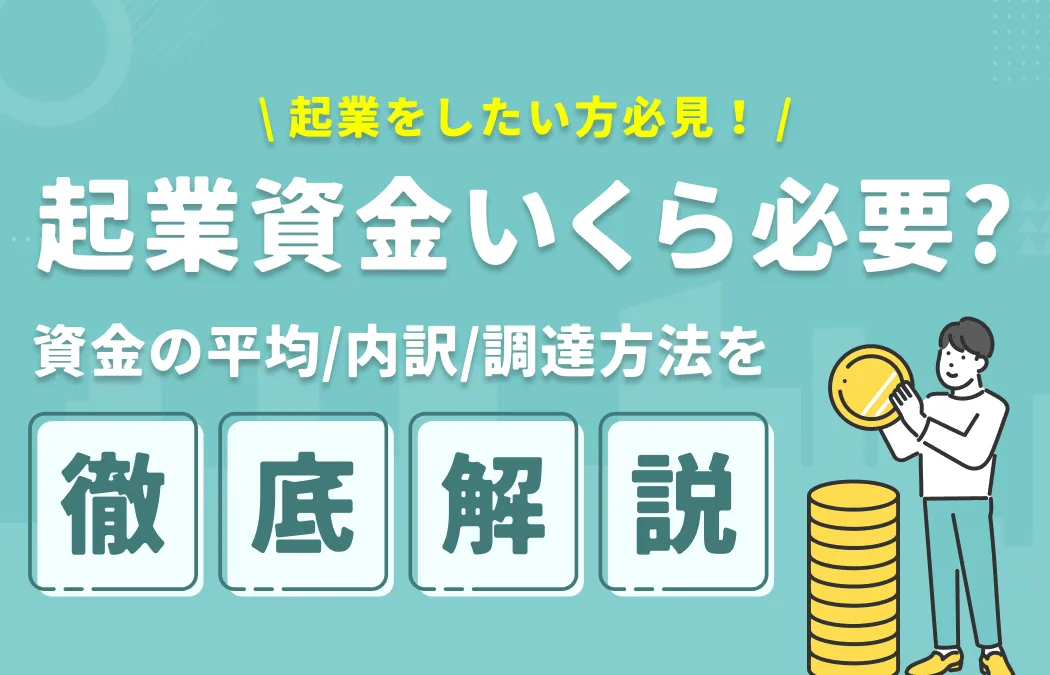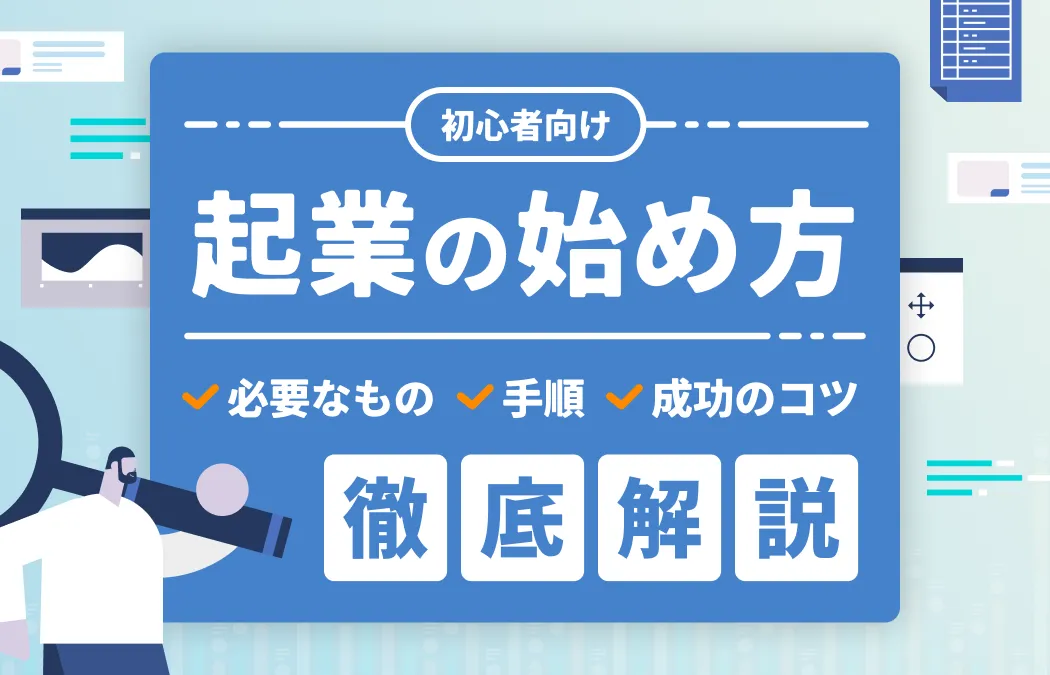「開業資金を集める方法を知りたい」
飲食業界は、個人事業主のなかでも人気の業界です。最近では未経験からの飲食店開業も増えてきており、誰もが自分のお店をもてる時代になってきました。しかし初めて飲食店をオープンさせる方が悩まれるのが「いくら開業資金が必要になるか」という点です。 漠然とした夢ではなく、叶えられる目標にするためにも飲食店の開業資金について知っておきましょう。そこで本記事では、飲食店開業にかかる費用や、自己資金額、資金調達の手段について解説していきます。
目次
飲食店の開業資金はいくら必要?業態別の平均と計画の立て方
業態別に見る開業資金の平均
飲食店の開業資金は、業態や店舗規模、立地条件によって大きく異なります。 一般的に、 カフェや小規模店舗では500〜800万円前後、居酒屋やレストランでは800〜1,200万円以上が目安 です。
以下の表は、代表的な業態ごとの平均的な開業資金をまとめたものです。
| 業態 | 平均開業資金 | 主な費用要素 |
|---|---|---|
| カフェ | 約500〜800万円 | 内装費・設備・厨房機器 |
| 居酒屋 | 約800〜1,200万円 | 物件取得費・厨房設備費・人件費 |
| ラーメン店 | 約700〜1,000万円 | 厨房設備・原材料費・看板費用 |
| テイクアウト専門店 | 約300〜600万円 | 小規模店舗・省スペース設計 |
| レストラン | 約1,000〜1,500万円 | 内装デザイン・大型厨房機器 |
これらの数字はあくまで平均値ですが、 「どんな規模・スタイルで始めたいか」によって必要額が大きく変動 します。
特に内装工事や物件取得費は予算の50%以上を占めるケースも多く、慎重な計画が必要です。
立地・店舗規模・客単価による資金の違い
同じ業態でも、立地や店舗規模によって必要資金は大きく変わります。 駅前や商店街など 集客力の高いエリアは家賃が高く、初期投資も膨らむ 傾向があります。 一方、住宅街や郊外で 小規模に始める場合は、家賃を抑えつつ内装に投資できるケース もあります。
| 要素 | コストに影響するポイント | 平均的な費用感 |
|---|---|---|
| 立地 | 駅前や繁華街は家賃・保証金が高い | 家賃:15〜30万円/月・保証金:6〜12ヶ月分 |
| 店舗規模 | 広ければ内装・人件費・備品費用が増加 | 坪単価10〜15万円が内装目安 |
| 客単価 | 高単価業態ほど、内装・調理設備費が上がる | 1,000円客単価と5,000円客単価で設備差大 |
資金計画を立てる際のポイント
「いくら必要か」はもちろん重要ですが、 “どう準備し、どの順序で支出するか”が開業成功のカギ です。 資金計画を立てる際は、次の3ステップを意識しましょう。
- 必要資金の総額を算出する
物件取得・設備・運転資金をすべて洗い出し、全体像を把握します。 - 自己資金と融資のバランスを決める
一般的には「自己資金3割・融資7割」が目安。
自己資金が少ない場合は、補助金や専門支援サービスを検討します。 - 返済計画を立てる
開業後3〜6ヶ月は赤字を想定し、余裕を持った返済期間を設定しましょう。
\ 開業資金の計画で迷ったら専門家に無料相談! /
「0円創業くん」なら、資金計画から融資サポート、物件探しまでトータルで支援。
自己資金が少なくても、あなたの開業を現実にできます。
初期費用と運転資金の違いとは?飲食店開業で失敗しないための資金計画
初期資金と運転資金の違いを理解する
飲食店を開業する際、 多くの人が「初期費用だけあれば大丈夫」と考えがちですが、これは大きな誤解 です。 実際には、開業までに必要な「初期費用」だけでなく、開業後の数ヶ月を支える「運転資金」も不可欠です。
この2つの違いを明確に理解しておくことが、開業後の資金ショートを防ぐポイントとなります。
| 資金の種類 | 内容 | 主な項目 | 支出タイミング |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 開店までにかかる費用 | 物件取得費・内装工事・厨房設備・広告宣伝費 | 開店前 |
| 運転資金 | 開店後にかかる継続的な費用 | 仕入れ・人件費・家賃・光熱費 | 開店後〜営業継続中 |
特に飲食業は、 売上回収までに時間がかかる(仕入れ先への支払い先行など)ため、3〜6ヶ月分の運転資金を用意するのが理想 です。
-
理解しておくべきポイント
- ・初期費用は“一度きり”の投資だが、運転資金は“毎月発生”するコスト。
・開業直後は売上が安定しないため、運転資金が不足すると黒字化前に閉店リスクが高まる。
・資金調達時は「開業費用+半年分の運転資金」をセットで考えるのが安全。
どのくらいの運転資金を確保すべきか
開業初期は固定費の支払いが重なり、黒字化までは時間がかかることが一般的です。 したがって、 最低でも開業後3〜6ヶ月分の運転資金を確保しておく必要があります 。 以下は、月間固定費の目安と、6ヶ月分を確保する場合のシミュレーション例です。
| 費用項目 | 月額の目安 | 6ヶ月分の目安 |
|---|---|---|
| 家賃 | 20万円 | 120万円 |
| 人件費(2名) | 30万円 | 180万円 |
| 光熱費 | 5万円 | 30万円 |
| 仕入れ | 10万円 | 60万円 |
| 広告・販促費 | 5万円 | 30万円 |
| 合計 | 70万円/月 | 420万円前後 |
-
運転資金を守る3つのコツ
- 1. 固定費を抑える立地・物件選び(例:居抜き物件の活用)
2. 変動費をコントロール(例:仕入れを定期契約に)
3. 初期段階で余裕資金を確保(例:融資+補助金を併用)
初期費用と運転資金のバランスをとる資金計画
開業成功のポイントは、「初期費用にかけすぎない」ことです。 内装デザインや設備投資に予算を集中させすぎると、開業後の運転資金が枯渇してしまう危険 があります。 資金計画を立てる際は、次のようなバランスを意識しましょう。
| 費用区分 | 理想的な配分 | 解説 |
|---|---|---|
| 初期費用(物件・内装・設備など) | 約60〜70% | 居抜き・中古設備活用で削減可能 |
| 運転資金(人件費・家賃・仕入れなど) | 約30〜40% | 開業後半年分を確保するのが理想 |
-
良くある失敗パターン
- ・内装にお金をかけすぎて、オープン後3ヶ月で資金が底をつく
・広告宣伝に費用をかけず、集客が追いつかない
これを防ぐためには、自己資金+融資の総額を“経営が安定するまでの半年”を見越して計画することが重要です。
飲食店の物件取得費はいくら?立地・物件タイプ別の初期コスト比較
立地・物件タイプ別の初期コスト比較
飲食店の開業において、 物件取得費は初期費用の中でも最も大きな割合を占める 項目です。 費用は「立地」「物件タイプ」「契約条件」によって大きく異なります。 下表は、立地別・物件タイプ別に見た平均的な初期コストの比較です。
| リッチタイプ | 月額家賃の目安 | 契約時の保証金・礼金 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 駅前・繁華街 | 20〜40万円 | 家賃6〜12ヶ月分+礼金1〜2ヶ月 | 高い集客力だが初期費用負担大 |
| 商店街・住宅街 | 10〜25万円 | 家賃3〜6ヶ月分 | 安定した固定客を狙いやすい |
| 郊外・ロードサイド | 5〜15万円 | 家賃3〜5ヶ月分 | 駐車場付きで車利用客向けに有利 |
| スケルトン物件 | 家賃+工事費 | なし〜礼金1ヶ月 | 自由設計できるが工事費が高い |
| 居抜き物件 | 家賃+譲渡費用 | 家賃数ヶ月分+譲渡料50〜200万円 | 初期費用を抑えやすいが制約あり |
-
チェックリスト:物件取得時に確認すべき項目
- ・契約形態(定期借家契約 or 普通借家契約)
・解約時の原状回復義務の範囲
・看板・外装の改修可否
・厨房ダクト・排水など設備条件の確認
これらを事前に把握することで、想定外の出費やトラブルを防げます。
居抜き物件活用でコストを抑える方法
「居抜き物件」とは、 前の店舗が使用していた内装や厨房機器などをそのまま引き継いで開業できる物件 のことです。 この形態を上手く活用すれば、開業資金を30〜50%程度削減できる場合もあります。
| 費用比較 | スケルトン物件 | 居抜き物件 |
|---|---|---|
| 内装工事費 | 300〜800万円 | 50〜200万円 |
| 設備導入費 | 200〜400万円 | 0〜100万円 |
| 工期 | 約2〜3ヶ月 | 1〜2週間程度 |
| 総額目安 | 約700〜1,200万円 | 約300〜700万円 |
-
注意点
- ・設備の劣化や衛生状態を必ずチェック(特に給排水・ガス)
・譲渡契約書の内容を明確に(残置物・修繕責任の所在)
・前店舗の評判が悪い場合、イメージの引き継ぎに注意

編集部
物件選びでは、「安い=得」とは限りません。
“内装・設備がそのまま使えるか”を冷静に見極めることが、最終的なコスト削減につながります。
飲食店開業で利用できる国・自治体の融資制度とは?公的支援で資金調達をスムーズに
日本政策金融公庫の創業融資制度
飲食店開業を目指す人の多くが利用しているのが、 日本政策金融公庫(国の金融機関)による「新創業融資制度」です。 この制度は、創業前や創業間もない個人事業主・中小企業を対象に、無担保・無保証人で利用できる融資として非常に人気があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 新規開業者・開業5年以内の事業者 |
| 融資限度額 | 最大3,000万円(うち運転資金は1,500万円まで) |
| 金利 | 年2〜3%前後(時期・条件により変動) |
| 返済期間 | 原則7年以内(措置期間あり) |
| 保証人・担保 | 原則不要 |
| 審査ポイント | 経営経験、自己資金比率、事業計画書の内容 |
-
申請までの流れ
- 1. 開業計画の整理(必要資金・事業内容を明確化)
2. 事業計画書・収支予測を作成
3. 公庫への申し込み → 面談 → 審査
4. 融資決定 → 資金入金
■審査期間はおおむね2〜3週間。
提出書類の不備や計画書の不明瞭さがあると遅れるため、初めての人ほど専門家サポートを受けた方がスムーズです。
家族や友人から資金を借りるときの注意点|トラブルを防ぐためのポイント
家族・友人からの借り入れで注意すべき3つのリスク
家族や友人からの 借り入れは、審査不要・手続きが早い というメリットがあります。 しかし一方で、金銭トラブルや信頼関係の悪化など、感情的なリスクが非常に大きい資金調達方法でもあります。 以下の3つのリスクを把握した上で、慎重に判断することが重要です。
主なリスク一覧
| リスク | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 信頼関係の崩壊 | 返済が遅れたり未払いになると、人間関係に亀裂が走る | 「返す返すと言っても…」とトラブル化 |
| 書面がなくトラブルになりやすい | 借用書を作らないまま貸し借りを行うケースが多い | 税務上「贈与」とみなされる可能性も |
| 税務リスク | 金利設定や返済記録がないと贈与税対象になることも | 税務署から指摘を受ける例もある |
トラブルを防ぐために必ず行うべき対策
家族・友人間での借り入れを円滑に進めるには、 「信頼を守る仕組みづくり」が欠かせません。 曖昧な約束ではなく、書面化・記録化・説明責任を徹底することで、トラブルを未然に防げます。
対策リスト
- 借用書(契約書)を作成する
金額・返済期日・利息・返済方法を明記した書面を作成。
→ 契約書があれば「贈与ではなく貸付」として法的効力を持ちます。 - 返済計画を明確に共有する
「毎月◯万円×◯回」といった返済スケジュールを作り、相手の了承を得ておく。
→ 支払いの透明性を高め、誤解を防ぐ。 - 返済実績を記録に残す
銀行振込で返済し、通帳や振込明細を証拠として保管。
→ 証拠があれば税務上も正当な貸付と認められやすい。
飲食店開業で資金調達に失敗しないための5つのポイント
融資審査で重視される3つのチェック項目を理解する
飲食店の開業資金を融資で調達する際、 金融機関は主に「自己資金」「経験」「事業計画」の3点を重点的にチェック します。 これらを押さえて準備することで、審査通過率が大幅に高まります。
| チェック項目 | 審査で見られる内容 | 対策ポイント |
|---|---|---|
| 自己資金 | どの程度の自己投資意欲があるか | 目安は総額の3割以上が理想。通帳履歴で確認されるため、計画的に貯蓄を。 |
| 経営・飲食経験 | 開業する業種の経験年数やスキル | 「調理経験+店舗運営経験」があると信頼度が上がる。 |
| 事業計画書 | 収支計画・採算性・リスク管理 | 数値に根拠を持たせる。売上根拠や原価率を明確に。 |
資金調達方法は複数を組み合わせる
開業資金は、 1つの手段に頼るよりも複数の資金源を組み合わせる方がリスクが少なく安定的 です。 たとえば、自己資金・公的融資・補助金をバランスよく活用することで、無理のない資金計画が立てられます。
組み合わせ例
| 資金源 | 特徴 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 自己資金 | 自由度が高く即時利用可 | 最低限の初期投資に活用 |
| 公的融資(公庫・自治体) | 低金利・長期返済可能 | 開業資金のメインに設定 |
| 補助金・助成金 | 返済不要だが採択制 | 事前準備とタイミングが重要 |
| クラウドファンディング | 宣伝効果も兼ねる | 店舗のコンセプト発信に活用 |
返済計画とキャッシュフローを可視化する
融資を受けた後、 最も多い失敗は「返済負担の見込み違い」 です。 特に飲食店は売上が季節や曜日によって変動しやすく、固定費の支払いに追われるケースも少なくありません。 そのため、返済シミュレーションと月次キャッシュフロー管理を徹底しましょう。
-
返済シミュレーション例(公庫融資 500万円・年利2.5%)
-
返済期間 月々の返済額 総返済額 3年 約14.4万円 約518万円 5年 約8.9万円 約533万円 7年 約6.6万円 約554万円
専門家に相談して融資成功率を上げる
融資審査や補助金申請は、書類の精度や説明の一貫性で大きく結果が変わります。 専門家(行政書士・中小企業診断士など)に相談することで、通過率・スピード・信頼性のすべてが向上 します。
専門家に依頼するメリット
- 書類作成を代行してくれるため、申請ミス・不備を防止
- 審査で聞かれやすい質問に対する回答準備ができる
- 補助金・助成金の併用提案や最新制度の紹介が受けられる
開業資金を抑えるための方法
居抜き物件の利用
居抜き物件を利用することで、飲食店の開業資金を大幅に抑えることができます。 居抜き物件とは、前の店舗の内装や設備をそのまま引き継ぐ物件 のことです。
例えば、ラーメン屋さんだった場所をそのまま使って、新しいラーメン店を開業するようなイメージです。 この方法のメリットは、内装工事費や厨房設備の購入費用を節約できることです。通常、これらの費用は開業資金の大きな部分を占めますが、居抜き物件ならその心配がありません。
ただし、 前の店舗のコンセプトや雰囲気が残るため、自分の理想とは異なる可能性があります 。また、設備の老朽化や衛生面のチェックも必要です。 それでも、開業資金を抑えたい方にとっては、居抜き物件は魅力的な選択肢となるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 居抜き物件のメリット | 内装工事費・設備購入費の節約 |
| 注意点 | 前店舗の雰囲気が残る、設備の老朽化 |
| 適している人 | 開業資金を抑えたい人 |
中古備品の活用
飲食店開業時、 新品の厨房機器や家具は高価ですが、中古品なら大幅に費用を削減 できます。例えば、新品の業務用冷蔵庫が50万円するところ、中古なら半額以下で手に入ることもあります。
ただし、中古品選びには注意が必要です。動作確認はもちろん、衛生面や耐久性もチェックしましょう。中古品を購入する際は、信頼できる業者から購入するのがおすすめです。中古備品のメリットは、コスト削減だけではありません。まだ利用できるものをゴミにするのではなく、再利用することは環境にやさしい選択でもあり、SDGsの観点からも注目されています。
リースを活用するメリット
備品を リースで活用することは、飲食店開業時の初期コストを大幅に抑える 強力な味方です。例えば、高額な厨房機器などは、購入すれば数百万円かかりますが、リースなら月々数万円で利用できることもあります。
リースで備品を用意することで、初期投資を抑えられるだけでなく、資金繰りの負担も軽減できます。 さらに、リースには設備の更新や保守が含まれることもあるので、故障時なども安心です。ただし、長期的にはリースの方が高くつく可能性もあるので、慎重に検討しましょう。
📩 開業資金や準備に関するご相談はこちら
「資金計画の立て方が分からない」「自分のケースでも大丈夫?」
そんな不安は、専門スタッフに直接ご相談ください。
- ✔ 飲食店開業の経験豊富な相談員が対応
- ✔ 初期費用や資金調達の疑問を丁寧にサポート
- ✔ ご相談はオンライン・電話でも可能です
補助金・助成金を活用する方法
補助金・助成金の種類
飲食店開業に利用できる補助金や助成金は、起業家の強い味方です。例えば、 中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」は、販路開拓や業務効率化に使える最大50万円の補助金 です。
また、 東京都の「創業助成事業」では、最大300万円の助成金が受けられる可能性 があります。
これらの制度を上手に活用することで、開業時の資金負担を大幅に軽減できるでしょう。ただし、申請には綿密な事業計画が必要です。早めの情報収集と準備が成功の鍵となります。
| 補助金・助成金の種類 | 概要 | 上限額 |
|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓・業務効率化支援 | 50万円 |
| 東京都創業助成事業 | 創業時の経費助成 | 300万円 |
申請方法と必要書類
-
STEP.1
申請書類の準備
事業計画書や収支計画書、そして申請者の資格を証明する書類が必要
-
STEP.2
申請手続き
申請方法は、オンラインや郵送、窓口提出など様々です。締め切りを確認し、余裕を持って準備することが大切です。書類作成に不安がある場合は、地域の商工会議所や中小企業支援センターに相談するのも良いでしょう。
-
STEP.3
審査
審査には通常2ヶ月程度かかります。この間、追加資料の提出を求められることもあるので、連絡を見逃さないようにし
-
STEP.4
採択通知を受け取る
支給されるまでの流れと注意点
補助金や助成金の 申請書類を提出したら、審査を経て、採択通知を受け取ります 。その後、 事業実施、実績報告書の提出、そして最後に補助金の支給という順序 です。
注意点としては、採択後も計画通りに事業を進める必要があります。途中で大きな変更があると、補助金が減額されたり、最悪の場合、支給されないこともあります。また、 支給は基本的に事業完了後となるため、申請から支給までに数ヶ月以上かかることがあります 。その期間の資金繰りも考慮しておきましょう。
よくある質問
A
飲食店の開業資金は、立地や規模によって大きく変動しますが、一般的には1000万円から3000万円程度が目安となります。開業資金の内訳としては、物件取得費、内装工事費、厨房設備費、備品購入費、そして運転資金などが挙げられます。
A
はい、公的融資(日本政策金融公庫など)や補助金制度を活用すれば可能です。事業計画書をしっかり作成すれば、自己資金が少なくても審査に通る例もあります。
A
まずは事業計画書の作成と申請書の提出から始めましょう。必要書類を整え、面談で事業内容を丁寧に説明することが審査通過のカギです。
A
代表的なものに「小規模事業者持続化補助金」や「創業支援補助金(自治体)」があります。どちらも返済不要で、設備・宣伝費などに活用できます。
A
主な原因は、自己資金不足・事業計画の甘さ・返済根拠の不明確さです。数字に基づいた計画書を作成し、収支根拠を明確にすることで改善できます。
💡 自己資金ゼロから飲食店開業を目指せます!
「開業したいけど資金が足りない…」
そんなあなたを、開業資金のプロがサポートします。
- ✔ 自己資金ゼロからの開業支援に特化
- ✔ 融資・補助金・事業計画までまるごと相談OK
- ✔ 初回無料で、相談だけでも大歓迎!
まとめ
飲食店の開業には、想定以上に多くの資金が必要となります。
自己資金だけで賄うのは難しくても、公的融資や補助金を活用すれば、無理のない資金計画が可能です。特に日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や自治体の制度融資は、低金利・無担保で利用できるため、多くの開業希望者に選ばれています。
また、設備投資や運転資金などの内訳を明確にし、返済計画を立てることが成功のカギです。初めての方は、専門家のサポートを受けながら準備を進めると安心でしょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!