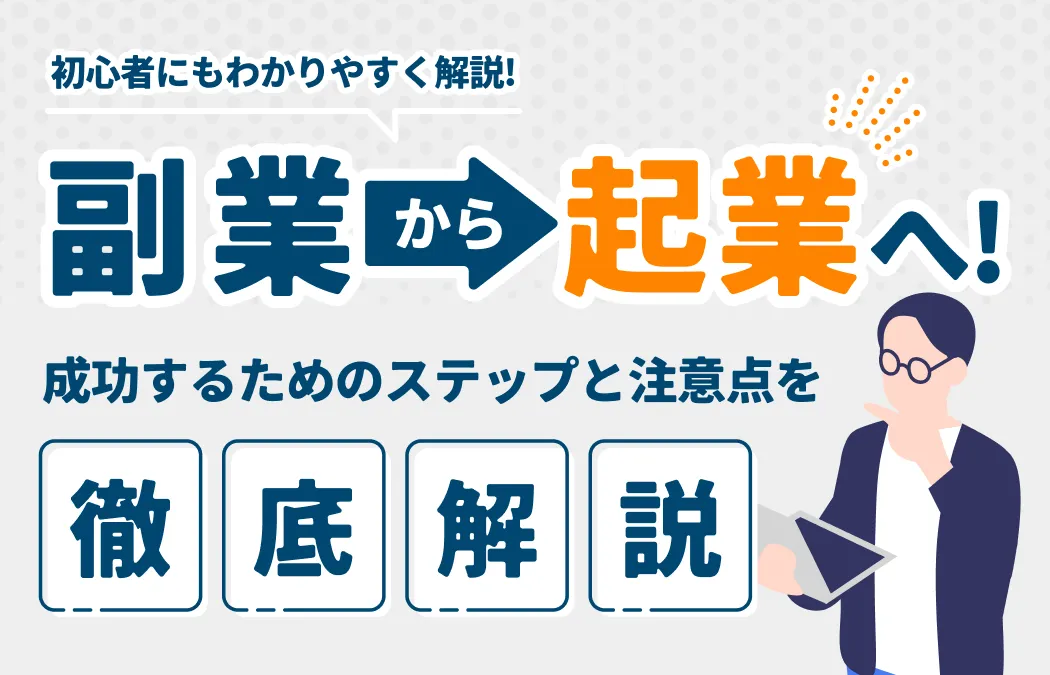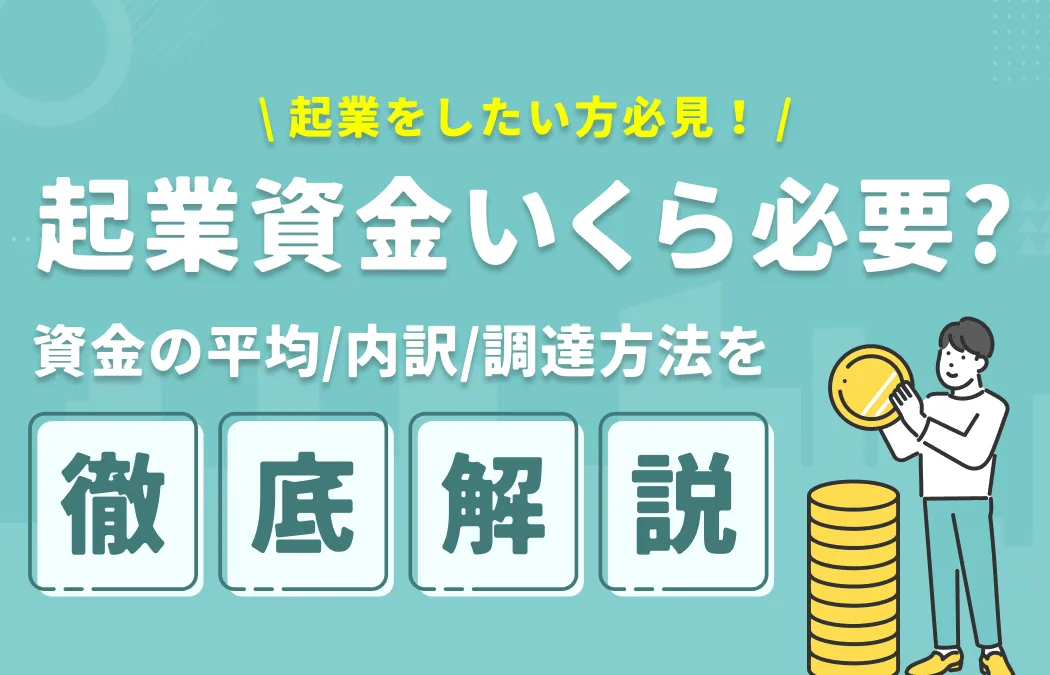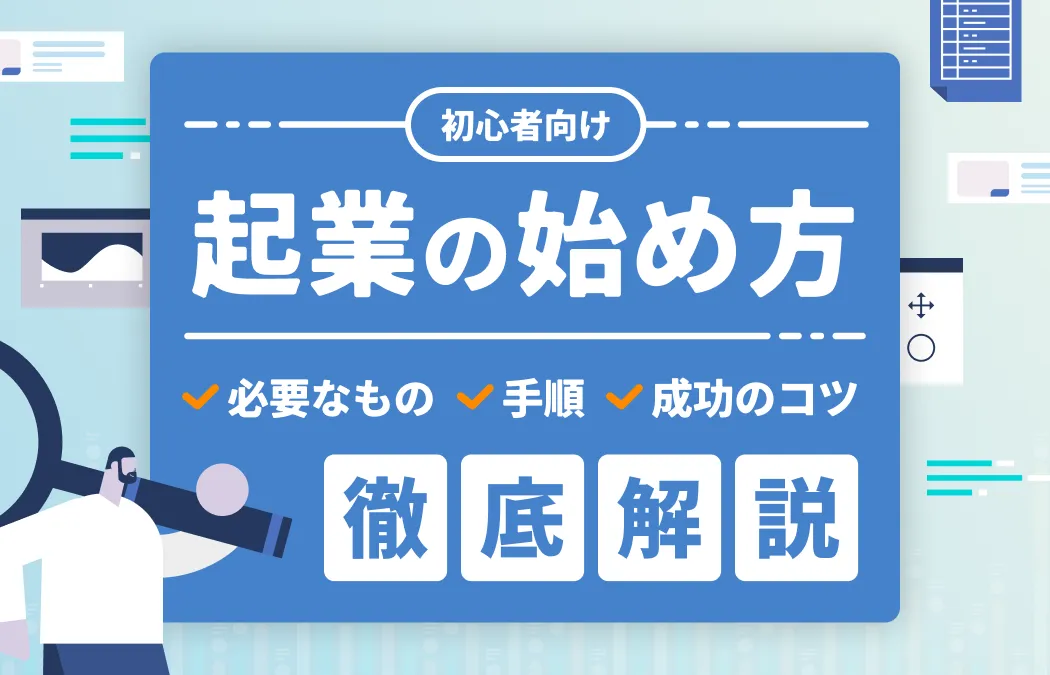「どうやって作るの?」
販売計画とは、売上目標を達成するために、販売する商品やサービスの価格・数量・時期を具体的に定めた行動プランのことです。
事業を軌道に乗せるためには、感覚に頼らず、明確な根拠に基づいて計画を立てることが欠かせません。
しかし、「どこから手をつければいいのかわからない」「数字の立て方が難しい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、販売計画の基本から、実際の立て方、活用するためのポイントまでをわかりやすく解説します。
\開業支援200社超!起業の不安もここで解消/
目次
▼この記事で紹介している商品
販売計画とは?定義・目的
販売計画とは「売上目標を達成するための行動プラン」
販売計画とは、 売上目標を達成するために、商品の販売数量や価格などを具体的に定める計画 のことです。
英語では「セールスプラン(sales plan)」とも呼ばれ、経営の進捗や成果を判断するうえで重要な指標となります。
一般的には、短期(1年以内)と長期(3〜5年)の計画に分け、年間の予算を月間・週間・日間単位に細分化して作成することで、売上達成率の把握や改善策の検討が可能になります。
販売計画の目的は2つ
販売計画には、 経営者自身のためと、社内外の関係者のためという2つの目的 があります。
まず経営者にとっては、企業の成功イメージを客観的に把握し、商品の価格設定や従業員一人あたりの利益などを踏まえた、確実な事業設計を行うための指針となります。
一方、社内外の関係者に向けては、今後の事業展開や将来の見通しを共有する役割を果たします。
これにより従業員は同じ目標に向かって動きやすくなり、取引先や株主からの信頼と賛同を得て、事業の成長を後押しすることが可能です。
販売計画と営業戦略・マーケティングの違い

販売計画は、売上目標を達成するために、具体的な販売数量や価格設定を定める実務的な計画です。
一方、 営業戦略は「どのような顧客層を狙い、どのような営業活動を行うか」といった大枠の方針 を指します。
また、マーケティングは市場調査や広告・PRなどを通じて顧客のニーズを掘り起こす活動であり、販売計画はその成果を数値目標として具体化するものといえます。
販売計画に必須の3つの要素とは?
販売計画には、予算を達成するための具体的な手段を明確に記入しましょう。
まず検討すべきは、「ターゲットの詳細」「金額と数量」「商品の内容」の3点です。数字を記入する前に、これらを丁寧に整理しておくことが重要です。
販売計画の要素1:ターゲットの詳細
販売計画を作成する際は、製品を購入する消費者像(ターゲット)を具体的に設定することが重要です。
性別や年齢、関心事、商品を購入する際に重視するポイントなどを細かく調査 しましょう。
ターゲットを明確にすることで、商品の価格設定や必要な販売数量を決めやすくなります。
ターゲットが曖昧だと商品の強みを見失う
ターゲットが曖昧なまま販売計画を立てると、商品の強みを見失いやすくなります。
また、販促活動においてもターゲットの軸がなければPR方法がぶれやすくなるため、ターゲットは必ず明確に設定しましょう。
販売計画の要素2:金額や数量
次に、商品をいくらで販売し、どれだけの数量を売るかを決めていきます。
製品を販売する際は、 原材料費や人件費などの経費がかかるため、経費と売上のバランスを考慮した価格設定 が重要です。
また、販売数量を誤ると在庫が過剰になり倉庫コストなど余計な費用が発生する可能性があるため、慎重に判断しましょう。
販売計画の要素3:商品・サービスの内容
売上は「購入数 × 金額」で算出されますが、 消費者によってPRすべき商品は異なるため、複数のターゲットに向けて商品内容を決める 必要があります。
例えば、若年層向けのカジュアル商品と中高年向けの高機能商品では、PRポイントや訴求内容が異なり、それぞれに適した商品ラインナップが求められます。
開業当初は商品数が少ないこともありますが、ターゲットを絞り込むにつれて、扱う商品数も増えていくでしょう。
活動計画も重要
販売計画を作成したら、次に活動計画を立てましょう。活動計画とは、 販売計画を実行するための具体的な行動計画書 のことです。
どれだけ優れた販売計画を作成しても、実行方法を明確にした活動計画書がなければ、予算未達のリスクが高まります。
例えば、集客が多い時間帯にSNS広告を強化したり、店舗では試供品配布を行うなど、実行可能な施策を明確にしましょう。
販売計画作成時のポイント①:具体的な金額や数量の算出方法
販売計画を作成する際、販売価格や販売数量を決めることに難しさを感じる方も多いでしょう。
しかし、数値目標を導き出すための計算式を活用すれば、具体的な目安を知ることができます。
販売計画で金額や数量を算出するメリット
販売計画で金額や数量を算出することで、 利益が出始める時期や資金繰りの見通しが立ち、経営判断がしやすくなります 。
いつ頃赤字から黒字に転換するかがわかる
商品には「プロダクトサイクル」と呼ばれる一連の流れがあります。
発売当初は売上よりも広告費が上回ることが多く、初期投資がかさむ時期です。その後、PR効果によって商品知名度が向上し、急速に黒字化して安定期に入ります。
月別の販売計画を立てることで、赤字から黒字に転換する時期を予測しやすくなり、適切な施策のタイミングを見極めることが可能です。
資金の動きが予測できる
経営においては、商品を販売してから黒字化するまでにタイムラグが生じることが少なくありません。
毎月の販売計画を立てることで、売上や経費、入金のタイミングを把握し、資金不足が起こりやすい時期を予測できるようになります。
事業拡大のタイミングを見極める上でも、販売計画は欠かせない重要なツールです。
金額を算出する方法
商品の 価格を決める際は、まずコストや競合他社の価格を調査することが重要 です。
一般的に価格設定には、「コストプラス法」と「マーケットプライス法」2つが用いられます。
コストプラス法
コストプラス法とは、商品の総コストに希望する利益を上乗せして価格を決定する方法です。
利益を確実に確保できる一方で、ターゲットユーザーの予算とかけ離れるリスクがあります。
マーケットプライス法
マーケットプライス法とは、市場が求める価格に合わせて販売価格を設定する方法です。
市場ニーズに合致しやすい反面、営業利益が低くなり、採算が合わなくなる可能性もあります。
数量を算出する方法
商品の 販売数量は、来客数に基づいて設定 します。また、全来客数のうち何割が対象商品を購入するかも予測することが重要です。
来客数が増えれば販売数量も増加しますが、1日の来客数には上限がある点を忘れてはいけません。
業種ごとの特性に合わせた経営指標を参考に、1日の来客数の上限を設定し、それをもとに販売数量を算出しましょう。
売上原価を算出する方法
原価の区分には、 固定費と変動費に分ける方法と、売上原価と販売管理費に分ける方法の2つ があります。
固定費と変動費に分ける方法
まず1つ目は、「固定費」と「変動費」に分ける方法です。
固定費は毎月一定額かかる家賃などを指し、変動費は原材料費や光熱費のように、売上や生産量に応じて変動する費用を指します。
売上原価と販売管理費に分ける方法
もう1つは、「売上原価」と「販売管理費」に分ける方法です。
売上原価とは、売上に直接関わる費用で、小売業なら仕入れや製造費、サービス業なら人件費などが該当します。
一方、販売管理費は売上に間接的に関係する費用で、広告宣伝費や販売員の給与など、営業活動や管理業務にかかる費用を含みます。
販売計画作成時のポイント②:ケース別の作成方法
販売計画の作成ポイントは店舗で取り扱う商品数や、業種によって異なります。
商品・サービスの数が少ないとき
開業間もない事業者は、取り扱う商品やサービスの数が少なく、事業規模も小さい傾向にあります。販売計画の基準となる基本的な計算式は以下の通りです。
売上目標 = 平均商品単価 × 年間販売数
※平均商品単価:取り扱う商品の平均的な販売価格
※年間販売数:1年間に販売する商品やサービスの総数
もし主力商品がある場合は、 主力商品の販売計画とその他商品の販売計画を分けて立てることもおすすめ です。
年間販売数を増やすためには、キャンペーンや広告などの販促活動を効果的に活用しましょう。これにより新規顧客の獲得やリピーターの増加が期待できます。
商品・サービスの数が多いとき
ターゲットが増えると商品も多様化し、単価の異なる商品が増えるため、商品数が少ない頃に使った単純な計算式は適用しにくくなります。
商品数が増えてきた場合の計算式
売上目標 = 1日の来客数 × 客単価 × 年間営業日数
売上達成のポイントは、いかに客単価を上げるか にあります。商品の陳列方法を工夫したり、販促活動を効果的に活用することが重要です。
特売セールなどによる集客は一時的な効果が期待できますが、長期的な売上にはつながりにくいため注意が必要です。
代わりに試供品の配布やSNSを活用したターゲット層へのアプローチなど、注目を集めやすい方法を選びましょう。
店舗販売の場合
飲食店やサービス業など、 店舗を中心に営業している場合は、店舗の面積あたりの年間売上を考慮することが重要 です。
例えば、30坪の店舗と60坪の店舗では集客数の上限が異なるため、販売計画もそれに合わせて立てる必要があります。
店舗販売での計算式
売上目標 = 1坪あたりの年間売上 × 売場面積
なお、1坪あたりの年間売上の目安は、経済産業省のホームページで公開されている各種統計データから確認可能です。データは、多数の企業の経営状況をもとに算出されています。
参考資料:「平成9年商業統計 業態別統計編(小売業)<概況>」 経済産業省
飲食店、理美容店などの場合
飲食店や美容院では、 1日にどれだけのお客様を対応できるかを示す「回転率」が重要な指標 となります。
例えば、10席しかない店舗でも1日に100人の集客があれば、10回転したことになります。回転率が上がれば、それに比例して売上も増加します。
売上目標 = 客単価 × 席数 × 回転率 × 営業日数
ただし、店舗のブランディングによっては、高い回転率を求めないケースもあります。
一般的に、ファストフード店など客単価が低い業態は回転率が高く、美容院のように客単価が高い業態は回転率が低い傾向にあります。自店舗のイメージとターゲットをしっかり分析することが重要です。
実務での販売計画活用事例
販売計画は単なる目標の羅列ではなく、売上拡大・収益改善のための「行動設計図」として実務で活用されてこそ真価を発揮します。
SaaS企業の月次運用例
SaaS企業では、月額収益がビジネスの柱となるため、「新規契約数」「解約率」「顧客単価(ARPU)」などの数値を正確に把握し、計画的に改善する必要があります。
売上は契約数や解約率によって大きく左右されるため、定期的な販売計画と進捗管理は必須 です。
特にサブスクモデルでは、目先の契約だけでなく、顧客の継続率やLTV(顧客生涯価値)を高める戦略が成果に直結します。
月次の販売計画で見るポイント
- 新規獲得数:今月新しく契約してくれる顧客数の目標
- 解約率(Churn):解約してしまう顧客の割合
- 顧客単価(ARPU):顧客1人あたりが払う平均金額
- 売上目標:今月の総売上(MRR:月次定期収益)
- 広告予算・効果:広告費をいくらかけ、どれだけ獲得できたか
💡 販売計画に不慣れな場合は、まず「新規獲得数」と「解約率」の2つに絞ってスタートしましょう。シンプルなKPI(目標数値)から始めて、毎月振り返りと改善を繰り返すことが重要です。
実務での運用フロー例
| 月初:計画の策定 | 月中:進捗確認と調整 | 月末:実績確認と改善点の整理 |
|---|---|---|
|
|
|
D2Cブランドでの年間計画活用
D2Cビジネスでは、年間を通じて売上の波を予測し、在庫やマーケティング施策を最適化することが求められます。
特にセール時期、季節変動、広告予算などが売上に大きく影響するため、「いつ、どの商品を、どのチャネルで、どれだけ売るか」を明確に する年間計画が欠かせません。
計画をもとに、プロモーションのタイミングや在庫調整を行えば、無駄なコストや機会損失を回避できます。
D2Cブランドにおける年間販売計画の構成要素
- 「月別売上目標」から逆算して主力商品の販売数を設定
- 広告予算、プロモーション内容、在庫計画をセットで設計
- ブラックフライデーやクリスマスなど販促時期も計画に含める
- 過去実績と前年比データを元に、現実的かつ戦略的に設計
実務での運用フロー例
| 年初 年間全体の販売計画を立案 |
月初 月間KPIと施策の細分化 |
月中 進捗チェックと改善アクション |
月末 実績の集計と振り返り |
四半期ごと 中間レビューと戦略修正 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
販売計画作成時によくある失敗と対策
販売計画は事業成長の道標ですが、実際には失敗に終わるケースも少なくありません。
多くの失敗は、計画段階の見通しの甘さや、作成後の運用不足に起因しています。
目標が現実離れしていたケース
「前年比200%成長」といった 過度な売上目標を掲げると、現場の士気を削ぎ、結果として達成率が大きく下がる 傾向があります。
非現実的な目標設定は、社内のリソースや市場環境を無視して作成されたケースに多く見られます。
対策としては、過去データや競合分析をもとに、具体的かつ達成可能なKPIを段階的に設定することが重要です。
また、定期的な見直しで目標の調整を図る柔軟性も成功の鍵となります。
運用されずに放置されたケース
販売計画を策定しても、 日々の業務に追われて活用されず、単なる「作成して終わり」の状態になる ことがあります。
計画が現場レベルまで落とし込まれておらず、実行の仕組みが不十分な場合に起こりやすい失敗です。
対策としては、週次や月次で進捗を確認する運用フローの整備が効果的です。
さらに、チーム単位での目標共有や、達成度に応じたインセンティブ設計など、現場を巻き込む工夫も求められます。
まとめ
販売計画は、売上目標を達成するために「誰に・何を・いくらで・どれだけ」売るのかを明確にする、経営に欠かせないツールです。
営業戦略やマーケティング施策と連動させながら、現実的な数値目標と行動計画を立てることで、黒字転換の時期や資金の動きを予測でき、事業の安定と成長を後押しします。
特に開業初期は、「この計画で本当に大丈夫か」「数字に自信が持てない」と不安に感じる方も少なくありません。そうしたときは、プロのサポートを受けることで、確かな根拠をもった計画づくりが可能になります。
販売計画に不安がある方は、「0円創業くん」へお気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください!
【無料】お問い合わせはこちら特徴・料金プランを徹底解説!
【無料】資料ダウンロード

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!