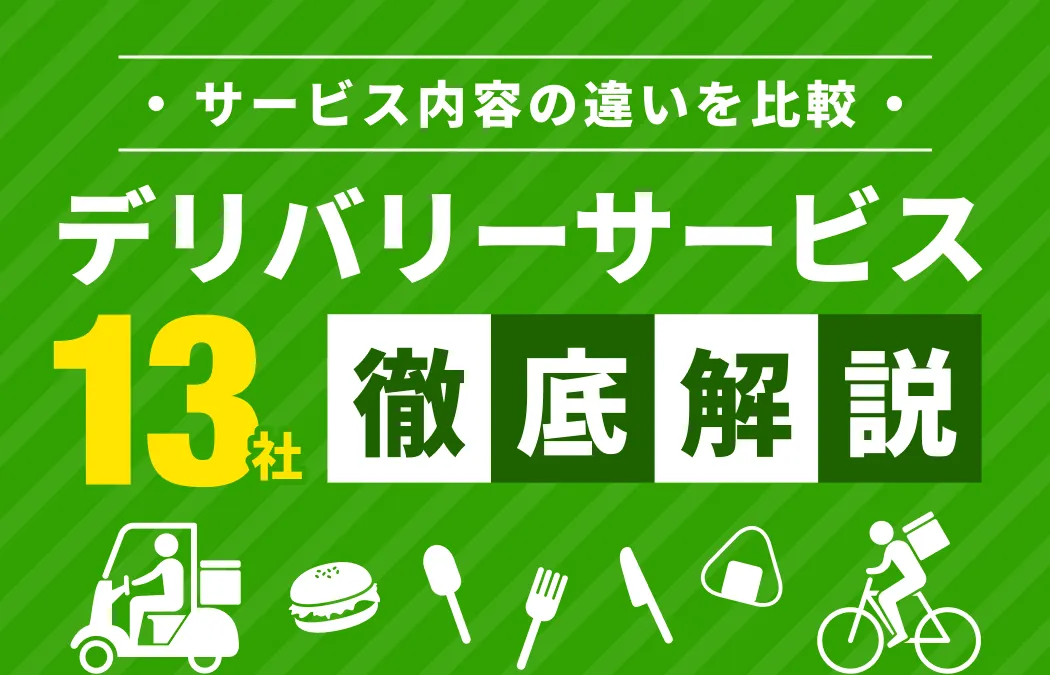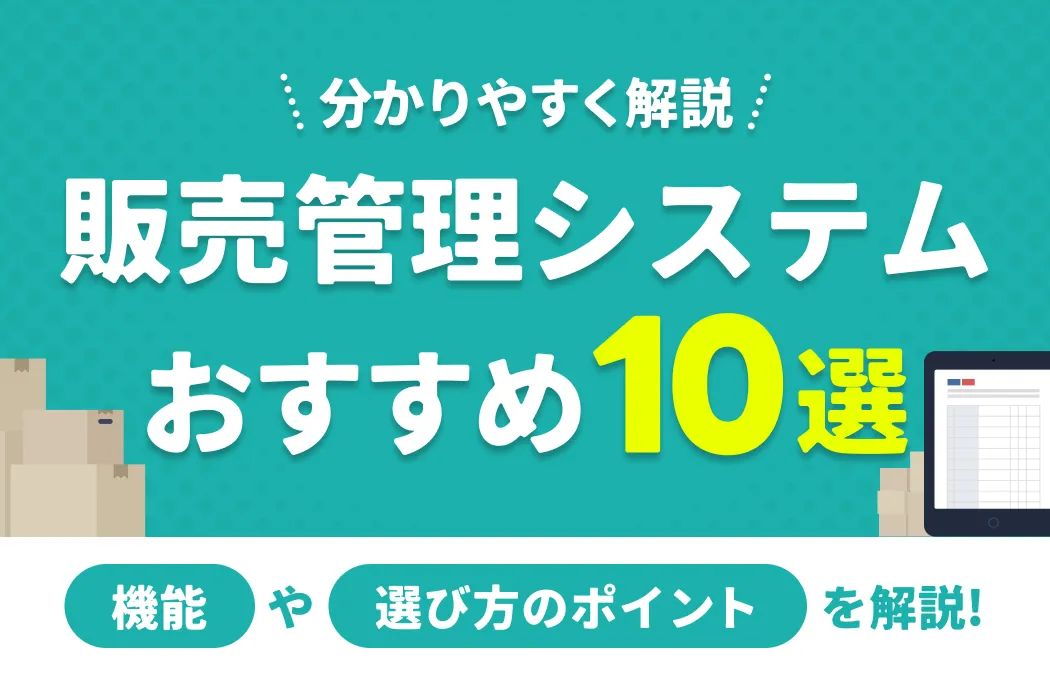「バーコード決済との違いは?」
キャッシュレス決済の普及に伴い、QRコード決済やバーコード決済を利用するユーザーと、対応する店舗も増加しています。
しかし、「レジでの操作はめんどくさい?」「手数料はかかる?」といった疑問を抱く方も多く見られます。
本記事では、QRコード決済の仕組みを解説し、店舗への導入メリット、サービスの選び方を紹介します。
キャッシュレス決済の導入を検討中の事業者は必見です。
目次
▼この記事で紹介している商品
QRコード決済とは?まずは基本を解説
QRコード決済とは?
QRコード決済とは、スマートフォンと専用アプリを使って支払いを行うキャッシュレス決済方法です。
店舗側のバーコードリーダーや顧客側のスマホで決済用のQRコードを読み取ると、代金の支払いが完了 します。
近年では、コンビニや飲食店、小売店など多くの店舗で導入され、生活の中に広く浸透しています。
精算方法は3通り
- 前払い(プリペイド型):あらかじめチャージ(入金)しておいた残高の範囲内で支払いを行う方式
- 即時払い(デビット型):支払い時、即座に銀行口座から引き落とされる決済方式。
- 後払い(ポストペイ型):決済会社が支払いを立て替え、一定期間分の利用額を後からまとめて精算する方式。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 前払い(プリペイド型) | 事前に必要な額だけ入金することで、使いすぎを防げる | 残高が不足すると支払いができない 定期的にチャージが必要なので手間がかかる |
| 即時払い(デビット型) | 口座残高の範囲でのみ利用でき、使いすぎを防止できる | 銀行口座の残高が不足していると利用できない |
| 後払い(ポストペイ型) | 手持ちの現金がなくても支払いが可能 | 支払い能力を超えた利用をしてしまうリスク 分割払いやリボ払いで利子や手数料が発生し、割高になるリスク |

QRコード決済とバーコード決済の違い
QRコード決済とバーコード決済は、 コードの種類に違いがあります 。
- QRコード:縦横2次元で情報を読み取るため、より多くの情報を素早く正確に読み込めるのが特長。
- バーコード:横方向の1次元情報しか読み取れず、読み取りには専用のスキャナーが必要な場合も。
QRコード決済の仕組み
QRコード決済の仕組みは、主に 「QRコード(2次元コード)技術」「インターネット通信技術」「決済システム(決済ゲートウェイ)」 によって成り立っています。
利用者はアプリでQRコードを表示または読み取ることで、決済情報がサーバーに送信され、リアルタイムで処理されます。
通信にはSSLなどの暗号化技術が使われており、安全性も確保されています。
QRコードでの決済方法は2通り
QRコード決済には、「ユーザースキャン方式」「ストアスキャン方式」があります。
ユーザースキャン方式
店舗側が提示したQRコードを、消費者が自分のスマホで読み取って決済を行う方法です。
ユーザースキャン方式は、さらに2種類に分けられます。
店舗側で金額を登録し、タブレット等にQRコードを表示する方式
- 店舗側がPOSレジやタブレット端末に金額を入力すると、決済アプリ用のQRコードが画面上に表示される
- 顧客はQRコードをスマートフォンでスキャンする
- 入力した金額が自動で反映され、決済が処理される
- 後日決済会社から店舗に入金される
紙媒体のQRコードを顧客が読み取り、顧客自身で金額を入力する方式
- 店舗側は、あらかじめ決済用のQRコードを発行しておく
※紙媒体の決済用QRコードには、店舗の決済用アカウントIDや決済サービスのURLスキームが埋め込まれています - 顧客はスマホで決済アプリを起動し、QRコードを読み取って支払金額を入力後、決済実行ボタンを押す
- 入力した金額が自動で決済が処理される
- 店舗スタッフが支払い完了画面を確認
- 後日決済会社から店舗に入金される
△金額の入力間違いや未払いのリスクがあるため注意が必要。
ストアスキャン
顧客のスマホに表示したQRコードを、店舗スタッフが読み取る方式です。
- POSレジやバーコードの読み取り端末に支払金額を入力
- 顧客のスマホで決済アプリを開き、決済用のQRコードを表示
- 店舗側の読み取り端末でQRコードをスキャン
- 決済が処理される
- 後日決済会社から店舗に入金される
QRコード決済が広まった背景
QRコード決済が急速に広まった背景には、 スマートフォンの普及とキャッシュレス推進政策の影響 があります。
特に2019年以降、日本政府によるポイント還元制度や、消費税増税時の負担軽減策が導入され、多キャッシュレス決済そのものが普及し始めました。
その中でQRコード決済は、店舗側も導入コストが低く、現金管理の負担を軽減できる点から導入が進みました。
店舗がQRコード決済を導入するメリット
- 他のキャッシュレス決済と比べて手数料が安い
- レジ業務が効率化できる
- 導入費用を抑えやすい
- 出張販売やイベント出店にも使用可能
- 集客効果や売上アップに繋がりやすい
他のキャッシュレス決済と比べて手数料が安い
QRコード決済は、 クレジットカード決済などと比べて加盟店側の手数料が低く設定されていることが多く 、店舗にとってコスト面でメリットがあります。
特に中小規模の店舗では、カード決済の高い手数料が負担になりがちですが、QRコード決済なら数%程度の手数料で済むケースが一般的です。
一部の事業者はキャンペーンや期間限定で手数料無料プランも提供しており、初期導入のハードルも低くなっています。
レジ業務が効率化できる
QRコード決済は、 現金の受け渡しが不要なため、レジ作業の時間を短縮 できます。
お金を数えたり、お釣りの準備や確認をしたりする必要がなくなり、レジミスも減少。
ピーク時の混雑緩和やスタッフの業務負担の軽減にもつながるため、効率的な店舗運営が可能になります。
導入費用を抑えやすい
QRコード決済は、 専用の端末や機器なしでの運用も可能 なため、導入コストを大幅に抑えることができます。
基本的には、スマートフォンやタブレットがあれば運用可能 です。
特に、ユーザースキャン方式で紙媒体のQRコードを提示する場合は、端末が一切必要ありません。
また、補助金や支援制度を活用することで、さらに負担を軽減することも可能です。出張販売やイベント出店にも使用可能
QRコード決済は、移動販売やイベント出店にも最適です。
特に、紙媒体のQRコードを用いたユーザースキャン方式では、インターネットや電源がない場所でもキャッシュレス対応できて便利 です。
また、QRコードを用いることで現金を扱わずに済むため、不特定多数の人が出入りするイベント会場や、セキュリティ設備のない屋外での出店時も盗難リスクを減らせます。
集客効果や売上アップに繋がりやすい
QRコード決済を導入することで、 キャッシュレス派の消費者を取り込むことができ、集客効果が期待できます 。
特に若年層や訪日外国人観光客は、現金を持ち歩かないことも多く、決済手段の多様化が来店動機になります。
また、各決済サービスが提供するポイント還元やキャンペーンと連動することで、顧客の購買意欲を刺激し、リピート率や客単価の向上にもつながります。
結果として売上アップの可能性が広がります。
QRコード決済がもたらす利用者側のメリット
- 財布を持ち歩かずに済む
- 支払いがスピーディーでスムーズ
- 現金のやり取りが不要で衛生的
- ポイント還元やキャンペーンが豊富
- 支出管理がアプリで簡単にできる
- スキミングのリスクを低減
店舗がQRコード決済を運用するデメリットや注意点
- 初期費用やランニングコストが発生
- 現金化まで時間がかかる
- セキュリティ面のリスク
- 通信トラブルやシステム不具合のリスク
初期費用やランニングコストが発生
QRコード決済は他のキャッシュレス手段に比べて導入がしやすいとはいえ、完全に無料で運用できるわけではありません。
決済端末の購入や、アプリ操作のためのタブレット・Wi-Fi環境の整備など 、初期費用がかかることもあります。
また、利用ごとに発生する決済手数料、月額利用料、場合によっては専用システムの保守費用など、ランニングコストも発生します。
現金化まで時間がかかる
多くのQRコード決済サービスでは、 売上が入金されるまでに数日から1週間程度のタイムラグがあります 。
会計後、即座に振り込まれるわけではないため、日々の資金繰りや現金が必要な業務(仕入れや支払い)に支障をきたす可能性がある点に注意が必要です。
決済代行会社によっては振込手数料がかかる場合もあり、頻繁な入金を希望する店舗にとっては不便に感じることも。
セキュリティ面のリスク
QRコード決済は基本的に安全な設計ですが、不正アクセス等のリスクが完全にゼロではありません。
特に、 偽のQRコードを貼り替えて売上を横領する「QRコード置き換え詐欺」には注意が必要です。
また、店舗が使用する端末がウイルスに感染していると、個人情報が漏洩する危険もあります。
さらに、顧客がQRコードを読み取った後、支払い完了した素振りを見せ、意図的に未払いのまま立ち去ってしまう手口にも注意しましょう。
通信トラブルやシステム不具合のリスク
QRコード決済はインターネット接続が必須のため、 通信障害やサーバーダウンが発生した場合には決済ができなくなるリスク があります。
特にイベント出店や移動販売などでは、通信環境が不安定になりやすく注意が必要です。
また、決済アプリやPOSシステム側のバグ、メンテナンスによって一時的に利用不可となることもあります。
店舗がQRコード決済を導入する際に必要なもの
- スマートフォンまたはタブレット端末
- 安定したインターネット環境
- QRコード決済サービスへの加盟登録
- 専用のQRコードリーダー端末(必要に応じて)
- 従業員への操作マニュアル・トレーニング
スマートフォンまたはタブレット端末
店舗側で決済システムを操作・管理したい場合は、スマートフォンやタブレットが必要です。
決済システムの 専用アプリをインストールすることで、決済の確認、金額入力、売上管理などを行え ます。
安定したインターネット環境
店舗側でデバイスを用意する場合は、管理画面にアクセスするためのインターネット接続が必要です。
通信が不安定だと決済がうまく処理されなくなったり、中断されたりするリスクが高まる ため、常にスムーズな通信ができる環境を整えましょう。
QRコード決済サービスへの加盟登録
店舗でQRコード決済を利用するには、各決済サービス(例:PayPay、楽天ペイ、d払いなど)への加盟申請が必要です。
申請はオンラインで可能で、店舗情報や銀行口座などを登録して審査を受けます 。
導入までの期間は事業者によって異なりますが、数日から1週間程度が一般的です。
専用のQRコードリーダー端末(必要に応じて)
ストアスキャン方式(店舗側がQRコードを読み取る方式)を採用する場合 は、専用のQRコードリーダーが必要です。
既存のPOSレジと連携できるものや、POSシステムから独自して決済できるモデルまで、様々な種類があります。
従業員への操作マニュアル・トレーニング
スムーズにQRコード決済を運用するには、従業員への操作指導も欠かせません。
アプリの使い方、決済の流れ、トラブル時の対応など、最低限の知識を共有しておく ことで、現場での混乱を防ぐことができます。
特に繁忙期や新人スタッフが多い店舗では、簡潔でわかりやすい操作マニュアルを用意しておくことがおすすめです。
店舗がQRコード決済のシステムを選ぶポイント
- セキュリティ水準
- 初期費用やランニングコスト
- 操作性の高さ
- 他システムとの連携
セキュリティ水準
QRコード決済を導入する際、最も重視すべきポイントの一つがセキュリティです。
顧客の個人情報や決済情報を扱うため、 通信の暗号化や不正利用防止機能、ログイン認証などのセキュリティ対策 がしっかりしているか確認しましょう。
国内外の大手決済サービスでは、常に最新のセキュリティ技術を導入している場合が多く安心です。
また、情報漏洩やトラブル発生時のサポート体制の有無も、システム選定時の重要な基準となります。
初期費用やランニングコスト
QRコード決済システムの導入にかかる初期費用と、その後のランニングコストも比較すべきポイントです。
システムによっては、導入費用が無料であったり、端末の提供が無償だったりすることもありますが、毎回の決済ごとに手数料が発生します。
月額使用料や振込手数料も事業者によって異なるため、 店舗の売上規模や業態に応じて、最もコストパフォーマンスの良いサービスを選ぶ ことが経営効率の向上につながります。
操作性の高さ
日常業務で頻繁に利用するシステムだからこそ、操作性の高さは非常に重要です。
スタッフが直感的に使えるインターフェース であること、 決済から確認・キャンセルなどの操作がスムーズにできること が理想です。
また、ベンダーから提供されるマニュアルやサポート体制が整っていれば、教育コストも抑えられます。
トライアル期間があるサービスを活用し、実際の使い勝手を確認すると安心です。
他システムとの連携
会計ソフト、 POSレジ、在庫管理システムなど、他の業務システムと連携できるかどうか も、QRコード決済システム選びの大きなポイントです。
システム連携をうまく活用できれば、手作業によるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
特に売上管理や帳簿作成が自動化できると、日々の業務が大幅に効率化されます。
また、システムの拡張性やAPIの提供有無なども事前にチェックしておきたい項目です。
QRコード決済導入を検討中の方はこちら!
【無料】お問い合わせはこちらQRコード決済の費用相場
初期費用の内訳と相場
QRコード決済の初期費用としては、主に機器の購入費用が発生します。
POSレジと連携する場合や専用タブレット、プリンター、コード読み取り機などの端末は、 1台あたり1万〜5万円程度が相場 です。
ただし、 既存のタブレットを使う場合や、紙媒体のQRコードを使用する場合、決済事業者への申し込みと店舗情報の登録のみで開始でき、費用がかからない場合もあります。
ランニングコストの内訳と相場
QRコード決済のランニングコストの主な内訳は、 月額利用料(0円〜数千円)、システム保守費、レジシステム連携費など です。
中には、中小店舗向けには月額無料プランを提供している決済事業者も多いため、コストを抑えた運用も可能です。
費用が発生する場合でも、1,000円〜3,000円程度が一般的な相場とされています。
決済手数料の相場
決済手数料は、QRコード決済を利用した際に店舗側が支払う手数料です。
一般的な相場は、売上金額の2.0〜3.5%程度 で、事業者や契約内容により異なります。
月間売上が多い店舗では、手数料率が優遇されるプランが用意されている場合もあるため、比較検討が大切です。
入金手数料の相場
QRコード決済で得た売上金を店舗の銀行口座に振り込む際、入金手数料がかかる場合があります。
手数料の相場は100円〜300円程度 で、振込先の金融機関や振込頻度によって異なります。
中には、週1回の入金は無料でも、即時入金を希望する場合は有料となるケースもあります。
決済事業者によっては、特定の銀行に振り込む場合のみ手数料が無料になることもあるため、契約前に条件をよく確認しましょう。
店舗にキャッシュレス決済を導入する2つの方法
決済会社との直接契約
クレジットカード会社(Visa、Mastercard、JCBなど)や電子マネー会社(Suica、WAON、楽天Edyなど)と個別に契約し、決済システムを導入する形態です。
- 決済手数料を比較的低く抑えられる
- 契約内容を自由にカスタマイズできるため、店舗のビジネスモデルに合った条件を交渉可能
- 複数の決済会社と個別に契約する必要があるため、導入の手続きが煩雑になりやすく、管理の手間も増える
決済代行会社経由での契約
決済代行会社(PayPay、Square、STORES決済、AirPAYなど)は、複数の決済手段を一括で導入できるサービスを提供しています。
これを利用することで、店舗は 1つの契約でクレジットカード決済、電子マネー決済、QRコード決済などをまとめて利用できます 。
- 導入手続きが簡単で、管理の手間が大幅に削減できる
- 決済代行会社が設定する決済手数料がやや高めになる
主要なQRコード決済サービスを比較
PayPay
PayPayは、日本国内のQR決済利用率No.1のサービスとして知られており、QRコード決済利用者の64.9%が利用しているというデータもあります。
その人気の秘密は、 加盟店の多さやポイント還元率の高さ にあります。誰でも無料で利用でき、支払い方法も多様です。
近年では、店舗だけでなく、病院や自治体などでも導入事例が増えています。
使える場所の多さによる利便性から主要な決済手段として利用しているユーザーも多く、高い導入効果が期待できるでしょう。
| 運営会社 | PayPay株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%〜2% |
| 決済額の上限 | 50万円/回 ※本人確認を行なっていない場合10万円/回 |
| 支払い方法 | ■銀行口座 ■PayPayカード ■キャリア決済(ソフトバンク、ワイモバイル) ■セブン銀行ATM ■ローソン銀行ATM ■Yahoo!フリマ、Yahoo!オークションの売上金 ■PayPayクレジット |
| 店舗側の決済手数料 | 3.45% |

編集部
対象者の46.3%が、メインで利用しているQRコードとして「PayPay」を挙げたデータもあります。(※)
楽天ペイ
楽天ペイは、楽天グループが提供するQRコード決済サービスです。 支払額に応じて楽天ポイントを貯めたり使ったりできる のが特徴です。
楽天ポイントは、楽天市場、フリマアプリのラクマをはじめ、 全国600万カ所以上の店舗やオンラインショップで利用できます 。
Android版の楽天ペイアプリでは交通系電子マネーの「Suica」の発行もできるようになり、チャージにより楽天ポイントをためることができます。
店舗に導入した場合は、楽天ペイの決済に対応できるだけでなく、カードリーダーの購入でクレジットカードや電子マネーの決済にも対応可能です。
| 運営会社 | 楽天ペイメント株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0%~1.5% |
| 決済額の上限 | 50万円/回 |
| 支払い方法 | ■楽天カード ■銀行口座 ■セブン銀行ATM ■ローソン銀行ATM ■ラクマの売上金 ■楽天ウォレット ■楽天ギフトカード ■楽天Edy |
| 店舗側の決済手数料 | 3.24% |
d払い
d払いは、NTTドコモが提供するQRコード決済サービスです。 ドコモユーザー以外も利用可能 で、決済を行うことでdポイントを貯めたり、使ったりできます。
公共料金の支払いにも対応している点も大きな特徴で、電気代や水道代など、面倒な手続きがスマートフォン一つで完結します。
店舗に導入した場合、d払いとメルカリの共通コードを利用して、フリマアプリ「メルカリ」の決済サービスであるメルペイユーザーの集客にもつなげることができます。
※dカード以外のクレジットカードで支払う場合、本人確認を実施済みであれば50万円/月、本人確認を未実施であれば5万円/月が支払い金額の上限となります。
| 運営会社 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 店舗:0.5% ネット:1.0% |
| 決済額の上限 | ネット決済:100万円/回 dカード決済:dカードの利用限度額 |
| 支払い方法 | ■銀行口座 ■クレジットカード、 ■キャリア決済 ■セブン銀行ATM |
| 店舗側の決済手数料 | 2.6% |
d払いのユーザーメリット
d払いの最大の特徴は支払いに利用することでdポイントがたまる点です。
店舗での利用で200円につき1ポイント、ネットショップでの利用で100円につき1ポイントが貯まります。
また、 dクレジットカードを支払い方法に設定しておくことで、dカードのポイントとd払いのポイントを二重取りが可能 です。
d払いの店舗メリット
店舗にd払いを導入することで、約7,500万人いると言われているdポイントクラブ会員への幅広い集客効果が期待できます。
決済手数料も2.6%と、他社決済サービスよりも低く設定されている ため、ランニングコストを抑えながら運用が可能です。
au PAY
au PAYは、KDDIが提供するQRコード決済サービスで、 au以外のユーザーも利用可能です。支払い額に応じてPontaポイントがたまります 。
KDDIと楽天が提携したことにより使えるお店も増えたうえ、毎月お得なキャンペーンも開催されているので、効率良くポイントを貯められます。
店舗へau PAYを導入することで、2,300万人のau PAY会員やPontaユーザーに対しての集客効果が期待できます。
また、売上金の入金の際の振込手数料はどの金融機関を利用した場合でも0円なので、コストを抑えて継続して利用しやすいサービスです。
| 運営会社 | auペイメント株式会社 |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5% ※au スマートパスプレミアム会員:1.5% |
| 決済額の上限 | 30万円/回、50万円/日、200万円/月 |
| 支払い方法 | ■銀行口座 ■au PAYカード ■クレジットカード ■auかんたん決済 ■Pontaポイント ■auじぶん銀行 ■セブン銀行ATM ■ローソン銀行ATM ■au PAYギフトカード ■au PAY スマートローン(au WALLET スマートローン) ■au PAY プリペイドカード |
| 店舗側の決済手数料 | 2.6% |
au PAYのユーザーメリット
au PAYを決済に使うだけで、 通常200円につき1ポイント、auスマートパスプレミアム会員であれば200円につき3ポイント 、Pontaポイントをためることができます。
また、チャージ方法も競合サービスの中で群を抜いて豊富なので、利便性の高さも魅力です。
au PAYの店舗メリット
au PAYは、 初期費用や入金手数料が無料で決済手数料も2.6% と、費用負担を極力抑えた導入・運用が可能です。
他社サービスでは、条件付きや特定の金融機関のみ入金手数料が無料になる場合もありますが、au PAYはどの金融機関を振込先に指定しても無料で利用できます。
さらに、au PAYを導入することで中国の2大決済サービスである「Alipay(アリペイ)」と「WeChat Pay」が利用でき、インバウンド対策にも役立ちます。
≫au PAY(auペイ)とは?EC・店舗事業者向けのメリット・手数料・導入方法をわかりやすく解説
メルペイ
メルペイは、フリマアプリ「メルカリ」の子会社である株式会社メルペイが提供しているQRコード決済サービスです。
最大の特徴は、 メルカリでの売上金をメルペイを通して決済に利用できる 点で、売上金以外にも銀行口座からのチャージも可能です。
メルカリポイントとの連携で、貯まったポイントを1ポイント1円として使えるので、フリマでの売買がそのまま日常の買い物につながります。
d払いと連携しているため、店舗にメルペイを導入することで、d払いユーザーの集客にも繋がる でしょう。
| 運営会社 | 株式会社メルペイ |
|---|---|
| ポイント還元率 | 1.0% ※メルペイのあと払い(メルカードを含む)の利用でポイントの還元対象となる |
| 決済額の上限 | 銀行口座登録または本人確認済:100万円/回・日、300万円/月 上記以外:10万円/回・日・月 ※メルペイスマート払いの場合は任意で決めた上限金額の範囲 |
| 支払い方法 | ■銀行口座 ■メルカリの売上金 ■セブン銀行ATM(チャージ) ■メルペイスマート払い(後払い) |
| 店舗側の決済手数料 | 2.6% |
FamiPay(ファミペイ)
FamiPay(ファミペイ)は、ファミペイアプリで利用できるバーコード決済サービスで、 実店舗だけでなくオンライン店舗にも導入可能 です。
ファミリーマートやFamiPay加盟店での決済に利用するとFamiPayボーナスがたまり、さらにdポイント、楽天ポイント、Tポイントのいずれかも二重取りできます。
実店舗であれば店舗のPOSやタブレットでお客様のバーコードを読み取り決済が可能で、オンラインの店舗は決済代行プラットホームを利用して導入ができます。
| 運営会社 | 株式会社ファミリーマート |
|---|---|
| ポイント還元率 | 0.5%~1.0% |
| 決済額の上限 | 30万円/回 |
| 支払い方法 | ■銀行口座 ■クレジットカード ■店頭での現金チャージ ■Apple Pay ■FamiPayギフトコード |
| 店舗側の決済手数料 | 2.94% |
QRコード決済に関するよくある質問
A
QRコード決済の仕組みは、主に「QRコード(2次元コード)技術」と「インターネット通信技術」、そして「決済システム(決済ゲートウェイ)」によって成り立っています。
A
一部の利用者から「QRコード決済はめんどくさい」と感じられる理由には、アプリの起動や操作の手間が挙げられます。支払い時にスマホを取り出し、アプリを開き、QRコードを表示またはスキャンするステップが必要で、特に急いでいる場面では不便と感じられることもあります。
まとめ
QRコード決済は、スマートフォンを活用して簡単・スピーディーに支払いができる、現代のライフスタイルに合ったキャッシュレス決済手段です。
店舗側にとっては、導入コストが低く、レジ業務の効率化や売上アップにつながるなど、多くのメリットがあります。
ただし、セキュリティ対策や通信環境の整備、コスト面の見極めといった注意点もあるため、導入にあたっては自店舗に合ったシステムを慎重に選ぶことが重要です。
今後も実店舗とECをつなぐハイブリッドな決済手段として、QRコード決済はますます重要な存在になるでしょう。
小規模店舗から大規模チェーンまで、誰でも手軽に始められるこの決済手段を、ビジネスの強力な武器として活用してみてはいかがでしょうか。
QRコード決済導入を検討中の方はこちら!
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!