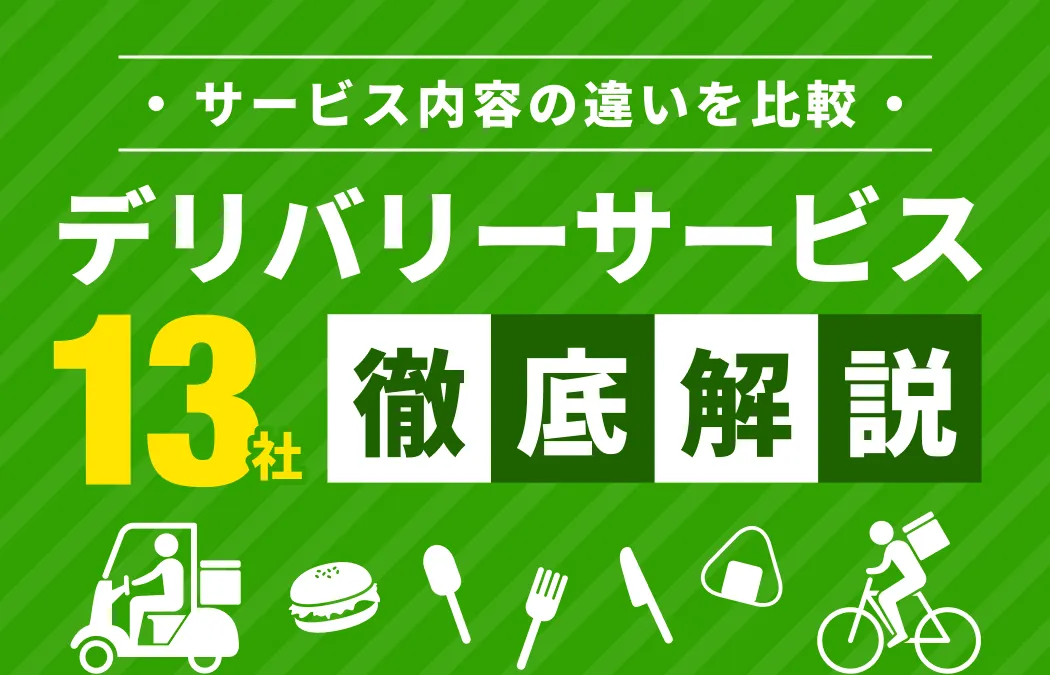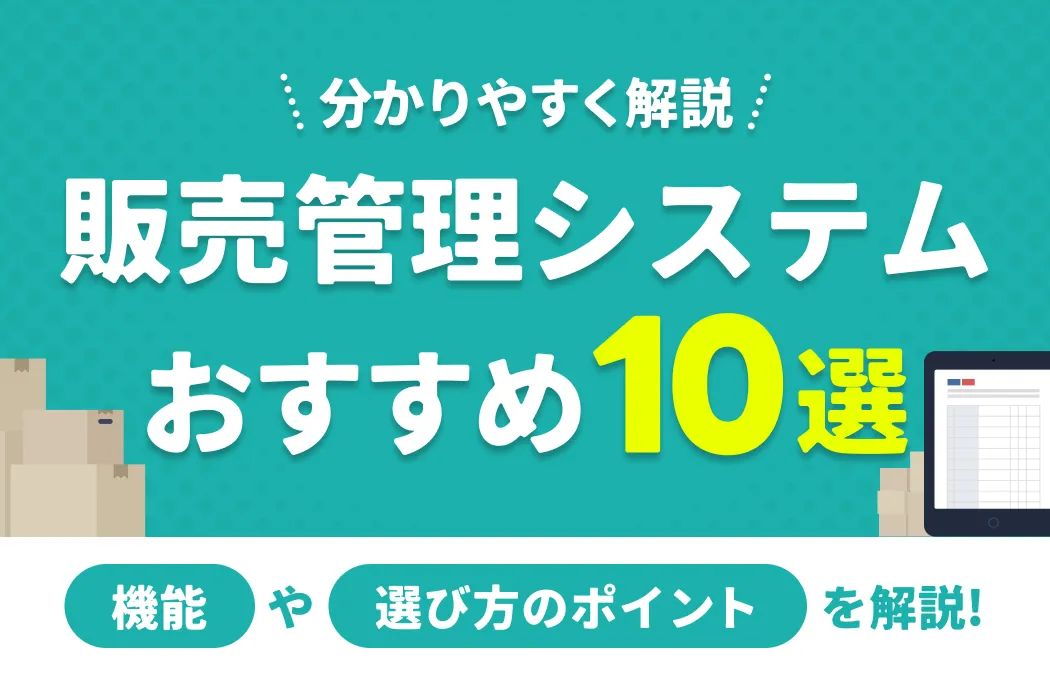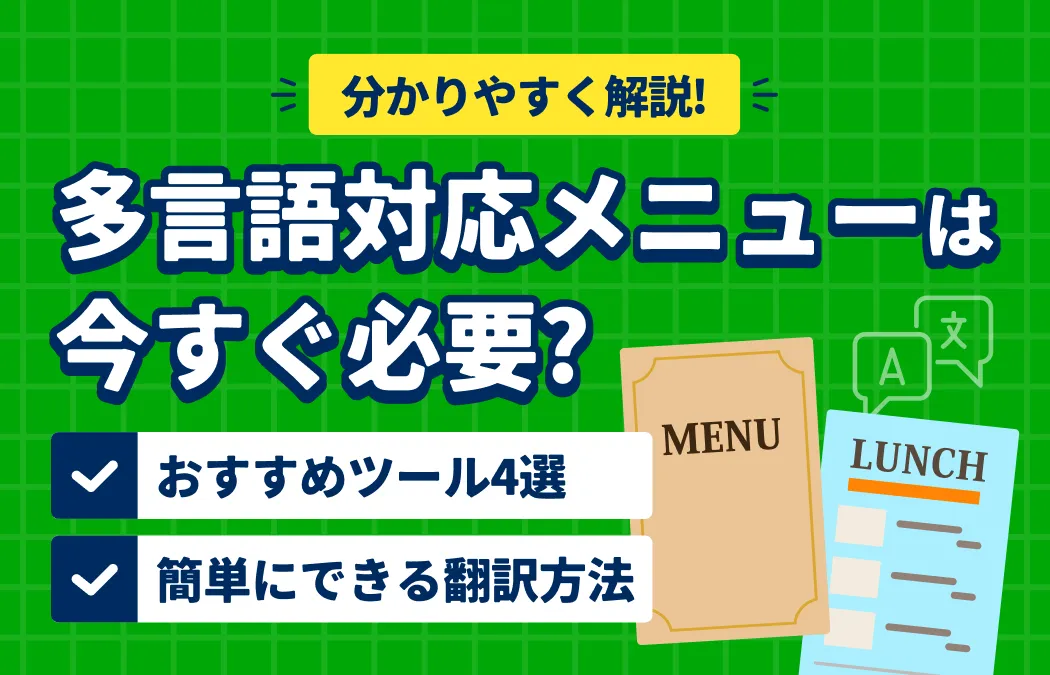「導入に必要なものは?」
電子マネーは、現金を使わずに商品やサービスの代金を支払えるキャッシュレス決済の一種です。
しかし、「費用の内訳や目安は?」「どんな種類がある?」など疑問も多いはずです。
本記事では、電子マネーの仕組みや導入メリットとデメリット、運用に置いて知っておきたいポイントを解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
電子マネー決済とは
電子マネー決済とは
電子マネー決済とは、現金を使わずに商品やサービスの代金を支払う方法の一つです。 事前にチャージされたデジタル形式の残高で決済を行います 。
利用者は専用のカードやスマートフォンアプリを通じて支払いを行い、レジでの支払い時間の短縮やキャッシュレスの利便性を実感できます。
ポイント還元などの特典があることも魅力の一つです。
電子マネー決済の仕組み
電子マネー決済の基本的な仕組みは、利用者が 事前に電子マネー残高をチャージし、そのチャージされた金額から商品・サービスの代金が差し引かれる という流れです。
支払い時には、ICカードやスマートフォンを専用の読み取り端末にかざすだけで決済が完了します。
決済情報は決済センターに送信され、利用者の残高が確認されてから支払いが認証されます。利用後は残高が即時反映され、リアルタイムでの管理が可能です。
店舗には後日、一定期間分の売上高がまとめて入金されます。
電子マネー決済の代金が入金されるまでの流れ
店舗側が電子マネーで会計を処理した場合、決済情報は決済代行業者や電子マネー発行会社を通じて処理されます。
あらかじめ締め日が決まっており、 日ごとや月ごとにまとめて売上が精算され、指定の口座に振り込まれます 。
振込日は契約内容により異なり、数日から数週間のタイムラグが発生することもあります。
このため、資金繰りを考慮して導入する必要がありますが、現金管理の手間が省けるというメリットもあります。
電子マネー決済の導入が進んでいる背景
電子マネー決済の導入が進んでいる背景には、 消費者のキャッシュレス志向の高まりと、店舗側の業務効率化のニーズ があります。
また、新型コロナウイルスの影響で非接触型の支払い方法が注目されたことも、普及を後押ししました。
政府も「キャッシュレス推進」を掲げており、導入費用の補助や税制優遇などの支援策を実施しています。
さらに、訪日外国人観光客の増加も、国際的な決済手段への対応として電子マネー導入の一因となっています。

電子マネーの種類
交通系電子マネー|Suica・PASMOなど
交通系電子マネーは、もともと 電車やバスなどの公共交通機関の運賃支払いを目的に開発された電子マネー です。
代表的なものに「Suica(スイカ)」や「PASMO(パスモ)」があり、全国の幅広い地域で利用可能です。
ICカードやスマートフォンを改札でかざすだけでスムーズに通過できるほか、近年ではコンビニや飲食店などの一般店舗で決済をする際にも使えるようになり、利便性が大きく向上しています。
流通系電子マネー|WAON・nanacoなど
流通系電子マネーは、 スーパーやコンビニなどの小売店を運営する企業が独自に提供している電子マネー です。
代表例には、イオングループの「WAON(ワオン)」やセブン&アイグループの「nanaco(ナナコ)」があります。
主に、特定の系列店で買い物をする際にチャージした金額で支払いでき、使用金額に応じてポイントが貯まる仕組みになっています。
クレジットカード系電子マネー|ID・QUICPayなど
クレジットカード系電子マネーは、 クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードを紐づけて使う電子マネー です。
代表的なサービスに「ID(アイディ)」や「QUICPay(クイックペイ)」があります。
プリペイド型・デビット型・ポストペイ型を柔軟に選択できる点が魅力です。
特に、ポストペイ型であれば事前のチャージが不要で、利用額は後日クレジットカードの請求と一緒に引き落とされるため、残高を気にせず使える利便性があります。
- プリペイド型(前払い):事前にチャージした残高で支払う。
- デビット型(即時払い):決済と同時に指定口座から利用分の代金が引き落とされる。
- ポストペイ型(後払い):電子マネーに紐づけたクレジットカードで決済処理され、後日まとめて精算。
電子マネー決済のコスト内訳と相場
初期費用の内訳と相場
電子マネー決済の初期費用には、 決済端末の購入費用、設置工事費、契約事務手数料など が含まれます。
端末価格は一般的に2万円〜5万円程度で、非接触型IC対応モデルや複数決済に対応する端末ほど高価になります。
設置費や設定費用を含めると、初期費用はトータルで3万〜10万円程度が相場です。
決済代行会社によっては初期費用が無料のキャンペーンを実施している場合もあるため、複数社の比較検討が重要です。
ランニングコストの内訳と相場
電子マネー決済にかかるランニングコストには、 端末の保守費用、システム利用料など があります。
端末の保守契約費用は、月額1,000〜3,000円程度が目安です。
また、一部の決済代行業者では、システム利用料として月額固定費(1,000円〜5,000円程度)を設定している場合もあります。
決済手数料の相場
決済手数料とは、売上の一部を決済代行会社に支払う手数料で、電子マネー決済の場合はおおむね 決済金額の3%〜4%が相場 とされています。
例えば、1,000円の取引があった場合、30円〜40円が手数料として差し引かれます。
ただし、この手数料率は導入する決済ブランドや業種、取引額などによって変動することがあります。
また、決済代行会社で複数の決済手段を一括導入する場合は、手数料率が統一されるケースもあります。
入金手数料の相場
入金手数料は、売上金を加盟店の銀行口座へ振り込む際に発生する費用です。
多くの決済代行業者では 1回あたりの振込手数料が200円〜500円程度 で設定されており、振込回数や銀行によって異なります。
月に数回の振込を希望する場合や、売上が少額でも定期的に振込がある場合は、この手数料が負担になることもあります。
ただし、一部の業者では一定金額以上の売上で無料になるサービスもあるため、事前に条件を確認することが大切です。
店舗に電子マネーを導入するメリット
レジ業務の効率化
電子マネー決済は、カードやスマートフォンをかざすだけで支払いが完了するため、レジでの処理時間を大幅に短縮できます。
お釣りのやり取りや金額入力の必要がなく、スタッフの負担が軽減 されるので、ピーク時のレジ待ち時間の短縮にもつながります。
また、レジ締め作業も簡素化され、業務の正確性とスピードが向上します。

編集部
少人数で運営する店舗や混雑しやすい飲食店などでは、特にその効果を実感しやすいでしょう。
集客の促進と売上拡大
電子マネー対応をすることで、 キャッシュレス派の顧客や訪日外国人など、より幅広い層を取り込むことが可能 になります。
また、ポイント還元キャンペーンやキャッシュレス決済の利便性を求める顧客にとって魅力的な店舗となり、リピーターの増加にも貢献します。
特に若年層を中心に現金を持ち歩かない傾向が強まっていることから、電子マネーを導入することで機会損失を防ぎ、売上拡大を目指せます。
ミスや不正の防止
現金を扱わない電子マネー決済では、 釣銭の渡し間違いやレジ金の過不足といったミスが起こりにくく、ヒューマンエラーを防止 できます。
また、取引履歴が自動で記録されるため、従業員による不正防止にもつながります。
さらに、精算時のチェック作業も簡略化できるため、店舗管理の精度も向上します。
現金管理の手間を軽減
電子マネーを導入することで、 現金の受け渡しや釣銭準備、売上金の入金業務など、現金に関する煩雑な作業を大幅に削減 できます。
現金を扱う機会が減ることで、防犯面でも安心感が高まり、店舗運営の効率性と安全性が向上します。
特に少人数で店舗を運営している場合、他のメイン業務に集中しやすくなるという利点もあります。
電子マネー決済導入の方法
電子マネーの導入方法は、基本的に「決済会社との直接契約」または「決済代行会社経由での契約」のいずれかです。
1種類の電子マネーを導入する場合
特定の電子マネー1種類のみを導入する場合は、 該当する電子マネー発行会社に直接申し込み、または決済代行業者に申し込む 形のどちらかになります。
比較的シンプルな手続きで導入可能で、必要な端末も限定的です。導入費用も比較的安価で済むことが多く、初めて電子マネーを導入する小規模店舗に適しています 。
ただし、複数のブランドには対応できないため、特定顧客層にしかアプローチできないという制約もあります。
複数の電子マネーに対応したい場合
複数の電子マネーに対応したい場合は、 決済代行会社を通じて一括契約を行うのが一般的 です。
この場合、複数ブランド対応の統合型端末が必要となり、初期費用はやや高くなりますが、より多くの顧客のニーズに応えることができます。
代行会社が各電子マネー会社との調整を代行してくれるため、手続きが一元化されて導入もスムーズです。今後の拡張性を考慮するなら、複数対応が有利です。
他のキャッシュレス決済と合わせて導入する場合
電子マネーだけでなく、クレジットカード、QRコード決済なども一緒に導入したい場合は、 総合キャッシュレス対応のPOSレジやマルチ決済端末の導入がおすすめ です。
このタイプは幅広い決済手段に対応できるため、顧客の利便性が大幅に向上し、機会損失の削減にもつながります。
決済代行会社によっては、初期費用や月額料金を抑えたパッケージプランもあるため、コストを抑えながら多機能化が可能です。

電子マネー決済端末の種類
据え置きタイプ
据え置きタイプの電子マネー決済端末は、カウンターやレジ横に固定して使用するタイプです。
ディスプレイやICカードリーダーが一体化しており、安定した通信環境と操作性が特徴 です。
コンビニや飲食店、スーパーなど、レジに一定のスペースがある中〜大規模店舗に適しています。
- 安定性が高く、決済処理が高速
- 1台で複数の決済手段に対応できるモデルも多い
- 設置工事や電源の確保が必要な場合もある
- 導入までに一定の準備や期間が必要
モバイルタイプ
モバイルタイプは、小型かつ軽量で持ち運びが可能な決済端末です。
BluetoothやWi-Fi、モバイル回線を利用して接続し、スマートフォンやタブレットと連携して使う のが一般的です。
特に、スペースが限られている個人店や、移動販売やイベント出店など、場所を選ばず決済を行いたい事業者に最適です。- 初期費用が比較的安価
- アプリによっては売上管理機能も利用可能
- 据え置き型に比べると処理速度や安定性で劣る場合がある
マルチタイプ
マルチタイプ端末は、電子マネー、クレジットカード、QRコード決済など 複数の決済手段に対応したオールインワン型の端末 です。
多機能型POSレジと連携することで、在庫管理や売上分析との一元管理も可能となり、業務の効率化が図れます。
- 1台であらゆる決済方法に対応でき、多様なニーズに応えられる
- 中長期的な運営を考慮すれば高いコストパフォーマンスを発揮
- 初期導入費やランニングコストは高め
電子マネー決済端末を選ぶポイント
- 複数の決済方法で利用可能か
- 入金までの日数
- 操作のしやすさ
- 店舗に合った形態か
複数の決済方法で利用可能か
複数の決済手段に対応することで、幅広い顧客に対応でき、機会損失を防ぐ ことができます。
顧客のニーズが多様化する中で、1台で多くの決済方法を処理できる端末は、集客力と利便性の両面で大きな強みになります。
ただし、対応の幅が広いほど高いスペックの専用機器が必要となるため、その分初期費用も高くなります。
集客効果の上がり幅とコストのバランスを考慮しながら、費用対効果を重視して検討しましょう。
入金までの日数
売上が店舗の口座に入金されるまでの日数も重要なポイントです。業者によって、翌営業日入金のケースもあれば、週1回や月2回など間隔がある場合もあります。
入金のタイミングが遅いと、資金繰りに影響を及ぼす可能性がある ため、できるだけ早期入金に対応している業者や、手数料とのバランスを見ながら選ぶことが大切です。
また、入金スケジュールは契約内容によっても異なるため、事前の確認が不可欠です。
操作のしやすさ
端末の操作性も、選定における大きな要素です。特にアルバイトやパートが多い店舗では、誰でも簡単に使いこなせる設計が重要です。
タッチパネルのレスポンスの良さや表示の分かりやすさ、操作メニューのシンプルさ など、日々使用する店舗スタッフがストレスなく扱えるかを確認しましょう。
デモ機を触ってみる、あるいは利用中の他店舗の評判を確認することで、実際の使い勝手を把握することが可能です。
店舗に合った形態か
電子マネー端末の形態(据え置き型・モバイル型・マルチ型)は、店舗の業態や規模によって最適なものが異なります。
- スペースが確保できる中規模店舗:据え置き型
- 移動販売やイベント出店が多い場合:モバイル型が便利
- 業務の一元管理を重視する場合:POSレジ連携可能なマルチタイプ
自店の業務フローにフィットする形態を選ぶことで、導入効果を最大限に引き出せます。
キャッシュレスの導線相談はこちら!
【無料】お問い合わせ電子マネー決済を導入する手順
-
STEP.1
導入サービスの検討
まずはどの電子マネー決済を導入するかを検討します。
店舗の顧客層や業種、利用されやすい決済手段を分析し、自店に合ったものを見極める ことが大切です。
また、費用、対応端末、入金スケジュールなどの条件を比較することで、最適なサービス選びができます。
-
STEP.2
決済代行会社の選定
決済代行会社は、複数の決済ブランドと加盟店との間を仲介し、契約手続きや決済処理、入金管理などを一括して担います。
選定の際は、 手数料率、サポート体制、入金スピード、対応端末の種類などを総合的に比較検討 しましょう。
-
STEP.3
契約
契約時には、店舗情報、銀行口座情報、営業許可証のコピーなどが必要となる場合があります。
契約内容には、 決済手数料や入金条件、端末の保守体制などが記載されているため、内容をしっかり確認 しましょう。
特に、解約時の条件や契約期間の縛りがあるかも確認しておくことが重要です。不明点がある場合は事前に質問しておくと安心です。
-
STEP.4
決済端末の導入
契約が完了したら、決済端末の設置と設定に進みます。
据え置き型の場合は設置工事や電源確保が必要なこともあり、導入スケジュールに余裕を持って対応しましょう。モバイル型や簡易型の端末は、比較的すぐに使える状態にできます。
導入後には端末の使い方やトラブル対応についてスタッフへの研修を行う と、現場でのスムーズな運用が可能になります。
顧客が電子マネー決済を利用するメリット
- 現金を持ち歩かずに済み、支払いがスピーディー
- ポイントが貯められてお得
- 審査がいらず、手軽に利用できる
- 前払い型なら使いすぎの心配がない
電子マネー決済に関するよくある質問
A
はい、電子マネー決済の導入にあたっては、国や自治体が実施している補助金・助成金を活用できる場合があります。
特に中小企業や個人事業主を対象とした「キャッシュレス導入支援事業」では、端末の購入費用や決済手数料の一部が補助される制度があります。
補助金の対象となる条件や申請期間は地域や年度によって異なるため、商工会議所や公式サイトで最新情報を確認することが重要です。
A
個人経営の飲食店や小売店には、手軽に導入できる「モバイル型」や「小型マルチ決済端末」がおすすめです。
A
電子マネー決済を導入する際には、手数料や入金タイミング、契約条件をよく確認することが大切です。また、契約期間の縛りや解約時のペナルティの有無も要チェックです。さらに、スタッフへの操作指導やトラブル対応の準備も忘れずに行いましょう。
まとめ
電子マネー決済の導入は、レジ業務の効率化や売上拡大、顧客満足度の向上といった多くのメリットをもたらします。
初期費用やランニングコスト、決済手数料、入金サイクルなど、コスト面も事前にしっかり確認しておくことで、スムーズな運用が可能です。
また、近年は政府によるキャッシュレス推進政策や補助金制度も整備されており、個人店や中小企業でも導入しやすい環境が整っています。
自店に最適な決済手段を見極め、操作性やサポート体制も含めた総合的な視点で導入を進めることが、店舗の成長と顧客満足につながるでしょう。
キャッシュレスの導線相談はこちら!
【無料】お問い合わせ

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!