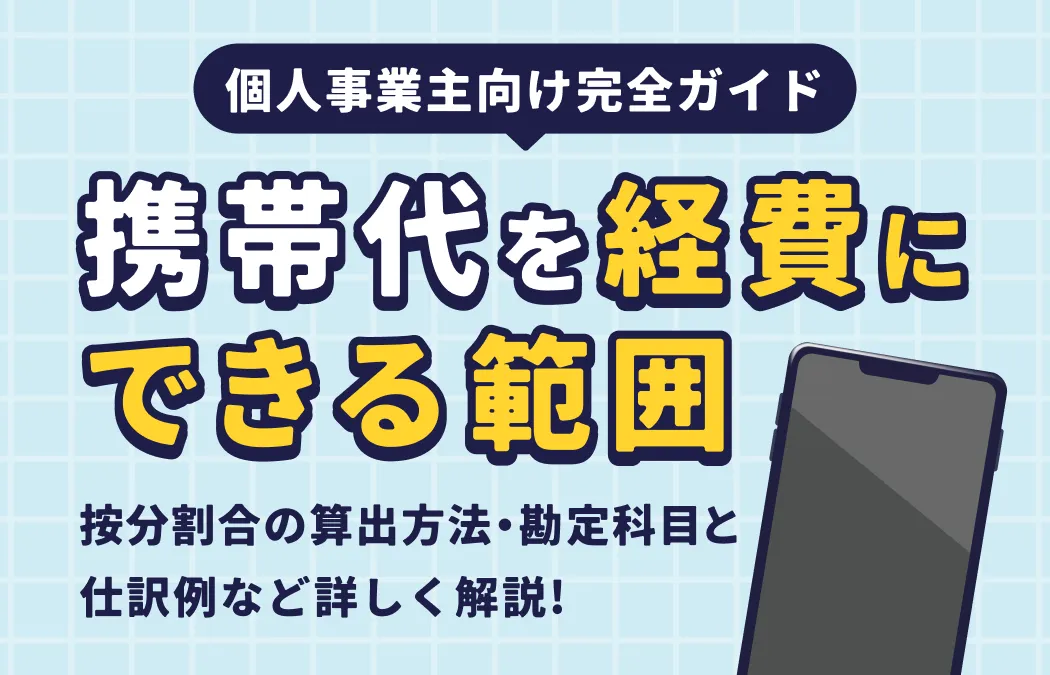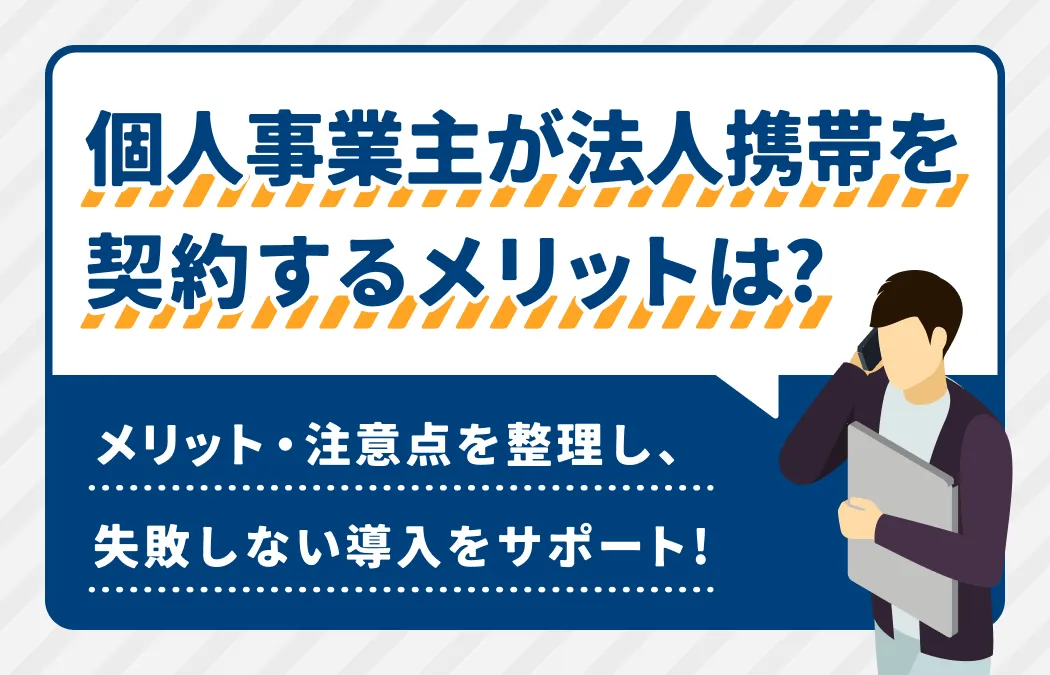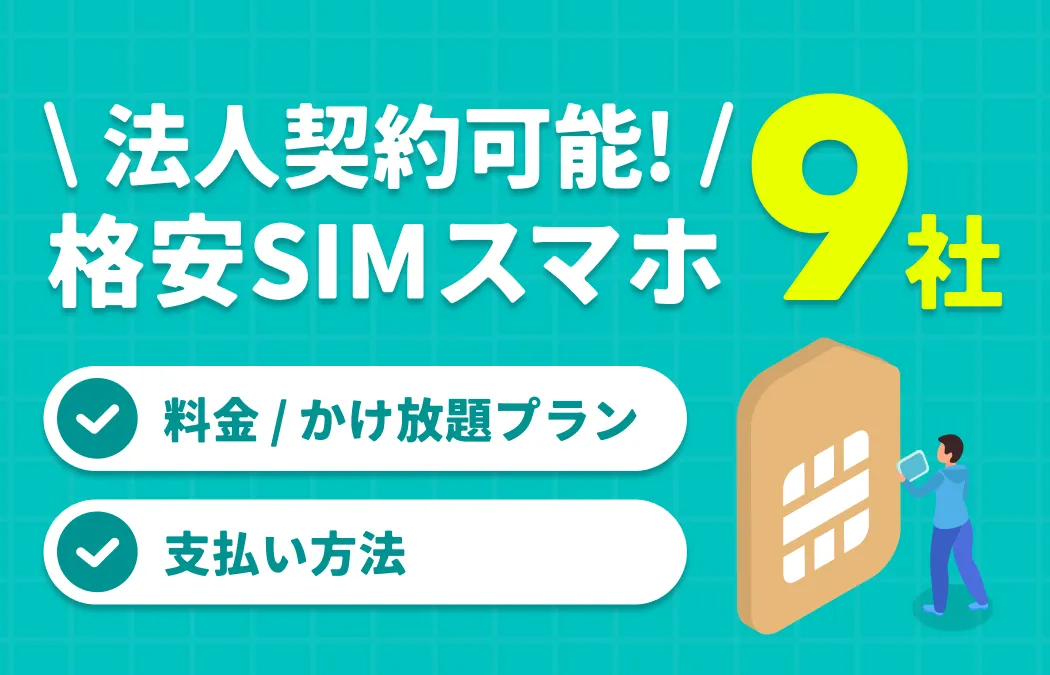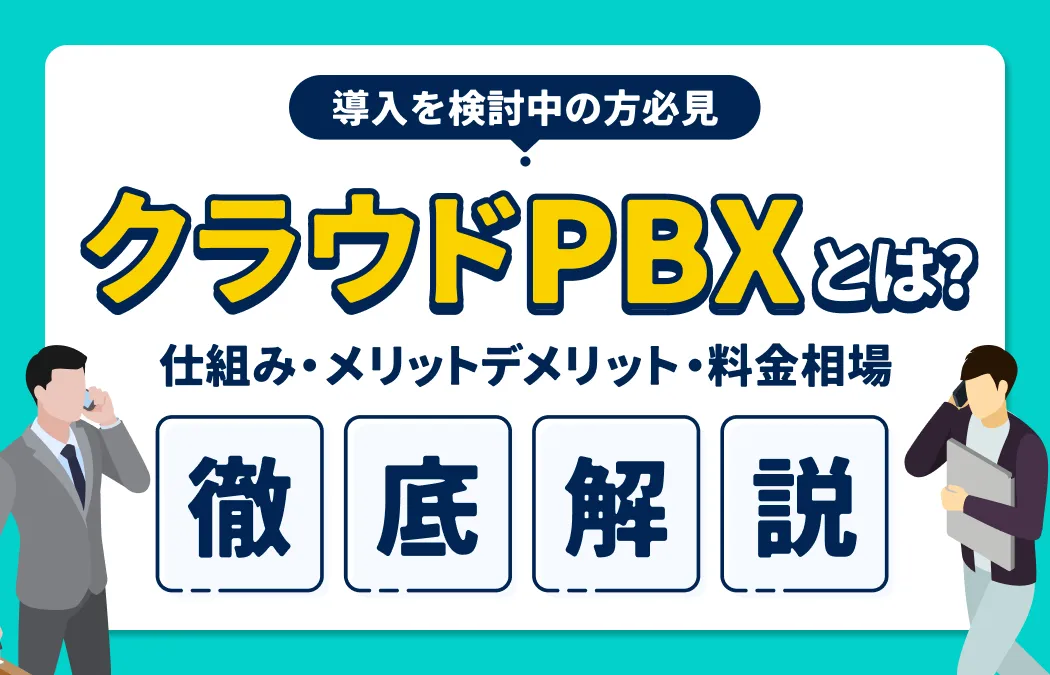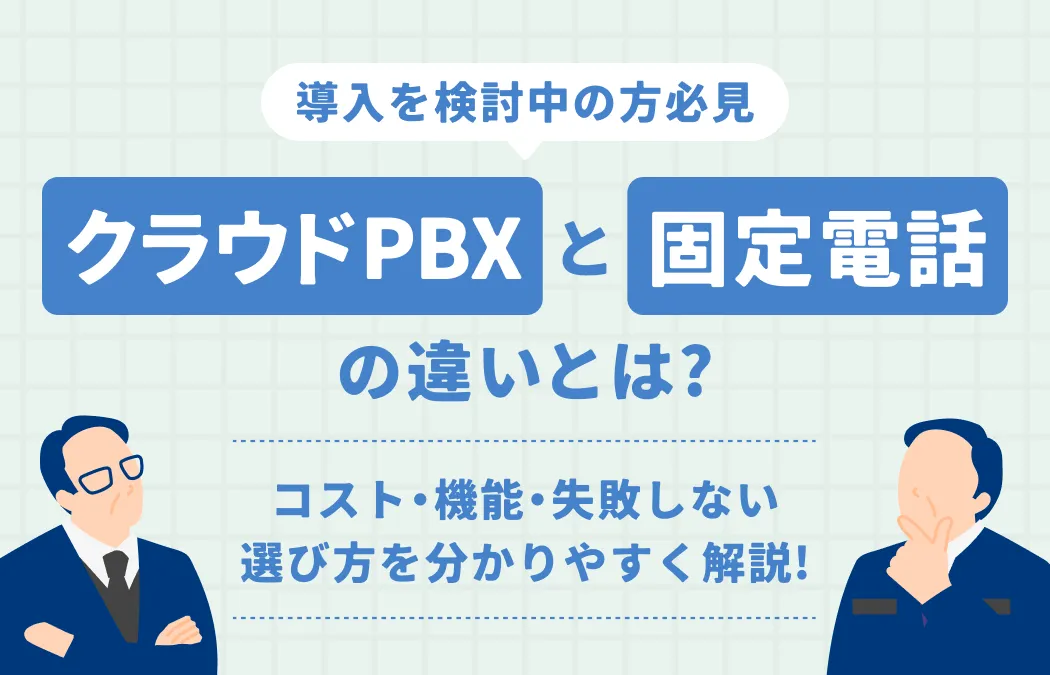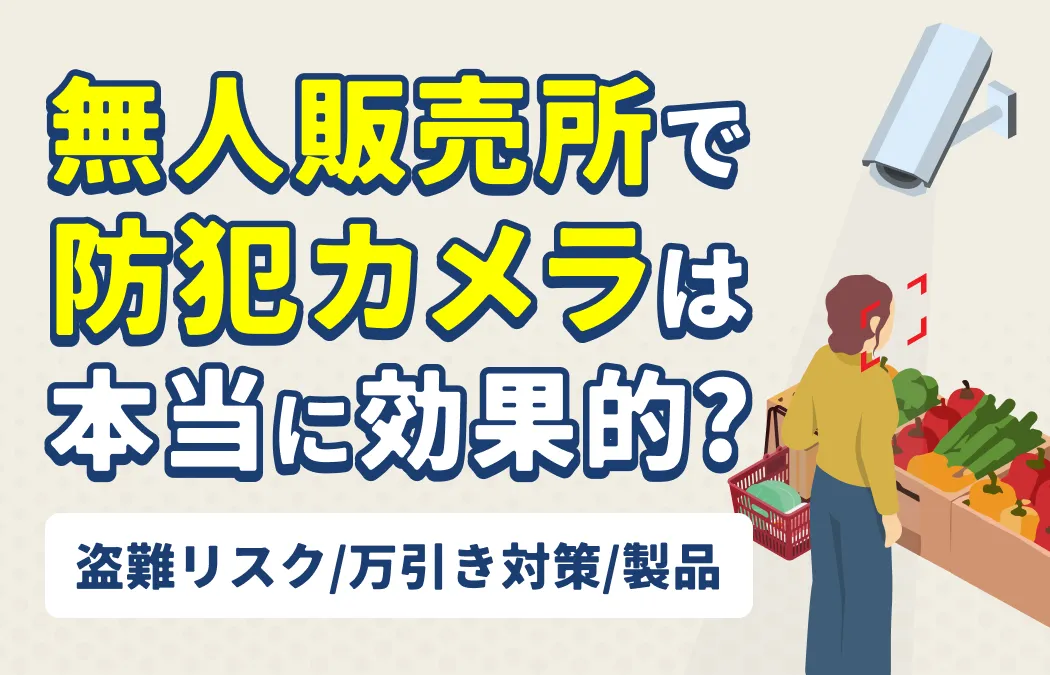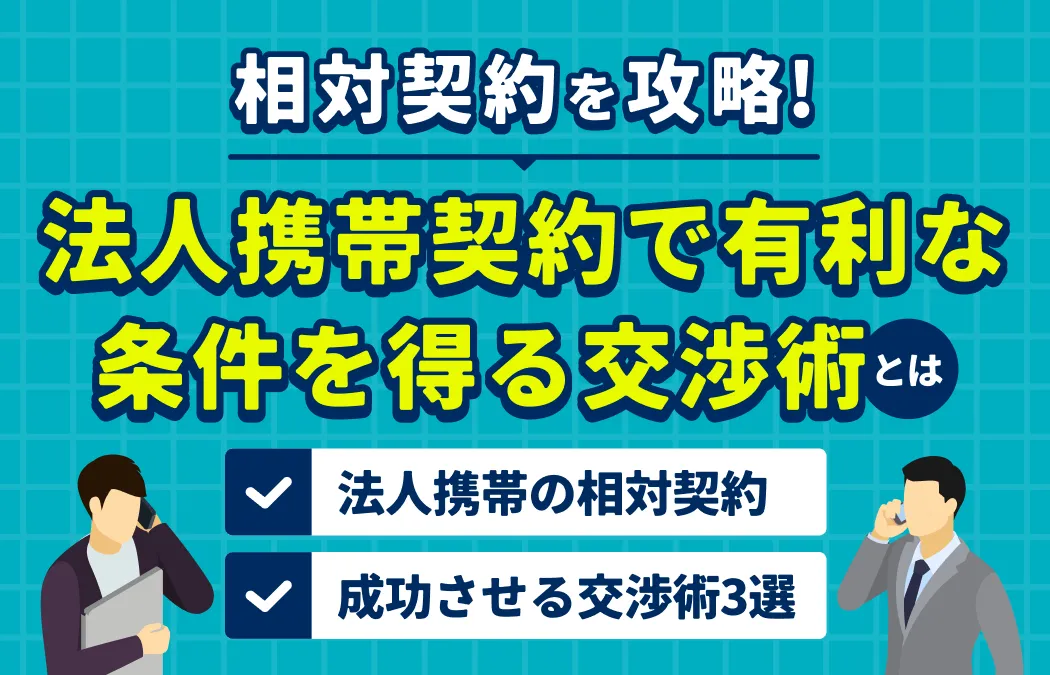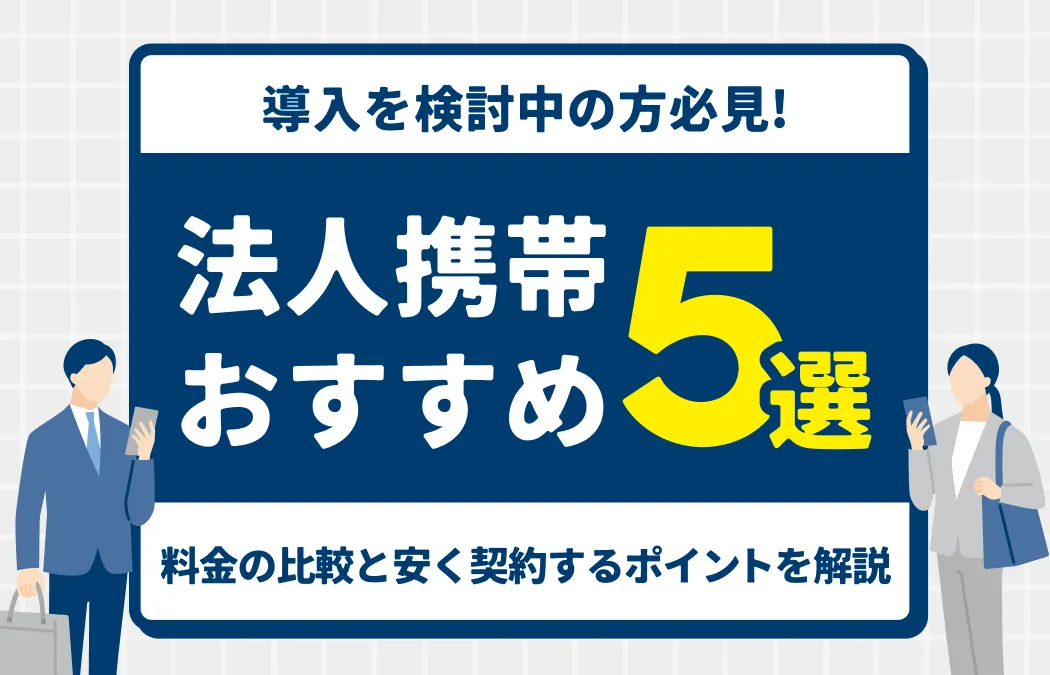「家事按分ってどうやって計算するの?」
業務とプライベートでスマホを兼用している場合、業務で使った分の携帯代(通信費や端末代)は経費計上できます。
しかし、「端末の費用区分は消耗品費と工具器具備品のどっち?」「経費計上する際の注意点は?」など疑問も多いはずです。
本記事では、按分割合の算出方法・勘定科目と仕訳例・法人契約との違い・節税メリットを詳しく解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
携帯代を経費にできる範囲とは?
個人事業主が携帯代を経費化する基本ルール
携帯代は、 業務で使用した分に限り経費として計上できます 。これは「必要経費」の原則に基づき、事業の遂行に直接関係する支出のみが認められるためです。
たとえば、顧客との通話やオンライン会議、業務連絡などに使う分は経費となります。
ただし、業務用と私用でスマホを兼用している場合、全額を経費にすることはできません。特に個人名義で契約している携帯電話は、事業とプライベートの境界が曖昧になりがちです。
そのため、業務使用割合に応じた「家事按分」という方法で、合理的に分けて計上する必要があります。
家事按分の具体的な方法と目安
家事按分とは、 事業利用とプライベート利用の割合を明確にし、事業利用分のみを経費として計上する方法で す。
按分計算においては、「通話時間」「使用日数」「用途別の利用割合」などをもとに業務使用割合を算出します。
具体的には、「平日はほぼ業務連絡に使っているため8割」「土日は私用が多いため5割」といった判断が一般的です。
税務調査に備えて、根拠となる使用実態やメモを残しておくと安心です。目安としては業務利用が中心なら7〜8割、半々なら5割程度が現実的なラインとなります。
携帯代の勘定科目と仕訳例
通信費|基本料金、通話料、データ通信料
携帯代のうち、 月々の基本料金や通話料、データ通信料は「通信費」として仕訳する のが一般的です。
仕訳では、勘定科目に「通信費」、摘要に「〇月携帯料金(按分〇%)」などと記載します。
たとえば月額10,000円のうち業務使用が70%であれば、7,000円を通信費として計上します。残りの3,000円は経費にならないため、記帳対象外となります。
確定申告の際にも、この按分処理を適切に行うことで節税にもつながり、税務署からの指摘を避けるポイントになります。
事業用と私用の使い分けを意識し、毎月の処理を丁寧に行いましょう。
端末購入費・周辺機器の仕訳区分
携帯端末の購入費は、金額によって経費の扱いが異なります。
- 購入価格が10万円未満の場合:「消耗品費」として一括で経費計上が可能
- 購入価格が10万円以上の場合:「工具器具備品」として資産計上し、複数年にわたり減価償却する
また、充電器やケースなどの周辺機器は、基本的に少額であるため「消耗品費」として処理されます。
これらの区分を誤ると税務調査で否認されるリスクもあるため、請求書や領収書を確認し、勘定科目を正しく分けて記帳することが大切です。
法人契約との比較・メリット
携帯を法人契約する経費面でのメリット
- 携帯が「業務専用」とみなされるため家事按分が不要になり、経理処理がシンプルに
- 携帯代を全額経費にできる
- 社員の業務用スマホ複数台を一括管理でき、経理や管理部門の手間を削減可能
- 法人向けプランは複数台の契約で割引適用される場合が多く、コストパフォーマンスの向上に
個人事業主でも法人契約が可能な場合があるため、業務利用が明確な方には検討をおすすめします。
携帯代を経費処理する注意点・留意事項
携帯代を経費として処理する際は、業務使用の実態が伴っているかが問われます。 業務での利用が明らかでないと、税務署に否認される恐れがあるため注意が必要 です。
また、按分割合が不自然に高すぎると、根拠の提出を求められることもあります。たとえば、家族と共用しているスマホで9割を経費にするなどはリスクが高いです。
日常的にどの程度業務に使っているかをメモで記録したり、請求書の保存を徹底するなど、証拠を残す運用も重要です。節税目的だけでなく、正しい記帳の積み重ねが信頼を築きます。
経費計上による節税効果と実務的注意点
節税効果を最大化するポイント
携帯代を適切に 経費計上することで、課税所得が減り、結果として節税につながります 。
たとえば、月1万円の携帯代のうち7割を経費とすれば、年間で8万4千円を経費化できます。これが税率20%の方であれば、1.6万円以上の節税効果が期待できます。
特に、事業初期で他の固定費が少ない場合は、携帯代の占める比率が高く、影響も大きくなります。
法人契約に切り替えることで全額経費としやすくなるため、業務用途が明確な方は法人携帯の導入も検討すると良いでしょう。

税務リスクを避けるための注意点
携帯代の経費計上が否認される主な原因は、「業務使用の証拠が不十分」なことです。
たとえば、私用と明確に区別できないまま全額を経費にすると、税務署に疑問を持たれやすくなります。そのため、 使用用途の記録や按分の根拠を残すことが重要 です。
具体的には、通話履歴の保存や、按分比率を算出したメモ、明細の保管などが有効です。また、端末代が高額な場合は減価償却を行い、会計処理の整合性を保つ必要があります。
日々の運用で記録を残すクセをつけることで、安心して経費処理ができるようになります。
まとめ
携帯代は、業務で使用した分に限り経費として計上でき、家事按分を活用すればプライベートとの兼用も適切に処理できます。
端末費用の区分や仕訳方法、法人契約のメリットを押さえることで、節税効果も期待できます。
ただし、税務上のトラブルを避けるには、使用実態の記録や領収書の保管が欠かせません。
もし携帯を業務専用にして経理処理を簡略化したい場合は、法人携帯の導入をおすすめします。
最新機種や大人気スマホが月額990円〜
【無料】導入相談はこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!