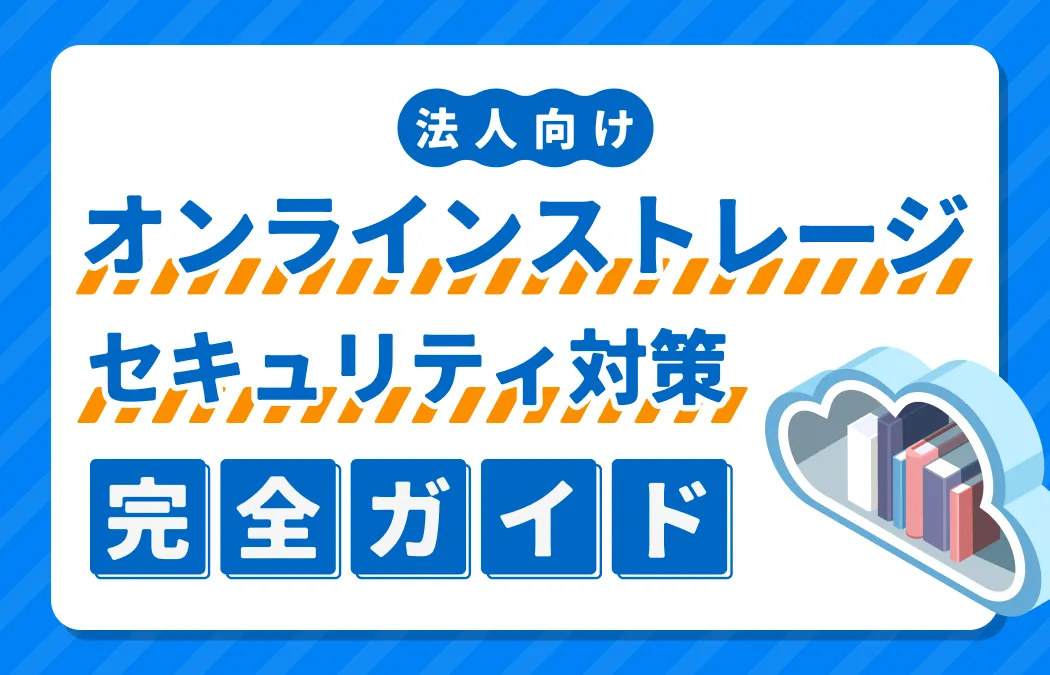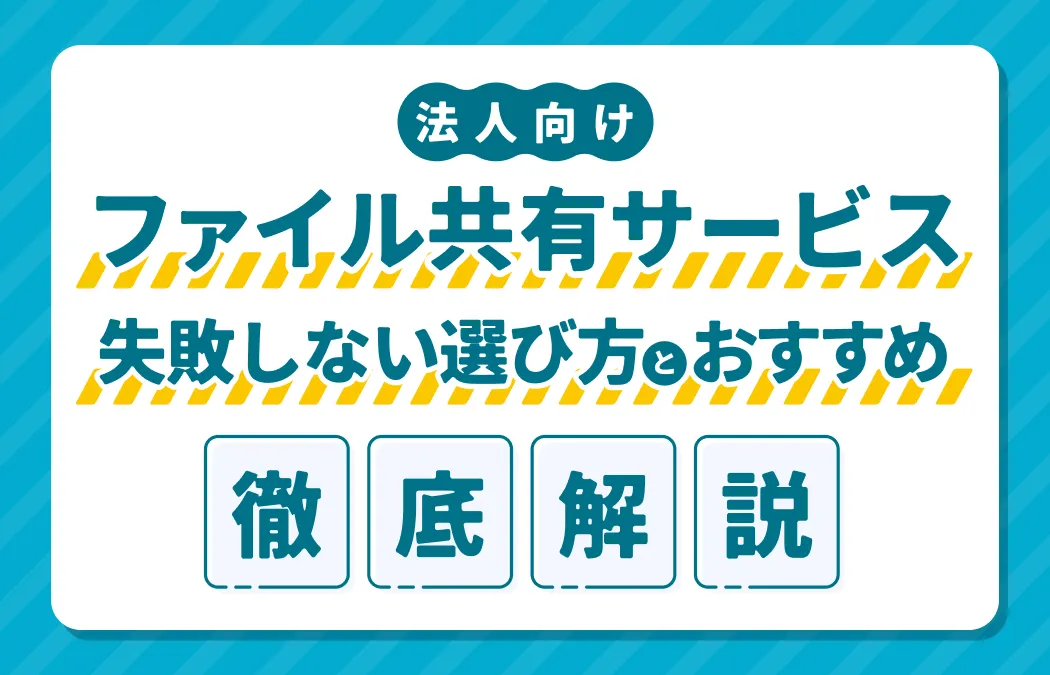「どんなセキュリティ対策を取ればいいの?」
オンラインストレージとは、インターネット上にデータを保存・共有できるサービスで、いつでもどこでもアクセス可能な利便性が特徴です。
しかし、その利便性ゆえに「情報漏洩」「不正アクセス」といったセキュリティリスクも存在します。
本記事では、主なセキュリティリスクと原因を整理し、そのうえで法人が安心して使えるオンラインストレージの選び方・対策方法を解説します。
目次
オンラインストレージのセキュリティ対策が必要な理由
テレワーク・データ共有機能拡大でファイル管理が分散化
テレワークの普及やクラウド活用の拡大により、企業のデータ管理はオフィス内だけで完結しなくなりました。
社外や自宅、出張先など、 あらゆる場所からアクセスできるようになった一方で、情報が分散しやすくなり、管理が複雑化 しています。
特にファイル共有や外部連携が増えると、誤送信や不正アクセスのリスクも高まります。
こうした背景から、オンラインストレージを安全に運用するためのセキュリティ対策は、もはや「選択肢」ではなく「必須条件」と言えるでしょう。
法人利用で特に注意すべきセキュリティリスク
法人がオンラインストレージを利用する際に注意すべきリスクは、主に 「情報漏洩」「不正アクセス」「マルウェア感染」「誤共有」 の4つです。
たとえば、社員が個人アカウントで社外とデータ共有した場合、意図せず機密情報が第三者に渡る恐れがあります。また、脆弱なパスワード設定や端末紛失も情報流出の原因になります。
こうしたリスクは、組織の信用や取引継続にも直結するため、オンラインストレージの利便性を活かしながら、確実なセキュリティ対策を講じることが重要です。
競合サービスの比較から見える“セキュリティ機能差”
オンラインストレージ各社では、提供するセキュリティ機能に大きな差があります。
たとえば「Box」や「Dropbox Business」は、 二段階認証や通信・保存時の暗号化、アクセスログ管理 などが充実しています。
一方、無料サービスや個人向けサービスでは、これらの機能が制限されている場合もあります。
法人利用では、コストよりも「どこまでリスクを想定し、どの機能で防ぐか」を重視すべきです。比較検討の段階からセキュリティ性能を最優先にすることで、導入後のトラブルを未然に防げます。
オンラインストレージ導入前に知るべきリスクと原因
技術的リスク:暗号化・通信経路・クラウド保存先の脆弱性
オンラインストレージはインターネット経由でデータをやり取りするため、通信経路や保存先サーバーが攻撃対象となるリスクがあります。
特に 暗号化が不十分なサービスでは、通信途中でデータが盗み見られる「中間者攻撃」などが発生する可能性 があります。
また、データが海外サーバーに保存される場合は、国内法とは異なる法規制の影響を受ける点にも注意が必要です。
こうしたリスクを防ぐためには、「通信・保存の両方を暗号化」「国内データセンター採用」などの技術要件を確認しておくことが大切です。
運用的リスク:アクセス管理、ユーザーの使い方、社内ポリシー欠如
セキュリティの脆弱性は、技術面だけでなく「人の運用」から生じるケースも多いです。
たとえば、 退職者のアカウントを削除せず放置したり、共有リンクを無期限で公開してしまったり といった事例は少なくありません。
これらは社内ポリシーの欠如や管理体制の甘さが原因です。
運用面では「権限の最小化」「アクセス期限の設定」「アカウント管理の定期見直し」をルール化することで、リスクを大幅に低減できます。技術と運用の両輪でセキュリティを確保しましょう。
契約・サービス選定リスク:ISMAP登録・データセンター所在地・ログ管理
法人利用では、セキュリティ体制を“サービス提供側”の観点からも精査する必要があります。
- 政府基準のISMAP(情報セキュリティ評価制度):登録されていないサービスでは、情報管理水準が明確でない可能性
- データセンターの場所:データセンターが海外にあると、現地法により情報開示を求められるリスクも存在
- ログ管理や監査対応機能:機能が不十分だと、不正利用を追跡できない
契約前には、技術仕様だけでなく「どのように安全性を担保しているか」を確認することが不可欠です。
ケーススタディ:過去の情報漏洩・ランサム実例(法人での失敗)
過去には、企業がクラウドストレージを利用中に発生した情報漏洩事例が多数報告されています。
典型的なのは、 アクセス制限を設定していない共有URLが検索エンジンに表示され、第三者に閲覧されてしまうケース です。
また、ストレージに保存されたデータがランサムウェアに感染し、業務停止に追い込まれた企業もあります。
これらは設定不備や運用の油断が原因であり、システム自体の問題ではないことも多いです。過去の失敗事例を他山の石とし、初期設定からルール作りまで徹底することが重要です。
オンラインストレージ選定時のセキュリティチェックリスト
必須セキュリティ機能
- 暗号化:データの盗み見防止
- 二段階認証:不正ログイン対策
- アクセスログ管理:不審操作の追跡
- バージョン管理:誤って上書きや削除をした際、データを元に戻せる
これらの機能が標準搭載されているか、無料・有料で差があるかを確認 することで、導入後のセキュリティレベルを大きく左右します。
法人視点で確認すべき項目
法人契約では、機能面だけでなく「契約条件」も重要です。
- SLA(サービス品質保証)にセキュリティ対応や稼働率保証が明記されているか
- データ保管場所が国内か国外か
- 社員が利用する端末を制限できる「デバイス制御」や「IP制限」機能があるか(漏洩リスクを低減)
見落としがちな項目ほど、トラブル時のリスクが大きいため、 導入前にチェックリスト化して社内で検討する のがおすすめです。
運用視点でのポイント
セキュリティ対策はシステム導入で終わりではなく、運用ルールの徹底がカギを握ります。
たとえば、 共有リンクの公開範囲や有効期限を定める社内規定を作成し、社員に教育 することでリスクを防げます。
また、異動・退職時のアカウント削除フローを明確にし、アクセス権限を定期的に見直すことも有効です。
どれほど高機能なサービスでも、使い方が甘ければ情報漏洩は防げません。ツールと運用ルールの両立こそが、法人における実効性あるセキュリティ対策です。
自社導入フローとセキュリティ運用をスムーズにするための手順
導入時には、 セキュリティ体制を段階的に整えることが大切 です。
- まずは試験的に特定部署で利用し、アクセス権限や共有設定の運用ルールを検証
- 次に、全社展開の前にリスク評価を行い、監査ログや利用履歴の保存方法を明確化
- 運用開始後は、定期的なセキュリティチェックや社内教育を行い、継続的に改善を図る
この流れを事前に整理しておくことで、導入後のトラブルや設定ミスを最小限に抑えられます。
導入後に実践すべきセキュリティ対策とベストプラクティス
アクセス権限設計と定期レビュー
オンラインストレージ運用の基本は「最小権限の原則」です。 必要な人だけが必要な範囲にアクセスできるよう権限を細かく設定 しましょう。
部署異動やプロジェクト終了後も権限を放置すると、不要な情報閲覧や漏洩につながります。定期的な権限レビューを行い、不要な共有リンクやユーザーを削除することが重要です。
組織の変化に合わせた柔軟な管理体制を維持することで、内部不正や誤操作を防ぎ、データの安全性を高められます。
ログ・アラート管理と定期監査
セキュリティを可視化する上で欠かせないのが「ログ管理」と「アラート機能」です。
誰が・いつ・どのファイルにアクセスしたかを記録し、不審な行動を早期に発見できる仕組み を整えましょう。
たとえば、深夜の大量ダウンロードや海外IPからのアクセスを検知して自動通知する設定も有効です。これにより、不正利用を事前に察知し迅速な対応が可能になります。
ログを定期的に監査し、問題発生時に証跡を追える体制を整えることが、継続的な安全運用の鍵です。
端末・ネットワーク連携のセキュリティ(VPN、端末管理、MFA)
オンラインストレージはクラウド上のサービスであるため、アクセス元となる端末やネットワークのセキュリティも欠かせません。
特に 社外アクセスが多い場合、VPN接続やモバイル端末管理(MDM)を導入し、セキュリティ水準を統一 することが大切です。
また、IDとパスワードだけでなく、多要素認証(MFA)を導入することで、不正ログインのリスクを大幅に減らせます。
システム面とネットワーク面の両方で守りを固めることが、安全なクラウド利用の基本です。
バックアップ・災害対策(BCP視点)とデータ復旧訓練
クラウドだからといって、データ消失のリスクがゼロになるわけではありません。 システム障害や人的ミスに備え、定期的なバックアップと復旧テストを行うことが重要 です。
特にBCP(事業継続計画)の観点からは、クラウド外への二重バックアップや復元手順の明文化も必要です。
また、災害やサイバー攻撃発生時に迅速に業務再開できるよう、復旧訓練を年数回実施する企業も増えています。
バックアップは「保存」ではなく「復元」を前提に設計するのが鉄則です。
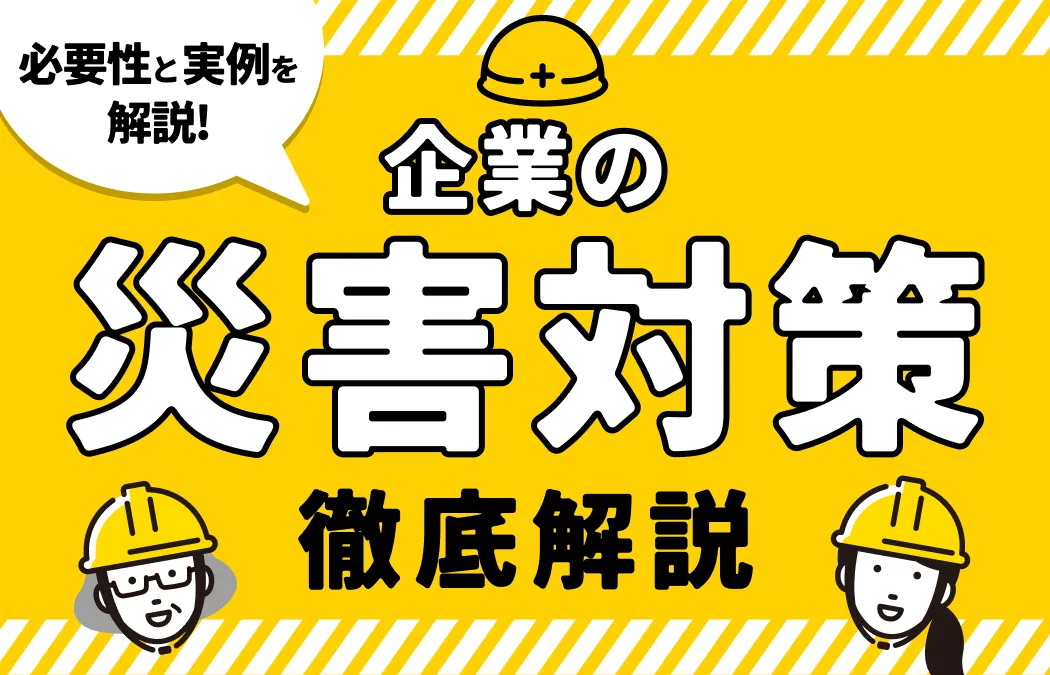
利用終了・退職時のデータ削除・アカウント管理
退職者や取引終了先のアカウントが残ったままでは、情報漏洩の温床になりかねません。以下のような対策でリスクを極力回避することが重要です。
- 利用終了時には、アカウント削除・権限剥奪・データ削除を確実に実施
- アクセス権限の引き継ぎ手順をマニュアル化しておくことで、引き継ぎ漏れによるリスクを防止可能
- 削除したデータが完全に復元できない形で処理されているかも確認
組織の入退管理と情報セキュリティを連動させることが、安全運用の持続に直結します。
【法人向け】おすすめオンラインストレージを比較
| 主な特徴 | 料金 | |
|---|---|---|
| Box | 高いセキュリティ 柔軟な権限設定が可能 |
月額:1,980円(税込)/ユーザー~ (最低購入ユーザー数3名) |
| Dropbox Business | シンプルなUIで操作性が高い 大容量ファイルの送信もスムーズ |
月額:1,500円(税込)/ユーザー~ ※個人向けプランは1,200円(税込)~ ※税表示なし |
| Google Drive (Google Workspace) |
Gmailやスプレッドシート等と連携可能。 操作が直感的 |
月額:800円/ユーザー~ ※税表示なし |
| OneDrive for Business | Microsoft 365との連携が強み | 月額:1,689円(税込)/ユーザー~ ※OneDriveのみは823円(税込)/ユーザー~ ※年間契約 |
自社導入に適した国内ベンダー・国産サービスの特徴
国産オンラインストレージは、 日本の法規制や商習慣に適した運用ができる点が強み です。
多くのサービスが国内データセンターを採用し、ISMS認証を取得しています。これにより、個人情報保護法やマイナンバー制度にも対応しやすく、コンプライアンス面で安心です。
さらに、日本語でのサポート対応が早く、トラブル時の復旧もスムーズです。海外製に比べてコストはやや高めですが、リスク回避と信頼性を重視する企業には適しています。
導入検討時に押さえたい”優先度”
オンラインストレージ選びでは、 「利便性を取るか、セキュリティを取るか」 というトレードオフを理解することが大切です。
たとえば、利便性を優先して共有範囲を広く設定すると、情報漏洩リスクが上がります。一方、厳重なアクセス制限をかけすぎると業務効率が低下します。
理想は「業務フローに支障を与えない範囲で最大限のセキュリティを担保する」ことです。導入前に、コスト・運用負荷・安全性のバランスを見極め、最適なサービスを選定しましょう。
導入後は継続的な監視と見直しも必須
オンラインストレージのセキュリティは「導入して終わり」ではなく、継続的な見直しが欠かせません。
システム更新や新機能追加により、設定内容や運用環境が変化するため、 初期設定のまま放置すると脆弱性が生じる恐れ があります。
少なくとも半年〜1年ごとに、アクセス権限・ログ設定・共有ルールを点検しましょう。また、社内の利用状況を分析して、運用ルールが現状に合っているか確認することも重要です。
定期的なセキュリティレビューを実施することで、リスクを早期に発見し、安全で持続的なクラウド活用が実現できます。
セキュリティ対策なら「おまかせサイバーみまもり」
おまかせサイバーみまもりは、NTT東日本が提供する法人向けのUTM(統合脅威管理)です。
専用BOXをネットワークの出入口に設置するだけで手軽にセキュリティ対策でき、通信のプロが通信状況のモニタリングや有事の際の復旧までサポートいたします。
標的型攻撃メールやウイルスへの対策はもちろん、フィッシングやスパイウェアまで幅広く対策できます。
なお、最新のパターンファイルへ自動更新されるため、常に社内のセキュリティ環境を最新状態に保つことが可能です。

導入を成功に導くためのステップ&社内体制作り
導入前チェックリスト
- 「どのファイルを・誰が・どの目的で共有するか」を明確化:導入前に既存データを棚卸しし、機密度ごとに分類
- アクセスが必要な社員・部署・外部取引先を洗い出し、不要な共有設定を削除:導入後のアクセス権設計がスムーズに
社内体制づくり
- ファイル共有やリンク発行に関する社内ポリシーを策定し、全社員に周知
- 情報管理の責任者やセキュリティ担当を設置し、運用状況を定期的に点検する仕組みを整える
- 社員向け研修を年1〜2回実施し、実際の操作ルールやトラブル事例を共有する
ルール・人・教育の三本柱で体制を固めることが、持続的な安全運用の鍵となります。
運用開始後のモニタリング&改善サイクル
導入後は 「モニタリング→改善→定着」のサイクルを回す ことで、安全性と利便性を高水準で維持できます。
アクセスログの分析や利用率の把握などを定期的に行い、リスク兆候を早期に検知しましょう。
さらに、改善に向けたKPI(例:アクセス権見直し率・教育受講率など)を設定し、社内レビュー会で成果を共有することも有効です。
運用上の課題が見つかった場合は、すぐにルールや設定を改善し、次の運用フェーズに反映します。
失敗回避のためのよくある落とし穴と対策(共有リンク・ID管理・権限放置)
オンラインストレージ導入で起こりがちな失敗は、 「共有リンクの管理不足」「退職者IDの放置」「アクセス権の過剰付与」 です。
特に、公開範囲が“全員アクセス可”のままになっているケースは情報漏洩の温床になります。
こうしたリスクを防ぐには、リンクの有効期限設定・権限の最小化・定期棚卸しの3点を徹底することが有効です。
また、システム設定変更時には必ず管理者レビューを挟む運用フローを設けると、ミスを防げます。小さな油断が大きな事故につながることを意識しましょう。
まとめ
オンラインストレージは、業務効率化やテレワーク推進に欠かせないツールですが、セキュリティを軽視すると大きなリスクを伴います。
本記事で解説したように、導入前のリスク把握・サービス選定・運用ルール策定・監視体制の整備が、安全運用の基本です。
特に法人利用では、アクセス権管理や社員教育、ログ監査など、人的・技術的な両面からの対策が不可欠です。
便利さだけに注目せず、「守る仕組み」をセットで整えることが、クラウド活用成功の鍵となります。
今すぐできる3つのアクション
- 共有設定・アクセス権限の棚卸し:誰がどのデータにアクセスできるかを明確化する
- 利用中ストレージのセキュリティ機能確認:暗号化・二段階認証・ログ管理の有無をチェック
- 社内ルールと教育体制の整備:共有リンクやパスワード管理に関するガイドラインを策定


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!