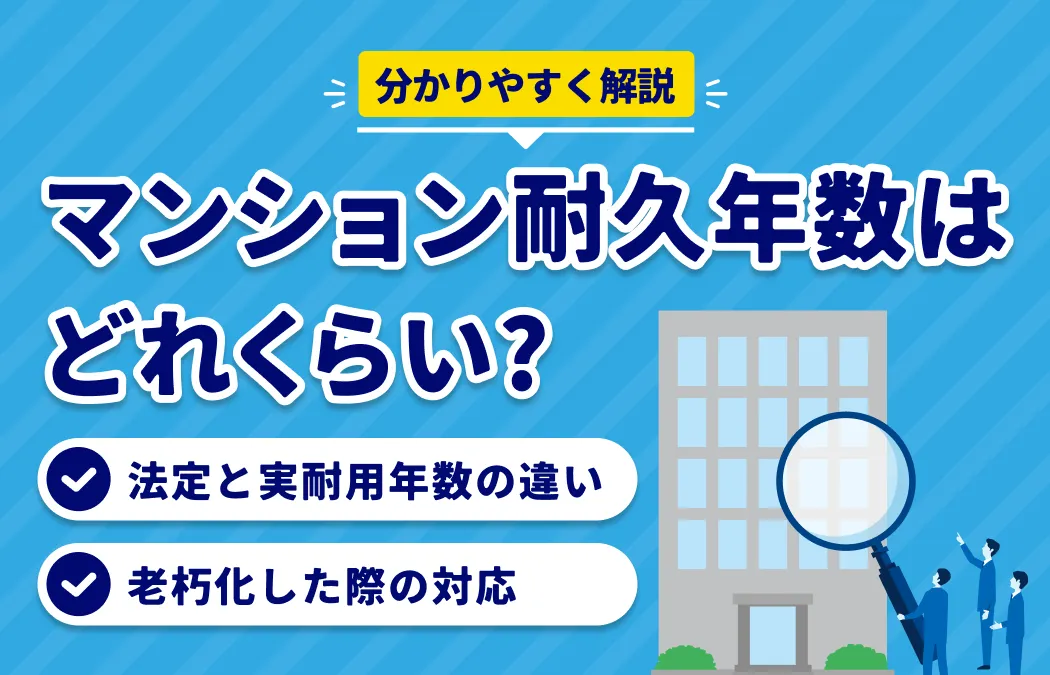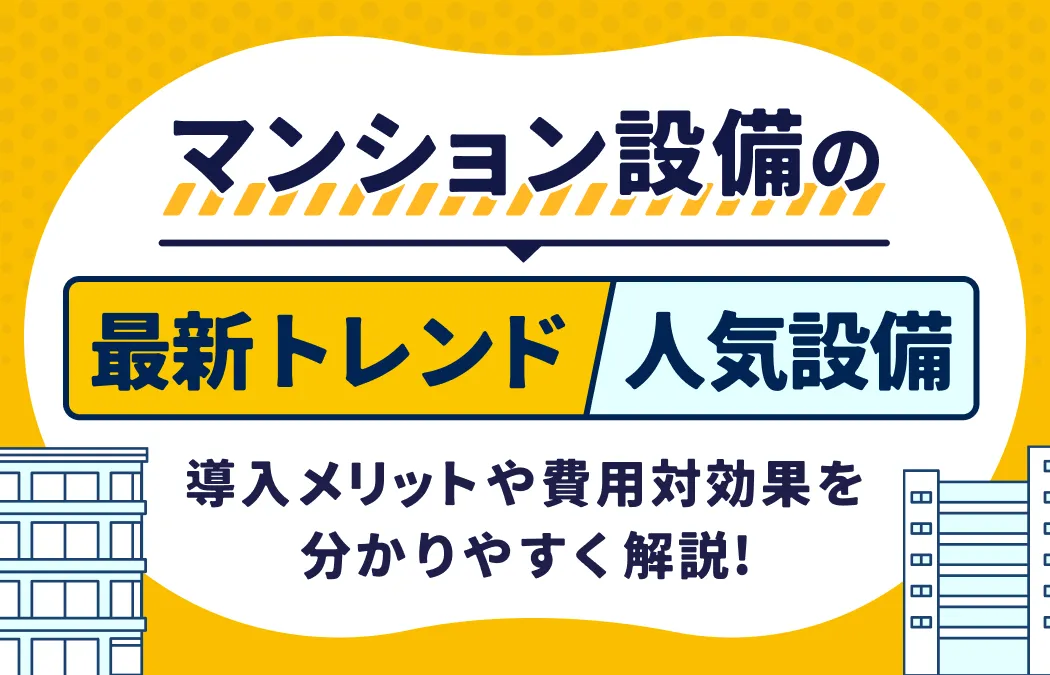「マンションの寿命を伸ばす方法は?」
「耐用年数が過ぎたらどうなる?建て替えは必要?」
マンションは、時間の経過に伴う設備や建物の老朽化を見越して、「耐用年数」が定められています。
所有する不動産物件の耐用年数は減価償却や融資の返済期間にも影響するため、正しい理解が必要です。
しかし。「中古でマンションを買う際、耐用年数はどうなる?」「修繕工事で耐用年数は伸ばせる?」など、疑問も多いはずです。
本記事では、法定耐用年数・実際の寿命・経済的残存耐用年数の違いを整理し、修繕・売却・住み続ける判断材料を提示します。
所有する物件が老朽化し、対応を判断しかねている方は必見です。
目次
▼この記事で紹介している商品
マンションの耐用年数とは?法定耐用年数と実際の寿命の違い
マンションには法定耐用年数が定められていますが、これはあくまで税務上の目安であり、実際の建物寿命とは異なります。
法定耐用年数は「税務上の基準」、実際の寿命は「管理状態や環境によって変動する実用期間」 と理解することが重要です。
法定耐用年数は「税務上の基準」
法定耐用年数とは、税法上で定められた建物や設備の使用可能期間を指し、減価償却の計算に用いられます。
たとえば、 RC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)のマンションは、法定耐用年数が47年 とされています。
これはあくまで税務上の基準であり、実際の寿命とは異なる点に注意が必要です。多くのオーナーは、この年数をもとに節税対策や資産計画を立てています。
法定耐用年数=物件が減価償却資産として扱われる期間、資産価値の見積もり基準
実質の寿命(実耐用年数)はどれくらいか?
マンションの実耐用年数、法定耐用年数よりも長くなるのが一般的です。RC造やSRC造の建物であれば、 適切な維持管理を行うことで60年〜100年以上使用できるケースも あります。
耐久性に優れた構造材を使用していても、劣化は避けられませんが、大規模修繕や定期的なメンテナンスによって建物の寿命を延ばすことが可能です。
特に外壁補修や配管の交換、防水工事などを計画的に実施している物件は、築年数が進んでも資産価値を維持しやすくなります。
実耐用年数は「使い方次第」で大きく変わる
耐用年数が不動産投資に与える影響
マンションの耐用年数は、不動産投資の収益性や資産価値に大きく関わります。 特に重要なのが、減価償却による節税効果と、金融機関の融資条件 です。
- 耐用年数が残っている物件:減価償却が取りやすく節税につながるため、投資家にとって魅力的な対象
- 法定耐用年数を超える築古物件:融資期間が短くなる傾向があり、返済計画に影響を及ぼすリスク
また、実際の建物寿命や修繕履歴が評価に加味されることもあり、築年数だけで判断するのは不十分です。
耐用年数は投資判断において「税務・資金調達・収益性」の3軸に影響する重要指標
減価償却・節税の計算への影響
投資用資産としてマンションを保有する場合、減価償却は節税の有効な手段です。
建物部分の取得費用を耐用年数に応じて分割し、毎年の経費として計上できる ため、課税所得を圧縮できます。
たとえば、RC造の法定耐用年数は47年ですが、中古物件では「残存耐用年数」を独自に算出することで、より短い期間で償却可能になるケースがあります。
これは短期間で経費を多く計上できるため、所得税や住民税の負担軽減に直結します。
ただし、土地部分は減価償却の対象外であり、建物と分けて評価する必要があります。耐用年数を正しく理解することは、節税戦略の第一歩となるのです。
融資期間や返済計画への影響
耐用年数は、金融機関が融資期間を決定するうえで重要な基準になります。
多くの場合、 建物の残存耐用年数が融資期間の上限とされるため、築古物件では返済期間が短くなる傾向 があります。
たとえば築30年のRC造マンションであれば、法定耐用年数47年から残り17年と判断され、その範囲内で融資が組まれることもあります。
返済期間が短くなれば、月々の返済額が増え、キャッシュフローに悪影響を与える可能性もあります。
そのため、収支計画を立てる際は、耐用年数と併せて修繕費や空室リスクも加味した慎重な資金計画が必要です。

編集部
耐用年数の理解は、融資交渉力と資産運用の安定性に直結
築年数が進んだマンション、どう判断・対処する?
築年数が進んだマンションは、資産としての扱いや今後の運用方針を慎重に見極める必要があります。老朽化によって修繕費が増え、入居者の募集にも影響を及ぼす可能性があるためです。
ただし、 築年数だけで判断するのではなく、残存耐用年数や修繕履歴、共用部の管理状態などもあわせて評価すべき です。
築年数経過時の残存耐用年数の計算方法
残存耐用年数は、 単に法定耐用年数から築年数を差し引くだけでなく、「簡便法」によって再算出されることも あります。
- 基本計算式(新築購入時)
残存耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数
(例)RC造マンション(法定耐用年数47年)、築30年の場合:47-30=17年 - 簡便法(中古購入時)
残存耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20% ※計算結果が法定耐用年数の20%に満たない場合は20%が下限
(例)RC造マンション(法定耐用年数47年)、築30年の場合:47-30+(30×0.2)=17+6=23年
税務上は短い年数で減価償却できるため、節税効果が高まりますが、金融機関が融資判断する際は、この年数がネックとなる場合もあるため注意が必要です。
残存耐用年数の理解は「税務戦略」と「資金調達戦略」の両面で欠かせない視点となるのです。
実際に寿命が近づいた物件の選択肢
築年数が法定耐用年数を超え、老朽化が進んだマンションを所有している場合、いくつかの選択肢があります。
- 資産価値が残っているうちに売却してキャピタルゲインを狙う
- 大規模修繕を行い、建物の寿命を延ばして賃貸収入を維持する
- 建て替えや他物件への買い替えを検討する
それぞれの選択肢にはメリットとリスクがあり、収益性や資産価値の将来を見据えた上での戦略が求められます。
重要なのは、 将来的な修繕費や空室リスクを考慮しながら、収支のバランスと資産価値の維持・向上を見据えた判断 を行うことです。
マンション寿命を延ばすための管理ポイント
マンションの 実際の寿命は、日常的な管理や定期的な修繕によって大きく左右されます 。構造がしっかりしていても、適切なメンテナンスがされていなければ劣化は加速します。
以下の管理ポイントを押さえることで、築年数を重ねたマンションでも資産価値を維持し、収益性を保ち続けることが可能になります。
定期的な修繕・ホームインスペクションの重要性
マンションの長寿命化には、 10〜15年ごとの大規模修繕 や、建物の状態を定期的に把握するためのホームインスペクション(住宅診断)が欠かせません。
外壁や屋上の防水工事、給排水管の交換などを定期的に行うことで、構造の劣化を防ぎ、建物の健全性を維持できます。
さらに、ホームインスペクションを活用すれば、目に見えない劣化や不具合を早期に発見でき、修繕の優先順位や時期の判断にも役立ちます。
こうした取り組みは入居者の安心感にもつながり、空室率の低下や資産価値の安定化にも貢献します。
プロによる定期点検と計画修繕の実施は、オーナーにとって“攻めの資産防衛策”
耐震等級、修繕履歴、住宅性能表示制度のチェックポイント
マンションの安全性や寿命を判断するうえで、確認すべき重要な指標がいくつかあります。
- 耐震等級:地震への強さを示す基準で、等級が高いほど安心して長く住み続けることが可能
- 修繕履歴:過去のメンテナンス状況を把握でき、今後の修繕計画や資産価値を見極める材料
- 住宅性能表示制度:断熱性や劣化対策などの性能を第三者機関が評価したもの
これらの情報を把握しておくことは、将来のリスクを未然に防ぎ、売却や賃貸時の差別化にもつながります。
築年数が進んだ物件の空室対策に役立つサービス
入居率向上を目指すオーナーにとって、物件の魅力を高める設備投資は有効な戦略です。
以下で紹介する設備の導入により、 築古物件であっても魅力を高め、長期的な収益性を確保することが可能 です。
SESAME
「SESAME」は、入居者が求める快適性と利便性を同時に提供できる最新のスマートロックシステムです。
スマホやICカードで玄関の施錠・解錠ができ、鍵の受け渡しや紛失トラブルを防止できます。また、オートロックや入退室履歴の管理機能により、防犯性も向上。
築年数の経過で競争力が下がりがちな物件でも、こうした先進設備の導入は他物件との差別化要因となり、長期的な空室対策として効果を発揮します。

フォーカスネット光
フォーカスネット光は、集合住宅向けのインターネットサービスです。
建物全体に高速で安定したインターネット環境を提供でき、入居者満足度の向上につながります。
最近ではネット完備が物件選びの条件になることも多く、インフラ整備は差別化要素としても有効です。

マンションの耐用年数に関するよくある質問
A
築年数が11~20年が経過している物件は、比較的需要が高く、売却しやすいタイミングといえます。これは、外観や設備などの劣化が目立ちにくい状態でありながら、新築の物件よりもリーズナブルな価格で購入できるためです。売主側としても、既に住宅ローンの返済が10年を超えているため、残債額が少なく、アンダーローンになりやすい点でメリットがあります。
まとめ
マンションの耐用年数は、単なる税法上の指標ではなく、投資判断や資産運用において極めて重要な要素です。
法定耐用年数だけでなく、実際の寿命や管理状況、修繕履歴を総合的に捉えることで、収益性や資産価値の維持が可能になります。
特に築年数が進んだ物件では、定期的なメンテナンスや設備更新が差別化の鍵となります。今一度、自身の物件の現状を見直してみてはいかがでしょうか。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!