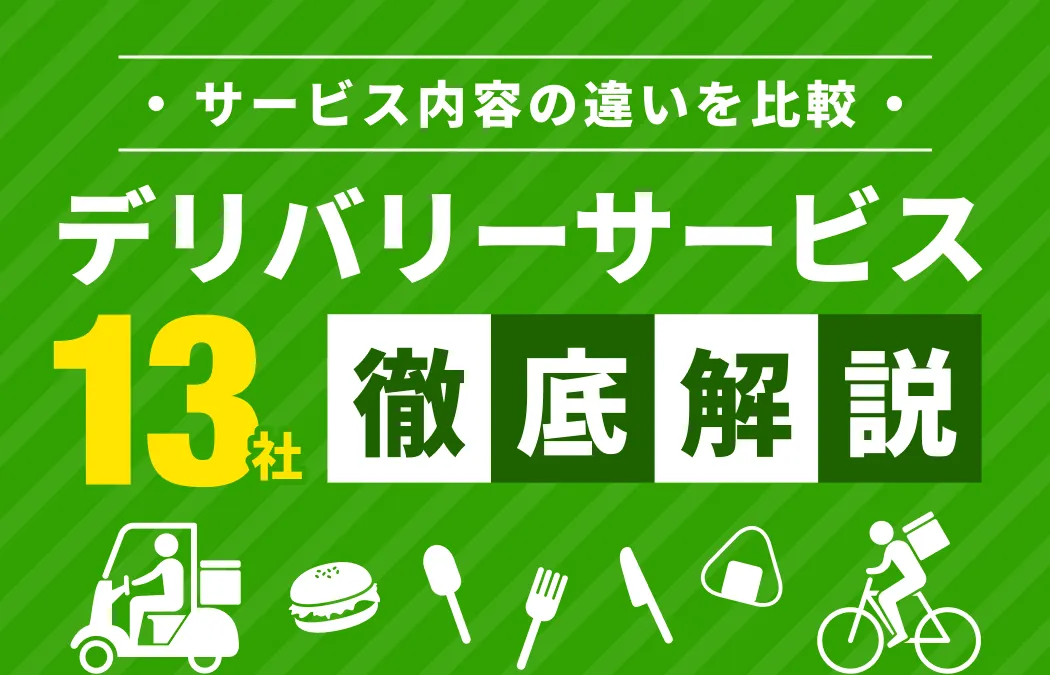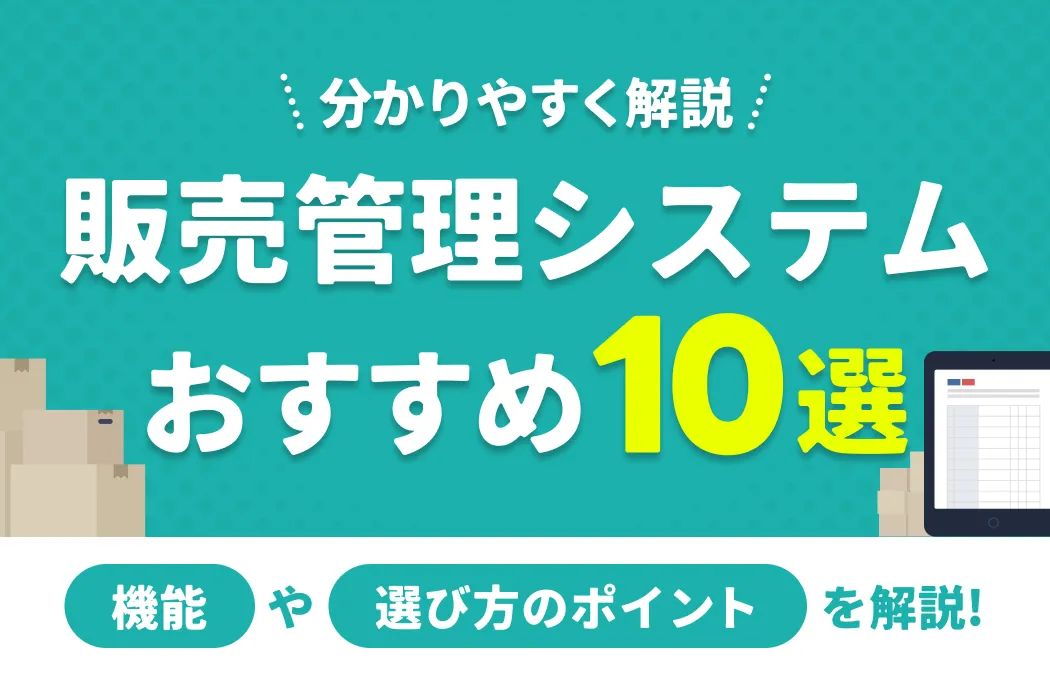「カフェやイベント、アイスクリーム販売には、どのような許可が必要?」
飲食店がテイクアウトを始めるには、飲食店営業許可があれば、追加の許可は不要です。
しかし、取り扱う食品の種類や提供方法によっては、新たな営業許可が必要になることもあります。
そこで本記事では、テイクアウトに新たな営業許可申請が必要なケースと、不要ケースを徹底解説していきます。
テイクアウトを始める準備・手順も紹介しているため、テイクアウトを始めて売上アップを図りたいオーナーの方は必見の内容です!
目次
▼この記事で紹介している商品
飲食店がテイクアウトを始めるのに保健所の許可は必要?

飲食店営業許可があり、店内調理・提供であれば別途許可不要
飲食店営業許可を取得済みで、店内調理したメニューをそのままテイクアウト販売する場合、基本的に追加の許可は不要 です。
ただし、取り扱う食品の種類や提供方法によっては、新たな営業許可が必要になることもあります。
許可が不要と思われる場合でも、事前に最寄りの保健所へ確認することをおすすめします。
食品衛生法とは?
食品衛生法は、 食品の安全性を確保し、国民の健康を守るための法律 です。
食品の製造・加工・販売に関する衛生管理基準を定め、食品添加物や農薬の使用基準、食品表示のルールなどを規制しています。
事業者にはHACCPに基づく衛生管理が義務付けられ、食品の安全性を徹底する体制が求められます。
違反があれば営業停止や罰則が科されることもあります。
テイクアウトに新たな営業許可申請が必要な場合

飲食店がテイクアウトを始めるにあたっては、 新たな営業許可や届出が必要になる場合もあります 。
以下のケースに当てはまる場合や、該当する商品を扱う場合は、所轄の保健所へ許可の申請を行いましょう。
別途許可が必要な食品を取り扱う場合
通常の店内メニューをテイクアウト販売する場合でも、 食品の種類によっては追加の許可が求められることがあります 。
例えば、アイスクリームや自家製生麺、乳製品などを販売する際は、各食品に応じた営業許可や届出が必要です。
店内提供のみなら「飲食店営業許可」で問題ありませんが、無許可で販売すると法令違反となるため、事前に確認しましょう。
-
▶許可が必要な食品
-
必要となる許可 対象となる食品 あん類製造業 つぶあん、こしあんなど アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混ぜたものを凍結させた食品 乳製品製造業 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するもの 魚肉ねり製品製造業 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するもの 清涼飲料水製造業 ジュース、コーヒーなどの清涼飲料水 乳酸菌飲料製造業 乳などに乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のもの 氷雪製造業 氷 食用油脂製造業 動物性、植物性を問わず、サラダ油やてんぷら油などの食用油脂 マーガリン又は
ショートニング製造業マーガリン又はショートニング みそ製造業 みそ 醤油製造業 醤油 ソース類製造業 ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズ 酒類製造業 酒の仕入から搾りまでを行う場合 豆腐製造業 豆腐そのものの製造 納豆製造業 納豆 麺類製造業 生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニなど そうざい製造業 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物 かん詰又は
びん詰食品製造業かん詰又はびん詰食品 添加物製造業 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物 乳処理業 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む)又は山羊乳の処理、製造 特別牛乳さく取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する 集乳業 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、保存する 食肉処理業 食用の目的でうさぎやいのしし等をと殺もしくは解体する営業、又は解体された鳥獣の肉、内臓などを分割、細切りする 食品の冷凍業又は
冷蔵業魚介類を冷凍又は冷蔵する、又は冷凍食品を製造する 食品の放射線照射業 食品に放射線を照射する 調味料等製造業 チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料 つけ物製造業 塩漬け及びぬか漬け以外の漬物 製菓材料等製造業 生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類 粉末食品製造業 粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもと、その他の粉末食品 
編集部
肉や魚介を含む鍋セットや、自宅で調理する焼肉セットなど、該当する食品を含む商品は許可が必要になります。判断が難しい場合は保健所に相談し「このような商品を取り扱いたい」と具体的に説明して確認しましょう。
お酒類を取り扱う場合
店内でお酒を提供している飲食店でも、テイクアウト販売には別途 「酒類小売業免許」 が必要です。
無許可で販売すると酒税法違反となるため、事前に必要な手続きを確認のうえ、適切な許可を取得しましょう。
菓子類(パン、ケーキなど)やアイスクリームを取り扱う場合
ケーキやアイスクリームをテイクアウト販売する場合、 「菓子製造業」 や 「アイスクリーム類製造業」 の許可が必要になります。
なお、ケーキやアイスクリームをテイクアウト販売する場合の許可は、令和3年6月1日の食品衛生法改正から必要になりました。
そのため、令和3年6月1日以前に飲食店営業許可を取得した店舗で「菓子製造業」や「アイスクリーム類製造業」の許可未取得の場合は、追加で申請しましょう。
-
ケーキや菓子類、パンなど▶菓子製造業の許可が必要
-
アイスクリーム▶アイスクリーム類製造業の許可が必要
冷凍食品を取り扱う場合
冷凍食品を販売するには 「食品の冷凍又は冷蔵業」 の許可が必要です。
例えば、そうざいを冷凍販売する場合「そうざい製造業」と「冷凍業」の両方の許可が求められます。
なお、冷凍食品とは製造・加工した食品や鮮魚介類の切り身・むき身を凍結させたものを指し、一部の食品は対象外となるため、事前に確認が必要です。
日持ちさせることを前提とした食品を取り扱う場合
調理した食品を真空包装などで長期保存できる形にする場合は、飲食店営業許可の範囲を超えます。
上記のケースでは、「そうざい製造業」など 扱う食品に応じた製造業の許可や届け出が必要 です。
-
そうざいを多めに作り、販売する場合▶総菜製造業の許可が必要
-
チャーシューなどを作り置きし、少しずつ販売する場合▶食肉製品製造業の許可が必要
店舗の厨房以外で調理したものを販売する場合
保健所は申請を受けて、厨房や店内の衛生状態を確認し、食中毒などのリスクがないことを確認した上で許可を出しています。
そのため、開業時に許可を得た店舗の厨房以外でテイクアウト用の商品を調理する場合、 別途保健所の許可を取得しなければなりません 。
例えば、店長が自宅のキッチンで調理した商品を販売する場合も、別途許可が必要となります。
営業許可を受けている飲食店内の一角で、テイクアウト専門店を新たに開業する場合
営業許可を受けている飲食店内であっても、営業許可を受けている事業とは別のテイクアウト専門店を開業する場合、 管轄の保健所で「飲食店営業許可証」を取得する必要があります 。
また、すでに飲食店を営業している飲食店がキッチンカーでテイクアウト営業を始める場合も、設備基準を満たし許可を取得しなければなりません。
キッチンカーなど自動車でテイクアウト販売する場合
自動車内で調理したものを屋外販売する場合
キッチンカーでクレープやたこ焼きを提供するなど、 自動車内で調理した食品を販売する場合、以下の許可を取得する必要があります 。
-
飲食店営業許可
-
喫茶店営業許可
-
菓子製造業
自動車で調理しない場合
移動型のお弁当屋さんのように、 自動車内で調理をせずに販売する場合、以下の許可が必要です 。
-
食料品等販売業
-
乳類販売業
-
食肉販売業
-
魚介類販売業
上記を含む 販売許可は、飲食店営業許可に比べて取得しやすい です。
ただし、認められるのは包装済み商品の販売に限られており、基本的に生ものの販売や温め、盛り付けはできないため注意しましょう。
-
▶自動車でテイクアウト販売をする際の注意点
-
移動販売を行う際、販売する場所ごとに保健所で許可を取得する必要があります。
許可を受けた場所以外での販売は禁止されているため注意が必要です。
例えば、渋谷区で許可を受けた場合、渋谷区内でのみ販売可能となり、新宿区では販売できません。
また、移動販売用の自動車にも営業許可が必要な場合があります。
店内で調理した食品を別の隣接施設でテイクアウトとして販売する場合
営業許可は、販売を行う施設ごとに取得する必要があります。
例えば、店舗で作っている焼き菓子を知り合いのお店で販売するという場合など、 飲食店内で調理した商品を別の施設で販売する際には、既存の営業許可は適用されない ため注意しましょう。
屋外で調理や販売をする場合
お祭りの出店のように、屋外に調理設備を設置し販売を行う場合、 店舗で取得した許可とは別に、飲食店営業許可を新たに取得する必要があります 。
屋外での調理は、異物の混入や温度管理が難しくなるため、衛生面での問題が発生しやすくなります。
そのため、保健所の審査が厳しくなり、別途許可が求められる場合もあります。
テイクアウトに新たな営業許可申請が不要な場合

店内で調理した料理をお持ち帰り用やテイクアウト用として販売する場合
飲食店の店内で調理したいつも出しているメニューを、お持ち帰り用やテイクアウト用に包み販売する場合は、 飲食店営業許可さえあれば他に許可は必要ありません 。
-
寿司屋で家族用に寿司を包んでもらう
-
居酒屋で焼き鳥を注文し、持ち帰りにする
-
中華料理屋で餃子を持ち帰る
飲食店がテイクアウトを始める準備・手順

STEP1|保健所に許可要否の確認を取る
販売する商品や方法によっては、新たに営業許可が必要となる場合があります。
また、自治体ごとに基準が異なるため、テイクアウトを始める際は事前に保健所へ相談すると安心です。
許可が必要か判断してもらうために、 レシピの概要や表示見本を用意することで、保健所での確認もスムーズになるでしょう 。
STEP2|テイクアウトに適したメニューを考える
テイクアウトでは、提供後すぐに食べられるとは限らないため、 持ち帰っても美味しさを保てるメニューを選ぶことが重要 です。
冷めても風味や見た目が落ちにくい料理を検討しましょう。
また、食中毒リスクの高いメニューは避けるか、提供方法を工夫するなど、衛生面にも配慮が必要です。
STEP3|市場調査を行う
大まかなメニューを決めた後は、既存の顧客層やエリアの需要、競合店の状況などを市場調査しましょう。
例えば、ドリンクのテイクアウトを考えている場合、ジムが近くにあれば高タンパクなスムージー、ビジネス街ならコーヒーがおすすめです。
エリアや客層によって求められる種類やサイズが異なるため、 需要に合ったメニューを展開できるよう準備を進めることが重要 です。
STEP4|テイクアウト容器や割り箸などを準備する
細かいメニューを決めた後は、 容器やカトラリーの準備が必要 です。
料理に適した容器を選ぶことが重要で、ご飯とおかずを分けられるものや、汁漏れを防ぐ密閉容器、保温性のあるものなど、メニューに応じた選定が求められます。
また、割り箸やスプーン、フォークも食べやすさを考慮し、環境に配慮した素材を選ぶことで、店舗の取り組みをアピールできます。
STEP5|衛生管理ルールを策定する
店内での飲食と異なり、テイクアウトでは料理が提供されてから食べるまでの時間を店舗側で管理できません。
そのため、 通常の衛生管理に加えて、テイクアウト専用のルールを設けることが重要 です。
食中毒を防ぐため、保管方法を明示したり、保冷剤をつける基準を決めたりするなど、食品の安全性を確保する対策を整えましょう。
テイクアウト商品に内容量・賞味期限・消費期限の表示は必要?
飲食店がその場で作った料理をテイクアウト販売する場合、 消費期限などの表示義務はありません 。
ただし、販売方法によっては食品表示法に基づく表示が必要になるため、事前に確認しておくと安心です。
また、食中毒を防ぐため、「本日中にお召し上がりください」と記載したシールを容器に貼るなど、適切な注意喚起を行いましょう。
STEP6|デリバリー導入の有無を検討する
テイクアウトを始める際には、デリバリーの導入もあわせて検討しましょう。
店頭受け取りのみにするか、配達もできるようにするかで、売上やオペレーションは大きく変動します。
デリバリーを導入する場合、 自社で配達を行うのか、フードデリバリーサービスを活用するのかも重要な判断 です。
人員やコスト、手数料などを考慮し、自店舗に適した方法を選びましょう。
STEP7|テイクアウトの告知を行う
テイクアウトを成功させるには、 しっかりと告知し、利用者に認知してもらうことが重要 です。
近年、テイクアウト市場は競争が激しいため、PRが不十分だと利用者の獲得は難しくなります。
Retty株式会社の調査によると、消費者がテイクアウトを知るきっかけは「SNS」が約41%、「お店の前の看板」が約38%という結果が出ています。
例えば、店頭でのPOPや看板に加え、SNSを活用して広く告知すると効果的です。
▶参照:テイクアウトの認知はSNS経由が4割!!消費者アンケートから見る緊急事態宣言後のテイクアウト事情 | Retty株式会社のプレスリリース
飲食店がテイクアウトを始める際の注意点

食中毒のリスクを防ぐため衛生管理を徹底する
テイクアウト販売では、店舗での飲食と比べて出来上がった料理を食べるまでに時間がかかるため、衛生管理がより重要になります。
調理後はできるだけ早く提供できる仕組みを整え、適切な賞味・消費期限を設定 しましょう。
万が一、提供した食品で食中毒が発生すると、保健所への通報や信用の低下につながり、営業に大きな影響を及ぼす可能性があります。
-
消費期限やアレルギー商品の伝達
-
ラップなどの異物が混入しないようにする
-
まな板や作業台、調理器具の除菌を徹底する
-
マスクとビニール手袋をする
生ものや半熟卵、レア肉などの提供は控える
テイクアウトでは、食材選びに十分注意しましょう。 生ものや半熟卵、レア肉の提供は避けるべき です。
特に、気温と湿度が高くなる夏場は食中毒のリスクを高めます。
例えば、店内で提供する半熟卵入りのサラダをテイクアウト用に変更する場合、代わりにゆで卵を使うなど、メニューの工夫が必要です。
価格を高く設定しすぎると、収益性が下がるリスクがある
テイクアウト販売では、価格設定に工夫が求められます。
店内での食事は3,000円以上でも支払う客が多い一方、テイクアウトでは2,000円を超えると高いと感じる人が増えます。
価格設定が不適切だと売れなくなり、安すぎれば収益が減少します。
そのため、 テイクアウトでは2,500円以上の高額な価格設定は避け 、適切な価格帯を見極めることが大切です。

編集部
テイクアウトでは「ランチで1,000円程度」「ディナーで2,000円弱」の価格帯がおすすめです!
許可が不要だと判断した場合も保健所に相談する
テイクアウトを開始する際、許可が不要と思われる場合でも、保健所に確認することが重要です。
新たに販売するメニューや、店内メニューでも販売方法や規模によっては許可が必要になる ことがあります。
無許可営業が判明すると法令違反となり、大きなリスクを伴います。迷った際は、自己判断せず、所轄の保健所に相談しましょう。
テイクアウトの売上を伸ばすためのポイント

容器のデザインにこだわる
テイクアウト容器を選ぶ際は、デザインにもこだわりましょう。同じ価格や味の料理でも、デザイン性を高めることで顧客にとっての魅力度は増します。
また、おしゃれな容器を使うことで、 ブランディングやSNSでの話題作りにもつながります 。特にSNS映えするデザインは、若年層の女性客に支持され、拡散される可能性が高まります。
容器のデザインは機能性同様、お店の魅力を引き出す重要な要素です。
食べるまでの時間を考慮する
テイクアウトでは、持ち帰りや配達の距離、お客さまの都合で、食べ始めるまでに時間が生じるため、 料理の食感やおいしさが損なわれることがあります 。
特に麺類は、時間が経つと麺がくっついてほぐれにくくなり、コシが失われるため、茹で時間を減らしたり麺の種類を変えたりなど対策が重要です。
ランニングコストを考慮する
テイクアウト販売では、使い捨てのプラスチック容器を使用するため、月々のランニングコストがかかります。
おしゃれな容器を採用することは重要ですが、 消耗品にコストをかけすぎると、長期的な運営を難しくすることもあります 。
テイクアウトの売上とランニングコストのバランスを考え、適切な価格設定を行うことが重要です。
電子決済サービス
キャッシュレス決済の需要が高まっている今、電子決済サービスの導入は有効です。
現金の受け渡しがないため感染症予防にもなり、 タッチ決済で素早く支払いが完了し、回転率を向上させることができます 。
また、急いでいる消費者にとって、電子決済で購入ハードルが下がり、スムーズに取引を進められるため、購買促進にもつながります。
フードデリバリーサービスの利用も検討する
テイクアウトを始めるにあたって、フードデリバリーサービスを利用することも有効です。
フードデリバリーサービスは、 プラットフォーム事業者が注文受付や配達を代行してくれる ため、自社の負担を軽減しながら売上を伸ばすことができます。
ただし、手数料がかかるため、コストと収益のバランスを見極めて導入を検討することが重要です。
関連記事
UberEatsとは?料金から使い方まで完全ガイド 【Uber Eatsの料金や仕組みは?】手数料やメリットも理解できる徹底解説! Uber Eats加盟店に店舗登録をする方法・出店する条件を解説【飲食店側】SNSやGoogle ビジネス プロフィールを活用して集客する
テイクアウトの売上を伸ばすためには、SNSやGoogleビジネスプロフィールを活用した集客が効果的です。
TwitterやInstagramなどの SNSは無料で運用でき、写真を使ってテイクアウトを宣伝できます 。自店舗に合ったSNSを選べば、高い効果が期待できます。
また、Googleビジネスプロフィールを更新し、テイクアウト対応店舗として認知されることで、集客を増やすことができます。
▶複数店舗の情報と口コミを一括管理・分析できるMEO対策ツール「口コミコム」の詳細はこちら

編集部
どんな商品を販売しているのかなど、見ただけですぐに分かるポップなどを作成するのもおすすめです!
飲食店のテイクアウトに関するよくある質問
A
テイクアウト専門店は、条件をクリアしていれば自宅でも開業することが可能です。
テイクアウト専門店を自宅で開業する為に必要な条件は以下の通りです。
・食品衛生責任者
・飲食店営業許可証
A
自宅でテイクアウト専門店を開業するまでの流れは以下の通りです。
1.コンセプト考案~事業計画書作成
2.保健所へ事前相談~施工業者の選定
3.許可申請~工事~立会検査
4.許可証交付~開業
A
ドリンクのテイクアウト販売で許可が必要なケースは以下の通りです。
・新たに店舗や設備を設ける場合
・新たに開業する場合
・お酒をテイクアウト販売する場合
A
テイクアウトのみでも飲食店営業許可は必要です。
A
焼き菓子のテイクアウト販売では「菓子製造業許可」「飲食店営業許可」が必要です。
A
すでにカフェを営業していて、普段の提供メニューをそのままパック詰めして販売するという場合は、新たな許可は必要ない場合がほとんどです。
しかし、テイクアウトを始める際に「新しい食品を販売する」や「新たな施設・設備を導入する」場合、既存の営業許可では衛生基準を満たせないことがあるため、管轄の保健所に相談するのがおすすめです。
A
イベントのテイクアウト販売では「飲食店営業許可」が必要です。
提供するメニューによっても追加の許可が必要なため、イベントの主催者や管轄の保健所に相談しましょう。
A
テイクアウトで作り置きは可能です。
ただし、飲食店内で提供する分を超えて作り置きしたり、真空パックや冷凍処理などで保存を前提とした商品を販売する場合、製造業などの許可が必要となります。
A
テイクアウト販売でフードデリバリーサービスを利用するメリットは以下の通りです。
・人員を増やさずに簡単に始めやすい
・幅広い人に利用してもらえる
・サービスを通じて、新規利用者を獲得できる
テイクアウト販売でフードデリバリーサービスを利用するデメリットは以下の通りです。
・新しいコストがかかる
・運びやすいメニューを考える必要がある
・配達用の容器を用意する必要がある
A
テイクアウト専門店とは、お持ち帰りに特化した飲食店のことです。
A
テイクアウト専門店のメリットは以下の通りです。
・小さな店舗で開業できるため初期費用を抑えやすい
・開業後も光熱費や人件費といった諸経費を抑えられる
・回転率が高い
テイクアウト専門店のデメリットは以下の通りです。
・メニューによってはテイクアウトに向かない
・原価率が低く、利益の高い商品が売れにくい
・衛生面も注意する必要がある
まとめ
テイクアウト販売を始める際、許可が必要かどうかは販売するメニューや規模によって異なります。
特に新たに販売する食品がある場合や、販売方法に変更がある場合は、保健所に確認することが重要です。
また、リソースが不足している場合や配送に手間がかかる場合、フードデリバリーサービスの利用を検討することも一つの手です。
これにより、配送業務を外部に委託し、自店の負担を軽減しながら、より多くの消費者にアプローチできます。
サービスの利用には手数料がかかりますが、集客や売上の拡大を期待できるため、コストと効果を比較して導入を考えましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!