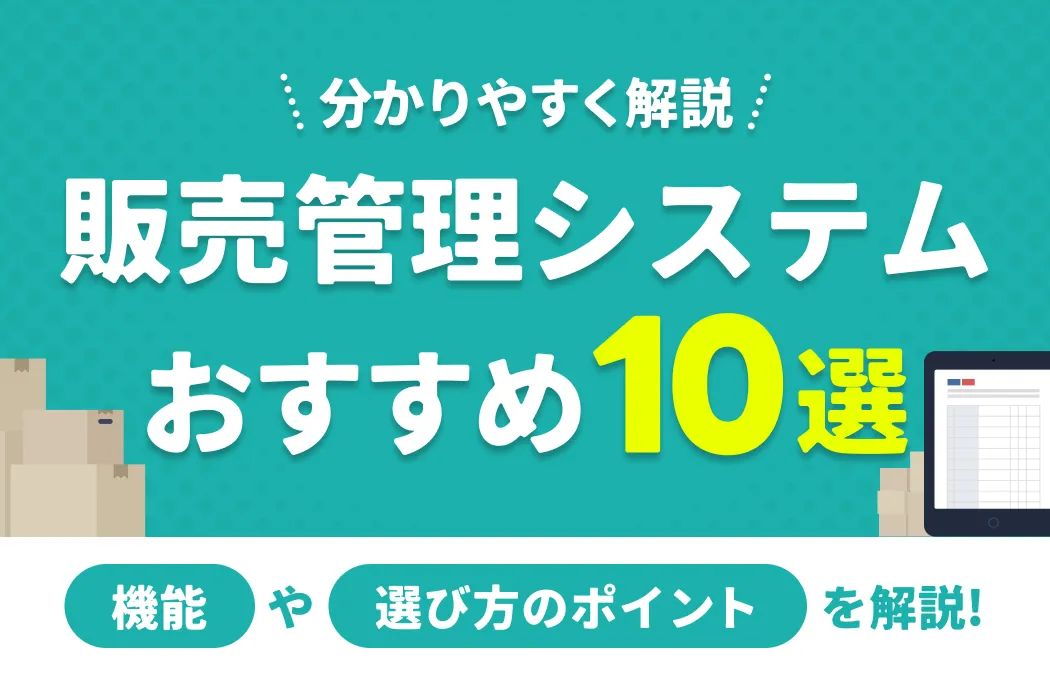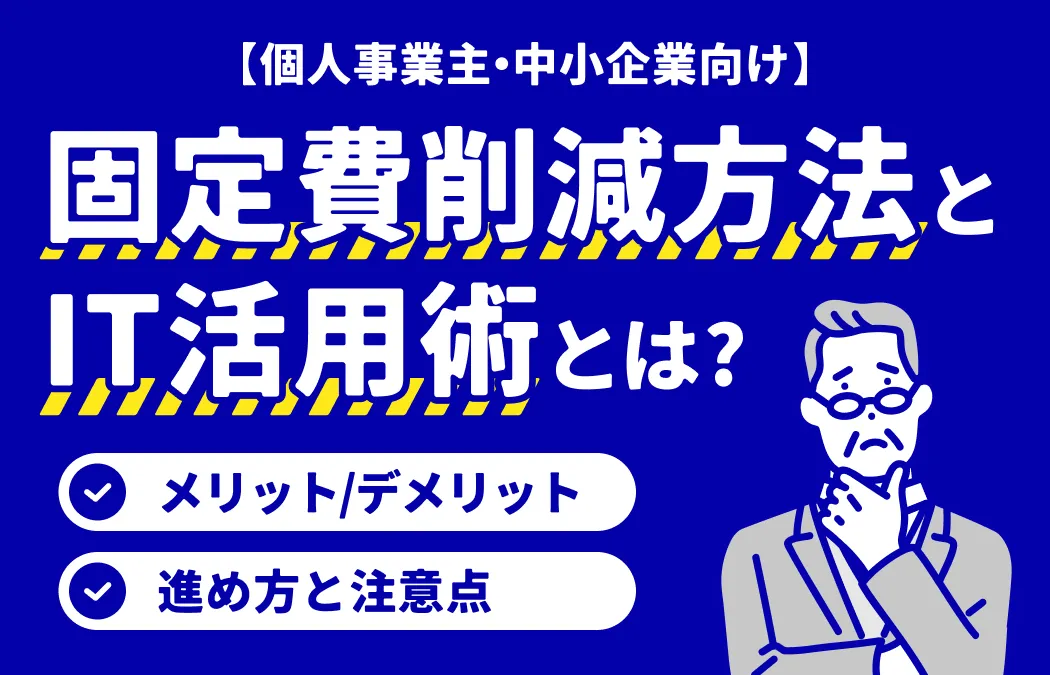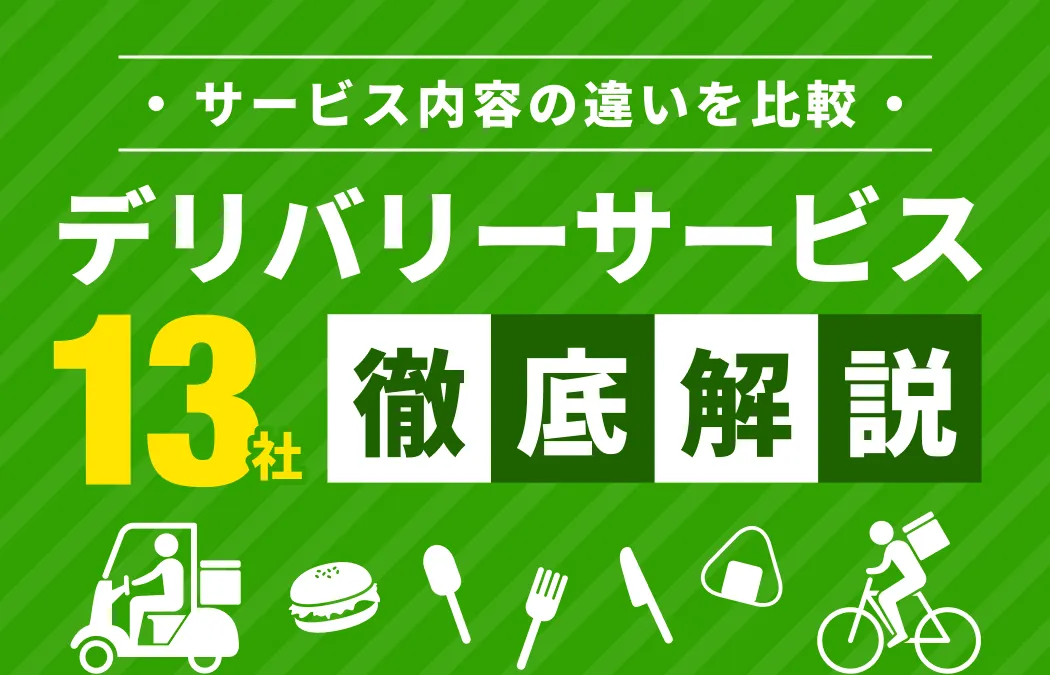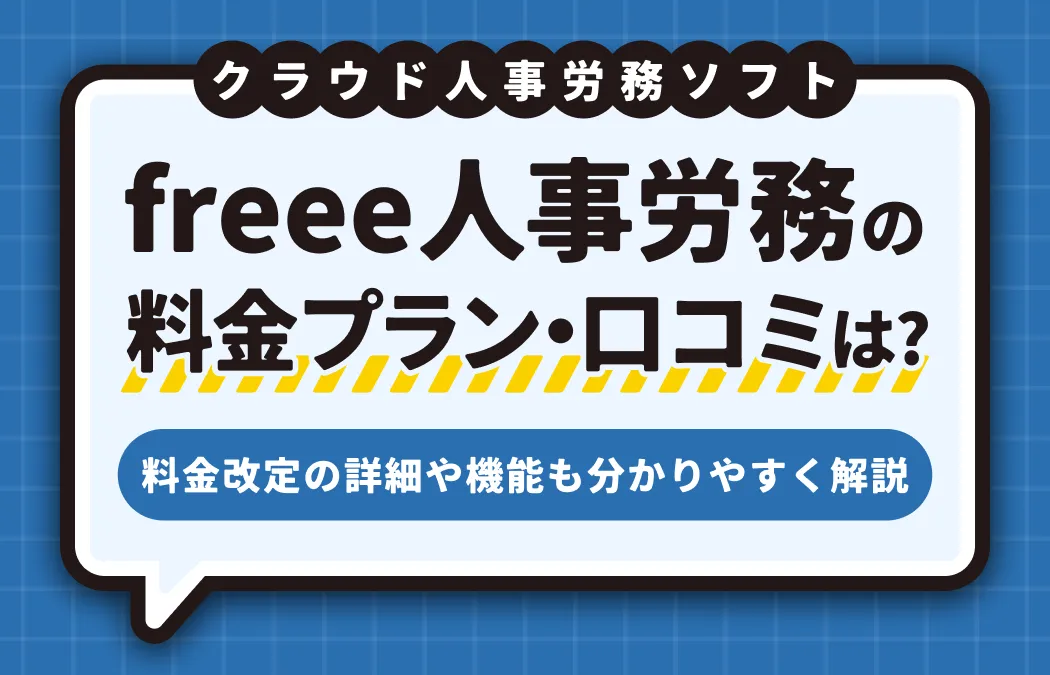「原価率の目安は何パーセント?」
原価率は、商品やサービスの売上に対して原価がどの程度を占めているかを示す重要な経営指標です。
飲食店や小売業では、適正な原価率を把握することで価格設定や利益確保の精度が大きく変わります。
しかし、原価率が高くなる要因を見落とすと、思わぬ赤字や経営悪化を招くリスクもあります。
本記事では、原価率の基本から計算方法、業態別の目安、高くなる原因と改善策まで、わかりやすく解説します。
目次
原価率とは「売上に対して原価が占める割合」
原価率とは、 売上高のうち仕入や材料費といった原価がどの程度を占めているかを示す指標 です。
飲食店や小売業などでは、メニューや商品ごとに原価率を把握することで利益の確保や価格設定の妥当性を判断するのに役立ちます。
数値化することで「どの商品が利益を押し上げているか」「どの商品が負担になっているか」が明確になり、経営改善の重要な基礎情報として活用できます。
原価率を把握するメリット
利益の管理がしやすくなる
原価率を定期的にチェックすることで、売上に対してどれだけ利益が確保できているかを把握できます。
特に利益率の低下にいち早く気づければ、 すぐに仕入先の見直しやメニュー価格の調整、ロス削減などの具体的な改善策を講じることが可能 です。
結果として赤字拡大を防ぎ、固定費を差し引いた後でも利益を確保しやすくなります。
粗利段階で収益性を管理できるので、安定した経営判断と長期的な成長を実現できます。
原価が妥当かどうか確認できる
原価率を把握することで、市場価格や仕入れ価格の変動を踏まえて、 自社の商品やサービスの原価が適正かどうかを検証 できます。
例えば同業他社と比較して原価率が高すぎる場合は、仕入れ条件の見直しや業者交渉が必要になります。
逆に低すぎる場合は品質低下や顧客満足度の低下につながる恐れもあり、バランスの取れた判断が欠かせません。
コスト削減の判断につながる
原価率を把握することは、コスト削減の優先順位を決める基準にもなります。
どの商品やサービスが過剰なコストを生んでいるかを見極めることで、 不要な経費を抑えつつ収益性を維持できます 。
単純なコストカットではなく、顧客満足を損なわない範囲での最適化が可能となり、持続的な利益体質の構築につながります。
原価率は高い方がいい?低い方がいい?
原価率は一概に高い・低いで良し悪しを判断できません 。
低ければ利益は確保しやすいですが、販売価格が高すぎると割高感を与え、サービスの質が低いと見なされて顧客離れにつながります。
一方で原価率が高い商品は利益率こそ低いものの、品質の高さや付加価値を伝える手段となり、リピーター獲得につながるケースもあります。
重要なのは業種や戦略に応じて「最適な原価率」を設定し、利益と顧客満足度の両立を図ることです。
原価率と利益率、粗利率、掛け率、値入率の違い
| 指標 | 定義 | 計算式 | 具体例 (販売価格1,000円・原価300円) |
活用シーン |
|---|---|---|---|---|
| 原価率 | 売上に対して原価が占める割合 | 原価 ÷ 売上 × 100 | 300 ÷ 1,000 × 100 = 30% |
商品の価格設定や利益確保の目安 |
| 利益率 | 売上に対する最終的な利益の割合 | 利益 ÷ 売上 × 100 | 700 ÷ 1,000 × 100 = 70% |
事業全体の収益性の確認 |
| 粗利率 | 売上から原価を差し引いた粗利の割合 | (売上 − 原価) ÷ 売上 × 100 | (1,000 − 300) ÷ 1,000 × 100 = 70% |
商品やサービス単位の収益力分析 |
| 掛け率 | 仕入原価に対する販売価格の倍率 | 販売価格 ÷ 仕入原価 | 1,000 ÷ 300 = 3.33倍 |
小売・卸売での価格交渉や仕入判断 |
| 値入率 | 販売価格に占める利益の割合 | (販売価格 − 仕入原価) ÷ 販売価格 × 100 | (1,000 − 300) ÷ 1,000 × 100 = 70% |
仕入時点での利益計画や価格戦略 |
これらの指標を正しく理解し使い分けることで、価格戦略や収益構造を的確にコントロールできます。
原価率の計算方法
販売価格1,000円の商品に対して原価が300円の場合
300円 ÷ 1,000円 × 100 = 原価率30%
原価率は上記の式で求められます。原価率を把握することで、 商品価格の適正さや利益の確保状況が明確に なります。
飲食店や小売業では、原価率の目安を決めておくことで、メニュー設計や仕入れ判断が効率的に行えます。
複雑に感じる計算も、基本の公式さえ覚えれば誰でも簡単に実践可能です。
原価率と合わせて確認したい数値
原価率だけでは利益の全体像を正確に把握できません。飲食店や小売業の経営改善には、ロス率や歩留まり、FLコストなど関連する指標も併せて確認することが重要です。
これらを 総合的に管理することで、売上だけでなく無駄の削減や利益率向上につながります 。
原価率はあくまで一つの基準であり、関連数値を組み合わせてこそ精度の高い経営判断が可能になります。
ロス率
ロス率とは、 仕入れた食材や商品が廃棄・劣化などで売上につながらなかった割合を示す指標 です。ロス率の計算式は以下の通りです。
原価率が理想的でも、ロス率が高ければ実際の利益は減少します。特に飲食店では、食材の在庫管理や発注精度の低さがロス率上昇の要因となります。
ロス率を定期的に確認し、仕入れ量や保存方法を改善することで、原価率の数値と実際の利益率の差を最小限に抑えることができます。
歩留まり
歩留まりとは、 仕入れた食材や原材料のうち、実際に使用できる割合を示す数値 です。歩留まりの計算式は以下の通りです。
例えば魚や肉では、骨や皮を取り除いた後の可食部分が実際の歩留まりとなります。
原価率の計算で仕入れ価格だけを基準にすると、実際よりも収益性を高く見積もってしまう危険があります。
歩留まりを正しく把握すれば、適正な価格設定が可能になり、原価管理の精度を高めることができます。
FLコスト
FLコストとは、 Food(食材費)とLabor(人件費)を合計した指標 で、飲食店の経営健全性を測る重要な基準です。FLコストの計算式は以下の通りです。
原価率が適正でも、人件費が膨らめば利益は圧迫されます。一般的にFLコストは売上の60%以内が理想とされ、これを超えると黒字経営が難しくなります。
原価率とあわせてFLコストを確認することで、店舗運営全体の収益性をより的確に把握できます。
経理業務システム化で人件費を削減!
【無料】freee会計の導入相談はこちら原価率の目安
企業規模別の原価率の目安
| 企業規模 | 原価率 |
|---|---|
| 個人企業 | 46.1% |
| 5人以下 | 66.2% |
| 5~20人 | 71.9% |
| 21~50人 | 75.1% |
| 50人以上 | 78.1% |
業界別の原価率の目安
| 業界別 | 原価率 |
|---|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | 36.68% |
| 情報通信業 | 52.40% |
| 不動産、物品賃貸業 | 53.66% |
| 小売業 | 69.58% |
| 建設業 | 76.13% |
| 製造業 | 79.27% |
| 卸売業 | 84.88% |
| 運輸業、郵便業 | 76.51% |
| 学術研究、 専門・技術サービス業 | 43.17% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 58.67% |
| サービス業 (他に分類されないもの) |
58.34% |
飲食店の原価率は30%前後が理想的
| 業態 | 理想的な 原価率の目安 |
特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 居酒屋・大衆店 | 25〜30% | 客単価は低めでも回転率で利益を確保。原価率は抑えつつボリューム感を重視。 |
| カフェ・軽食店 | 20〜25% | 原価率を低く抑えやすい。ドリンクやデザートで利益率を確保する戦略が多い。 |
| レストラン (中価格帯) |
30〜35% | 料理の質と価格のバランスを重視。一般的な飲食店での標準的な目安。 |
| 高級レストラン | 35〜40%以上 | 高品質食材やブランド価値を重視。原価率は高めでも客単価で十分に利益を確保。 |
飲食店経営では、 一般的に原価率30%前後が理想 とされています。25%を下回ると品質低下や割高感につながる恐れがあり、逆に35%を超えると利益が圧迫されやすくなります。
もちろん、居酒屋やカフェ、レストランなど業態によって適正値は異なりますが、目安を30%前後に設定することでバランスの取れた経営が可能です。
売上規模や回転率と合わせて調整することが、長期的な収益確保につながります。
-
原価率が高いもの、低いもの
-
原価率の高い食べ物・飲み物 原価率の低い食べ物・飲み物 - ハンバーガー
- 刺身
- アイスクリーム
- 日本酒
- ビール
- ワイン など
- フライドポテト
- ショートケーキ
- 餃子
- 冷奴
- ソフトドリンク
- カクテル
- ウーロンハイ
- テキーラ など
原価率が高くなる原因
- 販売価格が低い
- 仕入価格が高い
- ロス率が高い
- 原価率の低い商品の売上が少ない
販売価格が低い
販売価格を過度に下げてしまうと、 原価に対する売上比率が小さくなり、原価率は高まります 。
集客目的で安価に設定したメニューでも、利益を圧迫するリスクがあります。
値下げ戦略を取る場合は、客単価や他商品の注文率とのバランスを見極めることが重要です。
安売り競争に巻き込まれると持続的な経営が困難になるため、適正な価格設定が求められます。
仕入価格が高い
仕入価格の上昇は、直接的に原価率を押し上げます。特に 食材や原材料は季節や市場の需給で価格変動が大きく 、経営に大きな影響を与えます。
仕入先の見直しや仕入量の調整、複数業者との比較検討を行うことで、コスト抑制が可能です。
安さだけを重視せず、品質や安定供給とのバランスを考えることも、長期的な経営安定につながります。
ロス率が高い
仕入れた食材や商品が廃棄される割合を示す「ロス率」が高い と、原価率は実質的に上昇します。
飲食店では、過剰な仕入れや在庫管理の甘さ、オペレーションの不備がロスの原因となります。
廃棄を減らすには、需要予測の精度向上や仕入れの適正化が欠かせません。
なお、ロス率を下げることは、原価率改善だけでなく利益率アップや環境負荷削減にもつながります。
原価率の低い商品の売上が少ない
原価率が低い商品は利益を確保する上で重要ですが、それらが売れていないと全体の原価率は高まります。
例えば、 飲食店でドリンクやサイドメニューの注文が少ない場合、メイン料理の原価率が経営を圧迫する ことがあります。
販売促進策としてセットメニュー化やキャンペーンを活用し、原価率の低い商品を効果的に販売することで、店舗全体の収益性を改善できます。
原価率を下げる方法
- 仕入先や仕入量を見直し、廃棄ロスを減らす
- オーバーポーションをなくす
- 製造工程を見直す
- 売上構成を見直す
- 在庫管理方法を見直す
- メニュー全体を見直す
L 商品・サービスの種類を減らす
L 販売・メニュー価格を見直す
L メニューを改良し付加価値をつける
L 原価率が低い商品・サービスを開発する
L 原価率の異なる商品をセットで売り出す
仕入先や仕入量を見直し、廃棄ロスを減らす
原価率を下げる際、 仕入先を複数比較し、より有利な条件を選ぶことで仕入価格を抑えられます 。
また、需要に応じた仕入量を管理することで廃棄ロスを減らし、実質的な原価率を下げられます。
特に飲食店では、発注サイクルの見直しや在庫の適正在庫化が効果的です。仕入れとロスは直接的に利益に影響するため、定期的な見直しが欠かせません。
オーバーポーションをなくす
飲食店において、料理の提供量が過剰になる「オーバーポーション」は気づかぬうちに原価率を押し上げる原因です。
標準レシピを明確にし、スタッフ全員で分量を徹底しましょう。盛り付けや計量を統一することで食材の無駄を削減でき、品質の均一化にもつながります。
顧客満足度を保ちつつ、適正量での提供を行うことで、効率的な原価管理が可能となります。
製造工程を見直す
調理や製造工程に無駄があると、食材ロスや作業効率の低下につながり、原価率の悪化を招きます。
下処理の仕組みを改善したり 、 半加工品の活用を検討したり することで作業時間と材料ロスを削減可能です。
オペレーションを最適化することで人件費削減にも効果があり、結果的にFLコスト全体の改善につながります。
在庫管理方法を見直す
在庫管理が不十分だと、食材の劣化や廃棄が増え、原価率を押し上げます。
システムを導入して入出庫を管理したり 、 先入れ先出しを徹底したり することで無駄を減らしましょう。
また、在庫回転率を意識し、余剰在庫を抱えない仕組みを整えることも重要です。
効率的な在庫管理はロス削減だけでなく、キャッシュフロー改善にも直結し、経営の安定性を高めます。
売上構成やメニュー全体を見直す
商品・サービスの種類を減らす
商品やサービスが多すぎると、仕入れや在庫管理が複雑化し、ロス率増加や原価率上昇の原因となります。
ラインナップを絞り込むことで、 仕入れコストの一括交渉が可能になり、効率的な在庫管理が実現可能です。
また、メニュー数を減らすことで調理工程が簡素化し、オペレーション効率も向上します。
厳選した商品を提供することで、品質維持と収益性の改善を両立できます。
販売・メニュー価格を見直す
販売価格が低すぎると、原価率が高まり利益を圧迫します。市場価格や競合との比較を行い、 自社の商品価値に見合った適正な価格に設定することが重要 です。
値上げを行う際には、量や品質、サービス面で付加価値を訴求することで顧客の納得感を高められます。
価格戦略を見直すことは、原価率改善だけでなく、ブランドイメージ強化にもつながります。
メニューを改良し付加価値をつける
原価率を下げつつ顧客満足度を維持するためには、単純なコスト削減ではなく付加価値の提供が効果的です。
食材の組み合わせを工夫したり 、 調理法や盛り付けを改善したり することで、価格以上の価値を感じてもらえます。
また、少量の高原価食材をアクセントとして活用する方法も有効です。付加価値を高めることで、価格調整や利益率改善がスムーズになります。
原価率が低い商品・サービスを開発する
原価率を下げるためには、利益率の高い商品やサービスを新たに開発することも有効です。
例えば飲食店であれば、 原価率が低いドリンクやデザートを強化する ことで、全体の収益性を高められます。
小売業では、仕入れコストを抑えたオリジナル商品を開発する方法もあります。
戦略的に低原価の商品を組み込むことで、店舗全体の原価率を調整しやすくなります。
原価率の異なる商品をセットで売り出す
原価率の高い商品と低い商品を組み合わせて販売することで、全体の原価率をコントロールできます。
例えば、飲食店では 高原価のメイン料理に対して、低原価のドリンクやサイドメニューをセット化する ことで利益を確保しやすくなります。
セット販売は、お得感を演出しながら利益率を安定させられる点が魅力です。バランスを意識した商品構成は、原価率改善と顧客満足の両立を可能にします。
原価率を考慮する際の注意点
- 店舗全体の平均で捉える
- 人気商品は原価率が高くても維持する
- お客様に割高感を与えないようにする
- 品質低下を招かないよう注意する
- 原価率(食材費)以外のコスト削減にも取り組む
店舗全体の平均で捉える
原価率は商品ごとに差がありますが、 重要なのは店舗全体での平均値 です。
あるメニューで高い原価率でも、他の商品で低く抑えられれば、全体として利益を確保できます。
個別の商品にこだわりすぎると経営判断を誤る恐れがあるため、売上構成比と合わせて店舗全体の視点で数値を確認することが安定した経営につながります。
人気商品は原価率が高くても維持する
集客の柱となる人気商品は、多少原価率が高くても販売を維持することが有効です。 看板商品は顧客を呼び込み、他の商品購入につながる効果が期待できます 。
原価率だけを理由に削ると、来店動機が失われ売上減少のリスクも高まるため、戦略商品としての位置づけを意識し、他のメニューでバランスを取ることが賢明な経営判断です。
お客様に割高感を与えないようにする
原価率を下げようと価格を高く設定しすぎると、顧客に「コスパが悪い」という印象を与えてしまいます。
価格に見合った品質やサービスを提供できなければリピート率は下がり、長期的な売上減少につながりかねません。
価格と満足度のバランスを常に意識し、 顧客が納得できる価値を提供することが重要 です。
品質低下を招かないよう注意する
コスト削減を優先するあまり、食材やサービスの質を落とすと顧客離れを招く恐れがあり、かえって逆効果です。
原価率が多少高くても、 品質を維持することで顧客満足度が高まり、結果としてリピーターや口コミ増加につながる ケースも多くあります。
短期的な削減より、長期的なブランド価値を守ることが持続的な利益に直結します。
原価率(食材費)以外のコスト削減にも取り組む
経営改善には、食材費だけでなく人件費や光熱費などの固定費削減も重要です。
例えばシフト管理の最適化や省エネ設備の導入は、原価率に影響を与えずに利益率を改善できます。
原価率だけに注目するのではなく、 FLコストや営業経費全体を俯瞰して最適化を進める ことで、無理のない収益改善が実現可能となります。
販売価格の決め方
| 特徴 | 計算式 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|---|
| 原価(コスト) から考える |
商品の原価に対する比率を基準に販売価格を設定する方法 | 販売価格 = 原価(仕入価格)÷ 原価率 |
|
|
| 利益率を計算してから決める | 事前に利益率を算出し、商品販売時に確保したい利益額を基準に価格を決める方法 | 販売価格 = 原価(仕入価格)÷(1 − 利益率) |
||
| 市場ニーズや競合と比較して決める | マーケティング戦略の観点を取り入れて設定する販売価格の決め方 | ー |
|
|
販売価格を決める際の注意点
顧客の立場から考える
販売価格を決める際は、企業側の都合ではなく 「顧客がその価格に価値を感じるか」を基準にすることが重要 です。
価格が高すぎると購入意欲を失わせ、安すぎると品質への不安やブランド価値の低下を招きます。
顧客の視点を取り入れ、サービスや商品の魅力を伝えながら納得感のある価格を提示することが、長期的な信頼とリピートにつながります。
市場相場とかけ離れていないか確認する
市場価格や競合の設定と大きく異なる価格は、顧客に違和感を与えます。
相場より高ければ「割高感」、低すぎれば「安売りのイメージ」がつき、ブランド価値に悪影響を及ぼしかねません。
自社の強みや付加価値を明確にした上で、 相場と乖離しすぎない適正価格に設定することが重要 です。
市場調査を継続的に行い、価格戦略を柔軟に見直す姿勢も求められます。
初期設定の価格を過度に低くしない
新商品や新サービスを投入する際、顧客獲得を狙って価格を低く設定しすぎるのは危険です。
一度定着した低価格は後から値上げが難しく 、利益を圧迫する要因になります。
初期段階から適正な価格を設定し、必要であればキャンペーンや限定割引で集客する方が効果的です。
長期的に利益を確保できる価格設計こそが、持続的な成長の鍵となります。
コスト削減による利益最大化をめざすなら会計ソフト導入がおすすめ

コスト削減による利益最大化をめざすなら、クラウド会計ソフト「freee会計」が有効です。
経費精算や仕訳作業を自動化でき、人的コストを削減しながら会計処理の精度を高められます 。
数字をもとにした経営判断がスピーディに行えるため、無駄を省いて収益性を高めたい中小企業や店舗経営に最適です。
会計知識がなくても直感的に操作できる点も大きな魅力です。
【無料】お問い合わせはこちら原価率に関するよくある質問
A
高原価でも客単価を上げたり、回転率を高めれば利益を確保できます。
看板商品の価値を打ち出し、他メニューで利益率を補う戦略が有効です。
A
原価は仕入や製造にかかった実際の費用で、原価率は売上に対する原価の割合です。
混同しやすいですが、経営分析において別物として扱う必要があります。
まとめ
原価率は、売上に対する原価の割合を示す重要な経営指標です。
計算方法を理解し、業態別の目安を把握することで適正な価格設定や利益確保につながります。
原価率が高くなる原因には、仕入価格の上昇やロス率の増加などがあります。
改善には仕入や在庫管理、メニュー戦略の見直しが有効です。原価率を正しく活用し、持続的な利益最大化を目指しましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!
人気記事ランキング
関連記事
スポンサーリンク