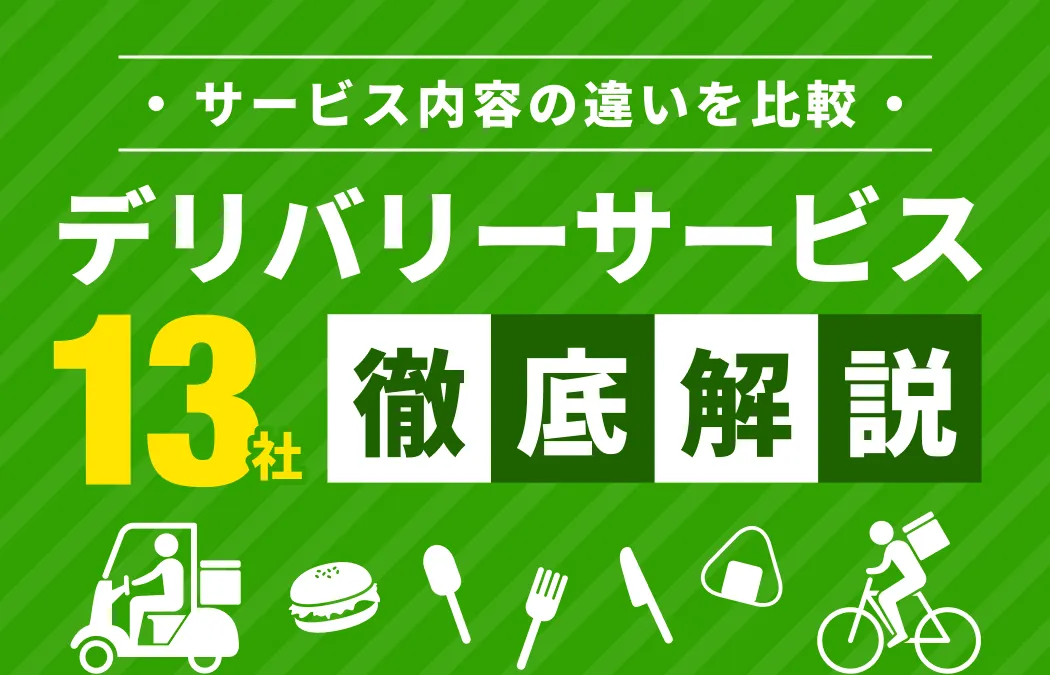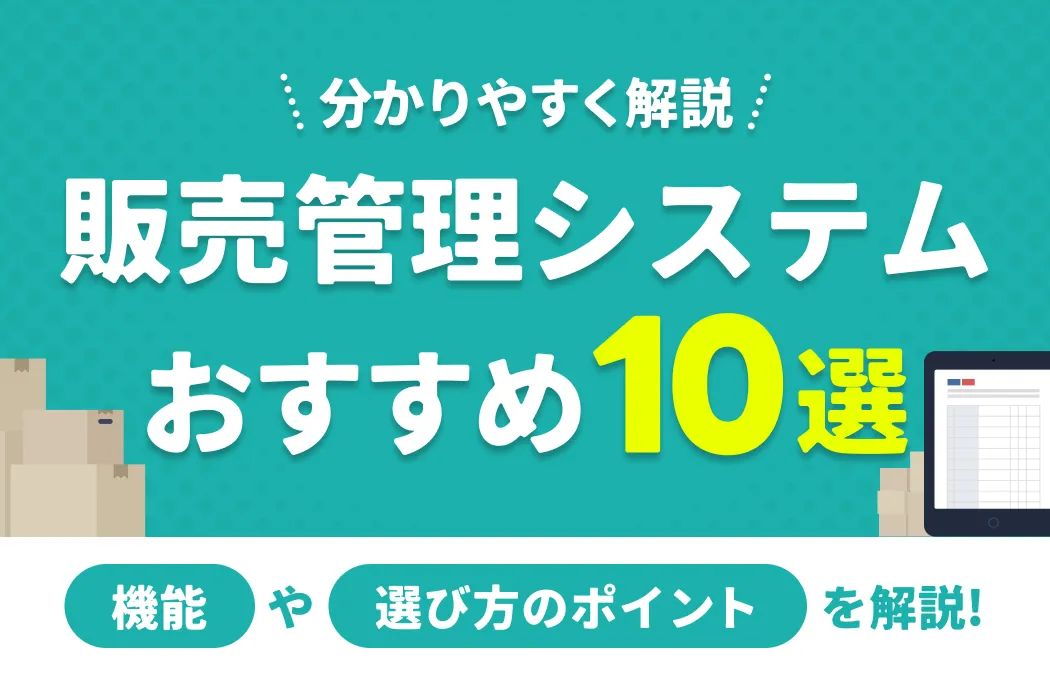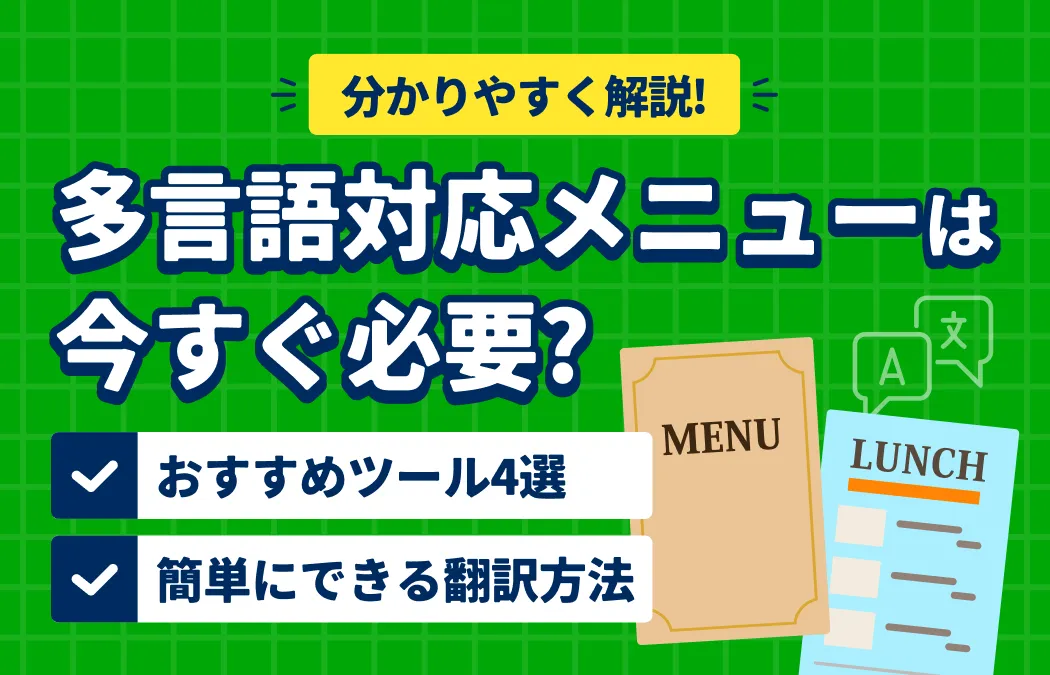観光地の小売店を営む中で、ふと感じたそんな実感。
クレジットカードには対応しているけれど、スマホ決済でスッと買い物を済ませたいという声に応えきれていないのが現状ではないでしょうか。
中でも利用率の高い「WeChat Pay」は、訪日中国人にとって当たり前の決済手段。導入するだけで、取りこぼしていた売上を確実にキャッチできます。
本記事では、WeChat Payの基本的な仕組みから、小規模店舗でも導入しやすい方法、実際のメリット・費用感までをわかりやすく整理。記事の最後では、自店に合った導入方法の無料相談先も紹介しています。
目次
WeChat Pay(ウィーチャットペイ)とは
WeChat Pay(ウィーチャットペイ)とは、 中国のIT大手テンセントが提供するモバイル決済サービスで、SNSアプリ「WeChat(微信)」に組み込まれている決済サービス です。
ユーザーは銀行口座やクレジットカードと連携させることで、スマートフォンひとつで買い物や送金、公共料金の支払いまで完結できます。中国国内では圧倒的な普及率を誇り、訪日中国人観光客の多くも利用しているため、日本国内の店舗でも導入が進んでいます。
特に小売業や飲食業では、インバウンド需要を逃さないための重要な決済手段です。
WeChat Pay(ウィーチャットペイ)のユーザー数
「WeChat Pay」は、2013年から中国でサービスを開始し、ユーザー数は8.9億人以上を突破、中国国内で広く認知されている決済サービスです。
日本国内でもドラックストアやコンビニ、百貨店、家電量販店をはじめ既に1,000店舗以上で利用されています。
WeChat Pay(ウィーチャットペイ)の特徴
多くのユーザー数を誇るWeChat Payは、どのような特徴があるのでしょうか。
SNSを強みとしている
WeChat Payは、SNS機能を活かして情報拡散が可能です。WeChat上では、写真や口コミが活発にシェアされており、WeChat Payからお得な情報やユーザーの口コミも知ることができます。
日本にくる中国人観光客は日本のお店の情報が多くない中、こういったお得な情報や口コミを見ることで集客効果が期待できます。
日本人でも利用できる
WeChat Payは中国人向けに作られているQRコード決済サービスになりますが、日本人でも中国の旅行などで利用しやすい機能が組み込まれています。
機能としては、日本語を含む20以上の言語に対応しており、iPhoneやAndroidでも利用できるようになっています。中国語を覚えなくても日本語でスムーズに登録や決済を行うことができます。中国では、QRコード決済サービスを導入している店舗が多いので、WeChat Payを持っておくだけで支払いが簡単になります。
あらゆる支払いが可能
WeChat Payはスマホで行うQRコード決済だけでなく、中国国内のあらゆる支払いを行うことができます。
支払いは、オンライン決済・割り勘・公共料金の支払い・個人間送金・投資まで全てWeChatで完結することができ、中国では交通違反の罰金にまでWeChat Payを利用することができます。
》マルチ決済「Star Pay(スターペイ)」でQRコード決済30種類に一括対応
Alipay(アリペイ)とWeChat Pay(ウィーチャットペイ)の比較
中国で2大決済サービスといわれている「Alipay(アリペイ・支付宝)」と「WeChat Pay(ウィーチャットペイ・微信支付)」。「Alipay」を運営しているアリババと「WeChat Pay」を運営しているテンセントが、モバイル決済市場全体の9割を占めていると言われています。
それぞれ、どのような違いがあるか明らかにいていきます。
・ユーザー数
Alipay:約12億人(2019年6月時点)
WeChat Pay:8億人以上(2019年3月時点)
・市場シェア率
Alipay:53.78%
WeChat Pay:38.87%(2018年第4四半期)
Alipayは、2010年にアリババ傘下のショッピングサイトであるタオバオの決済手段として誕生しました。タオバオは中国版のAmazonとも呼ばれる有名なショッピングサイトで、多くの中国人が利用しています。Alipayの拡大は、ショッピングサイトのユーザーを取り込んだことが最大の理由と考えられます。
一方、ライバルのWeChat Payは先ほどお伝えした通り、中国最大のチャットサービスであるWeChatに付随した決済サービスになります。
WeChat Payは2013年にサービスを開始し、Alipayから約10年遅れで登場したにも関わらず、市場シェア率は中国内のモバイル決済市場で2位を誇っています。
WeChat Payは、SNSのプラットフォームのユーザーをターゲットにしたことで、ここまでの短期間で拡大をしていると考えられます。
大手ショッピングサイトであるタオバオを運営するアリババは提供しているAlipayは、ネットショッピングなどのオンラインをの場を得意とし、SNSアプリであるWeChatに付随したWeChat Payは、日常生活と密接に繋がり、食事や交通などの日常のシーンで利用する傾向があると考えられます。 また、消費の額でも差があるようで少額の消費ではWeChat Payを利用し、Alipayは比較的大きな金額を支払う際に利用される傾向にあります。
WeChat Payを導入する方法【3つの選択肢を比較】
導入方法①:au PAY(auペイメント)経由で申し込む
KDDIグループの提供する 「au PAY」では、中国QRコード決済であるWeChat Payの取り扱いも可能 です。特にインバウンド対応に積極的な店舗や観光地の事業者に人気があり、WeChat Pay単体の導入が難しいケースでも、au PAY経由でスムーズに導入できるのが特長です。
導入の流れと必要なステップ
au PAY経由でWeChat Payを導入するには、以下のような手順を踏みます。
- KDDIの加盟店契約に申し込む(Webフォームまたは営業経由)
- 申請内容の審査(通常1週間程度)
- 専用端末またはPOSアプリを設定・設置
- 初期設定完了後、WeChat Payを含むQRコード決済が利用可能に
中小規模の事業者の場合、 POSレジに連携せず、スタンドアロン型の決済端末だけで運用するケースも多く 、初期費用やオペレーションの簡略化につながります。
費用・手数料の目安と注意点
WeChat Payの導入にかかる費用感は以下の通りです(※実際の金額は契約条件やキャンペーンにより異なる場合があります)。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 初期費用 | 無料〜30,000円程度 |
| 月額利用料 | 基本無料(条件により発生あり) |
| 決済手数料 | 約3.25%〜(要個別見積) |
この導入方法のメリット・デメリット
- 国内大手のKDDIが運営しており、サポートやセキュリティに安心感
- 他のQRコード決済もまとめて対応可能
- 地域によっては営業担当のサポートがある
- 手続きや審査にやや時間がかかる
- 専用端末を導入する場合、初期コストが発生することも
- WeChat Pay単体の料金プランが明示されにくい(全体契約に含まれる)
導入までのハードルはやや高めですが、 しっかりとした体制を求める法人店舗には最適 です。
どんな店舗に向いている?
以下のような事業者には、au PAY経由でのWeChat Pay導入が向いています。
- 観光地や空港、百貨店など中国人観光客の利用が多い店舗
- 一定の売上規模があり、導入後の手厚いサポートを求める事業者
- QRコード決済を複数まとめて一括管理したい店舗
導入方法②:STORES 決済を活用する
「STORES 決済」は、 小規模事業者にも使いやすいオールインワン型のキャッシュレス決済サービス です。
クレジットカードや交通系ICに加えて、WeChat PayやAlipayといった中国系QRコード決済にも対応、端末ひとつでまとめて管理できる点が特徴です。 Web上で申し込みが完結するため、導入のハードルが低く、スピーディーに使い始められるのも魅力 です。
導入の流れと必要なステップ
STORES 決済でWeChat Payを使うには、以下の手順で導入が可能です。
- STORES 決済の公式サイトからWeb申し込み(法人・個人事業主どちらも可)
- 必要書類(本人確認書類、銀行口座など)をアップロード
- 審査完了後、専用端末が郵送される
- 簡単な初期設定を行い、すぐに利用開始
導入までの 平均所要時間は3〜5営業日程度と非常にスピーディー 。POS連携も不要で、レジ横に端末を置くだけの簡易運用が可能です。
初期費用・月額料金・手数料まとめ
| 費用項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 初期費用 | 0円(キャンペーン中の場合) |
| 月額利用料 | 0円(端末保有のみ) |
| 決済手数料 | 約3.24%〜(決済種別により変動) |
| 対応決済一覧 | WeChat Pay、Alipay、PayPay 他 |
特に 注目すべきは「月額固定費が発生しない」 という点です。ランニングコストが抑えられるため、 売上の波がある業種でも安心して導入可能 です。
STORES 決済のメリット・デメリット
- 初期コスト・月額コストともに抑えやすい
- 申込みがWebで完結し、導入までが早い
- 国内外の主要キャッシュレス決済にまとめて対応できる
- 現金や独自ポイントとの連携はやや弱い
- サポートは基本的にオンライン(電話対応は限定)
この導入方法が向いている店舗は?
- 個人経営の小売店・飲食店・美容院など
- 専門スタッフを配置せずに運用したい事業者
- 海外からの観光客を一部ターゲットにしている事業者
- POSシステムを持っていない、もしくは簡易運用したい業態
特に 初めてQR決済を導入する店舗には、費用面・導入ステップの両面でメリットが多く 、第一歩として最適な選択肢です。
📲 端末ひとつでWeChat Payも!STORES決済で始めるインバウンド対応
導入はすべてオンライン完結。手間もコストも最小限で、すぐにインバウンド対応を始められます。
✅ STORES決済について相談する導入方法③:StarPayを利用して導入する
StarPayは、株式会社ネットスターズが提供する 多機能マルチ決済プラットフォームで、WeChat Pay・Alipayをはじめ、PayPay、メルペイ、クレジットカードなど20種類以上の決済手段に対応可能 です。
インバウンド向けの決済サービスにも強く、中国を含むアジア圏の決済ブランドを専用端末1台で対応可能で、政府機関や大手百貨店でも導入実績があり、信頼性の高い選択肢です。
導入の流れと運用ステップ
- StarPay公式サイトまたは代理店を通じて資料請求・相談
- 利用希望ブランド(WeChat Payなど)を選択し、申込手続き
- 審査完了後、専用端末 or アプリのセットアップ
- 初期設定完了後、即時利用可能
料金・導入コストの目安(参考)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期費用 | 無料〜(キャンペーン適用時) |
| 月額費用 | 0円(売上に応じた手数料型) |
| 決済手数料 | 約3.24%〜(要個別見積) |
| 対応決済 | WeChat Pay、Alipay、PayPay、Visa、Mastercard、交通系IC 他 |
STORES 決済のメリット・デメリット
- 中国決済(WeChat Pay・Alipay)の実績多数
- 国内外ブランド対応で汎用性が高い
- タブレット運用、専用端末、POS連携など柔軟な形態に対応
- サポートは主にオンライン・電話対応(対面導入サポートは限定的)
- 初期導入時にプランの整理が必要(対応ブランドが多いため)
StarPayが向いている店舗
- 幅広いキャッシュレス対応を求める中小企業・個人店舗
- POSや既存端末と併用して柔軟に運用したい店舗
- インバウンド対応を強化したいが、初期コストは抑えたいと考える事業者
WeChat Pay導入後のサポートと運用のポイント
導入後に必要な運用業務
WeChat Payを導入すれば終わりではありません。日々の売上確認、トラブル対応、スタッフ教育など、スムーズな運用のための業務があります。
特にインバウンド対応では、日本人顧客とは異なる対応力が求められるため、事前準備と習慣化が鍵になります。 ここでは、導入後に実際に行うべき主な運用業務を紹介します。
売上管理・入金確認業務
WeChat Payの 売上は、通常「決済後数営業日以内」にまとめて銀行口座に入金 されます。以下のような確認業務を日次または週次でルーチン化しましょう。
| 業務内容 | 頻度 | 方法 |
|---|---|---|
| 売上の確認 | 日次 | 管理画面 or 専用アプリ |
| 入金の確認 | 月数回 | 銀行口座の照合 |
| 手数料の確認 | 月次 | 利用明細ダウンロード |
トラブル時の対応マニュアルの整備
QRコード決済では、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 「決済ができない」と顧客から言われた
- レシートの印字が出ない/表示が消えた
- 売上明細と実際の入金額が異なる
こうしたケースに備えて、トラブル対応フローをあらかじめ紙やマニュアルにまとめておくことが肝心です。
スタッフ教育とリスク共有
WeChat Payの利用は店舗側にとって便利な反面、操作ミスや不慣れな接客によるトラブルリスクもあります。特に、以下のような教育が効果的です。
- 決済手順のデモ研修(動画 or ロールプレイ形式)
- よくあるエラーの見分け方と初期対応
- 外国人顧客対応における基本マナー(簡単な英語 or 中国語のフレーズカードなど)
まとめ
WeChat Payは、訪日中国人観光客への対応を強化したい店舗にとって非常に有効な決済手段です。本記事では、導入方法から運用時の注意点、不安への対策、そして準備すべきチェックリストまでを網羅的に解説しました。
スムーズに導入し、安心して運用を続けるためには、事前の情報収集と社内体制の整備がカギとなります。どの導入方法が最適か迷っている方は、まずは無料相談で自店に合った選択肢を確認してみてください。
※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!