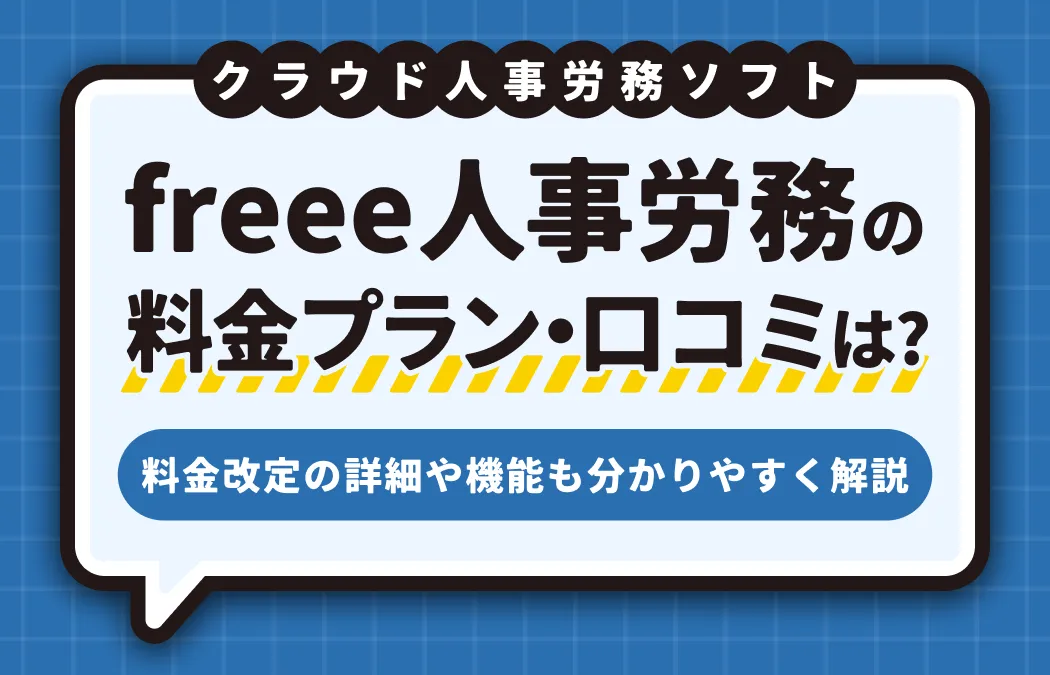「クラウド型とオンプレミス型どっちを選ぶべき?」
会計ソフトを選ぶ際は、導入形態やインターフェース、セキュリティ性、搭載機能など様々なポイントを検討する必要があります。
しかし、「そもそも導入すべきなのか分からない」「どんなメリットがあるの?」といった疑問を抱いている方も多いはずです。
本記事では、会計ソフト選びのポイントから、導入のメリット・デメリット、具体的な選定手順まで、会計ソフトの選び方に悩む初心者の方に向けて、わかりやすく解説します。
目次
会計ソフトの選び方・選定ポイント
クラウド型とインストール型の違いと選び方
会計ソフトには 「クラウド型」と「インストール型」の2種類 があります。企業の業務環境やセキュリティポリシーによって、最適な選択肢は異なります。
クラウド型
- インターネット環境があればどこでも利用可能
- 自動バックアップやアップデート対応
- サブスクリプション料金が中心
- 社内サーバーやPCに直接導入する形式
- オフラインでも操作可能
- 一括購入型が多く、長期的に見るとコストが安定

自社に合った導入形態か
会計ソフトを選ぶ際には、自社の経理業務の複雑さや人員規模を考慮し、必要な機能を明確にすることが重要です。
小規模事業ならばシンプルな機能のクラウド型ソフトが便利ですが、より大規模で複雑な業務がある場合はカスタマイズ可能なオンプレミス型が適しています。
また、 クラウド型は初期コストが低く、更新やセキュリティも自動で管理される ため、運用の負担を減らす利点があります
| クラウド型 | インストール型 | |
|---|---|---|
| 特徴 | インターネット環境があれば利用開始できる、スマホやタブレットなどマルチデバイス対応 | パソコンや自社サーバーにソフトをインストールして利用。 |
| メリット | 運用が手軽、初期費用が安い、データの消失リスクが低い | 一度購入すれば追加費用なく使い続けられる、インターネット環境が不要、カスタマイズ性に優れる |
| デメリット | 月額料金が発生、インターネット環境が必須 | 利用できるデバイスがパソコンに限定され、インターフェースが複雑な場合もある、データ消失のリスクが比較的高く、法改正への対応は別途バージョンアップが必要 |
自社の事業規模や業界に合っているか
会計ソフトを選ぶ際には、自社の事業規模や業界に適しているかをよく考慮することが大切です。
- 小規模企業や個人事業主:基本的な会計処理が手軽にできるシンプルなソフトが適していますが、
- 中小規模以上の企業や多くの取引を扱う業界:より高度な分析機能や複雑な会計処理に対応するソフト
個人事業主の場合、 シンプルで直感的な操作ができるクラウド型の会計ソフトがおすすめ です。freeeやマネーフォワードは青色申告にも対応しており、スマホでも仕訳やレシート登録が簡単にできます。
法人の場合は、 複数人での同時アクセスや仕訳承認機能が求められる こともあり、マネーフォワードや弥生のビジネスプランはこの点に強みがあります。
担当者のスキルに合った仕様か・使いやすいUIか
会計ソフトを選ぶ際、担当者のスキルに合った仕様や使いやすいUI(ユーザーインターフェース)も重要なポイントです。
初心者や経理業務に不慣れな担当者が使う場合、直感的な操作が可能で、複雑な知識を要さないソフトが適しています。
具体的には、 入力フォームが分かりやすく、ボタン配置が工夫されているなど、操作性が高いものが望ましい です。
さらに、頻繁に使用する帳簿やレポートへのアクセスが簡単で、エラーを防ぐチェック機能が搭載されていると安心です。
一方、経理に関する専門知識を持つ担当者がいる場合は、高度な機能やカスタマイズ性が求められることもあります。

編集部
担当者のスキルや使用頻度に応じたUI設計のソフトを選ぶことで、効率的かつ正確な業務が可能になります。
サポート体制は充実しているか
会計ソフトは法改正や業務内容の変化に伴い、操作や設定の調整が必要となるため、適切なサポートが不可欠です。
例えば、 トラブル発生時に迅速に対応してくれる電話やチャットサポートがあるか、専門的な質問に対応できる担当者がいるか などを確認しましょう。
また、サポートの対応時間や、公式ウェブサイトにあるFAQやマニュアルの充実度も重要です。
さらに、アップデートや新機能についてのトレーニングが提供されていると、担当者のスキル向上にも役立ちます。
サポート体制が整っているソフトを選ぶことで、トラブル対応の負担を軽減し、安心して業務を進められる環境が得られます。
バージョンアップに対応しているか
税制や会計基準は頻繁に改正されるため、 ソフトが最新の法規制に対応できるように定期的なアップデートが必要 です。
特に、クラウド型会計ソフトは自動でバージョンアップされることが多く、常に最新機能や法改正への対応が反映されるため、担当者が手動でアップデートする手間が省けます。
一方、パッケージ型のソフトの場合、アップデートの提供頻度や料金がどうなっているか、また新しいバージョンのインストールが簡便かも考慮する必要があります。
バージョンアップ対応がしっかりしたソフトを選ぶことで、法令遵守が容易になり、長期的に安定した会計業務の運用が可能になります。
自社の顧問税理士や会計士の利用ソフトとデータ共有ができるか
会計ソフトを選ぶ際には、 自社の顧問税理士や会計士が使用しているソフトとデータ共有が可能か も重要な選定ポイントです。
顧問税理士や会計士が自社と異なるソフトを使用している場合、データをエクスポートやインポートする際に手間がかかり、データの整合性が失われるリスクがあります。
一方で、データ共有がスムーズに行えるソフトを選ぶと、帳簿や財務データを直接確認してもらいやすくなり、やり取りの時間を短縮できます。
また、クラウド型の会計ソフトはインターネット経由でリアルタイムにデータを共有できるため、担当者と顧問税理士が随時データにアクセスし、迅速なアドバイスを得られるという利点もあります。
無料のお試し期間はあるか
無料のお試し期間が提供されていると、 実際にソフトを操作しながら、自社のニーズに合っているか、使いやすいかを見極めることが可能 です。
また、実際に業務で使用する担当者が事前に操作感を体験できるため、導入後のミスや操作の戸惑いを減らすことにもつながります。
さらに、お試し期間中にサポート体制や機能の充実度、他のシステムとの連携状況などもチェックできます。
特にクラウド型ソフトは、インストール不要でウェブ上から気軽に試せるものが多いため、積極的に利用してみると良いでしょう。
必要な機能がそろっているか
自社の経理業務の内容や将来の拡張性も考慮し、必要な機能が過不足なく揃っているソフトを選ぶ ことが、長期的な活用において重要です。
-
仕訳入力・帳簿作成:会計ソフトの基本機能
-
売掛・買掛管理、資産管理、部門別損益計算:規模が大きい企業や複雑な経理処理が必要な業種は必要
-
税制改正や法令対応の自動更新機能:法令変更に合わせて迅速に対応でき、コンプライアンスの維持に役立つ
-
他の業務ソフトとデータ連携できる機能:データの二重入力を防ぎ、業務効率が向上
クラウド型会計ソフトの比較|freee・マネーフォワード・弥生
| ソフト名 | 特徴 | 対応プラン | 電帳法対応 | 価格帯(月額) | 無料プランの有無 | おすすめの人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freee会計 | クラウド型。UIがシンプルで、初心者でも直感的に使える | スターター/スタンダード/プレミアム | ◎ | 約1,480円〜 | あり(お試し) | 会計ソフトが初めての人/スマホ重視 |
| マネーフォワードクラウド会計 | 自動連携・帳簿処理の機能が豊富。上級者にも対応 | パーソナル/パーソナルプラス | ◎ | 約1,280円〜 | あり(30日間無料) | 確定申告に慣れていて、効率重視の人 |
| やよいの青色申告 オンライン | 安価で必要機能がそろっており、税理士との連携にも強い | セルフプラン/ベーシックプラン | ◎ | 約2,000円〜 | あり(初年度無料) | コスパ重視/青色申告だけしたい人 |

freeeとマネーフォワードの違いを徹底比較!どっちがおすすめ?選び方を解説
freeeとマネーフォワードの個人事業主と法人企業のプランを、それぞれの機能や料金などの項目ごとに徹底比較!
詳しくはこちら予算に合う料金か
会計ソフトには、初期費用や月額・年額料金がかかるものが多く、 導入前に総コストを明確にする 必要があります。
クラウド型ソフトは月額制が主流で、初期費用が抑えられる反面、長期利用した場合に積み重なるコストを考慮することが大切です。
一方、インストール型は一度の購入費用が高めですが、長期間使用する場合にはコストパフォーマンスが良い場合もあります。
また、追加の機能やサポート、アップデートの料金が発生することもあるため、これらの費用も含めて予算に収まるかを確認することが重要です。
動作環境や利用デバイス、OSに適しているか
会計ソフトを選ぶ際には、ソフトが自社の動作環境や利用デバイス、OSに対応しているかを確認することが重要です。
ソフトによっては 特定のOS(WindowsやMacOSなど)やブラウザにしか対応していない場合がある ため、社内で使用しているパソコンやタブレットなどのデバイスに適合するかを事前に調べる必要があります。
クラウド型の会計ソフトは、インターネットに接続できる環境であればOSやデバイスを問わず利用できるものも多く、柔軟性が高いです。
電子帳簿保存法・インボイス制度に対応しているか
会計ソフトを選ぶ際には、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が必須です。
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使えば、改ざん防止や検索機能などの要件を満たし、法的に有効な電子保存が可能になります。
また、インボイス制度(適格請求書保存方式)に対応しているソフトであれば、消費税の仕入税額控除や正確な取引情報の記録が容易になり、制度遵守が実現できます。
これらの法制度に対応したソフトを選ぶことで、 コンプライアンスを確保し、税務調査のリスクを軽減できます 。
- 電子帳簿保存法
▶デジタル化された帳簿や領収書の保存に関する要件を定めた法律。税務署に提出する書類やデータの保存方法を規定しています。 - インボイス制度(適格請求書保存方式)
▶2023年に開始され、適格請求書の発行・保存が義務化されました。
他システムと連携できるか
会計ソフトが販売管理システムや在庫管理システム、給与計算システムなどとデータ連携できると、 各システム間でデータを自動で共有でき、手作業によるデータの二重入力や入力ミスを防げます 。
また、データの更新がリアルタイムで反映されるため、経営状況を即座に把握しやすくなり、迅速な意思決定にも役立ちます。
さらに、連携機能があることで日々の経理業務が効率化され、担当者の作業負担が軽減されるメリットもあります。
特にクラウド型ソフトではAPI連携などによって幅広いシステムとの接続が可能なものも多いため、自社の既存システムとの互換性も考慮して選ぶと、業務の一貫性と効率性を高めることが可能です。
freee会計やマネフォの導入相談はお気軽に!
【無料】お問い合わせはこちら会計ソフトとは
会計ソフトとは、 企業や個人事業主が日々の取引や財務状況を効率的に管理するためのソフトウェア です。
具体的には、売上や支出の記録、仕訳入力、帳簿作成、試算表や決算書の作成などの機能を備えており、経理作業の手間を大幅に削減します。
従来の紙やエクセルでの記帳に比べて、正確かつ迅速にデータを処理できるため、経理担当者の負担を軽減し、ミスを防止。
さらに、法改正や税制変更にも対応するため、適切な税務処理が可能です。近年ではクラウド型の会計ソフトも多く、インターネット経由でデータの保存・共有が可能で、複数拠点からのアクセスも便利です。

編集部
会計ソフトは、企業の経営判断に役立つ財務データの可視化を実現し、適切な経理運営をサポートするための重要なツールです。
会計ソフトの主な機能
入力支援機能
会計ソフトの入力支援機能は、 入力時に自動補完や候補提示を行い、売上や支出の記録、仕訳入力、帳簿作成などの入力作業を効率化 します
特に、AIによる自動仕訳機能を搭載した最新の会計ソフトでは、領収書やレシートをスマートフォンで撮影するだけで、経費データを自動で取り込むことが可能です。
銀行口座やクレジットカードとの連携機能により、取引データが自動で仕訳されるため、手作業による入力ミスを防ぎ、作業時間を大幅に削減できます。
さらに、過去の仕訳パターンを学習し、類似の取引を自動的に判別する機能も備わっています。
承認申請支援機能
会計ソフトの承認申請支援機能は、 経費精算や支払処理、購買申請などの承認フローを効率化する 機能で、会計業務全体の効率化と透明性の向上に寄与します。
通常、経理処理には上司や管理者の承認が必要な場面が多く、手作業による申請や承認は時間がかかり、ミスが発生しやすくなります。
しかし、承認申請支援機能により、担当者がソフト内で申請内容を入力すると、上司や経理担当者へ自動的に通知が届き、ワンクリックで承認・却下の処理ができるため、処理が迅速化されます。
また、承認状況がリアルタイムで確認できるため、申請がどの段階にあるかが分かりやすく、不正防止や適正な業務運用にも役立ちます。
さらに、承認履歴が記録として残るため、後からの確認や監査対応も容易です。
決済処理支援機能
会計ソフトの決済処理支援機能は、支払い業務を効率化・正確化するための機能です。キャッシュフロー管理や経理の負担軽減にも貢献します。
取引先への支払い日や金額を管理し、期日通りの決済を自動で行う設定ができる ため、支払い漏れや遅延を防ぎます。
また、複数の支払い方法や口座に対応しており、振込手続きや経費の支払いも簡単に実行可能です。
支払い内容はソフト内に記録され、会計データとして自動仕訳されるため、経理担当者が二重入力や入力ミスを避け、精度の高い処理が可能です。
さらに、承認機能と組み合わせることで、支払額の確認や不正防止も徹底されます。
バックアップ機能
会計ソフトのバックアップ機能は、 万が一のデータ消失やシステムトラブルに備えて、会計データを安全に保存・復元する機能 です。
会計データは企業の経営に直結する重要な情報であり、トラブルによる損失を防ぐためにバックアップ機能は不可欠です。
クラウド型ソフトの場合、サーバー上にデータが保存されるため、万一のPC故障や災害時にも安心です。誤ってデータを削除した場合やファイルが破損した際も、バックアップから容易に復元ができるため、業務の継続性を確保できます。

編集部
多くの会計ソフトは自動バックアップ機能を備えており、日次や週次で定期的にデータが保存されます。
制度変更対応機能
制度変更対応機能は、税制改正や会計基準の変更に迅速に対応するための機能です。
会計や税務の制度は頻繁に改正されるため、最新の法規制に適合することが企業のコンプライアンスを守る上で重要です。
制度変更対応機能により、 税率変更や新しい会計処理方法などが自動的に反映される ため、経理担当者が手動で設定を変更する手間が省け、ミスを防ぐことができます。
特にクラウド型ソフトでは、プロバイダー側でアップデートが行われ、常に最新の状態が保たれるため、担当者は法改正への対応にかかる負担を軽減できます。
また、改正内容に関する通知やサポートも提供されることが多く、安心して最新の制度に準拠した会計処理が可能です。

編集部
この機能により、企業は法令遵守を確実にしつつ、安定した経理業務の運用を実現できます。
自動仕訳機能
会計ソフトの自動仕訳機能は、 取引内容に基づいて会計上の仕訳を自動で生成する機能 です。正確で迅速な会計処理が実現し、業務全体の効率向上が図れます。
例えば、銀行取引明細やクレジットカードのデータを取り込むことで、入出金の内容に応じた仕訳が自動的に作成されるため、経理担当者が手作業で入力する手間を大幅に減らせます。
仕訳ルールの設定も可能で、定期的な取引やルーチン業務に対して自動で適切な勘定科目を割り当てられるため、処理が効率化されるだけでなく、入力ミスの防止にもつながります。
また、時間がかかりやすい仕訳入力の作業負担を軽減し、より重要な経理業務にリソースを集中させることが可能です。
明細自動取り込み機能
明細自動取り込み機能は、会計業務の効率化を実現する重要な機能です。 銀行口座やクレジットカードの取引明細を手動で入力する手間が省け、業務の効率化が図れます 。
この機能の利点は、ヒューマンエラーを防止できる点にもあります。手動入力によるミスがなくなるため、正確なデータ管理が実現します。
また、作業時間の節約にもつながり、経理業務にかかる負担を軽減します。
請求書等の書類作成機能
会計ソフトの請求書等の書類作成機能を利用することで、請求書、見積書、納品書などの各種書類を簡単に作成可能です。
通常、あらかじめ書類のテンプレートが用意されており、ユーザーは 取引先名、商品名、金額、消費税などの必要情報を入力するだけで、自動的に計算され、正確な請求書が生成されます 。
また、作成した書類はPDF形式で保存したり、メールで直接送信したりすることができるため、送付や管理の手間を大幅に削減できます。
さらに、取引先ごとに異なる請求書の設定や、定期的な請求書の自動作成機能も備えているソフトが多く、特に定期的な取引がある企業にとっては非常に便利です。

編集部
会計ソフトの書類作成機能は、業務の効率化だけでなく、正確性や迅速性を向上させるための強力なツールとなります。
会計ソフトでできること

保存が必要な帳簿書類を簡単に作成できる
会計ソフトを導入することで、 法定帳簿や各種伝票の作成が格段に効率化 されます。
従来の手作業による帳簿作成では、計算ミスや記入漏れのリスクが高く、多大な時間も必要でした。
しかし、会計ソフトを活用すれば、取引データを入力するだけで、仕訳帳や総勘定元帳、試算表などの法定帳簿が自動で作成されます。
これにより、経理担当者の作業時間を大幅に削減できるだけでなく、人為的なミスも防ぐことが可能です。
さらに、作成された帳簿を電子帳簿保存法に準拠した形式で保存できれば、税務調査の際にもスムーズな対応が可能です。

編集部
データはクラウド上に安全に保管されるため、紙の帳簿の保管スペースも不要になります。
財務状況を見える化できる
会計ソフトは、企業や個人事業主の財務状況を「見える化」する強力なツールです。
具体的には、 売上や経費、利益といった財務データをリアルタイムで記録・管理 し、月次や年次での収支状況を簡単に把握できます。
例えば、収入と支出の詳細を自動で集計し、損益計算書や貸借対照表といった財務諸表を瞬時に生成可能です。これにより、キャッシュフローや経営の健全性を客観的に分析でき、資金繰りの把握やコスト削減の検討が効率化されます。
また、多くの会計ソフトには視覚的なグラフやレポート機能があり、財務データの変動を直感的に理解できるため、経営判断の迅速化に役立ちます。
会計ソフトの運用形態は3種類
| 運用形態 | 料金形態 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|---|
| クラウド型 | クラウド上で運用されるシステムをインターネット経由で利用 | サブスクリプション方式が一般的 |
|
|
| パソコンインストール型 | 特定のPC端末にシステムをインストールして利用 | 買い切り型が一般的 |
|
|
| オンプレミス型 | 企業内のサーバーにソフトウェアをインストールして運用する | 買い切り型が一般的 |
|
|
クラウド型会計ソフト
クラウド型会計ソフトは、 インターネットを通じてサーバー上にあるソフトウェアを利用する形式 です。
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど様々なデバイスからアクセスでき、いつでもどこでも利用できる利便性が特徴です。
データはクラウド上に保存されるため、端末が故障してもデータは消失しにくいという利点があります。また、バックアップやソフトの更新が自動的に行われ、常に最新機能が利用可能です。
さらに、複数のユーザーが同時にアクセスできるため、リモートワークや外部会計士との共同作業も容易です。
費用面ではサブスクリプション方式が一般的で、初期費用が抑えられ、月額や年額での支払いが可能なため、特に中小企業やスタートアップにとって導入しやすい形式です。
編集部
パソコンインストール型会計ソフト
パソコンインストール型会計ソフトは、 ソフトウェアを特定のパソコンに直接インストールして利用する形式 です。
インターネット環境がなくても利用可能で、情報がローカルに保存されるため、セキュリティの面で安心感があるほか、オフライン環境でも作業ができる点も特徴です。
初期の購入費用は必要ですが、追加コストが少ないため、長期間の使用に適しています。
一方、バックアップの実施やソフトの更新作業が利用者の責任となり、複数のデバイスからアクセスする際には手動でのデータ共有が必要となります。

編集部
また、更新がないとソフトウェアが古くなる可能性があります。
オンプレミス型会計ソフト
サーバインストール型会計ソフトは、 企業内のサーバーにソフトウェアをインストールして運用する形式 です。
社内サーバーで管理するため、インターネットに接続せずに高いセキュリティで運用が可能で、特に機密性が重要な業種に適しています。
また、カスタマイズ性が高く、自社の業務プロセスに合わせた柔軟な設定が可能です。
ただし、導入や運用に高度なIT知識が必要で、初期コストやサーバー維持費、管理負担が大きくなります。

編集部
セキュリティ更新やバックアップも自ら行う必要があります
会計ソフトの導入メリット

業務を効率化し、担当者の負担を軽減できる
会計ソフトの導入により、会計業務が大幅に効率化され、担当者の負担を軽減できます。
例えば、 取引の記録が自動化され、売上や経費のデータ入力が簡単になるため、手作業によるミスが減少 します。
また、会計ソフトはリアルタイムで財務データを集計し、損益計算書や貸借対照表などの帳票を自動で作成できるため、報告業務が迅速に行えます。
さらに、銀行やクレジットカードと連携し、取引情報を自動で取り込み消込作業も簡略化できるため、日常の事務負担が軽減されます。
クラウド型の会計ソフトであれば、複数の担当者が同時にアクセスでき、遠隔地からの作業も可能です。

編集部
会計担当者はより戦略的な業務に集中でき、企業全体の生産性向上に貢献します。
会計上のミスが軽減できる
従来のような、手作業でのデータ入力や計算では、ヒューマンエラーが起こりやすく、特に伝票の転記ミスや計算ミスは財務報告の精度を低下させるリスクがあります。
しかし、会計ソフトでは 売上や経費のデータ入力が自動化され、定型的な計算処理も正確に行われる ため、ミスが減少します。
また、取引情報を銀行口座やクレジットカードと連携させることで、二重入力や入力漏れも防止できます。
さらに、多くの会計ソフトにはチェック機能が備わっており、エラーがあればリアルタイムで通知するため、修正が容易です。

編集部
これにより、正確な財務データが確保でき、企業の信頼性向上にも貢献します。
経費を抑えられる
会計ソフトの導入は、経費削減にも大きく貢献します。
まず、経理担当者の作業時間が短縮されることで、人件費を抑制できます。例えば、月次決算にかかる時間が半分になれば、その分を他の業務に充てることが可能です。
また、クラウド型の会計ソフトを選択することで、サーバー管理やシステム保守にかかるIT関連コストを削減できます。従来型の会計ソフトでは必要だった定期的なバージョンアップ費用も不要です。
さらに、会計ソフトの自動仕訳機能や経費精算機能を活用することで、請求書や領収書の紙の保管コストも削減できます。電子保存により、書類の印刷費や保管スペースの確保が不要になるためです。
加えて、 リアルタイムでの経費分析が可能になることで、無駄な支出の発見や予算管理の最適化も実現 できます。情報を一元管理できる
会計ソフトを導入することで、 売上データ、経費データ、給与データなど、これまで別々に管理していた情報を一つのシステムで統合的に扱える ため、経営状況の把握が容易になります。
重要な財務データが自動で集計・更新されるため、経営者や管理者は常に最新の財務状況を確認でき、現状の分析や将来予測に役立つでしょう。
また、経費精算システムと連携することで、従業員の経費申請から承認、会計処理までをシームレスに管理することが可能です。

編集部
クラウド型会計ソフトを活用すれば、複数の担当者がリアルタイムにデータへアクセス可能なため、遠隔地からでも財務状況を把握・共有できます。これにより、会議や打ち合わせで意思決定を行う際も正確なデータに基づいた判断ができ、迅速な対応が求められるビジネス環境での競争力向上に寄与します。
会計ソフトを導入するデメリット

コストがかかる
会計ソフトの導入には一定のコストが発生するため、特に小規模企業や個人事業主には負担となる場合があります。
クラウド型会計ソフトでは月額・年額のサブスクリプション費用がかかり、利用を続ける限り支払いが必要です。
また、パソコンインストール型やオンプレミス型では初期の導入費用が高額になり、さらにソフトのバージョンアップやサポート契約に別途費用がかかることもあります。
導入後も、従業員に対する操作研修やカスタマイズのための追加費用が発生するケースがあるため、総コストが増大するリスクがあります。

編集部
こうした 初期費用や維持費を考慮し、企業の規模や業務量に見合った会計ソフトを選ぶことが重要 です。コストがメリットを上回らないよう、慎重な判断が求められます。
操作スキルの習得に時間がかかる、研修が必要
会計ソフトを導入すると、操作スキルの習得に時間がかかり、研修が必要になる点がデメリットです。
多くの会計ソフトは豊富な機能を備えていますが、その反面、使いこなすためには一定の知識やスキルが求められます。
特に、経理に不慣れな担当者や新しく配属された従業員にとっては、基本操作や各機能の使い方を覚えるのに時間がかかる場合があります。
さらに、データの入力ミスや処理ミスを防ぐための正確な操作が求められるため、 企業としては初期段階でしっかりとした研修が必要 です。
データ漏えいや消失などのセキュリティリスク
会計ソフトの導入には、データ漏えいや消失といったセキュリティリスクが伴います。万が一、 外部に取引情報や機密データが漏れると、企業の信用に大きな影響を与えることになります 。
特にクラウド型会計ソフトでは、インターネットを介してデータを保存・共有するため、不正アクセスやサイバー攻撃の標的になる可能性が高まります。
また、データ消失のリスクも存在し、バックアップが不十分な場合には、予期せぬ障害によって重要な財務情報を失う恐れがあります。
さらに、オンプレミス型でも社内の管理体制や設備に不備があると、物理的な破損や誤操作によってデータが消失するリスクがあります。

編集部
こうしたリスクを軽減するため、ソフト選定時にはセキュリティ水準を重視すべきです。
会計ソフトを導入すべき企業や個人事業主
起業・開業したばかりの企業
起業当初は限られた人員で多くの業務をこなす必要があるため、 会計ソフトを使うことで経理の負担が軽減され、本業に集中できる環境を整えられます 。
会計ソフトは、売上や経費の管理、請求書の作成、取引の記録などを自動化し、財務データの把握や分析もリアルタイムで行えるため、経営状況を迅速に把握するのに役立つでしょう。
さらに、税務申告に必要な資料も簡単に出力できるため、確定申告や税務処理がスムーズになり、税理士費用の削減にもつながります。
経理の知識を持った人材がいない企業
会計ソフトは直感的なインターフェースを持ち、専門知識がなくても使いやすい設計 になっています。これにより、経理業務を担当するスタッフが少ない場合でも、簡単に取引の記録や請求書の作成が行えます。
また、自動計算機能や仕訳機能により、手動での計算ミスが防止されるため、正確な財務データを維持できます。その結果、税務申告や経営判断に必要な情報を迅速に提供可能です。
さらに、会計ソフトはデータのバックアップやセキュリティ対策が施されているため、重要な財務情報を安全に管理できます。
経理の専門知識がない企業でも、会計ソフトを導入することで、業務の透明性を高め、経営の健全性を確保することができるのです。

編集部
これにより、企業は成長に向けた戦略的な意思決定を行いやすくなります。
経理業務を効率化したい企業
会計ソフトは自動化機能を備えており、取引の記録や仕訳を迅速に行うことができます。これにより、手動での入力作業を省略し、ヒューマンエラーを防げるため、正確な財務データの維持が可能です。
また、テンプレートで迅速に書類を作成し、顧客への送付もスムーズに行えます。これにより、 請求書や領収書の作成、経費精算などの業務スピードが向上し、経理担当者はより戦略的なコア業務に集中できます 。
さらに、会計ソフトはリアルタイムでのデータ分析やレポート作成が可能です。これにより、経営者は迅速に業績を把握し、適切な意思決定を行うための情報を得ることができます。
このように、会計ソフトの導入は経理業務の効率化だけでなく、企業全体の生産性向上にも寄与します。
会計ソフトを導入する流れ
-
STEP.1
導入目的を決める
目的に合わない会計ソフトを導入してしまうと、業務効率の低下や予期せぬコスト増加を招く可能性があるため、導入目的の明確化は非常に重要です。
まず、「経理作業の効率化」「経営状況の可視化」「税理士とのスムーズな連携」など、自社の課題を具体的に洗い出しましょう。
また、 導入による具体的な数値目標も設定する ことをお勧めします。経理作業時間を半減させたい、月次決算を5日以内に完了させたいなど、明確な指標があれば、会計ソフト選びの判断基準になります。
さらに、現在の業務フローを分析し、どの部分を自動化したいのか、どの作業を効率化したいのかを特定することで、必要な機能要件が見えてきます。
-
STEP.2
導入スケジュールを立てる
会計ソフトの導入スケジュールは、慎重に計画を立てる必要があります。特に年度末や決算期などの繁忙期は避け、比較的業務に余裕のある時期を選びましょう。
一般的な導入期間は、規模にもよりますが3〜6ヶ月程度を見込むことをお勧めします 。まずは1ヶ月程度で複数の会計ソフトの比較検討を行い、その後1〜2ヶ月で試用期間を設けます。
導入が決まったら、データ移行やユーザー教育に1〜2ヶ月、本番稼働後の運用テストに1ヶ月程度を確保します。特に既存の会計データの移行は、エラーが発生しやすい作業のため、十分な時間を確保することが重要です。
-
STEP.3
会計ソフトを選定する
会計ソフトの選定では、まず自社の規模や業務内容に適したものを選ぶことが重要です。
・運用形態
・直感的な操作が可能なUIかどうか
・顧問税理士が使用しているソフトとの互換性
・費用対効果
・セキュリティ対策 -
STEP.4
会計ソフトを導入し、初期設定を行う
会計ソフトの導入が決まったら、まずは初期設定を丁寧に行うことが重要です。
特に、 勘定科目や部門コードの設定は、後々の業務効率に大きく影響するため、自社の会計基準に合わせて慎重に設定 しましょう。
データ移行は段階的に進めることをお勧めします。まずは直近の取引データから始め、問題がないことを確認してから過去のデータを移行していきます。
また、複数の担当者で利用する場合は、アクセス権限の設定も忘れずに行いましょう。経理担当者、管理者、閲覧のみ可能なユーザーなど、役割に応じて適切な権限を付与することで、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。
複数のサービスを比較することが重要
会計ソフトは、サービスによって特徴や機能、強みなどが異なるため、 複数のサービスを比較検討し、自社のニーズに最適なものを見極める ことが成功の鍵となります。
比較する際は、機能面だけでなく、コストパフォーマンスやサポート体制、セキュリティ対策なども総合的に評価しましょう。また、実際の使用感を確認するため、無料トライアル期間を積極的に活用することをお勧めします。経理担当者の使いやすさや、データ連携の円滑さ、レポート機能の充実度などを実践的にチェックできます。
さらに、他社の導入事例や口コミ情報も参考にしましょう。特に、同業種・同規模の企業の評価は、自社での運用イメージを具体化する上で貴重な情報となります。
まとめ
会計ソフトの選び方では、自社の事業規模や業務内容に合わせた選定が重要です。
適切な運用形態や担当者のスキルレベルに適した使いやすいUIを持つソフトを選ぶことで、導入効果を最大化できます。
特に注目すべきは、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応状況です。これらの制度改正に柔軟に対応できるソフトを選ぶことで、将来的なコンプライアンスリスクを軽減できます。
さらに、他システムとの連携性や、セキュリティ対策の充実度、データ移行のしやすさなども考慮に入れましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!