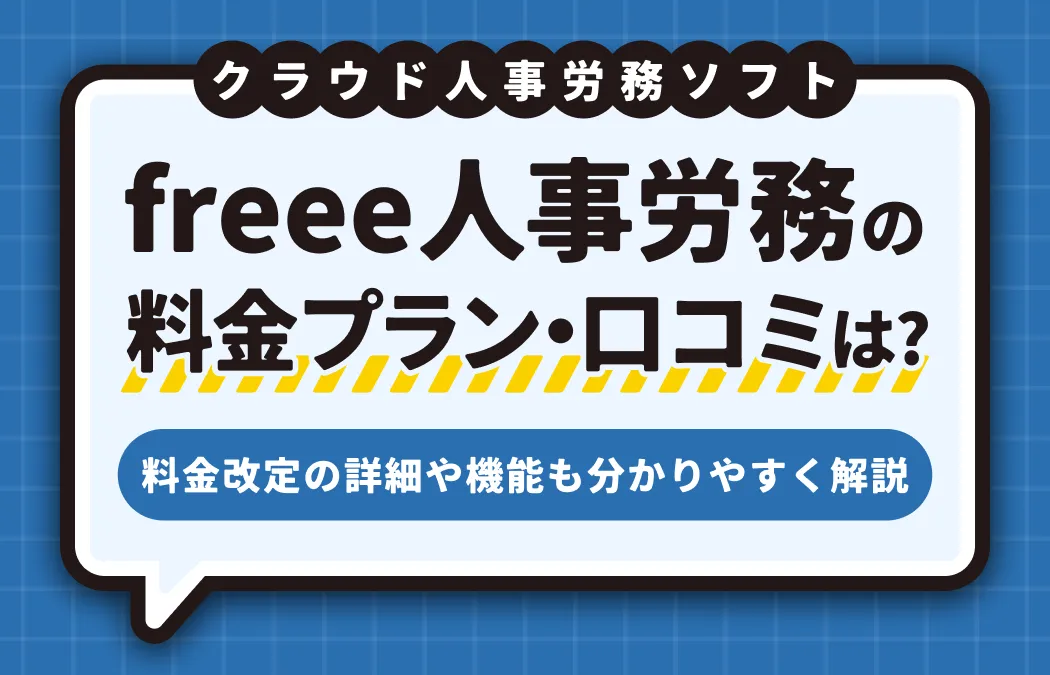「電子帳簿保存法は個人事業主も対応しなければならない?」
「電子帳簿保存法の対象書類は?」
2025年現在、電子帳簿保存法はすべての事業者にとって重要な制度となっており、とくに電子取引データの保存義務化により実務への影響が広がっています。
しかし「電子帳簿保存法についてよく分かっていない」「電子化するにはどんなルールがある?」など、まだ十分に理解していない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、電子帳簿保存法について、保存要件や対象書類、対応方法をわかりやすく解説していきます!
目次
電子帳簿保存法とは?わかりやすく解説
電子帳簿保存法とは、 帳簿や決算書、領収書などの国税関係書類を紙ではなく電子データで保存・管理することを認める法律 です。
1998年に施行され、その後、デジタル化や業務効率化のニーズの高まりを背景に、法改正が繰り返されてきました。
とくに2022年・2024年の改正により、スキャナ保存や電子取引データ保存の要件が大幅に緩和され、導入を検討する企業が増加。
正しく運用すれば、書類の保存業務にかかるコストの削減や効率化、テレワーク対応の強化など、さまざまなメリットがあります。
電子帳簿保存法が制定された背景とその目的
電子帳簿保存法が制定された背景には、 業務のIT化 や 電子商取引の拡大 があります。従来の紙による帳簿管理では、保管スペースの確保や検索性の低さなどが課題でした。
そこで、税務署への申請を条件に、電子データでの保存を認めることで、企業の業務効率向上とコスト削減を図ることを目的として制定されたのです。
また、国税庁側も帳簿の確認をデジタルで行えるようになるため、監査効率の向上という側面もあります。
近年では、テレワークの普及や電子インボイス制度との連動を踏まえ、制度がさらに柔軟に進化しています。
2022年1月に施行された電子帳簿保存法改正内容のポイント
- 事前承認制度の廃止
- 検索機能要件の緩和
- タイムスタンプ要件の緩和
- 適正事務処理要件の廃止
- ペナルティ・罰則規定の強化
- 電子取引における電子データ保存の義務化
2022年1月の改正では、 企業の電子化を後押しするため、手続きの簡素化と要件緩和が行われました。
具体的には、事前承認制度の廃止や、検索機能・タイムスタンプ要件の緩和などにより、より多くの事業者が電子保存を導入しやすくなりました。
一方で、電子取引に関するデータの電子保存が義務化され、違反時のペナルティ内容も明確化されたため、企業は改正内容を正しく理解し、社内の業務フローやシステムに確実に反映させることが求められます。
事前承認制度の廃止
従来、電子帳簿保存を行うにあたって、税務署への事前申請・承認が必要でしたが、 2022年の改正で事前承認制度の廃止は廃止 されました。
これにより、企業は税務署の許可を待たずに、自主的に電子保存の体制を整えることが可能になりました。
導入のハードルが大きく下がったことで、中小企業や個人事業主でも電子保存への移行が現実的な選択肢となっています。
検索機能要件の緩和
電子帳簿保存法改正前は、保存した電子データに対し、取引年月日・金額・取引先の3項目すべてで検索できるシステムが必要でした。
しかし改正により、 日付や金額の範囲指定や2項目以上の組み合わせ検索の義務が緩和 され、実質的には「税務調査時に速やかに出力できればよい」とされました。
これにより、一般的な会計ソフトやファイル管理でも対応しやすくなっています。
タイムスタンプ要件の緩和
電子データの信頼性確保のために求められていたタイムスタンプ付与も、電子帳簿保存法改正後は柔軟な運用が可能となりました。
例えば、 訂正削除履歴の残るシステムを使用していれば、タイムスタンプの代替と見なされます 。
保存後すぐでなくても、一定期間内(最長2カ月+7日以内)に付与すれば要件を満たすようになったため、運用負担が軽減されました。
適正事務処理要件の廃止
スキャナ保存において求められていた 「定期的な検査」や「相互けん制」などの適正事務処理要件が廃止 されました。
これにより、保存対象の書類を社内で一定の手続きに基づいてチェックする負担がなくなり、より柔軟な運用が可能になりました。
適正事務処理要件の廃止に伴い、企業の業務効率化だけでなく、電子保存を導入する企業の拡大も期待されます。ただし、不正防止の観点からも、社内管理体制の整備は依然重要です。
ペナルティ・罰則規定の強化
電子帳簿保存法の改正によって、要件を満たさずに電子保存した場合や、虚偽・隠蔽があった場合の罰則が明確化・強化されました。
帳簿書類が法令違反と判断されると、 青色申告の承認取消 や 重加算税の適用リスク もあります。
制度の緩和により導入しやすくなった一方で、正確な運用が求められるため、実務担当者には法令理解とシステム管理が必須です。
電子取引における電子データ保存の義務化
電子帳簿保存法の改正後、メールやWebサービスなどで請求書や領収書をやり取りする「電子取引」に関しては、 紙に印刷して保存する方法が原則認められなくなりました 。
改正前は、印刷して紙で保存することも可能でしたが、改正後はすべての事業者に対し、電子データでの保存が義務化されています。
対応には、ファイル名の付け方の工夫や保存フォルダの管理体制が求められるほか、改ざん防止措置も講じる必要があります。
電子帳簿保存法対応済!おすすめ会計ソフトはfreee
【無料】お問い合わせはこちら電子データ保存義務化はいつから実施される?
電子帳簿保存法における電子データ保存の義務化は、 2024年1月1日から本格的に適用 されています。
とくに、メールやクラウドでやり取りされる請求書や領収書といった「電子取引データ」については、紙に印刷して保存する方法が原則として認められなくなりました。
これにより、すべての事業者が電子データのままでの保存体制を整える必要があります。制度の猶予期間は終了し、完全義務化が始まった今、未対応の事業者は早急な対応が求められます。
2024年1月施行の令和5年度税制改正の要点
- 「優良な電子帳簿」の対象帳簿の明示
過少申告加算税が5%軽減される「優良電子帳簿」に該当する帳簿の種類が明示されました。 - 「スキャナ保存制度」の要件緩和
解像度・階調・サイズ情報の保存要件や、記録時の入力者に関する確認要件の廃止など、スキャナ保存に関する条件の見直しが行われました。 - 「電子取引」の保存要件の見直し
検索機能の確保が不要となる対象者の範囲が広がるなど、電子取引に関する保存要件の緩和が盛り込まれました。 - 「電子取引データの紙保存」に関する猶予措置
猶予措置は2023年12月末で終了し、2024年1月から新たな猶予制度が設けられ、実質的に恒久的な対応となりました。
電子帳簿保存法の対象者・企業
電子帳簿保存法は、 法人・個人を問わず、帳簿や領収書など国税関係書類を保存するすべての事業者が対象 です。
特に2024年1月からは、電子取引に関するデータ保存が全事業者に義務付けられたため、フリーランスや個人事業主も例外ではありません。
帳簿の電子保存は義務ではないものの、電子取引データの保存については法令遵守が求められます。今後は、企業規模を問わず電子保存の基盤整備が不可欠な時代となっています。
電子帳簿保存法の改正で個人事業主がするべきこと
個人事業主も、 クラウド請求書やネットバンクの取引履歴などを日常的に扱う場合、電子帳簿保存法への対応が必須 です。
特に電子取引データは印刷保存が認められず、データのまま保管しなければなりません。
保存要件として「ファイル名での管理」「日付・金額・取引先の検索性の確保」などが求められます。
会計ソフトやクラウドストレージの活用、適切な保存フォルダの作成など、日頃から対応を進めておくことが重要です。
電子帳簿保存法対応済!おすすめ会計ソフトはfreee
【無料】お問い合わせはこちら電子帳簿保存法の3つの区分と保存要件
【区分1】電子帳簿等保存:国税関係の帳簿や書類を電子形式で保存できる
「電子帳簿等保存」とは、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿類や決算関係書類を、 紙ではなく電子ファイルとして保存できる制度 です。
保存形式や入力方法に関する要件を満たすことで、紙での保管義務をなくすことができます。
税務調査時には、画面や書面で速やかに提示・出力できる体制が必要です。自社の会計ソフトが要件に対応しているか、事前に確認しておくことが重要です。
電子帳簿等保存の要件
電子帳簿等保存の区分では、下記の最低3つの要件を満たす必要があります。
- システム関係書類などの備え付けていること
- 電子データを保存するシステムの操作マニュアルを保存しておき、データをすぐに出力できる状態にしておくこと(見読可能性の確保)
- 税務職員による電子データのダウンロードに対応していること
また、上記のほかに定められた要件を満たすことで、 過少申告加算税の軽減や65万円の青色申告特別控除などのメリットを受けることができます 。
| 電子帳簿等保存の要件 | 優良な電子帳簿 | その他の電子帳簿 (最低限満たすべき要件) |
|
|---|---|---|---|
| 真実性の確保 | 訂正・削除履歴の確保 | ○ | ー |
| 相互関連性の確保 | ○ | ー | |
| システム関係書類などの備え付け | ○ | ○ | |
| 可視性の確保 | 見読可能性の確保 | ○ | ○ |
| 検索機能の確保 | ○*¹ | ー | |
| 税務職員による電子データのダウンロードに 対応していること |
ー*¹ | ○*² | |
※1 ダウンロードに対応しているときは検索機能の一部要件が不要
※2 優良な電子帳簿の要件を全て満たしているときは不要
【区分2】スキャナ保存:紙の国税関係書類をスキャンして電子化・保存できる
「スキャナ保存」は、請求書や領収書など紙で受け取った国税関係書類を、 一定のルールに基づいてスキャンし、電子データとして保存できる制度 です。
スマートフォンや複合機で撮影・スキャンした画像データも活用可能で、紙の保管スペース削減や業務効率化に効果的です。
改正により、タイムスタンプの猶予期間延長や適正事務処理要件の廃止など、要件も大幅に緩和されています。
スキャナ保存の要件
スキャナ保存の要件は、書類によって異なり、 重要書類と一般書類に分類されます 。重要書類はより厳しい要件が定められています。
- 重要書類:契約書、領収書、請求書、納品書など、資金や物の流れに直結・連動する書類
- 一般書類:検収書、見積書、注文書など、資金や物の流れに直結・連動しない書類
| スキャン保存の要件 | 重要書類 | 一般書類 | |
|---|---|---|---|
| 真実性の確保 | 入力期間の制限 (通常の期間を経過した後、速やかに入力) |
◯ | ー |
| 解像度(200dpi以上)による読み取り | ◯ | ◯ | |
| カラー画像による読み取り (赤・緑・青それぞれ256階調<約1677万色>以上) |
◯ | ※1 | |
| タイムスタンプの付与 | ◯ | ◯ | |
| 読み取り情報の保存 | ◯ | ー | |
| バージョン管理 (訂正または削除の事実および内容の確認) |
◯ | ◯ | |
| 入力者等情報の確認 | ◯ | ◯ | |
| 可視性の確保 | スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 | ◯ | ◯ |
| 見読可能装置の備え付け | ◯ | ◯ | |
| 整然・明瞭出力 | ◯ | ◯ | |
| 電子計算機処理システムの 開発関係書類等の備え付け |
◯ | ◯ | |
| 検索機能の確保 | ◯ | ◯ |
※1 一般書類の場合、カラー画像ではなくグレースケールでの保存可。
また、スキャナ保存は解像度や色の階調などの要件が細かく定められており、要件を満たせばスマホやデジタルカメラを利用した保存も可能です。
他の電子保存区分と比較して要件が多いため、全ての要件の抜けがないよう、細かく要件を確認する必要があります。
【区分3】電子取引データ保存:電子取引によるデータは電子のまま保存が義務
「電子取引データ保存」は、電子メールやクラウドサービスなどで授受した請求書・領収書などの電子データを、 紙に印刷せずに電子のまま保存することが義務付けられた制度 です。
2024年1月以降、全事業者が対象となり、要件を満たさない場合は青色申告の承認取消リスクもあります。
保存方法には「検索性」や「改ざん防止措置」が求められ、実務に即した保存体制の整備が必要です。
電子取引データ保存の要件
電子取引データの保存では、メールやクラウド経由で授受した請求書や領収書などを、電子データのまま保存することが義務づけられています。
電子取引は、インターネット通販やEDI取引、電子メール、クラウドサービスなど、対象となる書類が幅広いことが特徴です。
保存要件は以下の通りで、 「真実性の確保」「可視性の確保」「検索機能の確保」 の3点が基本です。
特に、改ざん防止措置(タイムスタンプや訂正削除履歴)と検索性の確保が重要視されています。
| 電子取引の要件 | ||
|---|---|---|
| 真実性の確保 (4つのうち、いずれかの措置を行う) |
タイムスタンプを付けた後、取引情報の授受を行う | |
| 取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付け、保存者または監督者に関する情報を確認できるようにする | ||
| 情報の訂正や削除を行った場合にその記録が残るシステム、 または訂正や削除ができないシステムで取引情報の授受や保存を行う |
||
| 訂正や削除を防止する規程を定めて運用を行う | ||
| 可視性の確保 | 保存場所に、電子計算機(パソコンなど)やディスプレイ、プリンタなどの操作マニュアルを備え付け、 整った形式や明瞭な表示で速やかに出力できるようにする |
|
| 電子計算機処理システムの概要書を備え付ける | ||
| 検索機能を確保する*¹ | ①取引年月日その他日付、取引金額、取引先について検索できる | |
| ②日付または金額の範囲指定により検索できる | ||
| ③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できる | ||
※1 税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロードの求めに応じる場合には、②と③の検索要件は不要
電子帳簿保存法対応済!おすすめ会計ソフトはfreee
【無料】お問い合わせはこちら電子帳簿保存法の対象となる書類・ならない書類
| 書類の種類 | 具体例 | 電子帳簿保存法の対象 | 適用区分 |
|---|---|---|---|
| 帳簿類 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳など | 対象 | 電子帳簿等保存 |
| 決算関係書類 | 貸借対照表、損益計算書など | 対象 | 電子帳簿等保存 |
| 国税関係書類 (紙) |
請求書、領収書、契約書、見積書、納品書など | 対象 | スキャナ保存 |
| 国税関係書類 (電子取引) |
メールで受領した請求書・領収書、クラウド上の契約書、EDI取引データなど | 対象 | 電子取引データ保存 |
| 名刺・挨拶状 | 名刺、年賀状、暑中見舞い、案内状など | 対象外 | – |
| 社内文書 | 会議メモ、稟議書、社内連絡書類など | 対象外 | – |
| 販促資料 | カタログ、チラシ、パンフレット、サンプルなど | 対象外 | – |
| プライベート文書 | 私的なメモ、個人的なスケジュール表など | 対象外 | – |
対象書類
【区分1】電子帳簿等保存:仕訳帳・決算関係書類・請求書の写しなど
電子帳簿等保存の対象となるのは、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳などの帳簿類、および貸借対照表や損益計算書などの 決算関係書類 です。
請求書の控えなども対象になります。これらは最初から電子的に作成・保存されるケースが多く、改ざん防止や検索性などの要件を満たせば、紙での保存は不要になります。
【区分2】スキャナ保存:紙で受領・発行した請求書契約書など
スキャナ保存の対象は、紙で受領・発行した請求書・領収書・契約書・見積書など、 国税関係書類全般 です。
取引から一定期間内にスキャンし、電子化された画像データを保存することで、紙の保管が不要になります。
スマートフォンのカメラやスキャナーでの読み取りも可能で、要件を満たせば有効な電子保存と認められます。
【区分3】電子取引データ保存:電子的に受領した請求書・領収書など
電子取引データ保存の対象は、メールやクラウドで受け取った請求書・領収書・契約書・注文書など、 電子的に授受されたすべての国税関係書類 です。
PDF・CSV・Excelなどのデータ形式で受け取る書類も含まれます。
これらは印刷して保存することは原則認められず、電子データのまま要件を満たした方法で保存しなければなりません。
対象外書類
電子帳簿保存法の対象外となる書類も存在します。例えば、名刺・社内メモ・議事録・社外との非取引的なやり取り文書(挨拶状や案内文)などは、 国税関係書類に該当しないため保存義務はありません 。
また、広告チラシやサンプル資料なども対象外です。ただし、取引に関連する契約書・請求書と混同しやすいため、社内で保存対象の明確なルールを定めておくと安心です。
電子帳簿保存法の対応方法・進め方
電子帳簿保存法対応ステップ
【Step 1】保存対象の書類を整理する
→ 電子帳簿・紙の書類・電子取引データを区分ごとに分類
【Step 2】各区分の保存要件を確認する
→ 区分1:電子帳簿等保存
→ 区分2:スキャナ保存
→ 区分3:電子取引データ保存
【Step 3】現状の保存・運用方法を見直す
→ 紙中心か?電子化されているか?運用ルールがあるか?
【Step 4】必要なシステムやツールを選定・導入
→ 会計ソフト/ストレージ/スキャンアプリなど
【Step 5】社内運用ルールを整備・従業員へ共有
→ スキャン期限、ファイル命名ルール、検索性の確保など
【Step 6】実際の保存運用を開始・定着させる
→ 定期的に運用状況を確認・改善
【Step 7】税務調査への備え
→ 出力・検索対応がスムーズにできる体制を整備
【区分1】電子帳簿等保存の対応方法
電子帳簿等保存に対応するには、 帳簿や決算関係書類を電子的に作成・保存できる体制を整える必要があります 。
主に対応すべき要件は「改ざん防止措置」「検索機能の確保」「画面表示や出力の可視性」です。
対応ソフトを導入するか、既存の会計ソフトが電子帳簿保存法に準拠しているかを確認しましょう。
帳簿作成時点から電子管理を徹底することで、紙保存の必要がなくなります。
【区分2】スキャナ保存の対応方法
紙で受け取った請求書や領収書などをスキャンして保存するには、「スキャナ保存」の要件に沿った運用が必要です。
具体的には、 受領から最長2カ月7日以内にスキャンし、タイムスタンプの付与または訂正削除が記録されるシステムを使う ことが求められます。
また、画像が明瞭であることや、画面表示・出力が可能な状態で保存することも重要です。モバイルアプリやクラウドサービスを活用すると効率的です。
【区分3】電子取引データ保存の対応方法
電子取引データ保存では、PDFやCSVなど電子的に受領・送付した請求書・領収書などを電子のまま保存しなければなりません。
保存要件として「改ざん防止」「検索性の確保」「出力対応」が求められるため、 ファイル名の付け方やフォルダ構成をルール化し、誰でも検索できるように管理体制を整えることが必要 です。
対応が難しい場合は、電子帳簿保存法対応のストレージサービスの導入も有効です。
電子帳簿保存法対応済!おすすめ会計ソフトはfreee
【無料】お問い合わせはこちら電子帳簿保存法でよくある誤解・注意点
すべての書類を電子化・電子保存する必要がある?
電子帳簿保存法では、 「すべての書類を電子保存しなければならない」というわけではありません 。
電子取引データ(PDF請求書など)は電子保存が義務ですが、帳簿や紙で受領した書類は、これまで通り紙での保存も認められています。
あくまで、電子で授受・作成したものは電子のまま保存する必要があるという点が重要です。不要な電子化によって業務を複雑化させないよう、対象範囲を正確に見極めましょう。
対応には必ず何らかのシステムを導入しないといけない?
電子帳簿保存法への対応にあたって、 必ずしも専用システムの導入が必要というわけではありません 。
要件を満たせば、ExcelやPDF、一般的なクラウドストレージなどを活用して対応することも可能です。
例えば、ファイル名に日付や取引先を入れる、訂正・削除履歴の残る保存先を選ぶなど、運用ルールの整備だけで対応できるケースもあります。コストを抑えつつ実務に合った方法を検討しましょう。
すぐに対応しなくても罰則は発生しない?
2024年1月以降、電子取引データの保存はすべての事業者に義務付けられています。
これに違反した場合、青色申告の承認取消や重加算税の対象になる可能性もあり 、決して軽視できるものではありません。
「罰則はないから後回しでいい」というのは大きな誤解です。特に電子請求書の保存が紙で済まされている企業は、すぐにでも保存ルールを見直し、法令順守の体制を整える必要があります。
電子帳簿保存法に違反したときの罰則
- 青色申告承認の取り消し
- 追徴課税
- 推計課税
- 会社法による過料
電子帳簿保存法に違反した場合、 単なる是正指導にとどまらず、重大な税務上の不利益を受ける可能性があります 。
特に、青色申告の承認取消や重加算税などの追徴課税、さらには帳簿不備による推計課税が適用されるケースもあります。また、会社法上の規定に違反すれば、過料の対象にもなりえます。
制度緩和により導入しやすくなった一方で、ルールを守らなければリスクは高まるため、正確な運用が不可欠です。
青色申告承認の取り消し
電子帳簿保存法に違反し、帳簿や書類の保存が不適切と判断された場合、税務署から「青色申告の承認取消」を受ける可能性があります。
青色申告は最大65万円の特別控除など、多くの税制優遇が受けられる制度であり、 取消となれば税負担が大きく増加 します。
電子保存に移行した場合でも、保存要件を満たさないまま運用すると青色申告が認められない可能性があるため、要件確認と運用体制の整備が重要です。
追徴課税
電子帳簿保存法の違反により、過少申告や不正経理が発覚した場合、重加算税を含む追徴課税が課されることがあります。
特に、保存義務のある電子取引データを削除したり、改ざん・隠ぺいを行ったりした場合には、 通常より重い税率(重加算税35%など)が適用される可能性があります 。
税務署は帳簿書類の保存状態を厳しくチェックするため、法令違反がないよう注意が必要です。
推計課税
帳簿や証憑類が整備されていない場合、税務署は事業実態に基づく申告内容の正確性を確認できず、「推計課税」を行うことがあります。
推計課税は 過去の売上や業界平均などを基に課税額を概算で決定する もので、実際より高額になることも少なくありません。
電子帳簿保存法違反により帳簿の信頼性が損なわれれば、適正な税務処理ができないと見なされるため、注意が必要です。
会社法による過料
電子帳簿保存法と直接関係しないように思えるかもしれませんが、 会社法でも帳簿・書類の保存義務が規定されており 、違反した場合は過料(罰金に近い行政処分)が科されることがあります。
例えば、取締役が会社の帳簿を不適切に扱った場合、100万円以下の過料が課されることも考えられます。電子化に際しても、会社法上の保存義務との整合性を意識した運用が求められます。
電子帳簿保存法対応済!おすすめ会計ソフトはfreee
【無料】お問い合わせはこちら電子帳簿保存法による企業への影響
電子帳簿保存法に対応するメリット・期待できること
- ペーパーレス化によってコストを削減できる
- 紙媒体特有のリスクを回避できる
- 帳簿や書類の検索性が向上し、業務が効率化される
- テレワークの推進と定着につながる
- コンプライアンスやガバナンス体制の強化につながる
ペーパーレス化によってコストを削減できる
紙の帳簿や書類を電子化することで、 印刷・コピー代、保管スペース、郵送費などの間接コストを大幅に削減 できます。
特に中小企業やスタートアップにとっては、物理的な保管コストの負担が軽くなることは大きなメリットです。
電子帳簿保存法をきっかけにペーパーレス化を進めることで、業務全体のスマート化も加速し、経営資源の最適化にもつながります。
紙媒体特有のリスクを回避できる
紙の帳簿や書類には、紛失・劣化・水濡れ・火災といった物理的リスクが常につきまといます。
電子化することで、こうしたリスクを回避し、 安全なクラウド環境やバックアップでの保管が可能に なります。
セキュリティ対策が万全な保存体制を構築すれば、情報の改ざんや不正アクセスといったリスクも抑制でき、信頼性の高いデータ管理が実現します。
帳簿や書類の検索性が向上し、業務が効率化される
電子データとして保存された帳簿や書類は、日付・取引先・金額などのキーワードで迅速に検索できるため、 情報の取り出しにかかる時間を大幅に短縮できます 。
紙資料を手作業で探す手間がなくなることで、ミスの削減や社内対応のスピードアップが可能になり、業務全体の効率化に直結します。
特に経理・総務部門での業務負担軽減に大きく貢献します。
テレワークの推進と定着につながる
帳簿や証憑が電子化されていれば、クラウド上で安全に共有・閲覧ができるため、 オフィスに出社しなくても多くの業務が対応可能に なります。
これにより、テレワークや在宅勤務といった柔軟な働き方が定着しやすくなり、社員のワークライフバランス向上にも貢献します。
また、災害時や感染症拡大時など、緊急対応にも強い業務体制を構築できます。
コンプライアンスやガバナンス体制の強化につながる
電子帳簿保存法への対応を通じて、帳簿・書類管理の標準化や社内ルールの明確化が進むため、企業のコンプライアンス(法令遵守)意識も向上します。
改ざん防止やアクセス管理を徹底することで、 内部統制や情報セキュリティも強化され、ガバナンス(企業統治)体制の信頼性が高まります 。
また、対外的な信用向上にもつながるため、中長期的に企業価値を高める要素にもなります。
電子帳簿保存法に対応するデメリット・負荷
- 請求書の形式ごとに異なる保存方法が求められる
- 運用にあたってルール整備が必要になる
- システムトラブルのリスクを伴う
請求書の形式ごとに異なる保存方法が求められる
請求書や領収書が「紙」「PDF」「クラウド上の電子データ」など形式ごとに異なる場合、 それぞれに適した保存方法を用意しなければなりません 。
紙で受け取った場合はスキャナ保存、電子で受け取った場合は電子取引データ保存が義務づけられるなど、保存区分ごとに異なる要件が適用されます。
そのため、取引先の請求書送付方法に応じた柔軟な運用体制が求められる点が実務上の負担になります。
運用にあたってルール整備が必要になる
電子帳簿保存を正しく行うには、「いつスキャンするか」「ファイル名はどう付けるか」「どのフォルダに保存するか」といった社内ルールを明確に定める必要があります。
ルールが曖昧だと、保存漏れや検索性の低下につながり、業務効率の低下や法令違反を招くリスクも高まります。
全社員が共通認識を持てるように マニュアルを整備 し、 定期的な見直しを行う体制づくりを徹底しましょう。
システムトラブルのリスクを伴う
電子保存のメリットを活かす一方で、システム障害やクラウドサービスの不具合といったトラブルが発生するリスクも考慮する必要があります。
バックアップ体制が不十分だと、帳簿や証憑データの消失につながる 可能性もあり、税務対応や信頼性に大きな影響を与えます。
システム導入時には、復旧体制やデータ保全ポリシーの確認を行いましょう。
電子帳簿保存法に対応するシステムの選び方
- 電子保存したい帳簿や書類を洗い出す
- 自社に必要な機能が備わっているか確認する
- JIIMA認証を取得しているシステムか確認する
- 既存システムと連携できるかどうかも重要
- IT導入補助金の活用を検討するのも有効
電子保存したい帳簿や書類を洗い出す
まず最初に、 自社でどの帳簿・書類を電子保存の対象とするのかを明確に しましょう。
仕訳帳や総勘定元帳、請求書、領収書、契約書など、取引形態や業種によって対象範囲は異なります。
保存区分(電子帳簿等保存/スキャナ保存/電子取引保存)ごとの要件に沿って分類することで、必要な機能が明確になり、システム選定の方向性が定まります。
自社に必要な機能が備わっているか確認する
電子帳簿保存法に対応したシステムを選ぶ際は、単に保存できるだけでなく、 自社業務に即した機能が揃っているかを確認することが重要 です。
例えば、証憑の自動収集や支払管理との連携、仕訳の自動化などがあれば、保存だけでなく業務全体の効率化にもつながります。
以下では、特に注目すべき機能を4つ紹介します。
証憑を自動で集められる機能があるか
メール添付の請求書やクラウドサービス上の領収書などを、自動で取得・保存できる機能は、証憑の取りこぼしを防ぎ、作業負担の軽減につながります。
受領した証憑が自動でフォルダに仕分けされる機能や、取引先ごとの自動分類ができるシステムであれば、保存要件を満たしつつミスのない運用が可能になります。
支払業務まで効率化できるかどうか
保存した請求書データをもとに、支払処理や振込データ作成まで一括して行えるシステム であれば、バックオフィス業務を大幅に効率化できます。
会計ソフトや銀行口座との連携機能があると、二重入力の手間や人為的ミスを防げるため、経理担当者の負荷軽減に有効です。
取引データを自動で電子化できるか
紙で受領した書類やスキャン画像を、 OCR(文字認識)などで自動的にデータ化できる機能 があれば、電子保存の手間が大きく削減されます。
手作業での入力や分類が不要になることで、業務スピードが向上し、ヒューマンエラーも減らせます。スキャナ保存との相性も良いため、対応範囲を広げる上で有効な機能です。
仕訳の自動作成が可能かどうか
取引データから自動で仕訳を生成する機能があると、会計業務の効率が格段に上がります。
電子保存だけでなく、会計処理まで一気通貫で行えることで、入力ミスや処理漏れを防ぎ、月次決算のスピードアップにも繋がるでしょう。
仕訳ルールの自動学習 や テンプレート登録機能 があるかどうかも、導入時の確認ポイントです。
JIIMA認証を取得しているシステムか確認する
電子帳簿保存法対応システムを選ぶ際は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を取得しているかを確認しましょう。
JIIMA認証は、 法令要件に適合していることの第三者認証 であり、信頼性の高い製品であることの目安になります。認証済みのシステムであれば、税務調査時の対応でも安心です。
既存システムと連携できるかどうかも重要
新たに導入するシステムが、 現在使用している会計ソフトや経費精算ツール、販売管理システムなどと連携できるか どうかも重要なポイントです。
連携性が低いとデータの二重管理が発生し、かえって手間が増えることになります。API連携やCSVインポート/エクスポート機能の有無など、事前に仕様を確認しましょう。
IT導入補助金の活用を検討するのも有効
電子帳簿保存法対応のシステムは、初期費用や運用コストが発生するため、 IT導入補助金の活用も視野に入れる とよいでしょう。
対象となるシステムであれば、最大2分の1〜3分の2の費用補助を受けられるケースもあります。
申請には事前準備が必要なため、早めに制度内容や対象製品を調べ、導入時のコスト負担軽減に役立てましょう。
電子帳簿保存法に対応したおすすめ会計ソフト
freee

freeeは、クラウド型会計ソフトの先駆けとして多くの中小企業や個人事業主に利用されています。
電子帳簿保存法にも対応しており、 電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存の各要件をクリア しています。
証憑の自動取得や仕訳の自動生成、改ざん防止機能も備えており、JIIMA認証も取得済み。
スマホからのスキャン機能もあり、ペーパーレス経理を効率的に実現できます。特にバックオフィス業務の一元管理を目指す方におすすめです。
【無料】お問い合わせはこちら経費精算に特化したい場合は「freee経費精算」
日々の経費精算を効率化したい個人事業主や中小企業には、「freee経費精算」の活用が効果的です。
スマホやPCから領収書の撮影・申請ができ、承認フローの自動化や定型仕訳の自動反映など、経理作業の手間を大幅に削減できます。
交通費・立替金・出張費など多様な経費に対応し、会計ソフト「freee会計」との連携で帳簿記帳もスムーズです。
人的ミスの防止や申告時の証憑整理にも強く、経費管理の精度とスピードを同時に高められるサービス です。
マネーフォワードクラウド

マネーフォワードクラウドは、会計だけでなく請求書・経費・給与など幅広い業務をカバーする統合型のクラウド会計ソフトです。
電子帳簿保存法の全3区分に対応しており、スキャナ保存・電子取引データの保存機能、検索・改ざん防止要件もクリア 。JIIMA認証も取得しており、安心して法令対応が可能です。
電子証憑の自動収集や仕訳ルールの学習機能が充実しているため、経理業務の省力化にもつながります。導入から定着までのサポートも手厚く安心です。
【無料】お問い合わせはこちら電子帳簿保存法に関するよくある質問
A
紙で受け取った請求書や領収書は、スキャナ保存の要件を満たせば電子保存が可能です。
スキャン期限やタイムスタンプの付与、可視性・検索性の確保が求められます。
A
自社発行の書類は、PDFなど電子で作成した場合、そのまま電子帳簿等保存の要件に沿って保存します。
紙で作成した場合はスキャナ保存が必要です。
A
キャッシュレス決済でも領収書や明細の保存は必要です。
電子明細は電子取引として電子保存が義務付けられ、紙のレシートはスキャナ保存の対象です。
まとめ
2025年現在、電子帳簿保存法はすべての事業者にとって無視できない制度です。
対象書類や保存区分を正しく理解し、自社に合ったシステムと運用ルールを整えることが法令遵守と業務効率化の両立につながります。
メリット・デメリットを踏まえ、段階的な対応を進めましょう。
電子帳簿保存法対応済!おすすめ会計ソフトはfreee
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!