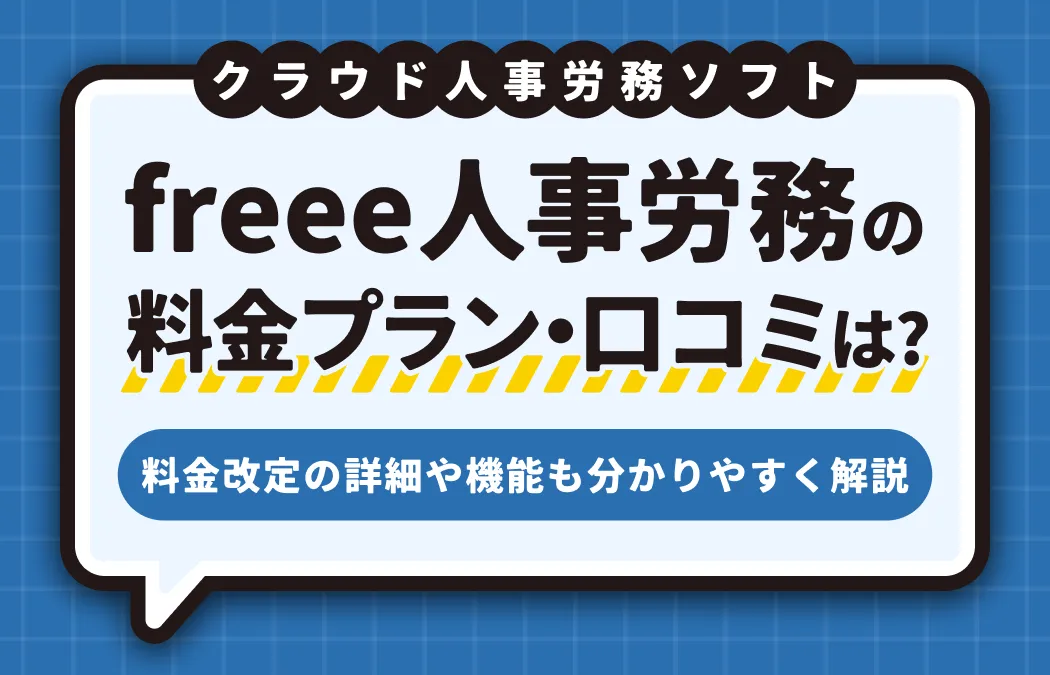そう感じながらも、つい後回しにしてしまう記帳作業。経理担当が手一杯だったり、そもそも専任がいない中小企業や個人事業主にとって、記帳は地味だけど確実に時間を奪う業務です。
そんなときに検討したいのが“記帳代行”という選択肢です。
最近はfreeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトと連携できるサービスも多く、手間もコストも想像以上に抑えられるようになっています。
本記事では、記帳代行の仕組みや料金相場、サービス選びのポイントから、おすすめ業者の比較までわかりやすく解説します。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
目次
▼この記事で紹介している商品
記帳代行とは記帳業務をアウトソーシングすること

記帳業務のアウトソーシング
記帳代行とは、企業におけるお金の支出入を整理し、必要書類を渡したうえで 記帳作業を外部へ委託するサービス です。
記帳作業とは、経営に関わるお金の動きを記録する作業のことで、確定申告や日々の経営状況の把握などにおいても重要になります。
記帳とは、日々の収入や支出を帳簿に記録することです。帳簿は、収入や支出の詳細を書き留めるための記録用の帳面やファイルのことを指します。
帳簿作成は財務管理や法的要件の遵守、税務申告、そして事業の成長と評価において不可欠な役割を果たします。
特に、法人税や所得税などの税務申告の際には、帳簿に記録された情報をもとに計算するので、適切な記帳・管理が大切です。
経理業務の負担を一気に軽減
記帳代行では、日々の記帳業務を外部へ依頼することで、経理担当者の負担を軽減できるほか、業務効率化にもつながります。
毎日記帳をするのは手間である上に、簿記の知識がなければ簡単には行えません。仕訳件数が多ければ更に時間もかかってしまいます。
帳簿作成をプロに任せれば、帳簿を適切に記録し、税務申告や財務管理のために必要な情報を提供してくれる上、 帳簿の正確性や適切さを確保することも可能 です。
記帳代行の料金相場は100仕訳1万円程度

記帳代行の料金比較表
| サービス名 | 料金(税込) | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50仕訳 | 100仕訳 | 300仕訳 | 500仕訳 | ||
| 経理外注 記帳代行センター |
1万6,500円 | 2万4,750円 | 251仕訳以降は100仕訳増加につき +1万6,500円 |
・50仕訳ごとの段階的に設定 ・251仕訳以降は100仕訳増加につき+1万6,500円 ・記帳代行丸投げサポートの料金 |
|
| 辻内税理士 社会保険労務士事務所 |
年間1,000仕訳未満で6,050円 ※月平均100仕訳の場合年間1,200仕訳となり、月額1万2,100円 |
・年間仕訳数で月額料金を設定 ・1,000仕訳ごとに+6,050円で設定 |
|||
| 松﨑佳史税理士事務所 | 5,500円 | 9,900円 | 2万9,700円 | 401仕訳以降は50仕訳増加につき+5,500円 | ・段階的に設定 ・401仕訳以降は50仕訳増加につき+5,500円 ・年間契約した場合は3カ月無料 ・3カ月間の平均仕訳数で料金決定 |
| 経理・記帳代行 サポートオフィス |
ー | 1万1,000円 | 3万3,000円 | 5万5,000円 | ・50仕訳ごとの段階的に設定 ・楽々コースでの料金(書類提出後、代行) ・501仕訳以降は別途見積り |
| 京都 決算・経理 相談センター |
3,300円 | 1万1,000円 | 3万3,000円 | 4万4,000円 | ・30仕訳から段階的に設定 ・スタンダードプランの料金(書類提出後、代行) ・600仕訳以降は100仕訳増加につき+5,500円 |
※「記帳代行 料金」検索結果1ページ目の上位サービスを対象
※料金は該当仕訳数時点での月額料金
記帳代行の相場は100仕訳1万円程度
記帳代行の料金について、料金比較表を踏まえてみると、 100仕訳あたり1万円程度が相場 と言えます。
相場を100仕訳1万円程度として考えた場合、検討するサービスが安いのか高いのか、平均的なのかどうかを判断しやすくなります。
また、料金設定の仕方や仕訳数の範囲、従量料金についてはサービスごとに異なるため事前にホームページや問い合わせをするなどして正確な料金を確認してみましょう。
記帳代行は仕訳数によって料金が異なる
|
記帳代行の料金は、簿記上の取引を借方と貸方に分類して記載する仕訳数によって料金が異なります。
上限を設定した仕訳数に応じて段階別に料金を設定しているサービスと、1仕訳分の料金を設定しているものが一般的です。
しかし 仕訳数が多くなるにつれてお得になるサービスもある ため、検討しているサービスの料金設定について比較や確認をしましょう。
記帳代行に資格は必要?依頼時に見るべきポイント
記帳代行に資格は不要だが注意点あり
記帳代行は、特別な国家資格がなくても提供できる業務です。これは、税務代理や申告業務とは異なり、「日々の取引の仕訳・帳簿付け」に限られるため、税理士法の規制対象外とされているからです。
ただし、誰でもできる=安心して任せられるわけではありません。経理知識の浅い業者に依頼すると、仕訳ミスや帳簿の不備が発生し、最終的に税務調査などでトラブルにつながる恐れもあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、実績や体制なども含めて総合的にチェックしましょう。
記帳代行業者に必要なスキル・知識とは?
たとえ資格が不要でも、以下のスキル・経験を持つ業者であれば、安心して任せやすくなります。
必要なスキル・知識の一例
-
枠付きリスト。border部分取ったらこうなる
-
会計知識はある程度あるので、サポートは不要
-
枠付きリスト。border部分取ったらこうなる
-
会計知識はある程度あるので、サポートは不要
これらのスキルを備えているかを、面談や事前の質問で確認しましょう。スキル不足の業者に任せると、二度手間になりかねません。
業者選定時のチェックリスト
業者選定の際は、スキルだけでなく、対応力・信頼性・コストなども考慮することが重要です。以下のようなチェックリストをもとに、複数社を比較検討しましょう。
記帳代行業者を選ぶためのチェック項目
| チェック項目 | 確認ポイント例 |
|---|---|
| ✅ 実績・顧客数 | どんな業種・規模の会社に対応しているか |
| ✅ 会計ソフト対応 | 自社のソフトに対応しているか |
| ✅ セキュリティ | 個人情報保護方針は整備されているか |
| ✅ レスポンスの速さ | メールや電話での対応は迅速か |
| ✅ 価格・コスト構造 | 料金が明朗で、追加費用の発生条件も明記されているか |
選定の失敗を防ぐためには、無料相談やトライアル対応の有無も確認すると良いでしょう。
📩 記帳代行サービスについてご相談やご質問がある方は こちらの問い合わせフォーム からお気軽にご連絡ください。
記帳代行と経理代行の違いは「業務範囲」

記帳代行は経理代行に含まれる
記帳代行は、経理業務全体を代行する経理代行サービスのなかの、ひとつの作業として含まれています。
しかし経理代行の一部として提供されるだけでなく、記帳代行だけを利用できる独立したサービスもあります。
費用面の違い
記帳代行は記帳作業分のみを代行し、経理代行は幅広い経理業務全体を代行するため、料金も異なります。
記帳代行は、経理業務のなかの記帳作業のみなので 経理代行よりも安く利用できるのが一般的 です。
記帳代行でできること
記帳代行は、日々の記帳作業を代行します。毎日の会社のお金の動きを記録し、仕訳に応じた記帳で定期的に帳簿を更新します。
経理担当者の負担になりやすい膨大で細かい日々の業務を依頼できることで、業務負担の軽減や業務効率化の実現が可能です。
・決算書の作成
・取引記録の入力
・帳簿の作成と管理
・税務申告のサポート
・仕訳の作成・帳簿への反映
経理代行でできること
経理代行は、経理業務の全般を代行します。記帳業務、給与計算、年末調整業務など幅広い経理業務が含まれます。
経理代行を利用することで、経理担当者が不在の企業でも、安心して経理業務を任せることができます。
・経営指標の分析
・予算策定と財務計画の支援
・税務のアドバイスや問題解決のサポート
・決算業務(勘定の集計/書類作成など)
・税務申告の準備

編集部
記帳代行は主に帳簿作成業務に特化しており、経理代行はその他の経理業務や経営サポートにも幅広く対応する点が異なります。自社のニーズや予算に応じて選びましょう。
なぜ記帳が重要?義務化された背景と実務対応

記帳義務化とは?対象と背景を解説
記帳業務は、かつて一部の事業者を除いて義務ではありませんでしたが、 2014年の改正により、白色申告者も含めてすべての個人事業主に記帳と帳簿保存が義務化 されました。
さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法の整備により、法人・個人問わず、帳簿の正確性と保存性が強く求められる時代となっています。
- 不適切な申告を減らし、税務の透明性を高める
- 電子化・デジタル化に対応した税務監査の効率化
- 消費税の適正な納付(インボイス制度の導入)
-
各制度ごとに対象範囲も異なります。
-
制度名 対象事業者 業務内容 白色申告の記帳義務化 全個人事業主 記帳と7年間の帳簿保存 電子帳簿保存法 法人・個人 電子保存要件を満たす形式での記録保管 インボイス制度 課税事業者 的確請求書発行・記録管理の徹底
義務化で何が変わる?実務で必要な対応とは
帳簿義務化によって、「とりあえず手元で管理しておけばいい」という感覚では通用しなくなりました。税務調査でのチェック項目が細かくなり、特にインボイス制度の開始により、仕入控除や経費処理に直結する記帳ミスが大きな損失を招くリスクがあります。
📌 実務上の主な対応ポイント
- 取引日・取引内容・金額を正確に記録する
→ スプレッドシートやメモでは不十分、形式要件のある帳簿が必要 - 会計ソフトによる記帳・管理体制を整備する
→ 電子帳簿保存法に対応したツールを選定 - 証憑(レシート・請求書)の保存・分類ルールを整える
→ 電子保存 or スキャン対応が求められる場面もあり
記帳は「税務署に見せるための作業」ではなく、「事業を守る防衛線」です。税務調査で否認リスクを避け、資金繰りの可視化にもつながります。
記帳代行のメリット

負担を軽減
記帳代行を利用すれば、経理担当者の業務過多を改善できます。
経理担当者は、帳簿作成業務だけでなく給与計算や売掛金・買掛金管理など幅広い業務があるため、毎日の記帳作業がなくなるだけでも負担軽減に繋がります。
本業に専念できる
記帳代行を利用することで、業務効率化につながります。
経理担当者は記帳以外の経理業務に集中でき、他業務と兼務の場合は本業に集中できるため、時間やコストをうまく活用できるでしょう。
大幅なコストダウンが実現
記帳代行を利用することで、人件費の削減に繋がります。経理担当者の残業代や採用・教育コスト削減に繋がるでしょう。
たとえば記帳をメイン業務とする従業員を月給20万円で雇用している場合、月額5万円の記帳代行に切り替えれば、毎月15万円を削減できます。
業務の質が上がる
記帳代行では、細かい毎日の記帳作業におけるミスの軽減や、法改正にも迅速に対応できるようになります。
記帳代行は経験豊富な経理のプロが作業するため、業務の質向上も期待できます。とくに経理の人材が確保できていない場合におすすめです。

編集部
プロであれば適切な仕訳や帳簿の整理を行い、より正確な記録を保持できます。企業は信頼性の高い財務情報を得られるため、外部や利害関係者に対する透明性の向上にもつながるでしょう。
不正防止につながる
記帳代行を利用することで、経理数値の不正も抑止できます。第三者が入ることで、経理内容をオープンにし、不正を未然に防げます。
一般的には限られた人しか把握することのできない社内の経理データを、改ざんしたり横領される危険を抑止できるでしょう。

編集部
プロが帳簿を管理・監査することで、不正や誤りを早期に発見・修正できるようになります。
企業全体の動きを把握できる
記帳代行では、経理業務のすべてを委託するわけではないので、企業全体の動きを見失いません。
しかし経理代行では、すべての経理業務を外部業者に委託するため、経理数値に関する動きが把握しにくくなる可能性があります。

編集部
帳簿代行であれば正確な財務情報もとに、企業の状況やトレンドを把握し、適切な意思決定を行うことができます。
経理代行と比べて安価
記帳代行は、経理業務の一部のみを依頼するため、経理業務全体を依頼する経理代行と比較すると安価に利用できます。
業務負担を軽減しつつ、コスト削減につなげられる可能性もあるので、一石二鳥と言えるでしょう。
節税のアドバイスをもらえる
記帳代行サービスに税理士が在籍している場合、節税のアドバイスをもらえる可能性があります。
節税は、大幅なコスト削減に繋がる可能性もありますので、企業としては特に意識しておきたいところです。

編集部
プロによる適切な帳簿の管理や財務戦略の立案を通じて、企業は節税効果を得ることができます。
簡単に契約が変更できる
記帳代行サービスの契約は数か月単位での契約が基本であるため、自社と合わないと感じた場合は別の業者に切り替えることもできます。
年間契約のように、事前にまとめて長期間分の料金を支払う必要がないものも多いため、まずは気軽に利用してみるのもおすすめです。
記帳代行のデメリット

違法な業者に注意する必要がある
記帳代行サービスに提携できる税理士がいない場合、税務申告はできません。税務申告自体は有資格者のみが行えるものです。
記帳代行と一緒のサービスで税務申告まで依頼したい場合は、 提携の税理士がいるかどうかを確認 しましょう。

編集部
帳簿の記録や処理には法的な規制があります。適切な帳簿管理が行われないと、税務申告や法定の帳簿記録に関する法令違反につながるため、サービスの選定には要注意です。
料金設定が曖昧な場合がある
記帳代行を利用する場合は、あらかじめ料金を確認しましょう。 サービスによっては、追加料金がかかる 場合があります。
料金設定が不明瞭な場合、結果的に予算より高い料金になる可能性もゼロではありません。見積もりや計算をして料金を明確にしましょう。
外部へ情報流出する可能性がある
記帳代行を利用するということは、社外の第三者が経理データを扱うことになり、情報流出する可能性もゼロではありません。
記帳代行サービスを選定する際に、 セキュリティの強さや企業としての信頼性を確認 したうえで安心できるサービスを選びましょう。

編集部
帳簿には機密性の高い情報が含まれる場合があるので、信頼性の高い業者を選ぶことが重要です。
経理状況の把握がしにくい
記帳業務を利用することで、自社におけるお金の細かい動きについて、把握しにくくなる可能性もあります。
経理代行を利用する場合は、なにか問題が起こった際にも対応してくれる サポート体制が強いサービスを選ぶと安心 です。

編集部
帳簿の記録内容や進捗状況を適切に把握するためには、定期的な報告やコミュニケーションが必要です。
外注管理の手間がかかる
記帳代行を利用することで、これまではなかったアウトソーシングの管理をする手間が発生します。
記帳代行の費用把握や依頼・確認などの管理業務が発生するため、担当者はあらかじめ管理業務が発生することも踏まえて検討しましょう。
記帳代行と相性のよい会計ソフト3選
freee会計との連携が得意な代行業者とは?
クラウド型会計ソフトの代表格である 「freee会計」は、記帳代行との相性が非常に高いソフト です。取引データの取り込みや自動仕訳が可能なうえ、事業者と代行業者でアカウント共有することで、リアルタイムで帳簿の確認・修正が可能になります。
freee会計を使うメリット
- 銀行・クレカとの自動連携で入力ミスを削減
- スマホからも領収書アップロード可能
- 仕訳ルールの自動化で効率的な処理が実現
freeeに強い代行業者を選べば、ツール設定から日々の記帳まで一貫して任せられるため、 開業間もない事業者にも特におすすめ です。
マネーフォワードクラウド対応の業者を選ぶ理由
「マネーフォワード クラウド会計」は、 中小企業からの支持が高いクラウド会計ソフト です。操作画面が直感的で、レポート機能も充実しているため、経営者自身が状況を把握しやすいのが特長です。
マネーフォワードの特長
- 日々の入出金を自動取得&AI仕訳
- 費用の部門別管理やキャッシュフローの可視化に強み
- 顧問税理士との連携実績も豊富
弥生会計の記帳代行も可能?対応業者の探し方
「弥生会計」は、インストール型ソフトながら中小企業・個人事業主に長く愛されており、 オフライン環境でも使える点が大きな魅力 です。特に 青色申告や複式簿記に対応しているため、帳簿の正確性を求められる業種に適して います。
ただし、弥生会計での記帳代行を依頼する場合には、ソフト操作に慣れた業者を選ぶ必要があります。クラウド型と異なり、データの受け渡しやバージョン対応など、細かな調整が必要です。
弥生対応業者の選び方ポイント
- バージョン互換性の有無(例:やよいの青色申告21対応)
- データ共有方法(USB/CSV/クラウドアップロード対応など)
- 操作経験・代行実績の豊富さ
業者の選定では、 対応ソフトの指定があるかどうかも必ずチェック しましょう。
自社の会計ソフトに対応してもらえるか確認を
記帳代行を依頼するうえで見落としがちなのが、会計ソフトとの「対応可否」です。業者によっては特定のソフトにしか対応していない場合もあり、無理に依頼するとフォーマット変換など二重作業が発生するリスクがあります。
✅ 依頼前に確認すべきチェックリスト
- 自社で使用している会計ソフトは何か?
- データ形式はCSV形式か専用ファイルか?
- 双方のやり取りはクラウド共有?メール添付?
- ソフトのバージョンやプランは一致しているか?
業者サイトに「対応ソフト一覧」があれば、まずはそこをチェックし、必要に応じて事前に相談を行うのが賢明です。
記帳代行はこんな人におすすめ!

フリーランスや個人事業主
記帳代行はフリーランスや個人事業主におすすめです。本人が経理作業も行う場合、毎日の記帳作業が負担になり、本業が疎かになりかねません。
すべて自分で行うのではなく、記帳代行を活用して、売上アップに注力しましょう。
中小企業
記帳代行は、経理担当者が少ない場合の中小企業にも有効です。経理担当者が少数の場合、ひとりひとりの作業負担が重くなります。
記帳業務を外部に依頼して、全体の経理業務を調整することで、負担軽減に繋がります。
ベンチャー企業
記帳代行は人材不足に陥りやすいベンチャー企業もおすすめです。専任の経理担当者がいない場合や経営者が行っている場合もあるでしょう。
経理業務の負担軽減だけでなく、記帳業務のノウハウを相談する機会にも繋がります。
記帳代行サービスの種類と選び方

記帳代行を依頼できる種類一覧表
| 業務種類 | 導入方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 記帳代行会社 | 契約 | ・料金がお得(税理士事務所等と比較して) ・経験豊富なスタッフが代行 ・短期間契約で解約しやすい場合が多い |
・決算申告はできない場合が多い ・税務業務ができない場合がある ・節税対策にならない場合がある |
| 会計ソフト | インストール | ・料金を抑えられる ・クラウド型ならリアルタイムで確認できる |
・書類準備等の手間がかかる ・システムを理解する必要がある ・決算申告が必要 ・バージョンアップを行う必要がある |
| クラウド | |||
| 税理士事務所会計事務所 | 契約 | ・信頼性が高い ・税理士資格があれば決算申告もできる ・節税対策にも繋がる |
・料金が高い傾向にある ・年間契約の場合、解約しにくい |
| フリーランス | 契約 | ・紹介などで信用できる人に直接依頼できる ・交渉次第で料金を抑えられる場合がある |
・連絡が取りにくい場合がある ・信頼できるかどうかがわかりにくい |
帳簿単位で依頼するスポット型
スポット型の記帳代行は、 特定期間や一定量の記帳作業だけを依頼する契約形態 です。「開業初期の数ヶ月だけ」「決算期直前の記帳だけ」といったように、必要なタイミングで必要な範囲のみを外注できます。
スポット型の主な特徴
- 単発で依頼可能(例:1ヶ月分、1年分)
- コストを抑えやすく、小規模事業者に向く
- 緊急対応や繁忙期の一時的な活用に便利
ただし、継続的な記帳管理には向かず、 経理体制を整えたい事業者にはやや不向き です。記帳ミスの発見が遅れるリスクもあるため、定期利用を視野に入れて検討しましょう。
毎月対応してくれる月次パック型
「月次パック型」は、 毎月の仕訳や帳簿作成を継続的に外注するサービス形態 です。売上・経費の記録、銀行取引の仕訳など、日常の記帳業務を定期的に任せることで、経営者が本業に集中できるメリットがあります。
月次パック型の主な利点
- 毎月決まった仕訳数まで対応(例:300仕訳まで 月額◯円)
- 会計ソフトへの直接入力にも対応可能
- 税理士連携・決算支援が含まれる場合もある
フルアウトソース型(経理一括)
フルアウトソース型は、 記帳だけでなく請求書発行、経費精算、入出金管理まで一括で代行してくれるハイレベルなサービス形態 です。経理担当者を雇用する代わりに、専門業者に経理部門ごとアウトソースする形となります。
フルアウトソース型の対象業務例
- 日常の記帳業務
- 請求書・領収書の発行代行
- 経費精算・立替処理
- 売掛金管理・支払い処理
- 試算表の作成
中小企業や急成長中のスタートアップにとって、 内部リソースを割かずに専門性を確保できるメリットが大きいですが、その分、月額コストも高めになる傾向 があります。
税理士事務所併設型との違い
一部の記帳代行業者は、税理士事務所と提携または併設しており、 記帳業務から確定申告・税務相談まで一貫対応が可能 です。一方、記帳専門業者は税務代理権限を持たないため、 申告前には別途税理士と契約が必要 になります。
比較表:税理士併設型 vs 専門業者
| 項目 | 税理士併設型 | 記帳代行専門業者 |
|---|---|---|
| 記帳 | ○ | ○ |
| 税務相談・申告 | ○ | ✕(別途契約) |
| コスト | 高め | 比較的安価 |
| 柔軟性 | 低め | 高め |
「将来的に申告もまとめてお願いしたい」という方には併設型が向きますが、コストを抑えてまずは記帳だけ外注したい場合は専門業者がおすすめです。
選び方のポイントは「業務範囲とコスト」
どの記帳代行サービスが最適かは、 業務範囲とコストのバランスで判断するのが基本 です。例えば、記帳だけを外注して他は社内処理したいなら「月次パック型」、経理全体を任せたいなら「フルアウトソース型」が向いています。
選定時のチェックポイント
- 自社の記帳量(月間仕訳数など)
- 会計ソフトとの相性(freee、弥生など)
- 必要なアウトソース範囲(記帳のみ or 経理全般)
- 初期費用・月額コスト
記帳代行のサービス導入の流れややり方

-
STEP.1
打ち合わせ・プラン決定
経理代行サービスとプランや記帳業務について打ち合わせ
-
STEP.2
送付する資料の準備とチェック
依頼主が記帳代行サービスへ送付する記帳に必要な領収書や書類を準備
-
STEP.3
経理資料の送付
記帳業務に必要な書類が揃ったら、記帳代行サービスへ、資料を送付
-
STEP.4
会計システムへの記帳
記帳代行サービスが、送付されてきた書類をもとに、会計ソフトへ情報を入力
-
STEP.5
月次決算等の作成
記帳代行サービスは、記帳内容に基づき、月次試算表等を作成
-
STEP.6
依頼主への報告書提出および承認
記帳代行サービスは、依頼主へ月次試算表等を提出します。
-
記帳代行契約の注意点と雛形チェックポイント

記帳代行契約に含めるべき基本項目
記帳代行契約を結ぶ際は、 業務の内容・責任範囲・費用などの条件を明文化 しておくことが非常に重要です。契約があいまいなまま依頼を始めると、「やってもらえると思っていた作業が対象外だった」「納品時期が合わない」などのトラブルにつながります。
契約書に記載すべき主な項目
- サービス内容(仕訳範囲、会計ソフトの種類)
- 納期・納品形式
- 報酬金額・支払い方法・追加費用条件
- 秘密保持に関する条項(NDA)
- 契約期間と解約条件
- 責任の所在・免責事項
これらを事前に確認し、双方で認識にズレがないことを文書で残しておくことが信頼関係を築く第一歩です。
トラブルを防ぐための契約書チェックリスト
契約後に発生しがちなトラブルは、 契約時点での認識不足や曖昧な表現が原因となっていることが多く あります。これを防ぐためには、契約書の内容を細かく確認し、抜け漏れや曖昧表現がないかをチェックすることが重要です。
| チェック項目 | 内容の確認ポイント |
|---|---|
| サービス範囲 | 記帳対象の月次・年次・仕訳数などが明記されているか |
| ソフト指定 | 対応会計ソフトが明記されているか(freee、弥生など) |
| データ提出方法 | 資料の受け渡し形式(クラウド/紙/CSVなど) |
| 納品期日 | 納期と遅延時の対応方法が記載されているか |
| セキュリティ対応 | 秘密保持義務・情報漏洩対策について記載があるか |
これらのチェック項目を契約前に確認しておくことで、トラブルの未然防止が可能になります。
契約前に確認したい「よくある失敗例」
記帳代行を初めて依頼する事業者に多いのが、 「つい契約内容を細かく確認せずに進めてしまった」というケース です。その結果、想定外の費用請求や納期遅延など、後悔につながる失敗を経験してしまうこともあります。
よくある失敗例
- 「◯◯の作業は別料金です」と後から言われた
- 月末納品と思っていたが、実際は翌月中旬だった
- 担当者が変更され、対応品質が下がった
- 領収書の提出方法に制限があり、やり直しになった
こうした事態を防ぐには、 契約前の擦り合わせ・書面化・担当者との顔合わせ(対面orオンライン) が効果的です。
契約書の雛形はどう活用すべきか?
契約書の雛形は、 記帳代行業者や会計事務所、クラウドサービス提供会社のサイトなどで入手可能 です。ただし、そのまま使うのではなく、自社の業務内容や方針に合うようにカスタマイズすることが重要です。
雛形を活用する際のポイント
- 雛形にない項目(納期、納品形式など)を追記する
- 曖昧な表現(「必要に応じて」など)を明確にする
- 契約相手と事前に内容を共有し、修正・合意を取る
- 不安があれば専門家(税理士・社労士)にレビューを依頼
記帳代行の利用時に必要な資料

|
記帳代行を依頼する場合も、必要書類や資料の準備を行います。記帳に必要な書類を、漏れなく準備しなくてはならないという点は認識しておきましょう。
※上記以外にも必要書類がある場合があります
記帳代行を使ううえでの5つの注意点

契約期間があるかどうか
記帳代行サービスを利用するうえで、契約期間の定めがあるかを確認しておきましょう。求めている内容と異なった場合、長期間の契約をしていると契約解除ができない場合があります。
長期契約をして問題が発生した場合、コストも時間も無駄になってしまいます。サービスを契約する場合は、契約期間の定めの有無を確認しておきましょう。
情報管理が強化されているか
記帳代行を利用する場合、機密情報の取り扱いや守秘義務の明記など、情報管理が強化されているかどうかを注意しておかなくてはなりません。
会社の経理データは重要な機密情報のひとつです。信頼できるサービスなのかを計るうえでも、検討している記帳代行サービスがどのような情報管理を敷いているか確認しておきましょう。
決算申告は誰がするのか
記帳代行を利用する際は、決算申告業務を誰が担うのかという点を明確にしておきましょう。記帳業務は誰でも行えますが、決算申告は、納税者もしくは税理士しか行うことができません。
記帳代行を利用しているからといって、決算申告を代行してもらえるわけではないため、あらかじめ誰が決算申告を行うのか明確にしておくことがおすすめです。
コミュニケーションが密にとれるか
記帳代行を利用する際に、担当者との連携が取りやすいかどうかも重要です。連携を取るためのツールが使い慣れているものを使えるかどうかを確認しておくことがおすすめです。
仮に連携するツールが導入していないツールの場合、スムーズな連携が取れない場合もあり得ます。連携手段を事前に確認したり、希望のツールを伝えておきましょう。
価格設定が明確か
記帳代行を依頼する場合は、費用を明確にしましょう。基本料金やオプション料金が設定されている場合には、見積を行い、費用がいくらかかるのかを事前に計算しておくのがおすすめです。
仕訳数や規模、選ぶサービスによって費用は異なります。価格設定が明確なサービスや見積などを利用して、予算とのズレを生じさせないためにも、入念に確認しておきましょう。
おすすめの記帳代行サービス7選

おすすめ記帳代行サービス一覧表
| サービス名 | HP | 会計ソフト | 特徴 |
|---|---|---|---|
| KANBEI | HP | freee | ・低価格で記帳代行を利用可能 ・プランによって売上UPやコスト削減のサポートあり |
| CAV | HP | 弥生会計 等 | ・会計事務所からの依頼のみに特化 ・入力のみならず残高照会まで対応 |
| 経理外注・ 記帳代行センター |
HP | freee (要問合せ) |
・記帳代行だけでなく経理業務の各代行プランあり ・中小企業を中心にサポート |
| HELP YOU | HP | 要問合せ | ・オンラインアウトソーシング ・チームを組んで代行するため迅速な納品が可能 |
| Tax House | HP | 要問合せ | ・税理士と会計事務所のネットワークを活用した記帳代行サービス ・経営に必要な支援メニューが充実 |
| フジ子さん | HP | 要問合せ | ・オンラインアウトソーシング ・業界内でも特に安価な料金でサービスを提供 |
| ライト・コミュニケーションズ | HP | 要問合せ | ・10年以上の実績を持つ記帳代行サービス ・最短5営業日の納品が可能 |
KANBEI
KANBEIは株式会社Wizが展開する会計ソフトfreeeを利用した記帳代行サービスで、領収書、請求書などを送るだけで記帳をしてもらえます。
個人事業主などで経理担当者を雇う余裕がない場合や、中小企業で経理担当者が突然退職してしまった場合でも、経理人材を雇うより低コストに済みます。
▶KANBEIの詳細や資料DLはこちらCAV
CAVは株式会社Create Accounting Valueが運営する会計事務所に特化した記帳代行サービスです。仕訳が多い会計事務所でも、記帳業務のみを委託することで、他業務に専念できます。
残高照会や各種確認事項など、経理代行に近い業務も委託できます。確定申告月のみなど、突発的な依頼ができる点も魅力です。
▶CAVはこちら経理外注・記帳代行センター
経理外注・記帳代行センターはマクシブ総合会計事務所が運営する記帳代行サービスです。中小企業を中心に記帳業務をサポートしています。
CAVでは記帳代行サービスだけでなく、給与計算や年末調整代行サポートなど、様々な経理業務のサポートプランを展開しているのが特徴です。
▶経理外注・記帳代行センターはこちらHELP YOU
HELP YOUは株式会社ニットが運営する記帳代行サービスです。チームを組んで帳簿代行するため、迅速な納品が期待できます。
500人の優秀なアシスタントの中から自社に合った人がついてくれるので、業務のスピードだけでなく質の高さも両立できるのが特徴です。
Tax House
Tax Houseは株式会社エフアンドエムが運営する記帳代行サービスです。全国に約370店舗の税理士事務所が加盟しており、税理士と会計事務所のネットワークを活用しています。
帳簿代行だけでなく、財務・補助金など中小企業の経営において必要な支援メニューも充実しているので、経営全般に不安があり相談してみたい場合におすすめです。
フジ子さん
フジ子さんはBPOテクノロジー株式会社が運営する記帳代行サービスです。業界内でも特に安価な料金でサービスを提供しています。
フジ子さんであれば、無料トライアルで実務能力の事前チェックだけでなく翌月解約もできるので、帳簿代行に不安がある場合におすすめです。
ライト・コミュニケーションズ
ライト・コミュニケーションズはライト・コミュニケーションズ株式会社が運営する記帳代行サービスです。帳簿代行は10年以上・毎日150社以上と豊富な実績があります。
初期登録料として2万7,500円(税込)が必要ですが、専任の担当者が毎月帳簿代行をするので、迅速・柔軟な対応が期待できるのが魅力的なポイントです。
記帳代行ならKANBEI
記帳代行サービスでは、KANBEIがおすすめです。KANBEIは、導入実績1000社を突破し、クラウド会計freeeに特化した内容で膨大な経理業務を代行サポート!経理担当者の業務負担軽減に役立ちます。
KANBEIでは、ミニマムプラン(30記帳)、ベーシックプラン(100記帳)、バリュープラン(500記帳まで)の3種類のプランを展開しています。
契約するプランによっては、経理関連のDX、売上UP、総合的なコスト削減、補助金活用など経営サポートも行えます。以下のバナーでは、簡単にKANBEIに関する「資料DL」が可能です。ぜひ活用してみてください!
記帳代行のまとめ
記帳業務は、会社のお金の動きを把握するために重要な業務です。しかし毎日の取引や確認作業により、経理担当者に負担がかかる業務でもあります。
そこでおすすめしたいのが記帳業務を外部に依頼できる「記帳代行サービス」。経理のプロが企業の経理担当者に代わって記帳業務を行います。
記帳代行サービスは経理代行と比べても、比較的安価に利用できるうえに、セキュリティ面を担保しつつ自社のお金の動きを把握できるのが利点です。
当サイトではおすすめしている記帳代行サービスKANBEIでは、日々の記帳業務や経理業務の効率化に有効です。
以下のリンクから、KANBEIの詳細や資料DLも可能になっているので、ぜひご活用活用ください!


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!