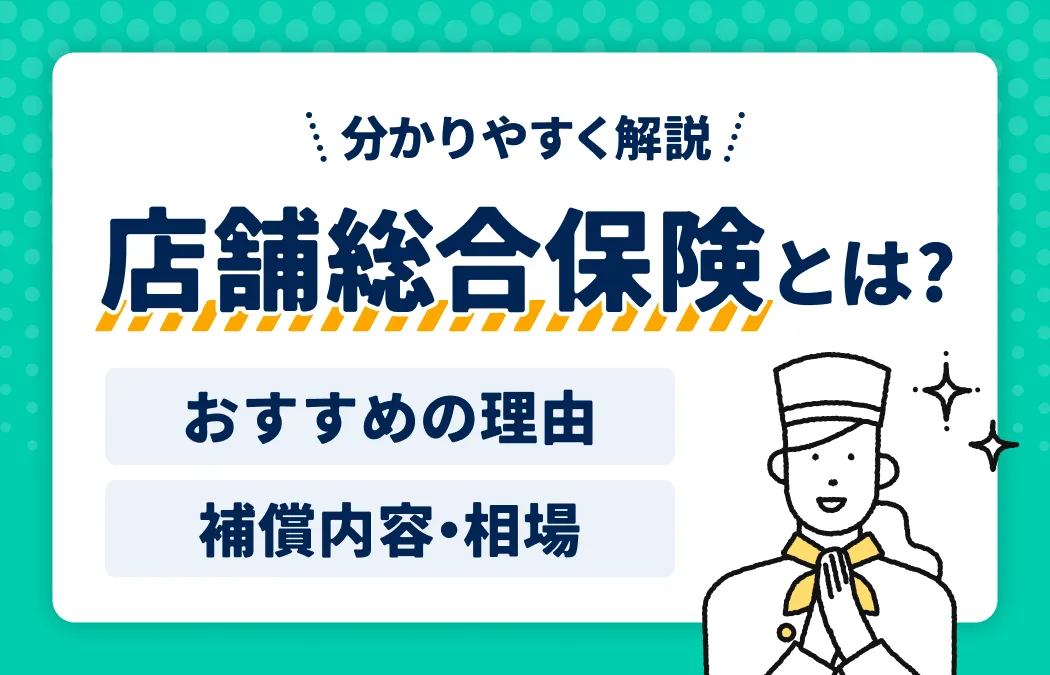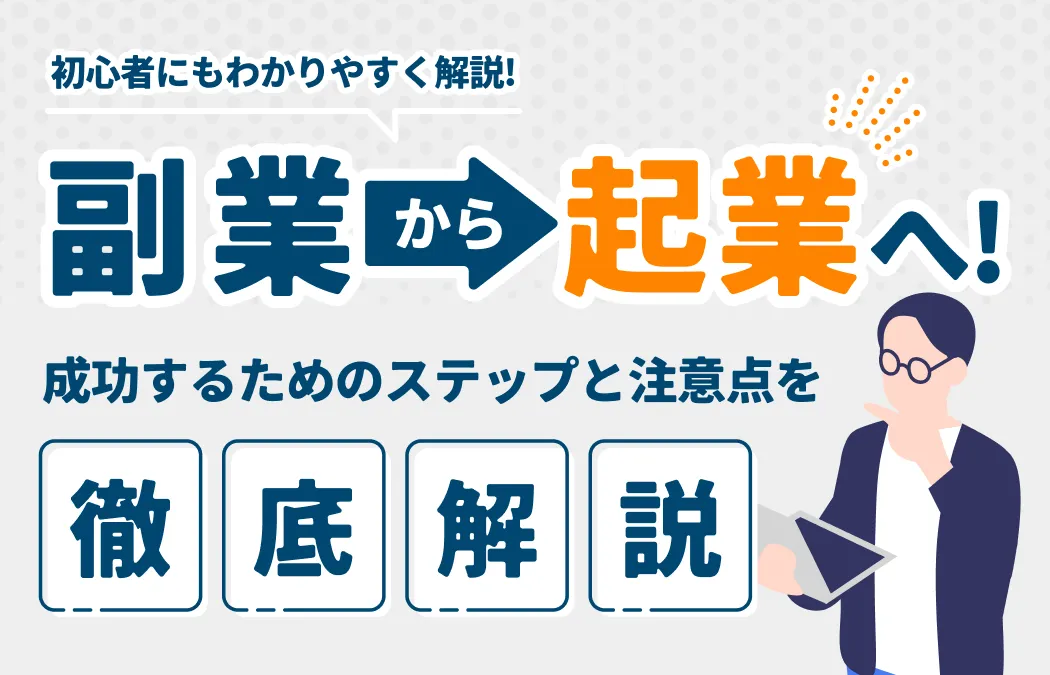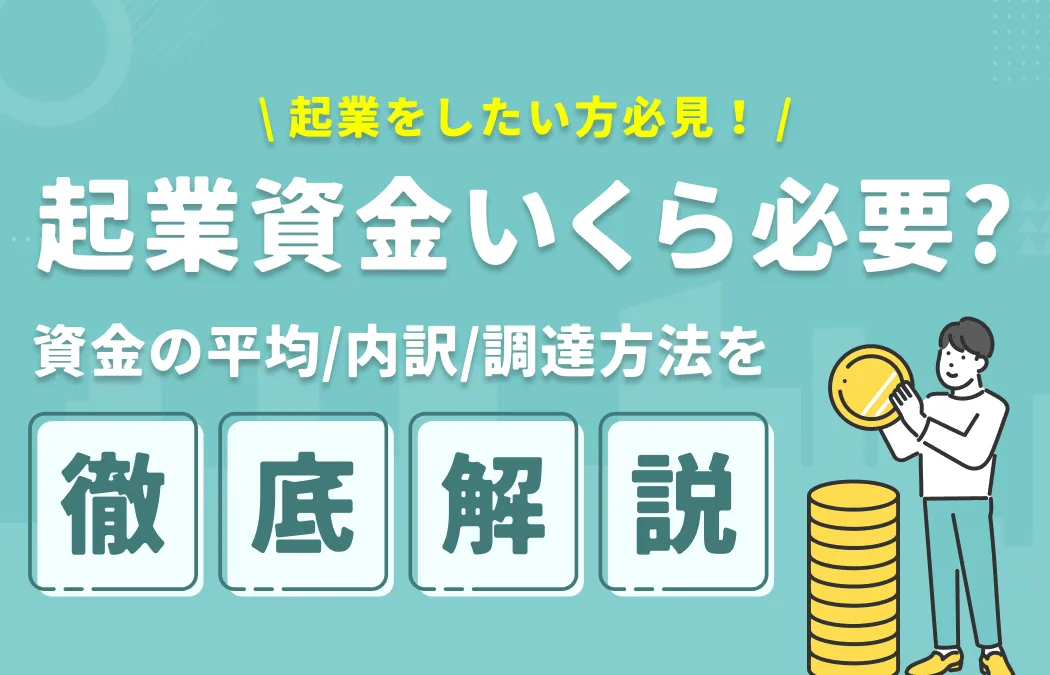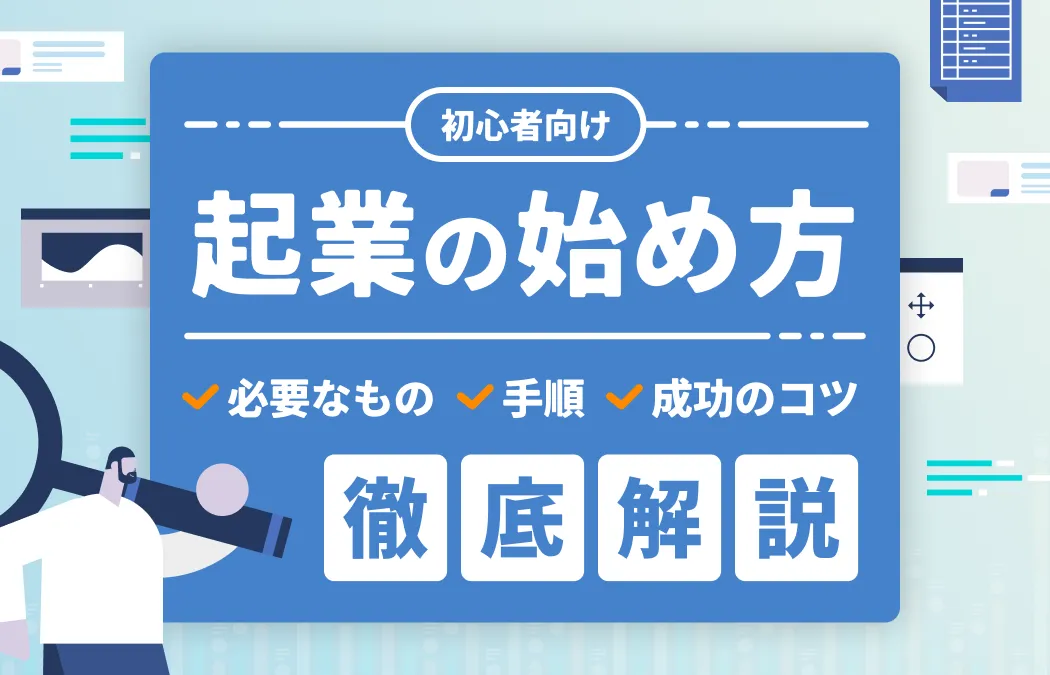「年収いくらから開業届を出す必要がある?」
「税金面でのメリットはある?」
会社員の副業で開業届は必要? 条件
しかし、「開業届を出す条件が分からない」「会社に副業がばれる?」「出してないことで罰則はある?」など気になる点も多いはずです。
本記事では、開業届を出すメリット・デメリット、提出を検討すべきタイミングなどを解説します。
目次
開業届とは?基本をおさらい
開業届を出すと個人事業主として認められる
開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれる書類で、 税務署に提出することで個人事業主としての活動が公式に認められます 。
これにより、確定申告が必要な「事業所得」として収入を計上できるほか、青色申告の特典(最大65万円の控除など)も受けられるようになります。
個人事業主は法人とは異なり、登記の必要がなく手続きが比較的簡単です。
- 提出先:事業を行う地域を管轄する税務署
- 提出のタイミング:原則、開業から1か月以内

編集部
開業届は、これからフリーランスや個人でビジネスを始める方にとって第一歩となる重要な届け出です。
事業所得がある場合は基本的に開業届が必要
事業所得とは、 継続的かつ反復的に収入を得る業務から発生する所得 を指し、フリーランスの仕事や自営業での収入が該当します。
このような所得がある場合、収入の規模に関係なく、基本的に開業届の提出が求められます。
事業所得として申告することで青色申告の対象となり、税制上のメリット(控除や家族の給与計上など)を受けることが可能です。
もし開業届を提出せず、事業所得ではなく「雑所得」として申告すると、これらの優遇措置を受けられなくなるため注意が必要です。
副業で開業届が必要なケース
開業届を 提出しないことで罰則を科されることはありませんが、提出義務自体はある ため注意が必要です。
例えば、フリーランスのライターやハンドメイド作品の販売など、収益を得ることを目的として反復的に行っている場合は「事業所得」とみなされる可能性が高く、開業届を出すのが望ましいです。
一方で、不定期で収入も少なく趣味の延長と考えられる場合は「雑所得」に該当し、開業届が不要な場合もあります。
個人事業主・自営業・フリーランスの違い
- 個人事業主:開業届を提出し、個人で事業を営んでいる人の法的な呼び方。
- 自営業:広義には法人も含むが、一般的には個人で商売をしている人を指す口語的表現。
- フリーランス:特定の雇用主に属さず、案件ごとに契約して働くスタイル。個人事業主である場合が多い。
| 定義 | 法的な位置づけ | 使用される場面 | |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 税務署に開業届を提出した人 | 法的に認められた事業形態 | 税務署・書類などの正式な場面 |
| 自営業 | 自分で事業を行う人の一般的な呼び名 | 明確な法的定義なし | 日常会話やビジネス一般用語 |
| フリーランス | 企業や事業主に雇用されない働き方 | 法的には個人事業主が多い | 働き方としての呼称 |
副業で開業届を出すメリット
-
経費の範囲が広がる
-
青色申告特別控除が受けられる
-
損益通算ができる
-
損失の繰越控除ができる
-
小規模企業共済に加入できる
-
屋号名義の銀行口座を開設できる
-
事業の証明ができる/就労証明書代わりになる
-
補助金や給付金を申請できる
経費の範囲が広がる
副業で開業届を提出し、個人事業主として認められると、事業に関わる支出を「経費」として計上できるようになります。
例えば、仕事に使うパソコンの購入費用や通信費、取材や打ち合わせの交通費などを経費にすることで、課税対象となる所得を減らせます。
経費の範囲が明確に広がることで、節税効果が高まり、手元に残る利益が増える可能性 があります。
開業届を出さずに雑所得で申告している場合、経費が限定的にしか認められないことが多いため、事業としての認定を受けることは大きなメリットです。
青色申告特別控除が受けられる
青色申告を選択することで、 最大65万円(簡易簿記なら10万円)の「青色申告特別控除」 が受けられます。
これは、所得からの直接控除による大きな節税効果を持つ制度で、開業届と青色申告承認申請書を提出して初めて利用可能になります。
帳簿の作成や記帳義務はあるものの、ソフトなどを使えば管理は比較的簡単です。副業収入が増えてきた場合には、積極的に活用しましょう。

個人事業主におすすめの会計(確定申告)ソフト5選比較!無料ソフトも紹介
確定申告ソフトの人気おすすめランキングを徹底比較することに加えて、ソフトの選び方などついても徹底解説していきます。
詳しくはこちら
損益通算ができる
副業の事業で赤字が出た場合でも、他の所得(たとえば本業の給与所得など)と合算して税金を計算できる のが「損益通算」です。
例えば、副業で10万円の赤字があった場合、その分を本業の収入から差し引いて課税所得を減らすことができ、結果として所得税や住民税の軽減につながります。
雑所得ではこの損益通算は基本的に認められないため、開業届を出しておくことで得られる大きな税務メリットです。
損失の繰越控除ができる
青色申告をしている個人事業主は、 事業で発生した赤字(損失)を最長3年間にわたって繰り越して、将来の黒字と相殺する 「繰越控除」が可能になります。
例えば、副業で初年度に赤字が出ても、次年度以降に黒字になれば、その赤字分を差し引いた金額に対して課税されるため、結果的に税金が安くなります。
また、赤字による損失の軽減だけでなく、翌年以降に利益が出た際の税負担軽減にもつながります。
開業届と青色申告の手続きをしていなければこの制度は利用できないため、長期的な視点で副業を考えるなら大きなメリットです。小規模企業共済に加入できる
開業届を提出して個人事業主となることで、中小機構が提供する「小規模企業共済」に加入できるようになります。
これは、 事業主のための退職金制度のようなもので、毎月の掛金は全額が所得控除の対象になる ため、節税効果も高いです。
さらに、事業を廃止した際や老後の生活資金として共済金を受け取ることができ、将来に備える資産形成にもなります。
副業でも安定的に事業を継続していく予定がある場合には、リスク管理と老後資金対策の一環として非常に有効な制度です。
屋号名義の銀行口座を開設できる
開業届を出す際に「屋号(ビジネスネーム)」を設定すれば、その名前を使った銀行口座を開設することが可能です。
これにより、 プライベートの資金と事業の収支を明確に分けて管理できるため、帳簿の作成や確定申告が格段にしやすく なります。
また、取引先からの信頼感も高まり、ビジネスとしての信用力が向上します。
屋号口座を持つことで一段とプロフェッショナルな印象を与え、取引先からの信頼感も高まり、ビジネスとしての信用力が向上します。
事業の証明ができる/就労証明書代わりになる
開業届を出しておくことで、「私はこの業務で事業を営んでいます」という公的な証明になります。
これにより、例えば子どもが保育園へ入園する際、申し込み時に必要な就労証明書の代わりに使えることもあります。
また、フリーランスとして活動している場合、取引先や行政から「事業実態の確認」が求められることもありますが、開業届を提出していればその証明になります。
副業でも継続的に活動している場合、 信頼性の証として、また行政サービスの申請にも役立つ大切な書類 となります。
補助金や給付金を申請できる
開業届を提出して事業として認められていれば、 国や自治体が実施する補助金・助成金・給付金などの支援制度に応募することが可能 になります。
例えば、コロナ禍で支給された「持続化給付金」なども、開業届の提出が要件の一つでした。
こうした制度は設備投資や販路開拓、IT導入などに使えるものも多く、資金的な後押しになります。
副業で新しいサービスや商品を展開する際にも、これらの支援を受けることで事業の拡大をスムーズに進められる可能性が高まります。
副業で開業届を出すデメリットと注意点
- 失業手当が受けられない
- 会社に副業がばれる可能性
- 確定申告の手続きが煩雑
- 帳簿作成の義務が発生
- 扶養のまま健康保険を継続できない可能性
- 所得が増えれば納税額が増える
失業手当が受けられない
開業届を提出し個人事業主として登録されると、 「就業状態」と見なされるため、原則として雇用保険の失業手当(基本手当)は受け取れなくなります 。
これは、副業であっても「独立して働く意志がある」と判断されるためです。
基本的にハローワークでは、求職活動をしながら失業状態を保つ必要があるため、事業を始めた時点で支給対象外となる可能性が高いと考えましょう。
副業を本格化させる前に、失業給付との兼ね合いやタイミングを十分に確認しておくことが重要です。
会社に副業がばれる可能性
開業届を出して事業収入を申告すると、 住民税の計算にも反映されるため、本業の給与と合算された住民税額が会社に通知されます 。
その結果、住民税が不自然に高くなり、経理担当者などに副業が発覚する可能性があります。
副業禁止規定がある会社では、懲戒処分の対象になることもあるため、事前に会社の就業規則を確認し、慎重な対応が求められます。
副業が会社に知られないようにする方法|住民税の納付方法で「普通徴収」を選択する
副業による住民税の通知を会社に知られないようにするには、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」にするのが有効です。
通常、会社員の住民税は、勤務先が給与から天引きする「特別徴収」という方法で支払います。
しかし、 「普通徴収」にすることで、副業分の住民税は自宅に届き、自分で納める形になるため、会社の給与支払報告書には副業収入分が反映されません 。
会社には副業所得による住民税の追加分の情報が通知されないため、副業を知られるリスクを軽減できます。
ただし、市区町村によっては自動的に「特別徴収(給与から天引き)」へ変更される場合もあるため、確定申告後は役所に確認することをおすすめします。
-
「普通徴収」を選択する方法
-
【確定申告をする場合】
確定申告をする場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄で「自分で納付」を選ぶと、普通徴収に切り替えられます。

【確定申告をしない場合】
副業収入の確定申告が不要な場合も、市町村への住民税申告が必要です。住民税の申告書に「普通徴収」にしたい旨を記載し、市町村に申告しましょう。

確定申告の手続きが煩雑
副業で収入を得るようになると、原則として確定申告が必要になります。
特に開業届を出して個人事業主となった場合、 所得の種類は「事業所得」となり、必要経費や控除の記載、帳簿に基づいた収支内訳の作成など、提出書類も多くなります 。
青色申告を選ぶとさらに帳簿の要件が増えるため、会計ソフトの導入や記帳ルールの習得が必要です。
帳簿作成の義務が発生
開業届を提出すると、 事業所得としての収入に対して帳簿の作成と保存が義務づけられます 。
白色申告でも簡易帳簿の記録が必要で、青色申告を選択した場合には複式簿記など、より詳細な帳簿管理が求められます。
日々の収入と経費をきちんと記録しておかないと、確定申告の際に正しい計算ができず、場合によっては税務署から指摘を受ける可能性もあります。
帳簿付けが苦手な人や本業が忙しい方にとっては、この作業がストレスになるでしょう。
扶養のまま健康保険を継続できない可能性
扶養内で副業をしている場合、 年間の収入が130万円を超えると配偶者や親の扶養から外れ、自身で国民健康保険に加入する必要が生じます 。
また、収入の見込みによって扶養から外れる可能性があるため、開業届の提出は保険上の取り扱いにも影響します。
特に副業収入が増えた場合は、保険料の負担が一気に増えることもあるため、収入と保険の関係を事前に確認しておくことが重要です。
所得が増えれば納税額が増える
副業で得た所得は、給与所得と合算されて課税対象となるため、 収入が増える分、所得税・住民税・国民健康保険料などの負担も増えます 。
特に、副業で成功して本業に匹敵する収入を得た場合、税率の高い課税区分に入ってしまい、税金の負担が急激に増加する可能性があります。
節税対策として青色申告や経費計上を活用することは可能ですが、ある程度の知識と準備が必要です。
副業の開業届を出して個人事業主になるための手続き
| 税務署への手続き |
|
|---|---|
| 税事務所への手続き |
|
| 勤務先への手続き |
|
| そのほかの手続き |
|
税務署への手続き
副業で個人事業を始める際はまず、 開業届(=個人事業の開業・廃業等届出書)を事業を行う住所を管轄する税務署へ提出 しましょう。
また、青色申告を希望する場合は、同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出が必要です。これにより、青色申告の特典(控除や繰越控除)が受けられるようになります。
なお、各書類は国税庁のホームページからダウンロード可能です。税事務所への手続き
税務署と似ていますが、 「税事務所」は地方税(住民税・事業税など)を扱う都道府県の機関 です。
通常、開業届を税務署に提出すれば、地方自治体にも情報が共有されますが、自治体によっては「事業開始等申告書」の提出が別途必要になる場合もあります。
これは、個人事業税や住民税の算出のために使われるため、地域によっては提出漏れがあると後で通知が届くことも。
事業を始める前に、居住地の都道府県や市区町村のウェブサイトで、必要書類の有無や提出方法を確認しておくことが安心です。
勤務先への手続き
副業として開業する場合、勤務先に届け出る義務があるかどうかは会社の就業規則によります。
企業によっては事前申請・承認が必要な場合もある ため、トラブルを防ぐためにも事前に規則を確認しておきましょう。
特に、公務員や一部の業種では副業が法律で制限されているケースもあります。
申告せずに副業を行っていたことが判明した場合、懲戒の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
そのほかの手続き
副業での開業後、事業の規模や内容によっては、その他の手続きも必要になる場合があります。
例えば、飲食業や美容業など 特定業種では、保健所や消防署などへの営業許可や届出が求められることがあります 。
また、事業用の屋号名義の銀行口座を開設したり、必要に応じて事業用の電話番号やホームページを整備することも検討しましょう。
なお、適格請求書発行事業者になるには消費税課税事業者に登録する必要があり、「適格請求書発行事業者登録申請書」も必要となります。
開業届の書き方・提出方法・タイミング
開業届の記載事項
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)には、 氏名・住所・屋号・事業開始日・職業・事業の概要・事業所所在地など を記載します。
屋号は任意ですが、銀行口座開設や請求書の発行などに便利なため、設定する人も多いです。
「事業の概要」欄には、簡潔に業務内容を記載するのがポイントです。
本業と副業の開業届の違い
開業届の書き方は、本業でも副業でも基本は同じ ですが、以下の点に注意しましょう。
自宅で副業を始めた場合の書き方
事業所所在地には「自宅住所」を記載します。自宅兼用でも問題ありませんが、マンション名・部屋番号まで正確に書きましょう。
家賃や光熱費の一部を経費にできる可能性もあります。
副業別の職業欄や事業の概要の書き方
例えば、ライターなら「Webライター業」、ハンドメイド販売なら「クラフト製作・販売業」などと記載。
「事業の概要」欄には、「○○に関する記事作成及び編集業務」や「ハンドメイド作品のネット販売」など、具体的かつ簡潔に書くことが大切です。
開業届の提出方法は3種類|窓口・郵送・ネット
- 税務署窓口での提出:書類を直接持参する方法。その場で受理印の押された控えをもらえます。
- 郵送による提出:提出用と控え用の2部を同封し、返信用封筒(切手貼付)を同封すれば、控えが返送されます。
- e-Taxでの電子申請:マイナンバーカードを使ってオンラインで完結できます。控えはPDFで発行されます。
開業届を出す際に必要な書類・もの
- 個人事業の開業・廃業等届出書(原則2部:提出用と控え用)
- 本人確認書類(窓口提出時)
- 印鑑(認印でOK)
- 返信用封筒と切手(郵送の場合)
- 印鑑(認印でOK)
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告を希望する場合)
各書類は、税務署での記入も可能ですが、事前に記入しておくとスムーズです。国税庁の公式サイトからPDFをダウンロードできます。
開業届の提出期限はいつまで?
開業届は、 事業を開始した日から1ヶ月以内に提出することが原則 とされています。ただし、遅れて提出しても罰則はありません。
青色申告の控除を受けたい場合は、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、開業届も同時に提出しておくのが安心です。
申請が遅れると、その年の青色申告ができず、控除などのメリットが受けられなくなるため、早めの提出が推奨されます。
開業届にかかる費⽤
開業届の提出では、手数料や提出費用は一切かかりません 。
郵送の場合は返信用封筒と切手代がかかりますが、それ以外の実費負担は基本的に発生しないため、収入の規模に関わらず早めに出しておくのが得策です。
創業資金が最大0円!
【無料】お問い合わせはこちら開業届を出す際の注意点
開業届の提出時に選ぶ「職業」によって税率が変わる
開業届に記載する「職業」や「事業の概要」は、将来的な個人事業税に影響を与えることがあります。
個人事業税は、事業の種類によって税率が異なり、例えば「物品販売業」は税率5%、「文筆業」は3%などと定められています (都道府県により多少の違いあり)。
ただし、すべての職業が課税対象ではなく、例えば「アフィリエイト収入」などは非課税とされるケースもあります。
開業届の職業欄は税率にも注意しつつ、なるべく正確に記載しましょう。迷った場合は、税務署に確認するのがおすすめです。
就業規則で副業が禁止されている場合もある
現在の勤務先が副業を禁止している場合、 開業届の提出によって会社に副業が発覚し、懲戒処分などに発展するリスク があります。
開業届を提出する前に、就業規則に明記されている「副業禁止」のルールや、事前申請・承認制度があるかを必ず確認しましょう。
特に公務員や一部の企業では、法律や社内規定により副業が明確に制限されているため注意が必要です。
副業を始める際の社会保険と年金への影響
副業を始めて開業届を出すと、収入によっては健康保険や年金の負担が増えることがあります。
特に、配偶者の扶養に入っている場合、 年間収入が130万円を超えると扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます 。
また、会社員として厚生年金に加入している人は、通常は副業収入によって保険の資格が変わることはありませんが、住民税や所得税の増加に伴って、間接的な負担増を感じることも。
副業を本格化させる前に、社会保険の加入条件や扶養基準をしっかり確認しておくことが安心です。
副業で開業届が必要になる目安は所得がいくらから?
開業届を出すべきパターン
- 副業での年間所得金額が20万円を超えた
- 節税効果で手取りを増やしたい
- 将来的に事業を拡大したい
- 売上が増えて納税義務が発生した
副業での年間所得金額が20万円を超える場合
副業による 年間所得(=収入から必要経費を差し引いた金額)が20万円を超えると、原則として確定申告が必要に なります。
このタイミングで開業届を提出しておくことで、所得を「事業所得」として申告でき、青色申告の特典や経費計上の幅が広がります。
なお、所得が20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があるため、税務署や市区町村に確認しましょう。
また、20万円はあくまで「所得」であり、売上(収入)ではない点に注意が必要です。
節税効果で手取りを増やしたい場合
開業届を出し 「青色申告」を選択することで、最大65万円の特別控除が受けられ、結果として税負担を大きく削減 できます。
さらに、諸コストを経費として計上できるようになり、実質的な手取り額を増やすことも可能です。
副業が軌道に乗りはじめたら、節税効果を最大限に活かすために開業届の提出を検討しましょう。
将来的に事業を拡大したい場合
今は副業でも、将来的に独立や事業拡大を目指している場合は、早い段階で開業届を出しておくのがおすすめです。
これにより、 屋号付きの銀行口座の開設、補助金の申請、小規模企業共済への加入など、事業運営に役立つ制度が利用可能 になります。
また、開業日が明確になることで、ビジネス歴や実績の証明としても活用できます。
納税義務が発生した場合
副業で一定の所得を得ていれば、たとえ本業がある会社員であっても納税の義務が生じます。
開業届を出すことで、 事業所得としての計上が可能になり、損益通算や繰越控除などの税務上のメリット を受けられるようになります。
逆に、開業届を出さずに雑所得として申告するとこれらの優遇措置が使えず、不利になるケースがあります。
開業届を出さない方が良いパターン
副業の所得がごく少額で、たとえば 年間所得が20万円以下、または数回だけのスポット収入にとどまる場合 は、無理に開業届を出す必要はありません。
このようなケースでは「雑所得」として確定申告することで問題なく処理できます。
開業届を出さないとどうなる?
開業届を出さないことで罰則はあるの?
開業届を提出しなかったとしても、 罰則やペナルティは原則としてありません 。
ただし、確定申告義務があるにもかかわらず申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税などの追徴課税の対象になることがあります。
確定申告をするにあたって、青色申告特別控除などの優遇を受けられるという観点から、開業届は自身が損をしないために重要な届出と考えましょう。収入が「雑所得」として扱われる
開業届を提出していない場合、副業収入は「雑所得」として扱われることが一般的です。
雑所得では、経費として認められる範囲が限られており、青色申告ができない、損益通算ができないなどのデメリットがあります。
また、 事業としての実態があるにもかかわらず雑所得として申告すると、税務調査で指摘される可能性 も。
事業的な収益性や継続性がある場合は、開業届を出しておくのが安全です。
社会的信用が得られにくい
開業届を出していないと、屋号付きの銀行口座の開設や補助金の申請、事業実績の証明などが難しくなります。
たとえば、子どもの保育園の入園手続きで「就労証明書」が必要な場合や、 取引先に事業者であることを証明したい時に、開業届を提出していないと対応できない ことがあります。
副業でも社会的信用を高め、ビジネスとしての信頼性を持たせたい場合は、開業届の提出が有効です。
将来の事業拡大の足かせになることも
副業から本業へと事業を拡大したいと考えている場合、 開業届を出していないと、経歴や実績の証明が曖昧になり、融資や補助金の申請時に不利になる ことがあります。
また、帳簿が整っておらず、過去の収支を証明できないことで、金融機関や自治体の支援を受けにくくなるリスクも。
将来を見据えて、事業の信頼性を築くためにも、早い段階で開業届を提出しておくのが賢明です。
副業として個人事業主になれる職業
- 物販
- ライティング
- アフィリエイト
- 宅配
- 写真撮影、コンサルティング、Webデザイン、ITエンジニア、翻訳
物販
物販は、メルカリやヤフオク、BASE、Amazon、楽天などの ECプラットフォームを活用して、商品を販売するスタイル です。
業者から仕入れた商品のほか、ハンドメイド品の販売も含まれます。
売上から仕入れや送料、梱包費などを差し引いた金額が「所得」となり、一定以上の利益が出れば開業届を出して個人事業主として活動できます。
ライティング
Webライターや記事作成、コンテンツ制作などの仕事 は、在宅でできるため副業に非常に人気です。
継続的に受注し収益を上げている場合、開業届を提出して個人事業主として活動することが可能。
事業の概要欄には「Webライター業」や「コンテンツ制作業」と記載しましょう。
アフィリエイト
ブログやSNSを活用して広告収入を得る「アフィリエイト」 も、一定の収入が継続的に発生していれば事業とみなされ、個人事業主になることが可能です。
Google AdSenseやA8.netなどの広告収入は、仕組み上、自動で報酬が発生することが多いですが、コンテンツ作成やSEO対策などの継続的な努力が伴うため、事業性が認められやすい業種です。
職業欄には「インターネット広告業」などと記載します。
宅配
Uber Eatsや出前館、Amazon Flexなどの個人宅配ドライバー も、業務委託契約で働くため、労働者ではなく「個人事業主」として扱われます。
開業届を提出することで、ガソリン代や車両の整備費、スマホ通信費などを経費として計上でき、節税効果が期待できます。
事業の概要には「軽貨物運送業」や「配達業務」と記載し、事業用としての記録をしっかりと残しておくことが大切です。
写真撮影、コンサルティング、Webデザイン、ITエンジニア、翻訳など
写真撮影、コンサルティング、Webデザイン、ITエンジニア、翻訳などの職業は、すべてフリーランスや副業として成立しやすく、個人事業主としても十分活動可能です。
撮影業務であれば「写真業」、コンサルティングなら「経営コンサル業」、Webデザインなら「デザイン業」など、具体的な業務に合わせて開業届の職業欄に記載します。
共通するのは、継続的にクライアントからの依頼を受け、報酬を得ている点です。 専門スキルを活かした職種は、信用のためにも開業届を出すことが有利に働きます 。
【注意】個人事業主になれない職業がある
すべての職業が個人事業主として認められるわけではありません。
- 雇用契約のもとで働く会社員やパート、アルバイト
- 医師、弁護士、税理士など特定の資格を必要とする職業は、開業にあたって所定の登録や届出が別途必要
- 風俗業や一部のギャンブル関連事業などは、法的に認可を受けなければ開業できません
自分の副業が該当するかどうかは、税務署や専門家に相談するのが確実です。
副業の開業届に関するよくある質問
A
メルカリやラクマなどのフリマアプリで得た収益については、その目的と取引の継続性によって開業届が必要かどうかが異なります。自宅にある不用品をたまに売る程度であれば、「一時所得」や「雑所得」として扱われ、開業届は不要です。しかし、商品を仕入れて販売するなど、継続的に利益を得るビジネスとして行っている場合は「事業所得」とみなされ、開業届の提出が推奨されます。目安として、継続性と営利性があるかどうかが判断基準です。
A
ハンドメイド作品をminneやBASE、Creemaなどで継続的に販売し、利益を得ている場合は、個人事業主としての開業届を提出するのが望ましいです。趣味の範囲でたまに販売するだけなら雑所得で問題ありませんが、仕入れや制作に費用をかけ、定期的に収益を得ているなら「事業」と見なされます。開業届を提出すれば、必要経費を計上しやすくなり、青色申告などの節税効果も得られるため、収入が安定してきたら早めの届け出をおすすめします。
A
複数の副業をしている場合でも、開業届は一枚でOKです。その際、「職業」欄や「事業の概要」欄に、行っているすべての業務内容をまとめて記載します。たとえば「Webライター・アフィリエイト・ネット物販」など、複数の内容を記載すれば、幅広い事業として認められます。また、今後事業内容が増えても、再度開業届を出す必要はありません。変更がある場合は「変更届出書」を提出することで対応できますので、柔軟に管理が可能です。
A
複数の副業をしている場合でも、開業届は一枚でOKです。その際、「職業」欄や「事業の概要」欄に、行っているすべての業務内容をまとめて記載します。たとえば「Webライター・アフィリエイト・ネット物販」など、複数の内容を記載すれば、幅広い事業として認められます。また、今後事業内容が増えても、再度開業届を出す必要はありません。変更がある場合は「変更届出書」を提出することで対応できますので、柔軟に管理が可能です。
A
開業届を出すことで、健康保険や雇用保険に直接の影響は基本的にありません。ただし、副業の所得が一定以上(年収130万円以上)になると、配偶者の扶養から外れる可能性があり、その場合は自分で国民健康保険に加入する必要があります。また、雇用保険の面では、個人事業主として事業を行っていると見なされると、失業手当の支給要件を満たさないことも。副業でも収入が増えてきた場合には、保険制度の影響を事前に確認しておくことが大切です
まとめ
近年、副業による収益活動が一般化する中で、開業届の提出は個人の事業活動を法的に明確化し、税務上の適切な管理を行う上で重要な手続きです。
開業届を提出することで「事業所得」として申告でき、青色申告による特別控除や損益通算、赤字の繰越控除など、多くの税制上の優遇措置を受けることが可能となります。
また、屋号名義の銀行口座の開設や、補助金・助成金の申請、小規模企業共済への加入といった、事業基盤の整備にも開業届は欠かせません。
副業で開業届を提出するか否かは、税務処理の正確性に加え、事業の継続性や信頼性にも関わる重要な判断事項です。収益の有無だけでなく、将来的な展望も踏まえたうえで、適切な手続きを行うことが求められます。
創業資金が最大0円!
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!