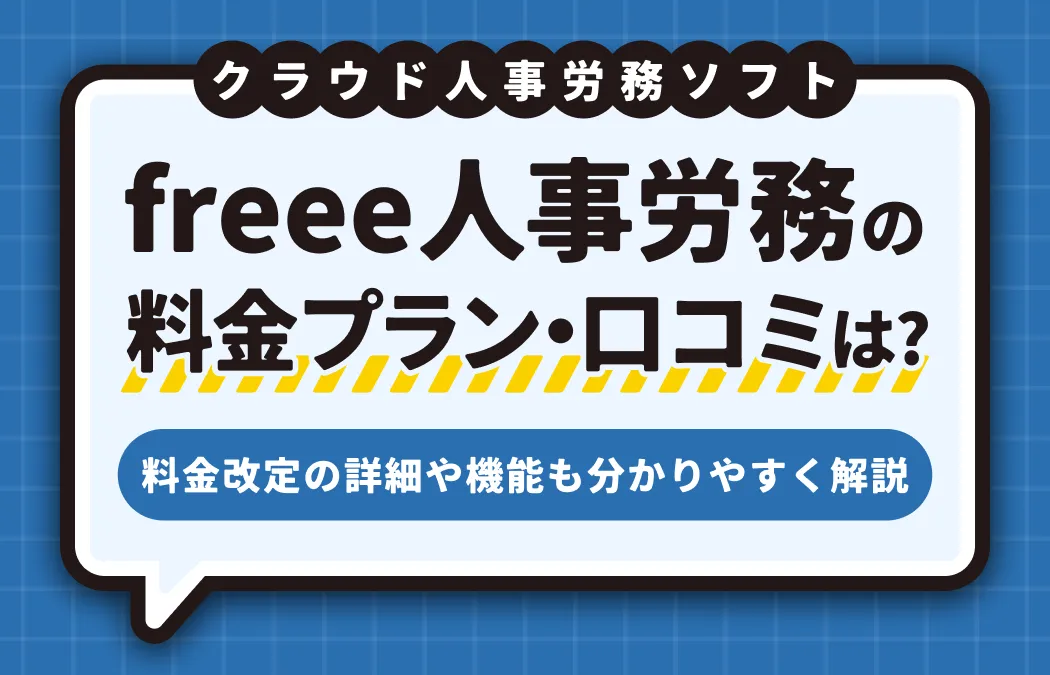「どの書類が自分に必要か、見極め方がわからない…」
「初めての青色申告、ミスなく行いたい!」
青色申告では、帳簿の作成に加えて、所定の書類を期限内に正しく提出する必要があります。
とはいえ、どんな書類が必要で、いつ・どのように提出すればよいのか、初めての方にはわかりにくい点も多いでしょう。
この記事では、青色申告に必要な提出書類を中心に、申請の手順や帳簿の準備までをやさしく解説します。
申告の基本をしっかり押さえて、スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事はアフィリエイト広告を含みます。
目次
▼この記事で紹介している商品
青色申告とは?
青色申告とは「帳簿づけにより税金が安くなる制度」
青色申告とは、 所定の方式で帳簿をつけて確定申告することで、税金の優遇を受けられる制度 です。
例えば、最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越せたりと、節税に役立つメリットが多くあります。
白色申告に比べて手間はかかりますが、帳簿ソフトやクラウド会計を活用すれば、初心者でも十分に対応可能です。

青色申告とは?個人事業主・フリーランスの確定申告をわかりやすく解説
青色申告と白色申告の違いはもちろん、それぞれのメリット・デメリット、必要な準備や手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
詳しくはこちら青色申告には事前の申請が必須
青色申告を始めるには、 「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出 する必要があります。
誰でも自動的に青色申告できるわけではないため、注意しましょう。
開業後すぐに青色申告をしたい場合は、開業届と一緒に申請書も提出しておくとスムーズです。
申請期限は2月16日から3月15日までが通例
青色申告の承認申請書は、 原則として「青色申告を始めたい年の3月15日まで」に税務署へ提出 する必要があります。
ただし、新たに事業を始めた場合(開業した場合)は、開業日から2か月以内に提出すれば問題ありません。
期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告が利用できなくなるため、早めの準備が重要です。
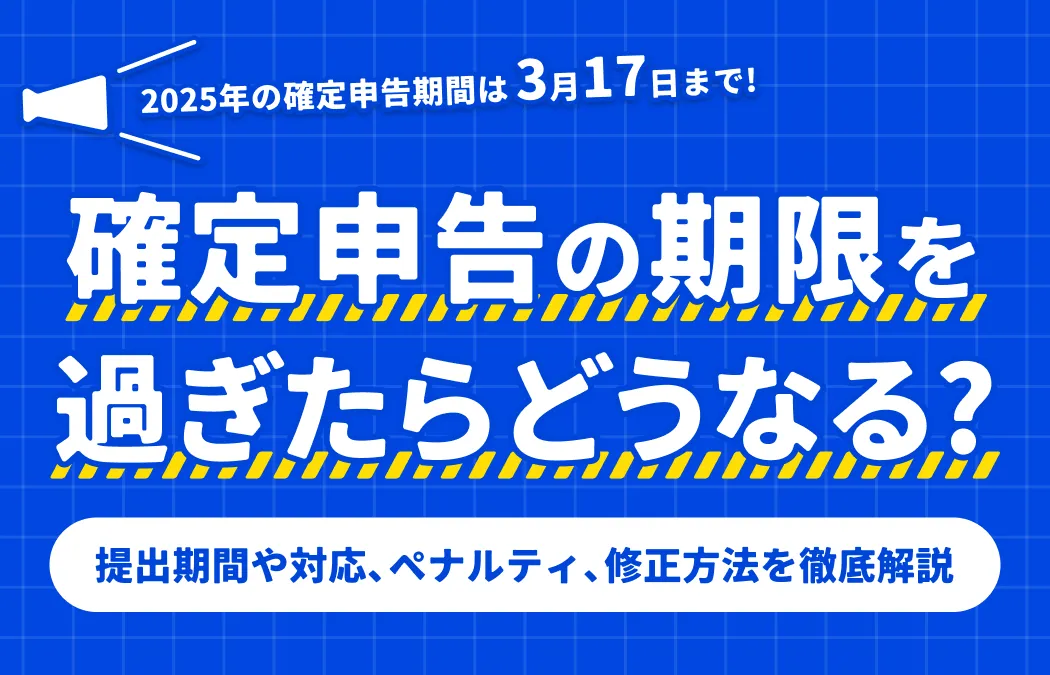
青色申告に必要な書類一覧
- 確定申告書
・申告書 第一表(提出用)
・申告書 第二表(提出用) - 青色申告決算書
・損益計算書
・損益計算書の内訳(1)
・損益計算書の内訳(2)
・貸借対照表 - 支払調書
※源泉徴収されている場合
※支払元が多い→所得の内訳書も作成 - 所得控除証明書
- そのほか書類
・本人確認書類
・金融機関の口座番号
・所得を証明できる書類
提出書類1:確定申告書
第一表・第二表は全員に必須
確定申告をするすべての人が提出するのが「第一表」と「第二表」です。
第一表では、収入や控除、税額などの全体的な情報をまとめて記入します。一方、第二表は、第一表で書いた金額の内訳を記載する欄です。
基本的には、 まず第二表で各種の明細を入力し、その数値を第一表に転記していくとスムーズ に作成できます。どちらも確定申告の基本書類なので、必ず用意しましょう。
第三表・第四表は特定のケースに該当する人だけが提出
第三表と第四表は、 特定のケースに該当する人だけが提出する追加の申告書 です。
第三表は、不動産や株の売却益など「分離課税の所得」や「山林所得」がある人が使用します。
第四表は、青色申告者が、過去3年以内の赤字と今年の利益を相殺(損益通算)する場合に必要です。
ただし、今年だけの赤字で、他の所得と合算してプラスになる場合は提出不要です。自分の状況に応じて、必要書類を確認しましょう。

提出書類2:青色申告決算書
青色申告決算書は所得の種類によって使い分ける
青色申告決算書には、 一般用、不動産所得用、農業所得用、現金主義用の4種類 があります。
所得の種類によって使う用紙が異なるため、間違えないように注意しましょう。
例えば、不動産賃貸収入がある人は不動産所得用、農業をしている人は農業所得用を使います。
兼業で複数の所得がある場合は、それぞれ該当する用紙を提出する必要があります。
青色申告決算書は全4ページで構成されている
青色申告決算書は合計4ページで構成されています。
1ページ目は損益計算書、2・3ページ目は損益計算書の内訳、4ページ目は貸借対照表 です。
これらは年間の収入や経費、資産の状況をまとめる書類で、青色申告で正しく申告するために重要な書類です。
全体の構成をまず理解してから記入を始めるとスムーズに進められます。
1ページ目:損益計算書
1ページ目は損益計算書と呼ばれ、 1年間の売上や経費、利益などの収支の流れをまとめるページ です。
収入から必要経費を引いて所得金額を計算し、その結果が確定申告の基礎となります。青色申告特別控除の金額も1ページ目で計算します。
2ページ目:損益計算書の内訳(1)
2ページ目では、 損益計算書に記載する売上や仕入、給料、地代家賃、減価償却費などの詳細な内訳を記入 します。
帳簿をもとにして、項目ごとに具体的な数字を記載していくため、日々の記帳が重要です。
正確な内訳を書くことで、1ページ目の損益計算書が正しく作成されます。
3ページ目:損益計算書の内訳(2)
3ページ目も2ページ目と同様に内訳を書くページで、 税理士報酬や弁護士費用、特殊事情など特別な支出の内訳を記入 します。
また、売上の変動が大きい場合は、その理由を「特殊事情」の欄に記載し、税務署への説明とします。こうした詳細が、申告内容の正当性を補強します。
4ページ目:貸借対照表
4ページ目は貸借対照表といい、 期首と期末の資産や負債の状況を記録するページ です。
預貯金や借入金、備品や売掛金など、事業の財産の状態を示します。
青色申告特別控除を受ける人は必須の書類で、財産の増減が一目で分かるため、申告内容の信頼性向上につながります。
青色申告決算書は2・3ページ目から書く
青色申告決算書はページ順に作成すると手間が増えてしまうため、2・3ページ目の内訳ページから記入を始めるのがおすすめです。
2・3ページ目で正確な数字を書いた後、1ページ目の損益計算書に転記 してまとめます。
最後に4ページ目の貸借対照表を作成すると、書類全体がスムーズに仕上がります。
提出書類3:支払調書
源泉徴収されている場合は支払調書を提出
支払調書は、報酬からあらかじめ税金(源泉徴収税)が差し引かれていることを証明する大切な書類です。
フリーランスや個人事業主は、支払調書を確定申告書に添付して税務署に提出します。
支払調書は、 報酬を支払った会社が1月末までに税務署に提出し、通常2月ごろに本人にも届きます 。
もし支払調書が届かない場合は、支払元に確認し、それでももらえなければ入金額を収入として申告してください。
支払元が多い場合は「所得の内訳書」も作成
もし支払元が複数あるときは、「所得の内訳書」という書類を作る必要があります。
所得の内訳書は 各支払元ごとの支払い金額や源泉徴収税額をまとめたもの で、税務署が正しく税金を管理するために使われます。
国税庁のホームページから用紙をダウンロードできますが、Excelで作ると管理しやすく便利です。
支払先が少ない場合は、内訳書は不要で、確定申告書の指定欄に記入すれば問題ありません。
提出書類4:所得控除証明書
所得控除一覧・添付書類
| 所得控除名 | 控除額の目安 | 添付書類例 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額により48万円~0円 | 特になし |
| 雑損控除 | 損失額から一定割合を差し引いた金額 | 災害被害の証明書 領収書など |
| 医療費控除 | 支払った医療費-10万円または 総所得金額の5%のいずれか多い方 |
医療費控除の明細書 医療費通知、領収書 |
| 社会保険料控除 | 支払った社会保険料の全額 | 保険料の控除証明書 |
| 小規模企業 共済等掛金控除 |
支払った掛金の全額 | 掛金証明書 |
| 生命保険料控除 | 支払った生命保険料などのうち一定額(上限合計12万円) | 生命保険料控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 支払った地震保険料の全額 (上限5万円) |
地震保険料控除証明書 |
| 寄付金控除 | 寄付金額-2,000円 (上限は総所得の40%相当) |
寄付金の受領証明書 認定証など |
| 障害者控除 | 27万円(特別障害者は40万円、 同居特別障害者は75万円) |
障害者手帳などの証明書 |
| ひとり親控除 | 35万円(該当しない寡婦は27万円) | なし |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 障害者手帳などの証明書 |
| 配偶者控除 | 13~48万円(本人の所得制限あり) | なし |
| 配偶者特別控除 | 所得に応じて変動(上限38万円程度) | なし |
| 扶養控除 | 38万円(扶養親族1人あたり) | なし |
所得控除1:医療費が一定額を超えた
1年間に支払った 医療費が「10万円」または「所得の5%」を超える場合、上限200万円まで医療費控除 を受けられます。
通院の交通費や市販薬の購入費も対象になりますが、美容目的の施術や予防を目的とした支出は対象外です。
また、保険金などで補てんされた金額は差し引く必要があります。
添付書類
- 医療費控除の明細書
- ※領収書は提出不要だが5年間保管
所得控除2:セルフメディケーション税制を使った
市販薬のうち 「特定一般用医薬品等」の購入額が年間1万2,000円を超えると、最大8万8,000円まで控除 されます。
健康診断やがん検診など、一定の健康取り組みを受けていることが条件です。
対象となる薬品には「★」マークがついていることが多く、レシートで確認できます。
ただし、医療費控除と併用できないため、どちらかを選ぶ必要があります。
添付書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 健康取組を証明する記載(明細書内)
- ※レシート・領収書は提出不要だが5年間保管
所得控除3:国民健康保険や年金を支払った
国民健康保険や年金などの 「社会保険料」を支払った場合、その全額を「社会保険料控除」として所得から差し引けます 。
過去の未納分や翌年分をまとめて払った場合でも、実際に支払った年に控除されます。
ただし、公的年金から自動的に差し引かれる介護保険料などは、申告者自身が支払ったわけではないため対象外です。
添付書類
- 国民年金保険料控除証明書(ハガキ形式)
- 支払証明書(民間の国保組合など)
所得控除4:天災や盗難で家財に被害を受けた
地震や台風などの 自然災害、火災、盗難によって家財に被害を受けた場合、「雑損控除」を受けられる 可能性があります。
損害の大きさや補償の有無に応じて、一定額が所得から差し引かれます。
災害時の支出が大きかった方は、損害金額を明記した書類や被害状況の写真などを準備しましょう。
控除額の計算方法
次のいずれか大きい金額が控除対象となります:
- 差引損失額 − 総所得金額 × 10%
- 災害関連のやむを得ない支出 − 5万円
※差引損失額 = 1.損害金額 + 2.やむを得ない支出 − 3.補てんされる金額
- 損害金額:損害を受けた資産の時価(壊れた時点の価値)
- やむを得ない支出:建物の撤去費用や、盗難被害の修復費など
- 補てんされる金額:保険金や損害賠償などで受け取った金額
添付書類
- 雑損控除に関する明細書
- 損害の発生を証明する資料(罹災証明書、被害届、写真など)
- 保険金の支払い通知書など(補填額を確認するため)
所得控除5:国からの認定された団体へ寄付した
特定のNPO法人や公益社団法人など、国が認めた団体に寄付をした場合、「寄付金控除」を受けられます。
支払った寄付金のうち2,000円を超える部分が控除の対象となり、最大で総所得の40%までが控除可能 です。
寄付先が控除対象団体であることを確認し、必ず領収書を受け取りましょう。
添付書類
- 寄付金の領収書(団体名・日付・金額記載)
- 認定NPO法人などであることが明記された書類(または領収書内の記載)
所得控除6:ふるさと納税をした
ふるさと納税を利用して自治体に寄付をした人は、確定申告を行うことで「寄付金控除」を受けられます。
ふるさと納税は名前に「納税」とついていますが、実際には自治体への「寄付」と同じ扱いです。
2,000円以上の寄付をすると、所得税や住民税が軽くなる税制上の優遇措置を受けられます 。
ただし、寄付した全額が控除されるわけではなく、控除の対象となる寄付金には「総所得金額の40%」という上限があります。
寄付金控除の計算式
- (寄附金額 - 2,000円)× 所得税率 × 1.021(復興特別所得税を含む)
- 例:事業所得が700万円、所得税率33%の人が10万円を寄附した場合
- (10万円 − 2,000円)×33%×1.021=約3万3,001円の控除
添付書類
- 寄付金受領証明書(自治体から送付)
- 寄付先や金額がわかる一覧表(複数ある場合)
提出書類5:そのほか書類
本人確認書類
確定申告では、本人確認とマイナンバー確認のために書類が必要です。
マイナンバーカードがあれば一枚で問題ありません が、ない場合は「番号確認書類」(住民票や通知カードなど)と「身元確認書類」(運転免許証やパスポートなど)を用意します。
通知カードは2020年以降廃止されましたが、内容が住民票と一致すれば使えます。
金融機関の口座番号
所得税の還付を受ける場合は、 振込先の銀行名や支店名、口座番号が分かる通帳やキャッシュカードが必要 です。
また、税金の納付を銀行引き落としにする際も口座情報が求められます。
口座情報は正確に記入し、還付や納付がスムーズに行われるよう準備しましょう。
所得を証明できる書類
確定申告には、事業所得のほか給与や配当、年金などさまざまな所得を記載するため、所得を証明する書類を揃える必要があります。
例えば、給与なら源泉徴収票、株の配当なら配当通知書、土地売買なら契約書など です。
所得を証明する書類は税務署の確認に備えて、申告後も5年間保存します。
| 所得の種類 | 証明できる書類の例 |
|---|---|
| 給与、報酬、賃金、年金 | 源泉徴収票の原本、支払調書の原本 |
| 配当所得、一時所得、雑所得 | 一時所得の場合: 生命保険の解約返戻金の通知書など |
| 特定口座での株式取引 | 年間取引報告書(源泉徴収なしの場合) |
| 土地、建物の譲渡 | 譲渡時の売買契約書、購入時の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書など |
青色申告に必要な帳簿・書類の保管期間
帳簿・書類は原則として7年間保管が必要
青色申告を行うには、 帳簿や領収書などの書類を原則として7年間保管 する必要があります。
保管方法は「紙に印刷して保存する」か「電子データとして保存する」かの2通りです。
特に、青色申告特別控除(65万円)を受けたい場合は、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が条件になります。
| 保存が必要な帳簿・書類 | 保存期間 | |
|---|---|---|
| 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 |
| その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
電子帳簿保存制度とは?ルールに則った保存を
電子帳簿保存制度は、会計ソフトなどで作成した帳簿や、電子取引でやり取りした書類を電子データのまま保存する制度です。
この制度を活用するメリットには、紙の保管スペースが不要になる点や、青色申告特別控除(65万円)の要件を満たせる点が挙げられます。
ただし、電子保存には「タイムスタンプの付与」や「検索機能の確保」など、国税庁が定める要件を満たす必要があるため、事前の準備が重要です。

記帳代行サービス「KANBEI」で経理の負担を大幅軽減

複雑な電子帳簿保存の要件や、日々の記帳作業は大きな負担になりがちです。
「KANBEI」なら、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応。 領収書のスキャンから会計ソフトへの登録まで、すべてお任せいただけます 。
月額1,100円〜と業界最安値級の価格で、面倒な記帳業務を徹底サポートします。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
導入実績1200社以上!
【無料】お問い合わせはこちらまるっと理解!基本情報ガイド
【無料】資料ダウンロード青色申告に必要な書類の提出方法
税務署の窓口に直接提出
確定申告書類は、最寄りの税務署の窓口に直接持って行って提出できます。
初めての申告で不安な方や、書類の内容を確認してもらいたい場合におすすめ です。
申告期間中は税務署に相談コーナーも設置されており、職員や税理士に質問しながら申告書を作成できます。
税務署または業務センターに郵送
忙しくて税務署に行けない場合は、申告書類を郵送で提出することも可能です。
提出期限の3月15日までの消印が有効なので、余裕をもって送りましょう。
郵送時はトラブル防止のため、記録が残る特定記録郵便や簡易書留を利用すると安心 です。
また、宅配便でも提出可能ですが、期限内に税務署に届くよう早めに発送してください。
e-Taxで提出(おすすめ)
インターネットを使った「e-Tax」は、パソコンやスマホから簡単に申告書を提出できる便利な方法です。
青色申告を選んでいる人は、 e-Taxで提出すると特別控除が65万円に増え、節税効果が高まります 。
マイナンバーカードや事前準備が必要ですが、一度使い方を覚えれば、翌年以降の申告もスムーズに行えます。
会計ソフトが青色申告を劇的に楽にする!
青色申告に会計ソフトを使うメリット
青色申告を手書きやExcelで行うのは手間がかかり、ミスもしやすいものです。
会計ソフトを使えば、 日々の収支を入力するだけで自動で帳簿が作成され、確定申告書類の作成もスムーズに なります。
複式簿記も簡単に対応でき、65万円の控除を受ける条件もクリアしやすくなります。
初心者でも迷わず使える設計なので、「面倒そう…」と感じている人にこそおすすめです。
青色申告におすすめの会計ソフト3選
青色申告におすすめの会計ソフトは次の3つです。- freee(フリー):スマホ対応が充実しており、操作がとても直感的
- マネーフォワード クラウド:連携機能が豊富で、銀行口座やクレカ情報も自動で取り込める
- やよいの青色申告オンライン:実績豊富でサポート体制も手厚く、初めてでも安心して使える
それぞれ無料体験版もあるので、使いやすさを比較して選ぶのがポイントです。
会計ソフト導入後の“残高ズレ”に注意
会計ソフトは便利ですが、初心者がつまずくポイントも多いです。特に「支出と残高が合わない」と感じるケースがよくあります。
原因は、手入力と自動連携の重複や、現金取引の記録漏れ、初期残高の設定ミスなど です。
こうしたズレは、こまめな残高チェックや入力ルールの統一で防げます。わからない時は、ソフトのサポートや税理士に相談するのも大切です。
会計ソフトの実際の活用事例(freee)
- IT業界で20年経験後、閉塞感から独立を決意
- 50歳手前で「自分の責任で自由に働きたい」と起業
freee開業の導入理由と感想
- ネットで開業情報を調べ、freee開業を発見
- 無料&ステップ形式で使いやすく、予想以上に簡単だった
- 開業届と青色申告承認申請書をスムーズに作成・提出
- 事業用口座も案内に従いスムーズに開設
freee会計の導入と活用
- 開業後1か月以内にfreee会計を導入し環境を整備
- 請求書・見積書作成をfreeeで効率化(作成が10分に短縮)
- 経費精算を後回しにして苦労し、以後「すぐ処理」を習慣化
- レシートはスマホから入力、紙領収書は週ごとにCSVで一括登録
効率化・アウトソーシングの考え方
- 経理は「本業ではない」ためソフトや外注で効率化すべき
- Excelでの管理は時間の無駄、本業に集中する方が価値が高い
- freee会計でスキマ時間に処理、確定申告も簡単に
- 今後もfreeeを使って業務効率化と事業成長を目指す
参考:フリーランスが開業準備・確定申告をスムーズに行うコツとは│freee公式サイト
まとめ:青色申告は会計ソフトで簡単&お得!
青色申告は複雑なイメージがありますが、会計ソフトを使えば簡単に申告書の作成が可能です。
自動仕訳や帳簿管理の機能でミスを減らせるうえ、最大65万円の控除など節税効果も大きいのが魅力。
初めての方でも使いやすい操作画面が多く、効率的に経理ができるため、確定申告の負担を大幅に軽減できます。
青色申告のメリットを活かすなら、まずは会計ソフトの導入がおすすめです。
freee会計
【無料】お問い合わせはこちらマネーフォワード クラウド会計
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!