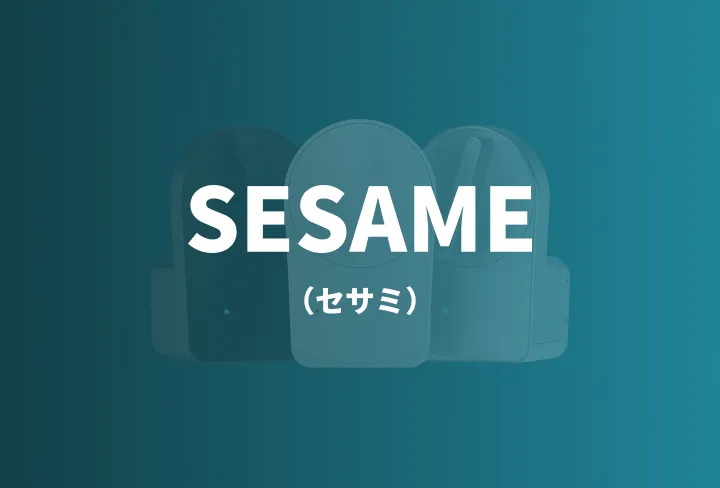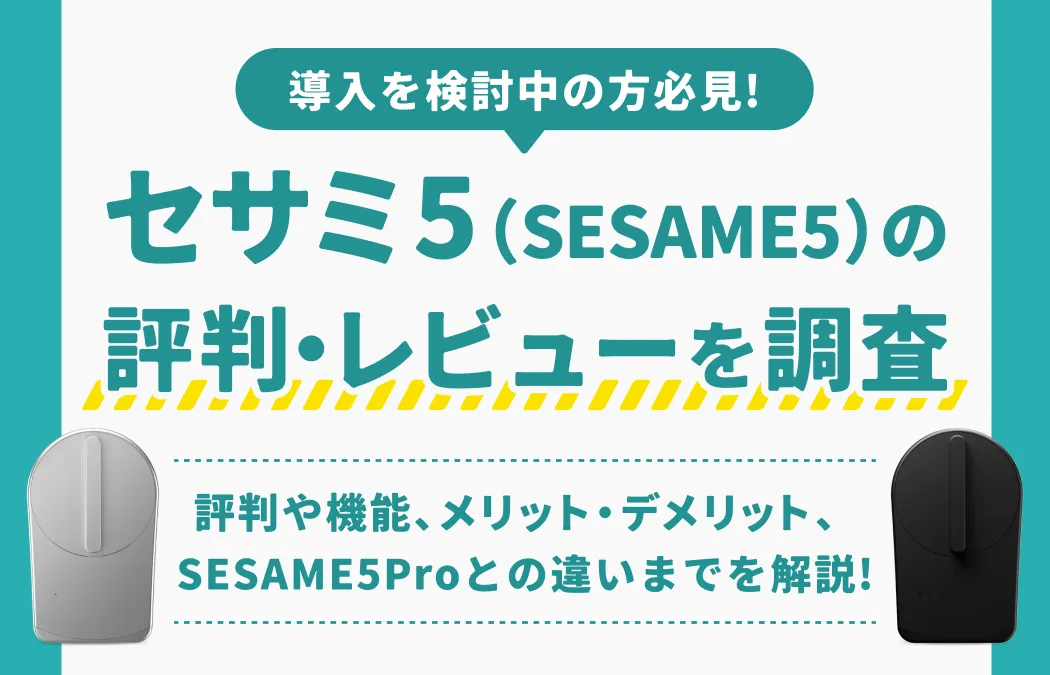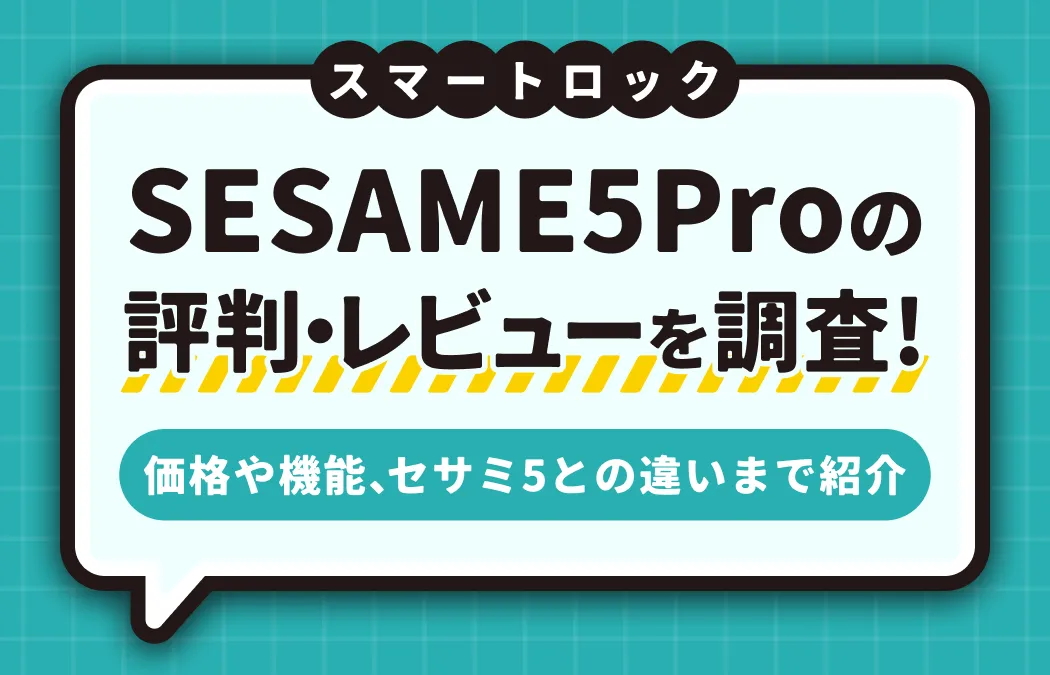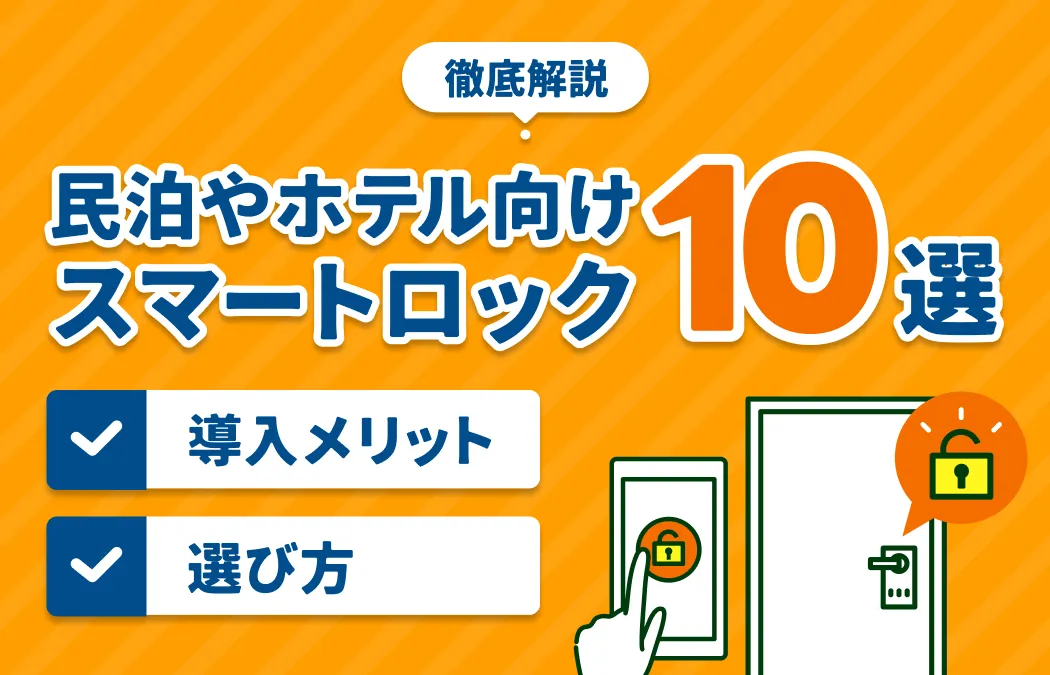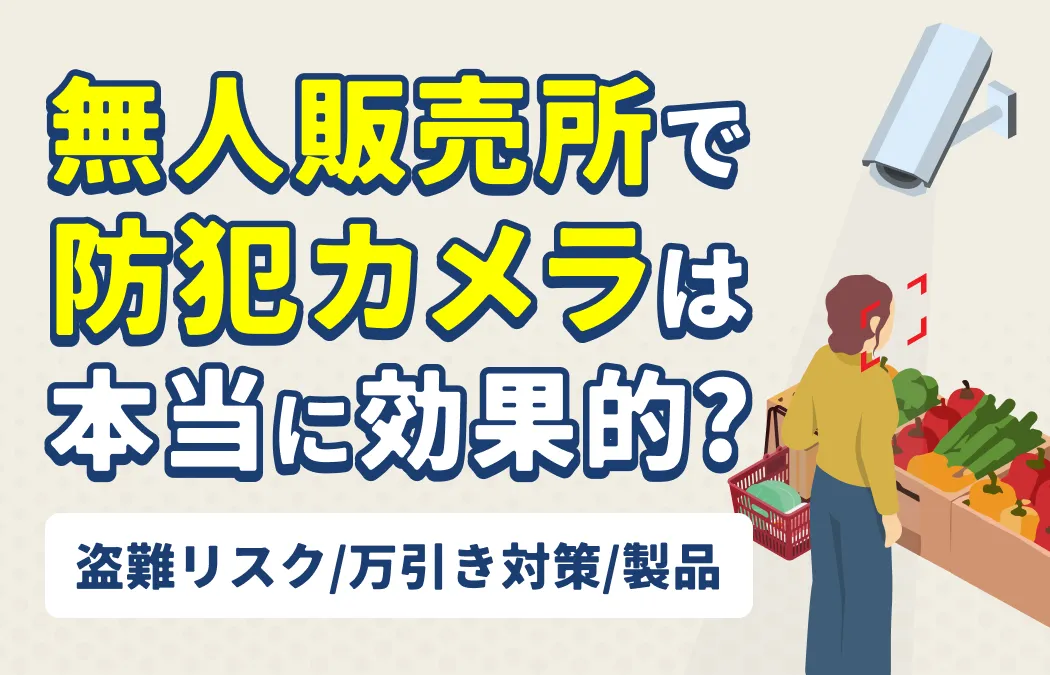「スマートロックは後付けできる?」
スマートロックを導入することで、オフィスのドアをセキュリティ強化できます。
しかし、「工事不要で設置できる?」「デメリットはある?」といった疑問も多くみられます。
今回は、オフィス向けスマートロックの種類やおすすめ製品を紹介します。
選定ポイントや導入手順も解説しているため、スマートロックを検討中の企業に役立つ記事です。
目次
▼この記事で紹介している商品
オフィス向けスマートロックとは

スマートロックとは、既設の鍵に電気通信機器を取り付けることで、 スマートフォンやICカード、暗証番号などを使った施錠・解錠を実現できるシステム です。
工事不要で簡単に設置できるものが多く、セキュリティ強化を目的としてオフィスに導入する企業も増えています。
中でもオフィス向けの製品は、家庭向けよりもセキュリティ性が高い、耐用年数が長い、登録できる合鍵の数が多い、といった特徴があります。
また近年は、オフィスだけでなくシェアオフィスやコワーキングスペースでも導入が進んでいます。
スマートロックのタイプ
- 後付け(貼り付け)タイプ
- シリンダー交換タイプ
- 穴あけ工事タイプ
スマートロックは、両面テープで簡単に後付けできるものから、ネジを使って固定するタイプまで様々です。
特に、工事が不要な 「後付け(貼り付け)タイプ」 は、賃貸オフィスにも取り付けられる点がメリットです。
一方、耐久性を重視する場合は 「シリンダー交換タイプ」 や 「穴あけ工事タイプ」 が適しています。用途に合わせて最適なものを選びましょう。
家庭向けとオフィス向けスマートロックの違い
オフィス向けスマートロックは、 家庭用と比べてセキュリティ性や機能性が充実 しています。
例えば、部屋ごとに入退室の権限を使い分けることで、特定の部屋に入室できる従業員を制限できます。
また、ICカードで出退勤情報を記録できる「勤怠管理機能」や、入退室の履歴を記録する「入退室管理機能」なども、オフィス向け製品ならではの機能です。
入退室管理システムとオフィス向けスマートロックの違い
スマートロックがドアの開閉をデジタル化するシステムなのに対し、 入退室管理システムは「誰が・いつ部屋に入ったか」という入退出情報を記録するシステムです。
入退室管理システムは 、入退室の管理を目的としたシステムなので、スマートロックと比べてセキュリティ性に優れています。
そのため、不特定多数が出入りする大規模オフィスなどセキュリティを重視する場合は、スマートロックと入退室管理システムを併用するのがおすすめです。
セキュリティ強化にスマートロックをおすすめする理由
スマートロックは、アクセス履歴の自動記録や、複雑なパスワードや顔認証など、従来の鍵では難しい高度な認証機能が搭載されています。
さらに、鍵の紛失や複製リスクを減らし、履歴機能により誰がどのタイミングで出入りしたかも追跡できます。
これにより、 部外者の立ち入りを防ぎ、セキュリティを大幅に強化できる ため、セキュリティ対策が必須なオフィスに最適と言えます。
【比較表】オフィス向けスマートロックの主な機能
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 解錠・施錠 | スマホやICカードなどを使って鍵を施解錠できる機能。 |
| 入退室管理 | 「誰が・いつ・どこに」入退室したか管理できる機能。 |
| 入退室権限の設定 | クラウド上で鍵の発行や無効化ができる機能。 来客時に一時的に使える鍵を発行したり、退職者の鍵を無効化したりと、鍵の受け渡しを効率化できる。 |
| 複数拠点の一括管理 | 複数拠点に設置したスマートロックを一括で管理できる機能。 遠隔操作で施解錠できる製品もある。 |
| セキュリティ対策 | 社員ごと、時間帯・曜日ごとに入退室エリアを制限できる機能。 |
| 外部システムとの連携 | 入退室ログを勤怠システムなどの外部システムと連携させる機能。 |
導入費用最安値!SESAMEでお得にセキュリティ強化
【無料】お問い合わせはこちら企業(会社)がスマートロックを導入するメリット
- 入退室の管理によってセキュリティを強化できる
- 物理鍵が不要で管理工数削減につながる
- 鍵を共有できる
- 遠隔での操作も可能
- 施解錠可能な社員やエリアを制限できる
- アクセス履歴を追跡できる
- 空室把握や勤怠管理にも活用できる
- オフィスのドアに工事不要で後付けできる
入退室の管理によってセキュリティを強化できる
企業がスマートロックを導入することで入退室管理が容易となり、オフィスのセキュリティを強化できます。
また、権限設定により「誰がどのエリアに入れるか」を制御し、曜日や時間帯による制限も可能 です。これにより、機密情報を保管している部屋へ立ち入れる社員を1部に限定できます。
さらに、パソコンやスマホで解錠状況や履歴を確認できるため、鍵のかけ忘れも防げます。オートロック機能搭載モデルであれば、施錠忘れそのものをなくしことも可能です。
加えて、異常時の通知や警備連動にも対応し、安心・安全なオフィス環境を実現します。
物理鍵が不要で管理工数削減につながる
従来の金属鍵は、社員数や扉の数に応じて鍵を複製したり、共有鍵の管理用金庫などを用意する必要がありました。
その点、スマートロックは手持ちのスマホや社員証を鍵代わりに使用できるため、 鍵を作成するコストや、鍵の保有・保管状況を管理する手間をなくせます 。
また、金属鍵を量産せずに済むため、盗難・紛失のリスクを低減できるというセキュリティ面のメリットもあります。
鍵を共有できる
企業がスマートロックを導入することで、管理画面から一時的な解錠アクセス権限を与えられるため、鍵の共有がスムーズになります。
社員それぞれに対し、必要な時だけ入出を許可するという運用ができるため、 鍵の持ち出し状況を記録したり、きちんと返却されているか確認したりする手間が不要 です。
遠隔での操作も可能
企業がスマートロックを導入することで、遠隔操作での施解錠が可能になり、外出先でも施錠状況を確認できます。
万が一鍵のかけ忘れがあっても、スマホで遠隔操作して閉められるため、緊急時や不在時でも柔軟に対応でき、セキュリティ強化に役立ちます。
施解錠可能な社員やエリアを制限できる
企業がスマートロックを導入することで、施解錠できる社員やエリアを制限できます。
機密情報の保管場所や重要な会議室など、 立ち入りを制御できるためセキュリティが向上します 。
また、有効期限付きの鍵も発行可能で、来客やパートスタッフの一時的な利用にも対応できます。
アクセス履歴を追跡できる
企業がスマートロックを導入することで、アクセス履歴を追跡できます。
誰がいつドアを開けたかを記録し、アプリやウェブポータルで確認可能なため、 セキュリティ上の問題発生時や特定のアクセス状況を把握したい場合に役立ちます 。
空室把握や勤怠管理にも活用できる
企業がスマートロックを導入することで、空室把握や勤怠管理にも活用できます。
会議室やフロアの空き状況を可視化でき、時間やスペースの有効活用にもつながります。
また、入退室データと勤怠管理システムを連動できるスマートロックの場合、 オフィスへの入退室記録を打刻に反映することも可能 です。
タイムカード等を使用せずとも、社員が入退室するだけで正確に勤怠状況を記録できるため、打刻漏れや不正打刻の防止につながるでしょう。
オフィスのドアに工事不要で後付けできる
貼り付けタイプのスマートロックは、工事不要で設置できる点もメリットです。
工事の手間やコストがかからないほか、 賃貸物件であっても設備を傷つけることなく手軽に設置できます 。
企業(会社)がスマートロックを導入するデメリット
- コストがかかる
- 製品によりセキュリティレベルが異なる
- 設置可能な玄関錠(サムターン形状)に制限がある
- 締め出しなどのトラブルに備えて対処が必要
- 錠や施錠ツールの電池量に注意
コストがかかる
スマートロックを設置・運用する場合、 初期費用や月額費用が発生 します。
特に、サブスクリプション型やシステム利用型の場合は、月々数千円程度の費用を払い続ける必要があるため、長期的な視点で見るとコストが膨らむ点に注意が必要です。
あらかじめ、「予算に見合う料金か」「費用対効果は得られるか」などを考慮したうえで導入を判断しましょう。
製品によりセキュリティレベルが異なる
スマートロックは、製品ごとにセキュリティレベルが異なります。
適切な製品を選ばないと、十分な安全性が確保できない場合がある ため、資料や問い合わせでセキュリティ機能を確認しましょう。
また、セキュリティパッチやアップデートが頻繁に行われているかを確認し、最新の機能を維持することも大切です。
設置可能な玄関錠(サムターン形状)に制限がある
スマートロックは、 取り付ける扉や鍵の形によって設置できる製品が異なり 、業者による工事が必要な場合もあります。
スムーズに導入するためにも、事前に取り付け可能な扉かどうかを調べることが大切です。
締め出しなどのトラブルに備えて対処が必要
スマートロックは、ハッキングや動作不良、ネットワークトラブル、システムの不具合などが起こるリスクもあります。
上記のような場合、締め出しに合うリスクもあるため、注意が必要です。
スマートロックを選ぶ際はサポート体制を重視するほか、 もしもの時に手動で解錠できる物理鍵を用意する など、緊急時に備えておきましょう。
錠や施錠ツールの電池量に注意
スマートロックは、本体や解錠に使うスマホの電源が切れてしまった場合、締め出されてしまうリスクもあります。
スマートフォンなどの充電はもちろん、錠の電池も定期的にチェックすることが重要 です。
中には、電池が少なくなると通知するサービスがあるため、事前に設定しておくことで、電池切れによるトラブルを防止できます。
コスパ重視ならSESAME 5 Pro
【無料】お問い合わせはこちらオフィス向けスマートロックの選び方・比較ポイント
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 利用人数・会社規模 | オフィスの規模や形態によって機能を選ぶ |
| ドアの形状 | 玄関錠のサムターンに対応しているか |
| セキュリティレベル | セキュリティ水準が十分か確認 |
| 工事の有無 | 取り付けの難易度や工事の要不要を確認 |
| 費用 | 「コストに見合う導入効果が得られるか」考慮しながら製品を検討 |
| 解錠方法 | ハンズフリー、スマホ、マルチデバイス、指紋認証、暗証番号など、複数の解錠方法を搭載しているか |
| 取り付け方法 | 取り付けは簡単か |
| オートロック形式 | オートロック形式の種類を確認 |
| スムーズに施解錠できるか | 反応速度や正確性、動作音の静音性をチェック |
| 施解錠の履歴・ログを 確認できるか |
アクセス履歴機能が充実したサービスを選ぶ |
| データ登録の容易性 | 人事情報システムと連携できるサービスが便利 |
| シェア機能・遠隔操作 機能の使いやすさ |
合鍵の作成と共有を管理画面上で完結できる |
| 勤怠管理への 活用のしやすさ |
社員の入退室ログを自社の勤怠管理システムとAPIで連携できる製品がおすすめ |
| 電池の持ち | 一般的には半年から1年程度 |
| サポート体制 | カスタマーサポートの対応時間の長さ、問い合わせ手段(電話、メール、チャット)の豊富さ、保証期間の長さなどがポイント |
| 耐用年数 | 一般的に7年 |
利用人数・会社規模
オフィスの規模や形態によって、最適なスマートロックは異なります。
小規模オフィスや倉庫であれば簡易的なスマートロックでも十分ですが、 不特定多数が出入りするオフィスではより高度なセキュリティ性 が求められます。
特に、社員数の多い企業の場合は、ICカードと人事情報の連携に手間がかかるため、人事労務システムと連携できる製品がおすすめです。
ドアの形状
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、玄関錠のサムターンに対応しているかどうかも確認しましょう。
サムターンとは、ドアの内側についている鍵のつまみのことです。
スマートロックが玄関錠のサムターンに対応していなければ、本体が上手くはまらず使用できません。
特に、 サムターンの形状が特殊な場合や、サムターン周辺のスペースが狭い場合は対応できない可能性が高い ので、購入前に必ず確認が必要です。
- 四角形・丸型・しずく型
- ドアノブに鍵がついている
- つまみの回転角度が大きい
- スマートロックを設置する十分なスペースがない/玄関錠とドア枠が近い
セキュリティレベル
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、暗号化技術の強度 、 多要素認証の有無 、 ファームウェア更新の頻度 などのセキュリティ水準が十分か確認しましょう。
信頼性の高いメーカーの製品を選ぶことで、不正アクセスやハッキングのリスクを低減し、より高い安全性を確保できます。
工事の有無
オフィス向けのスマートロック選びで、工事の有無は重要な比較ポイントです。多くのスマートロックは既存のドアに簡単に取り付けられ、工事不要なモデルも豊富です。
とはいえ、スマートロックの製品やドアの形状によっては工事が必須になる場合もあるため、注意しましょう。
特に賃貸のオフィス物件では、取り外し可能で原状回復が容易なタイプが適しています。
取り付けの難易度や工事の要不要を確認 し、工事スキルと物件の条件に合った製品を選ぶことが重要です。
費用
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は「コストに見合う導入効果が得られるか」考慮しながら製品を検討しましょう。
特に、入退室管理や勤怠管理など、システム利用を伴う場合は月額費用が発生するため、注意が必要です。
サービスによっても費用は異なるため、 数社で見積もりを取ってから判断することをおすすめ します。
- 本体価格
- 取付工事費
- サポート費用
- 月額料金(サブスクリプション型・システム利用料型の場合)
解錠方法
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、どんな手段で施錠や解錠を行えるのかもチェックポイントです。
製品によっては、 複数の解錠方法を搭載しているものもあるため、社内でどんな解錠手段が必要か優先順位をつけましょう。
ハンズフリータイプ:ドアに近づいて解錠できる
スマートロックの中でも、最も人気なのがハンズフリータイプです。
スマートロックとスマホの距離が一定になると、自動的に鍵を開け閉めしてくれます。
バックやポケットからスマホを取り出す必要がないため、書類の持ち運びで両手が塞がっているときに鍵を取り出す手間をなくせます。
- 手ぶら解錠の反応精度には違いがあるため、ドアにたどり着く前に開錠するものを選ぼう!
- 誤作動を防ぐため、オートロックは防犯性の高い開閉センサー式がおすすめ
スマホタイプ:タッチ解錠ができる
スマートロックのほとんどに搭載されているのが、スマホ操作タイプです。
スマートロックがついたドアの前で、スマホアプリを操作することで解錠できます。
鍵の開閉のためにスマホを取り出す必要はありますが、鍵穴に鍵を挿すという手間がなくなるので、物理鍵よりも利便性がアップします。
- スマホアプリを操作して解錠したい人は、アプリを探す手間を省くため、ウィジェット対応のものを選ぼう!
マルチデバイスタイプ:スマホが必要ない
スマートウォッチや専用のリモコンキー、ICカードなど、スマホ以外のデバイスで鍵の開け閉めができるのが、マルチデバイスタイプです。
特にICカードタイプは、普段利用している交通系ICカードを鍵代わりにできるタイプもあるため利便性が高く、スマホの電池切れなどで締め出された場合の代替策としても有効です。
指紋認証:指先だけで解錠できる
スマートロックのセンサーに指先で触れるだけで解錠できるのが指紋認証タイプです。
解錠のためにスマホやICカードなどを取り出す必要がないため、手がふさがっている状況でも簡単に解錠できて利便性が上がります。
また、解錠に使う物理デバイスの紛失リスクや複製リスクがないため、セキュリティレベルが最も高いといえます。
暗証番号タイプ:大人数が行き来する場所に最適
暗証番号タイプは、スマホやICカードといった物理的デバイスを使用せず、事前に設定した 暗証番号の入力で解錠できるタイプ です。
指紋認証と同じく、解錠に使うデバイスの紛失リスクや複製リスクがないため、セキュリティレベルが非常に高いと言えます。
また、「スマホやICカードなどの解錠デバイス持ち出し忘れて閉め出される」というトラブルも防止できます。
取り付け方法
後付け(貼り付け)タイプ
後付け(貼り付け)タイプのスマートロックは、 工事不要で手軽に取り付け・取り外しできる ため、賃貸のオフィスでも安心して利用可能です。
両面テープで貼り付けるだけで設置できるので、シール跡や塗装剥がれなどに注意すれば簡単に原状回復できます。
-
▶後付け(貼り付け)タイプの注意点
-
>貼り付けタイプは、両面テープの粘着力のみでスマートロックを支える形となるため、本体が重いモデルだと徐々に外れやすくなってきます。
また、スマートロックの装着位置を間違えて何度も付け直しすると粘着力が一気に落ちるため、両面テープを用意しておくのがおすすめです。
シリンダー交換タイプ
シリンダー交換タイプのスマートロックは、 既存のシリンダーを取り外してスマートロックに付け替えるタイ プです。
スマートロック本体をねじ止めする構造なので、落下の心配が少なく、長期間安心して利用できます。
ただし、シリンダーの交換時にドアを傷つけてしまうと原状回復が難しくなるため、賃貸のオフィスの場合は注意が必要です。
穴あけ工事タイプ
穴あけ工事タイプのスマートロックは、 ドアやシリンダーに直接加工を施して本体を固定 します。
落下の心配が少なく、搭載機能も充実しているため、暗証番号入力やICカードなど複数の解錠方法を取り入れたい場合におすすめです。
ただし、穴あけ工事タイプを設置したドアは原状回復ができないため、基本的に賃貸のオフィスでは利用できないと考えましょう。
オートロック形式
スマートロックを選ぶ際は、オートロック形式の種類に注目しましょう。
オートロックには複数の形式があり 、それぞれにメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 開閉センサー式 |
|
|
| ジャイロセンサー式 |
|
|
| タイマー式 |
|
|
スムーズに施解錠できるか
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際、スムーズな施解錠性能は重要な比較ポイントです。
反応速度や 正確性、 動作音の静音性をチェックし、スムーズな施解錠が可能か確認しましょう。
BluetoothやWi-Fi接続の安定性も影響するため、通信範囲や信号強度も確認することが大切です。
-
▶スマートロックの利便性を上げるならハブ付きモデルを選ぼう
-
スマートロック本体とスマホをBluetooth接続する際、Bluetoothの接続範囲内(約10m)でしかスマートロックを動かすことができません。
そのため、スマートロックの利便性を上げるなら、ハブ付きモデルを選ぶのがおすすめです。
ハブはWi-Fiとスマートロックを連携できるツールで、 ハブ付きのスマートロックを選ぶことで、BluetoothだけでなくWi-Fiも活用できます。
外出先でWi-Fiにアクセスすることで、スマートロックの遠隔操作が可能になります。
施解錠の履歴・ログを確認できるか
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、施解錠の履歴やログが確認できるかを確認しましょう。
製品によっては、 誰がどの鍵を施解錠したかの履歴を表示でき、施錠忘れの防止や防犯対策に役立ちます 。
特にオフィスでは個人情報保護や高いセキュリティレベルが求められるため、アクセス履歴機能が充実したサービスを選ぶことをおすすめします。
データ登録の容易性
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、データ登録の容易性を考慮しましょう。
システム上で権限を登録・管理する際、従業員数が多い企業では負担が大きくなります。
特に、 大規模な組織の場合は人事情報システムと連携できるサービスが便利 です。人事マスタから従業員データをインポートできる機能を備えていると、登録や管理の手間を軽減できます。
シェア機能・遠隔操作機能の使いやすさ
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、シェア機能と遠隔操作機能の使いやすさを重視しましょう。
シェア機能を利用すれば、合鍵の作成と共有を管理画面上で完結できるため、直接の鍵の受け渡しが不要になります。
さらに、遠隔操作機能があるスマートロックは、管理部門が現地にいなくても外部から施錠・解錠ができるため、非常時に役立ちます。
勤怠管理への活用のしやすさ
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、勤怠管理への活用のしやすさも考慮しましょう。
スマートロックの中には、 社員の入退室ログを自社の勤怠管理システムとAPIで連携できる製品もあります 。
これにより、タイムカードを廃止し、スマートロックを活用した効率的な勤怠管理が可能になります。
電池の持ち
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際、電池の持ちは重要な比較ポイントです。電池寿命は製品によって異なり、 一般的には半年から1年程度です。
使用する電池の種類(単三、リチウム電池など)や、省エネルギー設計の有無も影響します。電池残量の警告機能や、予備電池の交換の容易さも考慮すべきです。
電池寿命が短いものほど、電池交換を頻繁にする必要があるため、スマートロック購入前に電池がどれくらい持つか確認しましょう。
サポート体制
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際、サポート体制も重要な比較ポイントです。製品の故障や不具合が発生した場合に備え、迅速な対応が求められます。
例えば、 カスタマーサポートの対応時間の長さ、 問い合わせ手段(電話、メール、チャット)の豊富さ、 保証期間の長さなどがポイントです。
また、オンラインのFAQやトラブルシューティングガイドが充実しているかもチェックしましょう。
耐用年数
オフィス向けのスマートロックを選ぶ際は、耐用年数を確認することが重要です。
耐用年数が長い製品を選ぶことで、保守費用やメンテナンスの手間を減らすことができます。
スマートロックの耐用年数は一般的に7年 とされていますが、保証期間やバッテリー寿命は製品によって異なるため、導入前にしっかり確認しましょう。
オフィス向けスマートロックの導入手順・流れ

-
STEP.1
課題、ニーズを把握する
オフィス向きスマートロックを導入する際は、まず課題やニーズを把握することが重要です。
鍵管理の電子化や入退室情報の可視化など、解決したい課題を具体的に洗い出しましょう。自社に最適なスマートロックの選定がスムーズになります。
-
STEP.2
予算を確定する
オフィス向きスマートロックを導入する際は、予算の確定が重要です。
初期費用に加え、サブスクリプション型やレンタル型では月額利用料が発生します。
買い切り型は月額費用がかかりませんが、導入後のメンテナンス費用も考慮し、予算に合ったプランを選びましょう。
-
STEP.3
スマートロック製品を選定する
オフィス向きスマートロックを導入する際は、予算確定後に製品選定を行います。
設置・解錠方法や外部システムとの連携など、自社で使いやすいかを確認しましょう。
また、同規模・同業態での導入実績が多い製品は安心して利用できるため、実績も重要な判断材料です。
-
STEP.4
スマートロックを導入、設置する
スマートロック製品を選定したら、導入・設置を行います。
設置方法は「後付け型」と「交換型」があり、後付け型は自社で設置可能ですが、交換型は業者による工事が必要です。
賃貸オフィスでは、工事前に管理会社や家主の許可を取ることを忘れないようにしましょう。
-
STEP.5
スマートロックの設定、プログラミングを行う
スマートロックの設置後は、入退室の権限付与や外部システムとの連携などの設定を行います。
プログラミングが必要な場合もあるため注意が必要です。
また、使用方法や注意点を従業員に周知しないとトラブルが発生する恐れがあるため、オリエンテーションの実施がおすすめです。
-
STEP.6
スマートロックの運用を開始する
スマートロックの設定や従業員への周知が完了したら、運用を開始します。
運用後も定期的なメンテナンスや稼働状況の改善が必要です。
トラブル時には、サポートサービスを活用すると安心して運用できます。
オフィス向けスマートロックおすすめ7選【比較表】
| SESAME5 PRO | Akerun 入退室管理システム |
bitlock PRO | カギカン | RemoteLOCK | ALLIGATE | PicoA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 初期費用(税込) | 要問い合わせ | 0円 | 0円 | 0円 | 6万6,000円~ + 取付工事費 |
要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 月額費用(税込) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 5,000円~/台 | 4,950円~/台 ※利用者21名以上からは別途110円/名 |
1,650円/台 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
SESAME5 PRO

セサミ5PROは、 スマートウォッチや音声操作にも対応できる、高機能スマートロック です。
オートロック機能や遠隔操作機能など、セキュリティ面が充実しているほか、セキュリティシステムやスマートホームシステムとの統合も容易に行えます。
また、耐久性にも優れており、 1日200回の開け閉めでも10年以上利用できるため、人の出入りが多い大規模オフィスでも不自由なく利用できます。
▶業界最安値級&高性能!SESAME5の導入をプロがサポート
| 料金(税込) | 要問い合わせ |
|---|---|
| 解錠方法 |
|
Akerun入退室管理システム

Akerun入退室管理システムは、スマートロックの機能に加えて、「いつ・誰が・どこに入室したか」という 入退出情報を記録・管理することも可能 です。
曜日や時間帯ごとに鍵の権限をスケジュール指定したり、クラウド上でリアルタイムに鍵発行・剥奪したりできるので、施解錠管理が大幅に効率化されます。
両面テープで手軽に取り付けられ、配線工事も簡易的なもので済むため、賃貸オフィスでも気軽に設置できます。
| 料金(税込) |
|
|---|---|
| 解錠方法 |
|
bitlock PRO

bitlock PROは、 最短1日で導入できるサブスクリプション型のスマートロック です。
99.9%のサムターンタイプの鍵に対応しており、オートロック機能や、アプリを使った操作ログ機能も標準搭載されています。
周辺機器と組み合わせることで、手持ちのスマホやNFCカード、Apple watch、顔認証での解錠・施錠も可能です。
| 料金(税込) |
|
|---|---|
| 解錠方法 |
|
カギカン

カギカンは、遠隔での施解錠や施錠履歴の記録・管理にも対応できるスマートロックです。
日本国内にある約80%以上のドアに対応 しており、簡単にテープで貼り付けできるものから、耐久性に優れた要工事タイプまで、豊富なラインナップが揃っています。
故障時の交換や電池交換、運用サポートがすべて無料で受けられる点も魅力です。
| 料金(税込) |
|
|---|---|
| 解錠方法 |
|
RemoteLOCK

RemoteLOCKは、 アプリ不要のテンキー式スマートロック なので、カードキー等を持ち歩かずに手ぶらで解錠できます。
一つの鍵に複数の暗証番号を割り当てられるので、社員ごとに異なる暗証番号で権限を管理したり、同じ番号で異なる部屋に出入りすることも可能です。
また、予約管理サービスや宿泊管理システム、受付システムなどとAPI連携できるのも強みです。
| 料金(税込) |
|
|---|---|
| 解錠方法 |
|
ALLIGATE(アリゲイト)

ALLIGATEは、スマホアプリやICカードなどを使ってドアの施解錠を管理できるクラウド型入退室管理システムです。
入退室管理の専業メーカーとしての豊富なノウハウを活かし、 開き戸・引き戸・自動ドア・ガラス扉など、様々なタイプのドアに設置できます。
また、専用アプリ「ALLIGATE App」により、スマホひとつで解錠できる利便性に加え、Suicaや社員証を活用した認証にも対応しており、既存の運用資産を活かした導入ができます。
| 料金(税込) |
|
|---|---|
| 解錠方法 |
|
PicoA

PicoAは、 国内最大級のシェアを持つ鍵メーカー・美和ロック株式会社が提供 するスマートロックです。
室内側のカードリーダーにロータリースイッチが内蔵されており、その場で手軽にカードの権限を登録・抹消できます。
また、専用のアプリを使用して、履歴管理やカードデータをPCで一括管理することも可能です。
| 料金(税込) |
|
|---|---|
| 解錠方法 |
|
業界別スマートロックの導入事例

オフィス・事務所
オフィスや事務所でのスマートロック導入は、 セキュリティ強化に最適 です。
IDカードやスマートフォンでのアクセス管理により、入退室履歴を自動記録します。
不正アクセスを防ぎ、権限ごとの入室制限で機密情報も保護します。
レンタルスペース
スマートロックを活用すれば、 レンタルスペースの無人化・省人化が可能 です。
予約完了後に自動発行されるアクセスコードでスムーズな入退室を実現し、スタッフの負担を軽減します。
効率的な運営とセキュリティ強化にもつながります。
フィットネスジム
スマートロックは、 フィットネスジムの省人化・無人化に最適 です。
スマホやICカード、顔認証でロッカーや施設にアクセスでき、手ぶらでの入場が可能になります。
顧客の利便性向上と同時にセキュリティ強化も実現します。
オフィスや店舗の鍵ならSESAME
【無料】お問い合わせはこちらオフィス向けスマートロックの導入費用

オフィス向けスマートロックには、 「買い切り型」と「サブスク型」 があります。
- 買い切り型:導入時の初期費用が高額ですが、長期間使用するほど費用は割安。
- サブスク型:初期費用が安価な分、毎月一定のコストを支払う必要がある点に注意が必要。
初期費用
「買い切り型」の場合、スマートロック本体の購入費用は 一台あたり5,000~2万円程度 が目安です。
「サブスク型」は、本体を購入必要がないため、基本的に初期費用は発生しません。
月額費用
「サブスク型」の場合、 一台あたり月額1,000~5,000円程度 の月額費用が発生します。
一方「買い切り型」は、本体のレンタル料が不要なので、基本的に月額費用はかかりません。
ただし、スマートロックの管理システムを利用する場合は、買い切り型でも一台あたり月額1,000円程度のシステム利用料が発生すると考えましょう。
オフィス向けスマートロックに関するよくある質問
A
既存の鍵に後付けできるタイプを選べば、スマートロックの設置に工事は不要です。
A
遠隔での施錠・解錠は、主にスマートフォンやリモコンを使用して行います。
スマートフォンの場合、専用アプリでボタンを押すだけで簡単に施錠・解錠できるほか、暗証番号を入力して操作するタイプもあります。
A
スマートロックはハッキングのリスクを完全には排除できませんが、多くの製品では脆弱性診断や通信の暗号化など、セキュリティ対策が施されています。
また、施解錠履歴(アクセスログ)を記録するため、不正行為を防ぎやすい環境が整っています。
セキュリティに不安がある場合は、公式HPを確認したり、問い合わせを行ったりすることが重要です。
A
買い切りタイプのオフィス向けスマートロックは「monokoto sLock」です。
A
スマートロックにはハッキングや技術的不具合のリスクがあります。暗号化が不十分だと不正アクセスされる可能性もあります。
また、バッテリー切れやソフトウェアの不具合で操作ができなくなることも考えられます。
設定ミスやユーザー管理の不備も後悔の原因となるため、導入前にしっかり確認することが重要です。
A
カードキーの入退室管理システム導入にかかる費用相場は以下の通りです。
・端末費用(ICカードリーダー):約5万円前後/台
・コントローラー費用:約20~40万円前後
・サーバー費用:約20~50万円前後
・ICカード費用:1枚あたり数千円程度
・月額利用料:数千~数万円
・保守・サポート費用:システム提供会社による
A
賃貸に後付けできるスマートロックは以下の通りです。
・SESAME「SESAME5」
・Qrio「Qrio Lock(Q-SL2)」
・SwitchBot「SwitchBotロック」
A
戸建てにおすすめのスマートロックは以下の通りです。
・エピック(EPIC)「ES-F9000Kr」
・美和ロック(Miwalock)「DTRS Ⅲ smart」
・LIXIL(リクシル)「FamiLock」
まとめ
オフィス向けスマートロックを導入することで、セキュリティ向上や施解錠管理の効率化など、様々なメリットがあります。
また、勤怠管理システムとスマートロックを連携することで、社員の打刻管理も正確かつ効率的に行えます。
「オフィスのセキュリティを強化したい」「鍵の管理を効率的したい」という場合は、導入を検討しましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!