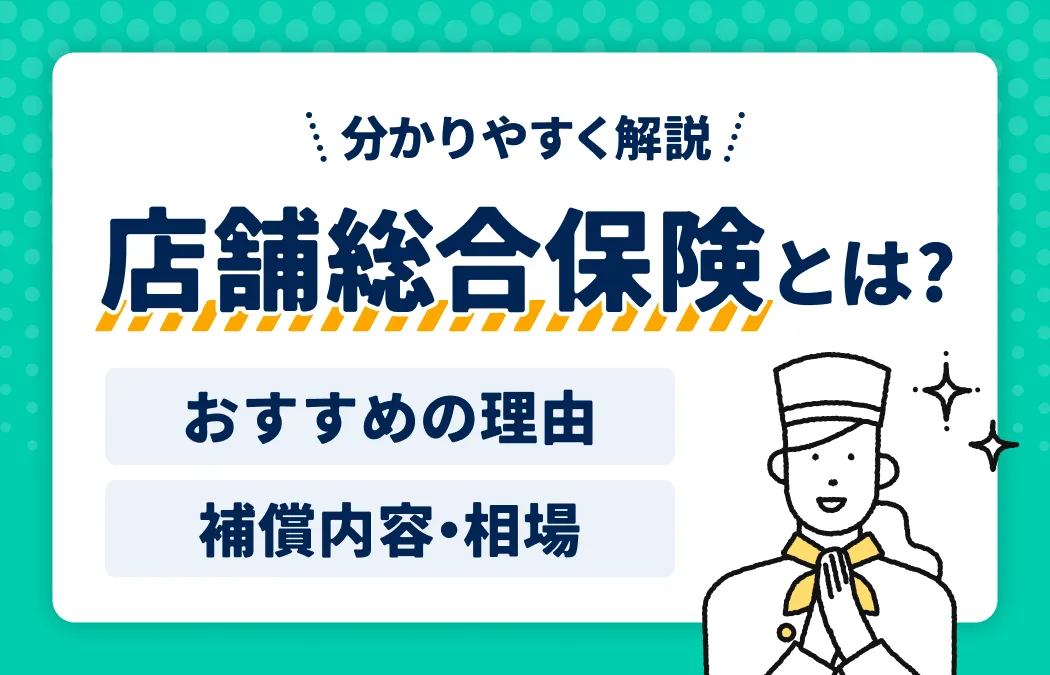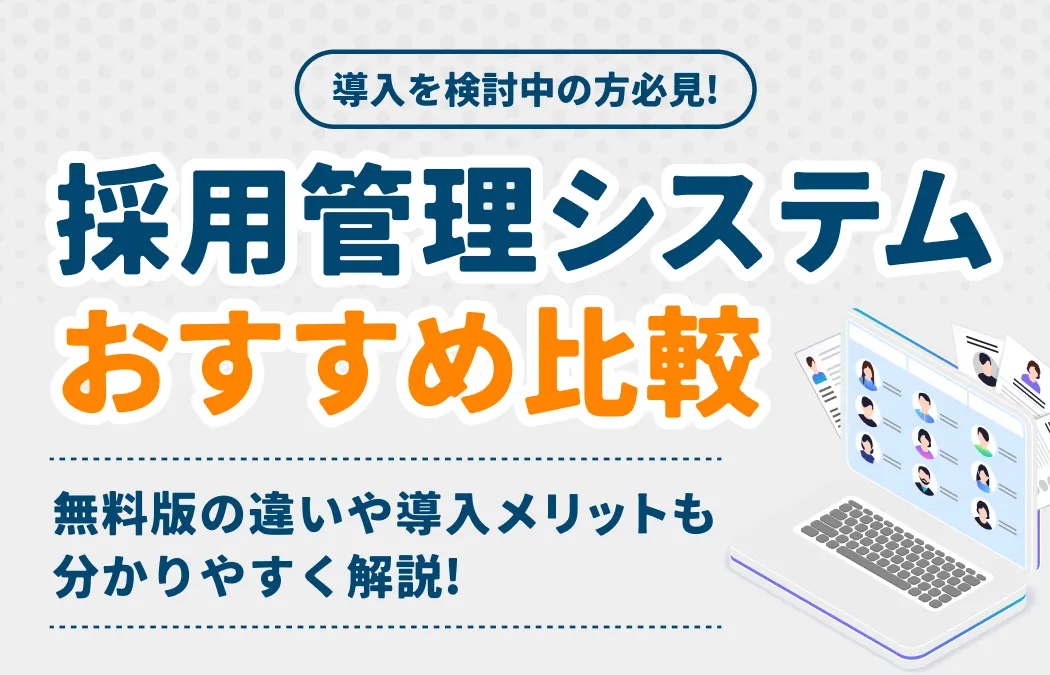社内で説明しようとすると意外と答えに詰まってしまう人は少なくありません。
ITはシステム導入や業務効率化の手段である一方、DXはそれを活用してビジネスや組織の在り方そのものを変革する取り組みです。
本記事では、両者の定義の違いを整理し、事例を交えて「IT化」と「DX」の線引きをわかりやすく解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)の、Transformationは「変容・変革」とという意味の英単語なので、DXを直訳すると「デジタルの変容・変革」になります。
単なるデジタル化というのではなく、デジタル技術を使うことで、人々の生活やビジネスが変容していくこと、変革を起こすことを「DX化」と言います。
DXの定義
DXとは、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念であり、その概念とは「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」というものです。またその特徴として、以下があげられます。
- 情報技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化
- デジタルオブジェクトが物理的現実の基本的な素材になる
- より本質的な情報技術研究のためのアプローチ、方法、技術を開発する必要がある
更に、2016年には、IT専門調査会者のIDC Japanが以下のようにDXを定義しています。

企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンス(経験、体験)の変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること
引用元:IDC Japan
つまりは 「デジタルを活用することで、ビジネスや私生活を取り巻く環境がより豊かになること」 と考えると、わかりやすいかもしれません。
ビジネスでのDXとは
DXやDX化というのが、最もわかりやすく感じられるのが、企業や店舗などのビジネスシーンでしょう。これは、デジタル技術を利用して、変化に対応し、より利便性に対応することを指しています。DXを進めることで、より効率的な業務を実現し、競走上の優位性を確立するものと捉えることができます。
企業やビジネスシーンでDX化が進むことで、デジタル技術を活用した、便利で快適なシステムを構築していくことが可能とされており、それがヒトや会社、社会にとってよりよい環境に変わっていくことを目指しているわけです。
DX推進のプロセスとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なるIT化ではなく、企業の仕組みやビジネスモデルそのものを変革する取り組み です。
しかし、いきなりDXを実現することは難しく、段階を踏んで推進していく必要があります。多くの企業では、まずITツールの導入から始まり、その後に業務フローや組織体制の改革、最終的に新しい価値創出へと進む流れを取ります。
ここでは、中小企業が理解しておくべき「段階的なステップ」と「直面しやすい課題と解決策」を整理します。
段階的なステップ(IT導入 → 業務変革 → DX化)
DX推進は以下のようなステップで進むのが一般的です。
-
STEP.1
IT導入(デジタル化の第一歩)
・例:紙の請求書をクラウド会計ソフトに置き換える
・解説:業務の効率化や作業負担軽減を目的とした基盤整備。ここではまだ「DX」とは呼べず、あくまで業務のデジタル化段階。 -
STEP.2
業務変革(プロセス改革)
・例:データを活用し、売上管理や在庫管理をリアルタイムで最適化
・解説:単なるツール導入に留まらず、業務プロセス全体を見直し、部門横断で効率化を実現。組織的な変革の要素が入る。 -
STEP.3
DX化(新たな価値創出)
・例:顧客データを活用した新サービスの提供、従来にない収益モデルの構築
・解説:デジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを刷新し、市場競争力を高める。ここに至って初めて「DX」と言える。
中小企業が直面しやすい課題と解決の方向性
中小企業にとって DX推進は必要性を理解していても、実行段階で多くの壁 があります。代表的な課題と解決の方向性を以下に整理しました。
- 課題①:コスト負担が大きい
→ 解決策:小規模から始められるクラウドサービスを利用し、初期投資を抑える。 - 課題②:専門人材が不足している
→ 解決策:外部ベンダーやITコンサルに一部を委託し、社内メンバーの学習も並行して進める。 - 課題③:社内の理解不足や抵抗感
→ 解決策:経営層が方針を明確に打ち出し、現場の負担軽減を具体的に示すことで合意形成を図る。 - 課題④:効果が見えにくい
→ 解決策:短期的に効果が出やすい業務(例:請求書発行や勤怠管理)から取り組み、成功体験を積む。
このように、 DXは大規模投資だけで実現するものではなく、小さく始めて段階的に拡張するアプローチが現実的 です。特に中小企業では「IT導入→業務改善→DX化」というプロセスを一歩ずつ踏むことで、コストやリスクを抑えつつ着実に成果を出せます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されている理由
何故、近年このようにDXが注目されているかというと、2018年に経済産業省が「デジタルガバナンス・コード2.0 (旧 DX推進ガイドライン) 」を定義し、企業におけるデジタル技術の活用を積極的に促進し始めたことが発端といえます。ここでは、今後のビジネス活動においてDXを推進できなければ、2025年以降に最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとしており、これをいわゆる “2025年の壁” と言っています。
このようなことから、現在政府はDXを行う企業に税優遇策を実施するなど、各支援策も充実させ始めています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワークやリモートワークの推進など、デジタル技術の活用は一気に広まってきています。
DX化のメリット
-
働き方改革の実現
-
人材不足の解消
-
業務効率化
-
新規事業や新サービスのスムーズな開発
働き方改革の実現
AIやRPAなど、現状の業務を自動化できるツールを活用することで、テレワークを導入しやすくなったり、従業員の業務効率化を図ることができるため、かねてから進められていた「働き方改革」の実現に大きく近づくことができます。人材不足の解消
DX化で働き方改革が実現されることにより、従業員にとって働きやすい環境が構築され、採用にも良い影響を与えるでしょう。もし今人材不足に悩んでいる企業があれば、DX化をはかることで、人材不足の解消にもつながるかもしれません。業務効率化
DX化によってAIやRPAなど、自動化ツールを活用することで、ヒューマンエラーを防ぐことにつながり、従業員はコア業務に集中することができるようになります。新規事業や新サービスのスムーズな開発
DXを実現することで、新規事業や新サービスもスムーズに開発することができるようになります。実際、小さなところでいえば無人コンビニなどにおいて、AIカメラを利用することでお客の行動状況を把握し、新しいマーケティングに役立てるという例も出てきています。
今後これまで以上に大量の情報を収集できたり、更にDXを促進したりすることができるようになれば、新サービスを続出させる企業が出てくるのも夢ではないかもしれません。
他企業に対する優位性を担保できる
実際のところ、多くの企業でDX化の推進が始まっています。DX化を成功させることができれば、他企業に対して優位性を担保することができ、ブランディング力の向上や、採用強化にもつながります。DXとITの違いを徹底解説
DXとITの定義比較表
まず、DXとITの定義を比較表で整理します。
| 項目 | IT | DX |
|---|---|---|
| 定義 | 情報技術そのもの、または業務効率化のための導入 | デジタル技術を活用した企業変革・新しい価値の創出 |
| 目的 | 業務効率化・コスト削減・業務の正確性向上 | 競争優位性の確立・新規事業創出・市場での変革 |
| 範囲 | 部分的なシステム導入(会計ソフト、勤怠管理など) | 組織全体やビジネスモデルの改革 |
| ゴール | 業務改善 | 企業の持続的成長・ビジネスモデルの革新 |
ITは主に「業務効率化」という内向きの効果に留まります。一方で、DXは「顧客体験や新規サービス」といった外向きの成果に直結します。
IT導入とDX推進の具体事例比較
実際の事例で、ITとDXの違いを確認しましょう。
IT導入の例
- 会計ソフトを導入して経理作業を効率化
- 勤怠管理システムを入れて残業時間を自動集計
DX推進の例
- 会計データを分析して新しい融資サービスを提供
- 勤怠データを活用し、従業員の働き方改革を推進
- 顧客行動データから新しい商品開発につなげる
よくある誤解(「IT導入=DX」と考えてしまうケース)
DX推進を 目指す企業でよく見られるのが、「システムを導入したからDXが進んでいる」という誤解 です。実際には、以下のようなケースが多く存在します。
-
誤解例1:クラウドツールを導入した=DX化
→ 実際は「デジタル化」に過ぎず、業務効率は向上しても新しい価値は生まれにくい。 -
誤解例2:ペーパーレス化=DX化
→ 紙をなくすこと自体は効率化だが、データ活用やサービス改革にまで至らなければDXとは言えない。 -
誤解例3:社内でアプリを活用=DX化
→ 部門単位の便利ツール導入はIT活用であり、企業全体の変革には直結しない。
DXとIoTの違いと関係性
DX(デジタルトランスフォーメーション)とIoT(Internet of Things)はしばしば混同されますが、両者は役割が異なります。
IoTは「モノや機器をインターネットにつなぎ、データを収集・活用する技術」です。一方DXは「そうした技術を活用して企業や社会の仕組みを変革する取り組み」を意味します。つまり、IoTはDXを実現するための手段のひとつに過ぎません。
IoTはDXを支える技術のひとつ
IoTは センサーやデバイスを通じて膨大なデータを収集し、それをリアルタイムに活用できる 点が大きな強みです。これにより、工場や店舗、家庭など多様な現場で効率化や自動化を実現できます。
IoTの具体例
- 工場設備にセンサーを取り付け、故障を未然に検知
- 農業分野で気温や土壌データを収集し、自動で灌漑を制御
- スマートホームで電気や家電を遠隔操作
これらの事例は非常に便利で効果的ですが、あくまで「データ収集や効率化のための技術活用」にとどまります。IoT自体は業務改善を支援しますが、企業戦略やビジネスモデルの転換にまで踏み込むものではありません。
IoT単体では変革にならない理由
DXとIoTの違いを理解するには、「成果の範囲」に注目することが大切です。
IoT単体の限界
- データ収集・自動化にとどまる
- 活用が部門や特定領域に限定される
- 組織やビジネス全体の変革には直結しない
- 収集したデータを活用し、新しいビジネスを創出
- 顧客体験や収益モデルを刷新
- 組織全体を横断的に変革
DXと混同されやすい関連用語の違い
ICTとの違い
ICT(Information and Communication Technology)は「 情報通信技術」の総称で、インターネットや通信回線、データの送受信技術を含み ます。主な目的は「情報伝達の効率化・迅速化」であり、企業内では業務効率の改善に活用されます。
ICTの特徴
- インフラ面が中心(ネットワーク、クラウド環境の整備など)
- 業務効率化・コミュニケーション改善が主な成果
- 企業文化やビジネスモデルの大転換までは想定しない
- ICT:通信・情報伝達を効率化する手段
- DX:ICTやITを含む技術を使い、企業全体を変革する戦略
解説:ICT導入で社内の情報共有はスムーズになりますが、それ自体では競争優位性や新しいサービスの創出には直結しません。DXはICTを活用しつつ「組織全体の変革」に結びつける点が大きな違いです。
IoT・AIなど他の関連用語との位置づけ
DXは「企業や社会を変革するゴール」であり、その実現を支えるのがIoTやAIなどの個別技術です。混同しやすい用語を以下に整理しました。
| 用語 | 定義 | 主な役割 | DXとの関係 |
|---|---|---|---|
| IoT | モノをインターネットにつなぐ技術 | データ収集・自動化 | DX実現のための手段 |
| AI | 人工知能、データから学習して予測・判断する技術 | 自動化・高度分析 | DXを推進する高度技術 |
| ICT | 情報通信技術 | 情報伝達・業務効率化 | DX基盤を支えるインフラ |
| IT | 情報技術全般 | 業務効率化・システム化 | DXの構成要素・出発点 |
解説:これらの用語はすべてDXと関係がありますが、DXそのものではありません。DXは「技術活用の結果として起こる変革」であり、IoTやAIはそのためのエンジン、ICTやITは基盤と位置づけると整理しやすくなります。
DXを成功させるうえでのポイント
まずはDXのガイドラインに目を通す
2018年12月に、経済産業省から「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」というものが公表されました。このガイドラインには、DXを推進するための指針が網羅的に記載されています。▶デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン
DX化を行う上で、失敗する企業が多い為、失敗を避けるためのヒント、また、日本企業のDX化を後押しするため、ガイドラインが作成されているため、DX化を検討している方は目を通しておくべきです。
なぜ失敗しているのか、何をすると失敗してしまうのか、失敗を避けるためにはどうすれば良いのか、など、予め知識を集めておきましょう。
3~5年後を想定して計画を立案
1つは、3~5年後を想定して計画を立案することです。DXの実現には早くても1年から3年ほどの時間がかかり、実際の成果を得られるには3から5年後であるといわれています。そのため、3~5年後に役立つDXでなければ意味がないというわけです。3~5年後に重視されているビジネスポイントは何なのか、自社の事業はどのように動いているのか、もしくは動かす予定なのかという点をイメージしながら、業務プロセスを加味し実現していくことが重要であるといえるでしょう。
既存システムからの脱却
DXにおいて、最大の壁となるといわれているのが「既存システム」です。既存システムの何が弱点になるのかといえば、既存システムに抱えている膨大なデータを、新規システムに移管させることができない、いわゆる変更も移動もしにくくなっている状況にある点です。既存システムの老朽化により、なかなかDXが進んでいない企業は少なくありません。どのように脱却するかを検討することも、DXを行うきぎょうにとって非常に重要なことであると言えます。
経営者・トップ層の参画
DXには、中途半端な投資を行わず、思い切った、かつ適正な投資をおこなうことも必要です。そのためには経営者、トップ層全員が同じ方向をむいてDXを促進していくことが重要であるといえるでしょう。うまく意見をまとめつつ、会社の方針を定めていくために、その時々で過不足のない適正な投資額を決定するような体制が欠かせません。
適正なシステムの導入
DXを行うには、何らかのデジタルシステムを導入することになります。つまりこの導入システムが社内ルールに合わない、従業員がうまく利用できないということが起これば、優秀なシステムを導入したとしても、その効果を発揮できずに失敗に終わってしまうというわけです。社内システムや、従業員にとって活用しやすいものなど、システムのもつ利点を大いに発揮できるような体制を整えつつ、適正なシステムを導入することも、DX成功に欠かせないことであるといえるでしょう。
DX成功事例|大企業と中小企業の取り組み
DXの実現方法は企業規模や業種によって大きく異なります。大企業では膨大なデータやリソースを活用して新しい事業モデルを作り出すケースが多い一方、中小企業では限られた予算や人員の中で効率化と収益改善を両立させる取り組みが中心です。
大企業の事例(大塚製薬/味の素など)
大企業は潤沢な資金と技術力を背景に、DXを通じて新しい市場を切り拓いています。
大塚製薬
- 健康管理アプリとIoT機器を組み合わせ、顧客の健康データを収集
- データをもとにパーソナライズされた健康提案を行い、新たなビジネスモデルを構築
味の素
- 生産ラインにセンサーを導入し、稼働データをリアルタイムで収集
- AI解析により設備故障を予測し、安定した生産体制を確立
中小企業の事例(販促のデジタル化/業務効率化など)
中小企業でも、身近な業務からDXを実現している事例があります。大規模投資を行わずとも、段階的な取り組みで成果を出すことが可能です。
販促のデジタル化
- 地域の飲食店がSNS広告を活用し、顧客データを分析
- リピーター獲得率が向上し、売上を安定化
業務効率化
- 製造業の中小企業がクラウド会計・在庫管理システムを導入
- 手作業による集計を削減し、経理担当者の工数を大幅に削減
リモートワーク推進
- ITサービス企業がオンライン会議システムを導入し、全国の社員が在宅勤務を実現
- 採用範囲が広がり、優秀な人材確保につながった
DXとIT活用の具体例
IT導入による業務効率化の例
IT導入は業務の効率化や人的負担の軽減を目的 とした第一歩です。
- 会計ソフトの導入
請求書作成や仕訳処理を自動化
経理担当者の工数削減、ヒューマンエラーの減少 - レジシステムの活用
POSレジで売上データを自動集計
在庫管理との連携により棚卸作業を効率化 - クラウド勤怠管理ツール
出退勤を自動で記録
勤怠集計の時間短縮と労務リスクの軽減
DX的変革を実現した例
DXでは、 ITを基盤に「新しい価値創出」や「事業モデルの変革」に踏み込むのが特徴 です。
- 新サービスの創出
会計ソフトで得られた企業データを分析し、中小企業向け融資サービスを展開
→ 単なる業務効率化から新たな収益源へ発展 - 顧客体験の改善
POSレジデータを分析して、顧客の購買履歴に基づいたパーソナライズ広告を配信
→ 顧客満足度の向上とリピーター増加につながる - 事業モデルの転換
勤怠データを活用して、従業員の働き方改善や人材戦略を最適化
→ 単なる労務管理から、企業文化や採用活動全体の変革へ
まとめ
DXとITは密接に関わりながらも目的や範囲が異なり、ITは業務効率化のための「手段」、DXは企業全体を変革する「ゴール」です。
本記事で紹介したように、同じツールを導入しても活用次第で単なるIT化にとどまるか、DXとして新しい価値を生み出すかが分かれます。まずは自社の現状を把握し、段階的に取り組むことが重要です。小さな業務改善から始め、将来的にビジネスモデルを進化させることを目指しましょう。
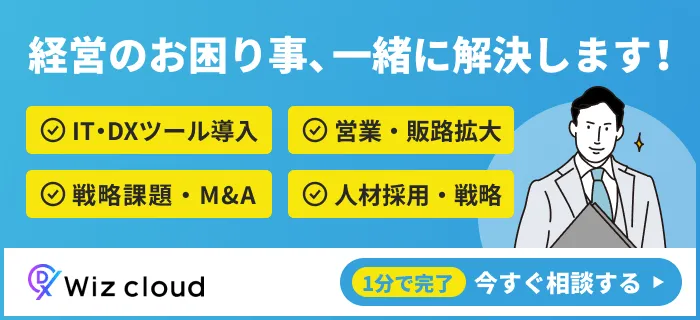

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!