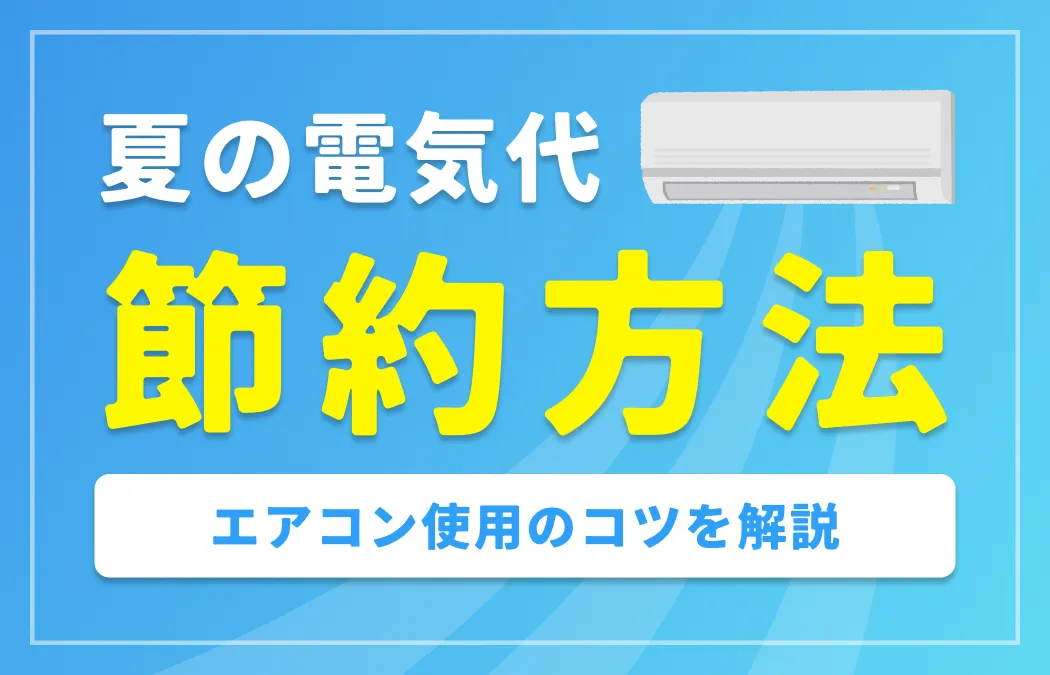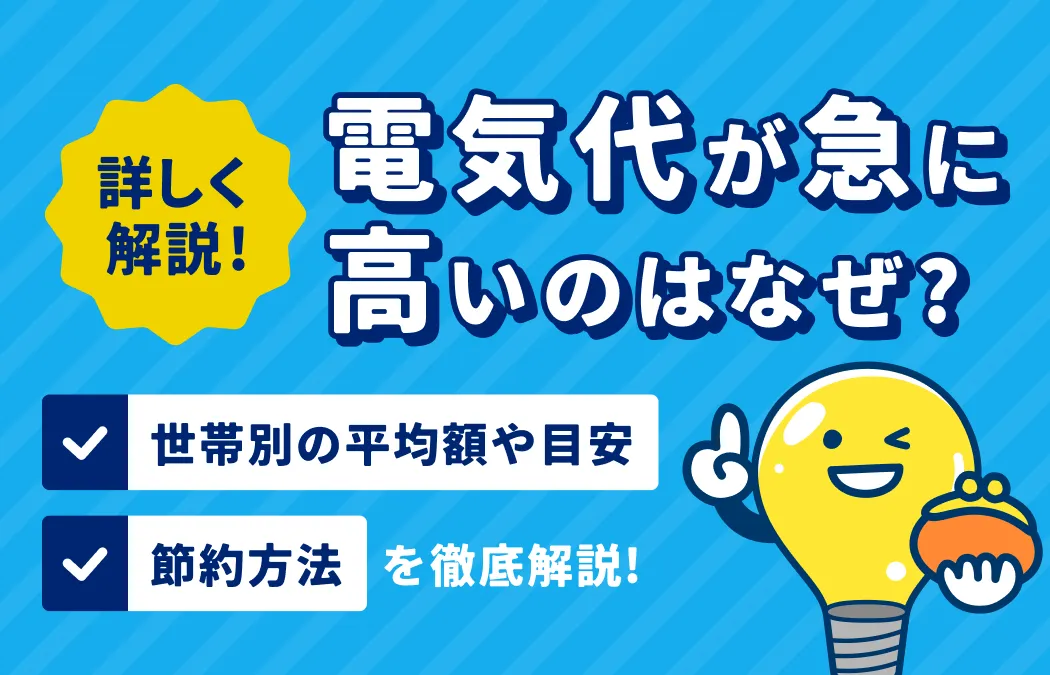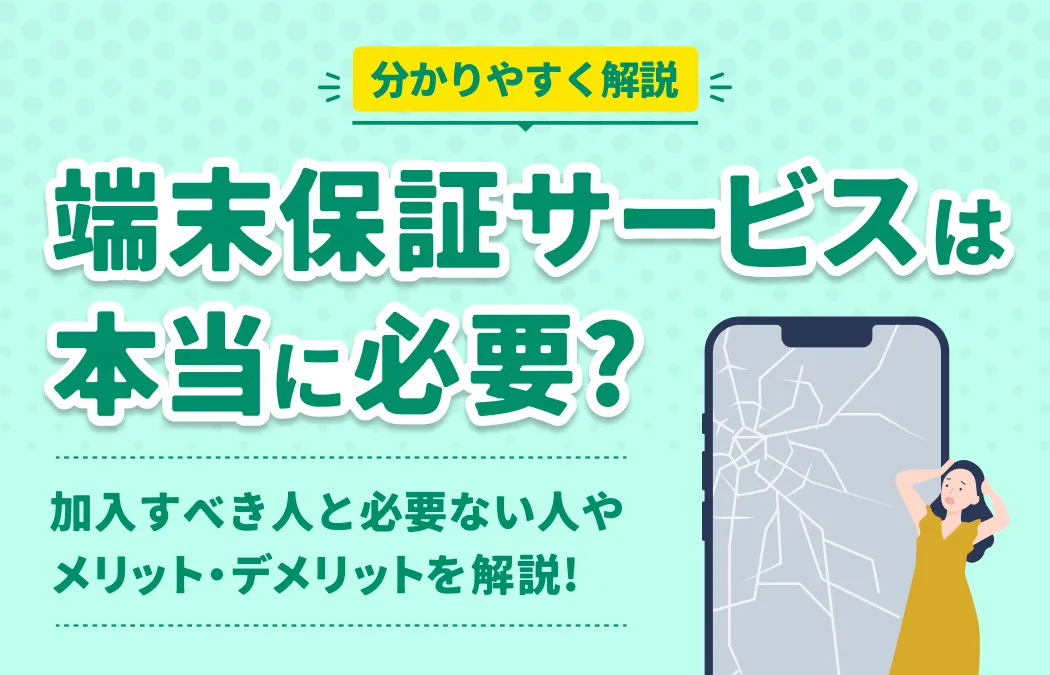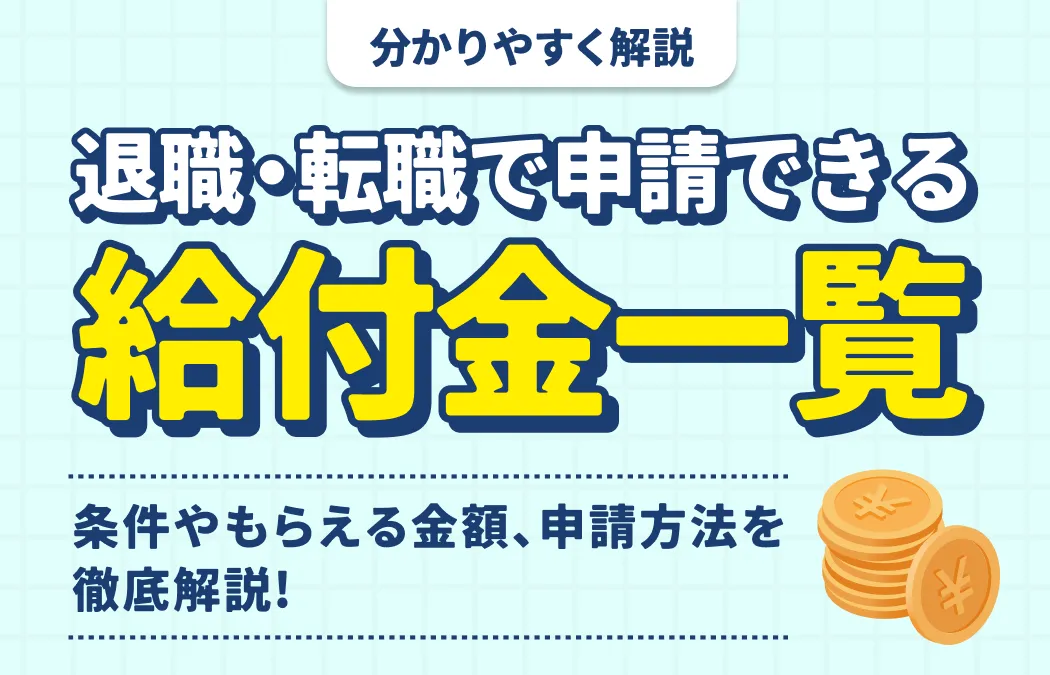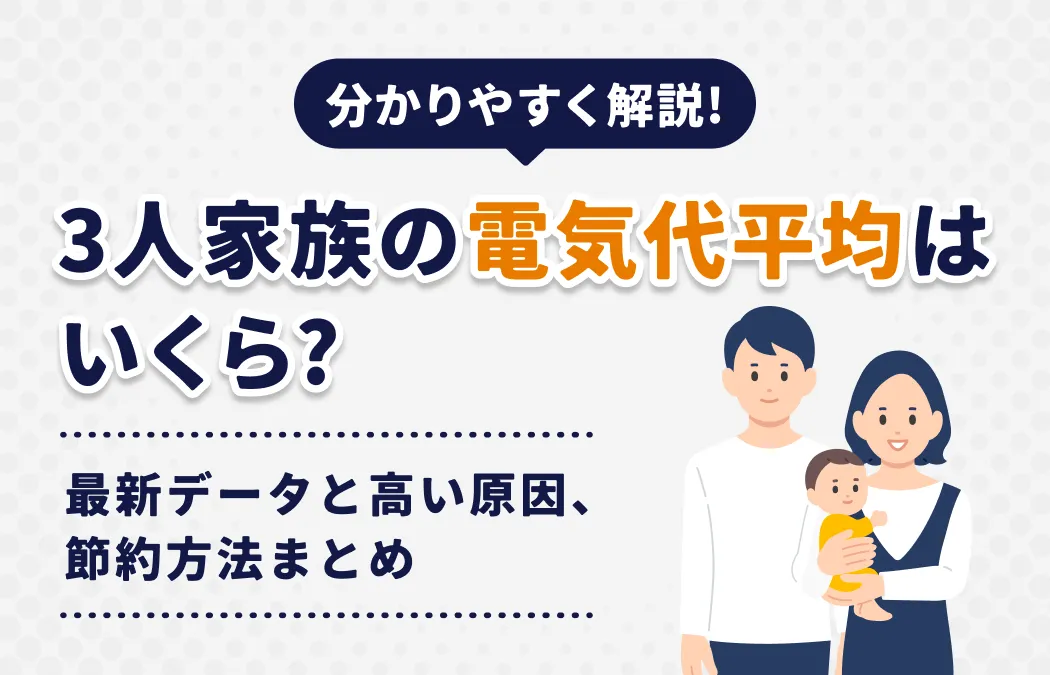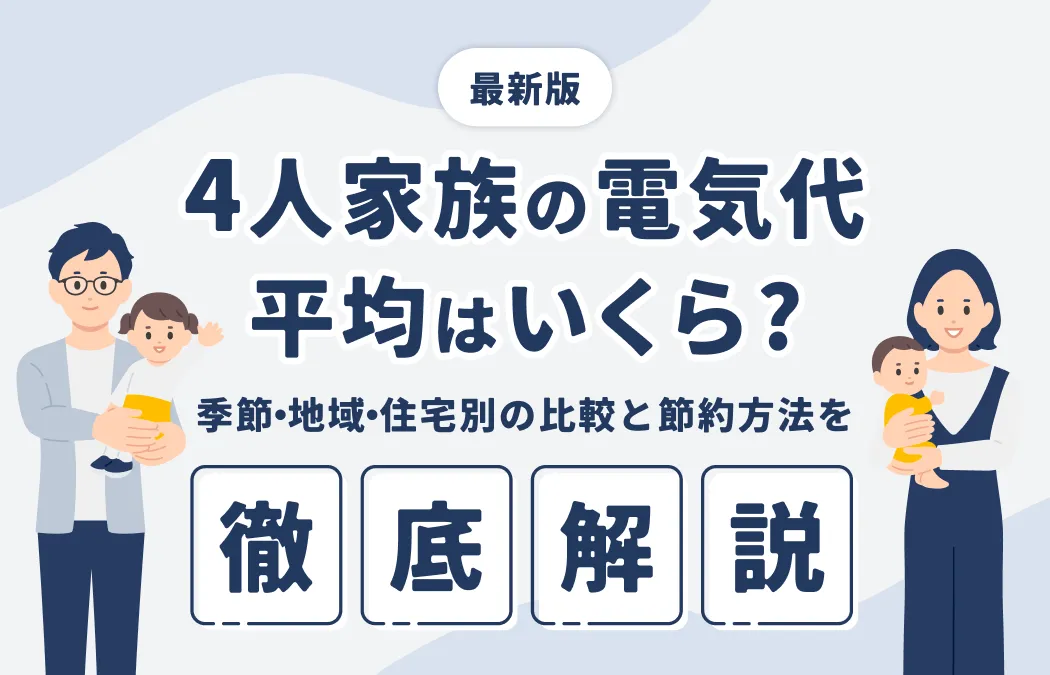「一人暮らしの電気代平均はいくらが相場?」
「電気代が高くておかしい!」
「夏と冬に電気代が跳ね上がる原因は?」
一人暮らし・単身世帯の電気代平均は6,000円台後半が目安です。
2022年以降、電気代の高騰が続く中で、「自分の電気代が高いかどうか判断できない」「今すぐできる節約方法は?」といった疑問を抱く方も多いはずです。
本記事では、最新データに基づいた「平均電気代」の実態、電気代が高くなる原因の具体例、節約術などを徹底解説します。一人暮らしの大学生や単身世帯の方は必見です。
※本記事はアフィリエイト広告を含みます。
目次
▼この記事で紹介している商品
一人暮らしの電気代はどれくらい?平均を地域・季節別に確認
単身世帯の電気代平均|過去5年の推移
| 金額 | |
|---|---|
| 2024年 | 6,756円 |
| 2023年 | 6,726円 |
| 2022年 | 6,808円 |
| 2021年 | 5,482円 |
| 2020年 | 5,791円 |
一人暮らし世帯の電気代平均は、 ひと月あたり6,000円台後半が目安 です。
2022年以降は燃料費の高騰により、平均額がそれ以前より1,000円程度上がったまま、高止まりが続いています。
なお、電気代平均は地域や時期によっても変動します。
【地域・時期別】単身世帯の電気代平均
| 年間 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 6,756円 | 7,150円 | 5,839円 | 6,771円 | 6,356円 |
| 北海道・東北地方 | 7,500円 | 8,056円 | 6,431円 | 6,459円 | 6,423円 |
| 関東地方 | 6,566円 | 7,109円 | 5,505円 | 6,137円 | 5,492円 |
| 北陸・東海地方 | 6,794円 | 7,514円 | 6,003円 | 7,700円 | 7,406円 |
| 近畿地方 | 6,648円 | 5,889円 | 5,873円 | 6,652円 | 6,226円 |
| 中国・四国地方 | 7,437円 | 7,868円 | 6,063円 | 7,286円 | 6,767円 |
| 九州・沖縄地方 | 6,274円 | 6,401円 | 5,571円 | 6,896円 | 6,572円 |
時期別の平均を比較すると、特に 寒さが強まる1~3月分は暖房を多く使用することもあり、電気代が他の時期より高くなりやすいです。
また、地域によって電気代平均に差が出るのは、電気料金単価の違いに加え、気候条件も大きな要因として考えられます。
特に、北海道、東北、北陸地方などの寒冷地では冬場の電気代が高くなる傾向があります。
反対に、関東や近畿、九州など、地理的条件で比較的温暖な地域は、平均金額が低い傾向です。
電気代に差が出るその他の要因
住居タイプ別の差
一人暮らしの電気代は、住んでいる住居タイプや、建物の素材によって大きく変わります。
集合住宅のアパートやマンションは、壁や床を隣人と共有しているため、外気の影響を受けにくく 、冷暖房の使用頻度が少なく済む傾向があります。
一方で一軒家や戸建ての場合、断熱性が低いと外気温の影響を受けやすく、エアコンや暖房の稼働時間が長くなり、電気代が高くなるケースが多いのです。
さらに、古い建物では断熱材や窓の性能が劣るため、冷暖房効率が悪くなることもあります。
賃貸の場合は築浅物件を選ぶ、持ち家の場合は断熱リフォームをするのが節電に有効
ライフスタイルによる差
一人暮らしの電気代は、ライフスタイルの違いでも大きな差が出ます。同じ地域・同じ間取りでも「どのくらい家にいるか」「どう使うか」で支出は変わるのです。
たとえば 在宅勤務など、自宅で過ごす時間が長い人は、冷暖房や照明、パソコンなどを常に使用するため、電気代が高くなりがち です。
逆に日中は外出が多い人であれば、冷暖房や家電の稼働時間が短く抑えられ、請求額は低めに推移します。
また、古い家電はエネルギー効率が悪く無駄な電力消費に繋がりやすいため、省エネ家電を使っている家庭に比べて電気代が高くなりやすいです。電気代が高くなる原因
夏と冬はエアコン使用時間の増加で電気代上昇
夏と冬に電気代が高くなる最大の理由は、冷暖房の稼働時間が長くなるためです。
夏は猛暑日が続き、室温を下げるためにエアコンを長時間運転する必要があります。一方で冬は日照時間が短く、外気温が低下することで暖房の使用時間が増えます。
人間が快適に感じる室温はおおよそ20〜28度の範囲ですが、外気温が大きく外れるとエアコンの負担が増加 し、消費電力量が跳ね上がります。
また、夜間や朝方の冷え込みに備えて暖房をつけっぱなしにする家庭も多く、これが冬の電気代を押し上げる要因になります。
夏と冬は「外気と室内の温度差」が大きいため、その差を埋めるために冷暖房に多くの電力を消費
家電の効率・古さ・待機電力などの要因
電気代の増加は、冷暖房以外の家電の使い方や性能にも影響されます。 古いエアコンや冷蔵庫は省エネ性能が低く、同じ稼働時間でも最新モデルより多くの電力を消費 します。
- 冷蔵庫:24時間稼働するため、消費電力の差が年間では数千円〜1万円規模になることも
- 待機電力:テレビや電子レンジは電源を切ったつもりでもコンセントに差したままだと常に微量の電力を消費
- エアコンの掃除不足:フィルターが目詰まりすると効率が落ち、余計な電力を使ってしまう
つまり、夏と冬に限らず、家電の性能や使い方を見直すことが電気代削減には不可欠なのです。
電気代の構成と価格を決める仕組み
契約アンペア/時間帯別料金プラン/自由料金 vs 規制料金
電気代は単純に「使った分」だけでなく、契約内容や料金体系によっても変わります。まず契約アンペア数は、同時に使える電気の上限を示すもので、大きいほど基本料金が高く設定されています。
必要以上に高いアンペア契約をしていると、使わない電気容量に対しても余計な料金を払っていることになる のです。
また、時間帯別料金プランを選べば、昼間の高い単価と夜間の安い単価をうまく活用でき、生活リズムに合わせて節約が可能です。
さらに電力自由化以降は、大手電力会社の「規制料金」と新電力の「自由料金」が存在します。自由料金は競争原理が働くため割安なケースも多く、比較検討することで数千円単位の節約が期待できます。
電力会社/プランの選び方のコツ
電力会社や料金プランを選ぶ際は、料金の安さだけでなく、 自分の生活スタイルとの相性を重視することが重要 です。
たとえば夜型の生活をしている人なら夜間単価が安いプランが向いており、日中の在宅が多い人には定額制や昼間割引が適しています。
また、電気とガスをセット契約すると割引になるケースもあり、光熱費全体での削減が可能です。
ただし、割引やキャンペーンに惑わされると、長期的には不利な契約になることもあります。
月々の電力使用量やピーク時間帯を確認し、自分の実態に合ったプランを選ぶことが大切

\ 電気代の見直しで家計をもっとお得に! /
電力会社や料金プランを切り替えることで、さらに大きなコスト削減が可能です。
専門スタッフがご家庭に合った最適なプランをご提案&手続きもサポート!
電気代節約術:今日から実践できるテクニック
家電の使い方/選び方
電気代を抑えるには、家電の使い方を工夫することが効果的です。
- 冷蔵庫の中は適度な容量にする
詰め込みすぎると冷気が循環せず効率が落ち、余分な電力を消費。逆にスカスカでも冷却効率が下がる。 - 省エネ家電への買い替え
古い家電はエネルギーの交換効率が低く無駄な電力を消費。特にエアコンや冷蔵庫、洗濯機は最新モデルに買い替えることで年間数千円〜1万円以上の節約につながることも。 - 待機電力を減らす
テレビや電子レンジはコンセントを抜く、または節電タップを活用する。
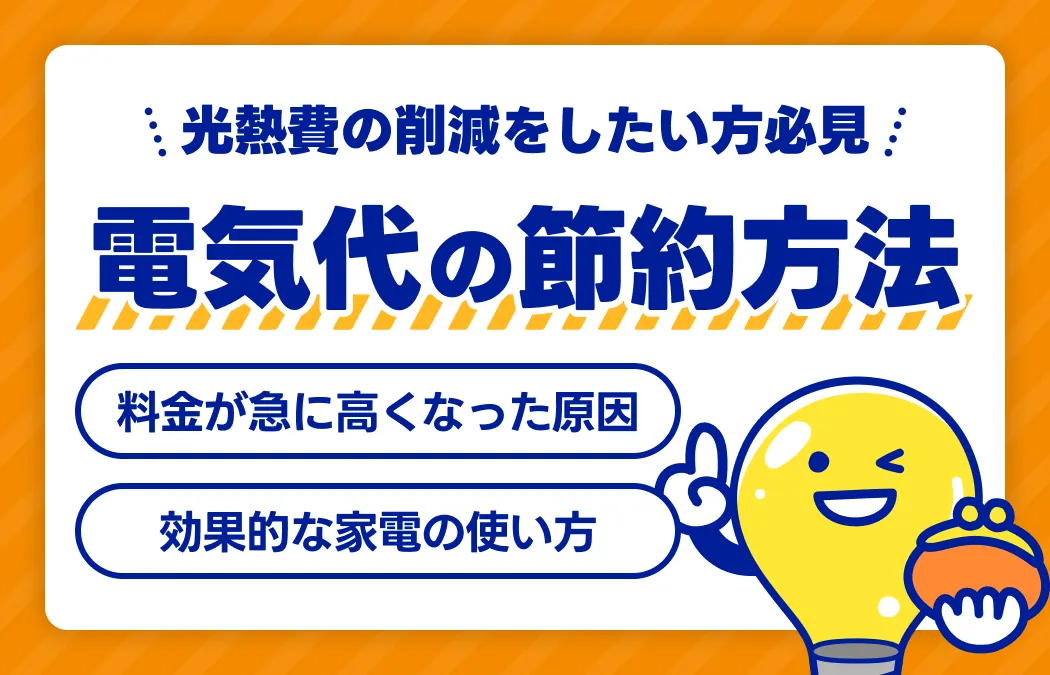
エアコンの温度設定と断熱対策
冷暖房の使い方を見直すことは、一人暮らしの節電効果が大きいポイントです。
- 設定温度
夏は28度、冬は20度前後が目安。温度を1℃変えると、冷房で約13%、暖房で約10%の消費電力量を削減できる - サーキュレーターを併用
空気の流れが良くなり、設定温度を無理に下げずとも快適に過ごせる - 断熱対策
厚手のカーテンや窓用の断熱シートを活用するだけで外気の影響を和らげ、無駄な電力消費を抑制
特に冬は窓から熱が逃げやすいため、簡易的な断熱で暖房効率が大きく改善します。
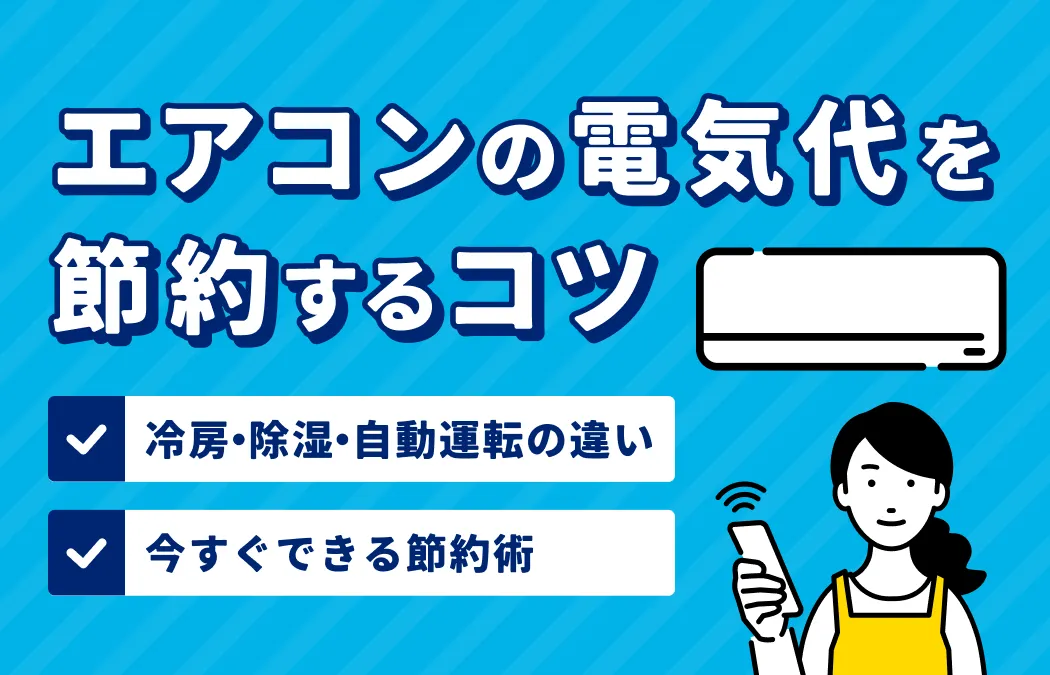
エアコンの電気代を節約するコツ!冷房・除湿・自動運転の違いや今すぐできる節約術を解説
節約につながるエアコンの使い方や空調効率を高めるコツ、冷房・除湿の違い、自動運転の効果まで徹底解説
詳しくはこちら
契約・プラン見直し/電力会社の乗り換えメリットと注意点
毎月の電気代を大きく下げたいなら、契約内容や電力会社の見直しが効果的です。
電力自由化以降、基本料金が安価なプランや、夜間・休日に単価が安くなる料金体系など、選択肢が豊富になりました。
ライフスタイルに合ったプランに変更するだけで、年間数千円から数万円の削減も可能 です。
また、新電力会社はガスやインターネットとのセット割を用意していることが多く、光熱費全体の節約につながります。
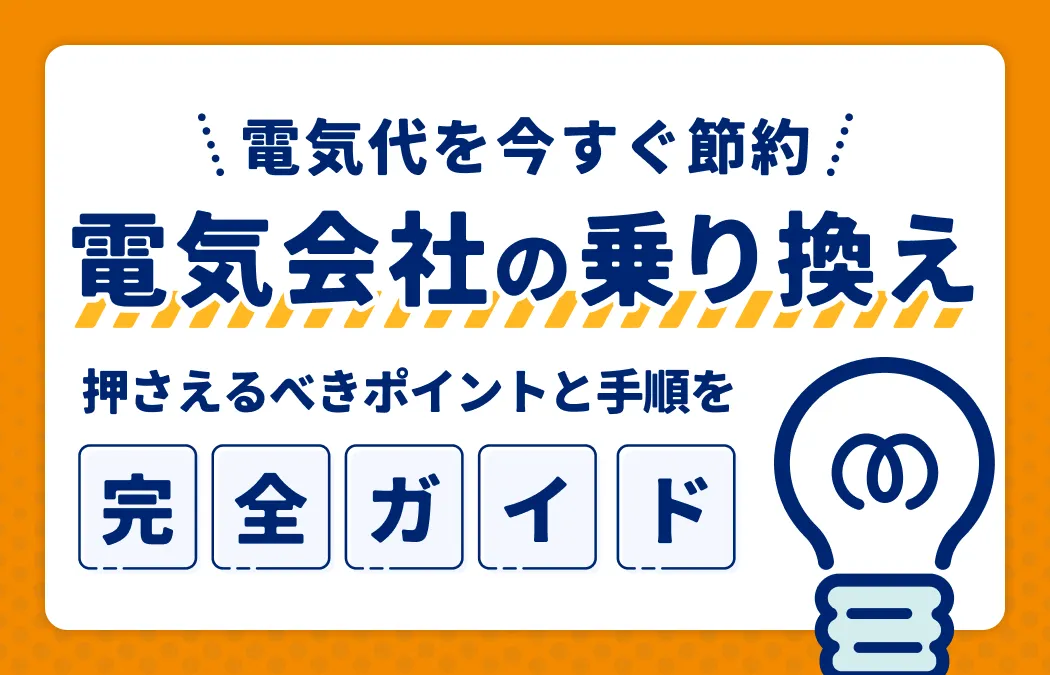
最新の値上げ情報・制度変更
最近の燃料費・原材料コストの動きと電気料金への影響
電気料金は、燃料費や原材料コストの変動によって大きく影響を受けます。
特に、火力発電に必要な 液化天然ガス(LNG)や石炭、原油の価格が国際的に高騰すると、電力会社はそのコストを「燃料費調整額」として利用者に転嫁 します。
2022年以降はウクライナ情勢や円安の影響で燃料費が上がり、日本の電気代も過去にない水準まで値上がりしました。
さらに2024年以降も、一部の電力会社が基本料金や従量料金の値上げを発表しており、家計への負担は依然として重い状況です。
定期的に値上げ情報をチェックすることが節約の第一歩
国・自治体の補助制度・省エネ支援制度
電気代の高騰を受け、国や自治体もさまざまな支援制度を実施しています。
たとえば国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」では、一定期間、使用量に応じて補助金が自動的に適用される仕組みが導入されました。
さらに自治体レベルでは、省エネ家電の買い替え補助や断熱リフォームの助成金が用意されており、条件を満たせば数万円単位の補助を受けられるケースもあります。
こうした制度を活用すれば、初期費用がかかる家電の更新や住まいの断熱対策も導入しやすくなります。
補助金や助成制度をうまく利用することで、短期的な家計の負担軽減だけでなく、中長期的な電気代削減にもつながる
自分の電気代が高いかどうかを判断するチェックリスト
使用量(kWh)・請求書の見方をチェック
電気代が妥当かどうかを判断するには、まず毎月の請求書を確認することが大切です。
請求書には「使用量(kWh)」と「単価(円/kWh)」 が記載されており、ここを把握することで平均と比較できます。
たとえば 一人暮らしなら月150〜200kWh前後が一般的な目安 で、これを大きく超えている場合は電気の使いすぎ、または契約プランが割高である可能性があります。
加えて、燃料費調整額や再エネ賦課金などの項目も確認すると、電気代の内訳が分かりやすくなります。
「総額」だけで判断するのではなく、使用量と単価を分けて確認することが、節約やプラン見直しのポイント
他の世帯(同じ地域・住居タイプ)との比較
自分の電気代が高いかどうかを知るには、同じ条件の人と比較するのが有効です。
たとえば 総務省の統計や電力会社の公表データでは、一人暮らしの平均電気代は月6,000円台後半 とされています。
ただし、地域や住居タイプによって差があり、寒冷地や戸建て住宅では平均より高くなる傾向があります。
もし自分の電気代が平均を大きく上回っている場合、使い方や契約内容に改善余地があると考えられます。
特に、地域は自分と同条件で比較するのがポイント
電力会社見直しでどれくらい節約できるか?実例シミュレーション
大手電力会社の従来プランから、基本料金の安い新電力のプランに乗り換えると、単価が約5〜10%下がる ことがあります。
一人暮らしで月6,500円の電気代を支払っている場合、これを年間に換算すると、およそ4,000〜8,000円の削減効果が期待できます。
さらにガスやインターネットとセット契約を選べば、追加で年間数千円の割引を受けられる場合もあります。
ただし、燃料費調整額の変動や契約条件によっては想定より節約額が小さくなることもあるため、必ず複数社でシミュレーションを行うことが重要です。
\ 電気代の見直しで家計をもっとお得に! /
電力会社や料金プランを切り替えることで、さらに大きなコスト削減が可能です。
専門スタッフがご家庭に合った最適なプランをご提案&手続きもサポート!
よくある質問(FAQ)
A
電気代が高い原因として代表的なのは「外気温」「家電の性能」「契約内容」の3要素です。特に、夏と冬はエアコンの稼働時間が増え、使用量が跳ね上がります。また、古い家電は省エネ性能が低く、同じ使用時間でも最新モデルより電力を多く消費してしまいます。さらに、契約アンペアが高すぎる場合や、ライフスタイルに合わない料金プランを利用している場合も、無駄な基本料金や高い単価を払う原因になります。
A
一人暮らしの平均電気代は月6,000代後半が目安なので、8,000円前後であれば平均よりやや高めですが、必ずしも異常というわけではありません。特に在宅勤務が多い人、エアコンや電気ストーブを長時間利用する人、寒冷地や戸建てに住んでいる人は、平均より高くなる傾向があります。
A
契約アンペア数は、一度に使用できる電気容量を表します。一般的に一人暮らしなら20A〜30Aが目安とされており、電子レンジやエアコン、ドライヤーを同時に使う場合でも30Aあれば十分です。必要以上に大きなアンペア契約をしていると、その分の基本料金を無駄に支払うことになります。逆に低すぎるアンペアにするとブレーカーが頻繁に落ちてしまい、生活に支障をきたす恐れがあります。
まとめ
一人暮らしの電気代は平均で月6,000円台後半が目安ですが、住居タイプやライフスタイル、家電の性能によって大きく変動します。
特に夏と冬は冷暖房の使用が増えるため、他の季節に比べて請求額が高くなる傾向があります。
しかし、家電の使い方や設定温度の工夫、断熱対策、さらに電力会社や料金プランの見直しを行えば、年間で数千円から数万円の節約も実現可能です。
請求書の内訳や使用量を確認し、自分の支払いが妥当かどうかを客観的に判断することが第一歩となります。電気代が高いと感じた方は、今こそ電力会社の乗り換えやプラン比較を検討してみてください。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!