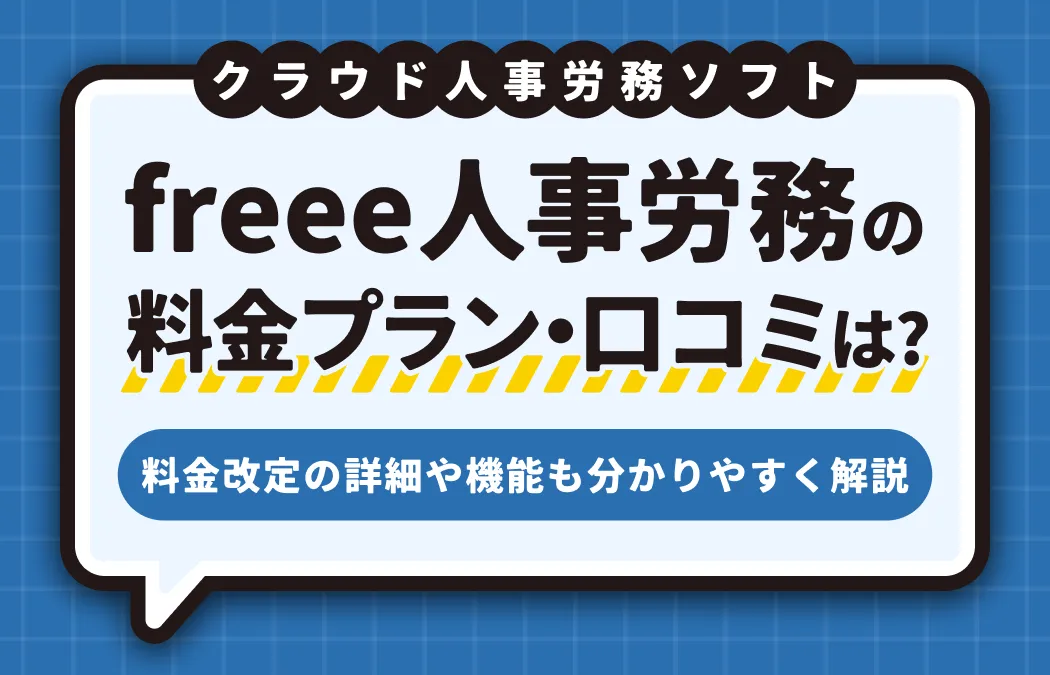「2割特例の対象者は?」
「2割特例と簡易課税、どっちが得?」
「2割特例」とは、インボイス制度による事業者の消費税負担を軽減するための経過措置です。
しかし、「事前に申請や届出は必要?」「適用の対象となる事業者は?」といった疑問も多くみられます。
今回は、2割特例の要件や適用期間、納税額の計算方法などを徹底解説します。
簡易課税との違いについても触れているため、インボイス制度を機に課税転換する事業者に役立つ記事です。
目次
▼この記事で紹介している商品
インボイス制度における特例とは

インボイス制度とは、複数税率に対応するための仕入税額控除の方式で、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。
課税事業者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必要ですが、免税事業者がインボイス発行事業者になると納税負担が増えてしまいます。
そのため、 政府は税負担軽減や事務負担を配慮し、段階的な経過措置などの特例を設けています 。
インボイス制度の2割特例とは「消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる制度」

2割特例とは、 インボイス制度による事業者の消費税負担を軽減する目的 で設けられた経過措置です。
免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者となった場合、一定期間は消費税の納税額が売上税額の2割に軽減されます。
導入の背景には、小規模事業者の税負担を緩和することで、インボイス登録を促す意図があります。
2割特例の内容
納税額が「売上分の消費税額×20%」に
2割特例では、 納税額が売上にかかる消費税額のおよそ2割に軽減 されます。
計算式は以下のようになり、売上対価の返還や貸倒金の回収に伴う消費税額なども含めて、特別控除税額が算出されます。

課税売上高1,000万円以下が対象
2割特例の対象となるのは、 インボイス制度の施行に伴い免税事業者から課税事業者に移行した場合 です。
つまり、次のような小規模事業者のみ、2割特例を使えます。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間の課税売上高または給与等の支払総額が1,000万円以下

編集部
上記の他にも、対象者になるための細かい条件があります。詳しくはこちらをご覧ください!
事前の届出は不要
2割特例は、 消費税の確定申告書に「2割特例の適用あり」と付記するだけで適用を受けられます。
つまり、制度利用にあたって事前に届出を提出したり、申請手続きをしたりする必要はありません。
「本則課税」「簡易課税」のどちらかを申告時に選択できる
インボイス登録の際に本則課税(原則課税)・簡易課税のいずれかを選択している場合も、消費税の申告時に希望すれば2割特例を適用できます。
そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、 2割特例の方が有利な場合は後者で申告することが可能です。
なぜインボイス制度で2割特例が導入された?
インボイス制度における2割特例は、インボイス発行事業者の登録が国の想定よりも増えなかったことを受けて導入されました 。
インボイス発行には課税事業者としての登録が必要ですが、小規模事業者には負担が重く、登録が進まない状況がありました。
そのため、国は納税額を売上消費税の2割に抑える「2割特例」を導入し、納税負担を軽減することで、インボイス制度への移行を促進しようとしています。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら2割特例の対象となる事業者・ならない事業者

2割特例の対象となる事業者
2割特例の対象となるのは、 インボイス制度の施行を機に免税事業者から課税事業者へと転換し、適格請求書発行事業者に登録した事業者です。
また、2割特例を適用するには「前々(事業)年度の課税売上が1,000万円以下」である必要もあります。-
2023年10月1日(日)~2026年9月30日(水)の課税期間中に免税事業者が新たに課税事業者になった
-
インボイス制度の開始を機に「適格請求書発行事業者」に登録した
-
前々(事業)年度の課税売上が1,000万円以下
-
法人が2割特例を適用する条件
-
法人が2割特例の対象となるには、インボイス制度開始前に免税事業者だったことが前提です。
もともと課税事業者だった場合や、資本金1,000万円以上で設立初年度から課税事業者とされる法人は対象外となるため、条件を満たすかどうかを事前に確認することが重要です。
2割特例の対象とならない事業者
以下のような事業者は、2割特例の対象となりません。
-
前々(事業)年度の課税売上が1,000万円を超える事業者
-
特定期間の課税売上高あるいは給与支払総額の両方が1,000万円を超える事業者
-
課税期間の特例の届出で、課税期間を1ヶ月あるいは3ヶ月に短縮している事業者
-
資本金1,000万円超の法人を設立したがために初年度から消費税を納めないといけない事業者
-
前々(事業)年度の課税売上が1,000万円以下だが、2023年10月1日の属する課税期間以前から課税事業者になっている事業者
-
課税事業者選択届出書を提出している事業者(例外あり)
-
相続などで他の事業者の納税義務を承継した事業者(例外あり)
-
課税事業者選択届出書を提出した後、100万円以上の固定資産を購入した事業者
-
本則課税(原則課税)で消費税を計算している課税期間で1,000万円以上の棚卸資産か固定資産を購入した事業者
-
2割特例が使えないと誤解してしまうケース
-
2割特例は受けられない条件が非常にわかりにくいため、様々な誤解が生じています。
- 誤解1.「課税事業者選択届出書+登録申請」だと2割特例を使えない
⇒課税事業者選択届出書提出後、インボイス登録しても、2割特例を使えない課税期間は「2023年(令和5年10月1日)を含む課税期間」だけです。2024年(令和6年1月1日)から2割特例を利用できます。 - 誤解2.今年の課税売上高1,000万円超だから2割特例を使えない
⇒2割特例を使えるか使えないかは、個人事業主の場合「前々年の1年間」か「前年の上半期」で判断します。そのため、今年1,000万円を超えていても「前々年の1年間」か「前年の上半期」が1,000万円以下であれば、2割特例を利用できます。
- 誤解1.「課税事業者選択届出書+登録申請」だと2割特例を使えない
2割特例が使えるかどうかのフローチャート
2割特例が使えるかどうか判断するには、 フローチャートの活用がおすすめ です。

2割特例を受けるために必要な要件

帳簿に関する要件
2割特例を適用するには、帳簿に特定の情報を正しく記載する必要があります。
- 取引先の氏名または名称
- 取引日
- 取引内容(経過措置対象であること)
- 支払金額
請求書などに関する要件
2割特例を受けるには、請求書などの書類に必要な項目を正確に記載することが求められます。
- 書類の作成者名
- 取引日
- 取引内容(経過措置対象である旨)
- 税率ごとの税込金額
- 受領事業者の氏名
電磁記録の保存に関する要件
2割特例を適用するには、 請求書の写しやその内容を記録した電磁的記録を適切に保存する必要があります 。
電子データでの管理も可能ですが、保存方法に不備があると特例の適用が認められないため、注意が必要です。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら2割特例と簡易課税の違い

2割特例と簡易課税の違いは 「適用できる事業者」 「事前手続きの有無」 「適用期間の制限」 「計算方法」 の4点です。
| 2割特例 | 簡易課税 | |
|---|---|---|
| 適用できる 事業者の条件 |
|
課税売上高が5,000万円以下 |
| 事前手続きの有無 | なし | あり |
| 適用期間の制限 | なし | あり (2年間の縛り) |
| 計算方法 | 売上にかかる消費税額×20% | 売上税額ー売上税額×みなし仕入率 |
適用できる事業者
2割特例は、 インボイス登録により新たに消費税の納税義務が発生した事業者のみが対象 です。
一方、簡易課税は課税売上高が5,000万円以下であれば適用可能で、課税事業者の届出を提出している事業者など、2割特例の対象外の事業者も含まれます。
事前の手続きの有無
2割特例は、 事前の届出や申請手続きが不要 で、要件を満たせば自動的に適用されます。
一方、簡易課税を利用するには、適用を希望する課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があり、事前準備が求められます。
適用期間の制限
2割特例は、 申告ごとに他の課税方法と自由に選択できる 柔軟さがあります。
一方、簡易課税は一度届出を行うと原則2年間は継続して適用しなければならず、変更には再度届出が必要です。
計算方法
2割特例では、 「課税標準額に対する消費税額×80%」というシンプルな計算 で納税額を算出します。
一方、簡易課税では、売上げに対する返還や割引分も含めた複雑な計算が必要です。返品や複数事業を行う場合には、2割特例の方が簡便な場合があります。
【結論】2割特例と簡易課税、どちらがお得?
簡易課税制度と2割特例のどちらが得かは、 業種や仕入金額の割合などによって異なります。
2割特例は、業種を問わず一律で売上税額の2割が納税額になる一方、簡易課税制度では業種ごとにみなし仕入率が異なるためです。
ほとんどの業種は、2割特例を選択した方が納税負担が軽くなりますが、卸売業に関しては簡易課税制度の方が税負担が軽くなります。
-
業種ごとのみなし仕入れ率
-
事業区分 みなし仕入率 該当する事業 第1種事業 90% 【卸売業】
(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)第2種事業 80% 【小売業】
(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する第1種事業以外のもの)
【農業、林業、漁業】
(飲食料品の譲渡に係る事業)第3種事業 70% 【農業、林業、漁業】
(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)
【鉱業、建設業、製造業】
(製造小売業を含む)
【電気業、ガス業、熱供給業および水道業】
※第1種事業、第2種事業に該当するもの・加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く第4種事業 60% 【第1種~第6種事業以外の事業】
(例:飲食店業など)
※第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も含む第5種事業 50% 【運輸通信業、金融業、保険業、サービス業】
※飲食店業に該当する事業を除く
※第1種~第3種事業までの事業に該当する事業を除く第6種事業 40% 不動産業
2割特例の適用期間
2割特例は、 2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間 でのみ適用が可能です。
個人
個人事業者は、一律で 2023年10月1日から2026年12月31日まで 2割特例を適用できます。

法人
法人は 「決算期がいつか」によって適用期間が変わります 。
例えば、3月決算の法人の場合、2023年10月1日から2027年3月31日までの各事業年度が対象となります。

インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら2割特例での納税額の計算方法・計算例

2割特例適用時は、 「納税額= 売上にかかる消費税額 × 20%」 で消費税額を算出します。
例えば、売上800万円(税額80万円の場合)、消費税の納税額は「80万円×20%=16万円」となります。
売上800万円(税額80万円)・経費200万円(税額20万円)・サービス業の場合、納税額はそれぞれ以下の通りです。
| 本則課税 (原則課税)の場合 |
納税額=80万円-20万円=60万円 |
|---|---|
| 簡易課税の場合 | 納税額=80万円-(80万円×50%*)=40万円 ※サービス業のみなし仕入れ率 |
| 2割特例の場合 | 納税額=80万円×20%=16万円 |
2割特例の適用を受けるための手続き

2割特例の申告に必要な書類
2割特例の申告に必要な書類は以下の通りです。
第1表は、 対象となる課税期間の末日までに簡易課税の選択届出書を提出していれば「簡易課税用」 を、 提出していない場合は「一般課税用」 を使用します。
- 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般課税用または簡易課税用)第1表
- 消費税及び地方消費税の確定申告書第2表
- 〔付表6〕税率別消費税額計算表
2割特例の申請方法
2割特例を利用するには、 確定申告書に「2割特例を適用する」旨を記載するだけでOK です。
事前の届出も必要なく、簡単な手続きです。申告書における付記のイメージは以下の通りです。


インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら2割特例を適用するメリット

事前の手続きなしで適用される
2割特例は、事前の届出や手続きなしで適用できる点がメリットです。
簡易課税の場合は、事前に簡易課税制度選択届出書を提出しなければ制度を利用できず、節税効果も得られません。
一方、2割特例は 申告書に「2割特例の適用あり」と追記するだけで済む ため、手続き忘れ等の心配も不要です。
事務の負担を軽減できる
2割特例を利用することで、インボイス制度で必要になる細かい消費税の計算や帳簿の管理が簡単になります。
例えば、支払いに関する消費税計算や、税区分に関する記帳、インボイス取引の確認も行う必要がなくなります。
実際に払った消費税の2割だけを納めればよい ため、複雑な事務作業が減り、実務対応の効率化につながります。
消費税額が少なくなり、節税効果がある
2割特例を適用すると、 ほとんどの場合で納税すべき消費税が減額され、節税効果が得られます 。
簡易課税と比較した場合、卸売業と小売業等以外の業種においては、2割特例のほうが控除割合が大きくなります。
そのため、課税事業者に転換して納税義務が発生した場合も、負担増大を抑える効果が期待できます。
納税額の計算がラクになる
本則課税(原則課税)の場合、売上にかかる消費税額だけでなく、経費にかかる消費税額も算出したうえで納税額を計算する必要があります。
また、「計算がカンタン」と言われている簡易課税でも、値引きや返品、割り戻しがあった際には計算が複雑になってしまいます。
その点、2割特例は「売上にかかる消費税額×20%」の式で、対価の返還等も含めずに計算するため、 経理業務の大幅な負担軽減にも繋がります 。
申告の都度ごとに算出方法を選択できる
簡易課税の届出を出すと、最低2年間は本則課税(原則課税)に切り替えができません。
そのため、売上額の変動などがあった場合、簡易課税の適用によりかえって税負担が大きくなってしまう可能性もあります。
その点、2割特例は継続適用の縛りがないため、 消費税申告の都度、有利な算出方法を選ぶことが可能 です。
段階的に制度を導入できる
2割特例を利用することで、インボイス制度への対応を段階的に進められるメリットがあります。
インボイス制度導入直後は税務処理や取引の見直しが必要となりますが、 まずは簡易な課税方式を選べることで負担を軽減しながら徐々に制度に慣れていくことが可能 です。
2割特例を適用するデメリット

業種によっては、納税額が増える可能性がある
2割特例を利用することで手続きは簡単になりますが、 業種によっては簡易課税方式の方が納税額を抑えられる場合があります 。
特に、みなし仕入率が高い卸売業などでは、2割特例より簡易課税の方が有利になるケースがあるため、事前の資産と比較が必要です。
対象者が課税事業者に限定される
2割特例を適用するには、免税事業者から課税事業者に転換したうえで、「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。
登録手続きが済んでいないと制度を利用できない ため、あらかじめ登録申請を済ませておきましょう。
なお、インボイス制度の経過措置として、登録日が2023年10月1日から2029年9月30日の間にある場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出を省略できます。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら2割特例の注意点

2割特例は期間限定の措置
2割特例は、「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間」のみ適用できる期間限定の経過措置です。
そのため、 一定期間が過ぎると2割特例による節税効果は得られなくなります。
経過措置の終了後は納税負担が増えることを見越したうえで、課税転換するかどうかを慎重に判断しましょう。
2年の継続適用の縛りはない
2割特例には、「最低○年間の継続適用」といった縛りが無く、 消費税の申告を行うたびに適用するかどうかを選択できます。
ただし、申告ごとに特例対象期間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税時期間)であるか否かの確認は必要なので、注意しましょう。
少しでも条件が外れたら適用不可
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合や、課税期間の短縮の届出を提出した場合は、2割特例を適用できなくなります。
消費税の申告をする際は、 自社が適用条件をきちんと満たしているか必ず確認しましょう。
高額な資産を購入した場合も対象外
基準期間の課税売上高などが1,000万円以下となっていても、 高額な資産を購入すると2割特例は受けられません 。
以下のようなケースが該当します。
- 「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に、一般課税で調整対象固定資産を取得した場合
- 特例により納税義務が免除されない新設法人などが、一般課税で調整対象固定資産を取得した場合
- 一般課税のもとで高額特定資産を取得した場合
簡易課税との選択適用は別途届出が必要
簡易課税と2割特例を適宜使い分けたいと考えている場合、 「簡易課税は事前に届け出が必要」という点に注意が必要 です。
簡易課税を選択したい場合は、2023年10月1日の属する課税期間の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しましょう。
インボイス制度開始前に課税事業者になっていると適用されない
インボイス制度の開始前にすでに課税事業者となっていた場合、2割特例は適用されません。
2割特例は、インボイス登録をきっかけに初めて課税事業者となった人向けの制度だからです。
ただし 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば、2割特例の対象になる可能性があります 。
「受け取った消費税<支払った消費税」の場合、還付はない
2割特例は簡易課税と同様、還付を受けられません。
つまり、 「預かり消費税<支払消費税」となった場合も、お金は戻ってこないということです。
特に、輸出免税を行っている事業者などは、還付を受けられる本則課税(原則課税)の方が得なケースもあるため、慎重に選択しましょう。
修正申告等で選択替えは不可
2割特例は、 一度適用の有無を選んで確定申告を行うと、後から修正申告や更正の請求で選択を変更することはできません 。
例えば、当初確定申告で2割特例を選んだ後に「本則課税(原則課税)の方が有利だった」と気づいても、切り替えは認められないため慎重に判断しましょう。
2割特例を適用しないほうが良い具体的なケース

簡易課税でみなし仕入れ率が80%以上の場合
卸売業など、 簡易課税でみなし仕入れ率が80%以上の業種の場合、簡易課税の方が有利になる ため、2割特例を適用しないほうが賢明でしょう。
簡易課税では、預かった消費税から高い仕入れ率分を差し引けるため、納税額が少なくなる場合があります。
そのため、税額だけを重視するなら、2割特例より簡易課税を選んだ方がお得になります。
- 2割特例
70万円-70万円×80%=14万円 - 簡易課税
70万円-70万円×90%(みなし仕入れ率)=7万円
本則課税で消費税が還付される場合
2割特例は消費税の還付が受けられないため、 本則課税(原則課税)で仕入税額控除により還付が見込まれる場合は不向き です。
本則課税(原則課税)では、仕入額が売上額を上回り、控除しきれない仕入税額部分があると、還付される可能性があります。
2割特例は消費税の還付を受けられないため、本則課税(原則課税)で消費税が還付されると分かっている状況であれば、2割特例より本則課税(原則課税)を選ぶ方が有利です。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちらインボイス制度におけるその他の経過措置

インボイス保存の少額特例
少額特例とは、仕入価格が1万円未満の場合、 一定の事項を記載した帳簿の保存していればインボイス無しでも仕入税額控除が受けられる というものです。
ただし、少額特例を適用できるのは、要件に当てはまる中小企業が国内で課税仕入れを行う場合に限定されます。
| 対象事業者 | 2年前の課税売上が1億円以下 または 前年の1~6月(法人は事業年度の上半期)の課税売上が5,000万円以下 |
|---|---|
| 対象期間 | 2023年10月1日(日)~2029年9月30日(日) |
持続化補助金の上乗せ
適格請求書発行事業者に登録することで、 持続化補助金の補助上限額が50万円上乗せされます。
持続化補助金とは、小規模事業者の業務効率化や販路開拓などを支援するための補助金制度です。
| 申請する枠 | 補助上限額 (本来の補助上限額) |
補助率 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 100万円 (50万円) |
原則2/3以内 |
| 成長・分配強化枠 (賃上げや事業規模の拡大) |
250万円 (200万円) |
|
| 新陳代謝枠 (創業・跡継ぎなど) |
250万円 (200万円) |
インボイス制度の2割特例に関するよくある質問
A
インボイス制度および経過措置に関する情報は、国税庁のHPから確認できます。
A
2割特例が有利か不利かは、事業の種類や売上、経費の状況によって異なるため、必ずしもすべての事業者にとって得になるわけではありません。
A
新設法人でも2割特例を適用できる場合がありますが、資本金が1,000万円を超える法人は適用できません。
資本金が1,000万円を超える場合、設立当初から課税事業者として扱われるため、インボイス制度による消費税納税義務が発生する条件に該当せず、2割特例の対象外となります。
A
2024年にインボイス制度に登録し、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合でも、条件を満たせば2割特例の適用対象となります。
ただし、インボイス登録後は2年間、課税事業者から免税事業者へ戻ることができないため、その点に注意が必要です。
なお、インボイス登録は書類提出日から15日以降の日に反映されます。
A
2割特例の期間終了(2026年10月1日)以降の課税期間は、要件を満たす事業者に限り簡易課税制度を選択できます。
また、売上が1,000万円を超えるなど、2割特例の期間中に対象事業者でなくなった場合に関しても、要件を満たしていれば翌課税期間から簡易課税制度を適用可能です。
2割特例の終了後、本則課税(原則課税)よりも納税額の軽減が期待できる場合は「簡易課税制度選択届出書」の届出を行い、簡易課税を利用できるようにしておきましょう。
A
インボイス制度の8割控除とは、免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の経過措置です。
導入後3年間は、インボイスがない取引でも支払消費税の80%を控除可能です。
買い手側の負担を軽減するための措置で、4年目以降は控除率が50%に引き下げられます。
まとめ
2割特例とは、インボイス制度による事業者の消費税負担を軽減する目的で設けられた経過措置です。
2割特例を適用することで、節税効果が得られたり、消費税額の計算がシンプルになることで経理業務の負担が軽減されたりします。
事前申請なしで利用できる制度なので、インボイス制度を機に課税転換する個人事業主やフリーランスは積極的に活用しましょう。
インボイス制度対応!請求書ソフトの相談はおまかせ
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!