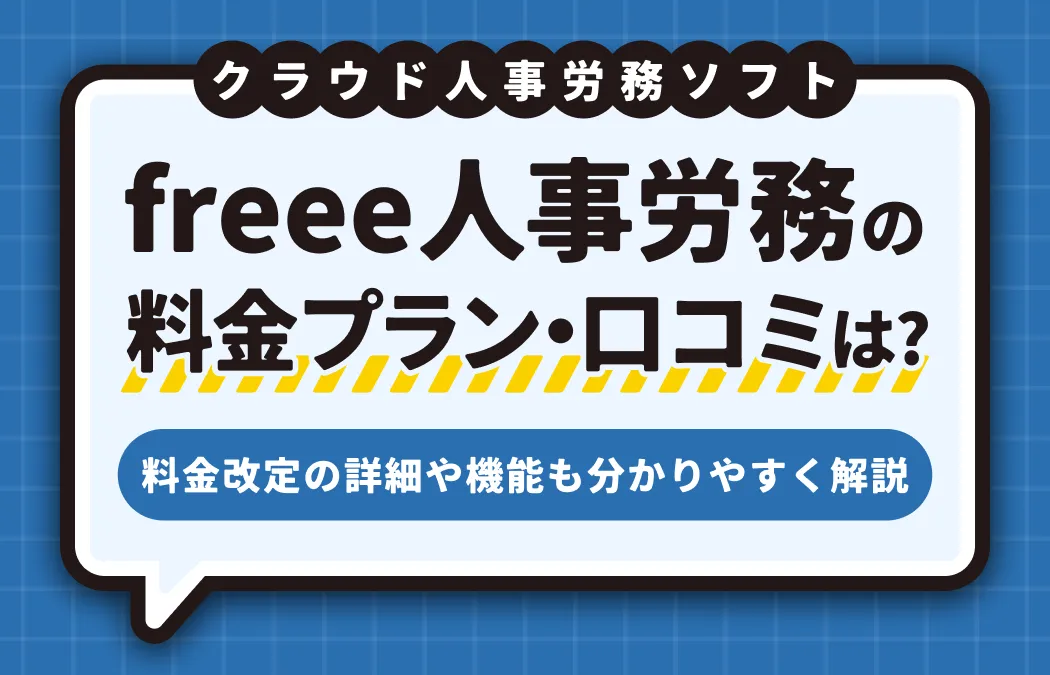「対応しないとどうなる?」
インボイス制度は、消費税の適正な管理と税務の透明性向上を目的とし、2023年10月に導入されました。適格請求書の発行・保存が義務化され、不正防止と正しい仕入税額控除が実現されます。
しかし、「制度の内容が難しい」「小規模事業者にはどんな影響があるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、制度の目的や経過措置の内容、対応に伴う業務負担とその解決策についてわかりやすく解説。個人事業主やフリーランスの方も必見の内容です。
目次
そもそもインボイス制度とは何か
インボイス制度とは、 買い手(仕入れ側)が消費税の「仕入税額控除」を受ける際に、売り手(請求側)から発行される「適格請求書(インボイス)」の保存が必要 になる制度です。
2023年10月に導入され、事業者間における消費税のやり取りに透明性が求められるようになりました。インボイスを発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみです。
売り手・買い手双方にとって、請求書の形式や取引先の登録状況の確認が重要になっています。

インボイス制度の目的は消費税の透明化
目的1.消費税の正確な税額管理
インボイス制度の最大の目的の一つが「消費税の正確な税額管理」です。
従来は、仕入れに対して一律の税率で控除を行う仕組みでしたが、実際の取引内容が不明確なまま処理されることも 多くありました。
インボイス(適格請求書)を用いることで、売手・買手の双方が正しい税率・税額を明記し、控除根拠を明確にできます。
目的2.税務の透明性向上と不正防止
インボイス制度のもう一つの大きな目的は「税務の透明性向上と不正防止」です。
従来の仕入税額控除※では、適切な証拠書類がなくても控除が認められるケースがあり、不正の温床 となっていました。
インボイス制度では、税務署に登録された事業者が発行するインボイスがなければ控除ができないため、不正請求や仮装経費の計上を防止できます。
※仕入税額控除:事業者が仕入れや経費で支払った消費税を、売上で預かった消費税から差し引いて納税できる制度。
インボイス制度導入の背景と経緯
複数税率の管理が必要になった
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2016年の税制改正大綱で初めて方針が示され、 2019年の消費税率10%引き上げと軽減税率8%の導入を契機に具体化 されました。
複数税率のもとでは、取引ごとの消費税額を正確に管理する必要が高まり、財務省と国税庁は税務の透明性向上と仕入税額控除の適正化を目的に制度導入を決定。
制度設計では、適格請求書に税率・税額を明記することで、税務処理の正確性と効率性を向上させる狙いがありました。
2023年10月に制度が正式施行
インボイス制度の施行に向けて、 2021年から適格請求書発行事業者の登録申請が始まり 、各事業者に制度の周知やシステム対応が進められてきました。
そして2023年10月1日、制度が正式に施行され、課税事業者には適格請求書の発行と保存が義務付けられました。
導入前には、中小事業者の負担増や電子化対応への懸念から反対意見もありましたが、説明会や補助金などの支援策により円滑な移行が図られています。
2026年9月まで2割特例の経過措置あり
インボイス制度開始に伴い、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者を支援する「2割特例」が設けられています。
2023年10月から2026年9月までは、免税事業者との取引でも仕入税額の80%まで控除可能 です。その後、2026年10月から2029年9月までは控除率が50%に縮小されます。
この経過措置は、免税事業者との取引が急減しないよう配慮されたもので、事業者は2029年9月までに対応方針を検討する必要があります。

インボイス制度導入で何が変わるのか
区分請求書から適格請求書に切り替わる
インボイス制度の導入により、 仕入税額控除に必要な請求書は、従来の「区分請求書」から「適格請求書」へと変更 されます。
適格請求書(インボイス)とは、税率や消費税額などの情報が明記された請求書のことで、仕入税額控除を受ける際には欠かせません。
適格請求書発行事業者である売り手は取引の際、買い手に対してこの適格請求書を必ず発行しなければなりません。
| 比較項目 | 区分記載請求書(旧制度) | 適格請求書(インボイス) |
|---|---|---|
| 発行できる 事業者 |
課税事業者・免税事業者 | 適格請求書発行事業者 (※課税事業者のみ) |
| 記載が必要な項目 | ・発行者の氏名または名称 ・取引年月日 ・取引内容(軽減税率対象品目の明示) ・税率ごとの合計額(税込または税抜) ・書類交付を受ける者の氏名または名称 |
区分記載請求書の項目に加え、 + 登録番号 + 適用税率 + 消費税額 (税率ごとに1回ずつ端数処理) |
| 消費税の仕入税額控除 | 基本的に控除可(~2023年9月) | インボイスがなければ控除不可 |

仕入税額控除の要件が厳しくなる
従来は「課税取引」であれば、買い手はすべての取引で仕入税額控除を受けることができました。
しかし インボイス制度の導入に伴い、売り手が発行した適格請求書を保存している取引のみが、仕入税額控除の対象 となります。
そのため、仕入れ時に適格請求書が発行されない場合、買い手は仕入税額控除が受けられず、売上時に受け取った消費税を全額支払わなければなりません。
インボイス制度導入後の納税額の計算
| 適格請求書が発行された場合 | 適格請求書"以外"の 請求書が発行された場合 |
|---|---|
| 納付する消費税額 =売上時に受け取った消費税額 - 仕入や経費にかかった消費税額 |
納付する消費税額 = 売上時に受け取った消費税額 |
| 計算例 売上時に受け取った消費税が10万円 仕入れや経費にかかった消費税が6万円の場合 |
|
| 納付税額 = 10万円 - 6万円 = 4万円 |
納付税額 = 10万円(仕入税額控除なし) |
インボイスなしでも帳簿保存だけで仕入税額控除が認められる取引
仕入税額控除を受けるには、基本的に帳簿と請求書を保存する必要があります。
ただし、 請求書の交付が難しい場合、帳簿だけの保存で控除が認められる特別な取引があります 。
- 公共交通機関の旅客運送(3万円未満)
- 入場券などの回収されるチケット類
- 古物営業者が、適格請求書を発行しない者から購入した古物
- 質屋が、適格請求書を発行しない者から取得した質物
- 宅地建物取引業者が、適格請求書を発行しない者から購入した建物
- 適格請求書を発行しない者から購入した再生資源や再生部品
- 自動販売機や自動サービス機で3万円未満の商品購入
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
- 従業員に支給する通常の出張旅費や通勤手当
インボイス制度が事業者に与える影響
課税事業者(売り手)は事務負担が増加する
インボイス制度の導入により、課税事業者は「適格請求書(インボイス)」の発行・保存が義務付けられました。
これに伴い、 税率や消費税額の正確な記載、請求書フォーマットの変更、会計システムの対応が必要となり、事務負担が増加 します。
さらに、取引先が免税事業者であれば買い手側の仕入税額控除が認められず、取引継続の見直しや価格交渉を迫られる可能性もあります。
免税事業者は課税転換を求められる
適格請求書を発行できない免税事業者は、取引先から「課税事業者への転換」を求められるケースが増加しています。
課税事業者になると、消費税の納税義務が生じるほか、帳簿作成や請求書対応などの事務作業も大幅に増えることに なります。
一方で、免税のままでいると「インボイスを発行できない事業者」として敬遠され、取引を失うリスクも否定できません。
ひどい・やばいと言われるのは実質的に「課税化を強いられる構造」だから
インボイス制度がひどい・やばいと言われるのは、実質的に免税事業者も課税事業者となることを余儀なくされる構造にあるからです。
免税事業者は取引を継続するために課税事業者へ移行せざるを得ず、消費税の納税義務が生じます。例えば、年商250万円の事業者であれば、約25万円の負担増になる計算です。
とはいえ、免税のままでいれば取引停止などのリスクがあり、小規模事業者にとっては事業継続に大きな壁となりかねません。
買い手も請求書確認などの事務負担が増える
買い手側の事業者も、仕入税額控除を受けるためには適格請求書の受領・保存が必須となります。
請求書に不備がないか、発行者が「適格請求書発行事業者」であるかを確認する作業が日常的に発生 し、経理部門の負担が増加します。
さらに、取引先に免税事業者が含まれる場合には、控除対象外の消費税の管理も必要です。
こうした背景から、制度対応として経理業務の見直しや、会計ソフトの導入・改修を進める企業が増えています。
会計ソフト選定をサポート!
【無料】お問い合わせはこちらインボイス制度の抜け道はある?
インボイス制度に抜け道はない
結論から言えば、インボイス制度には合法的な「抜け道」は存在しません。
免税事業者のままで取引を続けることは可能ですが、 仕入税額控除を受けられない買い手から敬遠される可能性があり、実質的に制度を回避することは困難 です。
また、制度を無視した取引や虚偽の申告は税務調査の対象となり、重い罰則を受けるリスクがあります。
ただし、事業規模に応じた負担軽減措置や、簡易課税制度などの支援策は用意されているため、自身の状況に応じて適切に制度を活用することが重要です。
インボイス制度の廃止の可能性は低い
インボイス制度の廃止を望む声はあるものの、 制度が撤回・廃止される可能性は現状では極めて低い と考えられます。
制度導入の目的は、消費税の適正な課税と納税を徹底し、不公平を是正することにあります。
特に免税事業者による“益税”を解消するという国の方針が背景にあるため、制度の根幹が覆されることは考えにくい状況です。
制度に対する不満や混乱が一部で起きているものの、今後は運用面での改善や支援策の拡充によって対応される可能性が高いでしょう。
インボイス制度に対応するメリット
経理業務の効率化とコスト削減
インボイス制度に対応することで、経理業務の効率化とコスト削減が期待できます。
特に、 電子インボイス対応の会計ツールを導入すれば、税率別の自動計算や仕訳処理が簡素化され、人的リソースの削減やミス防止に つながります。
中小企業にとっては、限られた人員でもスムーズに税務処理が行える体制を構築できる点が大きなメリットです。
取引先の拡大が期待できる
適格請求書の発行事業者になることで、仕入税額控除を求める企業から選ばれやすくなり、取引先の拡大が期待できます。
インボイス制度施行後、 多くの企業が適格請求書を発行できる取引先を優先するようになるため、課税事業者であることが一種の「信頼の証」として作用 するのです。
免税事業者のままでは商談や新規契約のチャンスを逃す可能性もあります。あらかじめ営業先候補を整理し、制度を商機と捉える姿勢が重要です。
消費税額を正確に計算できる
インボイス制度では、税率や消費税額を明記した「適格請求書」により税区分が明確になり、申告ミスを防げます。
従来の請求書では混在しがちだった 税率計算も、適格請求書なら自動化しやすくなり、税理士や会計担当者の負担を軽減することが可能 です。
さらに、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかのチェックが制度化されているため、不適切な取引による税務リスクの回避にも役立ちます。
インボイス制度対応のための準備とポイント
課税事業者(売り手)の対応
適格請求書発行事業者への登録
課税事業者は、 売り手として「適格請求書」を発行できるよう、必ず「適格請求書発行事業者」に登録 しましょう。
申請方法は、「e-Taxによる電子申請」または「納税地の所轄税務署へ書類を提出(郵送可)」のいずれかを選べます。
経理・会計システムの対応確認
現在 利用中の経理システムや会計ツールがインボイス制度に対応しているか、必ず確認 してください。
インボイス制度では、取引ごとに課税取引かどうかの仕分けや、適格請求書の保存が義務付けられています。
特にパッケージ型会計ソフトや独自設計のシステムを利用している場合は、将来の制度変更にも柔軟に対応できるよう、この機会にクラウド化を検討することをおすすめします。
免税事業者の対応
適格請求書発行事業者登録の検討
免税事業者は、「適格請求書発行事業者」への登録を検討しましょう。
課税事業者へ 転換する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者登録申請書」の提出が必要 です。
また、課税転換に伴い、納付額の計算や申請などの業務が発生するため、事前にノウハウの構築やリソースの確保を進めておくことが重要です。
取引先との協議
課税事業者と取引がある場合は、取引の継続や価格について事前に十分に話し合っておきましょう。
特に価格については、 「仕入税額控除ができない分の消費税分を値引いてほしい」といった交渉が発生する可能性 があります。
場合によっては取引先を失うリスクもあるため、相手の要望をしっかりと聞きながら、双方の意見を丁寧にすり合わせることが重要です。
買い手側の対応
社内研修・周知徹底
買い手側の事業者は、新制度への対応について社内研修を実施しましょう。
- 受け取った適格請求書を必ず保存すること
- 請求書等を受領した際は、適格請求書発行事業者の登録番号の有無を確認すること
- 経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要であること
仕入先の登録状況確認と対応
仕入先が免税事業者の場合は、インボイス発行事業者となる意向を事前に確認しておきましょう。
相手方が課税事業者へ転換しない場合、 仕入税額控除が受けられなくなるため、取引の継続や仕入価格の見直しも検討が必要 です。
また、仕入先がインボイス発行事業者になる場合は、請求書の様式や受領方法について認識を共有しておくことをおすすめします。
インボイス制度に関するよくある質問
A
免税事業者の取引先減少により、一部の個人事業主で廃業リスクが高まっているケースはあります。
A
制度導入により仕入税額控除の適正化が進み、税収の漏れを防げるため、税収増加が見込まれています。
A
適格請求書発行事業者となり正確な税務処理ができる事業者や、仕入税額控除を適用できる買い手側がメリットを得ます。
A
輸出インボイスは取引内容の明細書で、制度上のインボイスは消費税の適正申告に必要な「適格請求書」を指します。
まとめ
インボイス制度は、消費税の正確な管理と税務の透明性向上を目的に2023年10月に施行されました。
適格請求書の発行・保存が義務化され、不正防止と適正な仕入税額控除がより確実になります。特に小規模事業者向けの経過措置が2026年まで設けられており、制度移行をスムーズに進められます。
しかし、制度対応には請求書管理や税額計算の複雑化が避けられず、業務負担の増加が課題です。そんな時こそ、インボイス対応の会計ソフト導入が効果的な解決策となります。
会計ソフト選びや導入に不安があれば、ぜひWiz cloudにご相談ください。専門スタッフが最適なプランをご提案し、安心して制度対応できるようサポートいたします。
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!