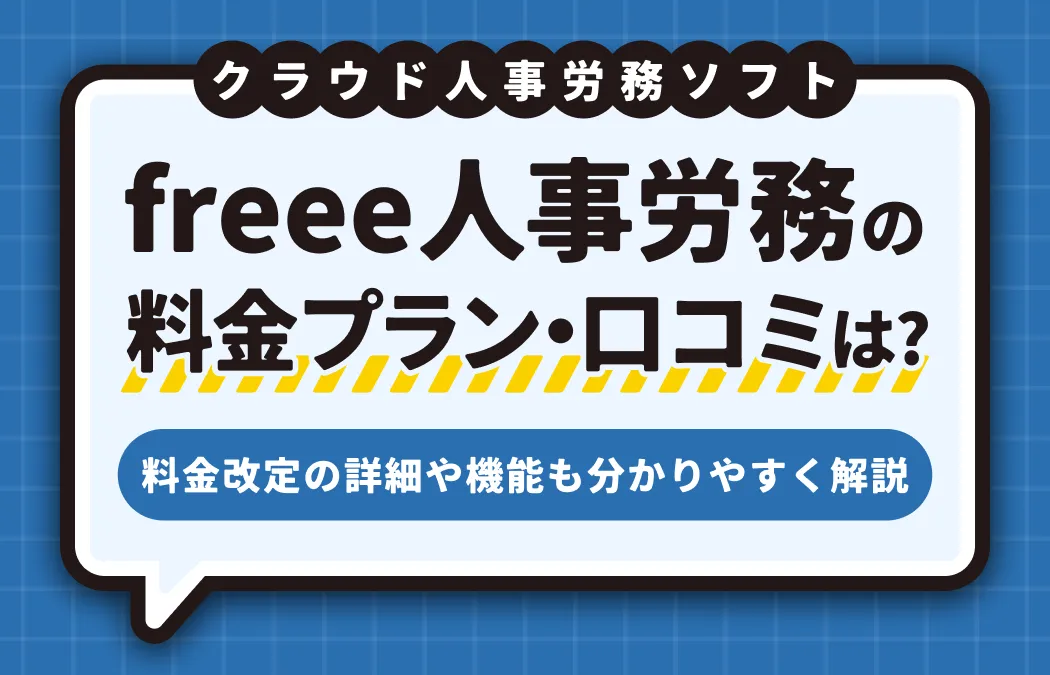「簡易課税ならインボイスは発行しなくていい?」
「2割特例と比べて、どっちが得なの?」
簡易課税制度とは、仕入税額控除を簡略化できる制度で、インボイス制度の導入後も引き続き利用可能です。
ただし、「2割特例との違い」「どちらが有利か」「計算方法は変わるのか」など、選択に迷うケースも少なくありません。
本記事では、インボイス制度と簡易課税の関係性や注意点、2割特例との違い、損をしない選び方のポイントをわかりやすく解説。
税負担が気になる中小企業・個人事業主の方、簡易課税を検討・利用中の方はぜひご覧ください。
※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。
目次
簡易課税制度とは?
簡易課税制度とは「納税事務負担を軽減する制度」
簡易課税制度は、 消費税の計算や申告手続きを大幅に簡素化することを目的とした制度 です。
中小企業の事務負担や費用負担を軽減するために設けられており、一定の要件を満たす課税事業者は任意で制度を適用することが可能です。
実際の仕入額を集計して控除する手間が省け、あらかじめ業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って簡易的に消費税の納税額を計算できます。
簡易課税と本則課税の違いは計算方法
- 本則課税:課税売上に係る消費税額 - 課税仕入に係る消費税額
- 簡易課税:課税売上に係る消費税額 ×(1 - みなし仕入率)
簡易課税と本則課税の最も大きな違いは、納めるべき消費税の算出方法にあります。
本則課税では、売上に係る税額から実際の仕入れに係る税額を差し引いた額が納税額 となります。
一方、簡易課税では、消費税の課税売上の合計金額に業種別の「みなし仕入率」を掛けて税額を計算します。みなし仕入れ率は「仕入税額控除を簡略化するための業種別割合」
みなし仕入率とは、実際の仕入額に代えて適用する、 業種ごとの定率(割合) のことです。
みなし仕入率は業種の特性に基づいて設定されており、第1種事業(卸売業)から第6種事業(不動産業)までの6区分があります。
商品をたくさん仕入れて販売する卸売業などは90%、逆に仕入れが少ない不動産業などは40%といったように、実態に即した割合が適用されます。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業の例 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業:仕入れた商品をそのまま他の事業者に売る事業(例:問屋) |
| 第2種事業 | 80% | 小売業:仕入れた商品をそのまま一般消費者などに販売する事業農業・林業・漁業(※飲食料品を扱う場合) |
| 第3種事業 | 70% | 製造業、建設業、鉱業、電気・ガス・水道業などのモノづくり・インフラ関連の事業※飲食料品を扱わない農業なども含む |
| 第4種事業 | 60% | 飲食店業など、他の事業区分に当てはまらない事業※加工賃などサービス提供も含む |
| 第5種事業 | 50% | 運送業、通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食店を除く) |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業(例:不動産の売買・賃貸) |
簡易課税制度の適用条件と申請提出期限
課税売上高が5,000万円以下であること
簡易課税制度を適用するための最も重要な条件は、課税売上高が5,000万円以下であることです。
判定基準となるのは、 個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度における課税売上高 となります。
例えば、令和4年の課税売上高が5,000万円以下であれば、令和6年から簡易課税制度での消費税申告が可能となります。
この基準期間の課税売上高は、消費税を含まない税抜金額で判定するため、売上台帳などの記録は税込・税抜を明確に分けておくことが重要です。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出
簡易課税制度を適用するには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
届出書には事業者の基本情報、適用を開始したい課税期間、主たる事業の種類などを記載 します。
一度簡易課税制度を適用すると、2年間は継続が義務づけられるため、提出前に自社にとってのメリットを慎重に検討しましょう。
簡易課税の届出は適用期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択届出書の 提出期限は、原則として「適用したい課税期間の初日の前日まで」 と定められています。
例えば、令和5年4月1日から始まる課税期間に適用したい場合、提出期限は令和5年3月31日までとなります。
提出期限を過ぎてしまうと、その課税期間からの適用はできず、次の課税期間からの適用となってしまうため注意が必要です。
簡易課税の届出の流れ
| 1.届出書を取得 | 2.必要事項を記入 | 3.提出期限を確認 | 4.提出方法 | 5.確認と保管 |
|---|---|---|---|---|
| 税務署の窓口または国税庁のウェブサイトから「消費税簡易課税制度選択届出書」を入手 | 届出書に以下の情報を記入:
|
■原則:適用を受けたい課税期間の開始前までに提出 ■新設法人:設立初年度の末日まで(特例あり) ■提出が遅れると適用が翌々期になる場合があるので注意 |
■税務署窓口:直接持参または郵送 ■e-Tax:電子申告システムを利用 ■提出先は事業所の所在地を管轄する税務署 |
■提出後、税務署から受付確認の連絡は通常ないため、提出した控え(コピーや送信データ)を保管 ■受理されると、指定した課税期間から簡易課税制度が適用開始 |
簡易課税制度とインボイス制度の関係
インボイス制度とは「消費税のやりとりを透明化する制度」
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の適正な徴収と仕入税額控除の透明化を目的に2023年10月に導入されました。
課税事業者は、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」として、法定項目を記載したインボイスを発行・保存 する義務があります。
これにより、売り手・買い手ともに正確な消費税処理が求められ、従来よりも厳格な帳簿管理が必要となります。

簡易課税制度とインボイス制度は無関係ではない
簡易課税制度は、小規模事業者の税額計算を簡素化する制度であり、仕入税額控除の計算にインボイスの保存は不要とされています。
しかし、 取引先が仕入税額控除を行うにはインボイスが必要なため、簡易課税事業者でもインボイス発行事業者の登録を求められる 場面が増えています。
つまり、両制度は実務上密接に関係しており、無関係とは言えません。
インボイス制度導入による間接的な影響と注意点
簡易課税制度を選択している事業者にも、インボイス制度は少なからず影響を与えています。
簡易課税制度の利便性を活かすには、 制度間の関係を理解し、取引先との調整を怠らないことが重要 です。
- 取引先からインボイス発行を求められる場合がある
- 複数事業の場合、経理作業が複雑化する可能性
- 一度選択すると2年間は本則課税に戻せない
取引先からインボイス発行を求められる場合がある
簡易課税事業者でも、取引先が仕入税額控除を行うにはインボイスが必要です。
そのため、「インボイスを発行できないなら他社に乗り換える」といった要望や交渉を受ける可能性もあります。
信頼関係や取引継続の観点から、取引先の要望に応じて適格請求書発行事業者への登録を検討するケースが増えています。
複数事業の場合、経理作業が複雑化する可能性
簡易課税制度では事業ごとに異なるみなし仕入率を用いるため、複数の業種を運営している場合は、売上の内訳を正確に把握しなければなりません。
そこにインボイス制度の管理が加わることで、帳簿記載や証憑管理がさらに複雑になります。
正確な処理を行うためには、制度への理解と会計ツールの整備が不可欠です。
一度選択すると2年間は本則課税に戻せない
簡易課税制度を一度選択すると、原則として2年間は変更できません。
また、簡易課税のままでインボイス発行事業者として登録しない場合、取引先が仕入税額控除を受けられず、取引の継続や請求書発行で支障が出ることがあります。
さらに、インボイス発行に伴う事務負担が増えるため、将来的に本則課税への移行を検討せざるを得ない場合もあります。
制度を選択する際は、売上規模や仕入内容、取引先の要望などを踏まえ、自社にとって最も合理的な方法を見極めることが重要です。
簡易課税制度を適用するメリット
インボイスの保存が不要で事務負担が軽減される
簡易課税制度を適用すれば、 仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)を保存する義務がなくなります 。
これにより、請求書の収集・管理や税額の突合といった煩雑な作業が不要となり、経理業務の負担が大幅に軽減されます。
特に小規模事業者や人手が限られる企業にとっては、インボイス対応にかかる事務コストを削減できる点が大きなメリットです。
みなし仕入率が高い業種は納税額を抑えられる
簡易課税制度では、実際の仕入額ではなく「みなし仕入率」に基づいて仕入税額控除を計算するため、 業種によっては納税額の削減が可能 です。
例えば、サービス業(みなし仕入率50%)よりも卸売業(90%)の方が控除額が大きくなりやすく、節税効果が見込めます。
特に、仕入れが少ないビジネスモデルの場合は、簡易課税を選択することで納税額を抑えられる可能性があります。
簡易課税制度と2割特例の違いを比較
2割特例はインボイス制度の税負担を軽減する経過措置
2割特例とは、免税事業者であった小規模事業者がインボイス発行事業者として登録した場合に、 納税額を売上にかかる消費税の2割に抑えられる特例措置 です。
簡易課税制度を選択している場合でも、確定申告時に納税額が少ない方の制度を選択して適用できます。
適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日までで、事前の届出は不要です。

簡易課税と2割特例、どちらが得か
簡易課税と2割特例はどちらも事務負担を軽減しつつ納税額を抑える制度ですが、 得かどうかは事業の実態によります 。
実際の仕入率がみなし仕入率より高いなら2割特例
実際の仕入率(仕入額÷売上高)がみなし仕入率より高い場合、 第2~6種事業では、2割特例が簡易課税より納税額を抑えられることが多い です。
ただし、卸売業など仕入率が80%を超える業種では、実際の仕入税額を反映する原則課税※が最も有利になる場合があります。
そのため、どの制度が自分にとって一番有利かは、事前にシミュレーションして見極めることが大切です。
※原則課税:実際の売上と仕入れにかかる消費税をもとに正確に計算する方法。帳簿や請求書の管理が必要だが、仕入れが多い場合は納税額を抑えられることがある。
原則課税・簡易課税・2割特例のシミュレーション例
| 項目 | 簡易課税が有利な例 (サービス業、第5種) |
2割特例が有利な例 (飲食業、第4種) |
原則課税が有利な例 (卸売業、第1種) |
|---|---|---|---|
| 前提条件 | - 業種:卸売業 (第1種、みなし仕入率90%) - 課税売上高:990万円(税込) - 売上税額:90万円 - 実際の仕入率:40%(仕入税額:990万×40%×10/110=36万円) |
- 業種:サービス業 (第1種、みなし仕入率60%) - 課税売上高:990万円(税込) - 売上税額:90万円 - 実際の仕入率:50%(仕入税額:990万×50%×10/110=45万円) |
- 業種:卸売業 (第1種、みなし仕入率90%) - 課税売上高:990万円(税込) - 売上税額:90万円 - 実際の仕入率:95%(仕入税額:990万×95%×10/110=86.4万円) |
| 簡易課税 の納税額 |
90万円 × (1 - 90%) = 9万円 |
90万円 × (1 - 60%) = 36万円 |
90万円 × (1 - 90%) = 9万円 |
| 2割特例 の納税額 |
90万円 × 20% = 18万円 |
90万円 × 20% = 18万円 |
90万円 × 20% = 18万円 |
| 原則課税 の納税額 |
90万円 - 36万円 = 54万円 |
90万円 - 45万円 = 45万円 |
90万円 - 86.4万円 = 3.6万円 |
| 有利な理由 | みなし仕入率(90%)が実際の仕入率(40%)より高く、控除額が過大に計算される | 実際の仕入率50%がみなし仕入率50%より低く、2割特例(20%)が有利 | 実際の仕入率95%がみなし仕入率90%を超え、実額控除で最小 |
| 事務負担 | 中:事業区分の判定が必要。インボイス保存は必要だが集計不要 | 低:事業区分不要、売上税額の20%計算のみ。インボイス保存必要 | 高:インボイス保存・仕入税額集計が必要 |
| 適用条件 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下。事前届出必要(2年継続義務) | 基準期間の課税売上高1,000万円以下、インボイス登録で課税事業者に。2026年9月30日まで | 課税事業者であれば誰でも適用可 |
| 将来リスク | 売上高5,000万円超で適用不可。継続義務で柔軟性低い | 2026年9月30日終了後、納税額増加(例:18万円→45万円) | 事務負担が継続。還付可能で柔軟性高い |
| 適用ケース | 原価率が低い卸売業や、経費が少ない事業(例:小規模卸売、仲介業) | 仕入や経費が少ない個人事業主(例:フリーランス、飲食業、不動産業)。2023年10月1日~2026年9月30日にインボイス登録した小規模事業者に限定 | 高額な設備投資や外注費が多い事業者(例:ITサービス、コンサルティング) |
事務負担は2割特例が最も軽い
2割特例は、インボイスを保存する必要があるものの、 実際の仕入額や請求書を集計する必要がなく、売上にかかる消費税の2割を納税するだけ で済みます。
仕入税額控除の計算も不要で、簡易課税よりもさらに手続きがシンプルなので、経理リソースに乏しい小規模事業者にとって最も手間の少ない選択肢といえます。
2割特例終了後は簡易課税/本則課税を申請できる
2割特例は2026年9月までの時限措置です。 特例終了後は、通常の本則課税または簡易課税制度のいずれかを選択して申請 する必要があります。
簡易課税を希望する場合は、事前に届出が必要で、2年間は継続適用となるため、制度の違いや納税額の変化をよく理解したうえで準備を進めることが重要です。
簡易課税・インボイス制度対応におすすめの会計ソフト
会計ソフト選びで重要なポイントは「制度対応」と「操作性」
簡易課税制度やインボイス制度に対応するためには、対応機能が備わった会計ソフトを選ぶことが必須です。
消費税の区分処理や仕入税額控除の判定など、 制度対応に加えて「誰でも使いやすい操作性」も重視したいポイント になります。
専門知識がなくても適切に処理できるか、サポート体制が充実しているかをチェックしましょう。
簡易課税やインボイス制度対応のクラウド会計ソフト3選
簡易課税やインボイス制度に対応したクラウド会計ソフトとしては、 「freee会計」「マネーフォワード クラウド会計」「弥生会計Next」の3つ が特におすすめです。
どれも適格請求書の発行や消費税の自動区分機能を備え、簡易課税の計算もスムーズに対応できます。
| 項目 | freee会計 | マネーフォワード クラウド会計 |
|
|---|---|---|---|
| 簡易課税対応 | ◎ 簡易課税の申告書作成をサポート。質問形式で事業区分をガイド、自動計算 | ◎ 簡易課税の申告書作成をサポート。事業区分ごとの売上割合を自動集計 | ○ 簡易課税申告書作成をサポート。事業区分設定は可能だが、詳細な自動化は今後強化予定 |
| インボイス 制度対応 |
◎ インボイス登録番号の管理、適格請求書の発行・保存、仕入税額控除の計算 | ◎ インボイス対応の請求書作成、自動仕訳、電子帳簿保存法対応 | ◎ インボイス対応請求書作成・保存、仕入税額控除計算、電子帳簿保存法対応。証憑アップロード時の自動データ連携強化 |
| 自動仕訳機能 | ◎ AIによる自動仕訳(銀行・カード連携)。簿記知識不要で初心者向け | ◎ AIが勘定科目を提案(2,300以上の金融機関連携)。学習で精度向上 | ○ AIによる自動仕訳対応。「かんたん開始仕訳」(特許登録)で初心者向けに創立費・開業費を簡易入力 |
| 事業区分の 管理 |
○ 簡易課税の事業区分を質問形式で設定可能だが、複数事業の計算はやや複雑 | ◎ 複数事業の売上割合を自動集計。事業区分の管理が直感的 | ○ 部門管理機能で店舗・支店ごとの仕訳チェック可能。複数事業の自動集計は発展途上 |
| 料金 ※年額(税込) 個人事業主 |
スターター:1万2,936円 消費税申告はスタンダード (2万6,136円~)以上が必要 |
パーソナル:1万6,896円~ パーソナルプラス:3万9,336円~(消費税申告対応) |
個人事業主向けは ・やよいの青色申告オンライン ・Misoca(請求書作成ソフト) |
| 料金 ※年額(税込) 法人 |
ひとり法人:3万9,336円~ スターター:7万2,336円~ 他プランあり |
スモールビジネス:3万9,336円~ ビジネス:6万5,736円~ |
エントリー:3万8,280円 ベーシック:5万5,440円 ベーシックプラス:9万2,400円 |
| サポート体制 | ◎ 電話・チャット・メール(スタンダード以上)。初心者向けガイド充実 | ◎ チャット・メール中心。電話サポートは上位プラン。マニュアル豊富 | ◎ 電話・メールサポート(導入相談窓口あり)。先行体験でサポート充実 |
| 連携サービス | ◎ POSレジ、ECサイト、CRMなど多彩(freeeアプリストア) | ◎ 2,300以上の金融機関・サービス連携(業界最多) | ◎ 2,500以上の金融機関と連携。POSレジやEC購買サービス連携も |
| 事務負担 簡易課税向け |
◎ 事業区分設定が簡単で、インボイス保存も自動化可能 | ◎ 複数事業の管理が効率的。インボイス対応の自動仕訳で負担軽減 | ○ インボイス管理や「かんたん開始仕訳」で負担軽減。複数事業の自動化は他社にやや劣る |
| おすすめの 事業者 |
簿記知識が少なく、簡易課税やインボイス対応を簡単に済ませたい個人事業主 | 複数事業や金融機関連携が多く、効率的な管理を求める事業者 | 弥生シリーズの既存ユーザーや、法人でインボイス対応を重視する事業者 |
freee会計
【無料】お問い合わせはこちらマネーフォワード クラウド会計
【無料】お問い合わせはこちら
簡易課税制度に関するよくある質問
A
インボイス制度の施行後も、簡易課税制度は廃止されません。また、内容や要件に変更などもありません。
A
簡易課税制度を利用している場合、仕入先から発行されたインボイスの保存は不要です。ただし、自らが売り手として取引先にインボイスを発行した場合は、その写しを保存する必要があります。
まとめ
簡易課税制度は、消費税の計算や申告を簡単にできる一方で、事業内容や取引先の状況によってはかえって不利になる場合もあります。
特にインボイス制度が始まって以降、免税事業者との取引や仕入税額控除の取り扱いなど、従来よりも検討すべき点が増えています。
制度の概要を理解できても、「自社の業種では簡易課税と本則、どちらを選ぶべきか?」「今使っている会計ソフトでインボイス制度に対応できるのか?」など、実務に即した判断に迷う場面も少なくありません。
こうしたお悩みは、対応している会計ソフトによっても選択肢や機能が変わってくるため、早めの確認が安心です。簡易課税制度やインボイス対応について、会計ソフトの導入・見直しを検討している方は、ぜひWiz Cloudまでお気軽にお問い合わせください。
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!