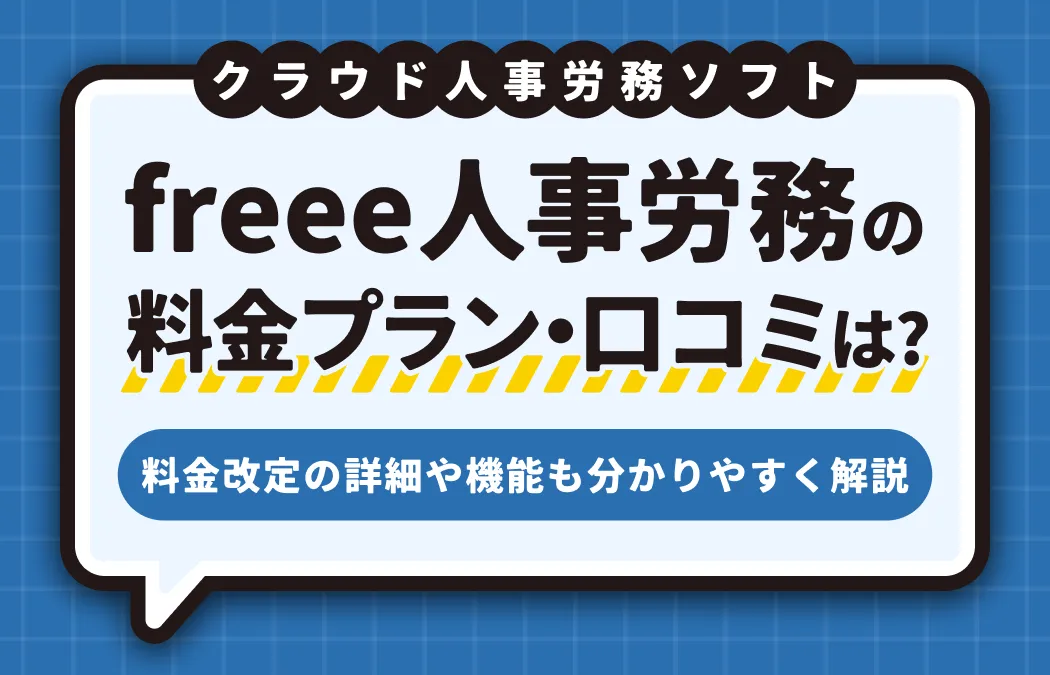「個人事業主向けや無料の会計ソフトはある?」
「導入に活用できる補助金は?」
インボイス制度の開始により、会計ソフトや請求書発行システムの見直しが求められています。業務の効率化や正確な税対応には、制度対応済みのツール導入が不可欠です。
とはいえ、「無料で使えるおすすめのソフトは?」「システム導入で何が変わる?」「補助金の対象になるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、インボイス対応が必要な業務範囲やシステム選定のポイント、導入時に活用できる補助金情報までを、わかりやすく解説します。
インボイス対応の会計ソフト選定をサポート!
【無料】お問い合わせはこちら ※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。目次
インボイス制度とは「消費税のやりとりを透明化する制度」
インボイス制度とは、 買い手(仕入れ側)が消費税の「仕入税額控除」を受けるにあたって、売り手(請求側)から発行される「適格請求書(インボイス)」が必要になる制度です。
2023年10月に導入され、事業者間における消費税のやり取りに透明性が求められるようになりました。インボイスを発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみです。
売り手・買い手双方にとって、請求書の形式や取引先の登録状況の確認が重要になっています。


【図解】インボイス制度の目的とは?背景・影響・対応まで徹底解説
制度の目的や経過措置の内容、対応に伴う業務負担とその解決策についてわかりやすく解説。個人事業主やフリーランスの方も必見の内容です。
詳しくはこちらインボイス制度で事業者が対応すべきポイント
課税事業者(売り手)が対応すべきこと
- 「適格請求書発行事業者」への登録
- 記載要件を満たしたインボイスの準備
- 請求書の写しを保存する体制の整備
「適格請求書発行事業者」への登録
売り手がインボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」への登録が必須です。申請方法は、次のいずれかです。
- e-Taxを利用した電子申請
- 納税地を管轄する税務署への書類提出(郵送も可)
記載要件を満たしたインボイスの準備
登録が完了したら、記載要件を満たすインボイス(請求書)のフォーマットを準備しましょう。新たに必要とされる主な記載項目は、以下の3点です。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
請求書の写しを保存する体制の整備
インボイス発行事業者には、発行したインボイスの写しを7年間保存する義務があります。
インボイスを電子データで保存する場合は、「電子帳簿保存法」の要件を満たすシステムの導入が必要です。

課税事業者(買い手)が対応すべきこと
- 取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する
- 請求書等の保存・管理体制を整える
取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する
まず、取引先が「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」として登録されているかを確認しましょう。
インボイスが発行される取引については、どの証憑書類が「適格請求書」に該当するのか、仕入先とあらかじめ認識を統一しておくことが重要です。
請求書等の保存・管理体制を整える
買い手側にも、受領したインボイスを7年間保存する義務があります。
紙媒体で保存するのか、電子データとして管理するのかを事前に決め、次のような業務フローを整備しておくと安心です。
- インボイスの受領方法
- データ化の手順(スキャナ保存・PDF化など)
- 会計処理への連携
- 保存方法(電子帳簿保存法への対応など
また、経理処理の効率化のため、請求書を登録番号の有無で区分して管理する体制を整えておくことが望ましいです。
免税事業者は「適格請求書発行事業者になるか」判断が必要
インボイス制度施行後、 免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外となるため、課税事業者のクライアントが減少したり、値下げ交渉を受けたりする 可能性があります。
このようなリスクを回避したい場合は、課税事業者への転換と適格請求書発行事業者への登録申請を検討しましょう。
なお、課税事業者へ転換する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者登録申請書」の提出が必要です。
インボイス制度で対応が求められるシステム
- 会計ソフト
- 請求書の発行システム
- 請求書の受領・保存システム
- 販売管理システム・受発注システム
- POSシステム
会計ソフト(消費税・仕入税額控除への対応)
インボイス制度では、適格請求書発行事業者からの請求書とそうでない請求書を区別して管理する必要があります。
そのため、 取引先ごとに税区分を自動切替できる会計ソフトが必須 です。
さらに、従来の割戻計算方式(※1)に加え、積上方式(※2)で消費税を算出できる機能があると、税額計算の正確さや利益の把握に役立ちます。
※1 割戻計算方式:税込み合計額から消費税を逆算する計算方法※2 積上方式:税抜き金額に税率を掛けて消費税を計算する方法

請求書の発行システム
請求書発行システムは、インボイス制度で求められる 「登録番号」や「適用税率」、「税率ごとの消費税額」などの新記載項目を満たした請求書を自動発行できることが重要 です。
制度対応が不十分なシステムを使うと手入力や修正作業が増え、ミスや業務負担が増大します。

請求書発行システムおすすめ20選|選び方・機能・費用を徹底比較
請求書発行システムの主要サービス20選を徹底分析して解説していくので、請求書発行システムの導入を検討している企業の方必見です。
詳しくはこちら請求書の受領・保存システム
買い手側は受け取ったインボイスを7年間保存する義務があります。
請求書の受領・保存システムを導入すれば、 受領した請求書を電子データ化し、自動で分類・保管することが可能 です。
これにより、書類管理の手間が大幅に軽減され、税務調査時の対応もスムーズになります。
販売管理システム・受発注システム
販売管理システムは、 課税事業者と免税事業者の取引を明確に区分できる機能が必要 です。
区分ができないと仕入税額控除の計算時に書類の分類・管理が煩雑になり、ミスや業務負担が増します。
既存システムを使う場合は、インボイス制度の請求書記載ルールに対応しているか事前に確認し、必要ならアップデートや切替を検討しましょう。

POSシステム(レジ連携・インボイス対応)
POSシステムはインボイスの必要事項を記載したレシートを発行できることが求められます。
特に 軽減税率対応(複数税率対応)は必須で、商品ごとの税率を正確に把握し表示できるかがポイント です。
これにより買い手が正しい税額控除を行え、売り手も正確な売上管理が可能です。レジのインボイス対応は今後の取引継続に直結します。

インボイス制度導入でレジの買い替えは必須?補助金やおすすめ対応レジも紹介!
インボイス制度に対応するために必要なレジやレシートの役割を解説し、インボイス登録の是非とともにおすすめの対応レジ7選をご紹介します。
詳しくはこちらインボイス対応システムの必要性
インボイス対応の効率化にはシステム導入が有効
インボイス制度への対応では、 請求書の発行・受領・保存にかかる業務が複雑化 します。
こうした事務処理を効率化するためには、インボイス制度に対応した会計ソフトや請求書管理システムの導入が効果的です。
自動仕訳やデータ連携によりミスや手間を削減でき、制度に沿った正確な対応が可能になります。とくに取引件数が多い事業者にとって、システム導入は必須といえるでしょう。
インボイス対応システム導入のメリット
- 請求書業務のペーパーレス化により印刷・郵送コストを削減
- 会計ソフトや販売管理システムとの連携で経理業務を効率化
- 自動仕訳や税区分の自動処理でミスの削減・作業時間の短縮
- 電子データでの保存により、紛失リスクを大幅に低減
- 過去の請求書検索が簡単になり、管理業務の手間が軽減
- アクセス権や編集履歴の管理によって内部統制が強化される
- インボイス制度に対応した正確な請求書の自動発行が可能
インボイス対応システム導入の 最大のメリットは、経理業務の効率化と正確な税務処理の両立 です。
インボイス制度では、仕入税額控除の要件を満たすために適格請求書の発行・受領・保存が必須となります。
対応システムを導入すれば、請求書の自動発行・保存・仕訳連携などが可能になり、手作業によるミスや確認作業の手間を大幅に削減できます。
インボイス対応システム導入のデメリット・注意点
- 初期費用や月額料金などの導入・運用コストがかかる
- 操作が複雑なシステムだと、かえって業務効率が下がる可能性がある
- 紙の請求書を希望する取引先には別対応が必要となる
- 既存の業務フローや他システムとの連携に手間がかかる場合がある
- 従業員への操作教育や運用ルール整備に時間がかかる
- クラウド型の場合、セキュリティや情報漏洩リスクへの対策が必要
- システム依存によるトラブル発生時の業務停止リスクがある
インボイス対応システム導入の 最大のデメリットは、初期導入費用や運用コストがかかる点 です。
システムの購入やサービスの契約には一定のコストが発生し、操作研修や運用体制の整備も必要なので、特に、小規模事業者にとっては導入負担が重く、費用対効果が見合わない場合もあります。
また、取引先によっては紙での請求を求められることもあり、システム化との両立が課題になるケースも少なくありません。
加えて、更新や仕様変更により継続的な対応が求められることもあるため注意が必要です。
インボイス対応システムが必要/不要な事業者
すべての事業者がインボイス対応システムを導入する必要はありません。
例えば、 免税事業者でありインボイスの発行義務がない場合や、取引件数が非常に少なく手作業でも対応可能な小規模事業者は、必ずしも導入の必要はない でしょう。
ただし、将来的に課税事業者となる予定がある場合や、取引先からインボイスの発行を求められる可能性がある場合は、早めの検討が望まれます。
| 必要な事業者 | 不要な事業者 |
|---|---|
|
|
【個人事業主向け】おすすめインボイス対応会計ソフト
freee会計(法人にもおすすめ)
freee会計は、freee株式会社が提供するクラウド型の会計ソフトで、主に個人事業主や中小企業の経理業務を効率化します。
例えば、 「売上はどれくらい?」「経費の内容は?」といったガイド付きの質問に答えるだけ で、青色申告決算書や法人税申告書の作成が可能です。
また、電子帳簿保存法に対応した電子証憑の保存機能や、インボイス制度に準拠した適格請求書の発行もサポートしており、法令対応も万全です。
| 個人事業主向けプラン | 法人向けプラン |
|---|---|
|
|
お気軽にお問い合わせください!
【無料】お問い合わせはこちら3分でわかる基本情報ガイド!
【無料】資料ダウンロード
マネーフォワード クラウド確定申告

「マネーフォワードクラウド確定申告」は、個人事業主向けのクラウド型確定申告ソフトです。
2024年度版では、 定額減税やマイナポータル連携による電子申告に対応し、各種控除証明書の自動取得・反映も可能 となりました。
税理士へのチャット相談や動画ガイドなどサポートも充実しているほか、青色申告・白色申告のどちらにも対応しているため、確定申告が初めての方でも安心です。
- パーソナルミニ:990円/月(税込)年契約
- パーソナル:1,408円/月(税込)年契約
- パーソナルプラス:3,278円/月(税込)年契約
やよいの白色申告/青色申告 オンライン

「やよいの白色申告/青色申告 オンライン」は、個人事業主向けのクラウド型会計ソフトです。
インボイス制度に対応した請求書作成や自動仕訳機能を備え、経理初心者でも簡単に確定申告 ができます。
| やよいの白色申告オンライン | やよいの青色申告オンライン |
|---|---|
|
|
やよいの白色申告オンライン
やよいの白色申告オンラインは、白色申告に特化したシンプルな設計で、収支内訳書の作成も簡単に行えます。
無料で使えるフリープランが用意されており、インボイス対応の請求書発行行(Misoca連携)にも対応。低コストで基本的な経理を行いたい個人事業主に最適です。
やよいの青色申告オンライン
やよいの青色申告オンラインは、青色申告に特化したクラウド型会計ソフトで、複式簿記や65万円の控除に対応しています。
自動仕訳や消費税申告機能も充実しており、確定申告を効率よく進めたい個人事業主におすすめです。
【法人向け】おすすめインボイス対応会計ソフト
マネーフォワードクラウド会計

マネーフォワード クラウド会計は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の会計ソフトです。
銀行やクレジットカード、電子マネーなどのサービスと連携して入出金明細を自動取得 し、AIが勘定科目を提案することで仕訳入力の時間を大幅に削減します。
また、請求管理、経費精算、給与計算、勤怠管理など、バックオフィス全体をカバーする機能があり、段階的な導入が可能です。
- スモールビジネスプラン:3,278円(税込)年契約の
- ビジネスプラン:5,478円(税込)年契約
- パーソナルプラン:1,408円~/月(税込)
- パーソナルプラスプラン:3,278円~(税込)契約
まずは無料で相談!
【無料】お問い合わせはこちら3分でさくっとご紹介!
【無料】資料ダウンロード弥生会計Next(2025年4月リリース)

弥生会計Nextとは、弥生株式会社が2025年4月に正式リリースした、法人向けのクラウド会計ソフト です。
会計だけでなく、請求書発行・経費精算・証憑管理といったバックオフィス業務を一元化 し、業務全体の効率化を実現します。
初期設定は質問に答えるだけ、仕訳もAIが自動提案するなど、会計初心者にもやさしい設計が特長です。
- エントリープラン:3万8,280円(税込)年契約
- ベーシックプラン:5万5,440円(税込)年契約
- ベーシックプラスプラン:9万2,400円(税込)年契約
勘定奉行クラウド

勘定奉行クラウドとは、株式会社オービックビジネスコンサルタントが提供する法人向けクラウド会計ソフトです。
金融機関データやExcelと連携し、AIによる自動仕訳や証憑管理で経理業務を効率化。改正電帳法やインボイス制度にも対応し、ペーパーレス化を実現します。
顧問税理士向けの専門家ライセンスが無償付属し、リアルタイムなデータ共有が可能に なるため、税務処理の精度向上や業務の効率化につながります。
- iEシステム:月額 7,750円~(小規模企業向け)
- iJシステム:月額 1万1,750円~(小規模企業向け)
- iAシステム:月額 1万9,500円~(中小企業向け)
- iBシステム:月額 2万3,500円~(中小企業向け)
- iSシステム:月額 2万8,000円~(中小企業向け)
- 要問い合わせ(中堅企業~グローバル企業)
インボイス対応の会計ソフトを選ぶポイント
適格請求書の発行・保存に完全対応しているか
会計ソフトを選ぶ際は、 適格請求書の発行・保存に対応しているかを最優先で確認 しましょう。
インボイス制度では、請求書に登録番号や税率ごとの消費税額など、法定の記載事項が必須です。また、発行・保存の両方を適切に管理できる機能も求められます。
帳票テンプレートが制度に準拠しているか、電子インボイスへの対応状況も併せてチェックすることが重要です。
仕入側・売上側の双方におけるインボイス管理が簡単か
インボイス制度は、 売上側だけでなく仕入側でも適格請求書の管理が必要となるため、両面に対応したソフトが理想 です。
例えば、仕入時に受け取った請求書が適格かどうかを自動判別したり、税率ごとに仕入税額控除を計算・記録したりする機能があると、経理作業の負担を大幅に軽減できます。
- 登録事業者かどうかを一目で判断できる仕入先管理
- インボイス番号や税率別集計の自動処理ができるか
- アップロードされた請求書データの自動読み取り(OCRやAI)対応
制度改正や電子帳簿保存法など将来の法対応への柔軟性
会計ソフトは 一度導入すると長期にわたり使うため、今後の法改正にも柔軟に対応できるかを見極めることが重要 です。
インボイス制度だけでなく、電子帳簿保存法や消費税率変更などが将来的に起こる可能性もあります。
自動アップデートやクラウド型であれば、新制度への対応もスムーズです。法令対応が迅速なベンダーを選ぶことで、安心して長く運用できます。
- ベンダーが頻繁に制度改正に追随するアップデートを行っているか
- 国税庁や公的機関との連携情報が豊富か(API連携・通知など)
- 補助金対象やクラウド対応など中小企業支援との親和性が高いか
インボイス対応ソフト導入の成功事例
- 導入企業:富士産業株式会社
- 導入した会計ソフト:freee会計
導入背景と決め手
- インボイス制度と電子帳簿保存法の対応を見据えて、制度施行の約1年前から準備を開始
- メインバンクからの紹介をきっかけに、クラウド会計ソフト「freee会計」を検討
- 転記の削減、ネットバンキングとの連携、属人化解消、BCP対策などの面で評価
- 導入時は銀行・ベンダーのサポートがあり、安心して移行できた
freee会計の導入効果
- 残業時間を3割削減。グループ3社の経理業務を6名で効率的に対応
- 経費精算がペーパーレス化され、営業担当者もスマホから申請可能に
- 会計事務所とのやり取りもクラウド上で完結し、郵送・FAXを廃止
- 部門別損益も可視化され、各部門長がリアルタイムでデータ確認可能に
インボイス制度対応
- freee会計の「取引先マスタ」機能により、登録番号や適格請求書の管理がスムーズに
- 制度施行後の混乱も、事前の社内説明やセミナー参加により最小限に抑えられた
- 従来の会計ソフトでは改修が必要だった機能も、freeeでは標準で対応
電子帳簿保存法対応
- 電子データは電子のまま保存。freeeのファイルボックス機能で基本要件に対応
- 外部アウトソースはセキュリティ面で不安があり、freee上での完結を選択
参考:「freee会計を入れていてよかった」複数の拠点をfreee会計でつなぎ業務効率化を達成│freee会計
freee会計について相談!
【無料】お問い合わせはこちら3分でわかる情報ガイド!
【無料】資料ダウンロードインボイス対応ソフト導入に活用できるIT導入補助金
IT導入補助金は、 中小企業や小規模事業者がインボイス対応のITツールを導入する際に活用できる支援制度 です。
会計ソフトや請求書作成ツールの導入費用の一部が補助され、業務効率化とインボイス制度への対応を同時に進められます。
申請には、対象ツールの選定や事業計画の提出が必要です。補助率は最大3/4で、補助額は数万円から数百万円まで幅広く設定されています。
IT導入補助金2025:最終の7次締切分は、2025年12月2日(火)17:00締切!

IT導入補助金とは?昨年との変更点や対象者、申請枠をわかりやすく解説
本記事では、2024年と2025年のIT導入補助金の違いを踏まえて、申請枠や補助額・補助率、スケジュールを徹底解説していきます!ト
詳しくはこちらインボイス対応ソフトに関するよくある質問
A
「やよいの白色申告オンライン」には、永年無料で利用できるプランがあります。また、以下のサービスには無料で利用できる期間が設定されています。
・やよいの青色申告オンライン:1年間
・freee会計:30日間
・弥生会計Next:最大3か月
・勘定奉行クラウド:30日間
A
インボイス制度下では、仕入金額と消費税額を、適格請求書に記載された内容に基づいて集計します。そのため、会計データを入力する際には、「税込または税抜の仕入金額」と「消費税額」の両方を入力する必要があります。
A
インボイス制度の導入に伴って発生した改修費用は、「修繕費」として取り扱われます。
まとめ
インボイス制度は、消費税の透明性を高めることを目的に導入された制度で、売り手・買い手の双方に新たな対応が求められます。
特に「適格請求書」の発行・保存には細かな要件があり、事務負担の増加は避けられません。
そのため、対応漏れを防ぎ、業務効率化を図るには、制度に準拠した会計ソフトや関連システムの導入が有効です。
インボイス対応の会計ソフトに関するご相談は、ぜひWizcloudまでお気軽にお問い合わせください。
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!