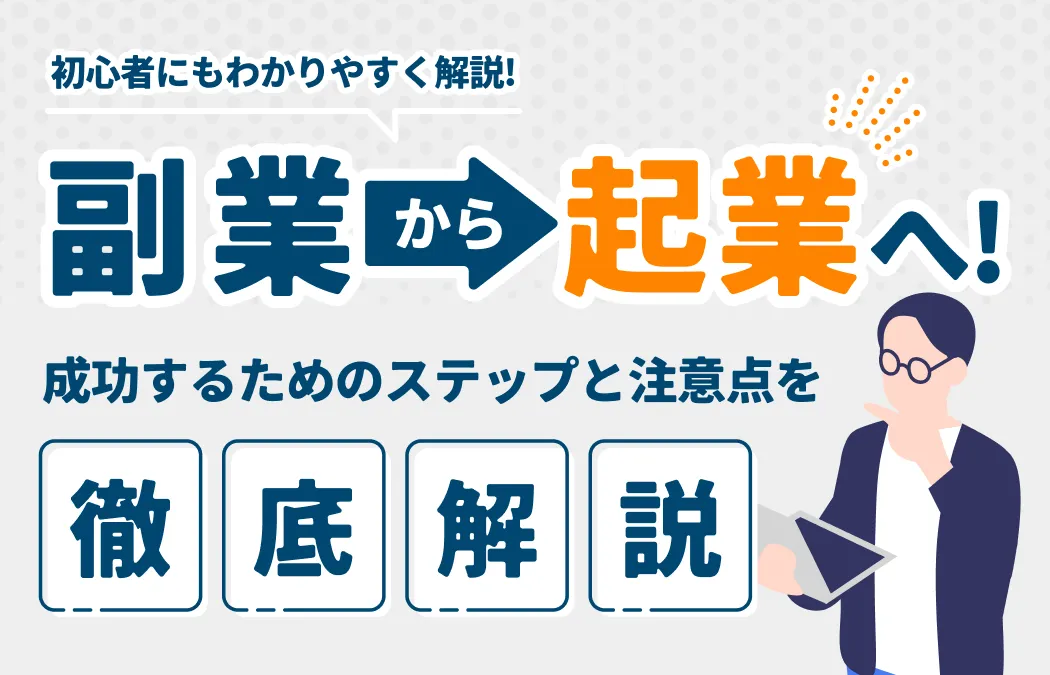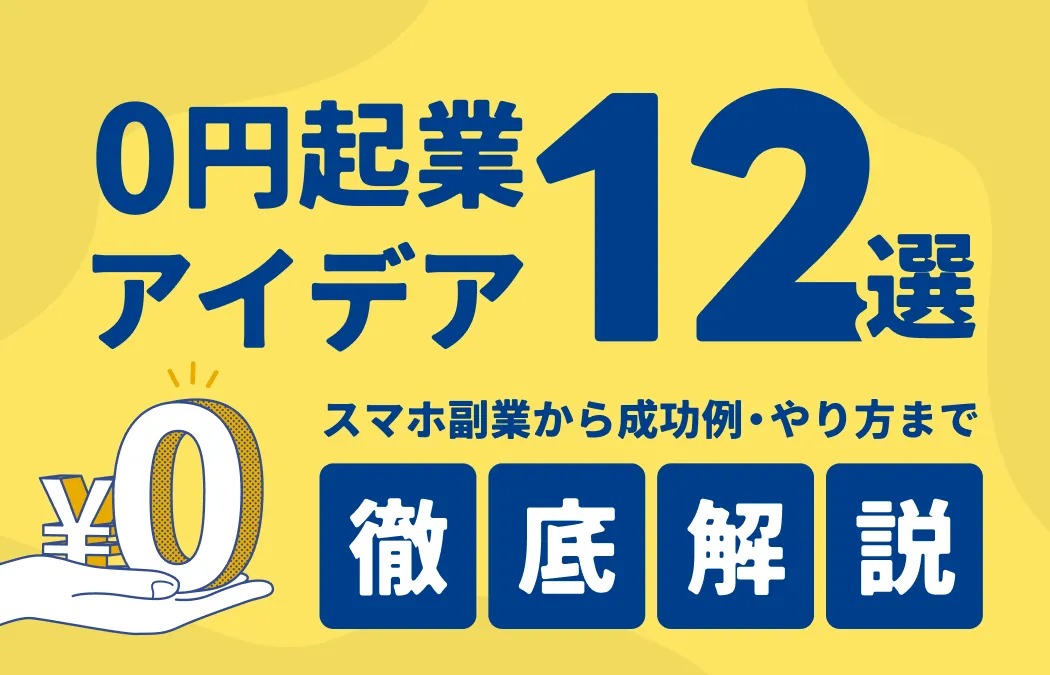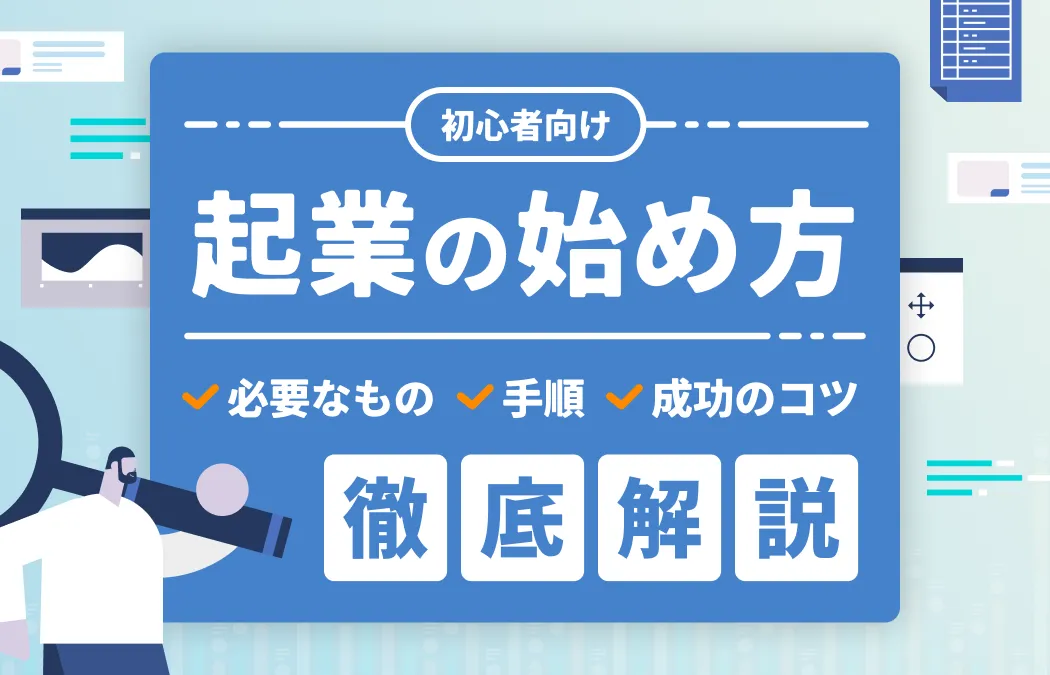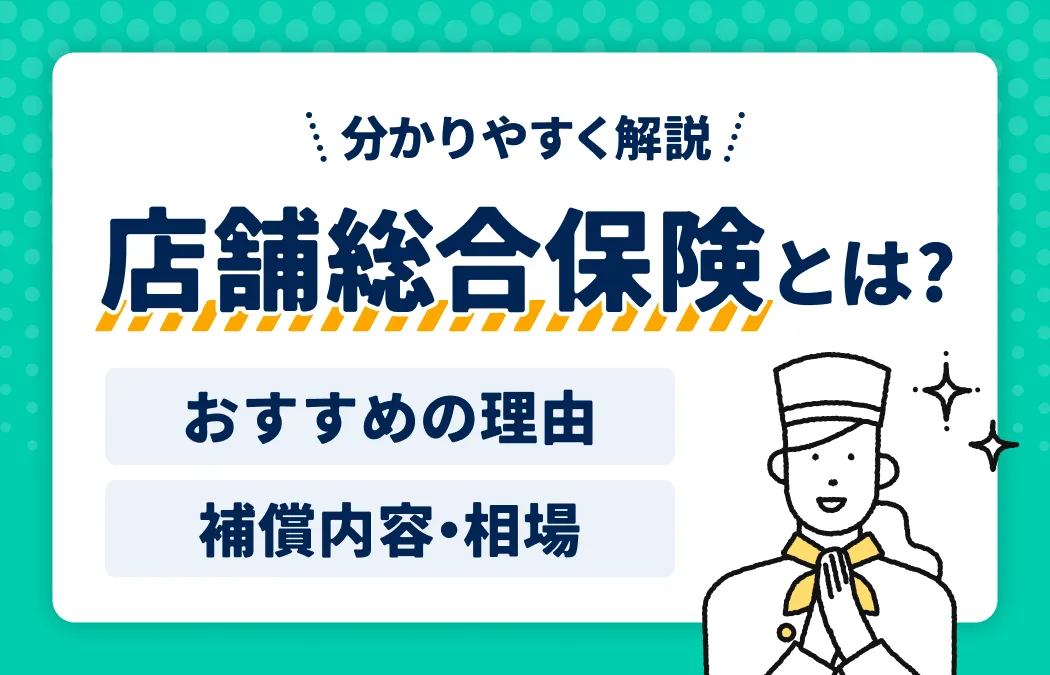「成功する秘訣や、失敗を避けるためのポイントは?」
「会社を辞めるタイミングやリスクが不安…」
近年、柔軟な働き方や収入の柱を増やしたいというニーズを背景に、副業をきっかけに起業する人が増えています。
しかし、「資金はいくら必要?」「よくある失敗や注意点は?」など、不安を抱える方も少なくありません。
本記事では、副業から起業するためのステップやメリット、注意点、資金調達方法、失敗を避けるためのポイントを網羅的に解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
副業から起業を目指す人が増えている背景
働き方改革・副業解禁の流れ
近年、副業から起業を目指す人が増えている大きな要因は「働き方改革」と「副業解禁の流れ」です。
大手企業でも副業を認める動きが広がり、本業に加えて小規模なビジネスを始める人が急増 しました。
これにより、従来は会社員として安定を求めるしかなかった層が、自分のスキルやアイデアを市場で試す環境を得ています。
特にリモートワークの普及で時間を有効に使えるようになったことが追い風となり、副業を通じて経験を積んだ後に独立するという流れが自然に生まれています。
収入の多様化・将来不安への備え
もう一つの背景は「収入の多様化」と「将来不安の回避」です。年金制度や雇用の安定性に対する不信感が高まる中、 一つの会社に依存せず収入源を複数持つことがリスクヘッジに なります。
副業から始めることで、大きなリスクを取らずに新しい収益の柱を作ることが可能です。
実際、フリーランスや個人事業主として小規模に活動しながら、需要が拡大したタイミングで法人化に踏み切るケースも多く見られます。
このように、副業は単なるお小遣い稼ぎにとどまらず、将来に備えた戦略的なキャリア形成の手段として注目されています。
副業から起業に進むメリットとデメリット
メリット
副業から起業を目指す最大のメリットは 「リスクを抑えながら実践的に挑戦できる」 点です。
会社員として安定した収入を維持しつつ、副業で事業を試すことで、いきなり退職して起業するよりも経済的な不安を軽減できます。
さらに副業は実際の市場でニーズを確かめるテストの場にもなり、顧客の反応や売上データを通じて事業モデルの妥当性を検証可能です。
小さな失敗であれば修正が容易なため、改善を繰り返すことで独立後の成功率が高まります。
デメリット
副業から起業を目指す際、最大の課題は「時間不足」です。 本業に加えて副業を行うため、体力面や精神面で負担が大きくなりがち です。
また、業務の両立が難しく、副業に注力しすぎると本業のパフォーマンスが下がる恐れもあります。
さらに、収入が増えることで確定申告や住民税の増加など、税務処理が複雑になる点も見逃せません。
副業から起業するまでのステップ
-
STEP.1
事業アイデアの検証
副業から起業へ進む第一歩は「事業アイデアの検証」です。やりたいことだけで始めてしまうと、需要がなければ失敗につながります。
そこで 市場調査を行い、ターゲット層のニーズや課題を把握する ことが欠かせません。
また、競合分析を通じて「他社にない強み」を見つけることも重要です。たとえば、同じサービスでも価格設定や提供方法を工夫するだけで差別化が可能です。
副業段階でテスト販売やアンケートを実施し、顧客の反応を確かめておくことで、起業後の方向性が明確になり、成功の確率を高められます。
-
STEP.2
小さく始めてスモールテストを繰り返す
事業は最初から大規模に展開するのではなく、「小さく始める」ことが成功の近道です。
副業であれば 少額の資金や限られた時間の中で運営できるため、失敗しても大きな損失にはなりません 。
例えばネットショップを開設し、商品の反応を少数顧客で試して改善を重ねる方法が有効です。これを繰り返すことで、どの商品やサービスが支持されるのか、どんな集客施策が有効かを学べます。
スモールテストを積み重ねることで、独立後に必要な運営ノウハウが蓄積され、リスクを抑えながら事業の成長基盤を作れるのです。
-
STEP.3
法人化のタイミングとメリット
副業が軌道に乗ったら「法人化」を検討するタイミング です。個人事業主のままでも活動は可能ですが、法人化には節税効果や社会的信用の向上といったメリットがあります。
例えば法人になると経費として認められる範囲が広がり、利益が増えた場合に節税につながります。また、法人名義の口座や契約が可能になるため、取引先からの信頼性も高まります。
ただし、法人化には登記費用や維持コストがかかるため、一定の売上や継続性が見込める段階で行うのが理想です。
準備を整えて適切なタイミングで法人化することが、安定した経営への第一歩となります。
起業に必要なお金と資金調達方法
初期費用の目安と自己資金の準備
起業にあたってまず考えるべきは「初期費用の把握」です。業種によって必要な金額は大きく異なりますが、オフィスを構えずにオンライン中心で始める場合は数十万円からでも可能です。
一方、店舗や設備投資が必要な事業では数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。
こうした 費用をすべて借入に頼るのはリスクが高いため、自己資金を準備することが重要 です。
自己資金がある程度あれば金融機関からの信頼度も上がり、融資を受けやすくなります。副業段階で少しずつ資金を積み立てておくことが、起業成功への第一歩になります。
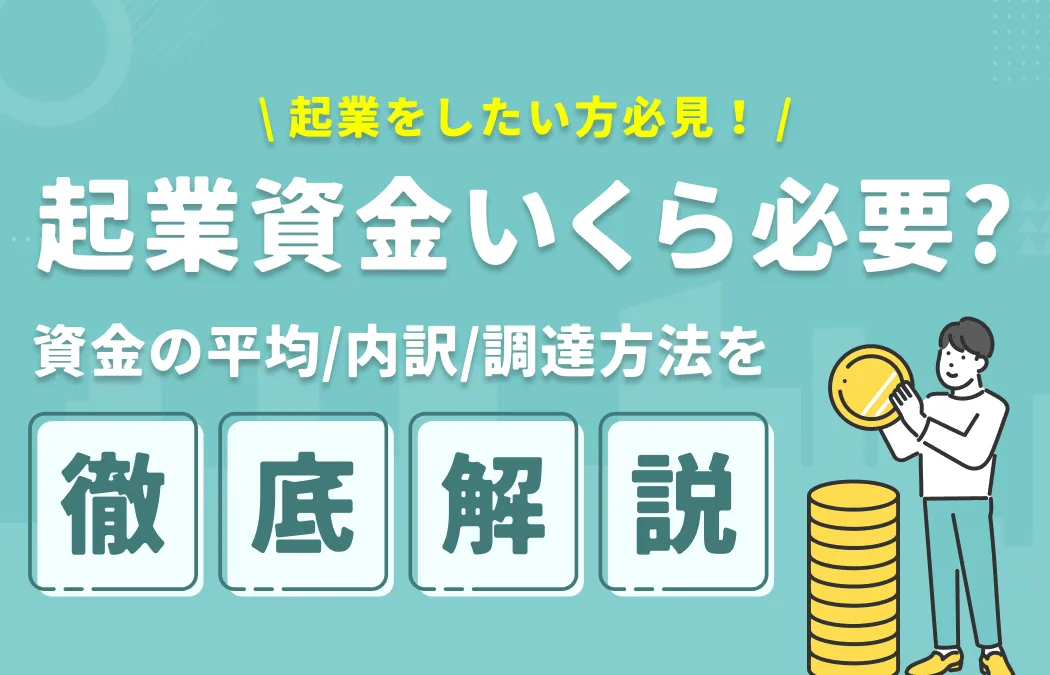
補助金・助成金の活用
起業資金を用意するうえで見逃せないのが「補助金・助成金」です。国や自治体は創業を後押しするため、条件を満たせば返済不要で資金を受け取れる制度を多数設けています。
代表的なものには 「創業補助金」や「小規模事業者持続化補助金」 があり、事業計画や販路拡大のための費用に利用可能です。
ただし、申請には事業計画書の提出や採択審査が必要となるため、準備に時間を要します。
早めに情報を収集し、専門家のサポートを受けながら申請することで採択率を高めることができます。補助金は資金負担を軽減する大きな武器となるため、積極的に検討しましょう。
融資・クラウドファンディングの選択肢
自己資金や補助金だけで足りない場合は「融資」や「クラウドファンディング」の活用を検討します。
- 融資
金融機関の融資は返済義務があるものの、安定的な資金調達が可能。創業直後は「日本政策金融公庫」の創業融資が利用しやすい。 - クラウドファンディング
資金調達と同時に事業の認知拡大やマーケティングにもつながる手法。特に新しいサービスや製品を展開する場合、支援者からの反応を得られる点が大きなメリット。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、 事業の特性やリスク許容度に応じて最適な方法を選択することが重要 です。

副業から起業する際によくある失敗と回避方法
事業計画が曖昧なまま起業
副業である程度収益が出たからといって、事業計画が不十分なまま独立すると失敗しやすくなります。
なぜなら、 本業の収入に支えられていた段階と違い、起業後は売上が生活のすべてを左右する からです。
市場規模や競合環境、ターゲット層を明確にせずに動き出すと、思ったように顧客を獲得できず資金が尽きるケースが多く見られます。
これを回避するには、売上や利益のシミュレーションを含めた事業計画を練り、第三者の目線でチェックを受けることが大切です。計画の精度を高めるほど、安定した成長につながります。

時間管理ができず本業・副業が中途半端になる
副業から起業を目指す人の多くが直面するのが「時間管理の難しさ」です。本業と副業を両立させようとすると、どちらも十分な成果を出せない状況に陥りやすいのです。
特に 副業に集中しすぎると本業に支障が出て、収入や信用を失うリスク があります。逆に副業に割く時間が足りなければ、事業が成長せず独立の目処が立ちません。
この問題を解決するには、時間の優先順位を明確にし、効率的なタスク管理を実行することが不可欠です。
税金や社会保険を軽視するリスク
副業から起業する際に意外と見落とされがちなのが「税金や社会保険の負担」です。
副収入が増えると住民税や所得税が上がり、確定申告が必要になります 。申告を怠ると追徴課税や延滞金が発生し、大きな負担となる可能性があります。
また、起業後は国民健康保険や国民年金への切り替えが必要になり、支出が増える点も注意が必要です。
これを避けるには、副業段階から収支を記録し、必要に応じて税理士に相談することが効果的です。税務を軽視せず正しく対応することで、起業後の資金繰りを安定させることができます。

成功事例から学ぶ!副業から起業した人のパターン
スキルを活かして起業(デザイナー・プログラマーなど)
自分の専門スキルを活かして独立するのは、副業から起業への代表的な成功パターンです。
例えばデザイナーやプログラマーであれば、 副業として受託案件を少しずつこなし、実績と顧客を積み重ねることが可能 です。
独立後はこれまでの実績が信用となり、新規顧客の獲得につながります。また、クラウドソーシングやSNSを活用することで営業コストを抑えながら案件を拡大できる点も強みです。
こうしたスキル系の起業は初期費用が少なく、経験値を直接収入に変えやすいというメリットがあり、副業から本格化しやすい分野といえます。
物販やECからの独立
ネットショップやECサイトを通じた物販も、副業から起業につながりやすい成功事例です。
最初はフリマアプリや小規模なオンラインショップで販売を開始し、 売れる商品を見極めながら規模を拡大していく流れが一般的 です。
特に在庫を持たずに始められるドロップシッピングや受注生産型のサービスを利用すれば、リスクを抑えてテスト販売が可能です。
販売実績が積み上がれば、独自ブランドを立ち上げたり、法人化して本格展開するケースも多くあります。小さく始められるEC事業は、副業からスムーズに独立する手段として有効です。
地域ビジネスや店舗型事業の拡大
飲食店やサロンなど地域に根ざした店舗ビジネス も、副業から起業につながるパターンがあります。
例えば週末だけ間借り営業を行い、顧客の反応を見ながらメニューやサービスを改善し、本格的な店舗オープンへと進める方法です。
副業で小規模に始めることで需要の有無を確認できるため、開業後の失敗リスクを回避しやすくなります。
また、SNSでの集客や口コミの活用によって地域での認知度を高め、開業時に顧客基盤を持った状態でスタートできるのも大きな強みです。
副業から起業する際の注意点
会社の就業規則・副業規制の確認
副業から起業を考える際には、まず「会社の就業規則」を確認することが重要です。
多くの企業では副業を解禁する動きが広がっていますが、依然として副業を禁止している会社も存在します。
もし 規則に違反すれば懲戒処分や信頼低下につながり、本業に悪影響を及ぼしかねません 。
また、同業他社での副業は競業避止義務に抵触する恐れもあります。起業を見据えて副業を始める場合は、必ず規定を確認し、必要であれば上司や人事部に相談してトラブルを回避しましょう。
確定申告や税務処理の基礎
副業収入が年間20万円を超えると、確定申告が必要 になります。
起業準備段階では「売上=利益」と考えがちですが、経費計上や青色申告特別控除などを正しく利用することで税負担を軽減できます。
また、申告を怠ると延滞税や追徴課税が発生し、せっかくの副収入が減ってしまうリスクもあります。
さらに、起業後は法人税や消費税の申告義務が発生する可能性もあるため、早い段階から税務知識を身につけておくことが大切です。
会計ソフトの活用や税理士への相談を取り入れることで、正確で効率的な管理が可能
リスク管理と生活費の確保
副業から独立する際に見落としがちなのが「生活費の確保」です。 最低でも半年から1年分の生活費を蓄えておく ことが安心につながります。
これは、独立後すぐに売上が安定するとは限らず、数か月間は赤字が続くケースも少なくないためです。
また、突然の病気やトラブルに備えて保険や緊急資金を確保することもリスク管理の一環です。リスクを想定して準備しておけば、精神的な余裕を持って事業に集中できます。
副業からの起業を成功に導くサポートサービス
専門家への相談(税理士・行政書士)
起業準備を進める際には、専門家への相談が大きな助けになります。特に税理士や行政書士は、開業届の提出や法人設立の手続き、税務処理など複雑な業務をサポートしてくれます。
自分だけで調べて対応することも可能ですが、 誤りがあると余計なコストや手間がかかり、最悪の場合は罰則につながるリスク もあります。
副業の段階から専門家に相談することで、正確な情報に基づいて判断でき、安心して事業を進められます。
また、補助金や助成金の申請サポートを依頼すれば、資金調達の幅を広げることにもつながります。
起業支援サービス「0円創業くん」の活用
0円創業くんは、インターネットや会計ソフトなど、起業時に必要なサービスをまとめて導入することで、 会社設立に必要な登記や書類作成を無料でサポートしてくれる企業支援サービス です。
- 通常であれば数万円以上かかる会社設立費用を最大0円に減額できる
- 定款作成・登記申請の代行など各種手続きも専門の司法書士に任せられる
- 創業時に必要なインフラやクラウドシステムを低コストで一括導入できる
起業時の疑問や心配事も専門家に無料相談でき、サポートが受けられるため、初めての起業でも安心して手続きを進められます。
副業から本格的に独立するタイミングで利用すれば、コストと手間を大幅に削減し、スムーズなスタートを切ることが可能です。

まとめ
副業から起業へ進む道は、リスクを抑えつつ自分の可能性を試せる有効な方法です。
しかし成功するためには、事業計画の明確化、資金調達の工夫、時間管理や税務への対応といった多くの準備が欠かせません。
スモールスタートで試行錯誤しながら市場の反応を確かめ、最適なタイミングで法人化を進めることが、安定した成長につながります。
また、補助金や専門家の活用によって不安を減らすことも重要です。起業を考える方は、まず一歩を踏み出す仕組みを整えることから始めましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!