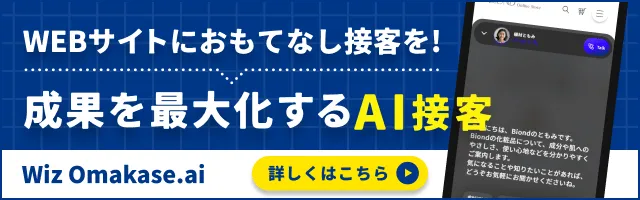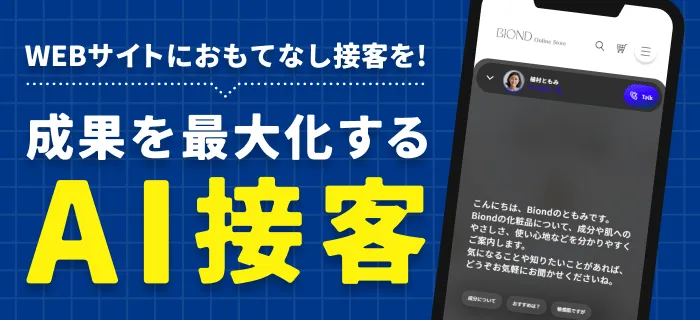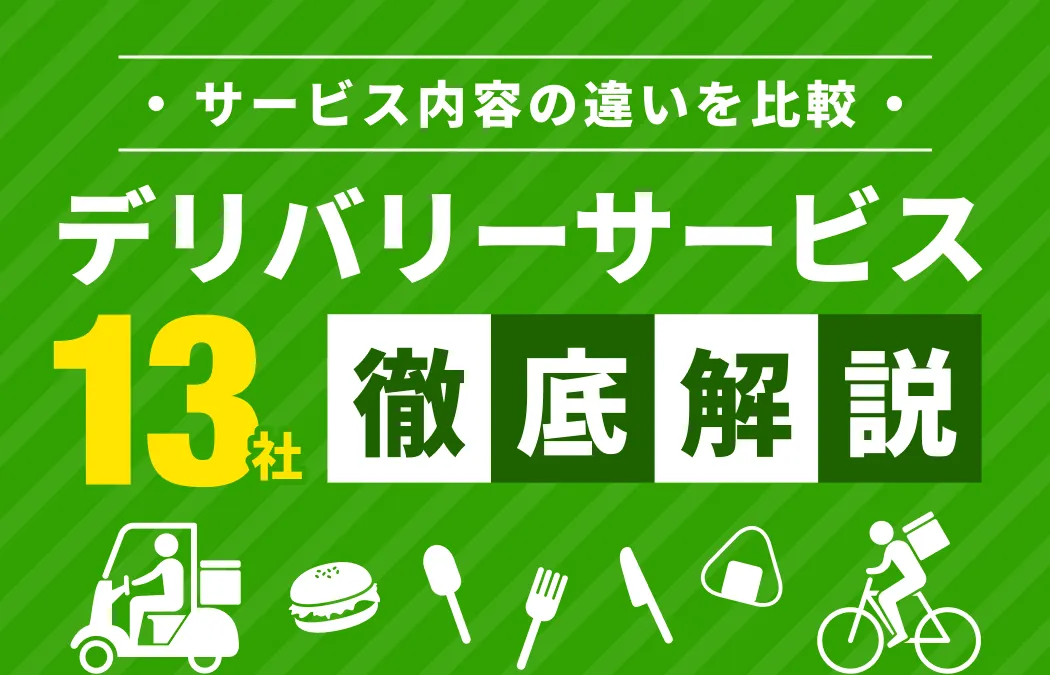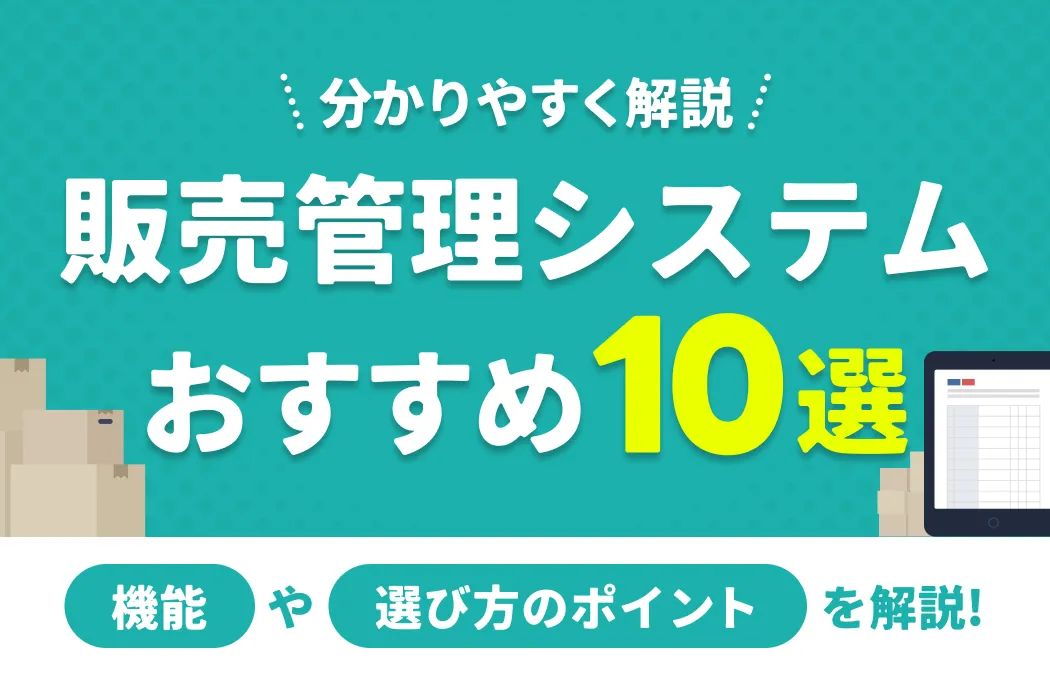「フードデリバリーのメリット・デメリットは?」
フードデリバリーサービスは、専用サイトやスマホアプリから料理を注文し、指定の場所や時間に配達してもらえる便利なサービスです。
しかし、フードデリバリーの導入に悩んでいる方の中には、仕組みやメリット・デメリットが気になるという方も多いでしょう。
そこで本記事では、フードデリバリーの基礎知識、さらに選び方やおすすめ4選も紹介していきます。
目次
▼この記事で紹介している商品
フードデリバリーサービスとは?

フードデリバリーサービスは、 専用サイトやスマホアプリから料理を注文し、指定の場所や時間に配達してもらえる便利なサービス です。
飲食店側は、配達時間に合わせて調理を行うだけで、接客や会計などの手間なく売上を作れます。
また、複数の飲食店と不特定多数の顧客をアプリで結びつけるというサービスの特性上、実店舗の営業よりも幅広いユーザーに利用してもらいやすいのもメリットです。
フードデリバリーサービスは、共働き世帯の増加やコロナ禍で需要が急増し、市場規模が拡大しています。
フードデリバリーサービスの仕組み
フードデリバリーサービスは 「利用者」「飲食店」「配達パートナー」の3者で成り立ちます 。
上記の3者を仲介するプラットフォームがサービス全体を管理し、注文から配達までスムーズに運営される仕組みです。
注文の流れ
- 注文者が専用アプリやサイトで料理を選び注文すると、内容が飲食店に送信されます 。
- 注文と同時に、店舗付近に待機している配達パートナーが選ばれ、商品を受け取って配達します。
配達は、デリバリープラットフォームに登録している個人事業主が行うため、 飲食店側で専任の配達員を雇用する必要がありません 。
お金の流れ
注文者は料理代金に配達手数料を加えた金額を支払い 、アプリで事前決済すれば受け取り時のやり取りは不要です。
支払い金額は運営会社に渡り、手数料を差し引いた額が飲食店へ、配達報酬が配達パートナーへ支払われます。
配送方法の種類
フードデリバリーの配送方法は主に2種類あります。
-
レストランが直接配送する方法
自社スタッフが届けるため対応や品質保持の面で安心です -
Uber Eatsや出前館などのサービスを利用する方法
配達員を雇う必要がないためオペレーション管理しやすく、人件費削減にもつながります
フードデリバリーの市場規模と需要

2024年のデリバリー市場規模は7967億円 と、前年同期比では減少したものの、コロナ前比では約90.5%増の水準を維持しています。
一方で、出勤増加に伴い外食需要が堅調に伸びる中、デリバリー利用は節約志向や消費行動の変化で減少傾向です。
今後は、消費者ニーズに合った新たな利用シーンの提案やサービス価値の訴求が成長のカギとなります。

編集部
フードデリバリー事業者の増加に加え、デリバリー専用のゴーストレストランやシェアキッチンといった新しい飲食店形態が登場しており、今後も市場の成長が見込まれています!
フードデリバリーの歴史
フードデリバリーの起源は19世紀のアメリカ にあり、当時は電話で注文し、バイクや自転車で配達されていました。
その後、インターネットの普及に伴って多様なサービスが登場し、特に2020年のパンデミック以降、需要が急増しました。
現在では、フードデリバリーは生活の一部を支えるサービスとして広く定着しています。
デリバリーとケータリングの違い
| デリバリー | ケータリング | |
|---|---|---|
| 対象 | 個人または小グループ向け | 大人数やイベント向け |
| サービス内容 | 食事の配達のみ | 食事の提供に加えて、イベントの演出や装飾も行う |
| カスタマイズの度合い | メニューが限られていることが多い | 顧客の要望に応じて高度にカスタマイズ可能 |
| 提供時間 | 注文後、短時間で提供される | 事前の準備が必要 |
デリバリーは、基本的に日常の食事を飲食店から配達するサービス です。
一方、ケータリングはイベントや大人数向けに食事を提供するサービスで、メニューのカスタマイズやビュッフェ形式、コース料理などが選べ、テーブルセッティングや装飾も含まれることがあります。
デリバリーは日常的な利用に対し、ケータリングは特別な集まりに使われる ことが多いです。
フードデリバリーが活用されるシーン
- 食事を用意するのが手間に感じる時
- 家庭内やオフィスでの誕生日パーティーや記念日といったイベント時
- 体調不良で食事の用意が負担な時
- 高齢者や障がい者など、日常的に食事を作るのが難しい人
フードデリバリーサービスのメリット

初期投資なしで手軽にフードデリバリーを始められる
フードデリバリーサービスを利用することで、自店で配送体制を整えるための人員や設備を増やすことなく、手軽にフードデリバリーを始めることができます。
配送に必要なスタッフや車両はサービス提供事業者が用意してくれる ため、バイクや備品を購入したり、オペレーションを変更したりする手間や費用を削減できます。
これにより、短期間でスムーズにデリバリーサービスを導入でき、コストも抑えることができます。
認知を高め、新たな顧客層を獲得できる
フードデリバリーサービスの導入は、店舗の認知度向上と売上拡大に効果的です。
特に、大手サービスでは幅広いユーザー基盤を活用し、 中距離圏内や外出が難しい顧客層にもリーチ可能 です。
また、アプリ内での露出やレビュー機能により、新規顧客の目に留まりやすく、利用促進の機会が広がります。

編集部
デリバリー利用をきっかけに、新規顧客が実店舗を訪れてくれる可能性もあります。
新たな収入源を確保できる
従来の店内飲食にデリバリー注文から得られる収益が加わることで、 販路が拡大し、売上を安定・向上させることが可能 です。
特にランチタイムやディナータイムに加えて、アイドルタイムなど店内が空いている時間帯にもデリバリーを活用することで、空き時間の収益化が実現します。
また、天候が悪い日や特別なイベント時など来店客が減少しがちな状況でも、デリバリー需要を取り込むことで安定的な収益を確保できます。
さらに、デリバリーは店舗の物理的なキャパシティを問わず注文を受け付けられるため、席数を増やすことなく売上拡大を図れる点も、新たな収入源としての魅力となっています。
飲食業界に新規参入しやすくなる
フードデリバリーサービスを利用すれば、 テイクアウトやデリバリー専門店として営業することも可能なため、飲食業界に新規参入しやすくなります 。
キッチンさえ準備できれば始められるため、店内の飲食スペースを準備する必要がなく、低コスト・低リスクでの開店が可能です。
配達業務を省力化できる
フードデリバリーサービスを利用することで、配達業務を専門の人材に任せることができ、 採用や教育にかかる手間やコストを削減できます 。
これにより、従業員の事故やトラブルのリスクも抑えながらデリバリー事業を開始できます。
フードデリバリーサービスのデメリット

市場競争の激化
フードデリバリーサービスの普及により、多くの飲食店が新規参入することによって、エリア内における競争が激化しています。
競争が激しくなると、価格競争に巻き込まれるリスクも高まり、利益が圧迫される可能性があります。
このため、各店舗は独自性の創出や競合店との差別化を強化し、安定的に集客できるよう工夫する必要があります 。
品質の低下
フードデリバリーでは、実店舗での提供と異なり、料理が届くまでに時間がかかるため、温度管理や品質の維持が課題となります。
具体的には、冷めても美味しく食べられる工夫や、風味が損なわれないメニュー開発が求められます。
デリバリー向けの調理方法や包装方法を工夫しましょう。
配達トラブル
フードデリバリーでは、 天候や交通渋滞などの影響で配達が遅れるリスクがあります 。
また、配達員のスキルや対応に差があるため、遅延や盛り付けの崩れ、マナーの不備が原因で、顧客からのクレームや不満が生じることもあります。
手数料の高さによる飲食店の経営圧迫
フードデリバリーサービスを利用すると、手数料が発生します。
特に、小規模店舗や低価格帯の商品を提供している場合、 手数料の負担が大きくなり、利益への影響が経営圧迫につながるなど、深刻になることがあります 。
出前館などが飲食店支援のために手数料上限の緊急措置を講じていますが、一時的な対策に過ぎず、手数料の根本的な見直しにはまだ進展がありません。
許可取得の手続きが必要なケースがある
フードデリバリーサービスを利用する際、基本的には飲食店営業許可の範囲内であれば新たな許可は不要ですが、 メニューによっては別途許可が必要となる場合があります 。
例えば、酒類などは店舗で提供していても、デリバリーには特別な手続きが求められることがあり、許可取得には時間と手間がかかります。
スムーズにデリバリーを始めるためにも、事前に必要な許可を確認し、適切な手続きを行いましょう。
-
おかずだけの販売▶惣菜製造業の許可申請
-
お酒のデリバリー▶酒類販売営業免許
-
デザートのデリバリー▶菓子製造業の許可
フードデリバリーサービス利用客側のメリット・デメリット

顧客がフードデリバリーを利用するメリット
- 外出せずに自宅で好きな料理を楽しめる
▶雨の日や体調が優れない時でも、スマートフォンで簡単に注文可能 - 店舗での待ち時間がなく、自分の都合に合わせて食事時間を調整できる
▶仕事や家事の合間にも、効率的に食事を済ませることが可能 - 普段は行けない距離にある店舗の料理も楽しめる
▶人気店の料理を並ばずに味わえる、新しい店舗を気軽に試せる
フードデリバリーサービスは、 特に子育て中の家族や在宅ワーカーにとって、大きな助けとなっています 。家から出られない状況でも、バラエティ豊かな食事を楽しむことができるからです。
顧客がフードデリバリーを利用するデメリット
- サービス料や配送料がかかる
▶料理も、店内飲食よりも値段設定が高い傾向にあるため、トータルの料金が高くなりがちです - 天候や配達員の状況によって到着時間が変動する
▶特に雨天時や混雑時は、予定より配達が遅れることもあるため、時間に余裕を持って注文する必要がある - 店舗での食事と比べて料理の品質が落ちる可能性もある
▶配送時間や梱包状態によっては、熱々の料理が冷めてしまったり、見た目が損なわれたりする - 注文時に料理の詳細を店員に確認できない
▶アレルギー対応や細かい要望を伝えにくい
フードデリバリーサービスを活用する際のポイント

コストと収益性のバランス
フードデリバリーサービスを活用する際、コストと収益性のバランスを考えることが重要です。
手数料や梱包資材などの費用がかかるため、 総合的なコストをしっかり把握して計画的に管理しましょう 。
無理なく利益を上げるためには、コストを抑える工夫や価格設定を見直すことも大切です。
品質維持できるデリバリー専用メニューの開発
フードデリバリーサービスを活用する際、 食中毒リスクを避けるために品質維持や衛生管理を徹底することが重要 です。
イートインと異なり、商品が届けられるまで時間がかかるため、デリバリーに適したメニュー開発が求められます。
メニュー選定や調理方法、温度管理、パッケージングを工夫し、店内と同じ「安心さ」と「美味しさ」を提供できるように工夫しましょう。

編集部
料理が冷めても美味しく食べられるような対策を講じ、デリバリー後も顧客が満足できる品質を保ちましょう!
マーケティングとプロモーション
フードデリバリーサービス市場で競争が激化している中、安定的に売上を得るためには 魅力的な画像選定やSNS・Webサイトでの情報発信が重要 です。
顧客に選ばれるためのプロモーション活動として、サービスやキャンペーンを積極的に紹介し、プラットフォーム内で注目を集める戦略を図りましょう。
店舗内オペレーション
フードデリバリーサービス導入に伴う店舗内オペレーションの見直しは、スムーズな運営のために欠かせません。
デリバリー注文が増えると、従来の店内サービスと並行して対応する必要があり、スタッフの業務負荷が増大します。
店内客とデリバリー注文の両立には、効率的な動線と作業工程の確立が重要 です。
特にピーク時には、店内とデリバリーの両方の注文が重なるため、効率的な調理や梱包、配達準備の体制が求められます。
-
時間帯別の人員配置を見直す(デリバリー注文と店内注文のピーク時間が異なることも多い)
-
必要に応じて、デリバリー専任スタッフの配置も検討
-
デリバリー専用の梱包資材や受け渡しスペースを確保
-
シフト管理や食材の在庫管理を最適化する
フードデリバリーサービスの選び方

サービスの利用タイプ
フードデリバリーサービスには 「マーケットプレイス型」と「デリバリープラットフォーム型」の2種類 があります。
目的や規模に合わせて、店舗に合うタイプを選びましょう。
| マーケットプレイス型 | デリバリープラットフォーム型 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 注文システムは運営会社提供、配達は店舗側が担当 | 注文受付から決済、配達まで一貫したサービスが提供される |
| メリット | ・配達品質を自店でコントロール可能 ・リーズナブルなプラットフォーム利用料 ・地域性を活かした展開 |
・初期投資が少なく、知名度を活かした集客が可能 ・配達スタッフの手配不要で調理に専念可能 |
| デメリット | ・配達スタッフの確保と管理が自己責任 ・配達員の人件費や車両維持費がかかる |
・売上に応じた手数料が発生 ・プラットフォームルールに従う必要がある |
| おすすめ店舗 | ・中規模店舗 ・配達品質にこだわりたい店舗 |
・新規参入の店舗 ・小規模店舗 |
マーケットプレイス型
マーケットプレイス型サービスは、 注文システムは運営会社が提供し、配達は店舗が行う形式 です。
配達品質を自店で管理できるほか、独自のエリア設定や時間調整が可能で、地域に合ったサービスを提供しやすい点も魅力です。中規模店舗や配達品質重視の店に適しています。
ただし、配達スタッフの手配や配送管理は店舗側の責任となるため注意が必要です。
デリバリープラットフォーム型
デリバリープラットフォーム型は、Uber Eatsや出前館などの大手プラットフォームを利用する形態です。
プラットフォーム側が、注文受付、決済、配達まで一括で請け負ってくれるため、初期投資が抑えられ、集客効果も期待できます。
また、配達スタッフの手配や管理が不要で、調理に専念できる点もメリットです。
ただし、売上に応じた手数料が発生するほか、プラットフォームのルールに従う必要があります。
知名度・シェア
フードデリバリーサービスを導入する際、知名度が高く、シェアの大きいプラットフォームを選ぶことが重要です。
大手のサービスは 登録ユーザーが多いため、顧客に自店舗を認知されやすく、注文数の増加が期待できます 。
さらに、注文に至らなくても、店舗情報が目に留まることで実店舗への来店促進にもつながる可能性があります。
登録店舗数
フードデリバリーサービスを導入する際、登録店舗数が多いサービスを選ぶことで、利用者に多くの選択肢を提供できます。
しかし、競争が激化するため、 目を引く写真を掲載したり、競合店のメニューや価格を分析して差別化を図ったりすることが重要 です。
サービス利用料・配達手数料
フードデリバリーサービスを導入する際には、サービス利用料や配達手数料などの費用が発生します。
一般的に、取引成立後の商品代金に対して30~40%程度の手数料が課されますが、 料率はサービス事業者によって異なります 。
加えて、加盟店登録料やカード決済手数料がかかることもあるため、各サービスを比較して選ぶことが重要です。
顧客から見た利便性
フードデリバリーサービスを導入する際、顧客視点での利便性も重要な選定ポイントです。
サービスサイトやアプリが使いやすくない場合、顧客は他のサービスに流れてしまう可能性があります。
店舗情報が見やすいか、注文までの手順がスムーズかをチェックすることが大切 です。
実際にサービスを利用して、使いやすさを確認し、顧客が快適に利用できるかどうかを見極めましょう。
サービスの評判
フードデリバリーサービスを導入する際、配達員やサポートセンターの評判を確認することも大切です。
配達員の対応が良ければ顧客は再利用を考えますが、対応が悪いと利用を避けられる可能性もあります。
顧客満足度を左右するこれらの対応は自店舗では管理できないため、 信頼できる評判のサービスを選ぶことが重要 です。
国内で人気のフードデリバリーサービスランキング
1位|Uber Eats(ウーバーイーツ)

Uber Eats(ウーバーイーツ)は、日本でフードデリバリーサービスを広めたパイオニア的存在のサービスです。現在では47都道府県で10万店以上が加盟しています。
加盟店数、登録ユーザー数ともに業界トップクラス を誇り、多彩なジャンルの料理を自由に選べます。
2023年8月から東京、大阪をはじめとした全国12都市の対象店舗で、24時間いつでも利用可能となり、より利便性が高まりました。
また、「最低注文価格」が設定されておらず、少量からでも気軽に注文できるため、単身者にも重宝です。(別途、少額注文手数料が発生する場合があります)
関連記事
【Uber Eatsの料金や仕組みは?】手数料やメリットを徹底解説! Uber Eats加盟店に店舗登録をする方法・出店する条件を解説【飲食店向け】 Uber Eatsの配達員の選ばれ方は?鳴る仕組みやAI攻略方法を徹底解説2位|出前館

出前館は、アクティブユーザー数約560万人、出店店舗数100,000店以上を誇る国内最大級のデリバリーサービスです。
加盟店は、宅配ピザや寿司、ファストフードやファミレスなどの 大手チェーンの比率が高く、反対に個人店が少ない傾向 にあります。
利用金額に応じてLINEポイントやdポイントなど、デリバリー以外の場面で使えるポイントがたまるのも魅力です。
関連記事
デリバリー「出前館」の店舗登録方法って?手数料や条件なども解説 出前館の評判や口コミをチェック!良い・悪い口コミを比較! 【出前館vsウーバーイーツ】手数料や違いを比較!結局どっちがメリット多い?3位|Wolt(ウォルト)

Woltは、世界110都市以上でサービスを展開している、北欧フィンランド発の外資系フードデリバリーサービスです。
加盟店・配達員どちらも、登録時に審査が設けられているため、サービス品質が比較的高い 点が最大の強みです。
また、トラブルを対処するためのサポート体制も、配達員・注文者の両方に向けて整備されているため、安心して利用できるサービスを選びたい方に最適でしょう。
Uber Eatsと同様に、綜合型のプラットフォームなので、様々なジャンルのお店を選べます。
4位|menu(メニュー)

menuは、 デリバリーとテイクアウトの両方に対応 しているサービスです。
大手チェーン店から個人店まで様々ジャンルの店舗が加盟しており、ミシュラン星付きの有名店や高級レストランなど、menuでしか注文できない人気店も出店しています。
テイクアウト対応している点が最大の特徴で、指定したエリアから気になる店舗を探し、注文から決済まで効率的に進められる点も魅力です。
また、フードデリバリーサービスの中では珍しく電話対応サポートも用意されているため、もしものトラブルでも安心です。
フードデリバリーサービスで商品が届くまでの流れ

STEP1|フードデリバリーサービスに登録
フードデリバリーサービスの利用を始めるには、まず登録が必要です。
氏名、配達先の住所、電話番号やメールアドレスなどを入力します 。
登録は、スマホのアプリやWebサイトで簡単に行えます。なお、登録した情報は会員情報として保存されるため、次回からはさらにスムーズに利用できます。
STEP2|注文する料理を選ぶ
フードデリバリーサービスのアプリやWebサイトで、注文する料理を選びます。
料理のジャンルや配達可能エリア、店舗名をもとに検索でき 、その日の気分や好みに合わせてメニューを選ぶことができます。
STEP3|オンライン決済で支払う
料理を決めたら、オンライン決済で支払いを行います。
支払い方法はサービスによって異なり、クレジットカードや電子マネーが一般的 ですが、Uber Eatsでは代引き決済にも対応しており、現金払いを希望する方にも対応可能です。
STEP4|料理が届くまで待つ
注文と決済が完了したら、指定した場所で料理が届くのを待ちましょう。
一部のフードデリバリーサービスでは、 配達予定時刻や配達員の現在地を確認できる機能があり 、料理がいつ届くかの不安を解消してくれます。
なお、配達可能エリア内であれば、指定した場所は自宅やオフィスに限らず、外出先や公園など柔軟に対応可能です。
フードデリバリーサービスに関するよくある質問
A
フードデリバリー配達員は多くが個人事業主であるため、労災保険が適用されず、事故時の補償が課題とされてきました。
近年では、各サービス事業者が補償制度を拡充し、安心して働ける環境づくりに注力しています。
例えば、Uber Eatsは配達中の事故補償を導入し、補償範囲や内容を改善しました。こうした取り組みは、業界の発展にもつながっています。
A
フードデリバリーはさらなる普及が予想され、AIやドローンを活用した効率的なサービスが期待されています。
また、環境に配慮したエコ配送の普及により、利便性と持続可能性の両立が進むでしょう。
A
海外で人気が高いフードデリバリーサービスは「DoorDash」や「Grubhub」「Deliveroo」です。
A
LINE公式アカウントを活用し、デリバリーやテイクアウト注文を受け付けることは可能です。
A
利用客側がフードデリバリーサービスを使う際の注意点はい以下の通りです。
・配送エリアの確認:住所によっては利用できない場合があるため、自分の住所が対象かどうかを確認しましょう。
・注文時の確認:アレルギー情報や配達時間、配達先は正確に入力しましょう。
A
1日3〜4時間の稼働で、平均報酬は4,000〜5,000円です。
注文が多い日は1日1万2,000円稼ぐ人もいます。
週2〜3回働いて月収は6〜7万円ほど。稼働時間を増やせば月10万円も可能です。
A
フードデリバリー配達員の業種は「運輸業」「郵便業」「宿泊業」「飲食サービス業」です。
A
デリバリーは、飲食店やレストランが提供する商品を、お客様が指定した場所まで直接配達することです。
一方で、ウーバーイーツは、デリバリーのサービスの一種です。
つまり、デリバリーは総称、ウーバーイーツは固有名詞になります。
まとめ
フードデリバリーサービスの導入は、飲食店にとって多くのメリットをもたらします。
効率的な集客や新たな売上機会の創出、ブランド認知度の向上が期待でき、特にコロナ禍以降、オンラインでの飲食体験を求める顧客に対応するためには欠かせないサービスとなっています。
デメリットもありますが、適切なメニュー選定や運営管理でリスクを抑え、競争力を高めることが可能です。ぜひこの機会に、フードデリバリーサービスを活用して、ビジネスの成長を目指しましょう。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!