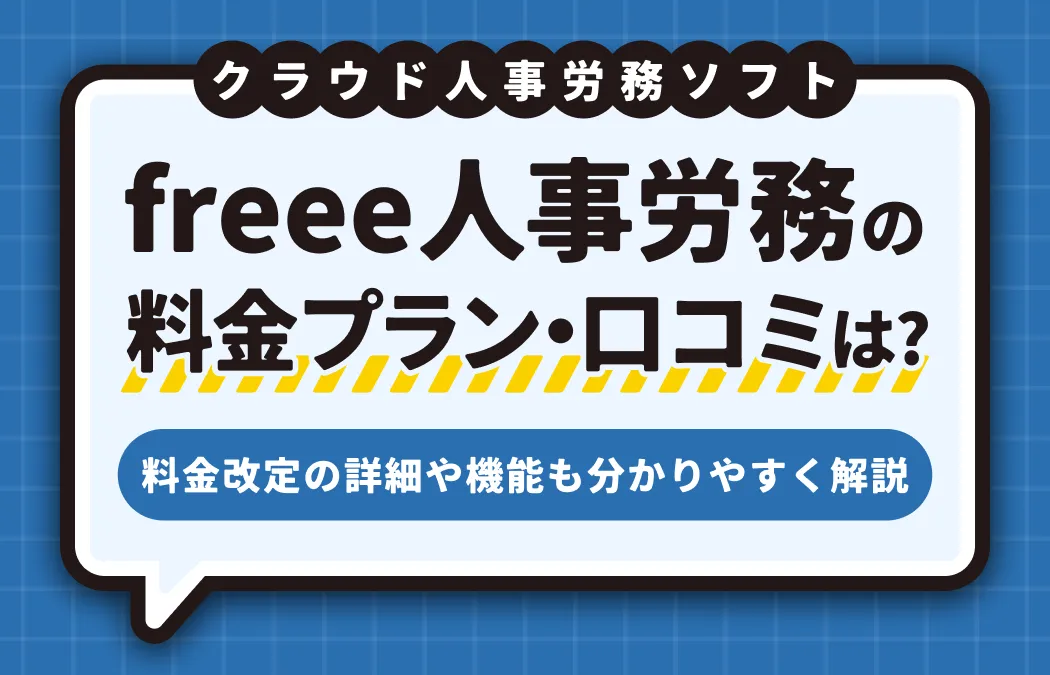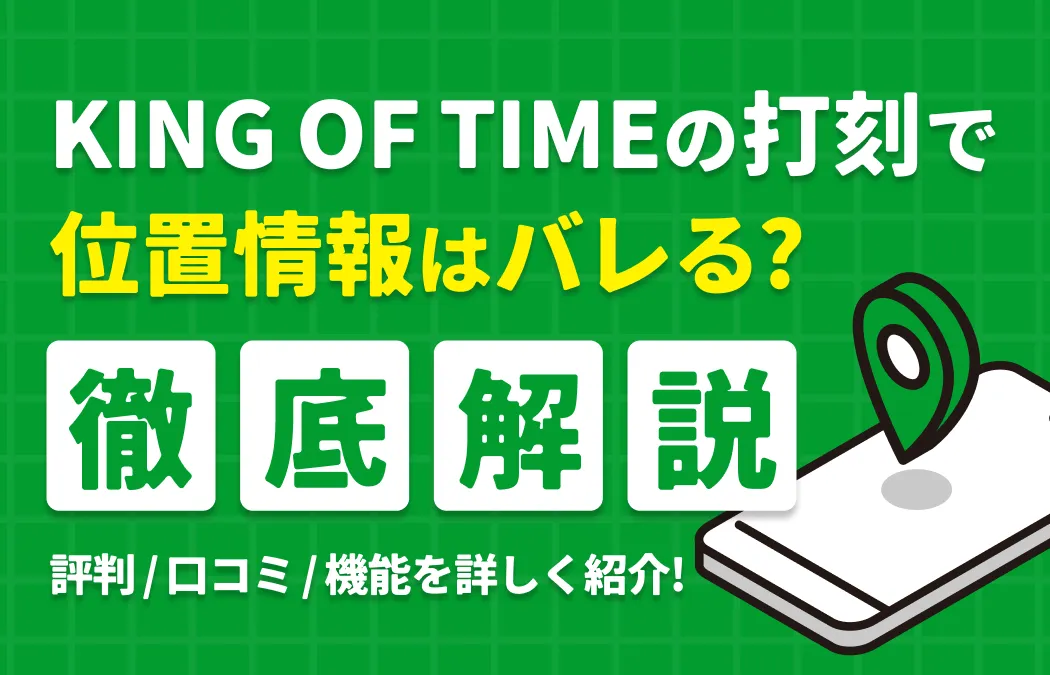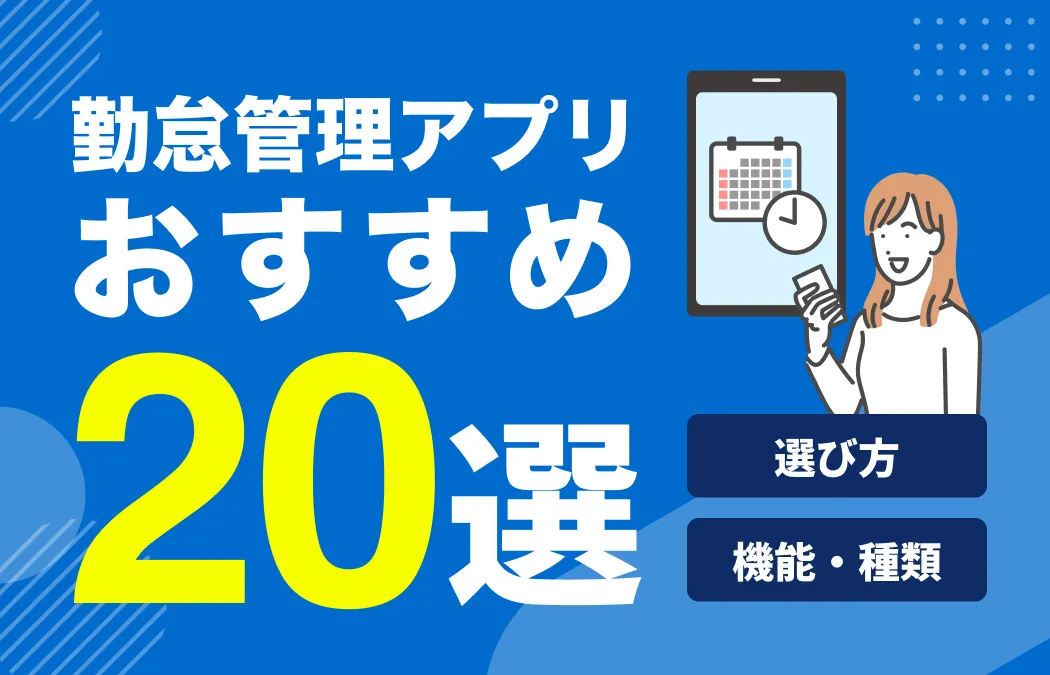「pdfの契約書をpdfでやり取りする場合に印紙税はかかる?」
国税庁は、電子契約書が課税文書に該当しないと公式に見解を示しています。
しかし、「そもそも印紙税とは?」「電子契約書を印刷したら印紙税は必要?」など、疑問も多いはずです。
本記事では、電子契約書に印紙税が課されない理由や、電子契約の印刷に関する注意点などを解説します。
電子契約のメリットや、文書を保管する際の注意点も紹介しているため、契約業務の電子化を推進したい事業者は必見です。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
目次
▼この記事で紹介している商品
印紙税とは? どのような契約書に必要?
印紙税とは
印紙税とは日本の国税の一つで、契約書や領収書、定款などの文書を作成する際に課されます。
対象となる文書を作成した際に所定金額の収入印紙を文書に貼付し、消印されることで納税とみなされる 仕組みです。
印紙税の目的は、文書の証拠性を高めるとともに、その作成行為自体に対する課税です。
納税がなされていない場合や消印の不備がある場合には、過怠税が課されることもあります。
印紙税の対象となる書類(=課税文書)
印紙税の課税対象となる文書は「課税文書」と呼ばれ、印紙税法で定められた20種類以上の文書が対象となります。
代表的なものとしては、 売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書、領収書、不動産の譲渡契約書など があります。
これらの文書を2通以上作成し、当事者がそれぞれ保管するような場合は、それぞれの文書に印紙を貼る必要があります。
また、原則として日本国内で作成された文書が課税対象ですが、国外で作成されたものでも、日本国内で効力を持たせる場合は対象となることがあります。
印紙税額は記載された金額により変わる
印紙税の金額は、契約書に記載された取引金額や契約内容によって変わります。
例えば、 請負契約書や金銭の貸借契約書では、契約金額の範囲ごとに印紙税額が異なり 、数百円~数万円と大きく変動します。
また、契約金額が1,000万円を超える場合は印紙税額が1万円になるなど、段階的に税額が定められています。
なお、金額の記載がない場合や無効な契約でも、印紙税の課税対象とされることがあるため注意が必要です。
印紙税は基本的に収入印紙で納付
印紙税は通常、文書に収入印紙を貼付した上で、割印または記名押印によって消印することにより納税が完了 する仕組みです。
収入印紙は郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入可能です。
収入印紙を貼り忘れた場合や消印を怠った場合には、最大で本来の税額の3倍に相当する過怠税が課されることもあります。
電子契約書では収入印紙が不要になる
近年、電子契約の普及により、契約書を紙ではなく電子データで取り交わすケースが増えています。
印紙税法上、 電子契約書は「文書の作成」に該当しないため、印紙税の対象外 となり、収入印紙を貼る必要がありません。
これは企業にとって、印紙代のコスト削減や書類管理の効率化につながる大きなメリットです。
ただし、PDFを印刷して署名する場合や、一方が紙で保管するケースでは課税対象となる可能性もあるため、運用方法には注意が必要です。
電子契約書で印紙税が不要な理由
- 電子契約の原本はデータであり、印刷したものは写しとみなされるため
- 電子メールに添付したPDFファイルやFAXによる契約書等の取り交わしは「文書を作成したこと」にあたらないため
- 電子契約を締結してファイルを相手方に送信する行為は「交付」に該当しないと解されているため"
紙の契約書に対する課税根拠
印紙税は、印紙税法によって「課税文書」の作成に対して課される国税です。ここで言う「文書」とは、紙に書かれた物理的な契約書を指します 。
契約内容が記載され、当事者間で署名・押印された紙の書類が正式な証拠文書と見なされるため、これを「作成」した場合は課税対象になります。
つまり、 「物理的な紙」によって契約が証明されるという性質から、その作成行為に対して印紙税が課される仕組み です。
電子契約書はこの「紙の作成」に該当しないため、印紙税が不要とされるのです。
国税庁による印紙税法の見解
国税庁は、電子契約について公式に「印紙税法上の課税文書には該当しない」との見解です。
印紙税法でいう「文書」は、あくまで紙により作成された物理的な文書を指し、 電子データによって締結された契約書は「文書の作成」に当たらないとしています 。
そのため、PDFやクラウドサービス上で完結する電子契約書には、収入印紙を貼る義務がないと明確にされています。
参議院質疑でも印紙税が非課税との答弁
電子契約書に印紙税が不要であることは、国会でも公式に確認されています。
2020年3月、 参議院の予算委員会において、当時の財務大臣が「電子契約書は印紙税の課税対象とならない」と明確に答弁 しました。
これにより、法的な解釈としても電子契約書が非課税であることが国の立場として裏付けられました。
電子契約の導入をプロに相談!
【無料】お問い合わせはこちら電子契約書とは?
電子契約書とは?
電子契約書とは、紙ではなく電子データ形式で締結される契約書のことです。
電子データで契約内容を確認・合意し、署名や記録をオンライン上で完結できます。
電子契約は、印刷や郵送の手間が省けて契約のスピード化・コスト削減・コンプライアンス強化に繋がる点がメリットです。
ただし、法的な効力を持たせるためには、電子署名やタイムスタンプなどの技術を活用し、本人確認や改ざん防止措置を講じる必要があります。
電子契約書に必要な電子署名とタイムスタンプ
電子契約書には、当事者の合意を証明し、 契約内容の信頼性を高めるために「電子署名」「電子証明書」「タイムスタンプ」などの導入が不可欠 です。
電子署名
電子署名は、紙の署名や押印に相当する技術で、契約書に誰が署名したかを示すためのデータです。本人性の証明や、改ざんの有無を確認する役割があります。
これにより、電子契約でも法的な効力を持たせることが可能です。
電子証明書
電子証明書は、電子署名の信頼性を支える証明書で、第三者機関(認証局)が発行します。
これにより、署名者の本人性が保証されます。企業や個人は、信頼性のある認証局から電子証明書を取得して利用します。
タイムスタンプ
タイムスタンプは、電子契約書の 契約内容がある時点で確定しており、それ以降に改ざんされていないことを証明する ために使われます。
電子署名とあわせて用いることで、契約の有効性と信頼性をより高められます。

電子契約書の印刷について
電子契約書の印刷は必要?
原則として、電子契約書は電子データのまま保存する必要がある ため、印刷は不要です。
むしろ、印刷した場合、法的な効力がなくなる可能性もあるため注意しましょう。
ただし、業務上の確認や社内承認フロー、取引先との共有などの目的で印刷されるケースもあります。
特に社内文書管理のルールとして紙のファイリングが必要な企業では、確認用として印刷されることがあります。
印刷した電子契約の法的効力
電子契約は、電子データ上で署名やタイムスタンプを適切に行っている場合、紙の契約書と同様に法的効力を持ちます。
しかし、電子契約を印刷した紙の文書には、 電子署名やタイムスタンプといった改ざん防止の証拠が印刷情報としては反映されないため、その紙だけでは契約の証拠力は弱まります 。
したがって、法的な効力を証明する際には、元の電子データを保管し、必要に応じて提示できるようにしておくことが重要です。
電子契約書を印刷した場合、印紙税は必要?
電子契約書は、電子データ上で契約が成立している限り、印紙税の課税対象にはなりません。
しかし、 電子契約書を印刷した紙を使って当事者間で署名・押印して契約書として扱う場合は「課税文書」とみなされ 、印紙税が発生する可能性 があります。
つまり、単に印刷するだけでは課税されませんが、それを契約の証拠文書として使用するかどうかが判断基準となります。
要件を満たせば印刷しての保管が認められる
電子契約書は原則、電子データとしての保管が求められますが、 「スキャナ保存制度」などの法的な要件を満たすことで、印刷物としての保管も一部認められています 。
例えば、真実性(改ざんがないこと)や可視性(誰でも読める状態)などの条件を満たすことで、印刷物でも税務署への保存要件に対応できる場合があります。
ただし、電子帳簿保存法の対象となる場合は、適切なシステムや手続きが必要です。運用前に社内の経理・法務部門と確認しましょう。
【注意】印刷した電子契約は再度電子化してはいけない
一度電子契約書を印刷した後、その印刷物を再スキャンして電子データとして保存し直す行為は、原則として認められていません。
印刷とスキャンを繰り返すと、改ざんの可能性や真正性の証明が難しくなり、法的な証拠力を損なう恐れ があるためです。
電子帳簿保存法や税法では「真正な電子記録の保存」という要件に反します。
電子契約は、最初の電子データのまま保管することが基本であり、正しい形式での保存と運用が求められます。
電子契約のメリット
- 印紙税が削減できる
- 印刷や郵送コストの削減
- 契約締結までがスピーディー
- 契約書の管理・保管が効率化
- 不正防止や改ざん防止
- 信頼性向上
- 法改正に対応しやすい
印紙税が削減できる
電子契約の最大のメリットの一つは、印紙税の支払いが不要になる点です。
印紙税法では「紙の文書の作成」に対してのみ税金が課されるため、 電子データで締結された契約書には課税されません 。
これにより、例えば1件1万円の印紙税が必要だった契約も、電子化することでそのコストを完全に削減できます。
取引件数の多い企業ほど、年間で数十万円〜数百万円規模のコスト削減につながることもあり、経理面でも非常に大きな利点があります。
印刷や郵送コストの削減
従来の紙の契約では、契約書を印刷・押印し、郵送で相手方に届ける必要がありました。
電子契約では、すべてのプロセスがオンライン上で完結するため、 紙代・インク代・封筒・切手・輸送費などのコストを大幅に削減で きます。
また、契約書の印刷や封入にかかる作業時間や人件費の削減にもつながります。
契約締結までがスピーディー
電子契約は、契約書の作成から署名・締結までをオンラインで即時に完結できるため、従来の紙契約に比べて圧倒的にスピーディーです。
印刷や押印、郵送の手間がなくなるため、最短数分で契約が完了するケースも あります。
特に、緊急を要する契約や複数当事者が関わる契約でも、リアルタイムでのやり取りが可能になるため、業務のスピードと柔軟性が格段に向上します。
ビジネスの機会を逃さず、意思決定の迅速化にも貢献します。
契約書の管理・保管が効率化
電子契約では、 契約書がデジタルデータとして保管されるため、紙でのファイリングや保管場所が不要 です。
契約書の検索もキーワードや日付、契約相手名などで簡単にでき、業務の効率が大幅に向上します。
また、保管期限の管理や更新のリマインド設定も自動化できるため、契約管理の漏れやミスも防げます。
紙の契約書のように紛失や劣化のリスクもなく、BCP(事業継続計画)の観点からも安心です。
不正防止や改ざん防止
電子契約には、 電子署名やタイムスタンプなどの技術が使われるため、文書の真正性や時刻の正確性が保証 されます。
これにより、契約後に内容が改ざんされたり、第三者がなりすまして署名するようなリスクを大幅に減らすことができます。
電子署名は本人確認の役割も果たし、記録も詳細に残るため、不正の抑止力にもなります。
また、アクセスログも自動で記録されるため、トラブル発生時の追跡も容易です。紙よりもセキュリティ性が高いといえます。
信頼性向上
電子契約は、法的に認められた電子署名やタイムスタンプを用いることで、 契約の証拠力と安全性が高まり、その結果、取引先からの信頼性も向上 します。
また、業務のスピード化や透明性が担保されるため、企業のガバナンス強化にもつながります。
ITを活用した契約プロセスを整備することは、現代のビジネス環境において「信頼される企業」としての評価を高める要因にもなり、ブランドイメージの向上にも寄与します。
法改正に対応しやすい
電子契約は、 クラウド型のサービスや電子文書管理システムを利用することで、最新の法令や規制の変更に迅速に対応できる のも大きなメリットです。
たとえば、電子帳簿保存法や個人情報保護法などの改正があった際にも、システム側で自動的にアップデートが行われる場合が多く、常に法令遵守を保つことができます。
紙契約では煩雑な運用変更が必要ですが、電子契約なら管理コストも抑えながら、コンプライアンスを強化することが可能です。
電子契約の導入をプロに相談!
【無料】お問い合わせはこちら電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、帳簿書類を紙ではなく電子データで保存することを認める法律で、1998年に施行されました。
これにより、 一定の条件を満たす場合、会計帳簿や取引書類を電子的に保存・管理することが可能 です。
特に、ペーパーレス化や業務効率化を進めたい企業にとっては重要な法律であり、2022年1月には法改正が行われ、電子取引データの電子保存が原則義務化されました。
企業は、信頼性の高いシステム環境を整え、法令に則った運用を行う必要があります。
対象になる書類
電子帳簿保存法の対象となるのは、大きく分けて 「帳簿」「決算関係書類」「取引関係書類」 の3つです。
| 帳簿類 | 仕訳帳・総勘定元帳など |
|---|---|
| 決算書類 | 貸借対照表や損益計算書など |
| 取引関係書類 | 見積書、注文書、請求書、契約書、領収書など |
これらを電子保存する場合には、一定の保存要件を満たす必要があります。特に電子メールやクラウド経由で受け取った書類も対象となるため、業務フローの見直しが求められます。
電子契約を電子保存する場合の要件
電子契約書を電子データのまま保存するには、電子帳簿保存法が定める以下のような保存要件を満たす必要があります。- 真実性が確保されていること
改ざんや削除がされていないことを保証するため、電子署名やタイムスタンプの付与、アクセス制限の設定、訂正・削除履歴の記録が必要。 - 見読性が確保されていること
保存した電子契約書が、パソコンなどの画面上で明確に読める状態であり、必要に応じて即座に出力できることが条件。 - マニュアルが設置されていること
保存方法・操作手順を記載した業務マニュアルを整備し、税務署の調査に対応できるよう備える必要がある。 - 検索機能が確保されていること
契約日・取引先名・金額などで検索できるようにすることが必要。検索条件の項目は要件に準じて備える。 - 定期的なバックアップ・システムの可用性確保
万一のデータ消失に備え、定期的なバックアップやシステム障害時の復旧体制が整っていることが重要。
これらの要件を満たすことで、電子契約書も法的に有効な保存手段として認められ、税務調査時にも証拠書類として提示できます。
電子契約を導入する際の注意点
-
費用対効果にあったサービスを導入する
-
電子契約で扱えない書類もある
-
法的証拠力を担保する要件を満たす必要がある
費用対効果にあったサービスを導入する
電子契約システムは多くのサービスが提供されていますが、導入時には 自社の業務規模や契約の頻度、セキュリティ要件に見合ったものを選ぶ ことが重要です。
たとえば、取引量が少ない中小企業が高機能で高額なサービスを導入しても、費用対効果が見合わない可能性があります。
一方で、業務が複雑で契約件数が多い企業では、検索機能やログ管理が充実したサービスを選ぶことで効率化につながります。
試用期間や無料トライアルを活用して、導入前にしっかり検討しましょう。
電子契約で扱えない書類もある
すべての契約書類が電子契約で対応できるわけではありません。
例えば、 不動産の登記申請に用いる契約書や公正証書が必要な書類、一部の労働契約など、法令により紙での作成が求められている文書も存在 します。
また、印紙税の回避を目的として電子契約に切り替えると、場合によっては法的な問題を引き起こすリスクもあります。
導入前には、自社が扱う契約書類の中で電子化が可能なもの・不可能なものを法務部門などとともに整理・確認することが大切です。
法的証拠力を担保する要件を満たす必要がある
電子契約書が法的に有効となるためには、一定の要件を満たす必要があります。
- 契約の真正性(改ざんがないこと)や当事者の意思の明確化を担保するため、電子署名・タイムスタンプの活用
- 電子帳簿保存法に基づく要件(真実性・見読性・検索性など)
これらが不十分だと、法的な証拠力が認められない可能性もあります。システム選定時には、対応している法的基準を必ず確認しましょう。
書面で締結した契約書を電子化する場合について
電子帳簿保存法スキャナ保存要件を満たせば、書面契約の電子化は可能
電子帳簿保存法に基づく 「スキャナ保存制度」により、紙の契約書をスキャンし、電子データとして保存することが法的に認められています 。
ただし、タイムスタンプの付与や、訂正・削除履歴の管理、所定の解像度・カラー・ファイル形式での保存など、真実性・見読性・検索性などの要件をすべてクリアする必要があります。
書面の契約書を電子化する場合の注意点
契約書の原本は紙のまま保存する
スキャナ保存を行った場合でも、契約書によっては「原本の保存」が法律や取引先の要望により求められるケースがあります。
特に、重要契約や長期保存が必要な書類については、紙のまま保管することが無難です。
スキャナー保存できないものもある
公正証書や登記関連書類、裁判所提出書類など、一部の文書はスキャナ保存の対象外 とされています。
これらは法令上、原本の保存や提出が義務づけられているため、電子化しても法的効力が認められない可能性があります。
印紙税の還付はできない
紙の契約書に収入印紙を貼付し、その後電子化して原本を廃棄した場合でも、すでに納付した印紙税の還付は原則として受けられません。
つまり、電子化によって過去に支払った印紙税が無効にならず、還付目的の電子化は意味がないため注意が必要です。
電子契約における印紙税に関するよくある質問
A
契約書をPDFファイルで作成し、メールなどで送受信するだけであれば、印紙税は課されません。
印紙税法では「紙に出力して作成された文書」が課税対象とされているため、データのまま契約が締結され、紙に印刷されない限り、課税文書とは見なされないからです。
ただし、PDFを印刷して署名・押印し、それを各当事者が保管する場合は、印紙税が必要になる可能性があります。
A
注文請書を電子契約としてオンライン上で取り交わし、紙に出力せずにデータのまま保管・管理している場合は、印紙税は不要です。
印紙税法においては、注文請書も「請負契約書」に該当する場合がありますが、電子的に締結された契約は「文書の作成」とは見なされず、課税文書に該当しません。。
まとめ
電子契約は、近年のデジタル化・業務効率化の流れの中で急速に普及しており、多くの企業が導入を進めています。
電子署名やタイムスタンプなどの技術により、契約の信頼性や安全性は紙契約と同等以上に確保されており、法的な証拠力も十分にあります。
また、電子契約を導入することで、印紙税の削減、郵送・印刷コストの削減、契約締結の迅速化、文書管理の効率化など、さまざまなメリットが得られます。
総じて、電子契約は今後の標準的な契約手段として、信頼性・効率性ともに高い選択肢であるといえるでしょう。適切な知識と準備をもって導入することで、企業活動の大きな武器になります。
電子契約の導入をプロに相談!
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!