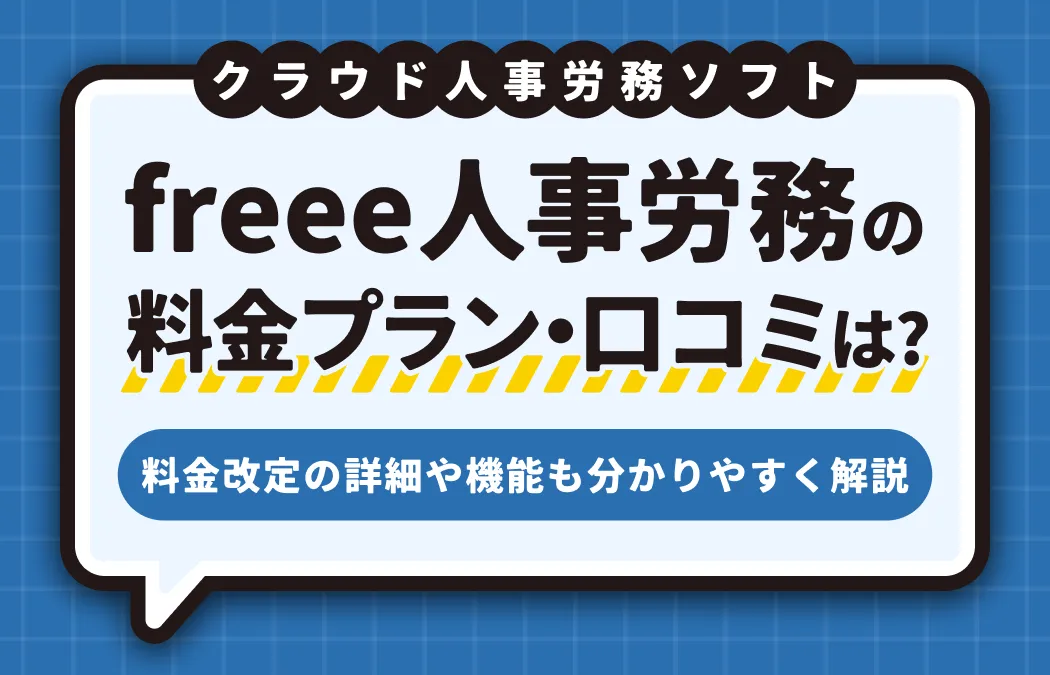「副業やアルバイト・フリーターは申告不要?」
年末調整は勤め先の会社で行い、確定申告は個人行主や副業をしている人が行うもので、どちらも「正しい納税額を確定する」ために行います。
しかし、「年末調整をしたので確定申告は必要ないのでは?」と、ご自身の納税処理方法が分からないと不安になる方もいらっしゃるでしょう。
中には、年末調整をしたけれど、確定申告が必要な場合もありますし、どちらかしか必要ではない場合もあります。
今回は、年末調整と確定申告の違いを解説しています。会社員・アルバイト・フリーター・副業・個人事業主の方、すべての方が参考にできます。
目次
▼この記事で紹介している商品
年末調整と確定申告の違いは?
年末調整は、会社員向けに簡略化された手続きであるのに対し、確定申告はより広い範囲の所得や控除を対象にした自己申告制度です。両者の目的や対象範囲が異なるため、自分の状況に応じて正しく手続きすることが大切です。
年末調整と確定申告の違い(比較表)
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きの主体 | 会社(給与支払者)が行う | 本人(納税者)が行う |
| 対象者 | 給与所得者(主に会社員) | 自営業者、フリーランス、個人事業主、副業収入がある人など |
| 手続きの時期 | 毎年11月〜12月頃 | 毎年2月16日〜3月15日 |
| 主な目的 | 所得税・住民税の精算(源泉徴収の調整) | 所得や控除額を確定させて税額を計算する |
| 必要な提出先 | 勤務先(会社) | 税務署 |
| 控除の種類 | 基礎控除、配偶者控除、扶養控除、保険料控除など(限定的) | 医療費控除、寄附金控除、雑損控除なども申請可能 |
| 対象の所得 | 給与所得のみ | 全所得(税務署から直接還付) |
| 還付の可能性 | あり(会社を通じて還付) | あり(税務署から直接還付) |
確定申告をスムーズに済ませるための5つのポイント
必要書類を早めに準備する
確定申告には、以下のような書類が必要です。
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- 医療費の領収書(医療費控除を受ける人)
- ふるさと納税の証明書
- 支払調書(副業やフリーランスの人)
- 保険料控除証明書 など
確定申告が必要かどうかを確認する
会社員でも、以下のようなケースでは確定申告が必要です。
- 副業の所得が20万円を超える
- 医療費が年間10万円以上かかった
- ふるさと納税をワンストップ特例で申請しなかった
- 住宅ローン控除の初年度
会計ソフトやアプリを活用する
freee(フリー)やマネーフォワードなどの確定申告ソフトを使えば、質問に答えるだけで申告書を自動で作成できます。 書類の提出も「e-Tax(ネット)」からそのままできるので、税務署に行かずに完結します。
-
e-Taxを使ってネットで提出する
- スマホやパソコンから提出できる「e-Tax」は、郵送よりも早く、確実に提出できます。
・マイナンバーカードとスマホがあれば簡単
・申告書の作成は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」がおすすめ
締切前に余裕をもって行動する
確定申告の 期間は 毎年2月16日〜3月15日 です。 ギリギリになると混雑したり、ミスが増えやすいので、2月中に終わらせるのが理想です。
「会計ソフト」であれば確定申告がスムーズに!
【無料】ご相談はこちらから年末調整とは?
年末調整は、 主に勤め先の会社で行うもので、年間で徴収した所得税額と正確な所得税額を照らし合わせ、過不足を精算する手続き です。
毎月の所得税は概算で徴収されるため、どうしても過不足が出てきてしまいます。
そのため、年間の所得額が確定する年末に正しい納税額を算出し、過不足分を従業員に還付または追加徴収します。
-
年末調整までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
-
12/31時点で会社に在籍している人
-
年の途中で、海外勤務により非居住者となった人
-
年の途中で退職した人※
※「年の途中で退職した人」に関しては以下に該当する場合。
|
年末調整手続きで提出が必要な書類
| 年末調整手続きで提出が必要な申告書 | 年末調整で提出が必要な控除証明書 |
|---|---|
|
|
年末調整の提出期限
-
企業側:1月31日まで
-
従業員側:11月~12月
年末調整を始める時期は、企業側であれば法律上1月31日までに提出すれば問題ありませんが、 毎年12月にしておくのが一般的 です。
一方で、従業員側は11月中旬ごろから12月にかけて、必要な書類の提出や申請を行うのが普通です。
企業によって具体的なスケジュールは異なるため年末調整と確定申告の違いを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
確定申告とは?
確定申告とは、年末調整の対象とならない、主に 個人事業主やフリーランスを含む個人が税務署に直接申告するもの です。
1月1日から、12月31日までの1年間で得た所得を税務署に申告し、その年の所得税額を確定します。
また、年末調整を受けた会社員であっても、 副収入や年末調整で処理できない控除がある場合は確定申告が必要 です。
▶確定申告ソフトを探している方はコチラもチェック
確定申告で提出が必要な書類
| 確定申告で提出が必要な申告書 | 確定申告で提出が必要な控除証明書 |
|---|---|
|
|
確定申告で提出が必要な書類は、 確定申告書と各種控除に必要な控除証明書 です。
特に、控除証明書は控除の適用を証明するための書類で、内容に不足や不備があると控除を受けることができません。
確定申告をする前に、あらかじめ必要な書類を精査して準備しておきましょう。
確定申告のご相談はこちら年末調整や確定申告で得られる控除
| 年末調整で受けられる控除 | 確定申告が必要な控除 |
|---|---|
|
|
年末調整や確定申告で得られる控除は、上記の表をご確認ください。
控除の種類によって要件や必要種類が異なる ため、自身に適用できる制度が無いか、あらかじめ確認しておきましょう。
年末調整後でも確定申告が必要なケースとは?
年末調整を受けている給与所得者でも、実は一部の人は別途、確定申告が必要となるケース があります。 以下に該当する場合は、年末調整だけでは正確な納税ができないため、確定申告が必要になります。事前に確認しておきましょう。
年末調整済みでも確定申告が必要なケース
| ケース | 説明 | チェックリスト |
|---|---|---|
| 副業の所得が年間20万円を超える | アルバイト、フリーランス、アフィリエイトなどの収入が対象。年末調整では反映されないため、申告が必要。 | □ |
| 医療費が年間10万円を超えた(医療費控除) | 家族の医療費を合算して控除対象にできるが、確定申告でしか適用できない。 | □ |
| ふるさと納税のワンストップ特例を使わなかった | 寄附先が6自治体を超えた、もしくは申請し忘れた場合は確定申告が必要。 | □ |
| 住宅ローン控除の初年度 | 初年度のみ確定申告が必要。2年目以降は年末調整で対応可能。 | □ |
| 年収2,000万円超の給与所得者 | 年末調整の対象外のため、必ず確定申告が必要。 | □ |
| 株式売買や仮想通貨などの譲渡益がある | 特定口座(源泉徴収なし)での取引は確定申告が必要。 | □ |
| 雑損控除、配当控除などの特殊な控除を受ける場合 | 年末調整では対応不可な控除は確定申告で申告する必要あり。 | □ |
-
年末調整と確定申告の両方を行う場合は源泉徴収票の紛失に注意
- 年末調整後に確定申告を行う際には、 勤務先から発行される源泉徴収票が必須書類 です。これは、1年間の給与所得とすでに源泉徴収された税額を証明するものであり、確定申告書に正確な数値を記載するために欠かせません。
年末調整と確定申告のやり方・流れ
年末調整の手続きの流れ
従業員側の手続き
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 提出書類 | ・扶養控除等(異動)申告書 ・保険料控除申告書 ・配偶者控除等申告書など |
| 提出時期 | 毎年11月〜12月上旬頃 (勤務先の指定による) |
| 追加で必要になるもの | ・生命保険・地震保険などの控除証明書 ・国民年金の控除証明書(ハガキ)など |
書類の不備があると控除が反映されないため、期限までに正確に提出しましょう。
企業(勤務先)側の流れ
- 従業員から書類を回収
- 各従業員の所得税を再計算(源泉徴収票を発行)
- 過不足を精算し、12月または1月の給与で調整
- 翌年1月末までに「法定調書」などを税務署に提出
確定申告の手続きの流れ
-
STEP.1
年間の所得金額と課税所得を確定
1年間の収入から経費を差し引き、所得金額を算出します。
さらに、そこから所得控除できるものを引き、最終的な課税所得を確定しましょう。 -
STEP.2
納税額の算出
課税所得が確定したら、所得金額ごとに決められた税率を掛けて納税額を求めます。
-
STEP.3
必要書類の準備
書類 説明 源泉徴収票 勤務先からもらう(給与所得者のみ) 控除証明書類 医療費領収書、ふるさと納税の寄附証明書など 本人確認書類 マイナンバーカード or 通知カード+身分証 その他 収支内訳書(事業所得者)、証券会社の年間取引報告書 など -
STEP.4
申告書の作成
・紙で作成する場合:国税庁のサイトから申告用紙を印刷、または税務署で入手
・オンラインで作成する場合:国税庁「確定申告書等作成コーナー」、もしくはfreeeや弥生などの会計ソフトを利用 -
STEP.5
提出方法と期間
方法 説明 郵送 作成した書類を税務署へ送付(消印有効) e-Tax オンラインで提出(マイナンバーカードまたはID・パスワード方式) 税務署へ持参 直接窓口に提出(混雑に注意) -
STEP.6
納付・還付
・納めすぎていた税金がある場合 → 還付金が1ヶ月程度で振込まれる
・不足分がある場合 → 銀行振込、コンビニ納付、口座振替などで支払う
年末調整と確定申告を両方行う際の注意点

転職や退職で確定申告が必要になるケースもある
-
12月31日時点で会社に所属していない場合
-
退職金の支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
-
失業保険の給付金は課税されない
12月31日時点で会社に所属していない場合
確定申告は、会社員として勤務している場合、退職するタイミングに注意が必要です。
年の途中で会社を退職し、その年の12月31日時点で会社に勤めていない場合 は、個人で確定申告を行う必要があります。
なお、退職して年内に再就職した場合は、新しい会社で前職分も含めて年末調整を受けられるため、確定申告が不要です。
退職金の支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
確定申告は、退職金支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、 納税額の精算のために提出が必要 です。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、確定申告は不要となります。
なお、退職金は「退職所得」に分類されるので、勤続年数に応じて一定額の所得が控除される仕組みです。
-
退職所得控除額の計算式
-
勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数
(上記計算で80万円に満たない場合は一律80万円)20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
失業保険の給付金は課税されない
失業給付は、再就職までの生活保障にあたるので、課税対象になりません。
したがって、 失業給付として受け取った分のお金に関しては、確定申告が不要 です。
-
失業給付とは
-
失業給付とは、退職者が再就職するまでの生活を支援する制度です。
退職後、一定期間が経過しても再就職先が決まらない場合は、雇用保険から失業給付を受けられます。
年末調整や確定申告の注意点

年末調整しなかった場合は個人で確定申告が必要
年末調整をしなかった場合や、期限内に必要な書類を提出できなかった場合は、個人で確定申告をする必要があります。
確定申告は税額計算等を自分で行わなければならなくなる ので、勤め先等で済ませておくのがオススメです。
自分での申告以外では控除を受けることができない
年末調整や確定申告で受けることができる控除は、 自身で必要書類の添付や申告手続きをしなければなりません。
誤った手続きをしてしまうと、税の控除ができず、節税効果が得られないため注意しましょう。
雇用主が年末調整をしなかった場合はペナルティがある
年末調整は、所得税法で定められた雇用主の"義務"となっています 。
企業が年末調整をしなければ、社員は払いすぎた税金を還付を受けられません。
そのため、企業が正しく年末調整を行っていない場合には、罰則が課せられます。
-
年末調整をしなかった場合に課される罰則
-
・年末調整をおこなわず、従業員から正しい税額を徴収しなかった場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法第242条)。
・年末調整をおこなったが、追加の徴収額を納付しなかった場合:10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方(所得税法第240条)。
確定申告をしないと控除や還付が受けられない
確定申告できちんと手続きをとらなければ、特定の控除や還付金を受けられなくなってしまいます。
申告しなくてもペナルティはありませんが、 控除や還付金を受けることで節税効果が得られる ので、使える制度は積極的に活用しましょう。
必要な申告しなかった場合ペナルティがある
確定申告の義務があるにもかかわらず、期限までに申告や納税をしなかった場合、延滞税や無申告加算などのペナルティが課されます。
無申告加算税を課される
無申告加算税とは、 確定申告の期限後に申告をした場合や、無申告であった場合に課される税金 を指します。
なお、無申告加算税の税率は、対象となる納税額によって変動します。
| 無申告加算税の金額 | |
|---|---|
| 納税額のうち50万円までの範囲 | 納税額の15% |
| 納税額が50万円を超える範囲 | 納税額の20% |
-
無申告加算税が軽減または免除されるケース
-
税務署の調査通知を受ける前に、自ら期限後申告をした場合は、無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されます。
また、期限後の申告であっても、以下のような要件を満たしている場合は、無申告加算税が免除されるケースがあります。
・申告期限後、1ヵ月以内に自主的に申告している
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する
延滞税を課される
延滞税とは、納めるべき税金を納付期限までに納付しなかった場合に追加徴収される税金 です。
確定申告が遅れた場合、納税が遅れた日数に応じて自動的に延滞税が加算されます。
なお、延滞税の最高税率は年14.6%です。具体的な金額は国税庁のウェブサイトでシミュレーションできます。
住民税にも延滞税が課される可能性がある
個人事業主やフリーランスは、 所得税の確定申告をすると住民税の納付書が送られてくる ようになっています。
万が一確定申告をしなかった場合、住民税の納付書が送られてこないので、知らぬ間に滞納してしまうリスクがあります。
住民税に関しても、納付期限を過ぎると延滞税が課されてしまうので注意が必要です。
「還付申告」すれば払いすぎた所得税の還付が受けられる
還付申告とは、確定申告をすることで、 払いすぎてしまった税金の還付を受けられる制度 です。
下記の要件に当てはまる方は、還付を受けることができるため、確認しておきましょう。
-
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
-
適用対象となる控除に関して、なんらかの事情で年末調整を受けられなかった場合
-
控除の申告を忘れてしまった場合
-
年末調整で控除できない控除の確定申告を忘れてしまった場合
アルバイト・フリーターの年末調整と確定申告

アルバイトやフリーターも年末調整の対象になる
年末調整は、アルバイトやフリーターであっても、会社から給料を支給されている場合は、 申請の対象となります。
また、家族の扶養内で働いている方も、年末調整の対象となるので、書類の記入・提出が必要です。
-
12月31日まで勤め先に在籍している
-
年末調整の申告書を会社に提出している
-
1つの会社だけで働いている
確定申告をしなければいけないケース
会社で年末調整が行われていない、または提出が遅れた場合
会社が年末調整を行わなかった場合や、期限までに書類を提出できなかった場合、 年収103万円以上の方に関しては確定申告が必要 です。
また、給与が8万8000円を超えた月があった場合は、年収が103万円以下でも、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
複数のアルバイトを掛け持ちしている
2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている場合は年間の合計所得を計算し、確定申告を行いましょう。
なお、納税額は、すべての勤務先で得た給与から給与所得控除などを差し引いた、年間所得をもとに計算します。
ただし、 すべての給与を合わせても、年収103万円を超えない場合は確定申告が不要 です。
年末前にアルバイトを辞めている
年末調整の対象となるのは、12月31日時点で会社に在籍している従業員のみです。
年収が103万円を超えており、年末前にアルバイトを辞めた場合は、個人で確定申告を行う必要があります。
-
年末調整のある勤務先を選ぶ
-
年の途中で勤め先を辞めない
-
年収103万円以下に収める
必要な確定申告をしないとどうなる?
所得税の還付が受けられなくなる
確定申告をすることで、年収103万円以下の方でも、所得税の還付を受けられるケースがあります 。
確定申告をしなければ、損をしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
無申告加算税や延滞税がかかることも
確定申告の義務があるにもかかわらず、期限内に手続きをしなかった場合、 無申告加算税や延滞税が課せられます。
なるべく無駄な出費をしないためにも、必要な手続きを見落とさないように注意しましょう。
確定申告をしたほうがお得になるケースもある
確定申告することで、年収が103万を超えない場合も、控除の対象となる ケースがあります。
下記に当てはまる方は、年末調整だけでなく確定申告を受けた方がお得になるため、検討しておきましょう。
-
翌年以降の所得控除:1年を通して月の収入が8万8000円以下だった方で、株式や為替などで大きな損失が出た場合
-
医療費控除:年間10万円以上の医療費を払った場合
学生アルバイトは勤労学生控除が受けられることもある
一定の条件を満たす学生であれば、年収が103万円を超えた場合も「勤労学生控除」を受けられます。
勤労学生控除を受けるには、確定申告書や年末調整の該当欄にチェックを入れ、「在学証明書」を添付します。
ただし、 親の扶養に入っている場合、年収103万円を超えると親の扶養控除がなくなり、税金が上がってしまう ので注意が必要です。
年末調整・確定申告のよくある質問
A
年末調整と確定申告を両方やるのは、特定の控除を受ける人や給与所得以外の収入が一定以上ある方です。
なお、年末調整と確定申告はそれぞれ異なる目的と手続きがあるため、重複した申告をしないよう注意しましょう。
A
その年の所得が全て給与所得であり、特定の控除を受ける必要がない場合、確定申告をする必要はありません。
ただし、兼業をしている方や事業所得がある方、特定の控除を受ける方は確定申告が必要になります。
A
基本的に会社で年末調整の手続きをした場合は個人での確定申告は不要です。
ただ、副業や兼業等で他に所得がある場合や医療費控除などがある場合は確定申告の必要があります。
A
年末調整は会社員の確定申告の手続きを不要にする制度でもあるため、どちらかで手続きをする必要があります。
申告漏れは脱税となり、ペナルティが課せられる可能性があるので注意しましょう。
A
税務署が市区町村に照会をした場合、扶養家族の年収が103万円以上ということがバレます。
A
課税対象額が1000万円を超えると税務調査に入られやすくなります。
ただ、明確な基準はないので、確定申告の対象の方は速やかに手続きをしましょう。
A
ネットオークションでの個人売買などの売上は、原則確定申告の対象になりません。
課税対象となる基準は「事業として収益を得ているか」です。
不用品の処分が目的の場合は、非課税となります。
A
年末調整と確定申告における税率は基本的に同じです。
ただし、個人事業主やフリーランスの場合、所得から経費を差し引いた金額が課税対象となります。
A
年末調整や確定申告を一切行わなかった場合、無申告加算税や延滞税を課されてしまう可能性があります。
必要な手続きさえとれば、納税額が上乗せされることはないので、期限内に必要な申請を完了させましょう。
A
給与以外の所得が年間で20万円を超えない場合、基本的に確定申告は不要です。
A
源泉徴収される所得税額は、基本的に概算で算出されているため、過不足が生じてしまいます。
そのため、年末調整で年間の徴収額を再計算し、払いすぎた税金がある場合は還付されるという仕組みです。
A
源泉徴収とは、会社が毎月の給与から従業員が支払う税金を差し引き、まとめて納税する制度です。
源泉徴収をすることで、個々の社員は自身の所得税分を確定申告せずに済みます。
まとめ
年末調整と確定申告の違いは、対象者や申告期間、処理できる控除などがあります。
両方の手続きが必要になるケースもある ため、控除なども含め自身に該当するものがないか確認しましょう。
特に、確定申告に関しては、期限内に手続きをしなければペナルティが課される可能性もあるので注意が必要です
▶確定申告をもっとカンタンに!会計ソフトの導入を検討している方はコチラ


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!