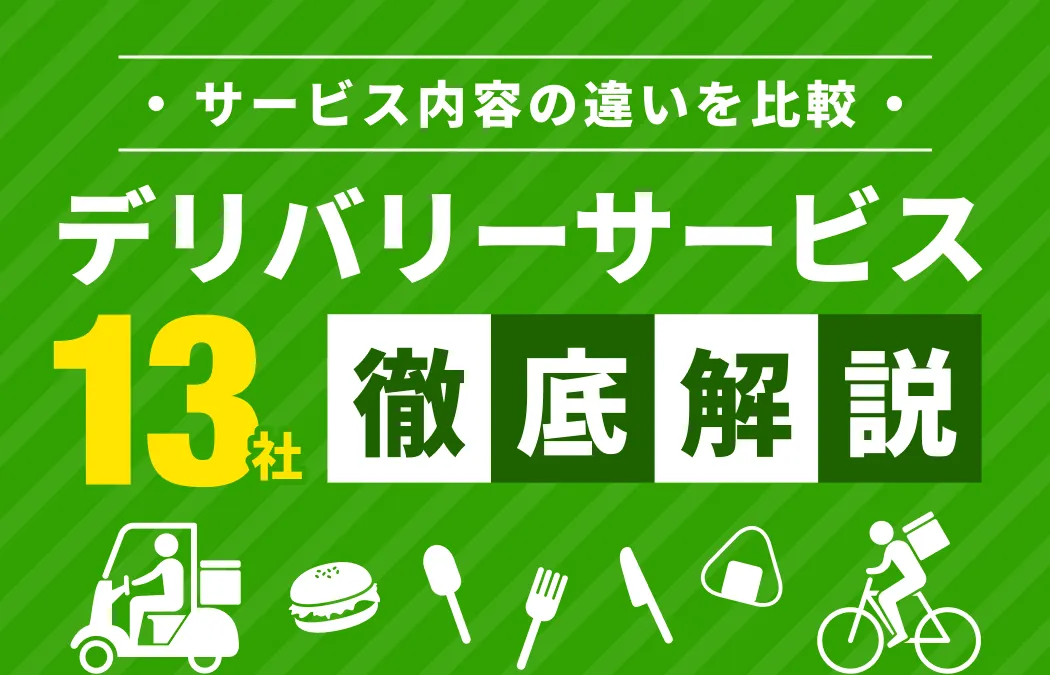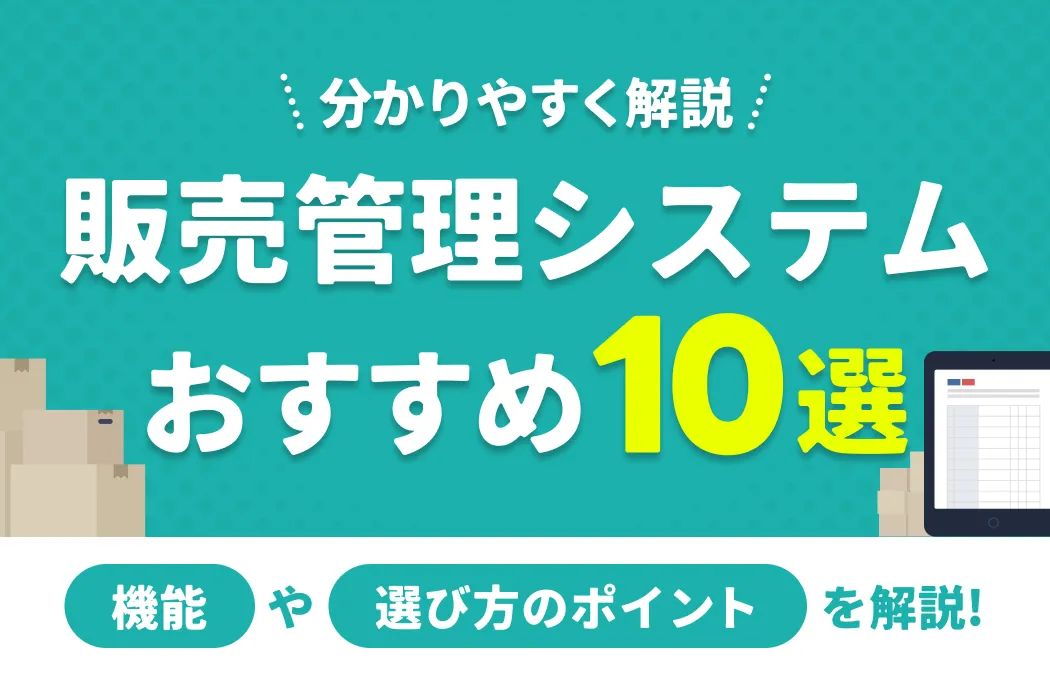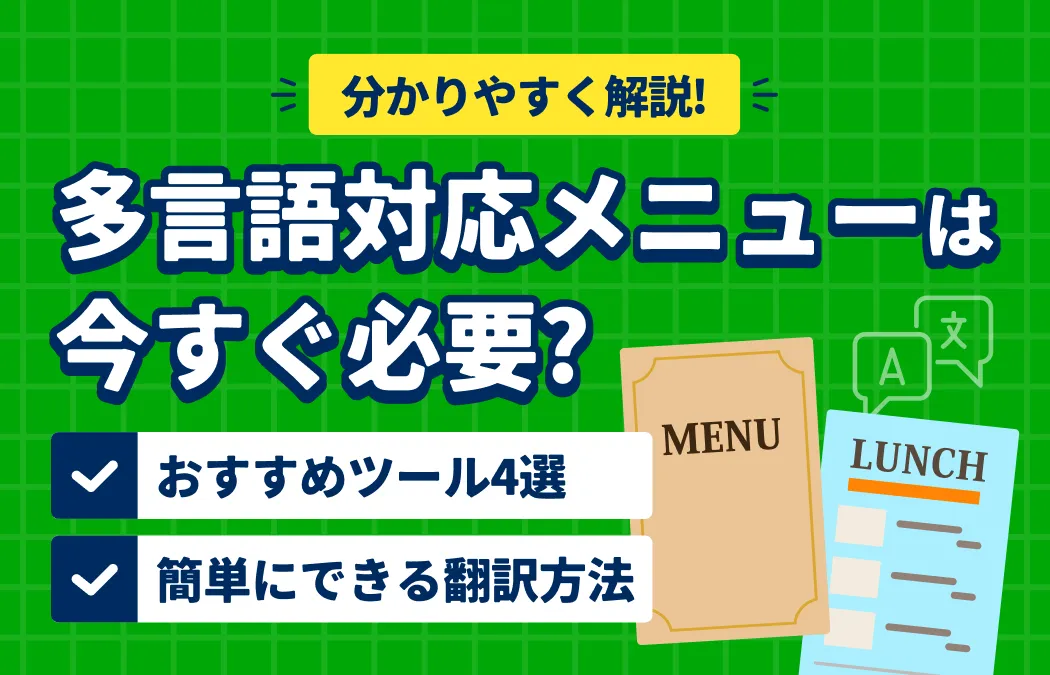「キャッシュレス決済との違いは?」
電子決済は、現金を使わず、スマートフォンやカードなどの電子的な手段で支払いを行う方法です。
しかし、「クレジットカードも電子決済に含まれる?」「手数料の相場は?」など、疑問も多いでしょう。
本記事では、電子決済の種類や店舗への導入メリット・デメリット、手数料の相場などを解説します。
【無料】電子決済のお問い合わせはこちら
目次
電子決済とは?基本を解説
電子決済とは
電子決済とは、 スマートフォンやICカード、クレジットカードなどの電子的な手段で商品やサービスの代金を支払う方法 です。
現金を使わずに、オンラインや店舗で素早く安全に決済が可能です。
電子決済の普及状況
日本では、以前は現金志向が強かったものの、 近年では急速に電子決済が普及 しています。
特に2020年の新型コロナウイルスの影響を受け、非接触での決済が求められるようになり、多くの店舗が電子決済に対応しました。
また、政府も「キャッシュレス・ビジョン」に基づき、キャッシュレス決済比率を2025年までに40%にするという目標を掲げています。
現在では、コンビニやスーパーはもちろん、個人経営の飲食店や病院などでも電子決済が可能となり、地方でも利用者が増加しています。
電子決済が推進されている理由
- 衛生面の配慮
現金を直接やり取りしないため衛生的であり、感染症対策としても効果的です。特に新型コロナ以降、この理由から電子決済の導入が一気に進みました。 - 業務効率化
店舗側にとっては、現金の管理が不要になり、レジ締めや入金作業の負担が軽減されます。さらに、売上データを自動的に記録できるため、経理業務の効率化にもつながります。これらは人員不足への対策にもつながります。 - インバウンド需要への対応
海外は日本以上にキャッシュレス化が進んでおり、訪日観光客は電子決済を好む傾向にあります。インバウンド需要に対応し、消費を促すするためにも、導入が求められています。 - 現金決済に関するコストの削減
ATMの設置や運営など、現金決済インフラの維持・管理には、コストがかかるため、これらを削減するためには、電子決済への移行が有効です。また、電子決済にすることで現金の偽造や盗難も防止できます。
電子決済の代金が入金される流れ
- 消費者が電子決済で支払うと、その決済情報がシステムを通じて処理され、決済代行業者やカード会社などを経由して、店舗側に「売上」として通知されます。
- その後、数日から数週間の間に、決済事業者から店舗の銀行口座に入金されます。この間に手数料が差し引かれる場合もあります。
例えば、クレジットカードの場合は通常、決済日から約1か月後に入金されるケースが多いです。
電子決済とキャッシュレス決済の違い
電子決済とキャッシュレス決済はほぼ同じ意味で使われますが、厳密に言うと、 キャッシュレス決済は現金を使わない決済手段の総称であり、電子決済はその一部 です。
電子決済は、物理的な現金を介さずに、電子的なデータを使って決済を行う方法を指します.
一方、「キャッシュレス決済」は、現金を使わないすべての決済方法を指し、電子決済だけでなく、商品券やプリペイドカードでの支払いも含まれます。

編集部
電子的に処理されるかどうかが両者の違いといえるでしょう。

電子決済の種類
| 特徴 | 代表的なサービス | |
|---|---|---|
| クレジットカード |
|
Visa、Mastercard、JCB、American Express |
| デビットカード |
|
J-Debit、Visaデビット、Mastercardデビット |
| プリペイドカード |
|
Suica、PASMO、nanaco、WAON、楽天Edy |
| QRコード決済 |
|
PayPay、楽天ペイ、d払い、メルペイ |
| 電子マネー |
|
ID、QUICPay |
| ネットバンキング |
|
楽天銀行、住信SBIネット銀行、ゆうちょ銀行 |
| キャリア決済 |
|
d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い |
クレジットカード
クレジットカードは、利用者が商品やサービスを購入する際に 代金を一時的にカード会社が立て替え、後日まとめて支払う「後払い」の決済手段 です。
多くのカードにはポイント還元や分割払いなどの機能があり、利便性が高いのが特徴です。セキュリティ面でも不正利用補償などの制度が整っています。
また、「Apple Pay」や「Google Pay」などと連携することで、スマートフォンによるタッチ決済にも対応します。
デビットカード
デビットカードは、 銀行口座と連動しており、決済と同時に口座から即時で引き落とされる仕組み です。
ネットショッピングや実店舗でも使え、セキュリティ対策も強化されています。使いすぎを防げる点や、リアルタイムで支出管理ができるのが大きなメリットです。
クレジットカードと違い、与信審査が不要なため、未成年や学生、高齢者なども比較的簡単に利用できます。
プリペイドカード
プリペイドカードは、 あらかじめチャージ(入金)した金額の範囲内で使用できる前払い型のカード です。
利用時は専用端末にカードをかざすだけで支払いが完了し、スムーズな取引が可能です。
コンビニや駅、スマホアプリで簡単にチャージできる点も魅力です。
QRコード決済
QRコード決済は、 スマートフォンアプリを使ってQRコードを読み取ることで支払い が行える方法です。
ユーザーは銀行口座やクレジットカードとアプリを連携し、必要に応じて残高をチャージして使います。
店舗のコードを読み取る「読み取り型」や、自分のコードを提示する「提示型」があり、小規模店舗から大手チェーンまで幅広く対応しています。
利用額に応じたポイント還元やキャンペーンも魅力です。

電子マネー
電子マネーは、 ICカードやスマホなどを決済端末にかざし、事前にチャージした残高で支払う 非接触型の決済方法です。
タッチするだけで決済が完了するため、スピーディーかつ簡単に支払いができます。

ネットバンキング(口座振込・口座振替)
ネットバンキングは、 インターネットを利用して銀行の口座から直接振込や振替を行うサービス です。スマホアプリやPCから24時間いつでも手続きが可能。
公共料金の引き落とし、ネットショッピングの支払い、定期的な会費の口座振替など、用途はさまざまです。
クレジットカードを使いたくない人や、高額決済時に安心感を求める人に選ばれています。
キャリア決済
キャリア決済は、決済した商品やサービスの代金を、携帯電話会社の利用料金とまとめて支払いできる決済方法です。
スマホでアプリやデジタルコンテンツ、ネットショッピングの 代金を支払うと、その金額が月々の携帯料金と合算されて請求されます 。
クレジットカードや銀行口座の登録が不要なため、若年層やクレジットカードを持たない人にも人気があります。
電子決済の支払い方法
前払い(プリペイド型)
プリペイド型は、 あらかじめチャージ(入金)しておいた金額の範囲内で支払いを行う方式 です。
交通系ICカード(Suica、PASMO)やプリペイド式の電子マネー(楽天Edy、WAON、nanacoなど)が代表的なサービスとして挙げられます。
- 事前に必要な額だけ入金することで、使いすぎを防げる
- 残高が不足すると都度チャージが必要になり、利用時に手間がかかる
即時払い(デビット型)
デビット型は、 支払い時に即座に銀行口座から引き落とされる決済方式 です。
代表的なものに「J-Debit」や、Visaデビット、Mastercardデビットなどがあります。また、PayPayなどQRコード決済のオートチャージも該当します。
- 口座残高の範囲でのみ利用でき、使いすぎを防止できる
- 銀行口座の残高が不足していると利用できないため、残高の管理が必要
後払い(ポストペイ型)
ポストペイ型は、利用者の 支払いを決済会社が一時的に立て替え、後から一定期間分の利用額をまとめて精算する方式 です。
代表的なものにクレジットカードや、携帯キャリア決済(PayPayあと払い、d払いの後払いサービスなど)があります。
- 毎月の利用額がまとめて請求されるため、一時的に手持ちの現金がなくても支払いが可能
- ポイント還元や分割払いなどの特典も魅力
- 支払い能力を超えた利用をしてしまうリスク
- 分割払いやリボ払いで利子や手数料が発生し、割高になる可能性
店舗に電子決済を導入するメリット
販売機会の拡大と機会損失の防止
電子決済を導入することで、 キャッシュレス派の消費者にも対応でき、顧客層の拡大と販売機会の損失防止 に繋がります。
特に若年層や外国人観光客、スマホ決済に慣れた利用者にとって、電子決済対応の有無は来店動機の一つになります。
現金しか使えない店舗では「買いたいけど手持ちが少なくて支払えない」という状況が発生する可能性があり、これが「機会損失」につながります。
多様な決済手段を用意することで、より多くの顧客にアプローチでき、結果として売上の増加が期待できます。
レジ業務や売上管理の効率化
電子決済は金銭の受け渡しが不要なため、レジ業務がスムーズになります。 現金の数え間違いやお釣りの受け渡しミスも減少し、スタッフの負担を軽減 。
また、多くの電子決済サービスは売上データを自動で記録してくれるため、手動での集計作業が不要になり、会計や日次レポート作成が効率化されます。
帳簿管理や経理処理もデジタル化されることで、全体の業務時間短縮やヒューマンエラーの削減にもつながります。
客単価が向上する
電子決済を導入すると、現金の所持額にとらわれずに商品を購入できるため、 顧客が「ついで買い」をしやすくなり、1回あたりの購買額(客単価)が向上する傾向 にあります。
特にクレジットカードやQRコード決済では、ポイント還元などの特典があるため、より多くの商品を購入しようとする心理が働きやくなるのです。
また、決済サービスのキャンペーンや値引きプロモーションと組み合わせることで、より一層の売上拡大が期待できます。
未収金発生の防止ができる
電子決済は即時決済が基本のため、 「後で払う」「ツケ払い」といった未収金の発生を未然に防ぐ ことができます。
特にサービス業や個人経営の店舗では、現金のやり取りによる貸し倒れや支払い忘れのリスクがありますが、電子決済ならその心配がありません。
決済が完了した時点で売上が確定するため、資金管理やキャッシュフローの面でも安定します。
こうした透明性とスピード感は、経営の健全化にも大きく寄与します。リピーターを獲得しやすくなる
多くの電子決済サービスでは、利用履歴やポイント制度があるため、顧客が「またこの店で買いたい」と感じやすくなります。
たとえば 「PayPay」や「楽天ペイ」では、支払い時にポイントが貯まるため、リピーター獲得の大きな武器 となります。
さらに、アプリを通じたクーポン配布やプッシュ通知など、販促機能も充実しており、顧客との接点を維持しやすくなります。
定期的な来店を促すことで、安定した売上が見込めます。
インバウンド需要に対応できる
キャッシュレス決済の導入は、訪日外国人観光客(インバウンド)への対応として非常に重要です。
外国人の多くは自国でキャッシュレス決済を日常的に利用しており、特に 中国や韓国、欧米諸国の旅行者は現金よりもクレジットカードやQRコード決済を好む傾向 があります。
キャッシュレス決済に対応しスムーズな支払いを実現することで、外国人観光客の消費が促され、売上の機会損失を防ぐげるほか、客単価アップにもつながります。
また、現金両替の手間を省き、観光客の利便性を向上させることが可能です。
店舗に電子決済を導入するデメリット・注意点
決済手数料がかかる
電子決済を導入すると、1回の取引ごとに決済手数料が発生します。
手数料の割合は決済方法やサービス提供会社によって異なりますが、 一般的に売上の数%(2〜5%程度)が差し引かれます 。
特に、小規模店舗や利益率の低い商品を扱う事業者にとっては、コスト負担が無視できません。
手数料を抑えるには、複数の決済サービスを比較検討し、最適なプランを選ぶことが大切です。
導入コストがかかる
電子決済を始めるには、 決済端末や専用アプリ、インターネット環境などの初期投資が必要 です。
特にクレジットカード対応の端末は1台数万円かかる場合もあり、導入をためらう店舗も少なくありません。
また、決済システムの導入に伴い、スタッフの教育やオペレーションの変更も必要です。
システムの不具合や通信トラブル時は決済できないリスク
電子決済はインターネットや通信回線を介して行われるため、システム障害や通信トラブルが発生すると、決済が一時的に利用できなくなるリスクがあります。
特に 繁忙時に決済ができなくなると、顧客満足度の低下や販売機会の損失につながりかねません 。
また、端末のバッテリー切れやアプリの不具合など、機器側のトラブルにも備える必要があります。
そのため、現金や他の決済手段と併用するなど、リスク分散が求められます。
高額な取引では利用できない決済方法もある
電子決済の中には、 1回あたりの利用限度額が設定されているものもあります 。
たとえば、プリペイド型の電子マネーやQRコード決済では、チャージ上限があるため、高額商品の購入には向かないことがあります。
また、顧客側のクレジットカード利用枠の問題で、決済が承認されないケースもあります。
高額商品を扱う業種では、複数の決済手段を用意しておくことが重要であり、場合によっては現金決済を併用する対応も必要です。
現金化に時間がかかる
電子決済は、売上が即座に口座へ入金されるわけではありません。 サービスによっては、入金までに数日から1週間、場合によっては月1回の入金など時間がかかることがあります 。
特に小規模店舗や資金繰りがタイトな事業者にとっては、現金が手元に入るまでのタイムラグが経営上の負担となることもあります。
即日または翌営業日入金が可能なサービスもあるため、選定時には入金サイクルの確認が重要です。
電子決済の導入方法
決済機関と直接契約する
電子決済を導入する方法の一つに、 クレジットカード会社や銀行などの決済機関と直接契約を結ぶ方法 があります。
- 手数料を比較的低く抑えられる
- トラブル発生時の対応が早いなど、直接的なやり取りによる信頼性が高い
- システムの構築や運用に一定の知識とコストが必要になる
- 加盟店として正式に登録される必要があり、審査や手続きに時間がかかることも
決済代行会社を利用する
決済代行会社は、 各決済機関との間に立ち、契約やシステム連携を一手に引き受けてくれます 。
特に中小企業やスタートアップにとっては、専門知識がなくても簡単に始められる点が魅力です。
- 複数の決済手段を一括で導入できて手軽
- 導入の手続きに手間がかからない
- 手数料がやや高めに設定されている場合がある
店舗に導入する電子決済サービスの選定ポイント
ユーザー層とユーザー数
電子決済サービスを選ぶ際には、 店舗の主な顧客層が利用している決済手段と一致しているかを確認する ことが重要です。
例えば、若年層が多い店舗であれば、スマートフォンで使えるQRコード決済や電子マネーの導入が有効です。
一方、年齢層が高い場合は、クレジットカードや交通系ICカードの方が受け入れられやすい傾向にあります。
顧客が利用しやすい決済手段を導入することで、会計のスムーズ化と顧客満足度の向上につながります。
導入費用や手数料は適切か
電子決済導入においては、初期費用や月額利用料、取引ごとの手数料など、トータルコストを把握することが大切です。
手数料が高すぎると利益を圧迫する可能性があります。 売上規模や利用頻度に応じたプランを比較し、費用対効果を重視 して選びましょう。
また、キャンペーンなどで初期費用が抑えられるサービスもあるため、タイミングの見極めも重要です。
-
サービスごとの決済手数料
-
クレジットカード 3.0%〜4.0%程度 デビットカード 1.5%〜3.0%程度 プリペイドカード 2.5%〜3.5%程度 QRコード決済 1.5%〜3.25%程度 電子マネー 3.0%〜3.75%程度 ネットバンキング 0円〜数百円/件(固定手数料) キャリア決済 5.0%〜10.0%程度
オペレーションしやすいか
店舗の規模や業態により、適した端末や操作方法は異なります。操 作が複雑だったり、決済に時間がかかると、レジ業務が滞り、顧客満足度の低下につながります 。
例えば、小規模店舗では持ち運びやすくてコンパクトな端末、大型店や固定レジがある店舗では据え置き型端末が適しているでしょう。
実際にデモ機での操作体験ができる場合は、スタッフの習熟度や業務フローとの相性を確かめることが望ましいです。
端末の種類:「据え置き型」と「モバイル型」
電子決済端末は大きく「据え置き型」と「モバイル型」に分類されます。
- 据え置き型:カウンターに固定設置され、高い処理性能が特徴。大型店舗やレジ台数が多い場所に適しています。
- モバイル型:持ち運びが可能で、イベント出店やテーブル会計が必要な飲食店など、柔軟な運用が求められる業態に最適。
トラブル時のサポート体制
電子決済は機器や通信トラブルが発生する可能性があるため、迅速かつ的確なサポート体制が整っているかは重要な選定ポイントです。
例えば、 24時間365日のサポートや日本語対応のコールセンターがあるか、訪問対応や代替機の提供など具体的な支援体制があるかを事前に確認 しましょう。
また、FAQやチャットボットなど、自己解決できる情報提供の有無もチェックポイントです。信頼できるサポートがあることで、安心して導入・運用できます。
対応している決済手段
導入するサービスが対応している決済手段の幅広さも重要です。
クレジットカードだけでなく、電子マネーやQRコード決済への対応も検討しましょう。
多様な決済手段に対応していれば、より多くの顧客ニーズに応えられ、売上アップにつながります 。
入金サイクル
電子決済では、売上金が店舗の口座に振り込まれるまでの「入金サイクル」も重要なポイントです。
入金の頻度はサービスによって異なり、即日〜月1回まで様々です。 資金繰りに直結するため、特に小規模事業者にとっては早期入金が可能なサービスを選ぶと安心 です。
また、入金手数料の有無や最低振込額の設定も確認しておくべきです。運転資金の流れに影響を与えないよう、入金条件をよく比較しましょう。
サービスによっては入金手数料が発生
入金手数料とは、決済代行会社やサービス提供元が売上金を店舗の銀行口座に振り込む際に発生する手数料のことです。
相場としては、1回あたり200円〜500円程度が一般的 ですが、振込金額の大きさや回数によって異なる場合があります。
また、一定額以上の売上で無料になるケースや、特定の銀行を指定口座にすることで手数料が優遇されるケース、「月1回まで無料でそれ以降は有料」という設定などもあります。
【顧客向け】電子決済のメリットとデメリット
【顧客向け】電子決済のメリット
- 現金の持ち歩きが不要で利便性が高い
- 支払いがスムーズに行える
- 決済履歴を確認・管理しやすい
- ポイントでおトクに買い物できる
- タッチやQRコードで非接触決済ができて衛生的
【顧客向け】電子決済のデメリット
- 決済方法によってはチャージの手間がかかる
- 使いすぎてしまうリスク
- 不正利用のリスク
- バッテリー切れや通信障害があると利用できない
- 店舗によっては利用できない決済手段がある
まとめ
電子決済とは、現金を使わずに商品やサービスの代金を支払う方法で、クレジットカードやQRコード、電子マネーなど多様な手段があります。
近年はスマートフォンの普及や非接触ニーズの高まりにより急速に広まり、消費者・店舗双方にとって利便性の高い決済手段となっています。
店舗にとっては業務効率化や売上拡大、顧客にとってはポイント還元やスムーズな支払いが魅力です。
電子決済の導入相談はこちら!
【無料】お問い合わせはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!