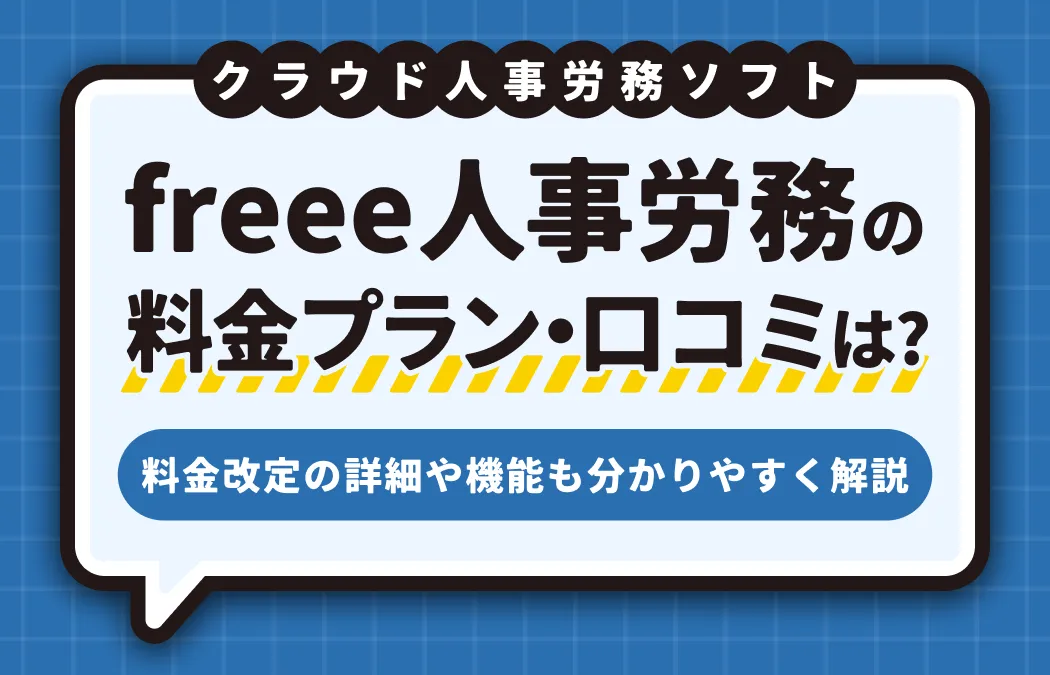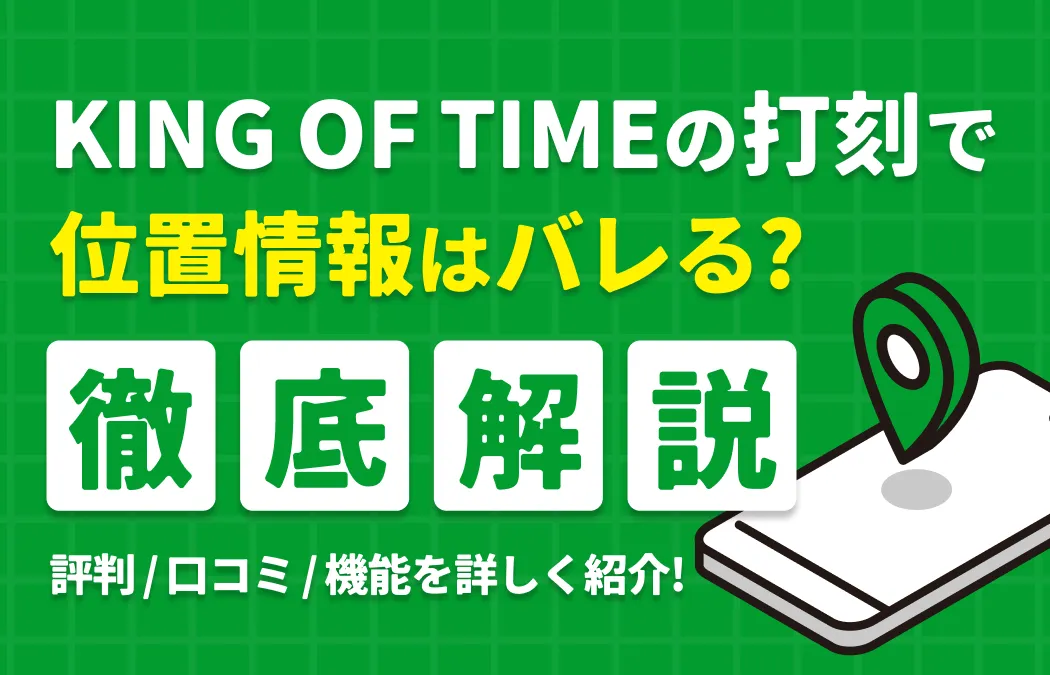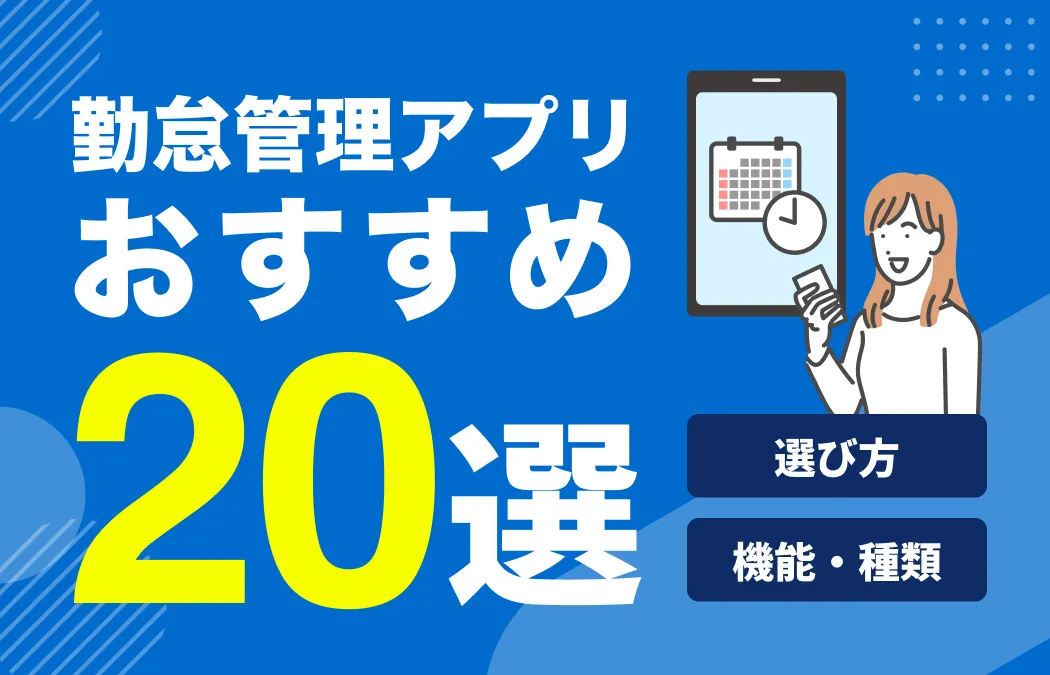「最新の法律改正はどんな内容なの?」
「条文を読んでもいまいち分からない」
電子契約の導においては、法的な要件を満たすことが不可欠です。
しかし、電子契約に関する法律は複雑多岐にわたっており、専門知識がないと理解が難しいという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、専門用語を避け、電子契約を利用する際に知っておくべき法律をわかりやすく解説します。
最新の改正点や実際の裁判例、厳選の電子契約システムもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
▼この記事で紹介している商品
電子契約とは「契約書を電子化して締結するもの」
電子契約とは「契約書を電子化して締結するもの」
電子契約とは、従来の紙の契約書に代わって、 電子データ化された契約書や電子署名、電子印鑑を用いて行う契約 のことです。
電子契約を用いることで、時間や場所の制約を受けずに契約を結ぶことができ、契約手続きの効率化やコスト削減につながります。
法令上の電子契約の定義
法令上も、電子署名法などの規定に基づき、紙の契約書と同様の法的効力を持つことが認められています。

この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。
電子委任状法2条2項
電子契約の成立要件
電子契約が有効に成立するためには、電子署名法、電子帳簿保存法、e-文書法といった法律で定められた要件を満たす必要があります。
1. 電子署名法で定められた要件
電子署名法は、電子署名を使った契約の有効性を定めた法律です。
電子契約で重要なのは、 契約内容が改ざんされていないことと、契約を結んだ人が本人であることを証明できること です。
- 本人確認: 電子署名によって、契約を結んだ人が本当に本人であることを確認すること。
- 改ざん防止: 電子署名によって、契約書の内容が後から改ざんされていないことを確認できること。
2. 電子帳簿保存法で定められた要件
電子帳簿保存法は、電子データで書類を保存する際のルールを定めた法律です。
電子契約で締結した契約書を電子データで保存する場合、この法律のルールに従う必要があります。
- 保存方法:いつでも内容を確認できるよう、適切な方法で保存すること。
- 検索性:必要なときにすぐに探し出せるように、検索機能などを備えておくこと。
3. e-文書法で定められた要件
e-文書法は、電子データで文書を保存する際に、その文書が正しく保存されていることを保証するための法律です。
- 読みやすさ:いつでも内容を確認できるよう、読みやすい形式で保存すること。
- 改ざん防止:一度作成したら、後から勝手に変更されないように保護すること。
- 機密性: 不正なアクセスや漏洩から守られていること。
- 検索性: 必要なときにすぐに探し出せるように、検索機能などを備えておくこと。

編集部
各法律の詳細や条文は、記事後半で解説します。
電子署名の仕組み
電子署名は、 ハッシュ値という「指紋」と、公開鍵・秘密鍵という鍵の仕組みを使って、文書の改ざんを防ぎ、作成者を特定 します。
文書の正当性は大きく分けて4つのステップで証明されます。
-
STEP.1
書類の「指紋」を作る
まず、電子文書をコンピュータが処理しやすい形に変換し、その特徴を表す「ハッシュ値」という文字列を作ります。これは、文書の「指紋」のようなもので、元の文書が少しでも変わると、このハッシュ値も必ず変わります。
-
STEP.2
「指紋」を暗号化する
次に、このハッシュ値を特別な鍵を使って暗号化します。鍵には、公開鍵と秘密鍵の2種類があります。公開鍵は誰でも使える鍵で、秘密鍵は本人しか持っていません。
-
STEP.3
暗号化した「指紋」を文書に添付
暗号化したハッシュ値を、元の文書に添付します。
-
STEP.4
受け取った相手が確認する
文書を受け取った人は、添付された暗号化したハッシュ値を、公開鍵を使って復号します。そして、復号したハッシュ値と、受け取った文書から新たに作ったハッシュ値を比較します。
もし、両方のハッシュ値が一致すれば、以下のことが証明できます。
✓ 文書が改ざんされていない:もし文書が途中で改ざんされていたら、新しく作ったハッシュ値と、添付されていたハッシュ値は一致しません。
✓ 文書を作成した人が本人である: 秘密鍵は本人しか持っていないため、この鍵を使って暗号化されたハッシュ値は、本人しか作成できません。
なぜ「電子証明書」が必要なのか?
万が一、悪意のある人が本人のふりをして偽の文書を作成し、本物の公開鍵と一緒に送ってきた場合、電子契約の信頼性は担保されません。
そこで登場するのが「電子証明書」です。 電子証明書は、信頼できる第三者機関が発行するもので、公開鍵が本当に本人のものであることを保証 してくれます。
紙契約のトラブルを解決!電子契約を導入する8つのメリット
電子契約は、コスト削減、時間短縮、業務効率化など、様々なメリットをもたらします。
特に、 リモートワークの普及やペーパーレス化の流れの中で、その重要性はますます高まっています 。
1. コスト削減
紙契約でよくあるトラブル「印刷・郵送費などのコストがかさむ」電子契約なら…- 印紙税不要: 電子契約は印紙税の対象外です。
- 事務費削減:印刷費、郵送費、保管費用などが削減できます。
2. 時間短縮
紙契約でよくあるトラブル「契約が遅れてしまう」電子契約なら…
- スピーディーな契約:インターネットで簡単に契約手続きが完了します。
- 業務効率化: 事務作業の削減により、他の業務に集中できます。
3. 管理の効率化
紙契約でよくあるトラブル「契約書が紛失したり、情報が漏れたりする」電子契約なら…
- データ化: 契約書を電子データで管理することで、検索や保管が容易になります。
- セキュリティ強化:契約書を安全に保管し、不正アクセスを防ぎます。
4. リモートワーク対応
紙契約でよくあるトラブル「契約書のやり取りに時間がかかる」電子契約なら…
- 場所を選ばない: 場所を選ばずに契約手続きが可能になります。
- テレワーク推進: リモートワーク環境下でもスムーズな契約締結が可能です。
5. 契約管理の強化
紙契約でよくあるトラブル「契約書の監査に時間がかかる」電子契約なら…
- 契約期限の通知: 契約更新時期を忘れずに通知できます。
- 契約履歴の管理: 過去の契約内容を簡単に検索・確認できます。
6. 契約書作成の効率化
紙契約でよくあるトラブル「入力ミスや内容の抜け漏れがある」電子契約なら…
- テンプレート活用: 既存の契約書を参考に、新しい契約書を簡単に作成できます。
- 検索機能: 類似の契約書を簡単に探し出すことができます。
7. コンプライアンス強化
紙契約でよくあるトラブル「契約内容が矛盾する」電子契約なら…
- 改ざん防止: 電子署名などにより、契約書の改ざんを防ぎます。
- 監査対応: 契約履歴を正確に記録し、監査に対応できます。
8. 環境負荷の軽減
- ペーパーレス化:紙の使用量を減らし、環境に配慮できます。
電子契約を利用する際に知っておくべき法律一覧
電子契約の法的効力に関する法律

相手企業に電子契約を提案する際、「法的な根拠」を問われることが多いです。電子契約が法的に有効である理由を理解し、相手に的確に説明できるようになりましょう。
民法「契約の形式は問わない」
契約は 書面だけでなく、口頭でも有効に成立 します(民法522条2項)。
しかし、裁判で証拠とするには、民事訴訟法228条1項に基づき、真正性を証明する必要があります。
民事訴訟法「書面契約の有効性は、二段の推定によって証明される」
従来の書面契約では、 実印を押すことで、その契約が本人の意思によって行われたことを証明 し、契約の有効性を担保していました。
この仕組みを「二段の推定」といいます。
- 1段階目の推定(経験則に基づく推定)
まず、契約書に押された実印が、本人のものであることが確認できれば、その印鑑は本人によって押されたものと推定されます。これは、長年の慣習や経験則に基づく推定です。 - 2段階目の推定(法律による推定)
1段階目の推定に基づき、本人の意思によって印鑑が押されたと認められれば、その契約書は、真正に成立したと推定されます。この考え方は、民事訴訟法228条4項に明記されています。
電子署名法「電子署名で契約の有効性を証明できる」
従来の書面契約では実印が重要でしたが、電子契約では電子署名がその役割を担います。
電子署名法3条では、 電子署名が付与された電子契約は、本人が作成したものであると推定される と定められています。
つまり、電子署名があることで、その契約が本人の意思によって行われたとみなされるのです。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
引用元:電子署名法3条
IT書面一括法
IT書面一括法は、簡単に言うと、「紙の書類を顧客の同意を得て、メールなど電子的な方法で送っても良い」というルールを定めた法律です。
電子帳簿保存法が、主に経理などの帳簿を電子化することを認めた法律なのに対し、IT書面一括法は、契約書などの様々な種類の書類を電子化することを認めている点が大きな違いです。
具体的には、以下のことができるようになりました。- 書面での提出も可能
従来通りの紙での提出も、引き続き認められています。 - 電子メールやFAXでの提出が可能に
多くの書類を、紙で印刷せずに電子ファイルで送れるようになりました。 - オンラインでの手続き
一部の行政手続きは、ウェブサイト上で直接ファイルをアップロードできるようになりました。
電子契約の利用者保護に関する法律

電子契約法(電子消費者契約法)
電子消費者契約法は、電子商取引において消費者が 誤って契約をしてしまった場合に、その契約を無効にできるという特例を定めた法律 です。

民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは、適用しない。
引用元:電子契約法第3条
-
ワンクリック詐欺防止: 思わぬ契約を結んでしまう「ワンクリック詐欺」を防げる
-
契約内容の明確化:契約の内容を事前にしっかりと確認できるようになり、トラブルを防げる
-
消費者の保護:間違えて商品を買ってしまうなど、消費者が損をするような契約を減らせる
下請法(下請代金支払遅延防止法)
下請法第3条は、発注者が下請け業者に対して、契約に関する事項を記載した書面を交付することを義務付けています。
しかし、 下請業者の同意を得ていれば、書面ではなく電子的な方法で契約内容を伝えることも可能 です。

親事業者は、法第三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下請事業者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
建設業法
建設業法では、工事の請負契約は原則として書面で結ぶ必要がありますが、 相手方と合意すれば、電子契約でも有効 となります。

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(略)
3建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
引用元:建設業法第19条
労働基準法
労働条件の通知は、原則として書面で行うことになっていましたが、 労働者の希望に応じて電子化できるように なりました。

法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一ファクシミリを利用してする送信の方法
二電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
引用元:労働基準法施行規則第5条4項
借地借家法
従来、借地借家法では、定期借地・定期建物賃貸借契約は必ず公正証書などで結ぶ必要がありました。
しかし、 2022年の改正により、電子契約でも有効 となりました。

存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(略)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
引用元:借地借家法第22条

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
引用元:借地借家法第38条
電子委任状法
企業の代表者が、 従業員に電子署名で契約書に署名する権限を与える ための「電子委任状」という仕組みがあります。
電子委任状法は2018年にスタートしましたが、同法に基づく事業者はまだ限られており、普及には至っていません。

この法律において「電子委任状取扱業務」とは、代理権授与を表示する目的で、電子契約の一方の当事者となる事業者の委託を受けて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、電子委任状を保管し、当該電子契約の他方の当事者となる者又はその使用人その他の関係者に対し、当該電子委任状(略)を提示し、又は提出する業務をいう。
引用元:電子委任状法第2条3項
特定商取引法
従来、特定商取引法では、契約書は必ず紙で渡さなければなりませんでした。
しかし、 2023年6月からの改正で、消費者が同意すれば、電子メールなどで送ることも可能に なりました。

販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
引用元:特定商取引法第13条2項
電子契約作成時に確認が必要な法律

デジタル改革関連法
デジタル改革関連法は、私たちの生活をより便利にするために、 様々な法律を一度に見直して、デジタル化を進めるための法律 です。
特に注目すべき点は、「押印・書面の交付等を求める手続きの見直し」です。
この見直しによって、多くの書類で押印や書面が不要になり、電子契約が利用できるようになったのです。
-
押印義務の廃止: 戸籍の届け出や不動産取引など、多くの手続きで押印が不要になりました。
-
書面化義務の緩和: 契約書など、これまで紙で作成・保管していた書類を、電子的に作成・保管できるようになりました。
宅建業法
2022年5月の改正宅建業法施行により、不動産取引を含む多くの契約書で電子契約が可能になりました。
しかし、 すべての契約書が電子化できるわけではありません 。
一部の契約書については、法律で書面契約が義務付けられているため、注意が必要です。
| 書面契約が必要な契約 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
|---|---|---|
| 事業用定期借地契約 | 借地借家法23条 | - |
| 企業担保権の設定又は 変更を目的とする契約 |
企業担保法3条 | - |
| 任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律3条 | - |
| 特定商取引(訪問販売等) の契約等書面 |
特定商取引法4条、5条、9条、18条、19条、37条、42条、55条 | 2023年6月 |
電子契約の保管要件に関する法律

電子契約は、通常の紙の契約書と同じように法的効力を持っているため、税務調査などにおいて、電子契約書の内容が求められることがあります。もし、 適切に保存されていなければ、ペナルティを受ける可能性があるため、正しい保存方法を理解しておくことが重要です。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、電子データで帳簿や書類を保存することを認める法律です。
法律の中で、電子契約は「電子取引」に該当するため、以下の電子取引要件を満たした保存が義務付けられています。
- 真実性の確保: データが改ざんされていないこと
- 検索機能の確保: 必要なデータを見つけられること
- 見読可能装置の備え: データを見ることができる状態であること
- 電子計算機処理システムの概要の記載:どんなシステムでデータを管理しているか
特に重要な2つの要件は次の2つです。
- ✓ 真実性の確保
タイムスタンプを付与したり、データの改ざんを防ぐ仕組みを導入したりすることで、データの信頼性を確保する必要があります。 - ✓ 検索機能
取引年月日、取引先名、取引金額の3つの項目で検索できることが最低限必要です。より詳細な検索機能があると、税務調査への対応がスムーズになります。
2022年1月の改正により、電子帳簿保存法の要件は緩和されましたが、 電子取引については、紙での保存は認められなくなり、電子保存が義務化 されました。

令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
法人税法
電子契約は、法人税法により、 原則7年間(繰越欠損金がある場合は10年間)の保存 が義務付けられています。
一方、電子署名法では、電子署名の有効期限が原則5年とされているため、電子契約の保存期間よりも早く有効期限が切れてしまいます。
そこで、契約内容の長期的な証拠として有効なのが、長期署名(電子署名+タイムスタンプ)です。
電子データの作成日時を証明するタイムスタンプと組み合わせることで、電子署名の有効性を長期にわたって保てるようになります。
|POINT| 紛争リスクを軽減するためには、長期署名に対応した電子契約サービスを選択する
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。
e-文書法
e-文書法は、紙の書類を電子データで保存する際のルールを定めた基本的な法律です。
会計ソフトなどで作成する 帳簿データの保存に関係する電子帳簿保存法も、e-文書法をベースに作られています 。
e-文書法で電子文書として保存するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 見読性: いつでも内容を確認できること
- 完全性: データが改ざんされていないこと
- 機密性: 盗難、漏洩、不正アクセスを防ぐこと
- 検索性:必要な文書を簡単に探し出せること
要件は、どんな種類の書類を電子化する場合でも共通して適用されるものです。
まずは、これらの要件を確認し、自社の電子化に備えましょう。
e-文書法に対応した電子化の方法には、大きく分けて以下の2つがあります。
- 電子データでの保存
仕訳帳や総勘定元帳など、会計ソフトで作成したデータは、電子帳簿保存法の要件を満たせば、電子データのまま保存できます。※注意: 税務署長の承認が必要な場合があり、複数の要件を満たす必要があります。 - スキャナでの保存
取引先から受け取った請求書など、紙の書類をスキャンして画像データとして保存する方法です。※注意:スキャン画像の解像度や、タイムスタンプの付与など、一定の要件を満たす必要があります。

編集部
現物が重要な書類や、法的な効力に影響が出る書類などは、電子化できない場合があります。各書類の取り扱いについて、それぞれの省庁の定めるルールを確認しましょう。
電子契約の印紙税非課税に関する法律(印紙税法)

印紙税とは、契約書などの紙の書類に貼る印紙に税金を払い、その書類が有効になるという仕組みの税金です。
印紙税法3条の規定により、 課税文書の対象は「紙」と解釈され、電子契約は該当しないため、非課税 となります。
2005年の国会でも、電子契約は印紙税の対象外であると明言されています。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
引用元:印紙税法3条
電子契約に関する主要な法律改正

【2024年1月義務化】電子取引データ保存
2024年1月から、メールの添付ファイルなどの電子取引データを、法定のルールに基づいて保存することが義務付けられました。
以前は紙での保存も認められていましたが、 今後は原則として電子データでの保存が求められます 。
個人事業主を含む多くの事業者が影響を受けるため、適切な保存方法を検討することが重要です。2023年の税制改正により、電子取引データ保存要件が大幅に緩和
- 変更点:検索機能不要の対象者が拡大
▶売上高5,000万円以下の事業者(改正前は1,000万円以下)
▶印刷物で管理している事業者※1 - 変更点:宥恕(ゆうじょ)期間の廃止・新たな猶予措置の創設
▶電子帳簿保存法への移行期間として設けられていた「宥恕期間※2」が終了し、2024年からは新たなルールに。
▶特別な理由があり、税務調査などでデータが必要なときに提供できれば、簡単な保存方法でも認められる。
- ※1 印刷物で管理している事業者:「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」
- ※2 宥恕(ゆうじょ)期間:2022年1月1日から2023年12月31日までのの間、特別な手続きなしに、紙で保存できる制度。猶予期間とは、2024年以降、特別な理由がある場合に、税務署に申請して認められれば、紙やダウンロードデータで保存できる制度。宥恕期間は誰でも利用できたのに対し、猶予期間は申請が必要で、認められるかどうかも分かりません。
- 参考:令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要│国税庁
なぜ緩和されたのか?
2024年1月から電子取引データの保存が義務化されることを受け、多くの事業者が準備を進めています。
しかし、 すべての事業者がすぐに新しいシステムを導入するのは難しいという状況を考慮 し、緩和措置が設けられたと考えられます。
緩和措置はあくまで一時的なものであり、将来的にはより厳格なルールが求められる可能性もあるため、自社の状況に合わせて適切な対応を進めることが重要です。
電子帳簿保存法の改正ポイント
2023年の税制改正により、電子帳簿保存法においても以下3つの大きな変更点がありました。
1. 優良な電子帳簿の範囲が明確化
申告所得税や法人税の申告において、優良な電子帳簿※として作成しなければならない帳簿の範囲が具体的に定められました。
具体的には、仕訳帳、総勘定元帳、その他の必要な帳簿(一定の記載事項を含む)が挙げられます。
-
※優良な電子帳簿とは?作ると何が得られるのか?
- ■優良な電子帳簿とは?
総勘定元帳、仕訳帳、その他必要な帳簿などを、法律で定められた要件を満たして保存している電子帳簿のことです。
■優良な電子帳簿を作ると何が得られるのか?
万が一申告漏れがあったとしても、ペナルティ(過少申告加算税)が5%軽減されます。税務調査の際にもスムーズに進められます。
2. スキャナ保存の要件が緩和
これまで、スキャナで読み取った書類を保存する際に、解像度や階調などの情報も保存する必要がありました。
しかし、税制改正により以下3つの要件が緩和されたため、スキャナ保存の手続きが簡素化されます。
- 画像の品質に関する要件の緩和
従来:スキャンした画像の解像度や色に関する細かい情報も保存。
改正後 細かい情報の保存は不要に。ただし、スキャン時の解像度(200dpi以上)や色は一定の基準を満たす必要がある。 - 入力者情報の保存不要
従来:スキャンした書類に誰がいつ入力したかなどの情報を記録。
改正後 入力者情報の記録は不要に。 - 帳簿との関連付けの緩和
従来:スキャンした書類は、自社の帳簿と紐づけて管理。
改正後 見積書や注文書など、お金の流れに直接関係のない書類については、帳簿と紐づける必要がなくなった。
デジタル改革関連法の影響
デジタル改革関連法の施行により、電子契約の法的環境が大きく変わりました。
デジタル庁の設置により、国全体のデジタル化が加速。個人情報保護法の改正で、データの利活用も促進されます。
さらに、マイナンバーカードの普及や押印・書面手続きの見直しにより、国民の手続き負担が軽減されるでしょう。
公的給付の迅速化や、緊急時の預貯金口座情報確認など、 国民生活の利便性向上に直結する施策が盛り込まれており、電子契約の普及にも追い風 となります。
デジタル改革が企業にもたらすもの
デジタル改革関連法は、企業にとって、 業務効率化と法的な安心感という大きなメリット をもたらします。
具体的には、「法的な根拠の明確化で電子契約導入のハードルが下がる」「データ利活用の促進で精度の高い経営判断が可能になる」「行政手続きの簡素化で企業の負担が軽減される」などです。
社会の変化を捉え、積極的に新しい技術や制度を取り入れれば、企業はより競争力のある組織へと成長することができます。
電子契約の普及と課題:業界別導入事例から学ぶ

不動産業における電子契約の注意点
2022年5月の 宅建業法改正により、重要事項の説明や契約書の作成・締結が電子化できるように なりました。
時間や場所の制約なく取引ができるようになり、業務効率化やコスト削減が期待されています。
しかし、高齢の賃貸人への配慮や、なりすまし防止など、課題も残されています。
このような課題に対して、全宅連は「ハトサポサイン」のような低価格サービスの提供や、マイナンバーカードを用いた本人確認の導入を進めていく方針です。
不動産取引のオンライン化を望む声も多く、今後さらなる普及が見込まれます。
金融業における電子契約の注意点
金融業界でも電子契約の導入が進んでおり、auじぶん銀行や大阪協栄信用組合、クレディセゾンなどが、業務効率化やコスト削減を実現しています。
しかし、金融機関特有の厳格な本人確認や、機密情報の取り扱いには注意が必要です。導入を検討する際は、セキュリティと法令遵守を念頭に置きましょう。
導入事例:大阪協栄信用組合(金融業)
大阪協栄信用組合は、電子署名を用いた融資契約のペーパーレス化を目的に、クラウドサインNOWを導入しました。
| ● 導入の効果 | |
| お客様の利便性向上 | 契約手続きが簡素化され、お客様の手間が大幅に削減した。 |
| 業務効率化 | 契約書管理の効率化、人件費削減を実現。 |
| セキュリティ強化 | 契約書のデータが安全に管理され、改ざんのリスクが軽減した。 |
| ● 成功の要因 | |
| ペーパーレスに対する 明確なビジョン |
単なる紙の削減ではなく、業務全体の効率化を目指した。 |
| 全社一丸となっての 取り組み |
全店舗で同時に導入し、従業員への徹底的な教育を実施。 |
| 外部の専門家との連携 | 弁護士ドットコムのサポートを受け、法的な問題をクリアにした。 |
一方で、 メール不着など、解決すべき課題も残っています。

契約書PDFのメール配信が、お客様のメール環境により滞るケースがありました。迷惑メール設定やキャリアメールの仕様が原因と考えられます。現在は個別に対応していますが、根本的な解決策を模索中です。
インタビュー記事をもとに、Wiz Cloud編集部が編集
その他業種の電子契約時の注意点
電子契約は、業種を問わず広く活用されていますが、導入時には注意点があります。
まず、 取引先の理解と同意を得る ことが重要です。特に、ITリテラシーの低い企業との取引では丁寧な説明が必要でしょう。
また、契約書の種類によっては電子化に適さないものもあるため、慎重な判断が求められます。
導入事例:株式会社JSOL(インターネット業)
株式会社JSOLJSOLは、業務委託先との契約業務の効率化を目的に、クラウドサインを導入しました。
| ● 導入の効果 | |
| 契約処理時間の短縮 | 平均5営業日以上かかっていた契約処理が、2日余りに短縮。 |
| 業務効率化 | 年間3000件以上の発注を4人で対応可能に。 |
| パートナー企業との 円滑な連携 |
パートナー企業側の負担も軽減され、スムーズな契約が可能に。 |
| 急な案件への 対応力向上 |
迅速な発注が可能になり、顧客への対応力が向上。 |
| ● 成功の要因 | |
| API連携による自動化 | Excelとの連携により、発注処理を効率化。 |
| 全社的な取り組み | 関係部署と連携し、スムーズな導入を実現。 |
| セキュリティへの配慮 | 日本総合研究所グループとしての高いセキュリティ基準をクリア。 |
ただし、すべての企業において、電子契約への移行がスムーズに進んだわけではありません。

クラウドサインの導入に際し、一部のパートナー企業様(数社)からはご賛同いただけないケースもありましたが、大多数の企業様からは、契約業務の効率化につながったと好評です。特に、印刷や郵送の手間が省ける点が評価されており、導入初期の理解不足も解消され、現在では広く認知されるようになっております。
インタビュー記事をもとに、Wiz Cloud編集部が編集
電子契約の導入は、業務効率化や顧客満足度向上に大きく貢献しますが、同時に様々な課題も浮上します。これらの課題を解決するためには、継続的な改善と、関係各所の協力が不可欠です。
電子契約で発生しうるトラブルとその対処法

電子契約に関する実際の裁判例
● 貸金返還等請求事件判決(東京地裁令和1年7月10日)
令和1年の裁判では、A社とB社の間で結ばれたお金の貸し借りの契約(電子契約)が本物かどうかが争われました。
B社は、この契約はA社が勝手に作ったものだと主張しましたが、 裁判所は、B社が実際にこのお金を使っていたという事実から、契約は本物だと判断 しました。
この裁判では、特別な証明書を使わずに、状況証拠だけで契約が本物だと認められたことが特徴です。
● 業務委託請求事件判決(東京地裁平成25年2月28日)
平成25年の裁判では、メールだけで契約が成立するかどうかの問題が争われました。
広告会社のC社が、D社からメールで広告を出してほしいと頼まれたのですが、D社は後で『メールは偽造だ』と主張しました。そこで裁判になったのです。
裁判所は、 メールが改ざんされた形跡がないことから、メールの内容は本当であり、契約は成立していると判断 しました。
この裁判は、厳密な契約書ではなく、普通のメールでも、証拠として認められる可能性があることを示しています。
電子契約の証拠力はまだ確立されていません。 これまでの裁判例では有効とされていますが、今後、新しい裁判が増えるにつれて、証拠力に関する考え方が変わる可能性があります。
電子契約を利用する際は、 本人確認がしっかりできるサービスを選びましょう。また、最新の裁判の動向を常にチェックすることも重要です。
電子契約でトラブルにあった際の一般的な対処法
万が一、トラブルが起こった場合に備えて、 対処法を押さえておきましょう。
-
STEP.1
契約書の内容を確認する
● 契約書に記載された内容、特にトラブルに関する条項や、紛争解決方法などを確認します。
● 電子署名やタイムスタンプなどの証拠となる部分も念入りに確認しましょう。 -
STEP.2
相手方との交渉
● まずは、相手方と直接交渉し、問題解決を試みます。
● 契約書の内容に基づいて、冷静かつ客観的に状況を説明し、解決策を模索しましょう。 -
STEP.3
証拠の収集
● メールのやり取り、チャット履歴など、トラブルに関する全ての証拠を収集・保管します。
● 電子証拠は、後々の裁判で重要な証拠となるため、適切な方法で保存しましょう。 -
STEP.4
弁護士への相談
● 契約内容が複雑であったり、交渉が難航する場合には、弁護士への相談がおすすめです。
● 弁護士は、法的な観点からアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きも代行してくれます。
電子契約サービス選定時の法的チェックポイント
チェックポイント①|電子署名法への対応状況
電子契約サービスを導入する際は、 まず「電子署名法」に準拠しているかどうかを確認しましょう 。
電子署名法とは、電子データでも本人が署名したことを法的に認めるための法律です。この法律に適合しているサービスは、第三者による認証(たとえば認定認証事業者の電子証明書)を利用して、署名者の本人性と改ざんの有無を保証します。
具体的には 「電子署名法対応」や「特定認証業者と連携済み」などの表記があるサービスを選ぶと安心 です。また、総務省や経済産業省が認定している事業者かどうかもチェックポイントになります。
チェックポイント②|証拠能力の保証
万が一の トラブル時に備えて、電子契約書の証拠能力がしっかりと確保されていることも重要 です。
証拠能力とは、裁判などで契約の存在や内容が証明できる力のことを指します。証拠能力を担保するには、電子署名のほかにも、改ざん防止機能(タイムスタンプやハッシュ値の記録)や、操作ログの自動保存が整備されていることがポイントです。
たとえば、 契約締結の日時、アクセス履歴、誰がどこで同意したかが明確に記録されるサービスは信頼性が高い です。このような機能があるかどうか、必ず導入前に確認しましょう。
チェックポイント③|電子帳簿保存法の遵守
電子契約書は、 単に作成するだけではなく、法律に基づいて正しく保存する必要 があり、中でも特に重要なのが「電子帳簿保存法」です。
電子帳簿保存法では、電子文書を保存する際のルールが定められており、契約書も例外ではありません。保存要件には「検索機能の確保」「改ざん防止措置」「保存期間(原則7年間)」などがあります。これらを満たしていないと、税務調査などで契約書が正式に認められないリスクがあります。
導入を検討しているサービスが、この 保存要件に対応しているかどうかを事前に確認し、必要であれば機能の詳細を資料請求などで把握しておきましょう 。
チェックポイント④|契約相手の本人確認プロセス
電子契約において、 相手が本当に契約当事者であるかを確認する「本人確認」は、法的にも実務的にも非常に重要 です。
本人確認が不十分な場合、契約の有効性が疑われるリスクがあるためです。安全性の高いサービスでは、運転免許証やマイナンバーカードを使った身元確認機能や、SMS・メールによる二段階認証などが導入されています。
さらに、 相手がログイン・署名した際のIPアドレスや端末情報を記録する機能があると、万一のトラブル時にも証明に役立ち ます。契約相手の本人確認機能が十分であるかを、導入前にしっかり確認しましょう。
チェックポイント⑤|セキュリティ基準の明確さ
電子契約は、 個人情報や企業の重要な契約情報を扱うため、高いセキュリティ水準が求められます 。
選ぶべきサービスは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に基づいた運用を行っており、たとえばISO/IEC 27001の認証を取得しているかどうかを確認しましょう。
また、 通信の暗号化(SSL/TLS)、定期的な脆弱性診断、サーバーの監視体制などの情報が公開されているサービスは信頼性が高い です。さらに、情報漏えいや不正アクセス発生時の対応ポリシーが明記されているかも大切なチェック項目です。
電子契約の具体的な契約締結プロセス

電子契約の手続きフロー
電子契約の手続きは、紙の契約と比べて簡素化され、よりスムーズに行うことができます。
一般的な電子契約の手続きフローは以下の通りです。
-
STEP.1
契約書の作成・準備
● 契約書テンプレートを活用する
● テンプレートをベースに、具体的な契約内容を記入していく
● 作成した契約書を関係者でレビューし、内容に誤りがないか確認する -
STEP.2
契約書の送信
● 作成した契約書を、電子契約サービスを通じて相手方に送信する
● 相手方は、送信された契約書へのアクセス許可を行う -
STEP.3
契約内容の確認と合意
● 相手方は、送信された契約書の内容を詳細に確認する
● 契約内容に問題がなければ、相手方は電子署名を行い、契約に合意する -
STEP.4
契約の締結
● 両者が電子署名を行うことで、契約が正式に締結される
● 契約締結の証拠として、タイムスタンプが自動的に付与される -
STEP.5
契約書の保管
● 締結された契約書は、電子契約サービスのクラウド上に安全に保管される
● 契約書へのアクセス権限は、必要に応じて設定する
スムーズかつ安全に電子契約を締結するための注意点
電子契約は、紙の契約と比べて簡便で迅速な契約締結が可能ですが、その一方で、特有の注意点も存在します。
スムーズかつ安全に電子契約を締結するために、以下の点に注意しましょう。
1. システムの選定
- コスト: 初期導入費用やランニングコストを比較検討しましょう。
- 操作性: 従業員が簡単に操作できる直感的なインターフェースが理想です。
- 法規制への対応:電子帳簿保存法など、関連する法規制に対応しているか確認しましょう。
- 機能性: 契約書の作成、承認、保管、検索など、必要な機能が備わっているかを確認しましょう。
- セキュリティ:契約内容の機密性を保持するため、高度なセキュリティ対策が施されているシステムを選ぶことが重要です。
2. 相手方の確認
- 身元の確認:相手方の身元をしっかりと確認しましょう。
- 契約相手先の信用力:相手先の信用力を事前に調査することも大切です。
- 電子署名の有効性: 相手方の電子署名が有効であることを確認しましょう。
3. 社内への周知
- メリットの周知:電子契約導入による業務効率化、コスト削減、セキュリティ向上などのメリットを全社員に周知徹底します。
- 操作方法の教育: 電子契約システムの操作方法を、全社員が理解できるように、マニュアル作成や研修の実施を行います。
- 抵抗感の解消: 紙の契約書に慣れている社員に対しては、電子契約の安全性や利便性について丁寧に説明し、抵抗感を解消します。
電子契約の導入は、業務効率化に大きく貢献しますが、 慎重な準備と運用が不可欠 です。上記の点に注意し、自社の状況に合わせて最適な電子契約システムを選定することで、スムーズな契約業務を実現できます。
無料で使えるおすすめ電子契約システム

無料で使えるおすすめ電子契約システム比較表
| KANBEI SIGN (カンベイサイン) |
電子印鑑 GMOサイン |
クラウドサイン | freeeサイン | BtoBプラットフォーム 契約書 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 最短3分で契約締結、中小企業が無料ではじめる電子契約サービス。 | 大企業GMOグループの安心セキュリティ、大手企業との連携実績豊富。 | 国内シェアNo.1、多様な業種に対応、使いやすいインターフェース。 | 統合型法務サービス、一連の契約業務をカバーする多くの機能を搭載。 | BtoB取引に特化、法的効力のある安全な電子契約サービス。 |
| 機能 | 契約書のひな形登録、メール認証署名、メンバー権限、タイムスタンプ機能、自社の印影で押印など | タイムスタンプ機能、署名互換機能、S/MIME対応、アクセスコードのSMS送信、アドレス帳機能など | 契約書作成、2段階・2要素認証、API連携、テンプレート設定、権限設、検索機能、インポートデータ保管など | 文書保管、CC送信、API/Webhook、文書配付、送信時ファイル添付、本人確認書類必須設定など | 契約書発行、電子契約、押印機能、差戻、権限管理、契約書関連付け機能、API連携、契約期限アラート機能など |
| 〇 強み | 契約書作成の効率化、中小企業のニーズに合わせた機能や料金プランが充実 | 長年の実績と信頼で選ばれる電子契約サービス、 契約書の管理・作成を網羅した機能 | 幅広い企業に利用されている、豊富な機能、高い信頼性 | Googleドキュメントで契約書作成効率化、月額固定料金のみで利用可能 | 送信料1通50円~の低コストで利用できる、充実したサポート体制、最大5社間契約 |
| ▲ 弱み | 大規模企業向けの機能が不足している場合がある | 機能が豊富な分、操作が複雑に感じるユーザーもいる | 送信1通あたり220円かかる | PDFでのフォーマット調整が手間という声もあり | 契約相手もIDの取得が必要で、手間がかかる |
| ターゲット層 | 中小企業向け | 幅広い業種、セキュリティを重視する企業、大企業 | 大企業から中小企業まで | 大企業から中小企業まで | 大企業から中小企業まで |
| 月額料金 (税込) |
2,200円 5,500円 2万2,000円 |
9,680円 | 1万1,000円 3万800円 ~お問合せ |
6,578円 3万2,780円 ~お問合せ |
1万円~ 3万円~ |
| 無料プラン | あり | あり | あり | あり | あり |
| 問い合わせ | KANBEI SIGNの お問い合わせはこちら |
電子印鑑GMOサインの 公式サイトはこちら |
クラウドサインの 公式サイトはこちら |
freeeサインの 公式サイトはこちら |
BtoBプラットフォーム 契約書の公式サイトはこちら |

KANBEI SIGN(カンベイサイン)
KANBEI SIGNは、 契約書作成から締結・管理までオンラインで完結できる電子契約サービス です。
契約書の郵送や、締結のための訪問が不要なため、印紙税や郵送費が削減できるほか、通常1週間以上かかっていた契約締結が最短3分に短縮されます。
初期費用無料かつ契約期間の縛りもないフリープランがあるので、手始めに使ってみたいという方におすすめです。


電子印鑑GMOサイン

電子印鑑GMOサインは、これまで 350万社以上が導入している電子契約サービス です。
契約の締結から、その後の管理までワンストップで行える他、契約データごとに暗号化して保存できるセキュリティレベルの高さが評価されています。
無料で利用できる「お試しフリープラン」も用意されているので、1度使ってみてから導入を検討すると良いでしょう。
公式サイトはこちら
クラウドサイン

クラウドサインは、 弁護士監修で設計されたシステムならではの安心感が特徴 です。
これまで10万社以上の導入実績があり、大手上場企業や金融業、士業など、幅広い業界で利用されています。
フリープランでは、契約書の送信・保管・検索といった基本機能のみ利用でき、作成できるアカウント数は1名、ひと月の送信件数は5件までとなっています。


freeeサイン

freeeサインは、Googleドキュメントを使用することで、 システム上でテンプレートやドラフトを編集できる機能が特徴 です。
また、書類の送信料が0円なので、送信件数が多い会社でも金額を気にせず利用できます。
ただし、無料プランで送信できるのは月に1通まで、Starterプランは1アカウントのみの利用料金である点には注意しましょう。
公式サイトはこちらBtoBプラットフォーム契約書
BtoBプラットフォーム契約書は、 フリープランでもワークフロー機能が利用できるのが特徴 です。
契約締結の起案や承認まで、社内稟議の全工程をクラウド上で一括管理できるため、業務フローの効率化を重視したい企業におすすめです。
また、アカウント数無制限で使え、電子契約書の保管もひと月3件までとなっているので、無料版でも様々な機能を試すことができます。
さらに、他のジンジャーシリーズとも連携できるため、問い合わせ先を1つのサービスに集約したい方に最適です。
公式サイトはこちら
よくある質問(FAQ)
A
電子契約書は裁判でも証拠として認められます。ただし、電子署名や本人確認の有無で証拠能力が大きく左右されますので注意が必要です。
A
電子署名がなくても契約自体は成立しますが、契約内容や合意を証明することが難しくなります。法的リスクを避けるためにも電子署名を推奨します。
A
導入時には、電子署名法への対応、電子帳簿保存法への遵守、改ざん防止措置が最低限必要です。必ず事前にサービスの仕様を確認しましょう。
A
法改正があっても、過去に作成された電子契約書が無効になることはありません。ただし、改正後の新規契約には改正法が適用されます。
A
電子帳簿保存法の対応義務は電子契約を利用する全ての事業者です。規模に関わらず、個人事業主から大企業まで適用されますので注意が必要です。
まとめ
電子契約を活用する際には、関連する法律の知識が求められます。
しかし、すべての法律を完璧に理解するのは難しいので、まずは基本的な法律から学ぶと良いでしょう。
その後、電子契約サービスの利用を検討すると、より安全に電子契約を導入できます。
自社に合った電子契約システム選びに迷っている場合や、詳細を知りたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【無料】お問い合わせはこちら
電子印鑑の作り方|無料で簡単!Excel・PDF・ツール別ガイドと導入のポイント
ExcelやPDF、無料ツールを活用した電子印鑑の作り方を詳しく解説。さらに、法的効力や注意点も紹介し、電子契約導入の第一歩をサポートします。
詳しくはこちら

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!