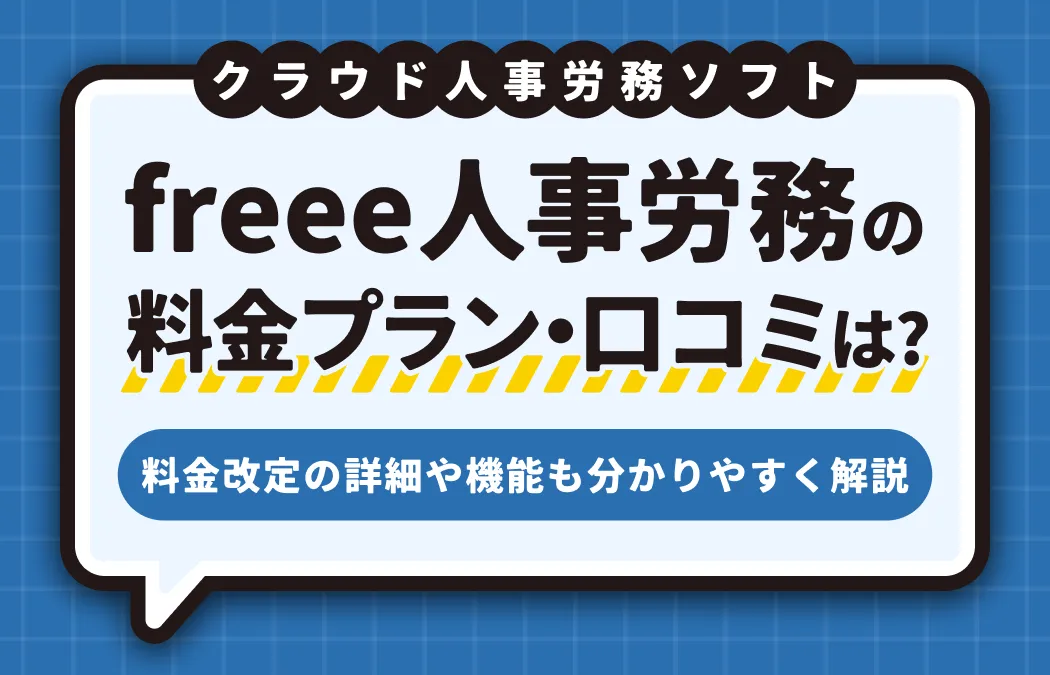「控除額の違いがわからない」
「結局、自分はいくら節税できるの?」
青色申告特別控除は、個人事業主やフリーランスが利用できる、最大65万円の所得控除です。
しかし、控除額が10万円・55万円・65万円と3段階に分かれており、それぞれ適用されるための条件が異なります。また、白色申告との違いや、制度を最大限に活用するための手続きに不安を感じる人も少なくありません。
本記事では、青色申告特別控除の基本から、控除額ごとの要件、そして具体的な節税効果までを、初心者にも分かりやすく解説します。この記事を読めば、青色申告特別控除を最大限に活用し、賢く税負担を軽減する方法が分かります。
目次
▼この記事で紹介している商品

青色申告特別控除とは
青色申告特別控除の概要と目的
青色申告特別控除は、 正確な帳簿を作成する個人事業主やフリーランスが利用できる税制優遇 です。
最大65万円(条件により55万円または10万円)の所得控除が認められ、課税所得を減らすことで所得税・住民税・国民健康保険料まで軽減できます。
制度の狙いは、複式簿記による取引の正確な記録を広め、納税者が自らの経営状況を数値で把握できるようにする点にあります。
青色申告と白色申告の違いは「税制優遇の有無」
青色申告と白色申告の最も大きな違いは、税制優遇の幅広さです。
白色申告は簡便な帳簿で申告できますが、特別控除はなく節税効果が限定的 です。
一方、青色申告では最大65万円控除に加え、赤字を3年間繰り越して将来の利益と相殺できる制度や、家族への給与を必要経費として計上できる制度が認められます。
これらの制度は経営規模が小さい事業者でも大きな効果を持ち、事業継続や資金繰りの安定に直結します。


青色申告特別控除の対象となる所得
- 事業所得(個人事業や副業の収入)
- 不動産所得(賃貸や貸家収入)
- 山林所得(森林・山林の譲渡益)
事業所得(個人事業や副業の収入)
青色申告特別控除の対象となるのは事業所得で、 小売・製造・サービス・農業・漁業など、継続的に営利を目的とした活動から得られる収入が該当 します。
フリーランスや個人事業主にとっては主たる収入源となりますが、副業収入も帳簿を適切に整備すれば事業所得として申告可能です。
ただし、記帳が不十分な場合は雑所得と判定され控除は受けられません。これは雑所得が事業所得と異なり事業的規模ではないため、青色申告特別控除の対象外とされているからです。
複式簿記と電子申告の要件を満たすことで最大65万円の控除を受けられるため、日常的な帳簿管理の徹底が不可欠です。
不動産所得(賃貸や貸家収入)
不動産所得も青色申告特別控除の対象で、 土地・建物の貸付収入に加え、船舶や航空機の賃貸収入も含まれます 。
注目点は「事業的規模」の基準で、アパート・マンション10室以上または独立家屋5棟以上が目安です。
この規模を満たすと65万円控除が認められ、満たさない場合でも10万円控除が受けられます。
山林所得(森林・山林の譲渡益)
山林所得とは、 森林を伐採して譲渡したり、立木のまま売却したりして得る所得を指します 。
青色申告特別控除は適用されますが、控除額は最大10万円に限定される点が特徴です。
特に注意すべきは、取得後5年以内に売却した場合で、この場合は山林所得ではなく事業所得や雑所得とみなされ、控除額や課税方法が変わります。
したがって、長期保有を前提とした譲渡であることが山林所得として認められる条件であり、節税計画に大きく影響します。
青色申告特別控除の対象外となる所得
青色申告特別控除は、 事業所得・不動産所得・山林所得のみに適用され、給与所得、利子所得、配当所得、一時所得などは対象外 です。
副業収入でも帳簿管理が不十分な場合は雑所得とされ、控除は認められません。
また、山林所得については、取得後5年以内に売却した譲渡益は青色申告特別控除の55万円・65万円の対象外となり、最大10万円控除に制限されます。
さらに、青色申告の承認を受けていない場合や申告期限後の提出、現金主義(※)による所得計算を選択している場合は、55万円・65万円控除は適用されず、最大10万円控除に制限される点に注意が必要です。
※現金主義…売上や経費を「現金の受け取り・支払いがあった時点」で計上する方法
青色申告特別控除額の種類と適用条件
青色申告の控除額ごとの要件まとめ表
| 要件区分 | 65万円控除(複式簿記・電子申告) | 55万円控除(複式簿記・紙申告) | 10万円控除(簡易簿記) |
|---|---|---|---|
| 対象所得 | 事業所得・事業的規模の不動産所得 | 事業所得・事業的規模の不動産所得 | 事業所得・不動産所得(規模不問) 山林所得 |
| 記帳方法 | 複式簿記(正規の簿記の原則) | 複式簿記(正規の簿記の原則) | 単式簿記(簡易簿記) |
| 提出書類 | 損益計算書+貸借対照表 | 損益計算書+貸借対照表 | 損益計算書のみ(貸借対照表は不要) |
| 申告方法 | e-Tax(電子申告)・または優良な電子帳簿の保存 | 紙提出(郵送・窓口)※電子申告や電子帳簿保存を行わない場合 | 郵送・窓口提出・e-Tax(ただし控除額は10万円) |
| 申告期限 | 原則翌年3月15日まで | 原則翌年3月15日まで | 原則翌年3月15日まで (期限後申告は自動的に10万円控除に) |
| その他 特記事項 |
現金主義特例は利用不可/所得金額が65万円未満の場合、その金額が限度/優良帳簿は事前届出が必要な場合あり/不動産所得→事業所得の順で控除適用 | 現金主義特例は利用不可/所得金額が55万円未満の場合、その金額が限度/65万円控除の要件を満たさない場合に適用/不動産所得→事業所得の順で控除適用 | 前々年の所得合計300万円以下なら現金主義選択可(届出必要)/所得金額が10万円未満の場合、その金額が限度/山林所得は10万円控除のみ対象/不動産所得→事業所得→山林所得の順で控除適用 |
65万円控除(複式簿記・電子申告)
青色申告の最大控除額である65万円は、事業所得または事業的規模の不動産所得を持つ事業者が対象です。
要件は、 複式簿記による正確な記帳、損益計算書と貸借対照表の添付、法定期限内の申告に加え、e-Taxでの電子申告または「優良な電子帳簿」の保存 が必要です。
現金主義による所得計算を選んでいる場合は適用できないため、帳簿方法や申告方式を見直すことが重要です。

55万円控除(複式簿記・紙申告)
青色申告の55万円控除は、複式簿記で記帳し必要書類を備えていても、電子申告や優良な電子帳簿保存を利用しない場合に適用されます。
対象は事業所得や事業的規模の不動産所得を有する青色申告者で、損益計算書・貸借対照表を添付し、期限内に申告することが条件 です。
紙媒体による確定申告を続ける事業者や、電子環境の整備が難しい小規模事業者にとって現実的な選択肢となります。こちらも現金主義の特例を選択すると控除は適用されません。
10万円控除(簡易簿記)
青色申告の10万円控除は、複式簿記を採用していない青色申告者に適用されます。
単式簿記(簡易簿記)による記帳で、事業所得、不動産所得(規模不問)、山林所得に利用可能 です。山林所得については、この10万円控除のみが対象となります。
また、前々年の所得が300万円以下の小規模事業者は、届出を行うことで現金主義による所得計算を選択でき、資金繰りを重視する事業者に有利な制度設計となっています。
青色申告特別控除額の計算方法
青色申告特別控除はどこから差し引かれるか
青色申告特別控除は、所得税を計算する際の所得金額から直接差し引かれる制度です。
具体的には、 収入(売上)から必要経費を引いた後に算出される事業所得・不動産所得・山林所得の金額から控除されます 。
所得金額で差し引かれることにより、課税所得が減少し、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の負担も軽くなります。
会計処理上は、青色申告決算書の損益計算書に反映され、最終的に確定申告書第一表へ控除額が記載される仕組みです。
青色申告特別控除額が0円になるケース
- 事業所得などが赤字、または所得が控除額未満の場合(控除0円)
- 青色申告特別控除の対象となる所得がない場合(控除0円)
- 青色申告の承認を受けていない場合(白色申告扱い)
- 確定申告期限後の申告(控除10万円)
- 現金主義を選択している場合(控除10万円)
青色申告特別控除額が0円になるのは、対象となる所得が存在しない場合や控除の条件を満たしていない場合 です。
具体的には、事業所得・不動産所得・山林所得の合計が赤字、または控除額より少ない場合、控除はその所得額を上限として計算されます。
また、青色申告の承認を受けていない場合や申告期限を過ぎた場合、現金主義による所得計算を選択している場合も、最大65万円や55万円の控除は適用されず、10万円控除に制限されるか適用外となります。
青色申告控除額(10万・55万・65万)の計算例
- 売上:600万円
- 経費:200万円
- 所得控除(基礎控除・医療費控除等):80万円
- 所得税率:10%(簡易計算)
- 控除前の課税所得:600万円 - 200万円 - 80万円 = 320万円
| 区分 | 控除額 | 課税所得 | 所得税額(概算) |
|---|---|---|---|
| 白色申告(控除なし) | 0円 | 320万円 | 320万×10%-9万7,500こと=22万2,500円 |
| 10万円控除 簡易簿記 |
10万円 | 310万円 | 310万×10%-9万7,500円 =21万2,500円 |
| 55万円控除 複式簿記・紙申告 |
55万円 | 265万円 | 265万×10%-9万7,500円 =16万7,500円 |
| 65万円控除 複式簿記・電子申告 |
65万円 | 255万円 | 255万×10%-9万7,500円 =15万7,500円 |

編集部
白色申告と比べて65万円控除を使うと、所得税だけで約6万5,000円の節税に。さらに住民税や国民健康保険料も軽くなるので、実際の負担減は10万円を超えるケースもあります。
青色申告特別控除を受けるための具体的な条件
- 申告期限内に確定申告を行うこと
- 事業所得・不動産・山林所得があること
- 青色申告決算書を添付すること(貸借対照表・損益計算書)
- 複式簿記または単式簿記で記帳すること
- e-Taxで電子申告または電子帳簿保存を行うこと
申告期限内に確定申告を行うこと
青色申告特別控除は、 法定申告期限(原則翌年3月15日)までに確定申告書を提出することが前提条件 です。
1日でも遅れると、複式簿記や書類添付など他の要件を満たしていても、55万円・65万円控除は認められず、一律10万円に制限されます。
期限後申告は青色の最大特典を失うため、申告スケジュールの管理が節税の第一歩となります。
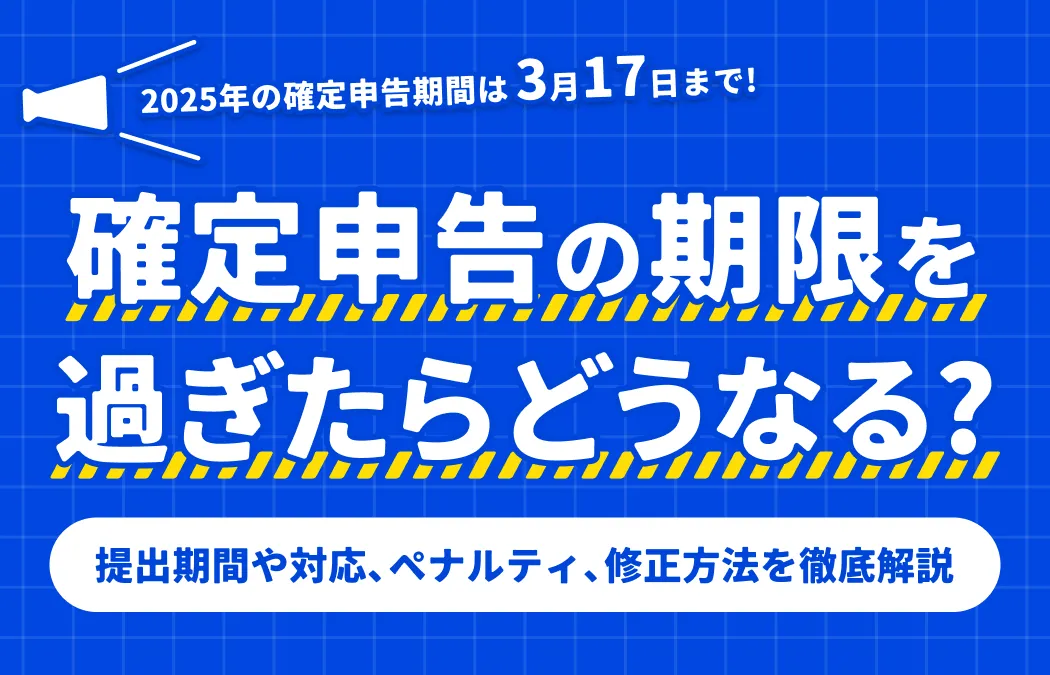
事業所得・不動産・山林所得があること
青色申告特別控除の対象となるのは、事業所得・不動産所得・山林所得の3種類です。
特に65万円・55万円控除を受けるには、事業所得か、アパート10室以上や戸建て5棟以上といった「事業的規模」の不動産所得が必要 です。山林所得の場合は、控除額が最大10万円に限定されます。
自分の所得区分を正しく判定し、どの控除額が適用されるか確認しておくことが、無駄のない節税につながります。
青色申告決算書を添付すること(貸借対照表・損益計算書)
青色申告特別控除を利用するには、確定申告書に青色申告決算書を添付する必要があります。
65万円・55万円控除を受ける場合は、貸借対照表と損益計算書を必ず提出することが条件 です。一方で10万円控除の場合は損益計算書のみで足ります。
青色申告決算書は「損益計算書」「損益計算書内訳」「貸借対照表」「貸借対照表内訳」の4枚で構成され、添付漏れがあると控除が認められないため、提出前の確認が重要です。

複式簿記または単式簿記で記帳すること
青色申告特別控除は記帳方法によって控除額が異なります。
65万円・55万円控除は複式簿記での記帳が必須であり、仕訳帳・総勘定元帳を整備する必要があります 。10万円控除であれば単式簿記(簡易簿記)でも認められます。
さらに、前々年の所得が300万円以下の小規模事業者は「現金主義による所得計算」を選択できますが、その場合は55万円・65万円控除を受けられません。

e-Taxで電子申告または電子帳簿保存を行うこと
青色申告で 最大65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳と決算書の添付に加え、e-Taxによる電子申告または「優良な電子帳簿」の保存が必要 です。
電子帳簿保存を選ぶ場合は、仕訳帳や総勘定元帳を基準に沿って保存し、事前に届出を提出しなければなりません。
電子申告は控除拡大だけでなく、自宅から申告を完結できる利便性も高く、環境整備がそのまま節税効果につながります。
青色申告特別控除の申告手続き
青色申告特別控除を受けるには、 まず開業後または適用を希望する年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署へ提出 する必要があります。
その後、毎年3月15日までに確定申告書と青色申告決算書を提出することが必須です。
65万円控除を利用する場合は、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存が条件となり、電子帳簿保存では事前届出が必要になる場合もあります。
期限を過ぎると控除額は10万円に制限されるため、厳格な期限管理が求められます。

青色申告特別控除額の選び方
- 事業規模と帳簿管理能力で判断
- 電子申告や帳簿保存の対応状況を確認
- 必要に応じて専門家に相談
事業規模と帳簿管理能力で判断
青色申告特別控除を選ぶ際は、事業規模と帳簿管理体制を冷静に見極めることが重要です。
売上規模が大きく取引件数も多い場合には、複式簿記を導入し65万円控除を活用することで、税負担を大きく軽減 できます。
逆に、規模が小さく取引が単純であれば、単式簿記で申告できる10万円控除が現実的です。
電子申告や帳簿保存の対応状況を確認
青色申告の65万円控除を受けるには、複式簿記に加えて、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存法に適合した「優良な電子帳簿」の保存が必要です。
電子帳簿保存を選択する際は、仕訳帳や総勘定元帳を所定の基準で管理し、事前届出が必要になる場合があります 。
これらの条件を満たせない事業者は、紙での申告が可能な55万円控除を選ぶのが現実的です。
控除額の差は10万円ですが、節税効果だけでなく申告環境や事務負担を踏まえて選択することが大切です。

必要に応じて専門家に相談
控除額の選択や要件の確認に不安がある場合は、税理士など専門家への相談が有効です。
専門家は、事業規模や業種ごとの特性に応じた帳簿管理方法や、控除を確実に適用するための実務的アドバイスを提供 してくれます。
さらに、誤りや提出遅延による控除額の減額リスクを防ぐことができ、税務調査への備えも強化できます。
結果として、納税者は制度を最大限に活用しつつ、本業の経営や事業拡大に集中できる環境を整えることが可能です。

青色申告特別控除による節税効果
- 所得税の軽減効果
- 住民税の軽減効果
- 国民健康保険料の軽減効果
- 赤字の繰越控除で将来の税負担を軽減
- 家族への給与を経費として計上できる
所得税の軽減効果
青色申告特別控除は、 課税所得から直接差し引かれるため、所得税の負担を大きく軽減します 。
日本の所得税は累進課税方式であり、控除額が増えるほど課税所得が低くなり、適用される税率も下がる場合があるのです。
例えば、課税所得400万円の事業者が65万円控除を受けると、課税所得は335万円となり、概算で13万円程度の税額が減少します。
この仕組みにより、収益規模が大きい事業者ほど青色申告特別控除の効果は高く、節税手段として極めて有効です。
住民税の軽減効果
青色申告特別控除は、住民税の負担にも直結します。
住民税は 確定申告で算定された課税所得を基に自治体が課す「賦課課税方式」であるため、控除で所得金額を減らせば住民税も自動的に下がります 。
住民税の所得割率は一律10%が基準となるため、65万円控除を適用すれば約6万5,000円の住民税軽減が見込まれるのです。
所得税と異なり税率は一定ですが、固定的に加算される均等割を除いた部分には大きな効果が期待できるため、長期的な節税に直結します。
国民健康保険料の軽減効果
国民健康保険料は、市区町村ごとに計算方式が異なりますが、多くの場合、住民税の所得割を基準に算定されます。
そのため、 青色申告特別控除によって課税所得が減れば、住民税と連動して国民健康保険料も減額されます 。
多くの所得控除は保険料計算には反映されませんが、青色申告特別控除は適用対象となる点が特徴です。
例えば、65万円控除を受けた場合、自治体によっては年間数万円規模で保険料が軽減されることがあり、医療制度負担の中で特に有効な節税策となります。
赤字の繰越控除で将来の税負担を軽減
青色申告者は、 赤字が発生した場合でも「純損失の繰越控除」により最大3年間、翌年以降の黒字所得と相殺できます 。
例えば、初年度に100万円の赤字が出ても、翌年に200万円の黒字があれば、課税対象は100万円に圧縮されます。
この制度は事業開始初期や収益が不安定な時期に大きな支えとなり、将来の税負担を軽減します。
ただし、適用を受けるには赤字の年でも必ず確定申告を行い、「第四表(損失申告用)」を期限内に添付することが条件です。
家族への給与を経費として計上できる
青色申告者は、一定の要件を満たすことで「青色事業専従者給与」を経費として計上できます。
対象となるのは、事業に専従して年間6か月以上従事する家族であり、給与額が労務の内容に照らして適正である 必要があります。
この制度を活用すれば、課税所得を減らし、所得税・住民税双方の軽減につながります。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することが必須であり、税務調査では実際の従事実態や給与水準が確認されるため、日常的な労務記録と給与計算根拠の整備が欠かせません。
青色申告特別控除を効率的に活用する方法
オンライン会計ソフトで記帳・申告を効率化
青色申告特別控除を最大限活用するには、オンライン会計ソフトの導入が効果的です。
簿記知識がなくても、取引を入力するだけで複式簿記の仕訳や損益計算書、貸借対照表を自動作成できます 。
さらに、多くのソフトはe-Taxと連携しており、電子申告に対応することで65万円控除の要件を容易に満たせます。
申告書類の作成を外部委託するよりコストを抑えられるため、特に小規模事業者やフリーランスにとって効率的な選択肢です。


freeeとマネーフォワードの違いを徹底比較!どっちがおすすめ?選び方を解説
freeeとマネーフォワードの個人事業主と法人企業のプランを、それぞれの機能や料金などの項目ごとに徹底比較
詳しくはこちら自動仕訳・法人カードで経理業務を簡略化
青色申告特別控除を活用するには、正確で効率的な記帳体制の構築が欠かせません。
オンライン会計ソフトを銀行口座やクレジットカードと連携させれば、取引データが自動で取り込まれ、AIが勘定科目を推定して仕訳するため、入力作業の手間を大幅に削減 できます。
さらに、法人カードを事業用と個人用で明確に分けることで、経費管理の透明性が高まり、記帳漏れや誤入力を防止できます。
法人カードの年会費自体も経費計上できるため、効率化と節税効果を同時に得られる点が強みです。

税理士相談やセミナーで不明点を解消
青色申告の控除額の選択や要件に迷う場合は、税理士や専門セミナーを活用するのが有効です。
専門家は 事業内容や規模に応じた帳簿管理の指導や、65万円控除を確実に適用するための手続きを助言してくれます 。
さらに、税務調査に備えた証憑書類の整備方法もサポートしてくれるため、安心感が高まります。
近年は会計ソフトの有料プランに、チャットや電話による税務相談が含まれることもあり、外部専門家に依頼する前のステップとして利用しやすい選択肢です。


まとめ
青色申告特別控除は、最大65万円の所得控除により、所得税、住民税、国民健康保険料を軽減できる制度です。
控除額は記帳方法と申告方法によって異なり、複式簿記とe-Taxによる電子申告で65万円、複式簿記と紙申告で55万円、簡易簿記では10万円の控除が受けられます。
この青色申告制度は、節税効果だけでなく、正確な帳簿付けによる経営状況の可視化、赤字の繰り越し、家族への給与を経費として計上できるなど、多くの利点があります。
事業の規模や状況に合わせて最適な方法を選び、会計ソフトなどを活用して効率的に記帳することが、青色申告の特典を最大限に活かす鍵です。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!