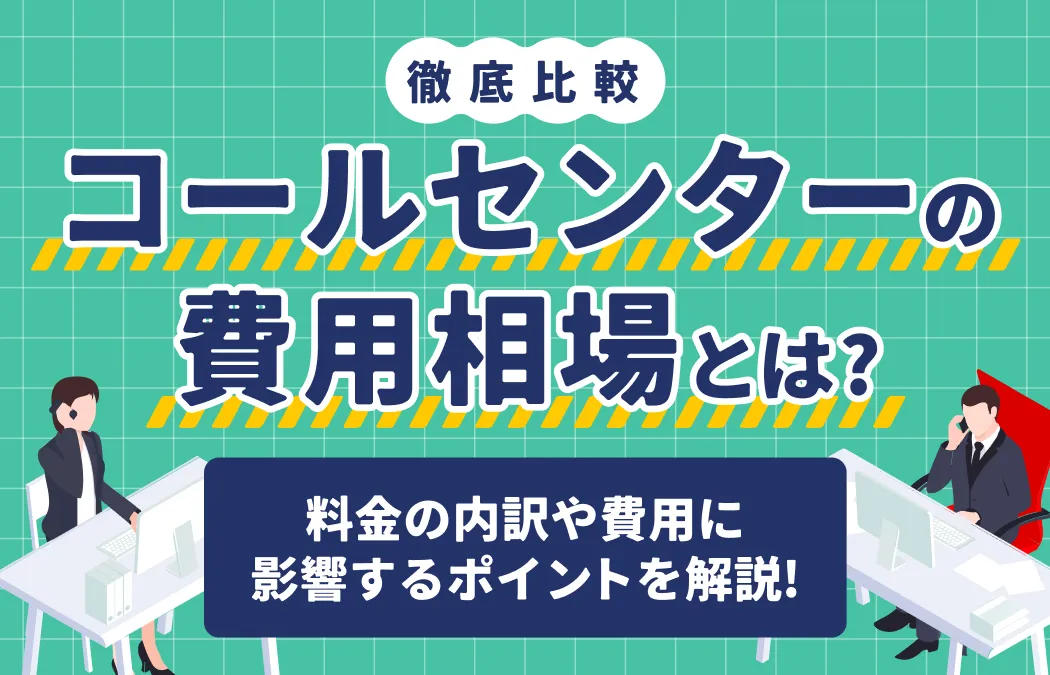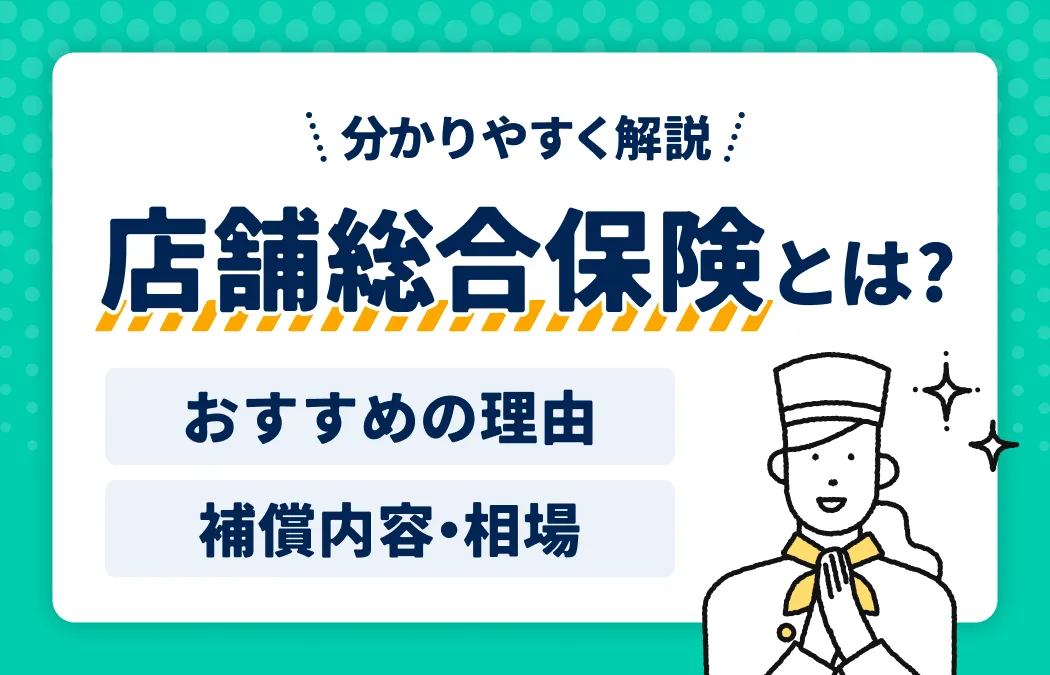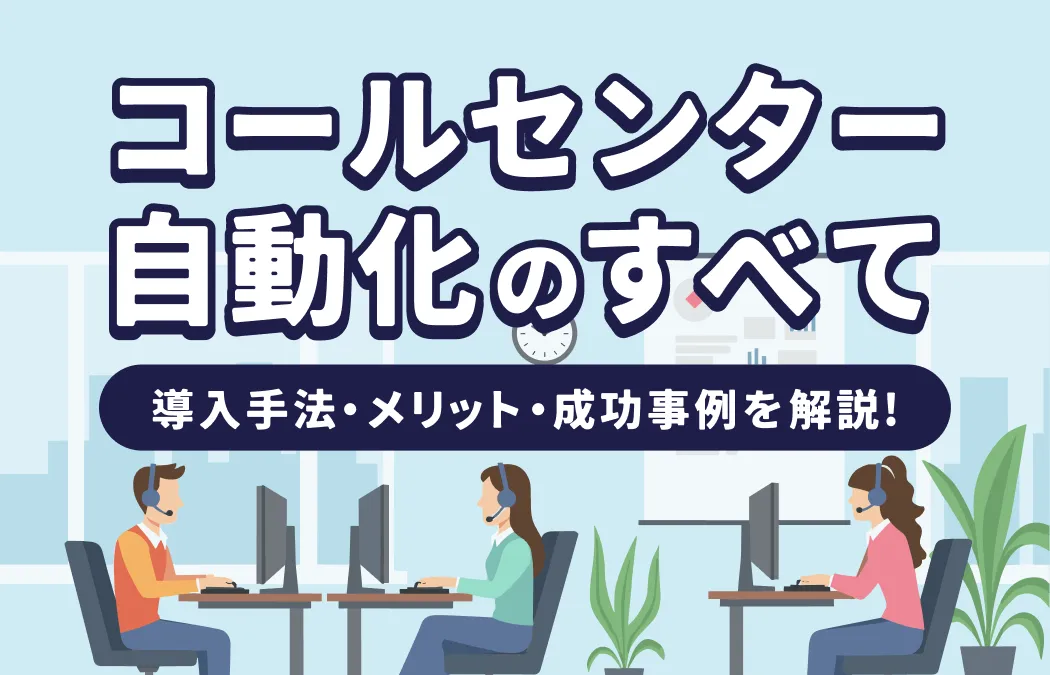「コールセンター運営で必要な経費には何があるのか」
そんな風に悩んでいる方は少なくありません。日々の業務をこなしながら、社員が兼務で電話を受け続けるのは限界がありますよね。
とはいえ、コールセンターの委託にはどんな料金体系があって、月にいくらくらいかかるのか、具体的な情報が見つけづらいのも事実です。
この記事では、外注と自社運営それぞれの費用相場や、料金の内訳、費用に影響するポイントを分かりやすく整理しています。
コストを抑えながら品質も確保したい中小企業の方に、判断材料として役立つ情報をお届けします。
目次
▼この記事で紹介している商品
コールセンターの費用相場をわかりやすく解説【料金体系別の目安つき】
コールセンター費用の内訳とは?(初期費用・月額費用・従量課金の違い)
コールセンターの導入・運営にかかる費用は、 「初期費用」「月額固定費」「従量課金(件数ベース)」の3つに大別 されます。これらの内訳を理解することで、適切な運用コストを見積もることが可能になります。
- 初期費用:委託先との契約やシステム初期設定費用など。5〜20万円が相場です。
- 月額固定費:オペレーターの待機費用や基本的な運用体制にかかる費用。5万円〜30万円程度。
- 従量課金:1件あたりの対応数や時間に応じて発生する費用。1件100円〜300円が目安です。
これらの 費用体系は委託内容(受電・発信・時間帯など)や対応レベルによって大きく変動するため、予算と業務範囲に応じて選択肢を絞り込む ことが重要です。
料金体系別の相場(固定料金制/従量課金制のメリットと相場感)
コールセンター委託の料金体系は主に 「月額固定制」と「従量課金制」 に分かれます。どちらを選ぶべきかは、対応件数や業務の安定性により異なります。
| 料金体系 | 特徴 | 相場 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 月額固定制 | 一定時間分の対応を月額で契約 | 月額5万〜30万円前後 | 件数が多く安定している業務 |
| 従量課金制 | 件数ごとに料金が加算される | 1件あたり100〜300円程度 | 月によって波がある業務 |
たとえば、繁忙期・閑散期の差が大きい通販事業では従量課金制のほうがコスト効率が良いこともあります。反対に、継続的に一定の受電がある業種では、固定制のほうがコスト予測がしやすくなります。
ソフトウェア費用とその選び方
業務量の違いによって、実際にかかる月額費用はどの程度になるのでしょうか。以下は、対応件数に応じた概算の費用イメージです。
| 月間対応件数 | 想定プラン内容 | 月額費用目安 |
|---|---|---|
| 100件 | 平日9-18時の一次受電、FAQ対応のみ | 約5万〜8万円 |
| 300件 | 土日含む10時間対応、個別応答あり | 約12万〜18万円 |
| 500件 | 24時間365日対応、緊急一次対応+CRM連携 | 約25万〜35万円 |
件数が増えるにつれ、 対応時間・人員・システム連携の必要性が増すため、費用も比例して高くなります 。また、夜間・土日対応などの追加オプションが含まれる場合は、さらに費用が上がる点にも留意が必要です。
費用に影響する主な要素(時間帯・業務範囲・言語対応・セキュリティなど)
コールセンターの費用は、単に件数だけで決まるわけではありません。以下のような要素も料金に大きく影響を及ぼします。
- 対応時間帯:深夜・早朝・土日祝などは割増料金が発生
- 業務範囲の広さ:FAQ対応か、クレーム・予約管理など複雑な応対か
- 多言語対応の有無:英語・中国語対応が必要な場合は専任人員を要する
- セキュリティ要件:金融・医療業界ではPマークやISMS対応が必要
たとえば、「夜間の緊急窓口として使いたい」「顧客情報を扱う業務が多い」などのケースでは、通常よりも費用が高めになることが想定されます。 要件定義の段階で、何にコストがかかるのかを明確にしておくとよい でしょう。

コールセンターを自社運営すべきか?外注との費用比較と判断ポイント
自社運営にかかる費用と内訳
自社でコールセンターを 運営する場合、初期投資と月々の固定費が発生 します。以下のような費用要素が必要になります。
- 人件費(時給×人数×稼働時間)
- 設備費(ブース設置・電話回線・PCなど)
- システム費(CTI・CRMなどの導入・保守)
- 教育・管理費(マニュアル整備・研修・SV人員など)
特に人件費とシステム費の割合が高く、継続的なコスト負担が発生します。 小規模企業にとってはコスト的・人的負担が大きいため、慎重な運用計画が必要 です。
外注にかかる費用と料金構造
外注型のコールセンターでは、自社運営に比べて「初期コストが小さく、柔軟な料金設計」が可能です。代表的な料金構造は以下の通りです。
- 初期費用:契約・設定・研修などに伴う一時的費用(5〜20万円程度)
- 月額費用:業務範囲・対応時間に応じた基本料金(5〜30万円程度)
- 従量課金:受電件数や対応時間に応じた変動費(1件100〜300円)
たとえば、月間300件の電話対応(10時〜18時)を依頼する場合、月額12万〜18万円ほどで委託できるケースが多く、自社で1人雇用するよりも安価に収まることもあります。
コスト構造の違いを比較
以下は、自社運営と外注の主な費用構造の違いを比較した表です。
| 費用項目 | 自社運営 | 外注委託 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 高(数十万〜100万円超) | 低(5万〜20万円) |
| 月額費用 | 高(人件費・システム維持) | 中(基本料金+従量課金) |
| 柔軟性 | 低(スケール調整が難しい) | 高(件数や時間に応じて調整可) |
| 管理負荷 | 高(採用・教育・品質管理) | 低(外注先が対応) |
このように、 初期費用やスケーラビリティにおいて、外注の方が優れているケースが多く 見られます。一方、自社でノウハウを蓄積したい場合は、運営を内製化する選択も一考に値します。
自社運営と外注、どちらが向いている?
最後に、 自社運営と外注のどちらが適しているかを判断するためのチェックリスト を紹介します。
自社運営が向いているケース
- 顧客情報が極めて機密で、社外に出せない
- 社内に対応ノウハウや人材リソースがある
- 長期的にコールセンターを自社資産として育てたい
外注が向いているケース
- 立ち上げ初期で人員・ノウハウが不足している
- 一時的な業務量の増加やキャンペーン対応
- 夜間・休日・多言語対応など柔軟性が必要
コールセンター外注の導入ステップと注意点【初めてでも安心】
外注導入までの一般的な流れ
初めてコールセンターを外注する場合、「何から始めて、どんな流れで進むのか?」という不安を抱える方も多いはずです。以下に、一般的な導入プロセスをステップごとに整理しました。
-
STEP.1
要件整理(業務範囲・件数・時間帯の明確化)
自社で 委託したい業務内容を洗い出し、対応してほしい時間帯や想定される件数などを具体化 します。ここが曖昧なままだと、見積もりや契約後に「想定と違った」といったトラブルにつながるため、導入の第一ステップとして非常に重要です。
-
STEP.2
外注先への問い合わせ・初回ヒアリング
整理した要件をもとに、外注先企業へ問い合わせを行い、初回ヒアリングを実施 します。対応可能な業務内容・料金体系・対応品質などについて情報収集し、自社ニーズとのマッチ度を見極めます。
-
STEP.3
見積もり取得と契約条件の確認
ヒアリング内容をもとに正式な見積もりが提示されます。 内訳(初期費用・月額・従量課金など)や、契約期間・途中解約時の条件など、金額以外の点もしっかり確認 しましょう。
-
STEP.4
業務マニュアル作成・オペレーター研修
実際の 運用に向けて、業務フローやFAQをもとにマニュアルを作成 し、オペレーター研修が行われます。業務の正確な伝達と品質維持のためには、自社のナレッジ提供も欠かせません。
-
STEP.5
テスト稼働とフィードバック調整
本格稼働の前に、数日〜数週間のテスト運用を実施 します。通話対応の品質・連携の流れ・レポート内容などを確認し、必要に応じて調整を行います。
-
STEP.6
本格運用スタート
テスト稼働での調整が完了したら、本番運用に移行 します。導入初期は定期的な打ち合わせやレポートレビューを行い、運用状況を可視化・改善しながら定着を図っていきます。
このように、導入は段階的に進行するため、焦らずひとつずつクリアしていけば、初めての外注でも安心してスタートできます。次のステップに進む前に、「自社の要件がしっかり固まっているか」を振り返ってみてください。
初めての外注で注意すべきポイントとは?
コールセンター外注は業務効率化の大きな手段ですが、 やり方を誤ると「品質が落ちた」「想定より費用がかかった」といった失敗に繋がる こともあります。以下のポイントに注意して進めましょう。
- 丸投げNG!業務範囲は明確に伝えること
曖昧な業務設計はミスの原因になります。 - 料金の内訳を理解する
初期費用・従量課金・オプション費など契約前に要確認。 - 品質管理体制の有無をチェック
通話録音、応対評価、フィードバック体制が整っているか。
また、セキュリティ要件やデータの取り扱いポリシーについても事前に確認しておくと安心です。信頼できる業者を選ぶことはもちろん、契約後も定期的なレポート確認や改善要望のすり合わせが重要です。
📘 「外注の進め方がよくわからない…」そんな方へ
Smart desk Wでは、初めての方でも安心して導入できるよう、要件整理からサポートしています。ヒアリングや費用見積もりは無料です。
▶ 無料で相談してみるコールセンター運営に必要なシステムと導入コストの目安
運営に必要な主なシステム機能とは?(CTI/CRM/IVR/通話録音など)
コールセンターを効率的に運営するには、業務に適した複数のシステムが必要です。代表的な機能は以下のとおりです。
- CTI(Computer Telephony Integration):着信と顧客情報を連携し、応答前に相手の情報を表示
- CRM(顧客管理システム):顧客の属性や過去の応対履歴を一元管理し、パーソナライズ対応が可能に
- IVR(自動音声応答):発信者に自動音声で案内し、適切な担当部門に振り分ける
- 通話録音・モニタリング機能:品質管理・トラブル対応・教育用途に活用
これらを組み合わせることで、顧客満足度の向上とオペレーターの生産性向上の両立が実現できます。
自社構築にかかるシステムコスト(導入・保守・ライセンス)
自社でこれらのシステムを構築・運用する場合、初期費用・ランニングコストの双方が発生します。以下は代表的な費用項目です。
| システム種別 | 初期費用の目安 | 月額費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CTI | 30万〜100万円 | 1万〜5万円 | オンプレ型は高額 |
| CRM | 10万〜50万円 | 1万〜3万円 | 契約数で価格変動あり |
| 通話録音 | 10万〜30万円 | 1万〜2万円 | 保存期間により変動 |
| IVR | 5万〜20万円 | 5千円〜2万円 | 回線数や機能数に依存する |
システムごとに料金体系が異なるため、導入前に全体のコスト構成を可視化し、自社のニーズと照らし合わせることが重要です。
システム機能の取捨選択で費用を最適化するポイント
全てのシステムをフル装備にする必要はありません。 業務内容や応答品質の要求レベルに応じて、導入すべき機能を見極めることが費用最適化の鍵 となります。以下の判断軸を参考にしてください。
- 最低限必要な機能は何か?(例:CTIと通話録音のみ)
- 応対業務の複雑度は?(IVRで自動化できるか)
- 連携先は必要か?(CRM・チャットなど他システムとの連動)
- 繁閑の差に対応可能か?(スケーラブルな設計か)
🛠️ 必要な機能だけに絞って、無駄なく導入しませんか?
Smart desk Wでは、業務に応じた最適なシステム構成をご提案します。まずは無料相談で、費用と機能のバランスを確認しましょう。
▶ システム構成の相談をするコールセンター品質を維持・向上させるための費用と管理手法
品質指標とは?
コールセンター業務における 品質を定量的に評価するには、複数の指標を用いる必要があります 。主な指標は以下の通りです。
- 応答率(接続率):かかってきた電話に対して何%対応できたか(90%以上が目安)
- 一次解決率(FCR):1回の通話で問題が解決した割合(80%以上が理想)
- 平均対応時間(AHT):1件あたりの応対時間(短すぎると品質低下の恐れ)
- 顧客満足度(CSAT):通話後アンケートなどで測る主観的評価
これらの数値をバランスよく改善することで、顧客ロイヤルティの向上と業務効率の両立が可能となります。
高品質運営に必要な人員と教育コスト
高品質な対応を実現するには、オペレーターのスキルと継続的な教育体制が不可欠です。以下のような人材コスト・教育コストが発生します。
| コスト項目 | 内容 |
|---|---|
| オペレーター人件費 | 業務に応じた専門知識・コミュニケーション力が必要 |
| 教育コスト | 初期研修・ロールプレイング・評価面談など |
| SV・管理者費用 | 品質評価・対応フォロー・トラブル対応を担う |
一般的に、 オペレーター1名の月額人件費は20万〜30万円が目安で、定期研修や品質チェックには月5万〜10万円のコスト が追加でかかります。これらは「対応品質を担保するための必要経費」として考えるべきです。
品質維持にかかる費用感と業務委託の効果
品質管理に注力するとコストが増えるのは事実ですが、外注の場合はこの負担を軽減できます。多くの委託先では、以下のような品質管理体制が標準で含まれているケースが多く見られます。
- 対応マニュアルの整備
- 通話内容のモニタリングとフィードバック
- 品質スコアリングとKPI報告
- 専任SVによるオペレーター育成
このような体制が 月額費用に含まれているため、自社で同様の管理を行うよりもコストパフォーマンスに優れた運営が可能 です。また、第三者の視点が入ることで、品質を数値化しやすくなるメリットもあります。
品質とコストの最適バランスを取るための外注活用術
すべての業務に高品質を求めれば、当然ながらコストは膨らみます。コールセンター運用では、業務の性質に応じて品質水準を調整することが、費用対効果の最大化に繋がります。以下のポイントを参考にしましょう。
- 一次対応は委託、二次対応は社内で実施
- FAQや定型応答は自動化ツールと併用
- 顧客満足度が低下しない範囲で対応時間帯を絞る
このように、品質とコストのバランスを見極めた外注設計が、効率的なコールセンター運営の鍵になります。Smart desk Wでは、業種や業務内容に応じた「品質×費用」の最適構成を柔軟に提案可能です。
Smartdesk Wなら、電話代行&IVRで業務効率化!
Smart desk Wは、電話代行とIVR(自動音声応答)を組み合わせたシステムで、24時間365日の対応可能なIVRが、時間外や休日の電話にも自動で対応できます。
さらに、 用件別に電話を自動振り分けすることで、不要な営業電話を排除し、担当部署へのスムーズな取り次ぎを実現 します。 電話代行では、優秀なオペレーターが対応し、リアルタイムで内容を共有。まるで自社のスタッフが対応しているかのような高品質なサービスを提供します。
Smart desk Wの最大の魅力は、高品質なサービスを低コストで提供できる点です。システムと電話代行を組み合わせた独自のアプローチにより、業界随一のコストパフォーマンスを実現しています。プランも柔軟で、企業のニーズに合わせて選択可能です。
-
24時間365日対応のIVR
-
用件別自動振り分け
-
高品質な電話代行
-
柔軟なプラン選択
よくある質問(FAQ)
A
最低契約期間は1〜3ヶ月程度が一般的ですが、短期スポット対応が可能なプランもあります。まずはご相談ください。
A
ヒアリングを通じて業務範囲の整理からサポートいたします。要件のたたき台がなくても問題ありません。
A
24時間365日対応が可能なプランもあります。対応時間に応じて料金が変動しますので、お気軽にご相談ください。
A
テスト稼働や短期契約にも対応可能です。繁忙期だけの活用など、柔軟にご提案できます。
A
いいえ、見積もり・初回相談はすべて無料です。費用感や適正な運用方法を知るだけでもお気軽にどうぞ。
まとめ
コールセンター業務を外注することで、業務効率の向上や人件費の削減、対応品質の平準化が図れます。
一方で、費用体系やシステム構成、品質管理体制などを理解せずに導入を進めると、かえってコストが膨らんだり、対応品質に課題が生じたりする可能性もあります。
本記事では、相場感から比較ポイント、導入ステップまで網羅的に解説しました。自社に最適な運用体制を構築するためにも、まずは専門の担当者に相談して、費用と業務内容を整理するところから始めてみてください。



この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!