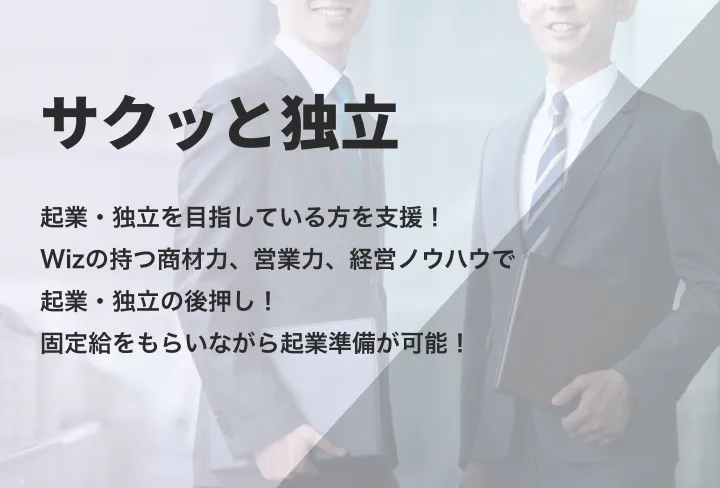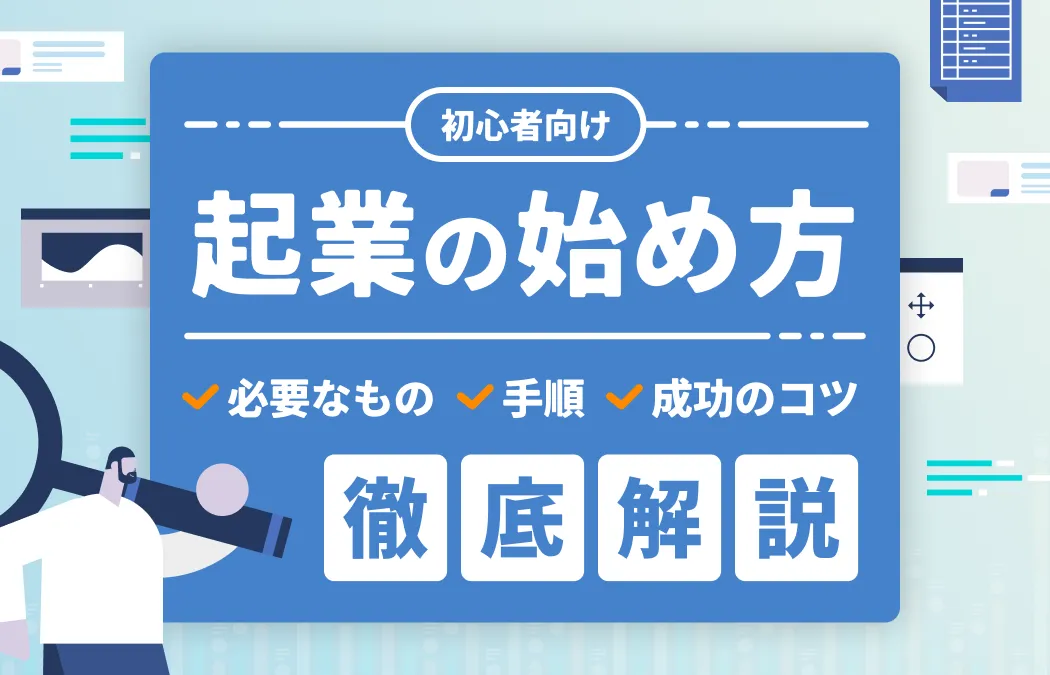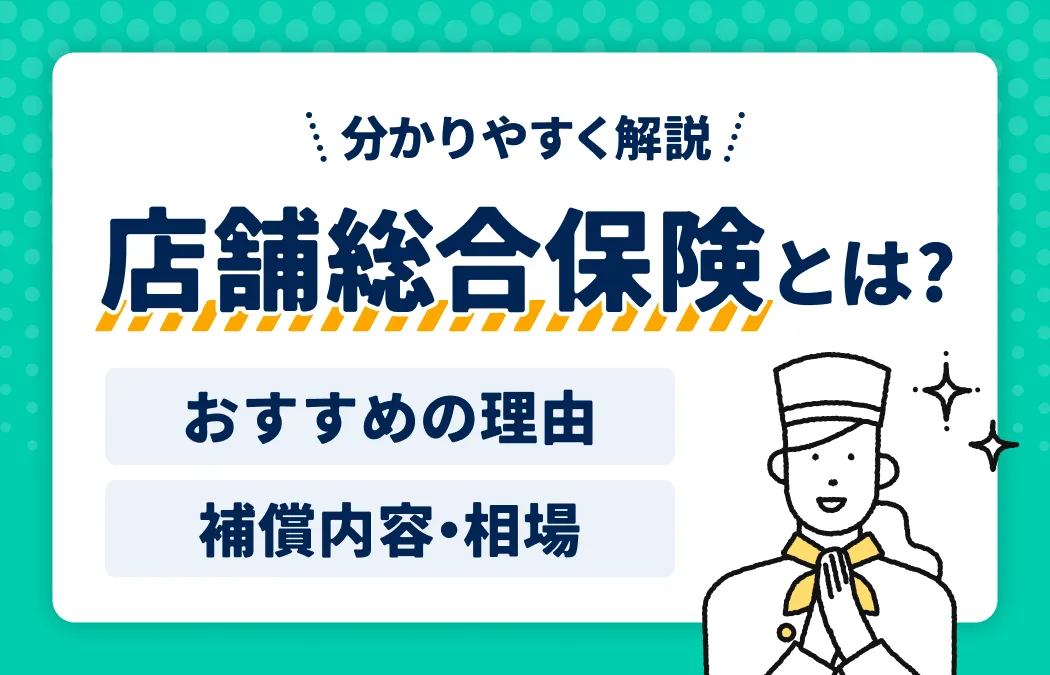「どの欄に何を書けばいいの?」
「間違えたらどうなるのか不安…」
開業届は、個人で事業を始める際に税務署へ提出する重要な書類です。
しかし、書式に見慣れない用語が多く、どこに何を記入すればよいのか迷う方も少なくありません。
この記事では、開業届の基本的な記入ルールから、各項目の具体的な書き方まで丁寧に解説します。
初めてでもスムーズに提出できるよう、記入例付きでわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
▼この記事で紹介している商品
開業届とは?提出期限・必要書類
開業届とは事業の実態を通知する届出書
開業届とは、 個人事業を始めたことを税務署に知らせるための書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」 です。
この届出により、税務署は事業を始めたことを把握し、今後の所得税や申告に関する案内を行います。
副業でも継続的な事業所得がある場合は、開業届を出しておくと青色申告などの制度も利用でき、節税面で有利になる場合があります。
事業開始日から1か月以内に税務署へ提出
開業届は、事業を始めた日から1か月以内に、所轄の税務署へ提出する必要があります。
開業日は「いつから始めたか」を本人が判断して決めて構いません 。
提出が遅れても罰則はありませんが、確定申告や各種手続きの準備がスムーズになるため、できるだけ早めの提出がおすすめです。
開業届とマイナンバーカードの2つを準備
開業届を提出する際に必要なのは、①開業届そのものと、②マイナンバーカードなどの本人確認書類の2点です。
マイナンバーカードがない場合は、通知カードやマイナンバー入りの住民票、運転免許証など を組み合わせて提出します。
また、青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も併せて提出すると、最大65万円の控除を受けられる可能性があるので、忘れずに準備しましょう。
>印刷:所得税の青色申告承認申請書
開業届の書き方【記入例付き】
まずは開業届の記入例を確認

開業届の項目別記入ポイント
1.税務署名・提出日
開業届を出す税務署の名前と、提出日を記入します。税務署名は、開業者の住所を管轄する税務署になります。
提出日は、基本的に開業日から1か月以内に設定するのが原則です。
どの税務署が担当か分からない場合は、国税庁のホームページで郵便番号から簡単に調べられます。
2.納税地・住所・電話番号
納税地とは、事業の拠点となる場所のことです。通常は自宅住所を「住所地」として選ぶのが一般的です。
別に店舗や事務所がある場合は「事業所」にチェックを入れて住所を記入しましょう。
電話番号は固定電話か携帯電話のどちらでも問題ありません。
3.氏名・生年月日・個人番号
開業する本人の氏名、生年月日、12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。
マイナンバーは、マイナンバーカードや通知カードで確認できます。
個人番号は税務署での本人確認に使われるため、正確に記入することが大切です。
4.職業・屋号
職業欄には「ライター」「カフェ経営」など、どんな仕事をするかを簡潔に記入します。
屋号は事業の名前で、店舗名やブランド名などがある場合に記載します。
屋号がまだ決まっていない場合は空欄で問題ありません。あとから変更も可能です。
5.届出の区分・所得の種類
開業届では、まず「開業」にチェックを入れましょう。
所得の種類は、物やサービスを売る仕事なら「事業所得」が基本です。不動産収入が主な場合は「不動産所得」を選びます。
複数の種類に該当する場合も、主となるものを1つ選んで記入しましょう。
6.事業を開始した日
実際に仕事を始めた日を「開業日」として記入します。
明確な日付が分かりにくい場合は、開業届の提出日や初めて報酬を得た日など、自分で基準を決めても問題ありません。
青色申告を希望する場合は、「開業日」から2か月以内の申請が必要です。
7.届出書の提出の有無
青色申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書を提出する」に「有」と記入します。下の欄では、消費税に関する届出の有無をチェックします。
事業の規模や今後の見込みによって判断が必要ですが、最初は「無」としておくのが一般的です。
8.事業の概要
行っている事業の内容は、誰にでも伝わるように、簡潔でわかりやすい言葉で記入します。
例えば、「フリーライターとして記事を執筆」「オンラインでアクセサリーを販売」など、仕事内容が具体的にイメージできる表現が理想的です。
9.給与等の支払の状況
家族や従業員に給与を支払う予定がある場合は、その人数を記入します。
記入の際は、家族(専従者)と家族以外の従業員(使用人)を分けて記載します。
また、給与から所得税を差し引く必要があるかどうかを確認し、「有」または「無」を選びましょう。
10.源泉所得税の納期の特例
従業員が少人数(常時10人未満)の場合は、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる特例があります。
この特例を利用するなら、「源泉所得税の納期の特例の申請書」を一緒に提出し、「有」にチェックします。
11.給与支払を開始する年月日
従業員への給与支払いを始めた日、または開始予定日を記入します。
すでに支払っている場合はその実際の日付、これから雇う予定なら「〇年〇月予定」といった書き方でも問題ありません。
源泉徴収の特例を適用するには、支払い開始日の前月までに申請が必要なので注意しましょう。
開業届は専用ソフトを使えば簡単に作成できる
開業届は、専用の無料ソフトを使えば誰でも簡単に作成できます。
例えば、 「マネーフォワード クラウド開業届」では、質問に沿って項目を入力していくだけで、自動で書類が完成 します。
記入例や解説もついているため、初めての方でも安心です。郵送やオンライン提出にも対応しており、税務署に行かずに済みます。
まずは話を聞いてみたい方
【無料】お問い合わせはこちら登録不要!
【無料】資料請求はこちら開業届の提出方法
税務署の窓口に直接提出
開業届は、最寄りの税務署へ直接持参して提出することができます。
提出時に「控え」も一緒に持参すれば、税務署が受付印を押して返却してくれます。
受付印のある控えは、各種手続きで必要になる場合があるため、大切に保管 しておきましょう。
閉庁時間帯は、税務署に設置された時間外収受箱へ投函することも可能です。
税務署または業務センターに郵送
税務署へ行く時間がない方は、開業届を郵送で提出することもできます。
提出時は、開業届の「控え」と返信用封筒(自分の住所・切手付き)を同封 しましょう。
税務署で受理された後、控えに受付印を押したうえで返送されます。
e-Taxで提出(おすすめ)
開業届は、国税庁の電子申告システム「e-Tax」からも提出できます。
マイナンバーカードとICカードリーダー、もしくはスマートフォンを使えば、自宅から24時間いつでも申請可能 です。
提出後は、「受付完了通知」がメッセージボックスに届き、それが受付印の代わりとなります。
開業届を提出するメリット
- 青色申告の特典を受けられる
- 社会的信用が向上する
- 屋号付きの銀行口座を作れる
- 小規模企業共済に加入できる
- 助成金・補助金を申請できる
青色申告の特典を受けられる
青色申告を選ぶには、開業届の提出とあわせて「青色申告承認申請書」が必要です。
この申請が受理されると、 最大65万円の控除が受けられたり、家族への給与を経費にできたりと、多くの節税効果 が得られます。
帳簿づけのルールは増えますが、その分、所得税の負担軽減につながる制度です。
白色申告よりも税制上のメリットが大きいため、事業を継続的に行うなら積極的に活用したいところです。

青色申告とは?個人事業主・フリーランスの確定申告をわかりやすく解説
青色申告と白色申告の違いはもちろん、それぞれのメリット・デメリット、必要な準備や手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
詳しくはこちら社会的信用が向上する
開業届を提出すると、正式に「個人事業主」であることが証明されます。
これにより、 社会的な信用が得られ、金融機関での融資や事業用クレジットカードの申請でも有利になる 場合があります。
書類一つで信用度が高まるため、事業を本業とする予定の場合や、将来ビジネスを広げたいと考えている人は、あらかじめ提出しておくと安心です。
屋号付きの銀行口座を作れる
開業届を出すと、屋号を使った銀行口座を開設できるようになります。
屋号口座は「〇〇商店」や「〇〇オフィス」など、 ビジネス名義で取引ができ、取引先や顧客からの信頼にもつながります 。
個人のプライベート口座と分けることで、収支管理や確定申告もスムーズになるのが利点です。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済は、 個人事業主やフリーランス向けの「退職金制度」として機能 します。
積み立てた掛金は全額が所得控除の対象となり、節税にも効果的です。
加入には、開業届や確定申告書の控えが必要ですので、開業届を提出しておくことが前提になります。
助成金・補助金を申請できる
国や自治体が提供する助成金や補助金は、事業の立ち上げや運営を支援する大きな味方です。
申請時には「開業届の控え」が必要とされるケースが多く、提出していないとチャンスを逃すことに なります。
返済不要の支援金もあるため、対象の制度をうまく活用すれば資金面での負担を軽減できます。
事業のスタートをスムーズにするためにも、事前の届出は欠かせません。

開業届を提出するデメリット
- 配偶者の扶養から外れる可能性
- 失業手当を受けられなくなる
- 確定申告が必要になる
配偶者の扶養から外れる可能性
開業届を提出し個人事業主として事業を始めると、所得が一定額を超えた場合に配偶者の扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れた場合は、 国民健康保険や国民年金への加入が必要になり、その保険料を自分で負担しなければなりません 。
保険料の支払いが生じることで、手取り額が想定より減るケースもあるため、事前に収支シミュレーションをしておくと安心です。
失業手当を受けられなくなる
失業手当(雇用保険の基本手当)は、再就職の意思がある「失業中の人」が対象です。
開業届を提出してしまうと、 たとえ収入がなくても「事業を始めた人」と見なされ、原則として受給資格を失います 。
もし退職後に開業を考えている場合は、失業手当の受給が終了してから届出を行うなど、タイミングを慎重に見極めることが重要です。
確定申告が必要になる
個人事業主として開業すると、毎年確定申告が必要になります。
会社員と異なり、 所得税の計算や帳簿の作成をすべて自分で行う必要があるため、税務の知識が求められます 。
特に青色申告を選ぶと、複式簿記による記帳や決算書の作成が求められるため、手間がかかると感じる方も少なくありません。
確定申告ソフトを活用すれば、初心者でも作業の負担を大きく軽減できます。

開業届は出さなくても罰則はない
開業届を提出しなくても法律による罰則はないため、提出を控える人もいます。
しかし、 所得税法では事業開始の日から1か月以内に開業届を提出することが求められています 。
実際には罰則が厳しくないため見落とされることもありますが、青色申告の特典や社会的信用の向上といった利点を享受できなくなる点には注意が必要です。
提出の有無はメリット・デメリットを踏まえて慎重に判断しましょう。
開業届以外に必要な届出
個人事業を始めると、税金や従業員の雇用に関して、さまざまな届出が必要になります。
届出先は税務署、都道府県税事務所、市区町村、労働基準監督署など多岐にわたり、それぞれ役割が異なります。
すべてが必須ではありませんが、提出することで節税につながるものもあるため、内容を理解して適切に対応することが大切です。
各行政機関と関連する届出一覧
| 提出先行政機関 | 提出書類 | 書類PDF | 必須/任意 | 必要なとき | 提出期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県税事務所 or市町村役場 |
事業開始等申告書 | 各都道府県のHP | 必須 | 個人事業を始めたとき | 開業日から1か月以内 ※自治体で異なる |
| 税務署 | 個人事業の開業・廃業等届出書(=開業届) | 必須 | 個人事業を始めたとき | 開業日から1か月以内 | |
| 税務署 | 消費税課税事業者選択届出書 | 任意 | 消費税の計算に簡易課税方式を選びたいとき | 適用希望年の前日(12月31日)まで | |
| 税務署 | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 任意 | 消費税の計算に簡易課税方式を選びたいとき | 適用希望年の前日(12月31日)まで | |
| 税務署 | 所得税の青色申告承認申請書 | 任意 | 青色申告を選択するとき | 事業開始年に申告→開業日から2か月以内/事業開始から2年目以降に申告→その年の3月15日まで | |
| 税務署 | 青色事業従者給与に関する届出書 | 任意 | 親族に「青色事業専従者」として働いてもらうとき | 事業開始年に申告→開業日から2か月以内/事業開始から2年目以降に申告→その年の3月15日まで | |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 場合により必須 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から1か月以内 | |
| 税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 場合により必須 | 従業員を雇用したとき | 随時 | |
| 税務署 | 所得税の「棚卸資産の評価方法」「減価償却資産の償却方法」の届出書 | 場合により必須 | 棚卸資産の評価方法・減価償却の計算方法を変更したいとき | 適用希望年の確定申告の期限(翌年の3月15日)まで | |
| 市町村役場 | 償却資産申告書 | 各都道府県のHP | 必須 | 償却資産の内容を届け出るとき | 毎年1月31日まで |
| 労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 窓口で入手/郵送 | 場合により必須 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から10日以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険概算保険料申告書 | 窓口で入手/郵送 | 場合により必須 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から50日以内 |
| 公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届 | サイトで同意必要 | 場合により必須 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から10日以内 |
| 公共職業安定所 | 雇用保険被保険者資格取得届 | サイトで同意必要 | 場合により必須 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日の翌日の10日まで |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 場合により必須 | 適用業種で5人以上の従業員を雇用したとき | 従業員が5人以上になった日から5日以内 | |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 場合により必須 | 従業員を雇用したとき | 従業員を雇用した日から5日以内 | |
| 年金事務所 | 健康保険被扶養者異動届 | ケース別一覧 | 場合により必須 | 従業員の家族(被扶養者)に社会保険を適用するとき | 従業員を雇用した日から5日以内 |
都道府県税事務所への届出(必須)
事業を始めたら、都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出する必要があります。
この届出により、事業税などの地方税に関する管理が始まります 。提出は開業後すみやかに行いましょう。
東京23区の場合は、都税事務所へ提出すれば、市区町村への提出は不要です。
税務署への届出(任意)
税務署へは、税金の計算方法や申告制度に関する任意の届出を出すことができます。
特に 「青色申告」や「インボイス制度」に関する届出は、提出することで大きな節税効果 があります。
届出は任意ですが、今後の経理や確定申告に備えて、できる限り早めに提出しておくのがおすすめです。
インボイス関連の申請書(任意)
適格請求書(インボイス)を発行したい場合は、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
また、免税事業者から課税事業者へ変更する場合は「消費税課税事業者選択届出書」も必要です。
取引先からインボイス対応を求められることもあるため、事前に準備しておくと安心です。

所得税の青色申告承認申請書(任意)
青色申告には帳簿の作成義務がある一方で、最大65万円の控除が受けられるなど、大きな税制メリットがあります。
この制度を利用するには、「青色申告承認申請書」を開業から2か月以内に提出する必要があります。
提出がない場合は自動的に白色申告となり、控除が受けられません。節税を考えている場合は、忘れずに届け出を行いましょう。

青色事業従者給与に関する届出書(任意)
家族を従業員として雇い、給与を経費に計上したい場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です。提出しないと給与が経費として認められません。
提出期限は、新規開業の場合は開業から2か月以内または翌年3月15日のいずれか早い方、給与支払い開始後は支払い開始から2か月以内です。
給与支払事務所等の開設届出書(場合により必須)
従業員や家族へ給与を支払う場合は、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を出します。
給与から源泉徴収を行う義務があるため、開設から1か月以内に届け出ましょう。従業員を雇う予定がある場合、事前の提出がおすすめです。
労働基準監督署への届出(場合により必須)
従業員を雇う場合は、雇用開始から10日以内に労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出 し、労災保険への加入が必要です。
また、労働保険に加入した際は「労働保険概算保険料申告書」も提出し、年度ごとの保険料を申告・納付します。
公共職業安定所への届出(場合により必須)
従業員を31日以上雇う見込みがあり、週の労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険への加入が義務 となります。
「雇用保険適用事業所設置届」や「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出しましょう。提出期限は雇用から10日以内です。
参考:雇用保険法第4条
年金事務所への届出(場合により必須)
従業員を雇った場合は、厚生年金や健康保険への加入も必要 です。「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などを年金事務所に提出します。
適用条件に該当する場合は、速やかに手続きしましょう。従業員の福利厚生を整えることは、信頼性の向上にもつながります。
開業届以外に準備しておきたい備品・ツール
最低限そろえておきたい備品・ツール
- 名刺
取引先や顧客に事業内容を伝えるために不可欠。ロゴや連絡先を入れると視覚的にも印象に残りやすくなります。 - 印鑑
契約や金融取引で使用し、重要な文書に必要。実印、角印、銀行印の使い分けを理解しておきましょう。 - 預金通帳
経理作業や税務申告に必要な口座管理に役立ちます。 - クレジットカード
事業費用を管理しやすくするための手段です。
印鑑登録と種類
印鑑は取引や手続きで重要な役割を果たします。 実印、角印、銀行印などの選択肢があり、それぞれの性質を理解して使い分けることが大切 です。- 実印:契約書など重要な取引に使用され、市区町村に登録が必要
- 角印:会社名や屋号が刻まれ、法人間の取引で利用される
- 銀行印:銀行口座の取引に必要で、金融機関に登録する
印鑑登録は市区町村で行い、使用に際しては公的な要件を満たす必要があります。
その他検討しておきたい備品・ツール
- パソコン・プリンタ
パソコンは私用と分けて事業用を持つと安心。書類を扱う業種なら、プリンタもあると便利です。 - 会計ソフト
会計ソフトがあれば、帳簿や申告作業がスムーズに。初心者向けや無料プランもあり、小規模事業者にも最適です。 - インターネット回線・電話
ネット環境は業務の基本。光回線やWi-Fiに加え、固定電話もあると信用度が上がります。セット契約でコストも節約可能。 - 電子契約
契約書のやり取りは、電子契約が便利。印刷・郵送が不要で管理もラク。業務効率化を図るなら導入がおすすめです。 - 勤怠管理システム
従業員の勤務時間は正確に管理が必要。クラウド勤怠システムを使えば、打刻や集計も自動化でき、負担を減らせます。
高価なモノを揃えるには、中古・割賦・リース・レンタルを検討
事業を運営する際には、厨房設備や自動車、コピー機(プリンタ複合機)など高価な備品を必要とすることがあります。
その際、中古や割賦、リース、レンタルなどの方法を検討することが重要です。
割賦は分割払い、リースは長期契約で月々のリース料を支払い、レンタルは必要なときに一時的に利用する方法 です。
初期費用を抑えつつ、使用頻度や特性に応じて適切な選択肢を考えましょう。
開業手続きの負担を軽減!0円創業くん
起業を考えていても、開業手続きの準備や費用に不安を感じる方は多いでしょう。そんなときに心強いのが「0円創業くん」です。
「0円創業くん」を利用すれば、 会社設立に必要な定款作成や登記申請などの手続きをプロが代行し、登記費用も大幅に削減 できます。
特に初めて起業する方にとっては、面倒な手続きを任せられるのは大きなメリット。手間やコストを抑えてスムーズに開業したい方におすすめのサービスです。
まずは話を聞いてみたい方
【無料】お問い合わせはこちら登録不要!
【無料】資料請求はこちらまとめ:開業届は事業の第一歩
開業届は、個人事業を始めたことを税務署に知らせるための大切な書類です。
提出することで青色申告が選べるようになり、節税効果や社会的信用の向上など多くのメリットが得られます。
提出は事業開始から1か月以内が原則で、郵送やe-Taxでも可能です。扶養や失業手当などへの影響もあるため、事前に内容をよく確認して判断しましょう。
あわせて、必要な届出や備品の準備も忘れずに行うことで、スムーズな開業につながります。
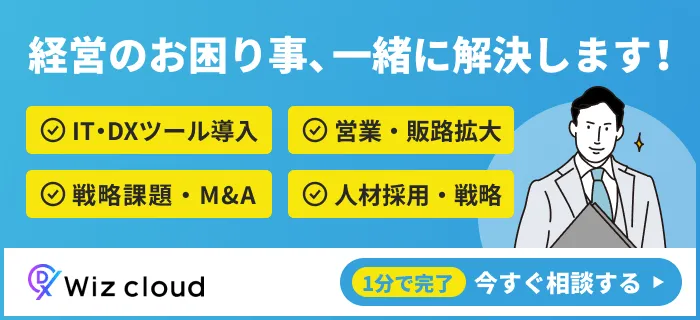

この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!