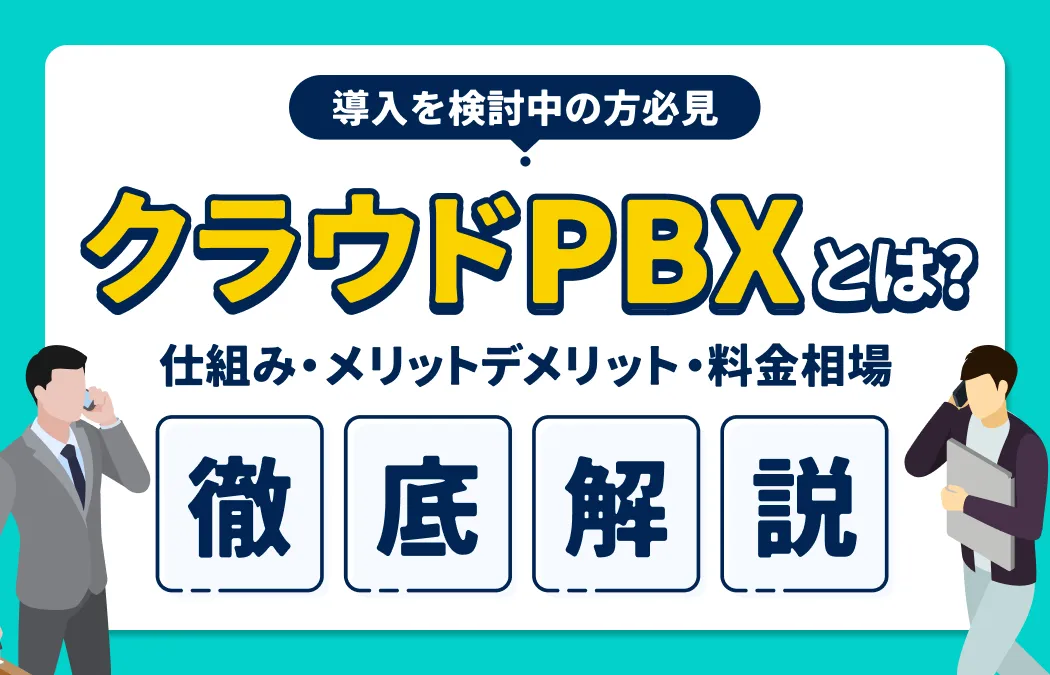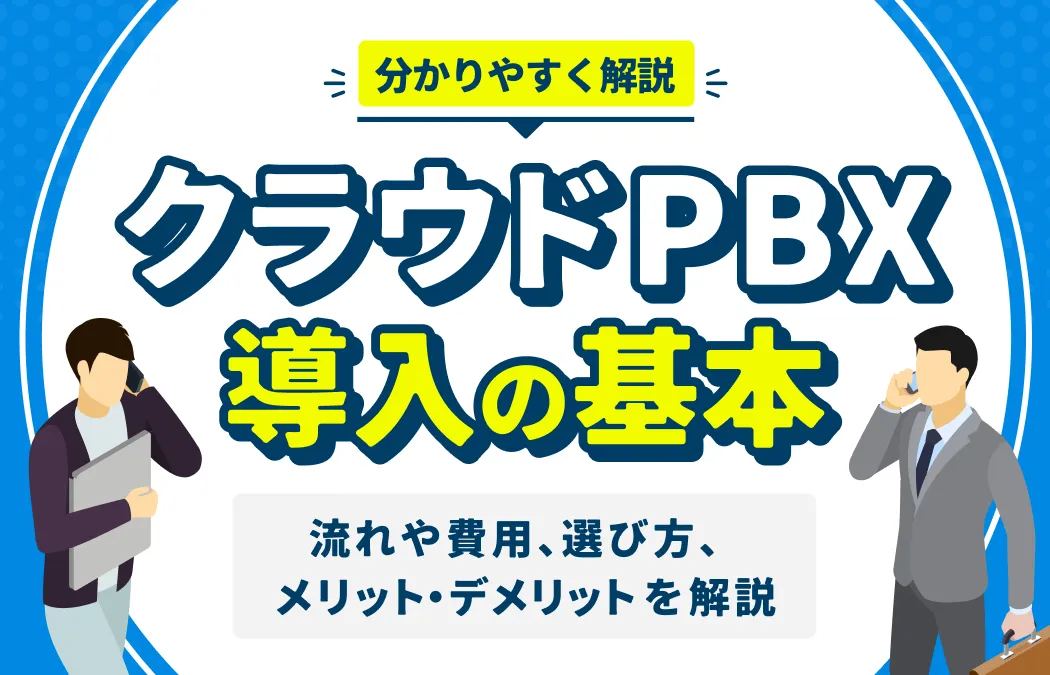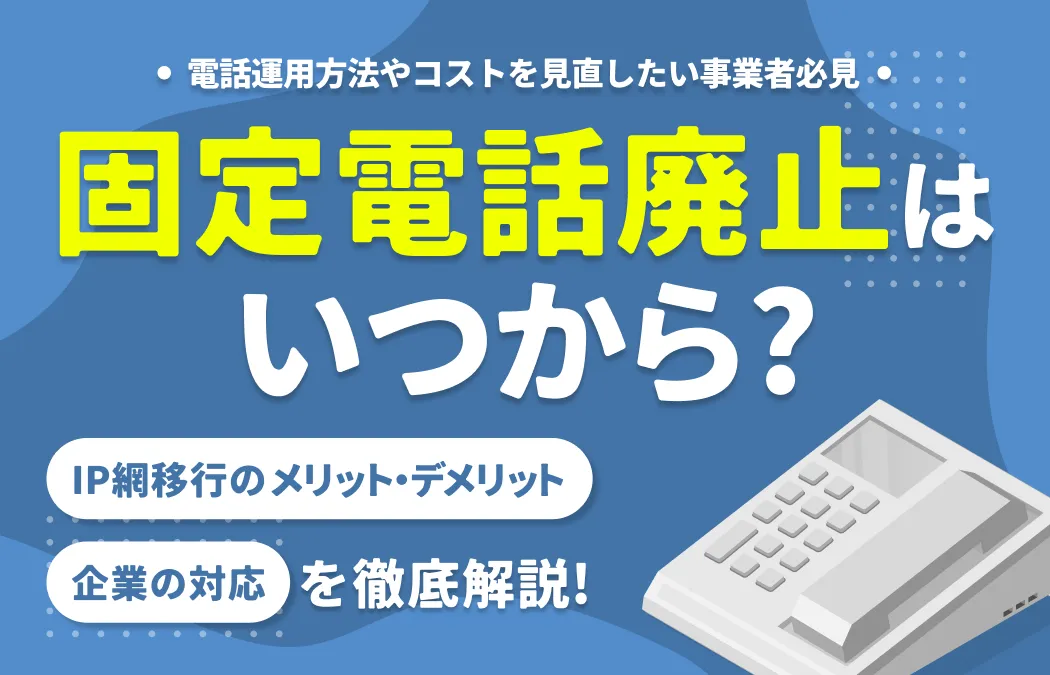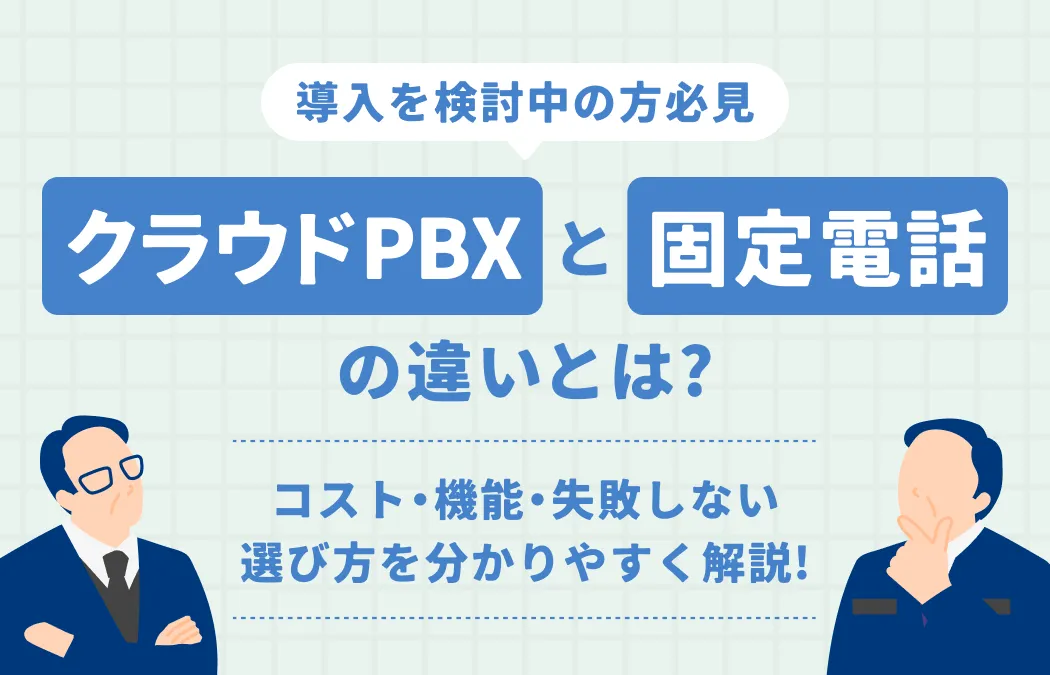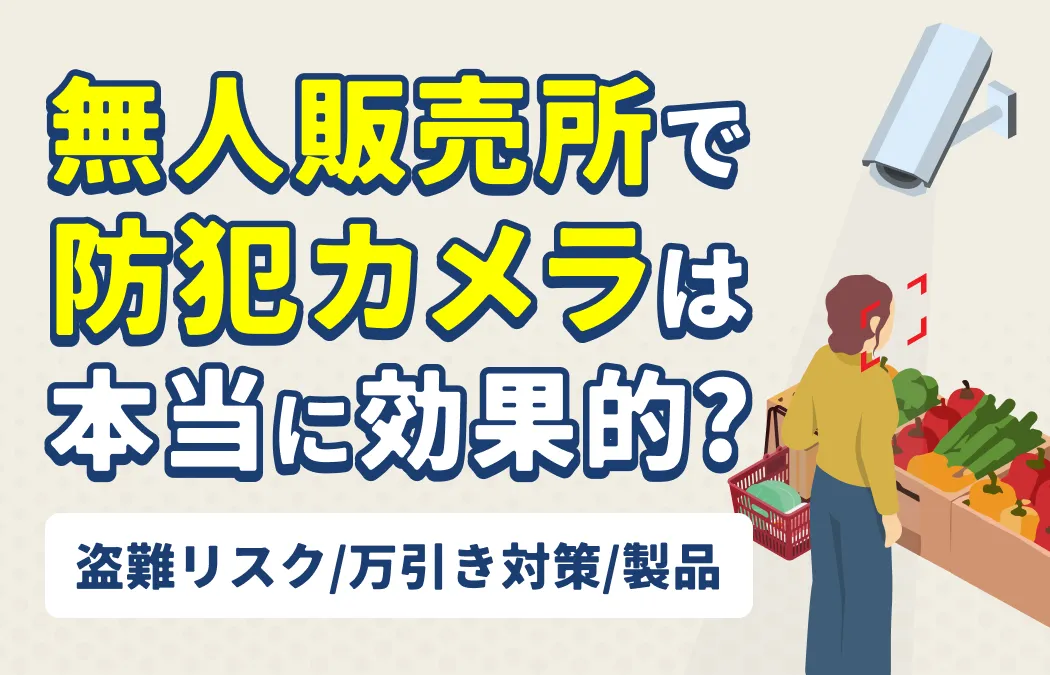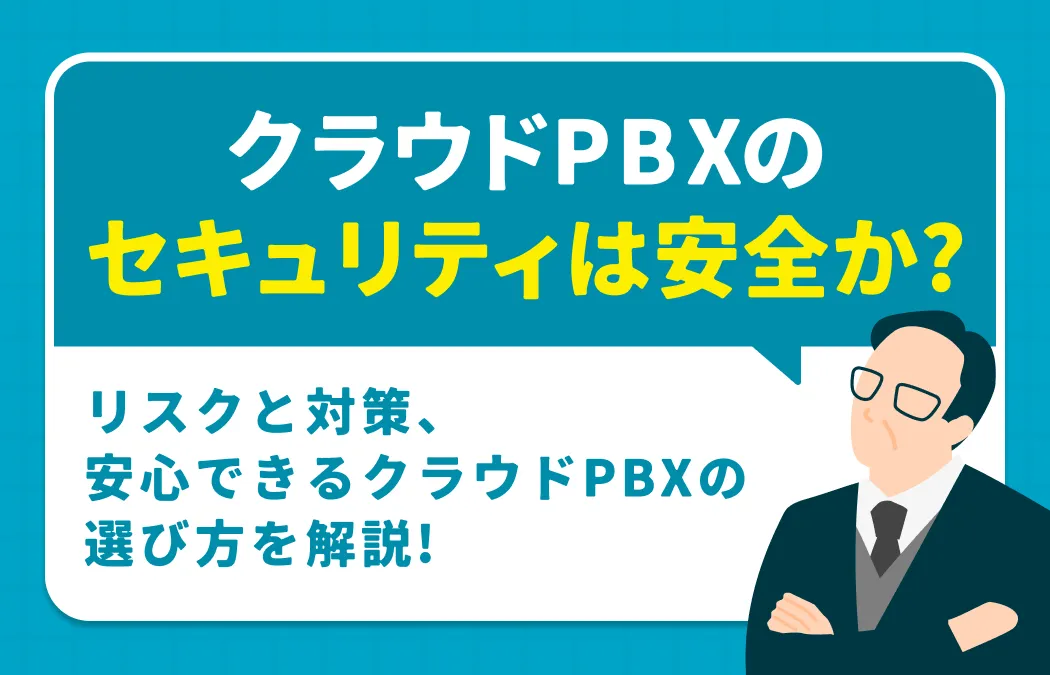「導入費用はどれくらいかかる?」
「家庭用電話機と何が違うの?」
ビジネスフォンは、複数の電話機を接続し、内線・外線通話を効率的に管理できるビジネス向けの電話サービスです。
しかし、具体的なメリットや費用が分からず、導入をためらっている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ビジネスフォンのメリット・デメリットだけでなく、仕組みや選び方まで詳しく解説します。
目次
▼この記事で紹介している商品
ビジネスフォンとは?基本をわかりやすく解説

ビジネスフォンは、 企業やオフィス向けに設計された多機能な電話システム です。
複数の電話機を接続して外線や内線を効率的に管理し、音声通話はもちろん、転送、保留、内線通話、会議通話など、ビジネスシーンで役立つ機能を豊富に備えています。
ITインフラとの連携により、クラウドやVoIP技術を活用することで、さらなる業務効率化を実現できます。
ビジネスフォンの仕組み

ビジネスフォンは、 「主装置」と「専用電話機」の2つの要素で構成 されています。
主装置と専用電話機は、基本的に同一メーカーや同一機種で統一し、必要な台数をセットで揃える必要があります。

編集部
ほとんどのビジネスフォンは、主装置と専用電話機を同一メーカー・機種で統一しないと動作しません。
主装置とは
主装置とは、 複数の外線を集約し、それぞれのの内線電話に振り分ける役割を果たす機器 です。ビジネスフォンの機能の大部分は主装置が担っています。
主装置には複数のスロット(細長い差し込み口)があり、さまざまな機能を持つ「ユニット」を追加することで、自社に必要な機能や規模に合わせてカスタマイズできます。
つまり、主装置は単体では使用できず、外線ユニットや内線ユニット、機能ユニットなどの追加ユニットを取り付けることで、ビジネスフォンとして機能を果たします。
-
▶主装置とPBXの違いは?
-
PBX(Private Branch Exchange)は、主装置と似た機能を持つ電話システムです。両者に明確な区別はなく、一般的には「主装置=PBX」として使われることが多いです。
PBXと主装置は、どちらも専用電話機や機器と接続して通話を管理しますが、オフィス電話の運用規模によって使い分けされます。
通常、主装置は最大数百台接続する中小規模オフィス向け、PBXは数千台接続する大規模オフィス向けに利用されています。
ビジネスフォンと家庭用電話機の違い
| 家庭用電話機 | ビジネスフォン | ||
|---|---|---|---|
| 機能 | 電話の発着信 | 1通話しかできない | 複数台の電話機で同時に発着信できる |
| 複数着信の 対応可否 |
複数からの着信に応答不可 | 複数からの着信に応答可能 | |
| 転送可否 | 内線転送不可 | 内線転送可能 | |
| 購入方法 | 製造メーカー | 家電メーカーが製造 | オフィス向けに専門メーカーが製造 |
| 販売チャネル | 家電量販店で購入可能 | オフィス機器専門店や ビジネスフォン販売業者で購入可能 |
|
| 設置方法 | 設置方法 | 配線を本体に接続するだけ | 主装置と呼ばれる交換機に接続する システムのカスタマイズが必要 |
| 設置難易度 | 簡単 | 難しい |
ビジネスフォンは複数台の電話機を同時に発信・着信できる

家庭用電話は、使用する電話機の数だけ電話回線が必要 になります。
一方、ビジネスフォンで複数チャネルを契約すれば、1つの電話回線を複数の電話機で共有できます。
電話回線1つと必要な台数の電話機を用意するだけで済むため、経済的かつ効率的に運用可能です。
ビジネスフォンは1つの電話番号を複数の電話機で共用できる

家庭用電話は、割り当てられた番号を特定の電話機1台でしか使用できません 。
一方、ビジネスフォンは複数チャネルを契約することで、1つの番号を複数の電話機で共有でき、同時に複数の着信に対応できます。
例えば、4回線を契約していれば、異なる4つの電話番号から同時に着信があっても、それぞれ別の電話機で対応可能です。
ビジネスフォンは転送機能で電話を別の担当者につなげられる

家庭用電話では、異なる電話機同士を内線接続できないため、通話の転送ができず、担当者は受電した電話機まで移動 する必要があります。
一方、ビジネスフォンを導入すれば、保留転送機能を使って着信を担当者の電話機につなげられるため、デスクから移動せずにスムーズに対応できます。

編集部
担当者が近くに居なくても保留転送で対応できるため、電話の取り逃しを防げます!
ビジネスフォンで何ができる?基本機能一覧
外線機能|1つの回線で同時に複数の通話ができる
ビジネスフォンの外線機能は、 ひとつの回線で複数の通話を同時に処理できる点が特徴です。
代表番号に複数の着信があった場合、空いている回線を自動的に選択し、異なる電話機で同時に通話できます。
これにより、複数の顧客対応や取引先との連絡が円滑に進み、効率的な電話業務が実現します。
内線機能|社内での通話ができる
ビジネスフォンの内線機能は、 社内の電話機同士で通話を行える機能です。
内線番号をダイヤルするだけで、他の部署や同僚と即座に連絡が取れます。これにより、迅速な情報共有や業務連携が可能となり、業務効率の向上に寄与します。

編集部
内線通話は外線を使わなず無料なため、通話コストの削減にもつながります!
-
▶着信が内線か外線かはディスプレイ表示と着信音で見分ける
-
オフィスの電話機に着信があった際、着信が内線か外線かはディスプレイ表示と着信音で見分けられます。
・内線の場合
内線番号が表示され、専用の着信音が鳴る
・外線の場合
外線ボタンが点滅し、異なる着信音が鳴るため、受話器を上げた後に点滅している外線ボタンを押して応答する。
保留・転送機能|担当者の不在時に利用する
ビジネスフォンの保留転送機能は、 担当者が近くにいない場合に便利です。
通話を繋げたまま保留ボタンを押し、担当者のデスクに設置された電話機へ内線転送することで、顧客を待たせずに対応を引き継げます。
また、転送先が不在の場合でも、別の担当者や部署に簡単に通話をつなげるため、顧客対応の効率が向上します。
鳴り分け機能|着信音を相手や発信元に応じて変えられる
ビジネスフォンの鳴り分け機能は、 着信音を相手や発信元に応じて変えられる便利な機能です。
例えば、重要な顧客からの電話や社内連絡を異なる着信音で区別でき、即座に対応の優先順位を判断可能です。
業務の効率化や重要な連絡の見逃し防止が可能となり、ビジネスコミュニケーションの質が向上します。
その他の便利機能
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 再ダイヤル (リダイヤル発信) |
過去の発信・着信履歴から電話番号を選んで簡単に再呼び出しできる |
| 短縮番号 | 短縮キーを設定することで、長い番号を直接入力する手間を省ける |
| ワンタッチ発信 (ワンタッチリダイヤル) |
指定した番号をショートカットキーに登録し、ボタンを押すだけでその番号に直接発信できる |
| 電話帳編集 | 連絡先の登録や削除を行う |
| 録音機能 | 通話内容を録音し、後から聞き返すことができる |
| 時間外案内機能(IVR) | 営業時間外にかかってきた際、受付時間外であることをガイダンスでお知らせする |
| スマホ連携 | スマホを内線化して、外出中やテレワーク中でも会社の代表電話番号で発着信できる |
| リモートコールバック | オフィスの留守電を携帯電話で確認できる |
ビジネスフォンを導入するメリット

1つの電話番号に複数の電話機で対応できる
ビジネスフォンを導入すると、複数の電話機で1つの電話番号を利用できるようになります。
これにより、同じ電話番号に複数の着信があった場合も同時に対応できるため、お客様を待たせずに済みます。
代表番号への着信を、要件によって各部門に振り分ければ、問合せへの的確な回答により、顧客対応の質を向上させることも可能です。
内線通話で業務の効率化&通信費削減
ビジネスフォンの内線通話機能は、社内コミュニケーションを円滑にし、業務効率を大幅にアップさせます。
例えば、営業部門から経理部門へ問い合わせが必要な場合も、内線番号をダイヤルするだけで即座に連絡が可能です。これにより、繁忙期も社内の連絡がスムーズに行えます。
また、内線は外線と違って通話料がかからない ため、社内連携の際にかかる通信費を削減できる点もメリットです。
1本の回線契約で済むため基本料金を抑えられる
家庭用電話機では、電話機を増設するたびに追加の回線契約が必要で、従業員が多いほど膨大なコストがかかっていました。
一方で、 ビジネスフォンは1回線で複数の電話機を使用でき 、回線契約のランニングコスト削減につながります。
ビジネスフォンを導入するデメリット・注意点
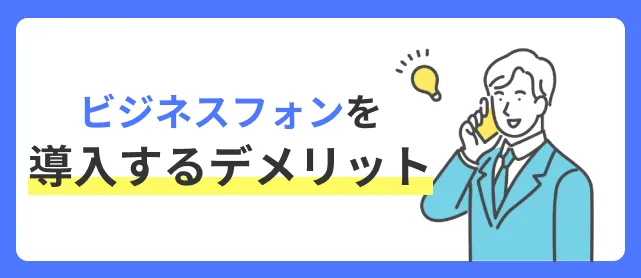
デメリット|主装置の設置など導入に高額な初期費用がかかる
ビジネスフォン導入の際、避けて通れないのが初期費用の問題です。 主装置の設置や配線工事など、導入時にまとまった出費が必要 となります。
例えば、10台程度の小規模システムでも、50万円から100万円ほどの費用がかかることも珍しくありません。
しかし、この投資は長期的に見れば十分に回収可能です。通信コストの削減や業務効率の向上によって、数年で元が取れるケースも多いのです。
また、リースやレンタルを利用すれば、初期費用を抑えることも可能です。導入を検討する際は、長期的な視点でコストパフォーマンスを考えましょう。
デメリット|導入・増設・移設のたびに工事が必要
ビジネスフォンは、導入・増設・移設のたびに工事が必要となり、手間やコストがかかる点がデメリットです。
設置には専門業者による配線作業が必要 で、オフィスのレイアウト変更や人員増減の際も配線を見直さなければなりません。
特に主装置から各機器への配線は専門知識が必要で、適切な対応には業者への依頼が不可欠なため、レイアウト変更には手間がかかります。
デメリット|メンテナンスや保守の負担がかかる
ビジネスフォンは精密機器のため、メンテナンスや保守の負担が増える点がデメリットです。
定期的な配線チェックや主装置の動作確認、クリーニング、データのバックアップが必要 となり、専用電話機の台数が多いほど手間も増えます。
また、故障や異常が発生した場合は修理や交換が必要になり、対応にコストや手間がかかることもあります。
注意点|誤操作しやすい
ビジネスフォンはボタンが多く、誤操作が発生しやすいため注意が必要です。回線が多いと担当者を間違えてつなぐ、誤って通話を切るといったミスが起こることがあります。
また、着信音が鳴らない、ディスプレイ表示が消えるといったトラブルも、誤操作が原因の場合が少なくありません。
デスク上に設置されているため、書類が当たってボタンを押してしまうこともあり、注意が必要です。 誤作動防止機能を備えた機種もある ため、導入時に確認するとよいでしょう。
リース契約と購入のそれぞれのメリット・デメリット

リース契約のメリット
初期費用が不要
ビジネスフォンをリース契約することで、初期費用を抑えられます。
リース会社が機器の費用を負担し、利用者は毎月のリース料金を支払う仕組みのため、導入時の大きな支出が不要になります。
ビジネスフォンは電話機や主装置、ユニットなど必要な機器が多いため、 一括購入の負担を避けられる点は大きな利点 です。
経費として計上ができる
ビジネスフォンをリース契約することで、毎月のリース料金を全額経費として計上できるため、節税効果が期待できます。
購入の場合は減価償却が必要ですが、リースなら手続きが簡単で管理の負担も軽減されます。
さらに、 所有権はリース会社にあるため、固定資産税の支払い義務も発生しません 。
コストを分散しつつ、税制上のメリットを活用できる点がリース契約の大きな利点です。
支払い期間が選べる
ビジネスフォンをリース契約することで、支払い期間を自由に選べる点がメリットです。
契約期間を柔軟に設定できるため、 財務状況に合わせた資金計画が立てやすくなります 。
一括購入のようなまとまった負担を避けつつ、無理のない範囲でコストを分散できるため、企業の資金繰りにも役立ちます。
補償サービスは別途契約が不要
ビジネスフォンをリース契約することで、別途補償サービスを契約する必要がなくなります。
リースには動産総合保険が付帯されているため、故障や破損時に修理や交換を受けられます 。
さらに、メーカーのサポートが含まれている場合は、より安心して利用できます。
万が一のトラブル時もメーカーに問い合わせるだけでよく、予期せぬ出費を抑えられる点が大きなメリットです。
リース契約のデメリット
料率が発生する
ビジネスフォンのリース契約は、料率に基づいて手数料が発生するため、 一括購入に比べて総支払額が高くなります 。
これは、リース料金には契約期間中の利息や手数料が含まれるためです。
途中解約ができない
ビジネスフォンのリース契約にはクーリング・オフが適用されない ため、契約者は途中解約できません。
もし会社が倒産したり、オフィスを縮小した場合でも、リース料金の支払い義務が残るため、不要になった場合でも契約を続けなければならない点がデメリットとなります。
審査が必要
ビジネスフォンのリース契約は、リース会社による審査が必要です。
審査に通過しない場合、契約が成立しない可能性があります 。
契約条件や会社の信用状況に基づいて審査が行われるため、リース契約を希望する際には、事前に審査の通過可能性を確認しておくことが重要です。
購入のメリット
総額が安く収まる
ビジネスフォンを購入することで、リース契約と比較して総額が安く抑えられます。
現金で一括購入する場合、手数料がかからず、機器本体の購入費用のみで済む ため、支払い金額が明確で無駄な費用が発生しません。
審査が不要
ビジネスフォンを購入する際、リース契約のような審査は不要です。
これにより、 スムーズに機器を手に入れることができ、迅速に業務を始めることが可能 です。
所有権が得られる
ビジネスフォンを購入することで、所有権を得られるというメリットがあります。
購入した機器は自社のものとなり、自由に利用・管理できます 。
一方、リース契約では所有権がリース会社にあり、カスタマイズ等の自由度が制限されるため、購入による所有権の取得は大きな利点です。
購入のデメリット
初期費用が高い
ビジネスフォンの購入は、初期費用が高くなるというデメリットがあります。
電話機本体だけでなく、主装置やユニットなどの周辺機器も購入する必要があり、まとまったが出費が発生します 。
経費処理が手間
ビジネスフォンの購入は、経費処理が手間になるというデメリットがあります。
所有権を得るため、減価償却や固定資産税の処理が必要となり、経理面での負担が増えます 。
また、固定資産税の支払い義務も発生するため、税金面でも負担が増えます。
補償サービスは別途契約が必要
ビジネスフォンの購入は、補償サービスが別途契約が必要というデメリットがあります。
リース契約では動産総合保険が付帯されることがありますが、 購入の場合は保険が含まれていません 。
メーカーサポートがない場合、故障やトラブル時には修理費用が発生する可能性があります。
ビジネスフォンの高額な導入費用を削減する方法

規模や用途に合った機器を選ぶ
ビジネスフォンの高額な導入費用を抑えるには、規模や用途に合った機器を選ぶことが大切です。
主装置はサイズや機能により価格が異なり、 規模が大きかったり、機能が豊富だったりするほど高価になります 。
そのため、 自社に必要な機能と規模に見合った製品を選べば、無駄なコストを削減できます 。
また、専用電話機も必要最低限の機能を持つものを選べば、過剰な機能に無理に投資することなくコストを抑えられます。
中古のビジネスフォンを選ぶ
ビジネスフォンの高額な導入費用を抑えるには、中古ビジネスフォン選ぶのもおすすめです。
ビジネスフォンは丈夫で長持ちするため、新品でなくても十分に使用可能 です。
特にNTT製品は導入実績が豊富かつ種類も多いため、自社に合う中古品を見つけやすく、コストを大幅に削減できる場合があります。
ビジネスフォンの代わりにクラウドPBXを導入する
ビジネスフォンの高額な導入費用を抑えるには、クラウドPBXを導入するのもおすすめです。
クラウドPBXは インターネット回線を利用するため、専用電話機や主装置の購入が不要で、初期費用を大幅に削減できます 。
また、スマホやタブレットを電話機として利用することができ、電話機の導入コストを抑えることも可能です。
さらに、内線通話が無料となり、通話費用の節約にもつながります。クラウドPBXはコスト削減だけでなく、効率化やBCP対策にも有効です。
ビジネスフォンの選び方

電話回線の種類で選ぶ
ビジネスフォンの回線を選ぶ際は、 加入電話 と IP電話 の2種類から選ぶ必要があります。
加入電話
加入電話とは、アナログ固定電話と同様のサービスで、信会社と契約し電話回線を利用する方式 です。
加入電話を選ぶ場合、インターネット回線とは別に契約が必要なため、電話料金とインターネット料金が二重で発生するほか、導入時に電話加入権を購入する必要があります。
IP電話
IP(インターネットプロトコル)電話とは インターネットを利用した電話サービス で、音声をデジタル化して伝達する仕組みです。
加入電話が電話会社の基地局を経由するのに対し、IP電話は光回線1本で電話とインターネット接続用回線の両方を利用できます。
インターネット回線があれば導入が簡単で、基本料金や通話料金も低コストで済む点がメリットです。
ただし、インターネット回線がない場合は新たに回線加入と工事が必要です。
必要な機能で選ぶ
ビジネスフォンには、 家庭用電話にはない多くの便利機能が搭載されています 。
業務で必要な機能を見極め、自社の業務に適した機能を選ぶことが重要です。
一方で、多機能な機種ほど価格が高くなるため、不要な機能が含まれていないか慎重に判断し、コストを抑えることも大切です。
内線機能が豊富か
ビジネスフォンには、社内の電話機同士で通話できる内線機能が備わっています。
業務の効率化につながるさまざまな内線機能があるため、 利用頻度や業務スタイルに応じて必要な機能を選ぶことが大切 です。
▼内線機能例
| 内線会議通話 | 複数人で会議のように内線利用が可能 |
|---|---|
| 不在メッセージ | 離席中、内線の発信相手のディスプレイに表示可能 |
| 不応答返答 | 一定のコール数で応答がない時に他の内線に転送可能 |
| 話中呼出 | 発信先が話し中でも内線の着信音を鳴らせる |
転送機能が豊富か
外線からの着信を担当者へ取り次ぐ機会が多い場合は、転送機能の充実度も重要なポイント です。
基本的な転送機能に加え、スムーズな対応を可能にする以下のような機能が搭載されているか確認しましょう。
▼転送機能例
| 保留転送 | 外線の着信を保留にしたまま担当者に転送可能 |
|---|---|
| 不在転送 | 離席中、内線の着信を他の内線や携帯電話に転送可能 |
| 代理応答 | 離席中の近くの席の着電を自分の電話機で対応可能 |
音声自動応答・案内(IVR)
音声自動応答・案内(IVR)は、 着信対応を自動化し、録音された案内メッセージやダイヤル操作で適切な部署へ誘導できる機能 です。
コールセンターや問い合わせの多い企業では、業務負担の軽減に役立ちます。
ビジネスフォンによってはオプション提供されているため、導入の可否や追加費用を事前に確認しておくと、将来的な運用の幅が広がります。
オフィス外で携帯電話でも利用できる機能
外回りなど外出が多い業種では、スマホや携帯電話と連携できるビジネスフォンが便利 です。
ビジネスフォンの定番機能である、オフィスの代表番号で発着信できる機能を利用すれば、外出先でもスムーズな顧客対応が可能になります。
▼外部から利用する時に便利な機能例
| 代表番号機能 | オフィスの代表番号で発着信できる |
|---|---|
| 不応答着信通知 | オフィスの電話機の着電に出られなかった時に通知がくる |
| 外線自動転送 | 事前に登録した番号からの着電を担当者の携帯電話などに自動転送 |
| リモートコールバック | オフィスの電話機の留守電を携帯電話で聞ける |
デザインやサイズ
機能やコストが同等であれば、デザインやサイズも選定基準の一つになります。
オフィスのレイアウトや雰囲気に合うカラーやコンパクトな機種を選ぶことで、統一感のある空間を維持できます 。
利用台数と同時接続数で選ぶ
ビジネスフォンは1つの回線で複数人が通話できるため、導入時には必要な電話機の台数と同時接続数を考慮することが重要です。
業務に支障が出ないよう、想定する利用人数と通話頻度に応じた機種を選びましょう 。
利用台数の決め方
ビジネスフォンの台数は、 基本的にオフィスに常駐しデスクを使用する従業員の人数に合わせるのが一般的 です。
ただし、社用スマホを活用している場合や、電話対応の頻度が少ないオフィスでは、必要最小限の台数でも十分運用できます。
同時接続数の選び方
ビジネスフォンでは、同じ番号でも複数の通話が可能で、 同時に接続できる通話数は外線数によって決まります 。
外線数は、主装置の種類やスペックによって異なり、「同時通話数」や「チャネル数」とも呼ばれます。
外部とのやり取りが多い業務では、十分な外線数を確保することが重要です。
契約種類と導入コストで選ぶ
ビジネスフォンの契約方法は 「新品購入」「中古品購入」「リース」「レンタル」 の4つの方法があり、それぞれによって初期費用やランニングコストが大きく異なります。
新品購入
新品のビジネスフォンは、 高機能で最新モデルが手に入りますが、初期費用が最も高額 です。
- 電話機:1台あたり1〜4万円程度が相場です。
- 主装置:20万円〜と高額で、接続台数が増えるほど価格が上がります。
| メリット | ● 最新機能が利用できる ● メーカー保証が付いている |
|---|---|
| デメリット | ● 初期費用が高額 ● 導入に時間がかかる場合がある |
中古品購入
中古のビジネスフォンは、 新品に比べて大幅に費用を抑えられます 。
- 電話機:1台あたり4,000円〜と、新品の1/5〜1/4程度で購入できます。
- 主装置:3〜5万円程度で購入できます。
| メリット | ● 初期費用が安い ● すぐに導入できる |
|---|---|
| デメリット | ● 故障のリスクがある ● 機能が古い場合がある ● メーカー保証がない場合がある |
リース
リースは、 月額料金を支払うことでビジネスフォンを利用できる方法 です。
- 月額料金:3,000〜1万2,000円程度が一般的です。
- 料金構成:電話機、主装置、回線数、設置費などを元に算出されます。
| メリット | ● 初期費用を抑えられる ● 最新モデルが利用できる ● 固定費で予算管理しやすい |
|---|---|
| デメリット | ● 長期的な契約が必要 ● リース期間中は自由に処分できない |
レンタル
レンタルは、 短期的な利用に最適な方法 です。
- 月額料金:電話機1台あたり1,500〜4,000円程度です。
- 料金構成:機種、回線数、設置工事費によって変動します。
| メリット | ● 柔軟な契約期間 ● 短期的な利用に最適 |
|---|---|
| デメリット | ● リースと比較して自由度が低い ● 長期利用には割高になる場合がある |
将来的な増設の可能性を考える
ビジネスフォンを選ぶ際は、導入後、従業員数や拠点の増加により外線数・端末数が必要になる可能性を見据えることが大切です。
増設時に大規模な工事が必要なのか、少しの拡張で済むのかを事前に確認しましょう。主装置に拡張性があれば、工事不要で回線を増やせるケースもあります。
基本的には同じビジネスフォンのメーカーや同じ機種でしか増設ができないため、 増設を前提としている場合は、拡張性が高いビジネスフォンを選びましょう 。
ビジネスフォンの配線方法
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| スター配線 |
|
|
| バス配線 |
|
|
| LAN配線 |
|
|
スター配線
スター配線とは、 主装置から各電話機に対して1本ずつ配線する仕様 で、現状最もスタンダードな配線方法です。
スター配線は各電話機に独立した配線を行うため、万が一電話機の1台が故障しても、他の電話機には影響を与えません。
ただし、電話機の数だけ配線が必要となるので、電話機が多いほど、どの電話機がどの配線に対応しているのか分かりづらくなるという注意点があります。
バス配線
バス回線とは、 主装置と電話機の間にローゼットと呼ばれる機器を経由させることで、複数の電話機への接続を可能にする配線方法 です。
バス配線はローゼットから電話機への接続を行うことで設置できるため、増設が非常に簡単です。
また、電話機と同じ数の回線が必要なスター配線に比べて、回線が少なく済むため、見た目もスマートです。
しかし、配線のどこかに問題が発生すると、接続しているすべての電話機に影響が及びます。問題の根本原因を特定しづらいため、解決には時間がかかる恐れがあります。
LAN配線
LAN配線とは、 LANケーブルを使用して配線する方法 です。一般的な電話機には対応しておらず、インターネット回線を利用するIP電話機のみで使用できます。
LANケーブルで配線を行うため、電話機の物理的な配線は不要です。また、パソコンをはじめとするインターネット回線をまとめて管理することも可能です。
ただし、LAN配線は電力供給が必要なため、給電HUBや給電アダプタなどを用意する必要があります。
ビジネスフォンの代替にはクラウドPBXがおすすめ
ビジネスフォンの代替として注目を集めているのが、クラウドPBXです。
従来のビジネスフォンと比べ、 大幅なコスト削減と業務効率化を実現 できます。
初期費用を抑えられ、月額料金も安価なため、特に中小企業にとって導入のハードルが低いのが特徴です。
さらに、スマホやPCで利用できるため、場所や時間に縛られない柔軟な働き方を可能にします。災害時のBCP対策としても有効です。
クラウドPBXは、ビジネスフォンの機能をほぼ踏襲しつつ、より使いやすく進化したコミュニケーションツールと言えるでしょう。
オフィスの電話は「CLOUD PHONE(クラウドフォン)」にお任せ!

「CLOUD PHONE(クラウドフォン)」は、 会社や店舗、事務所の代表電話をスマホでも着信・発信が可能なクラウドPBXサービス です。
これまでオフィスに設置していたPBX(交換機)本体を、クラウドネットワーク上に設置し、インターネット環境があれば手軽にビジネスフォンを利用できます。
交換機の設置が不要なことで、オフィス内の省スペース化や、ビジネスフォンの管理コストや導入コストを抑えることが可能です。
オフィス内でしか受けることができなかった内線電話も、スマホに転送することもできるため、外出先でも会社へかかってきた電話を受けることができます。

編集部
CLOUD PHONEは「最短1週間で利用開始」「圧倒的低コスト」「市外局番が使える」などの魅力があり、ビジネスフォンのメリットを超える電話サービスです!
ビジネスフォンに関するよくある質問
A
IP電話とは、インターネット回線を使って通話するデジタル方式の電話サービスです。
A
IP-PBXはオフィス内に設置し、インターネット回線で通話します。
一方、クラウドPBXはPBX自体がクラウドにあり、機器をオフィスに設置する必要がありません。
A
IP電話のメリット・デメリットは以下の通りです。
・メリット1:固定電話と比較して料金が安い
・メリット2:PCやスマホで通話できる
・デメリット1:停電時の利用・緊急通報ができない
・デメリット2:インターネット環境に左右される
A
クラウド型ビジネスフォンは、PBX機能をクラウドで提供し、スマホをビジネスフォンとして利用できます。
インターネット環境があれば、テレワークにも対応できます。
新規回線工事が不要で、主装置やPBX購入費もかかりません。月額料金のみで利用できます。
A
PBXとは、機内交換機と呼ばれ、ビジネスフォンの主装置と同じように外線と内線を制御する装置です。
PBXは大規模な環境向けで、端末台数や外線数が多く、機能も豊富ですが、価格はビジネスフォンより高いです。
まとめ
ビジネスフォンは、企業の通信効率を高め、コスト削減に貢献する重要なツールです。内線通話や多彩な機能により、業務の効率化が図れます。
しかし、初期費用や運用の手間など、デメリットも存在します。そこで注目されているのが、クラウドPBXです。
低コストで柔軟な運用が可能なクラウドPBXは、ビジネスフォンの代替として、魅力的な選択肢となっています。
通信環境の選択は、企業の規模や業務内容によって異なるため、専門家に相談専門家への相談をおすすめします。クラウドPBXの詳細を聞きたい場合は、Wiz Cloudへお気軽にお問い合わせください。


この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します!